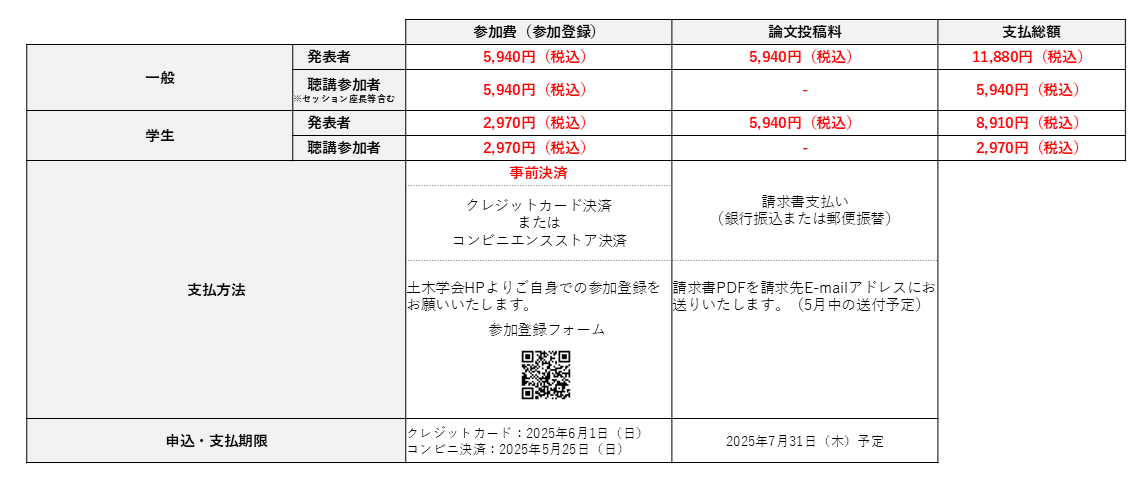#254 What We Talk About When We Talk About Travel Behavior: Location, Virtualization, and Open Science
Date
2025年7月7日
Venue
東京大学本郷キャンパス
What We Talk About When We Talk About Travel Behavior: Location, Virtualization, and Open Science
We will be holding an international research seminar will be held on July 7, titled:
“What We Talk About When We Talk About Travel Behavior: Location, Virtualization, and Open Science”
Presenters:
- Bastián Henríquez-Jara, Universidad de Chile: “Inferring and Analyzing Residential Relocation Patterns from Public Transport Smart Card Data”
- Hiroshi Uemura, the University of Tokyo: “Exploring the Impact of Availability of Bike Sharing Systems on Rental Housing Value: A case Study in Japanese Cites”
- Phoebe Ho, UC Berkeley: “Advancing Open Science Practices in Travel Behavior Research”
- Sung Hoo Kim, Hanyang University: “An exploration of spatiotemporal heterogeneity in food delivery demand”
Note: No registration is required.
#253 Sometimes wrong, but useful: integrating information in public transport
Date
2025年6月18日
Venue
名古屋大学 東山キャンパス
Sometimes wrong, but useful: integrating information in public transport
講演者:Prof. Francesco Corman(ETH Zurich)
講演題目:Sometimes wrong, but useful: integrating information in public transport
日時:2025年6月18日(水) 16:30-17:30
場所:名古屋大学 東山キャンパス ES館 033号室
参加登録リンク:https://forms.gle/KrTiH5KhgaPyHbbi6
概要:
Public transport networks are complex, and organized by an authority. This means that passengers can only use services, if they know they exist, and if they know when they run. The success of routing applications is due to the hep they provide on this task. The ideal case of routing apps matches to the assumption of shortest path, full compliance, and deterministic choice process that is almost universally used in understanding passenger flows in optimization of public transport. This talk reflects on cases when information is not available, is wrong, or contains “nudges” to steer behavior of passengers. The complexity is discussed over a few test cases.
#252 Graham教授をお招きした交通政策の集積効果に関するワークショップ
Date
2025年7月7日
Venue
Kobe Co CREATION CENTER
Graham教授をお招きした交通政策の集積効果に関するワークショップ
主旨:
世界に先駆けて英国の交通インフラの事業評価で実装された「Wider Economic Impacts (WEIs)」の開発者であるImperial College LondonのGraham教授を交えて,日英の交通インフラに関する事業評価の取組や集積効果の計測状況について意見交換を行います.
日時:2025年7月7日(月)15:00-17:00
場所:Kobe Co CREATION CENTER Room A and B(定員:70名)
https://maps.app.goo.gl/af1G3ViWDE7eEMx19
主催: 神戸大学
※なお,本ワークショップは国土交通省道路局が設置する新道路技術会議における技術研究開発の委託研究「望ましい事業評価の指針策定にむけた研究開発」の一環で開催するものです.
発表タイトル:
1.日本における事業評価改定に向けた取組:新たな事業評価指針の構築を目指して
発表者:小池淳司(神戸大学大学院 市民工学専攻 教授)
2.英国における交通インフラの事業評価と集積効果の計測
発表者:Daniel Graham, Imperial College London (Professor of Statistical Modelling, Department of Civil and Environmental Engineering)
3.日本における交通インフラの集積効果の計測
発表者:織田澤利守(神戸大学大学院 市民工学専攻 教授)
==========================
Workshop on Transport Infrastructure Appraisal: Exploring Agglomeration Effects of Wider Economic Impacts
Objective:
This workshop provides a unique opportunity to engage in a collaborative discussion on the appraisal of transport infrastructure projects, with a focus on agglomeration effects of Wider Economic Impacts (WEIs). We are honored to welcome Professor Graham from Imperial College London, a leading authority in the field who pioneered the implementation of WEIs in the UK’s transport infrastructure appraisal.
Date and Time: 7th July 2025, 15:00-17:00
Place: Kobe Co CREATION CENTER Room A and B
https://maps.app.goo.gl/af1G3ViWDE7eEMx19
Host: Kobe University
Presentations:
1. Initiatives for Revising Transport Appraisal System in Japan: Building a Framework for Future Guidelines
Atsushi Koike, Kobe University (Professor at the Departments of Civil Engineering)
2. Transport Appraisal and Measurement of Agglomeration Effects in the UK
Daniel Graham, Imperial College London (Professor of Statistical Modelling, Department of Civil and Environmental Engineering)
3. Measurement of Transport Agglomeration Effects in Japan
Toshimori Otazawa, Kobe University (Professor at the Departments of Civil Engineering)
#251 SATREPSプロジェクト(バンコク) キックオフシンポジウム
Date
2025年5月20日
Venue
Chulalongkorn University
SATREPSプロジェクト(バンコク) キックオフシンポジウム
このたび,JST-JICAのSATREPS(地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム)の新プロジェクトとして,タイ・バンコクの道路交通渋滞解消への貢献を企図した以下の研究課題(略称:3DTraffic)が本年4月より開始致しました。
「気候変動緩和に貢献する新興大都市におけるデータ駆動型の動的交通マネジメントに関する研究」(2025-2030年)
[研究代表:福田大輔(東京大学),共同代表:Kasem Choocharukul(チュラロンコン大学)]
プロジェクトWeb:https://www.3dtraffic.t.u-tokyo.ac.jp/
さて,プロジェクトの本格研究開始にあたり,下記の要領でキックオフシンポジウムを開始いたします。
シンポジウムでは,先達のバンコクSATREPSプロジェクト「Thailand4.0を実現するスマート交通戦略」を主導された林良嗣先生(東海学園大学)より,基調講演と私共の新たな活動へのエールを頂きます。そして,3DTrafficプロジェクトでこれから行う各サブテーマの研究構想について研究メンバーより説明し,最後に,林先生,大口先生,Kasem先生,Sorawit先生らによる,バンコク都市圏の交通問題に関するパネルディスカッションを行います。
https://drive.google.com/file/u/2/d/1zQHIr7qYqXNPJC3OZ08zlzu-5dYq2fJS/view?usp=sharing
The Kick-off Symposium of the 3DTraffic SATREPS Project in Bangkok “Toward the Realization of the Faster, Greener and Safer Traffic”
日時:2025年5月20日(火曜日)4.00pm – 7.00pm [日本時間](2:00 pm – 5:00 pm [タイ現地時間])
対面・オンライン(Zoomウェビナー)でのハイブリッド開催
現地会場:Meeting Hall, Floor 2, Engineering Building 4, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University https://maps.app.goo.gl/NNbiwJzJA1mmFAg89
プログラム:
1. Opening Remarks (Kasem Choocharukul, Chulalongkorn University [CU])
2. Remarks from our Honoured Guest (Haruka Ozawa, Embassy of Japan in Thailand)
3. Overview of the 3DTraffic Project (Daisuke Fukuda, The University of Tokyo [UT])
4. Keynote Lecture (Distinguished Professor Yoshitsugu Hayashi, Tokaigakuen University)
Title: “Overview of the Smart Transport Strategy for Thailand 4.0 Project and the Expectations for the 3DTraffic Project”
5. Introduction of the Study Plans of Each Working Group
i. WG1: Advanced Traffic Condition Estimation Methodology Using Data Fusion Techniques
(Toru Seo [Institute of Science of Tokyo] and Garavig Tanaksaranond [CU])
ii. WG2: Evaluation of Travel Demand Management Measures Using an Activity-based Microsimulation
(Daisuke Fukuda [UT] and Veera Muangsin [CU])
iii. WG3: Macroscopic Analysis of the Dynamic Traffic State on a City Scale
(Kentaro Wada [University of Tsukuba] and Chaodit Aswakul [CU])
iv. WG4: Proposal and Application of an Intersection-level Microscopic Traffic Signal Control
(Somporn Sahachaiseree [UT], Takashi Oguchi [UT] and Sorawit Narupiti [CU])
6. Panel Discussion: “Toward the Realization of the 3D Traffic in Bangkok”
- Yoshihisa Asada [Oriental Consultants Global, Moderator]
- Yoshitsugu Hayashi [Tokaigakuen University]
- Takashi Oguchi [UT]
- Sorawit Narupiti [CU]
- Kasem Choocharukul [CU]
7. Closing Remarks (Sorawit Narupiti [CU])
令和6年能登半島地震に関する特集企画のご案内
土木学会論文集・通常号(土木計画学:方法と技術),土木学会論文集・通常号(土木計画学:政策と実践),および,土木学会論文集・特集号(土木計画学)において,合同で能登半島地震に関する論文を募集します.
本特集企画に応募・掲載された論文については,各論文へのリンクを一体的にとりまとめた特設ページ(土木学会論文集(土木計画学):能登半島地震特集バーチャル企画)を土木計画学研究委員会ホームページの中に設け,研究成果の集約と一体的な公表を行います.
投稿資格,投稿から掲載決定・刊行までのスケジュールは,各論文の要項・要領に準拠します.詳しくは「災害関連調査情報」ページ最下段を参照ください.
<各論文募集の締切・要領>
●土木学会論文集・特集号(土木計画学)Vol. 81:2025年6月20日 → 投稿要領等はこちら
●土木学会論文集・通常号(土木計画学:方法と技術)/土木学会論文集・通常号(土木計画学:政策と実践)における本特集企画への応募期限:2025年12月12日
→ 投稿要領等はこちら
土木学会論文集・特集号 (土木計画学), Vol. 81, No. 20 への投稿論文募集
土木計画学研究委員会では,「土木学会論文集・特集号(土木計画学),Vol.81,No.20」および「Journal of JSCE ・Special issue(Infrastructure Planning and Management),Vol.81,No.2」(2026年4月発行予定)への投稿論文を募集します.土木計画学研究・講演集で発表された講演用論文の内容をさらに充実させた論文を,奮ってご投稿下さい.詳細はこちらのページをご参照下さい.
第72回土木計画学研究発表会・秋大会(企画提案型)
Date
2025年11月22日(土)・23日(日)・24日(月)
Venue
福井工業大学 福井キャンパス
第72回土木計画学研究発表会・秋大会(企画提案型)実施要領
第72回土木計画学研究発表会秋大会(企画提案型)の研究発表募集等について,以下のとおりお知らせいたします.
- 部門は(I)企画論文部門,(II)スペシャルセッション(SS)部門の2つです.企画論文部門は,オーガナイザーを公募し提案された企画テーマでの論文公募を行い,口頭発表またはポスター形式での発表を行うものです.SS部門は,原則として既存の研究小委員会が主催して,研究討議・意見交換を中心にセッションを構成するもので,本大会では12セッション(1セッション1コマ)を限度とします.セッション上限を超える応募があった場合の優先度は「土木計画学研究委員会主催,研究小委員会主催,その他」の順とし,採択できない応募がでる場合がありますこと,ご了承ください.また,企画論文部門・SS部門の並行セッションは最大10 会場を想定しております.
- 企画論文部門において,1人が発表者として発表できる件数は1件とします(連名は含みません).また,SS部門での発表および連名も含みません.なお,SS部門における発表も最大1回までとします.
- 応募後の論文タイトル・発表者・連名者の変更はできません.
- 発表会当日は,聴衆の便宜のため講演論文あるいは資料をお持ちいただいてもかまいません.
1. 実施期日
2025年11月22日(土)・23日(日)・24日(月)
*大会開催期間中は、秋の観光シーズンにおける連休期間のため、福井市内のホテルの逼迫が懸念されます。早めにホテルの予約を行なって頂きますようお願いいたします。
2. 開催場所
福井工業大学 福井キャンパス
3. 各部門への論文応募方法について
- いずれの部門もHPより応募してください.郵便でのお申込みは受け付けません.
- 最終プログラムは10月中旬に決定する予定です.また,発表会前(10月下旬を予定)に論文をWEBサイトよりダウンロードできるようにいたします.
企画論文部門
- 応募締切:2025年7月18日(金)17時まで
申込HP:https://jsceip.confit.atlas.jp/login
企画セッション一覧:PDFファイル
*新しい投稿システムに移行しました.申し込みにはA-Pass(旧Confitアカウント)が必要です.
- 発表会前原稿提出締切:2025年10月10日(金)正午まで
PDFファイル形式の原稿(土木学会論文集フォーマット,ただし英文要旨は任意,上限20ページ,PDFファイル容量の上限3.0メガバイト)をHPより投稿してください.これを用いて講演集を作成します.講演論文の執筆要領は,HPをご参照ください.
*企画論文部門では,締切日までにご投稿頂けない場合は講演集には論文が掲載されず,論文タイトル及び著者名の表記のみとなります.
スペシャルセッション (SS) 部門
- 当日資料のみでも結構です.新投稿システム移行にともない,SS部門における事前投稿については現在検討中です.
スペシャルセッション一覧:PDFファイル
4. 土木学会論文集・特集号(土木計画学)への投稿資格について
企画論文部門へ期限までに投稿された論文のうち,土木学会論文集・特集号(土木計画学)の投稿の手引に従った形式(ただし英文要旨は任意)で執筆され,かつ2ページ以上の分量である論文については,土木計画学研究・講演集に掲載される論文として見なされ,土木学会論文集・特集号(土木計画学)(以下,特集号と表記する)への投稿資格が得られます.論文タイトルと要旨のみで構成されており本文が記載されていないなど,定められた形式に従っていない原稿は,大会運営小委員会の判断により,土木計画学研究・講演集に掲載されません.その場合,土木学会論文集・特集号(土木計画学)への投稿資格は与えられませんのでご注意ください.ただし,特集号への投稿資格を満たさない投稿論文であっても,企画論文部門セッションで発表することは可能です.
また,論文投稿されたにも関わらず実際には大会にて発表されていない論文,著者以外により発表が行われた論文,およびSS部門へ投稿された論文についても,特集号への投稿資格はありません.詳しくは,計画学ホームページをご覧下さい.
https://jsce-ip.org/publications-journals/d3/
5. 今後の流れ
発表希望者
- HPを通して,第一希望のセッションを明記し論文発表を申し込む.続いて,事務局より発表希望者へ,2025年8月25日(月)から8月29日(金)の間に論文発表採否結果が連絡される.
- 発表が採択された場合は,期日までに論文をWebから投稿する.なお,発表採否の状況によっては,発表申込のキャンセル,または,第一希望セッション以外のセッションで発表をお願いする可能性があることをご承知おきください.
オーガナイザー
- 企画セッション:Web(詳細については後日メールにて送付)を通して,発表概要を確認して発表採否を決定する.採否は2025年8月1日(金)から8月22日(金)17時までに行う.
- SSセッション:Web(詳細については後日メールにて送付)を通して,2025年8月1日(金)までに発表者の登録を行う.
*企画論文部門における各テーマのセッション数は大会運営小委員会で決定する.発表論文の多いセッションについては,ポスターセッションを積極的に活用するなどして,討議時間を確保するよう調整を行う.セッションの成立要件は発表論文が5本以上であることとし,1つの企画論文部門テーマへの発表希望者数が5本に満たない場合には,原則として当該テーマは廃止される.ただし,他の企画論文部門テーマのオーガナイザーとの調整によりテーマを統合することは妨げない.
6. 論文投稿料について
- 企画部門の発表会投稿料は,講演1件につき5,940円です.発表会に参加するためには,別途参加費が必要となりますのでご注意ください.なお,オーガナイザーによる採否決定(2025年8月29日(金))後のキャンセルは,一切認められません.発表(講演)を辞退されても,発表会投稿料として料金を請求させて頂きますので十分にご注意ください.
- SS部門は,1セッションにつき,9,900円(参加費別)です.
7. 参加申込みについて
- 発表会に参加される方(発表者,一般聴講者,オーガナイザー)は全員参加登録および参加費の支払いが必要です.
- 参加費は一般5,940円,学生2,970円です.なお,お支払い頂いた参加費は返金できませんのでご注意ください.
- 参加費には土木計画学研究・講演集代も含まれます.参加登録者には,発表会前に原稿をウェブサイトよりダウンロードできるようにします.なお,講演集CD-ROMは廃止となりました.
- 新システム移行にともない,申込方法については現在詳細を検討中です.決まり次第HPでお知らせします.
8. 問い合わせ先
土木計画学研究委員会秋大会運営小委員会
e-mail: keikaku72@jsce.or.jp
※土木計画学研究委員会HP http://www.jsce.or.jp/committee/ip/index.htm
参考:各種スケジュールのまとめ
企画論文部門
- 企画テーマの応募 2025年6月13日(金)まで【終了しました】
- 発表希望者の論文題目・概要の登録 2025年6月20日(金)~2025年7月18日(金)
- オーガナイザーによる採否決定期間 2025年8月1日(金)~2025年8月22日(金)
- 発表希望者への採否通知期間 2025年8月25日(月)~2025年8月29日(金)
- 論文投稿 2025年10月10日(金)まで
スペシャルセッション(SS)部門
- テーマの申請 2025年6月13日(金)まで【終了しました】
- 発表者の決定 2025年8月1日(金)まで
研究発表会の人材育成への貢献
Date
2024年11月17日
Venue
第70回土木計画学研究発表会
(スペシャルセッション)
研究発表会の人材育成への貢献(主催:土木計画学研究委員会)
土木計画学研究発表会は,研究者同士の情報交換・交流の場であるとともに,学生の教育の場でもある.研究発表会で他の大学の学生や教員・実務者の発表に触れることが,学生のモチベーションの向上や,職業意識の醸成,土木計画や,その対象に対する愛着等の源泉になると考えられる.本セッションでは,若手の研究者である博士課程の学生に登壇いただき,博士進学のモチベーションを探るとともに,研究発表会への参加によって得られるものなどを聞くことで,これからの世代に魅力的な土木計画学とその対象,さらには研究発表会の在り方についての示唆を得るものとする.
■基調講演
「日本の都市・交通・インフラ計画の若手研究者への期待」 Kay W. Axhausen スイス連邦工科大学チューリッヒ校
■登壇者
・ 長曽我部まどか(鳥取大学工学部社会システム土木系学科)
・ 瀬谷 創(神戸大学大学院工学研究科市民工学専攻)
・ 渡邉 萌(東京大学大学院工学系研究科社会基盤学専攻)
#110 MaaSの実践・実証と理論の包括的研究小委員会 成果報告会
Date
2025年5月30日
Venue
日本教育会館(東京都千代田区一ツ橋)
#110 MaaSの実践・実証と理論の包括的研究小委員会 成果報告会
■ 開催日時:2025年5月30日(金)0930~1200
■ 場所:日本教育会館 第二会議室(東京都千代田区一ツ橋2丁目6−2) ※同日午後,同会場にて一般公開型の(一社)JCoMaaS総会を開催予定
■ 定員:対面のみ80名
■ 参加費の有無:なし
■ 主催:土木学会 土木計画学研究委員会「MaaSの実践・実証と理論の包括的研究小委員会」
■ 開催主旨:
土木学会土木計画学研究委員会「MaaSの実践・実証と理論の包括的研究小委員会」では,Mobility as a Service(MaaS)について,蓄積された実践・実証的知見と,理論面の双方から研究を展開することを趣旨として活動を行ってきた.我が国ではMaaS元年と称された2019年以降,様々なMaaS関連のパイロットプロジェクト(モデル事業)が全国各地で取り組まれてきた.MaaSの取り組みを通じ,都市部や地方部が抱える様々な交通や都市,ライフスタイルに関連する問題・課題の解決が期待されてきた.一方で,パイロットプロジェクトの実施から実装への移行がスムーズにできていないという現実や,技術シーズと地域ニーズのミスマッチも散見されるなどの課題も論じられる.これら潮流を踏まえ,当小委員会では日本国内を中心にMaaSの現在地,社会実装に至るまでのフェーズ,広い視点での価値の捉え方,都市政策との接続可能性などについて,議論や独自調査を重ねた.本セミナーでは,小委員会活動の取りまとめとして,各議論および調査から得られた成果を報告するとともに,更なる議論への展開を目指す.
■参加申し込み
オンラインフォームより参加申し込み
オンラインフォームへのアクセス方法を含めて詳細は小委員会ウェブサイトに記載
https://sites.google.com/view/jscemaas/home/events/1day-seminar/
■プログラム案:
- 開会挨拶・趣旨説明
- 小委員会における取り組みの概要報告
- 討議:委員からの話題提供・討議およびフロアとの質疑により構成
- 討議1「MaaSの現在地(仮)」(40分)
- MaaSの概念が提唱されて以降,各種の実証実験や実装の取り組みが行われてきた.一方,各取り組みにおいて何が目指され,検証され,残されたかについて,俯瞰的かつ横断的な検証は限定的である.本討議では,小委員会が実施した質問紙調査結果を織り込みながら,我が国におけるMaaSの現在地に関する議論を取り纏める.
- 討議2「MaaSのフェーズ(仮)」(40分)
- MaaS関連の実証実験が各地で実施されてきた一方,実装への到達には課題も散見される.その過程は実証実験・実証の二段階ではなく,地域における各関係主体の関与などを含めて,様々な段階があるように見受けられる.本討議では,MaaSの実装に至る「フェーズ」に関する仮説設定から一部検証を含めて,関連する話題提供を織り込みながら議論を取り纏める.
- 討議3「MaaSの社会的価値(仮)」(40分)
- MaaSにどのような価値や効果を求めるかは,実装に至る過程においても重要な要素となる.MaaSの取り組みを通じて得られうる価値は,直接的なものから間接的なものに至るまで広範にわたるが,包括的な議論は未だ限定的である.本討議ではMaaSがもたらしうる社会的な価値を広い視点で扱い,小委員会での一部検証を織り込みながら議論を取り纏める.
- 討議1「MaaSの現在地(仮)」(40分)
- 小委員会活動成果を踏まえた総括
第71回土木計画学研究発表会・春大会(自由投稿型)【開催は終了いたしました】
Date
2025年6月7日(土)–8日(日)
Venue
香川大学幸町キャンパス
第71回土木計画学研究発表会・春大会(自由投稿型)
実施要領
実施期日・開催場所
- 実施期日:2025年6月7日(土)・8日(日)
- 開催場所:香川大学幸町キャンパス
- 開催場所へのアクセス・会場配置図・会議室の予約等のご案内は,開催校 Web サイトを参照してください.
発表会プログラム
プログラム(暫定)は下記から参照してください.
- プログラム (PDF) [5/1版]
- 氏名・所属等,重要な修正事項がございましたら春大会運営小委員会までご連絡ください.
- 発表会までに発表取り下げ・セッション内での発表順序の変更などがある場合があります.発表会当日は必ず最新版をご参照の上ご来場ください.
発表要領
- 発表者の皆様は,発表要領 (PDF) をご確認の上ご準備ください.
参加申込み
参加申込サイト:土木学会本部行事参加フォーム
- 発表会に参加される方(発表者・セッション座長・一般聴講者等)は全員参加登録および参加費のお支払いが必要です.
- 参加費:一般 5,940 円,学生 2,970 円です.参加費の支払はクレジットカード決済(6/1(日) 17:00 まで)・コンビニエンスストア決済(5/25(日) 17:00 まで)のみです.請求書払いは対応しておりません.
- 当日参加の受付は行いません.確実に発表会までの参加登録をお願いいたします.特に,共著者のうち他の発表の発表者となっていない学会参加者の参加登録漏れにご注意ください.
講演申込み(論文投稿)
論文投稿
講演申込みは締め切りました.多数のご投稿ありがとうございました.
-
- 論文投稿料は講演1件につき 5,940 円です.投稿後に講演を辞退された場合であっても,論文投稿料を請求させていただきますのでご留意ください.投稿料の請求書は,4月下旬~5月上旬にメールにて配信される予定です.
- 発表会に参加するためには,別途参加登録が必要となりますのでご注意ください.
- 春大会への論文投稿は土木学会の正会員である必要はありません.後述する特集号へご投稿いただく場合は土木学会の正会員である必要があります.現在非会員で投稿を希望するみなさまは,お早めに入会手続きをお願いします.
発表希望分野の分類
以下から発表希望分野を選択してください.なお,プログラム編成の都合により第一希望に添えない場合があります.
- 発表希望分野Ⅰ(特別論文セッション)
充実した議論を実現するための「特別論文セッション」を実施します.特別論文セッションでは,最大で30編程度を採択し,論文内容を踏まえたコメントに基づいた議論を行います.- 投稿論文数・論文内容により,発表希望分野IIIでの発表となる場合があります.
- 1件当たりの持ち時間は45分です(発表25分・コメンテータによるコメント10分・討議10分).
- 特別論文セッションでの発表を希望される方は,8ページ以上の論文を投稿する必要があります.
- 発表者は投稿時に希望するコメンテータを伝えることができます.
- 発表希望分野II(手法等分野横断的区分)
研究対象ごとの発表区分(下記,発表希望分野III)に加えて,研究で用いた方法論に注目した分野横断的区分でセッションを構成します.分野横断的区分セッションで発表を希望される場合には,以下の5つから選択いただけます.さらに,ご希望の司会兼コメンテータを伝えることができ,これらの情報を参考に専門性の高い研究者への司会依頼を行うなどを検討します.発表希望分野IIの発表時間は12分を標準とします.なお,適切なセッションを組めない場合には,発表希望分野Ⅰのセッションでの発表になります.- 新分析手法:まだ適用事例の少ない統計的手法(例:機械学習的分析手法)や記述的研究(例:物語研究)などの有効性等を議論する研究
- 理論モデリング:実現象の理論的なモデリング,情報科学やゲーム理論などを駆使した手法について議論する研究
- 統計分析解釈:一般的な統計分析の考察が重要な位置を占めており,その内容や妥当性について重点的に議論する研究
- 海外事例:海外事例について集中的に議論したい研究
- その他:重点的に議論したい分野横断的内容があればそのキーワードを直接書いていただくことも可能です.
- 発表希望分野III(研究対象区分)
発表希望分野I・IIに当てはまらない発表については,下記の5分野から希望順に2つ選択し,キーワードから最大4つのキーワードを選んでください.適当なキーワードがない場合,投稿者によるキーワードを1つだけ加えてください.発表希望分野IIIの発表時間は12分を標準とします.- A. 計画論・計画情報:計画基礎論,計画手法論,システム分析,調査論,公共事業評価法,財源・制度論,プロジェクト構想,施工計画・管理,維持管理計画,意識調査分析,計画情報,情報処理,市民参加,GIS,リモートセンシング,測量,環境計画,防災計画,河川・水資源計画,ライフライン計画・設計,地球環境問題
- B. 地域・都市・景観:国土計画,地域計画,都市計画,地区計画,住宅立地,産業立地,人口分布,地価分析,土地利用,市街地整備,再開発,景観,公園・緑地,観光・余暇,空間設計,イメージ分析,土木史
- C. 交通現象分析:発生交通,目的地選択,交通手段選択,経路選択,出発時刻選択,活動分析,時間利用,交通行動調査,交通意識分析,交通行動分析,自動車保有・利用,駐車需要,交通ネットワーク分析,土地利用・交通・環境統合モデル,観光・余暇行動
- D. 交通基盤計画:総合交通計画,地区交通計画,公共交通計画,歩行者・自転車交通計画,道路計画,鉄道計画,空港・港湾計画,ターミナル計画,駐車場計画,物流計画
- E. 交通運用管理:交通流,交通容量,サービス水準,交通制御,交通管理,交通安全,交通情報,交通環境,公共交通運用,交通弱者対策,水上交通,空港管理,交通量計測,TDM,ITS,モビリティマネジメント(MM)
土木学会論文集・特集号(土木計画学)への投稿
本研究発表会で発表された論文のうち,一定の条件を満足する論文については,土木学会論文集・特集号(土木計画学)への投稿資格が与えられます.詳しくは,論文募集要項(2025年度)を参考にしてください.特に,特集号へご投稿いただく場合は土木学会の正会員である必要があります.現在非会員で投稿を希望するみなさまは,お早めに入会手続きをお願いします.
優秀ポスター賞
ポスターセッションで発表された研究のうち,発表時点における学生(博士学生含む)については,優秀ポスター賞の選考対象となります.本年度の受賞者はこちらの皆さんです.おめでとうございます.
CPD受講証明を必要とされる方へ
- 本研究発表会は土木学会継続教育CPD (Continuing Professional Development) プログラムの認定を受けています(JSCE25-0441,JSCE25-0442).受講証明書をご希望の方は現地会場の受付にて申請してください.
- 建設系CPD協議会加盟団体CPDシステム利用者は,各団体のルールに沿ってCPD単位の申請をお願いします.他団体へCPD単位を登録する場合はその団体の登録のルールに則って行われます.単位が認定されるかどうかは直接その団体にお問い合わせください.
注意事項
- 原則として口頭発表・ポスターセッションの全てについて対面で実施する予定であり,Web 配信は提供しません.
- 参加費の請求書払には対応していません.論文投稿料については請求書PDFを連絡先担当のアドレスに配信します.
- 参加費には土木計画学研究・講演集代も含まれます.参加登録者には,発表会前に原稿をウェブサイトよりダウンロードできるようにします.なお,講演集CD-ROMは廃止となりました.
- 行事参加費の決済(クレジットカード決済・コンビニエンスストア決済)完了後の返金はできません.
- 学会としての昼食・朝食等の提供はなく,参加費は食事代を含みません.学会期間中に利用可能な食堂等については開催校 Web サイトの案内を参照してください.
- 今大会では一時保育サービスの提供があります.
問い合わせ先
土木計画学研究委員会春大会運営小委員会
e-mail: keikaku71@jsce.or.jp
#11 地域の課題に徹底的に寄り添うITS事業形成を目指して
Date
2025年1月16日
Venue
コモレ四谷タワーコンファレンス
シンポジウム「地域の課題に徹底的に寄り添うITS事業形成を目指して」
■担当
多様な地域課題を解決する道路交通・ITS事業形成に向けた研究ネットワーク構築研究小委員会
■開催趣旨
土木学会では,1998年からITSに関する研究活動を継続してきた.25年間に渡る活動を通じて,地域での技術・サービスの実装にかかる現状と課題について,産官学からの多様な研究メンバー・関係者とによる実践活動を通じて整理してきたところである.
しかし,地域の道路・交通事業においてITSの存在感は決して大きくない.その理由について,地域における産官学ステークホルダーのITSに対する関心の低さにあるとの仮説に立ち,関心を高めるための仕掛けとして,多様なステークホルダーが参加する地域ミニシンポジウムを多数開催してきた.しかし,依然として道路交通分野以外のステークホルダーへのリーチに課題を抱えている.
本シンポジウムでは,多様な地域の課題に徹底的に寄り添うITSへの展開を目指して,活動中の「多様な地域課題を解決する道路交通・ITS事業形成に向けた研究ネットワーク構築研究小委員会(小委員長:清水哲夫(東京都立大学教授))」の委員が,これまでの活動状況を振り返りながら改めて地域実装に向けた課題を認識するとともに,深刻な地域課題を抱えるいくつかの地域から外部ゲストを招き,課題解決に向けてITS研究開発が持つべき視点や,これからの事業形成のあり方について議論する.
■日時・会場
2025年1月16日 13:00~17:30
コモレ四谷タワーコンファレンス(オンライン併用)
■定員
80名(会場),100名(オンライン)
■参加費
無料
■プログラム
第一部「多様な地域課題を解決する道路交通・ITS事業形成に向けた研究ネットワーク構築研究委員会の活動を振り返る」
13:00〜13:30 土木学会におけるこれまでのITS研究委員会活動 清水哲夫(東京都立大学)
13:30〜15:00 パネルディスカッション「小委員会メンバーが語る悩み・本音・野望を共有する」
コーディネーター:清水哲夫(東京都立大学)
話題提供・パネリスト:小委員会メンバー一同(一部オンライン参加)
パネリスト:竹下正一(国土交通省道路局ITS推進室長)
第二部「これからの課題解決型地域ITS事業を構想する」
15:30〜15:45 吉田正氏の業績を振り返る 菊地春海(横河ブリッジ)
15:45〜17:15 パネルディスカッション「地域からの課題解決ニーズを受け止める」
コーディネーター:清水哲夫(東京都立大学)
話題提供・パネリスト:赤星健太郎(台東区:浅草地区の新たなまちづくりを構想する立場から),沼田尚也(倶知安町:観光DXやオーバーツーリズム問題に取り組む立場から),塩士圭介(㈱日本海コンサルタント:能登半島地震・水害からの復旧・復興に関わる立場から)
パネリスト:岸邦彦(北海道大学:小委員会副委員長),廣瀬健二郎(国土交通省道路局道路経済調査室長)
コメンテーター:森地茂(政策研究大学院大学)
17:15〜17:30 まとめ〜研究小委員会の次の展開について
#250 The 15th UTokyoIPL-CUTI Special Seminar
Date
2024年11月13日
Venue
東京大学
#250 The 15th UTokyoIPL-CUTI Special Seminar
We will conduct a special seminar, in which Prof. Saksith Chalermpong (Chulalongkorn University) is invited to give a talk about electric motorcycles in Bangkok. This event is held in a hybrid style from 9:30am-11:00am (Japan Standard Time), November 13th (Wednesday), 2024.
We hope you will join us for the event and engage in this important conversation. The details are shown as follows. Thank you.
[The 15th UTokyoIPL-CUTI Special Seminar]
1) Time and day: 9:30am-11:00am (Japan Standard Time), November 13th (Wednesday), 2024
2) Place: Seminar room of International Project Lab, Department of Civil Engineering, UTokyo (3rd floor of Engineering Building No.11, Hongo Campus, UTokyo) and Zoom meeting room (https://u-tokyo-ac-jp.zoom.us/j/82526455613?pwd=anzCIUMZj9v7hIybPoYbhW1GgLlV0e.1, Meeting ID: 825 2645 5613, Passcode: 589918)
3) Presentation
– Presenter: Prof. Saksith Chalermpong (Chulalongkorn University)
– Title: Factors Influencing the Decision to Switch to Electric Motorcycles Among Various Motorcycle Driver Profiles in Bangkok
– Abstract: Carbon emissions, a major driver of climate change, represent a critical global challenge, with significant contributions from the transportation sector. To reduce carbon emissions from this sector, many countries have actively promoted the adoption of electric vehicles (EVs) as alternatives to internal combustion engine (ICE) vehicles. This study investigates the potential of electric motorcycles (EMs) to address these challenges in Bangkok, Thailand. By analyzing stated preference survey data through a binary logit model, we examined preferences among different types of motorcyclists, including traditional motorcycle taxi drivers, app-based motorcycle taxi drivers, and private motorcycle owners. Our analysis considered factors such as purchase price, maintenance cost, operational cost efficiency, and driving range. The findings indicate that socio-demographic attributes, driving behavior, and motorcycle usage significantly influence the likelihood of switching to EMs. Notably, app-based motorcycle taxi drivers are 17.5% less likely to switch to EMs compared to private motorcycle owners, while traditional motorcycle taxi drivers show no significant difference in switching likelihood. This study emphasizes the importance of targeted policies and incentives to foster EM adoption, offering valuable insights for policymakers and manufacturers aiming to enhance sustainable transportation in Bangkok and comparable regions in the global south.
4) Short bio of presenter
Saksith Chalermpong is Professor in Civil Engineering at Chulalongkorn University, where he teaches transportation engineering, planning, and policy. He also serves as Deputy Director of Chulalongkorn University Transportation Institute. His research interests include urban mobility, public and informal transportation, and sustainable transportation. He has published extensively in the field of transportation and has provided expert advice on important public issues to several government agencies in Thailand, including Department of Land Transport, Office of Transport Planning and Policy, and Bangkok Mass Transit Authority. Dr. Chalermpong received his bachelor’s degree in civil engineering from Chulalongkorn University, his master’s degree from MIT, and his doctoral degree from UC Irvine, both in the field of transportation.
5) Charge: free
6) Language: English only
7) Participation: Please contact Ms Tomoko Samukawa (samukawa@ip.civil.t.u-tokyo.ac.jp) for joining this seminar, but you can join the seminar even without pre-registration.
#249 Axhausen教授を囲む交通計画・交通行動分析の連続国際セミナー
Date
2024年11月7, 14, 26日
Venue
東京大学 本郷キャンパス
#249 Axhausen教授を囲む交通計画・交通行動分析の連続国際セミナー
この度、 Axhausen教授を囲む交通計画・交通行動分析の連続国際セミナーを以下通り開催します。
開催日は11月7日、11月14日及び11月26日で、場所と時間は以下の通りです。
場所:東京大学本郷キャンパス工学部14号館802号室 (8F)
時間:17時~19時
事前登録は不要です。皆様のご参加お待ちしております。
On November we will be holding a series of international seminars with the participation of Profesor Kay Axhausen.
The seminar will be held on November 7, November 14 and November 26. The place and time for all seminars is as follows:
Place: The University of Tokyo, Hongo Campus, Engineering Building 14th, Room 802 (8F)
Time: 17:00~19:00
Registration for these events is not required. We look forward to your participation.
詳細プログラム|Detailed Program:
第1回:11月7日(木) November 7th-Chair: Daisuke Fukuda, UTokyo
- Krittanai Sriwongphanawes – UTokyo (D2): “The Value of Predicting the Future: Valuation of Different Types of Information in Departure time choices Under Stochastic Traffic Conditions”
- Okazaki Ryota – Shibaura Tech (M2): “Personalized menu design for day-to-day home delivery management”
- Hiroshi Uemura – UTokyo (D2): “Preferences for Shared Micromobility Services in Japanese Urban Areas”
- Yusuke Hara – Tohoku University (Associate Professor): “Latent Alternative Model: How do we capture the unobservable attributes of activities?”
第2回:11月14日 (木) ・ November 14th-Chair: Giancarlos Parady, UTokyo
- Satoki Masuda – Utokyo (D2): “Dynamic Reconfiguration Strategies for Managing Shelter and Road Congestion in Urban Emergency Evacuations”
- Riki Kawase – Science Tokyo (Assistant Professor): Stochastic Dynamic Optimal Shared Autonomous Vehicle Systems: Exact Solutions and Theoretical Properties”
- Giancarlos Parady – UTokyo (Lecturer ): “Going the extra mile: Estimating the willingness to travel to meet with friends using a joint destination choice model”
- Toshinori Ariga – Chiba University (Associate Professor):”Location of Point of Interests and Dynamic Temporal Population Change”
第3回:11月26日 (火) ・ November 26th-Chair: Yuki Oyama, UTokyo
- Zhang Zhiwei – Kumamoto University (D1):” Immobility or soft refusal? Exploring respondent attitude on the quality of household travel survey “
- Koki Sato – UTokyo (M1):” Analysis of chat data in group destination choice using large language models”
- Yuki Oyama – UTokyo (Associate Professor): ” Global path preference and local response: A link-based route choice model with decomposed reward functions “
- Hajime Seya – Kobe University (Associate Professor) :” Global grid population projection by spatial econometric model considering rank-size rule “
#248 40th Science Tokyo TSU Seminar
Date
2024年11月6日
Venue
東京科学大学 大岡山キャンパス
#248 40th Science Tokyo TSU Seminar
11月6日に元デンマーク工科大学・交通研究所・主任研究員であったDr.Henrik Gudmundsson(ヘンリック・グッドムッドソン氏)をお招きし,大学統合後初めてのTSU(Transport Studies Unit)セミナーを下記の要領で開催いたします.
対面のみで開催予定ですが,オンラインでの参加を希望される方は花岡までご連絡をお願いします.
ご参加をお待ちしております.
日時:2024年11月6日(水)14:00-15:00頃
場所:東京科学大学大岡山キャンパス石川台3号館1階I3-107 (I311)
講演者:Dr.Henrik Gudmundsson, Senior Consultant, CONCITO, Denmark
題目:Sustainable Urban Mobility and Local Climate Planning in Europe and Denmark, in a Multi-level Governance Context.
概要:Transport is a main source of greenhouse gas emissions in most countries and cities. Transport is also an activity which can be hard, slow, and potentially costly to fully decarbonize. Moreover, decarbonization of transport must be considered in the context of other key functions and harmful impacts of the increasing demand for mobility. It is therefore widely recognized that policies at multiple levels should be well aligned if transport is to contribute to the timely end effective delivery of global, regional, national, and local climate targets. The presentation will introduce key European top-down policies for sustainable transport and decarbonization based in the so-called fit-for-55 package, as well as policies at the national and local level. The presentation will especially highlight the unique Danish example of voluntary local Climate Action Plans for all Danish municipalities and how these plans are addressing the transport decarbonization challenges. A topic for reflection is what local climate action can bring to the transformation of transport and mobility systems, and how such actions can be aligned with national and continental targets, policies, and governance frameworks for sustainability and decarbonization.
講演者紹介:ヘンリック・グッドムッドソン氏は,1988年にロスキレ大学を修了(環境計画)後,デンマーク環境保護省並びに空間計画省において,持続可能な交通とモビリティ,環境政策等の実務に従事されました.その後,1993年よりデンマーク国立環境研究所において研究員として勤務し,コペンハーゲン-マルメ間のウアスン海峡大橋をはじめとする,デンマークにおける幾つかの大規模プロジェクトの環境影響評価に携わっておられます.2000年にコペンハーゲン・ビジネススクールにおいて経営学博士号を取得後は,デンマーク工科大学・交通研究所において,主に,パフォーマンス指標とモニタリング,交通計画策定における知識技術の活用,交通政策の制度的側面等に関する研究及び実務に従事されました.また,同氏は,欧州連合・欧州議会の持続可能な交通に関するプロジェクトや,米国運輸学会における持続可能性並びにパフォーマンス指標に関する委員会のメンバーも勤めていました.
#10 気候変動適応におけるリアルオプションを考慮した沿岸まちづくり
Date
2024年11月5日
Venue
秋田アトリオン及びウェビナー
#10 気候変動適応におけるリアルオプションを考慮した沿岸まちづくり
■担当
沿岸まちづくりにおける経済学的手法研究小委員会
■概要
厳しい財政制約の中で不確実性の高い気候変動に適応していくには,これまで海側の論理だけで考えてきた海岸防災施設について陸側の状況を併せて考えるためのプロセスが必要になります.本小委員会では,海岸工学と土木計画の専門家が共同して,気候変動により今後予想される海面上昇と高潮・高波による被害の拡大に対応する最適な沿岸まちづくり施策について研究を行っています.リアルオプション法を適用することで,将来に実現し得るシナリオを網羅的に考慮しながら,海岸施設整備の組合せや,堤防嵩上げのタイミングと高さおよび回数,養浜の頻度と規模,高台移転等の土地利用施策について,タイミングと施策の組み合わせ最適化手法の構築を目指しています.本シンポジウムでは,本小員会のこれまでの研究成果を紹介します.
■日時・会場
2024年11月5日(火)18:00-19:30
秋田アトリオンホール
Zoomウェビナー
https://kanto-gakuin-ac-jp.zoom.us/j/82719256179?pwd=lw1GWebq30edXA0z80KtJgd38DL0J5.1
パスコード:848999
ウェビナーID:827 1925 6179
■事前登録
現地参加,ウェビナー参加のどちらも事前登録をお願いします.
https://www.jsce.or.jp/events/form/2624013
■参加費
無料
■プログラム
司会:福谷陽(関東学院大学)
シンポジウム開催の趣旨 関西大学 安田誠宏
海岸における気候変動対応について 国土交通省海岸室 井上剛介
自治体における海岸保全基本計画の検討状況 建設技術研究所 中園大介
東京湾における高潮リスクの評価 中央大学 有川太郎
リアルオプションを考慮した海岸整備:海岸工学と経済学 東北大学 河野達仁
リアルオプション手法 神戸大学 瀬木俊輔
高知海岸堤防嵩上げ整備計画への適用事例 関西大学 安田誠宏
大阪湾堤防嵩上げ整備計画への適用事例 京都大学 藤見俊夫
気候変動を考慮したまちづくり 東北大学 平野勝也
質疑・応答
■開催HPリンク
https://coastal.jp/lecture/coastalengineeringlecture/lecture71/sympo2/
■備考
本シンポジウム,海岸工学委員会・土木計画研究委員会が共同設置している小委員会である「沿岸まちづくりにおける経済学的手法研究小委員会」が執り行うシンポジウムです.
11月6〜8日にかけて秋田アトリオンで開催される第71回海岸工学講演会の「前日シンポジウム(2)」として実施されます.
https://coastal.jp/lecture/coastalengineeringlecture/lecture71/
#247 Prof. Kay Axhausen Lecture - Social Networks and Travel
Date
2024年10月31日
Venue
東京大学本郷キャンパス
Prof. Kay Axhausen Lecture - Social Networks and Travel
講演者:Kay Axhausen先生(チューリッヒ工科大学名誉教授・東京大学客員教授 )
講演題目:社会的ネットワークと交通
日時:2024年10月31日(木) 17:00-18:30
場所:東京大学 本郷キャンパス 工学部14号館144号室(2F)
Presenter:Professor Kay Axhausen( ETH Zurich Emeritus Professor, UTokyo Visiting Professor )
Date:October 31st, 17:00-18:30
Place:The University of Tokyo, Hongo Campus Engineering Building 14, Room 144 (2F)
#246 UT Transportation and Urban Research Hub - Research Seminar
Date
2024年10月11日
Venue
東京大学本郷キャンパス
UT Transportation and Urban Research Hub - Research Seminar
—
15:00-15:15 Ceremony
15:15-15:45 Yuito Hayashi (M2)
“Incorporating heterogeneity into traffic flow models with PINNs”
15:45-16:00 break
16:00-16:30 Daichi Ogawa (D1)
“Interaction Assignment in Mixed Traffic Flow”
“Game-theoretic Approaches for Urban Planning in Disaster-Prone Areas using Monte-Carlo-based deep reinforcement learning”
—
#245 Kay Axhausen教授,Moritz Kreuschner氏 特別講演会
Date
2024年10月15日
Venue
京都大学桂キャンパス
Kay_Axhausen教授,Moritz Kreuschner氏 特別講演会
どうぞよろしくお願いいたします.
日時: 10月15日(火) 16:00 ~18:00
場所: 京都大学桂キャンパスCクラスター C1-311 (Jinyu Hall)
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/access/campus/map6r_k.htm
講師: Kay Axhausen, ETH Zurich (Emiratus Professor)
題目: How to assess a major network change? The case of the e-bike city
講師: Moritz Kreuschner, TU Berlin (Research fellow)
題目: Citizen Assemblies Meet MATSim: Simulation-based Analysis of Mobility Concepts for Livable New Neighborhoods
#244 Kay Axhausen教授 講演会
Date
2024年10月7日
Venue
岐阜大学柳戸キャンパス
Kay Axhausen教授 講演会
現在名古屋大学に滞在されていらっしゃるKay Axhausen先生について,岐阜大学でも講演いただく運びとなりましたのでご案内差し上げます.参加希望の方は倉内までご連絡ください.
—-
講演者:Kay Axhausen先生(チューリッヒ工科大学教授)
講演題目:Recent experiences with GPS tracking
日時:2024年10月7日(月) 13:00-14:30
場所:岐阜大学柳戸キャンパス 工学部講義棟4階42番教室(以下のリンクの地図の17番の番号があるところ)
https://www.gifu-u.ac.jp/campus_map/tatemono_202404.png
#109 土木・都市分野への革新的技術の導入における市民合意形成上の課題にどう対処すべきか?
Date
2024年10月28日
Venue
土木学会 講堂(東京都新宿区四谷一丁目 外濠公園内)
NO.109 土木計画学ワンデイセミナー「土木・都市分野への革新的技術の導入における市民合意形成上の課題にどう対処すべきか?」
■セミナーの趣旨:
スマートシティや自動運転,AI,ドローンなどに代表される革新的技術が,土木・都市分野にも今後次々と導入され,社会課題が解決されていくことが期待されている.一方で,倫理や社会に関わる問題(プライバシー侵害,差別,社会分断,権威主義の台頭など)が生じることが懸念されている.今後導入される革新的技術が不確実なものであることから,社会へ及ぼす影響や深刻さについて予見することが難しい.
革新的技術導入における合意形成研究小委員会は,都市・地域の大きな技術的変革と,それに伴う新たな価値創造を導くことを意図し,革新的技術の導入に際して,市民との合意をどう形成するかなどについて,その方向性や制約条件について研究し,土木計画学から社会への働きかけのあり方について議論してきた.
本セミナーでは,その成果を報告し,議論することで,更なる研究のきっかけとしたい.
■日時: 2024年10月28日(月)13:30~16:30
■主催: 土木学会 土木計画学研究委員会 革新的技術導入における合意形成研究小委員会
■場所: 公益社団法人 土木学会 講堂(東京都新宿区四谷一丁目 外濠公園内) https://www.jsce.or.jp/contact/map.shtml
■方式:現地参加 及び Zoom参加
■参加費: 無料
■参加申込:
土木学会講堂参加 https://www.jsce.or.jp/events/form/402403
オンライン参加 https://www.jsce.or.jp/events/form/4024031
■プログラム:
司会:寺部慎太郎(小委員会幹事長)
13:30~13:40 :委員長挨拶 矢嶋宏光(小委員会委員長)
13:40~14:00 :革新技術導入への市民合意形成を妨げる課題 矢嶋宏光(小委員会委員長)
14:00~14:10 :革新的技術導入に伴い懸念される具体のリスク 寺部慎太郎(小委員会幹事長)
14:10~15:30 :委員等からの話題提供
● 土木・都市分野の技術の社会導入のガバナンス 松浦正浩(明治大学公共政策大学院)
● 自動運転システムの倫理規定 谷口綾子(筑波大学)
● 都市・地域計画における革新的技術導入に関わるアカウンタビリティ 羽鳥剛史(愛媛大学社会共創学部)
● 不確実性の高い技術導入に関する合意形成:フランスの地層処分場の受け入れ協議の例 青木俊明(東北大学大学院)
15:30~15:40 :休憩
15:40~16:00 :提言 矢嶋宏光(小委員会委員長)
16:00~16:20 :質疑応答・ディスカッション
16:20~16:30 :今後の展望 屋井鉄雄(運輸総合研究所)
#243 Yafeng Yin教授 東京大学工学系研究科フェロー就任記念講演
Date
2024年10月11日
Venue
東京大学工学部11号館 1階 HASEKO-KUMAホール+ラウンジ
Yafeng Yin教授 東京大学工学系研究科フェロー就任記念講演
東京大学 社会基盤学科 交通・都市・国土学研究室の大山です.
この度,ミシガン大学教授のYafeng Yin先生を東大にお招きし,以下の講演会を実施します.Yin先生が東大の工学系研究科フェロー (※) に就任されたことを記念しての会ではありますが,講演のみの聴講も可能ですので,皆様積極的なご参加をよろしくお願いいたします.
※The title of “Fellow, School of Engineering, The University of Tokyo” will be granted to persons who have their main base of activity at institutions abroad and who have carried out distinguished achievements in scholarship or education in the engineering field as well as meritorious service to the education or research at this school through exchanges with it and whose continued support via exchanges can be expected.
【Yafeng Yin教授 東京大学工学系研究科フェロー就任の記念講演】
■場所:東京大学工学部11号館 1階 HASEKO-KUMAホール+ラウンジ
■日にち:10/11 (金)
■スケジュール:
17:00-18:00 ウェルカム@ラウンジ
18:00-19:00 記念講演+記念写真撮影@KUMAホール
19:30-21:00 記念パーティー(東大キャンパス内,場所未定,5000円程度を想定)
■主催:東京大学 社会基盤学科 交通・都市・国土学研究室 / Transportation and Urban Research Hub at UT
■実施形式: ハイブリッド (オンラインの場合は18-19時のみ)
■申込フォーム:https://forms.gle/uR9NYv2Vsc3Q82M27
■記念講演概要:
Title: Modeling Mobility: The Quest for Behavioral Realism in Travel Forecasting
Abstract: Travel forecasting stands at the forefront of shaping future transportation landscapes, providing essential insights into the patterns of people and goods movement within a region. This modeling domain is crucial for guiding infrastructure development, policy adjustments, and the strategic planning to support growth. In this presentation, we delve into the transformative journey of travel forecasting methods over the past seven decades, tracing their evolution from the aggregate, zone-based four-step models from the 1950s to today’s sophisticated micro-behavioral activity-based models. We explore the paradigm shift in transportation network modeling, highlighting the progression towards increased behavioral realism. This shift has seen the conceptualization of travelers evolve from perfectly rational actors with deterministic behavior, to ‘economic individuals’ maximizing random utility, and finally to ‘social beings’ with bounded rationality. Our discussion highlights the interdisciplinary contributions from operations research, economics, and machine learning that have significantly enriched methodological approaches in travel forecasting. Furthermore, we examine the burgeoning role of artificial intelligence in travel forecasting, focusing on its potential to revolutionize model development.
#242 Abhilash C. Singh博士研究セミナー
Date
2024年9月27日
Venue
東京大学本郷キャンパス 工学部1号館 3F 324
Abhilash C. Singh博士研究セミナー
東京大学の渡邉萌です。
今週 27日 (金) AM10:00~11:00の時間帯で、東京大学本郷キャンパスにて研究セミナーを開催いたします。
私の共同研究者でもある若手研究者のAbhilash C. Singhに、欧州における調査により得られた自転車利用者の経路データの生成・経路選択モデルについて話してもらいます。
Abhilashはテキサス大学オースティン校にて修士号、2023年にImperial College Londonにて博士号を取得後、現在はダブリン大学トリニティ・カレッジ (アイルランド)にてポスドク研究員として働いています。
彼の研究内容は主に、発展的な行動モデルにより居住地の自己選択 (self-selection)による内生性に対処しながら世帯の交通行動を分析しており、これまでC.R.BhatやP.L.Mokhtarian、E.J. MillerやAruna Sivakumarらと共に実証的な研究論文を発表しています (詳しくはCVをご参照ください: https://x.gd/Abhilash)。
日時・場所は下記の通りです。私への事前連絡等は不要ですのでお気軽にご参加ください。よろしくお願いいたします。
日時: 9月27日 (金) AM10:00~11:00
場所: 東京大学本郷キャンパス 工学部1号館 3F 324
#18 計画論における生活者と来訪者(2024年・年次学術講演会)
Date
2024年9月6日
Venue
東北大学川内北キャンパス講義棟C棟C401
計画論における生活者と来訪者
特別セッション 計画論における生活者と来訪者
2024年9月6日(金) 13:30 〜 14:50
座長:金子 素子(アルメック)
[IV-122]
路面ひび割れに着目したサイクルルートのネットワークレベル舗装評価
*浅田 拓海、柳澤 ひかり (国立大学法人 室蘭工業大学)
キーワード:サイクルルート、点検支援技術、XRoad、安全性、地域インフラ群再生戦略マネジメント
[IV-123]
来訪者による交通事故の実態
*鈴木 美緒 (東海大学)
キーワード:交通事故統計、観光、来訪者
[IV-124]
観光産業における防災対応:新たな役割とエビデンスに基づく支援策
*梶谷 義雄1、吉田 護2、玉置 哲也1、山口 裕通3、鈴木 祥平4、小笠原 悠5 (1. 香川大学、2. 長崎大学、3. 金沢大学、4. 東京工科大学、5. 東京都立大学)
キーワード:能登半島地震、宿泊施設、時系列推移、復旧・復興施策
[IV-125]
観光学は地域住民にどう向き合ってきたか?
*栗原 剛 (東洋大学)
キーワード:観光学、持続可能な観光、DMO、地域住民、オーバーツーリズム
[IV-126]
人流ビッグデータを用いたニッチな観光スポットの検出
*羽間 真奈実1、福田 大輔2 (1. 大成建設株式会社、2. 東京大学)
キーワード:人流ビッグデータ、観光周遊、ニッチな観光スポット、観光マーケティング、ポアソン回帰、エシェロンスキャン法
#17 災害と復興、変わりゆく“風景”の評価(2024年・全国大会研究討論会)
Date
2024年9月2日
Venue
オンライン
災害と復興、変わりゆく“風景”の評価
令和6年度土木学会全国大会・研究討論会『災害と復興、変わりゆく“風景”の評価』
研究討論会『災害と復興、変わりゆく“風景”の評価』
概要:東日本大震災に限らず、日本では多くの災害が起き、復興への活動が続いている。そのさなか、能登半島地震が発生した。復興におけるインフラ整備は日常生活を守る防災機能にフォーカスがあたりがちだが、生活者の日々の眺めや暮らしぶりを変える影響は極めて大きい。また、被災構造物群や治水・砂防施設等が土木遺産に認定されるなど、観光資源としての側面もあり、復興により地域そのものの価値も大きく変わるといえる。いつどこで起こるかわからない災害からの復興において、風景への配慮はどれだけなされ、どのように評価されるべきなのか?
本セッションでは、被災地におけるインフラ整備の防災機能が生活への配慮に及ぼす影響や、風景としての評価、地震に限らずさまざまな災害からの復興における計画や政策の在り方について、東日本大震災での経験や、能登半島地震の復興に向けての動向とともに討論する。
討論会構成(敬称略):
1. 話題提供
長谷川 修一(香川大学)
谷下 雅義(中央大学)
片桐 由希子(金沢工業大学)
多々納 裕一(京都大学)
2. パネルディスカッション モデレーター:福田 大輔(東京大学)
パネラー:長谷川 修一(香川大学)/谷下 雅義(中央大学)/片桐 由希子(金沢工業大学)/多々納 裕一(京都大学)
第70回土木計画学研究発表会・秋大会(企画提案型)【開催は終了いたしました】
Date
2024年11月15日(金)・16日(土)・17日(日)
Venue
岡山大学 津島キャンパス
第70回土木計画学研究発表会・秋大会(企画提案型)
第70回土木計画学研究発表会秋大会(企画提案型)の概要について,以下のとおりお知らせいたします.
1. 実施期日・開催場所
2024年11月15日(金)・16日(土)・17日(日)
開催場所:岡山大学 津島キャンパス
- 大会開催期間中,岡山市内で複数の学会の開催が予定されています.早めにホテルの予約を行なって頂きますようお願いいたします.
2. 開催校ウェブサイト
開催場所へのアクセスや懇親会,一時保育等に関する情報は,開催校ウェブサイトにて配信いたします.
https://www.okayama-u.ac.jp/user/civil/Labs/regional/ip_70/index.html
3. 発表プログラム・発表要領・大会スケジュール
全体プログラム(2024年11月02日版)
詳細プログラム(2024年11月07日版)
- プログラムの内容は変更される可能性がございます.
- 大会参加者には発表会前に論文をHPよりダウンロードできるようにいたします.
発表要領
下記の発表要領を必ず確認の上,発表に臨んでいただくようお願いいたします.
*発表者にメールで添付した発表要領に誤記がありました:「11 交通計画・運用に向けた多様なデータ利活用」のコアタイムの時間帯1は正しくは 9:00-10:30 です.
第1日目 11月15日(金)
12:00 ~ エクスカーション「平成30年豪雨とその復旧・復興」に関する現地見学会
- 詳細と申込方法は開催校ウェブサイトをご覧ください.
https://www.okayama-u.ac.jp/user/civil/Labs/regional/ip_70/localsessions.html
16:00 ~ 17:00 委員会報告(岡山大学 津島キャンパス 共育共創コモンズ: OUX)
17:00 ~ 18:00 招待講演(岡山大学 津島キャンパス 共育共創コモンズ: OUX)
- 土木学会賞 論文賞:山下 三平(九州産業大学)「流域治水と雨庭の伝統」
- 土木学会賞 論文奨励賞:萩原 啓介(森ビル株式会社)「旧淀川(大川)河川沿公園形成史:明治期の公園構想と百年にわたる実現過程」
1日目には企画セッション・スペシャルセッションは実施しません.
第2日目 11月16日(土)
09:00 ~ 18:15 企画・スペシャルセッション(岡山大学 津島キャンパス 一般教育棟)
19:15 ~ 懇親会(ANAクラウンプラザホテル岡山)
- 懇親会への参加は任意です.懇親会の会費は発表会の参加費に含まれません.
- 懇親会に関する情報と申込方法は,開催校ウェブサイトをご覧ください.
https://www.okayama-u.ac.jp/user/civil/Labs/regional/ip_70/party.html
第3日目 11月17日(日)
09:00 ~ 18:15 企画・スペシャルセッション(岡山大学 津島キャンパス 一般教育棟)
4. 参加申込みについて
発表会に参加される方(発表者,一般聴講者,オーガナイザー)は,ウェブサイト上で参加登録を行ってください.
- 参加費:一般5,940円,学生2,970円(発表会講演集代含む)
- 支払いはクレジットカード払い,もしくは,コンビニエンスストア払いのみ受け付けております.請求書の発行はできません.
- お支払い頂いた参加費は返金できませんのでご注意ください.
- 申込締切はクレジットカード決済が11月10日(日)17:00まで,コンビニエンスストア決済が11/3(日)17:00までとなっております.早めの申し込みをお願いいたします.
- 当日参加の受付は行いません.確実に発表会までの参加登録をお願いいたします.特に,共著者のうち他の発表の発表者となっていない学会参加者の参加登録漏れにご注意ください.
5. 土木学会論文集・特集号(土木計画学)への投稿資格について
企画論文部門へ期限までに投稿された論文のうち,土木学会論文集・特集号(土木計画学)の投稿の手引に従った形式(ただし英文要旨は任意)で執筆され,かつ2ページ以上の分量である論文については,土木計画学研究・講演集に掲載される論文として見なされ,土木学会論文集・特集号(土木計画学)(以下,特集号と表記する)への投稿資格が得られます.論文タイトルと要旨のみで構成されており本文が記載されていないなど,定められた形式に従っていない原稿は,秋大会運営小委員会の判断により,土木計画学研究・講演集に掲載されません.その場合,土木学会論文集・特集号(土木計画学)への投稿資格は与えられませんのでご注意ください.ただし,特集号への投稿資格を満たさない投稿論文であっても,企画論文部門セッションで発表することは可能です.
また,論文投稿されたにも関わらず実際には秋大会にて発表されていない論文,およびSS部門へ投稿された論文についても,特集号への投稿資格はありません.詳しくは,計画学ホームページをご覧下さい.
https://jsce-ip.org/publications-journals/d3/
6. 論文投稿料について
企画部門の発表会投稿料は,講演1件につき5,940円です.発表会に参加するためには,別途参加登録が必要となりますのでご注意ください.SS部門は,1セッションにつき,9,900円(参加費別)です.なお,オーガナイザーによる採否決定(2024年8月30日(金))後のキャンセルは,一切認められません.発表(講演)を辞退されても,発表会投稿料として料金を請求させて頂きますので十分にご注意ください.
7. CPDについて
CPD受講証明を必要とされる方へ
- 本研究発表会は,土木学会継続教育CPDプログラムの認定を受けております.受講証明書をご希望の方は,現地会場の受付にて申請をお願いいたします.
- 建設系CPD協議会加盟団体CPDシステム利用者は,各団体のルールに沿って,CPD単位の申請をお願い致します.
- 他団体へCPD単位を登録する場合は,その団体の登録のルールに則って行われます.単位が認定されるかどうかは,直接その団体にお問合せください.
8. 問い合わせ先
土木計画学研究委員会秋大会運営小委員会
e-mail: keikaku70@jsce.or.jp
* 土木計画学研究委員会HP:http://www.jsce.or.jp/committee/ip/index.htm
#241 Abhilash Chandra Singh博士講演会
Date
2024年9月25日
Venue
名古屋大学NIC館3階会議室
Abhilash Chandra Singh博士講演会
名古屋大学の山本です.
講演会のご案内です.ご参加希望の方は,会場の都合がありますので私までご連絡いただければ幸いです.
講演者:Abhilash Chandra Singh博士(ダブリン大学)
https://abhilashcsingh.github.io/data/Singh_Abhilash_CV.pdf
講演題目:Cycling across Europe: Route choice analysis using multi-city data
日時:2024年9月25日(水) 10:30-12:00
場所:名古屋大学NIC館3階会議室
#240 Kay Axhausen教授講演会
Date
2024年9月18日
Venue
名古屋大学工学部5号館2階522講義室
Kay Axhausen教授講演会
名古屋大学の山本です.
講演会のご案内です.ご参加希望の方は,会場の都合がありますので私までご連絡いただければ幸いです.
講演者:Kay W. Axhausen先生(チューリッヒ工科大学)
講演題目:Assessing major changes in the transport systems: The case of the e-Bike-City
日時:2024年9月18日(水) 13:00-14:30
場所:名古屋大学工学部5号館2階522講義室
#239 The 13th UTokyoIPL-CUTI Special Seminar
Date
2024年7月18日
Venue
Seminar room of International Project Lab, Department of Civil Engineering, The University of Tokyo (Third floor, Engineering Building No.11, Hongo Campus
The 13th UTokyoIPL-CUTI Special Seminar
[The 13th UTokyoIPL-CUTI Special Seminar]
1) Time and day: 11:00am-12:30am (Japan Standard Time), July 18th (Thursday), 2024
2) Place: Seminar room of International Project Lab, Department of Civil Engineering, UTokyo (3rd floor of Engineering Building No.11, Hongo Campus, UTokyo) and Zoom meeting room
3) Presentation
– Presenter: Prof. Marlon Boarnet (University of Southern California)
– Title: Monetary cost, time cost, and mode choice: Transit and ridehailing in California
– Abstract: Recent studies explore how ridehailing competes with transit, documenting drops in transit ridership when ridehailing became available. However, few examine the extent to which ridehailing substitutes for other modes, such as walking or private automobiles. Using travel diary survey data and travel times and costs from the San Francisco Bay Area, we employ a mixed logit model to analyze how trip characteristics such as travel time and travel cost influence traveler’s mode choices. The results show that if ridehailing costs increase by 10%, ridehailing trips decrease by 6.97%. About half of the lost riders would switch to driving, and 20% to transit. Therefore, driving, rather than transit, is the closest substitute for ridehailing. Furthermore, 10% reductions in transit time and transit cost are associated with a 24.63% and 5.03% increase in transit trips, respectively, suggesting that reducing travel time is more effective in increasing transit ridership than lowering fares.
4) Short bio of presenter
Marlon Boarnet is Professor in the Sol Price School of Public Policy at the University of Southern California and Director of the METRANS Transportation Consortium. METRANS is the center for transportation research at USC, and a partnership of the Price School of Public Policy, the Viterbi School of Engineering, and California State University – Long Beach. METRANS spans over 15 academic departments and programs at USC, with links to over a dozen universities in the U.S. and abroad. Prior to directing METRANS, Boarnet was the founding chair of the Department of Urban Planning and Spatial Analysis at USC (2016-2022) and he served as Vice Dean for Academic Affairs in USC’s Price School from 2014 through 2015. Boarnet was chair of the Department of Planning, Policy, and Design at UC-Irvine from 2003 through 2006. Boarnet served as president of the Association of Collegiate Schools of Planning, the scholarly association of university planning departments and faculty members in the United States and Canada, from 2019-2021. Boarnet’s research focuses on land use and transportation, links between land use and travel behavior and associated implications for public health and greenhouse gas emissions, urban growth patterns, and the economic impacts of transportation. He is a fellow of both the Weimer School of the Homer Hoyt Institute for Real Estate and the Regional Science Association International. Boarnet has advised California state agencies on greenhouse gas emission reduction in the transport sector, the World Bank on transportation access as a poverty reduction tool, and numerous other public and private entities. He has been principal investigator on over four million dollars of research supported by agencies that include the U.S. and California Departments of Transportation, the U.S. Environmental Protection Agency, the California Air Resources Board, and the Robert Wood Johnson Foundation. Boarnet’s academic web page is: https://priceschool.usc.edu/people/marlon-boarnet/.
5) Charge: free
6) Language: English only
(講習会)『バスサービスハンドブック 改訂版』の出版および土木計画学講習会
Date
2024年7月30日
Venue
中央大学後楽園キャンパス
『バスサービスハンドブック ] 改訂版』の出版
および土木計画学講習会
長らく出版元品切れとなっていました『バスサービスハンドブック』の改訂版を出版いたしました.
詳細は下記のサイトをご覧下さい.
[丸善出版]
バスサービスハンドブック 改訂版 – 丸善出版 理工・医学・人文社会科学の専門書出版社 (maruzen-publishing.co.jp)
[土木学会]
土木学会 刊行物案内 (jsce.or.jp)
また,改訂版の発行を機に,下記の要領で土木計画学講習会「
日 時:2024年7月30日(火) 13:00~16:40
場 所:中央大学後楽園キャンパス3号館14階セミナールームA、B
地下鉄後楽園から徒歩5分: 文京区春日1-13-27
開催内容と申し込み方法は添付ファイルをご覧下さい.土木学会「
皆さまのご参加をお待ちしています.
#238 The 20th BinN International Research Seminar
Date
2024年6月24日
Venue
The University of Tokyo, Ito International Hall
The 20th BinN International Research Seminar
The 20th BinN International Research Seminar
Title: Future of transport planning and traffic analysis
Speaker: Honorary Prof. William Lam, University of Sydney Business School
Coordinator: Honorary Prof. Asakura Yasuo, University of Tokyo
Date:2024.6.24 1000-1130
Venue: The University of Tokyo, Ito International Hall, Special Conference Room on the 3rd Floor
Outline: Recent trends in research on transport planning and traffic forecasting, ITS technology and development, smart surveillance and traffic simulation, public transport and pedestrian studies have been supported by significant advancements in sensing technology and mathematical models. Lam, a key figure who has built a leading global transportation research community centered in Hong Kong since the 1990s, has produced many students and researchers. Through a discussion with Professor Yasuo Asakura, a close associate of Lam, we would like to explore the trends and future of advanced fields in ITS and transport research in Japan and China
#237 The 12th UTokyoIPL-CUTI Special Seminar
Date
2024年6月17日
Venue
Seminar room of International Project Lab, Department of Civil Engineering, The University of Tokyo (Third floor, Engineering Building No.11, Hongo Campus
The 12th UTokyoIPL-CUTI Special Seminar
[The 12th UTokyoIPL-CUTI Special Seminar]
1) Time and day: 4:30pm-6:00pm (Japan Standard Time), June 17th (Monday), 2024
2) Place: Seminar room of International Project Lab, Department of Civil Engineering, UTokyo (3rd floor of Engineering Building No.11, Hongo Campus, UTokyo) and Zoom meeting room
3) Presentation
Title: Strategic Investment for Green Growth in Uzbekistan
Abstract: Uzbekistan is expected to take a range of transformative actions for economic development and poverty reduction based on the concept of “green growth.” The country signed the Paris Agreement in April 2017 and submitted the 2nd Nationally Decided Contribution (NDC) in October 2021, with a target of reducing the country’s GHG emissions per unit of GDP by 35% below 2010 levels by 2030. The 2nd NDC further underlined the importance of climate resilience in promoting Uzbekistan’s socio-economic development as its landlocked territory is highly vulnerable to various natural disasters. To meet the low-carbon and climate resilient targets along the scope of green growth, the ADB’s economic diagnosis study (EDS) identifies Uzbekistan’s strategic investment options across critical infrastructure sectors — energy, transport, information and communication technology, water and waste management, and agriculture and food production systems. This study also refers to Uzbekistan’s recent urban development trends and adaptive spatial planning measures since the effectiveness of low-carbon, climate-resilient infrastructure investment for green growth depends on the degree and pattern of urbanization. From quantitative figures and qualitative discussions, key implications are drawn for Uzbekistan to leverage investment in critical infrastructure systems and move toward a green economy.
4) Short bio of presenter
Dr. Jin Murakami is Assistant Professor of Urban Planning at the Singapore University of Technology and Design (SUTD). He has specialized in the areas of transport and land use, urbanization, spatial planning and economic development, urban infrastructure finance and land policy, and urban climate policy and finance. His research focuses principally on spatial, financial, and technological drivers that influence city-regions’ global competitiveness and local livability. His current projects include an international case study of transit-oriented development (TOD) and land value capture (LVC), the impacts of airport connectivity and accessibility changes on cities, and the financialization of cities with ESG investing criteria (e.g., zero-emission transport and housing). His previous research projects have been published from international development, research, and educational institutes (e.g., World Bank, Lincoln Institute of Land Policy, Asian Development Bank) and SSCI-listed peer-reviewed journals in urban studies, economics, geography, transportation, land use policy, and environmental studies. In addition, Dr. Murakami served as Lead Author (LA) for the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) AR5 WGIII Chapter 12: Human Settlements, Infrastructure and Spatial Planning (2012-2014) and AR6 WGIII Chapter 8: Urban Systems and Other Settlement (2019-2022). He holds a Ph.D. in City and Regional Planning from the University of California, Berkeley and an M.Eng. in Civil Engineering from the University of Tokyo.
5) Charge: free
6) Language: English only
#9 令和6年能登半島地震対応特別プロジェクト・報告会【開催は終了しました】
Date
2024年5月26日
Venue
北海道大学・工学部
令和6年能登半島地震対応特別プロジェクト・報告会
【特別セッション概要】
2024年1月1日に発生した能登半島地震を受けて,土木計画学研究委員会では「令和6年能登半島地震対応特別プロジェクト」を立ち上げた.本プロジェクトでは,1.被災地域・地元大学の側方支援・技術支援,2.即応的な対応策の検討および実施機関への提示,3.被災・復旧・復興に関する共通知見化(災害現象の理解のため、将来災害に備えるため)をミッションとして掲げ,土木計画学研究委員会幹事会の統括のもと,交通・インフラWG,経済・観光WG,避難生活・復興WGとその下の各班を設置し,被災地の大学や関連他学会,行政機関,民間機関等とも連携しながら調査・分析を進めている.このセッションでは,本プロジェクトにおけるこれまでの調査・分析結果等を速報的に報告し,被災地域のよりよい復興に向けて土木計画学関係者が果たすべき役割について議論を行いたい.
【セッションの全体構成】
1. 特別プロジェクトの設置経緯と活動について(資料)
福田大輔(東京大学,土木計画学研究委員会幹事長)
2. 能登半島地震からの復興に向けて(資料)
高山純一(公立小松大学)
3.道路網被害と交通実態把握(資料)
浅田拓海(室蘭工業大学),井料隆雅(東北大学),浦田淳司(筑波大学),佐津川功季(金沢大学),力石真(広島大学),福田大輔(東京大学),山口裕通(金沢大学)
4.公共交通〜鉄道被害把握とバス輸送支援(資料1,資料2)
金山洋一(富山大学,運輸総合研究所),神田佑亮(呉工業高等専門学校)
5.緊急支援物資輸送の実態把握(資料)
樋口恵一(大同大学),山崎基浩(豊田都市交通研究所),河瀬理貴(東京工業大学),川本義海(福井大学),荒谷太郎(海上・港湾・航空技術研究所),間島隆博(海上・港湾・航空技術研究所),大窪和明(東北大学)
6.空港・港湾被害の実態把握(資料)
平田輝満(茨城大学),荒谷太郎(海上・港湾・航空技術研究所)
7.ライフライン被害の実態把握(資料)
浦田淳司(筑波大学),畑山満則(京都大学),中野一慶(電力中央研究所),廣井慧(京都大学),寺山一輝(石川工業高専)
8.地域経済・観光被害の実態把握(資料)
梶谷義雄(香川大学),藤見俊夫(京都大学),松島格也(京都大学),奥村誠(東北大学),吉田護(長崎大学),玉置哲也(香川大学),山口裕通(金沢大学)
9.インクルーシブの観点からの被災実態把握(資料)
崔善鏡(東京工業大学),小山真紀(岐阜大学)
10.地域建設業の災害時における役割
畑山満則(京都大学),柿本竜治(熊本大学),大西正光(京都大学)
11.総括コメント
多々納裕一(京都大学,土木計画学研究委員会委員長)
土木学会論文集・特集号における「政策と実践」論文の掲載について
土木学会論文集・特集号における「政策と実践」論文の掲載について
2024年5月29日
- 概要
本研究委員会の学術小委員会が審査・編集を行っている「土木学会論文集・特集号」に関して,令和6年6月募集予定の特集号より,従来の土木計画学論文(方法と技術)〔以下,方法・技術論文と略称〕に加えて,新たに土木計画学論文(政策と実践)〔以下,政策・実践論文と略称〕についても受付を行うことになりました. - 経緯
令和2年〜3年:これまで「土木計画学論文」と呼ばれてきた一群の論文群を,方法・技術論文と政策・実践論文の二つのカテゴリーに分類し,それぞれ異なる基準で査読することが適当であると決定しました.その上で,従来の土木学会論文集の「通常号」には「土木学会論文集D3(土木計画学)」(いわゆるD3)分冊だけが設置されていたところ,D3分冊:土木計画学(方法と技術),D4分冊:土木計画学(政策と実践)のという2つの分冊を設けることについて,委員会で継続的に検討してきました.
令和4年〜5年:その後の土木学会論文集の全面的な再編も相俟って,2023年より,通常号に関しては土木計画学(方法と技術),土木計画学(政策と実践)という土木計画学内の2つのカテゴリーが設けられ,それぞれ土木学会論文集編集委員会の41小委員会,42小委員会が査読を担当する体制で運用されています.一方,土木学会論文集の「特集号」に関しては,2023年までは「政策と実践」論文の受付はなされず,「方法と技術」論文のみが受付られている状況でした.また,土木計画学研究発表会(春大会・秋大会)にて発表された「政策と実践」論文は,通常号に随時投稿することを発表者各位に周知している状況でした.
令和6年前半:発表者各位の「特集号」への需要の存在を勘案すると,「通常号」のみならず,「特集号」においても「政策と技術」論文と「方法と実践」論文を併せて同時に受け付ける体制を整えることが発表者各位の利益増進に繋がるものとの認識のもと,幹事会,学術小委員会,「方法と技術」運営小委員会,「政策と実践」運営小委員会で議論を行ってきました.その上で,令和6年5月25日の土木計画学研究委員会にて,本提案が承認されました.
投稿方法の詳細については, 論文募集ページ をご確認下さい.
#236 The 11th UTokyoIPL-CUTI Special Seminar
Date
2024年4月25日
Venue
Seminar room of International Project Lab, Department of Civil Engineering, The University of Tokyo (Third floor, Engineering Building No.11, Hongo Campus
The 11th UTokyoIPL-CUTI Special Seminar
[The 11th UTokyoIPL-CUTI Special Seminar]
1) Time and day: 10:00am-11:30 am (Japan Standard Time), April 25 (Thursday), 2024
2) Place: Seminar room of International Project Lab, Department of Civil Engineering, UTokyo (3rd floor of Engineering Building No.11, Hongo Campus, UTokyo) and Zoom meeting room
3) Presentation
Title: Review on the development of transport infrastructure in Vietnam in past 30 years
Abstract: Transport infrastructure in Vietnam has been drastically improved, including road and expressway, deep seaports, and major airports, while national railway has been left behind and the development of urban railway in major cities is much slower than expected. During the past 30 years, GDP per capital of Vietnam has grown from 200 USD to over 4,000 USD. This presentation first reviews the development stages of transport infrastructure in Vietnam, together with the country’s development policies at each development stage, and then introduces recent discussion about a development plan for High-speed Railway in Vietnam.
4) Short bio of presenter
Dr. Phan Le BINH has started to work at Oriental Consultants Global (OCG) Co. Ltd. as the Deputy General Manager of OCG Hanoi Office from April 2024. He obtained his Ph.D. degree from the Department of Civil Engineering, The University of Tokyo in 2003. For nearly 20 years, he worked for Japan International Cooperation Agency (JICA), being responsible for many ODA projects in the field of transport and urban development in Asian developing countries including Vietnam, Myanmar, Laos, and Pakistan. He used to be also dispatched from JICA to Vietnam Japan University as a lecturer to teach transportation planning for five years.
5) Charge: free
6) Language: English only
#235 International Workshop on Urban Freight Analytics
Date
2024年4月23日
Venue
Kyoto University Tokyo Office
International Workshop on Urban Freight Analytics
Title: International Workshop on Urban Freight Analytics
Date: 23 April 2024, Tuesday 13:00-17:00
Organised by: Institute for City Logistics
Venue: Kyoto University Tokyo Office
Shin-Marunouchi Building, 10th floor, 1-5-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-6510
Kyoto University Tokyo Office | KYOTO UNIVERSITY (kyoto-u.ac.jp)
Language: English
Fee: free
Topic 1: Urban Freight Analytics
Speakers:
1. Professor Emeritus Eiichi Taniguchi (Kyoto University, Japan)
2. Professor Russell G. Thompson (The University of Melbourne, Australia)
3. Associate Professor Ali G. Qureshi (Kyoto University, Japan)
Topic 2: Agent-based Urban Freight Simulations
Speaker: Associate Professor Takanori Sakai (Tokyo University of Marine Science and Technology, Japan)
Abstract for Topic 1: Urban Freight Logistics
Urban Freight Analytics examines key concepts associated with development and application of decision support tools for evaluating and implementing city logistics solutions. New analytical methods are required for effectively planning and operating emerging technologies including the Internet of Things (IoT), Information and Communication Technologies (ICT) and Intelligent Transport Systems (ITS).
This workshop will provide a comprehensive overview of modelling and evaluation approaches of urban freight transport. This will include case studies from Japan, US, Europe and Australia that illustrate the experiences of cities that have already implemented city logistics, including analytical methods that address the complex issues associated with adopting advanced technologies such as autonomous vehicles and drones in urban freight transport.
The workshop will be based on the book, “Urban Freight Analytics: Big data, Models and Artificial intelligence” by E. Taniguchi, R.G. Thompson and A.G. Qureshi, CRC Press, London, 2023. Procedures for evaluating city logistics technologies and policy measures will be presented. An overview of advanced modelling approaches, including agent based modelling and machine learning will be provided. The essential features of optimisation and simulation models applied to city logistics will be highlighted. An overview of how models incorporating more uncertainty and dynamic data can be used to improve the sustainability and resilience of urban freight systems will be presented.
This workshop will also describe future directions in urban freight analytics, including hyperconnected city logistics based the Physical Internet (PI), digital twins, gamification and emerging technologies such as connected and autonomous vehicles in urban areas. An integrated modelling platform will be presented that considers multiple stakeholders or agents, including emerging organisations such as PI companies and entities such as crowd-shippers as well as traditional stakeholders such as shippers, receivers, carriers, administrators and residents.
Abstract for Topic 2: Agent-based Urban Freight Simulations
The urban freight transportation system has continually evolved with innovations in logistics and technology (e.g., urban consolidation, crowd shipping, cargo bikes, mobile hubs, parcel lockers, etc.). This evolution has been accompanied by a transformation of the retail market due to the rapid penetration of online shopping. In the coming years, urban freight transportation systems will face new challenges to bring sustainability (e.g., zero emissions) to the forefront, leverage new technologies (e.g., automated vehicles, delivery robots, drones), and accommodate further expansion of e-commerce. In this context, simulation tools are needed to evaluate new logistics solutions and provide insights to planners and policy makers.
In the field of freight modeling research, the methodology of agent-based microsimulations has received increasing attention in the last several years. SimMobility Freight (SMF), which is developed by the MIT ITS lab, is one of the state-of-the-art agent-based freight simulators and has been used for analyzing various urban logistics solutions and scenarios. In this session, Takanori will introduce key design features of SMF and studies that use SMF, including the evaluations of cargo hitching, parking demand management, off-peak deliveries, and congestion pricing, as well as recent applications of SMF in Tokyo for evaluating the locations of logistics facilities.
#234 Japan-Korea Transportation Research Networking Seminar
Date
2024年4月4日
Venue
広島大学国際協力研究科
Japan-Korea Transportation Research Networking Seminar
Japan-Korea Transportation Research Networking Seminar
Date and Time: 13:00-18:00, April 4th, 2024
Place: Large Conference Room, IDEC, Hiroshima University (https://maps.app.goo.gl/pEEiNLyqroaTLpG68)
Seminar Schedule
13:00-13:05 Opening Remark
Akimasa Fujiwara, Hiroshima University
13:05-13:15 Brief Introduction of Transportation Studies Group at Hiroshima University
Makoto Chikaraishi, Hiroshima University
Session 1: Public Transport (Chair: Giancarlos Parady, The University of Tokyo)
13:15-13:45 Metropolitan Area Size and Service Quality on Public Transport Satisfaction
Junghwa Kim, Assistant Professor, Kyonggi University
13:45-14:15 What drives the bus drivers’ job satisfaction?
Jihye Byun, Assistant Professor, University of Seoul
14:15-14:45 Mobility Experiment Twin: Shared Autonomous Vehicles for First-and-Last-Mile Public Transportation
Pham Van Son, PhD Student, Hiroshima University
14:45-15:00 Break
Session 2: Emerging Travel Modes and Active Travel (Chair: Nur Diana Safitri, Hiroshima Univ.)
15:00-15:30 Exploring attitudinal group differences in preferences for E-scooter options: focusing on the DC and LA contexts
Sung Hoo Kim, Assistant Professor, Hanyang University
15:30-16:00 Exploring Heterogeneous Private Car Sharing Decisions under Uncertainties
Li Mengxia, PhD Student, Hiroshima University
16:00-16:30 Modeling pedestrian behavior representing competitive nature between movers and stayers in urban public space
Keishi Fujiwara, PhD Student, Hiroshima University
16:30-16:45 Break
Session 3: Transportation Systems Analysis (Chair: AlOlabi Reem, Hiroshima University)
16:45-17:15 A Hazard-Based Duration Model to Quantify the Impact of Work-Related Distraction on Taxi Drivers’ Conflict Risk: A Driving Simulator Study
Tiantian Chen, Assistant Professor, KAIST
17:15-17:45 A dynamic system optimal dedicated lane design for connected and autonomous vehicles
Seunghyeon Lee, Associate Professor, University of Seoul
17:45-17:50 Concluding Remark
Feng Tao, Hiroshima University
#233 Freight Modeling and Data Collection Seminar
Date
2024年3月29日
Venue
東京海洋大学第4実験棟5階大教室
Freight Modeling and Data Collection Seminar
Freight Modeling and Data Collection Seminar
Date: March 29, 2024
Time: 13:20 – 16:30
Venue: Lecture Hall, Research Building No. 4 @ Etchujima Campus, Tokyo University of Marine Science and Technology (東京海洋大学第4実験棟5階大教室)
Program
13:20-13:30 Greetings
13:30-14:30 The following will be presented by Prof. Jose Holguin-Veras, Rensselaer Polytechnic Institute (RPI).
– Freight Demand Synthesis techniques that infer freight trips and freight flows using secondary data, such as a estimates of FTG and FG and traffic counts
– The Behavioral Microsimulation (BMS) an agent based simulator
14:30-14:40 Break
14:40-15:30 “Agent-based Urban Freight Simulations and Applications” by Prof. Takanori Sakai, Tokyo University of Marine Science and Technology.
15:30-16:20 “2023 Tokyo Metropolitan Freight Survey” by Dr. Takeshi Kenmochi, The Institute of Behavioral Sciences.
16:20-16:30 Closing
#232 International Symposium on Sustainable Urban Mobility through Modular and Integrated Transport System
Date
2024年3月28日
Venue
Okuma Hall, Nagoya University
International Symposium on Sustainable Urban Mobility through Modular and Integrated Transport System
International Symposium on Sustainable Urban Mobility through Modular and Integrated Transport System
Venue: Okuma Hall, Nagoya University
Date and time: Thursday, March 28, 2024, 13:30-17:45
Admission: Free
Language: English
Schedule:
13:30-13:40 Opening remark: Prof. Takayuki Morikawa (Nagoya University)
13:40-14:30 Prof. Yavuz Duvarci (Izmir Institute of Technology)
Drawing a vision for a more sustainable mobility: Example of PRT systems
14:30-15:20 Prof. Csaba Csiszár (Budapest University of Technology and Economics)
Reshaping mobility – merging transitional transportation modes
15:20-15:40 Coffee break
15:40-16:20 Prof. Shoshi Mizokami (Kumamoto Gakuen University)
Current status of smart mobility in Japan and Kumamoto-oriented MaaS
16:20-17:00 Dr. Giancarlos Parady (University of Tokyo)
Required simulated population ratios for valid assessment of shared autonomous vehicles’ impact using agent-based models
17:00-17:40 Dr. Lanhang Ye (Nagoya University)
Concept and simulation of door-to-door personal rapid transit system
17:40-17:45 Closing
土木学会論文集・特集号(土木計画学), Vol.79, No.20の最優秀論文選定について
土木学会論文集・特集号(土木計画学),Vol.79,No.20の優秀論文賞選定について
詳しくは,こちらをご覧ください。
#231 The 10th UTokyoIPL-CUTI Special Seminar
Date
2024年3月8日
Venue
Seminar room of International Project Lab, Department of Civil Engineering, The University of Tokyo (Third floor, Engineering Building No.11, Hongo Campus
The 10th UTokyoIPL-CUTI Special Seminar
[The 10th UTokyoIPL-CUTI Special Seminar]
1) Time and day: 10:00am-11:30am (Japan Standard Time), March 8 (Friday), 2024
2) Place: Seminar room of International Project Lab, Department of Civil Engineering, UTokyo (3rd floor of Engineering Building No.11, Hongo Campus, UTokyo) and Zoom meeting room
3) Presentation
Title: Urban Sociophysical Resilience: Modeling the Interplay of Human Dynamics and Infrastructure Systems during Disasters
Abstract: Cities are the main engines of productivity, innovation, and cultural diversity, owing to their ability to foster dense social and economic connections among people and organizations. However, cities are also at the forefront of unprecedented challenges, including increased frequency of climate change induced disasters, novel mobility technology, and growing inequality and segregation. To build urban resilience to such challenges, we need to understand better the cascading socioeconomic impacts of shocks, which are undergirded by complex interdependencies between social networks, urban infrastructure, and online systems. Leveraging the increasing availability of large-scale human behavior data collected from mobile devices (e.g., mobile phone GPS, social media, web search), I study the resilience of cities using a sociophysical systems lens. In this talk, I will discuss the results from my research on the resilience of cities to climate change induced disasters, focusing on the impacts of complex interdependencies between social dynamics and infrastructure systems. I will also introduce my ongoing research on the resilience of economic networks, and future vision on cross-city transfer learning approaches to prepare cities for unprecedented shocks.
4) Short bio of presenter
Dr. Takahiro Yabe is a tenure-track Assistant Professor at the Center for Urban Science and Progress and Department of Technology Management and Innovation at the Tandon School of Engineering, New York University. He was previously a Postdoctoral Associate at the MIT Institute for Data, Systems, and Society (IDSS) and Media Lab working with Alex ‘Sandy’ Pentland and Esteban Moro. Taka’s research develops data-driven methods to understand collective social dynamics during disruptions and to model the resilience of complex urban systems to natural hazards, pandemics, and mobility technology. His recent works have been published in journals such as PNAS, Nature Communications, and Nature Machine Intelligence. He received his Ph.D. from Purdue University and his Master’s and Bachelor’s Degrees from the University of Tokyo.
5) Charge: free
6) Language: English only
バスサービスハンドブック改訂版 刊行のお知らせ
この度,『バスサービスハンドブック改訂版』が刊行されました.
本書は,『バスサービスハンドブック』(2006年11月刊行 ISBN:978-4-8106-0452-8)の改訂版であり,編集者は,土木学会 土木計画学研究委員会 規制緩和後におけるバスサービスに関する研究小委員会(初版出版時) [編集代表:喜多 秀行] です.以下はその紹介です(土木学会本体ホームページより).
― 地域社会を支える公共交通サービスの体系的なつくり方が身につく一冊 ―
生活を支える公共交通サービスは一種の社会資本といえる.本書は,バスサービスのみならず人々が生活を営む上で必要な公共交通サービス一般について, “それを確保するための地域社会の役割は何か” という視座に立ち, 確保すべきミニマム水準,社会的公平性,運賃と税による負担のあり方,公共調達,事業効率性などに関する地域社会としての基本方針とその実現方策,そのために必要な計画技術を体系的に解説したハンドブックである.公共交通計画に関する類書の多くが維持・改善の対象としているのが公共交通事業であるのに対し,本書で維持・改善しようとする対象は地域住民の生活である.平易な記述に努めており,全国の自治体担当者やコンサルタントにぜひ一読していただきたい.
ご関心ある方は,是非ご購入をご検討下さい.丸善からもご購入頂けます.
#229 シンポジウム「都市洪水に対する交通システムの適応策―アジアの都市を事例として―」
Date
2024年2月17日
Venue
日本大学理工学部1号館121会議室
シンポジウム「都市洪水に対する交通システムの適応策―アジアの都市を事例として―」
シンポジウム「都市洪水に対する交通システムの適応策―アジアの都市を事例として―(Adaptation Measures for Transportation Systems to Urban Flooding -The Case Study of Asian Cities-)」
主催:日本大学理工学部
共催:EASTS-Japan・日本環境共生学会
日時:2024年2月17日(土)10:00-17:30
会場:日本大学理工学部1号館121会議室(東京都千代田区神田駿河台1-8-14)・オンライン配信(Zoom Webinar)
プログラム:
10:00-10:05 開会挨拶:小早川悟;日本大学理工学部
10:05-10:25 IRG-38の紹介:Prof. Alexis Fillone : De La Salle University
10:25-11:15 基調講演1 : Principles and Practices of Vulnerability Analysis (with an Emphasis on Urban Areas and Flooding(Prof. Michael Taylor: University of South Australia)
11:15-12:05 基調講演2 : Flood Mapping with Satellite Data and People Movement(長井正彦:山口大学)
13:10-15:20 アジアの都市を対象とした洪水発生時の交通システムに関する分析の事例紹介
(1) Mobility Management in Response to Urban Floods in HCMC, Vietnam: Behavioral Analysis, Weather-Traffic Short-term Prediction and Traffic Management Framework (Dr. Vu Anh Tuan: Vietnamese German University)
(2) Impact of Flooding on Truck Movement in Metro Manila, Philippines (Prof. Alexis Fillone)
(3) Evaluation of Vulnerable Routes and Simulation under Normal and Flood Conditions in Cagayan De Oro, Philippines (Prof. Anabel Abuzo: Xavier University, Anteneo de Cagayan)
(4) Synergizing Flood Risk and Road Network Dynamics for Optimized Evacuation Strategies (Dr. Suwanno Piyapong: Rajamangala University of Technology, Srivijaya)
(5) Integrated Framework for Evaluating Climate Change Adaptation Measures: A Case Study on Healthcare Accessibility Amid Pluvial Flooding in Bangkok (Dr. Varameth Vichiensan: Kasetsart University)
(6) The Impact of Riverine Flooding on the Relocation Choices of Residents in Ubon Ratchathani, Thailand (積田典泰:日本大学)
(7) What could we learn from case studies and summary (Prof. Alexis Fillone)
15:40-17:10 パネルディスカッション:Urban Flooding and Transport Adaptation Measures in Asian Cities
モデレータ:Dr. Sittha Jaensirisak : Ubon Ratchathani University,パネリスト:Prof. Alexis Fillone, Prof. Anabel Abuzo, Dr. Vu Anh Tuan, Dr. Varameth Vichiensan, 福田敦:日大学理工学部
17:10-17:20 日本大学災害研究ソサイエティ(NUDS)の紹介 石坂哲宏:日本大学理工学部
17:20-17:25 閉会挨拶:福田敦
使用言語:英 語
参加費: 無 料
#228 The 9th UTokyoIPL-CUTI Special Seminar
Date
2024年2月14日
Venue
Seminar room of International Project Lab, Department of Civil Engineering, The University of Tokyo (Third floor, Engineering Building No.11, Hongo Campus
The 9th UTokyoIPL-CUTI Special Seminar
[The 9th UTokyoIPL-CUTI Special Seminar]
1) Time and day: 10:00am-11:30am (Japan Standard Time), February 14 (Wednesday), 2024
2) Place: Seminar room of International Project Lab, Department of Civil Engineering, UTokyo (3rd floor of Engineering Building No.11, Hongo Campus, UTokyo) and Zoom meeting room
3) Presentation
Title: Modelling activity-travel choice behaviour in transport networks for a low-carbon future
Abstract: With the acceleration of urbanization in many regions, the intensity of human activities and the demand for transportation continue to increase. Residents’ daily activity-travel choice behaviours in transport networks are the main sources of carbon emissions in urban areas. Based on an activity-based travel analysis approach, this study explores how to relate residents’ complicated activity-travel choice behaviours to carbon emissions in transport networks. Influencing factors and measurements of carbon emissions from residents’ activity-travel choices are introduced. We try to understand the activity-travel choice behaviour for a low-carbon future using both the network equilibrium approach and data-driven approach. Some strategies for low-carbon transport management such as carbon credit charge scheme are discussed to jointly optimize urban land use plan and transport networks.
4) Short bio of presenter
Dr. Xiao FU is affiliated with School of Transportation in Southeast University, China as an associate professor and a visiting researcher at The University of Tokyo. She obtained her Ph.D. degree in Department of Civil and Environmental Engineering from The Hong Kong Polytechnic University, and was attached to National University of Singapore during the PhD study. Her research interests include activity-travel behaviour modelling, network equilibrium models, transport geography, spatial big data analytics, and carbon emissions in transport sector. Her works mainly appear in Transportation Research Part E, Transportation, Transportmetrica A, IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, etc. She is now serving as an Associate Editor of Transportmetrica A: Transport Science and Guest Editor of Multimodal Transportation. She is also a member of the Editorial Boards of Journal of Spatio-temporal Information and Journal of Chinese Geographical Science.
5) Charge: free
6) Language: English only
#108 インフラPPP事業における金融の果たす役割
Date
2024年3月13日
Venue
新宿区四谷一丁目 公社)土木学会講堂
NO.108 インフラPPP事業における金融の果たす役割
土木計画学セミナー 「インフラPPP事業における金融の果たす役割」
■セミナーの趣旨
我が国において、PFI・PPP 案件では,プロジェクトファイナンス(PF)を供与する金融機関によって民間事業者の事業審査とSPC 財務状況モニタリングが行われ、政府・自治体もそれを活用できることから、事業の安定的な実施に寄与できるとされているものの,我が国では、かかる金融の機能が具体的に有効に作用しているとの報告はほとんど聞かれない。
しかしながら、PFの事前の審査機能を通じて金融機関が齎す価値は、本来的にはこれに留まらない。本セミナーでは、PFを供与する金融機関の事前審査が、事業設計を担う公共主体や事業を実施する民間事業者に対してどのような価値を創造しているのかを改めて考察する。
また、ラオスにおける大型水力発電PPP事業に対するPF融資の経験を通じて、社会厚生的により望ましいファイナンスおよび PPP そのものの設計の在り方について併せて、インフラファイナンス研究小委員会での研究成果を踏まえて考察する。
■主催:土木学会 インフラファイナンス研究小委員会
■後援:一般財団法人海外投融資情報財団
■日時:2024年3月13日(水) 11:00 ~ 14:00(飲食持込可、但しゴミは自身で持ち帰り)
■会場:新宿区四谷一丁目 公社)土木学会講堂
■プログラム:
11:00~11:10 :委員長挨拶 安間匡明(インフラファイナンス研究小委員会委員長)
11:10~12:10 :PFI/PPP事業においてプロジェクトファイナンスが創出する価値 同上
12:10~12:30 :大型ダム事業を取り巻く環境 伊藤晋・新潟県立大学院教授
12:30~12:50 :ラオスナムニアップ1事業の事例 須内康史・双日㈱ワシントン事務所長
12:50~13:05 :コメント1、山林佳弘、㈱ニュージェック代表取締役社長
13:05~13:20 :コメント2、大西正光、京都大学大学院工学研究科 教授
13:20~14:00 :質疑応答
■参加者略歴
安間匡明:世界銀行出向、㈱国際協力銀行取締役、大和証券㈱顧問を経て、現在、一橋大学・福井県立大学の客員教授、PwCサステナビリティ合同会社執行役員常務。専門はインフラ官民連携とサステナビリティ経営。京都大学経済学部卒、LSE大学院Diploma(経済学)修了、東京大学博士(工学)
伊藤晋:国際協力銀行(JBIC)、国際協力機構(JICA)、中央大学等を経て、現在、新潟県立大学大学院国際地域学研究科教授、研究科長。専門は、国際開発政策、開発金融、東南アジア経済。博士(国際開発)。
須内康史:㈱国際協力銀行ワシントン事務所首席駐在員、管理部長、双日㈱インフラヘルスケア本部長補佐を経て双日米国会社ワシントン支店長(現任)、埼玉大学博士(経済学)
山林佳弘:1985年東京大学工学部土木工学科卒業、関西電力㈱入社、ラオス・ナムニアップ1発電会社社長、理事国際事業本部副事業本部長国際開発部門統括、㈱ニュージェック常務執行役員・技術本部副本部長を経て、2023年3月同社代表取締役社長
大西正光:京都大学大学院工学研究科都市社会工学専攻助教、京都大学防災研究所巨大災害研究センター准教授を経て、現在、京都大学大学院工学研究科都市社会工学専攻教授。専門は土木計画学、建設マネジメント、リスクガバナンス。京都大学博士(工学)
■参加費:無料
■方式:現地参加及びzoomの参加が可能です
■CPD あり
#227 The 8th UTokyoIPL-CUTI Special Seminar
Date
2023年12月15日
Venue
Seminar room of International Project Lab, Department of Civil Engineering, The University of Tokyo (Third floor, Engineering Building No.11, Hongo Campus
The 8th UTokyoIPL-CUTI Special Seminar
[The 8th UTokyoIPL-CUTI Special Seminar]
1) Time and day: 1:00pm-2:30pm (Japan Standard Time), December 15 (Friday), 2023
2) Place: Seminar room of International Project Lab, Department of Civil Engineering, The University of Tokyo (Third floor, Engineering Building No.11, Hongo Campus, https://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/cam01_04_12_j.html) + Zoom meeting room
3) Presenter: Jun KONDO (Senior Business Development Manager, Business Development Dept., Secure Technology & Solutions, Sony Corporation)
4) Presentation
-Title: Sony’s case studies in mobility payments implementation in Asia and changing mobility payments.
-Abstract: Asia is the largest and fastest-growing market for mobility services with significant plans and funding for transport infrastructure. Jun KONDO will share Sony’s case studies of mobility payments implementation in Asia and its technologies including NFC card and mobile payments. He will also talk about trend of mobility payments including technologies, schemes and applications: Sony and its business in mobility payments; About NFC FeliCa; Case studies in Asia; and Trend of mobility payments.
5) Short bio of presenter
Jun Kondo joined Sony Corporation, Tokyo, Japan, in 1992 and started his career in customer service section. He was in charge of service parts distribution planning and control, including assignment in Belgium as Assistant Manager at Sony Service Centre (Europe) – European hub of after-sale service operations. He was transferred to smart card business unit called FeliCa Business Division (currently called Secure Technology & Solutions) in 2001 and was involved in international business development mainly in Asia and promotion of NFC (Near Field Communication) FeliCa. Since then, he has been engaged in building the NFC FeliCa ecosystems in collaboration with international partners.
6) Charge: free
7) Language: English only
第69回土木計画学研究発表会・春大会(自由投稿型)【開催は終了いたしました】
Date
2024年5月25日(土)–26日(日)
Venue
北海道大学札幌キャンパス
第69回土木計画学研究発表会・春大会(自由投稿型)
実施要領
実施期日・開催場所
- 実施期日:2024年5月25日(土)・26日(日)
- 開催場所:北海道大学札幌キャンパス
- 開催場所へのアクセス・会場配置図・会議室の予約等のご案内は,開催校 Web サイト を参照してください.
発表会プログラム
プログラム(暫定)は下記から参照してください.
- プログラム (PDF) [5/24版]
- 氏名・所属等,重要な修正事項がございましたら春大会運営小委員会までご連絡ください.
- 発表会までに発表取り下げ・セッション内での発表順序の変更などがある場合があります.発表会当日は必ず最新版をご参照の上ご来場ください.
- 参考:発表一覧データ (Google SpreadSheet) [5/11版]
発表要領
- 発表者の皆様は,発表要領 (PDF) をご確認の上ご準備ください.
参加申込み
参加申込サイト:土木学会本部行事参加フォーム
- 発表会に参加される方(発表者・セッション座長・一般聴講者等)は全員参加登録および参加費のお支払いが必要です.
- 参加費:一般 5,940 円,学生 2,970 円です.参加費の支払はクレジットカード決済(5/19(日) 17:00 まで)・コンビニエンスストア決済(5/12(日) 17:00 まで)のみです.請求書払いは対応しておりません.
- 当日参加の受付は行いません.確実に発表会までの参加登録をお願いいたします.特に,共著者のうち他の発表の発表者となっていない学会参加者の参加登録漏れにご注意ください.
講演申込み(論文投稿)
論文投稿
講演申込みは締め切りました.多数のご投稿ありがとうございました.
-
- 論文投稿料は講演1件につき 5,940 円です.投稿後に講演を辞退された場合であっても,論文投稿料を請求させていただきますのでご留意ください.投稿料の請求書は,4月下旬~5月上旬にメールにて配信される予定です.
- 発表会に参加するためには,別途参加登録が必要となりますのでご注意ください.
- 春大会への論文投稿は土木学会の正会員である必要はありません.後述する特集号へご投稿いただく場合は土木学会の正会員である必要があります.現在非会員で投稿を希望するみなさまは,お早めに入会手続きをお願いします.
発表希望分野の分類
以下から発表希望分野を選択してください.なお,プログラム編成の都合により第一希望に添えない場合があります.
- 発表希望分野Ⅰ(特別論文セッション)
充実した議論を実現するための「特別論文セッション」を実施します.特別論文セッションでは,最大で30編程度を採択し,論文内容を踏まえたコメントに基づいた議論を行います.- 投稿論文数・論文内容により,発表希望分野IIIでの発表となる場合があります.
- 1件当たりの持ち時間は45分です(発表25分・コメンテータによるコメント10分・討議10分).
- 特別論文セッションでの発表を希望される方は,8ページ以上の論文を投稿する必要があります.
- 発表者は投稿時に希望するコメンテータを伝えることができます.
- 発表希望分野II(手法等分野横断的区分)
研究対象ごとの発表区分(下記,発表希望分野III)に加えて,研究で用いた方法論に注目した分野横断的区分でセッションを構成します.分野横断的区分セッションで発表を希望される場合には,以下の5つから選択いただけます.さらに,ご希望の司会兼コメンテータを伝えることができ,これらの情報を参考に専門性の高い研究者への司会依頼を行うなどを検討します.発表希望分野IIの発表時間は12分を標準とします.なお,適切なセッションを組めない場合には,発表希望分野Ⅰのセッションでの発表になります.- 新分析手法:まだ適用事例の少ない統計的手法(例:機械学習的分析手法)や記述的研究(例:物語研究)などの有効性等を議論する研究
- 理論モデリング:実現象の理論的なモデリング,情報科学やゲーム理論などを駆使した手法について議論する研究
- 統計分析解釈:一般的な統計分析の考察が重要な位置を占めており,その内容や妥当性について重点的に議論する研究
- 海外事例:海外事例について集中的に議論したい研究
- その他:重点的に議論したい分野横断的内容があればそのキーワードを直接書いていただくことも可能です.
- 発表希望分野III(研究対象区分)
発表希望分野I・IIに当てはまらない発表については,下記の5分野から希望順に2つ選択し,キーワードから最大4つのキーワードを選んでください.適当なキーワードがない場合,投稿者によるキーワードを1つだけ加えてください.発表希望分野IIIの発表時間は12分を標準とします.- A. 計画論・計画情報:計画基礎論,計画手法論,システム分析,調査論,公共事業評価法,財源・制度論,プロジェクト構想,施工計画・管理,維持管理計画,意識調査分析,計画情報,情報処理,市民参加,GIS,リモートセンシング,測量,環境計画,防災計画,河川・水資源計画,ライフライン計画・設計,地球環境問題
- B. 地域・都市・景観:国土計画,地域計画,都市計画,地区計画,住宅立地,産業立地,人口分布,地価分析,土地利用,市街地整備,再開発,景観,公園・緑地,観光・余暇,空間設計,イメージ分析,土木史
- C. 交通現象分析:発生交通,目的地選択,交通手段選択,経路選択,出発時刻選択,活動分析,時間利用,交通行動調査,交通意識分析,交通行動分析,自動車保有・利用,駐車需要,交通ネットワーク分析,土地利用・交通・環境統合モデル,観光・余暇行動
- D. 交通基盤計画:総合交通計画,地区交通計画,公共交通計画,歩行者・自転車交通計画,道路計画,鉄道計画,空港・港湾計画,ターミナル計画,駐車場計画,物流計画
- E. 交通運用管理:交通流,交通容量,サービス水準,交通制御,交通管理,交通安全,交通情報,交通環境,公共交通運用,交通弱者対策,水上交通,空港管理,交通量計測,TDM,ITS,モビリティマネジメント(MM)
土木学会論文集D3(土木計画学)特集号への投稿
本研究発表会で発表された論文のうち,一定の条件を満足する論文については,土木学会論文集・特集号(土木計画学)への投稿資格が与えられます.詳しくは,論文募集要項を参考にしてください.特に,特集号へご投稿いただく場合は土木学会の正会員である必要があります.現在非会員で投稿を希望するみなさまは,お早めに入会手続きをお願いします.
優秀ポスター賞
ポスターセッションで発表された研究のうち,発表時点における学生(博士学生含む)については,優秀ポスター賞の選考対象となります.表彰は学会2日目のランチョンミーティングにおいて実施されます.本年度の受賞者はこちらの皆さんです.おめでとうございます.
CPD受講証明を必要とされる方へ
- 本研究発表会は土木学会継続教育CPD (Continuing Professional Development) プログラムの認定を受けています(JSCE24-0401,JSCE24-0402).受講証明書をご希望の方は現地会場の受付にて申請してください.
- 建設系CPD協議会加盟団体CPDシステム利用者は,各団体のルールに沿ってCPD単位の申請をお願いします.他団体へCPD単位を登録する場合はその団体の登録のルールに則って行われます.単位が認定されるかどうかは直接その団体にお問い合わせください.
注意事項
- 原則として口頭発表・ポスターセッションの全てについて対面で実施する予定であり,Web 配信は提供しません.
- 参加費の請求書払には対応していません.論文投稿料については請求書PDFを連絡先担当のアドレスに配信します.
- 参加費には土木計画学研究・講演集代も含まれます.参加登録時にIDを発行し,発表会前に原稿をウェブサイトよりダウンロードできるようにします.また,事前申込をされた方には講演集CD-ROMをお送りします.
- 行事参加費の決済(クレジットカード決済・コンビニエンスストア決済)完了後の返金はできません.参加費に含まれるもの(講演集CD-ROM等)は大会に参加されなかった場合でもお送りします.
- 学会としての昼食・朝食等の提供はなく,参加費は食事代を含みません.学会期間中に利用可能な食堂等については開催校 Web サイトの案内を参照してください.
- 今大会では一時保育サービスの提供はございません.
問い合わせ先
土木計画学研究委員会春大会運営小委員会
e-mail: keikaku69@jsce.or.jp
#226 シンガポール国立大学(NUS)のプラティーク・バンサル先生と博士課程学生の講演会
Date
2023年11月20日,21日
Venue
京都大学(11月20日),東京大学(11月21日)
シンガポール国立大学(NUS)のプラティーク・バンサル先生と博士課程学生の講演会
シンガポール国立大学(NUS)のプラティーク・バンサル先生と博士課程学生の講演会
講演会1:
日時: 11月20日(月) 16:30 ~18:00
場所: 京都大学吉田キャンパス、38号館、共通4(入口は63号館の反対側)https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/access/campus/yoshida/map6r-y
講演会2
日時: 11月21日(火) 16:30 ~18:00
場所: 東大工学部本郷キャンパス工学部1号館4階セミナーA https://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/cam01_04_02_j.html
Prateek Bansal (https://www.prateekbansal.org/)
“Individual-level and System-level Behavioural Science in Transportation”
Bio: Dr Prateek Bansal is a Presidential Young (Assistant) Professor at the National University of Singapore (NUS). Before joining NUS in 2022, he was a Leverhulme Trust Early Career Fellow at Imperial College London and did a Ph.D. from Cornell, an MSc from UT Austin, a BTech from IIT Delhi. Prateek leads the Behavioural & Cognitive Science Lab at NUS, and is a co-principal investigator of the Adaptive Mobility module at Future Cities Laboratory, Singapore. His research group is interested in creating new methods to address challenging questions related to mobility behavior and the adoption of emerging technologies at an individual level and an urban scale. His research has led to over 55 journal articles. Apart from top Transportation journals, he regularly publishes in interdisciplinary journals like Energy Economics and Statistics and Computing. He is an Associate Editor of the Journal of Transport Economics & Policy and the Journal of Public Transportation. He also serves as the editorial board member of Transportation Research Part A: Policy and Practice, Transportation Research Part B: Methodological, and Journal of Choice Modelling, among others. He is a member of the TRB’s standing committees on Travel Survey Methods (AEP25) and Travel Forecasting (AEP50). Abstract: This talk will focus on system-level activity-based models and individual-level behaviour models. Specifically, three main system-level topics will be discussed: (i) novel deep generative models for feasible and diverse synthetic population, (ii) an analytical approach to simultaneously generate synthetic population and home-work locations by fusing travel survey data with the cellular signal data, (iii) generating synthetic population and activity chains by fusing travel survey data with the transit farecard data. The talk will conclude with an individual-level interpretable and flexible behaviour model, marrying data-driven and theory-driven approaches.
Xinwei Li:
“Marrying Cognitive Psychology and Behaviour Modelling: New Advancements and Results”
Bio: Ms. Xinwei Li is a Ph.D. student supervised by Dr. Prateek Bansal in the Civil and Environment Engineering Department at the National University of Singapore (NUS). Before joining the Behavioral & Cognitive lab, she achieved her MSc. in Statistics from NUS, and her B.S. in Mathematical Statistics from Renmin University of China. Xinwei focused on combining the discrete choice models with neurobiological data. Particularly, she is interested in Sequential Sampling Models(SSMs) developments, parameter estimations, and its extensions with choice process data like response time (RT) and eye-movement.
Abstract: This talk will focus on new models from mathematic psychology, known as sequential sampling models (SSMs), that are inherently dynamic to facilitate joint modelling of choice, response time (RT), and other data related to decision-making process (eye-movement of decision-makers). SSMs can also better explain the effect of nudges. The talk will focus on three main advancements in SSMs: (i) First empirical application of SSMs in transportation to explain the role of decoy effects in nudging ride-hailing drivers to adopt electric vehicles, (ii) mathematical proof for the value of involving RT into discrete choice models in terms of econometric estimation, (iii) Joint modelling of lab-based and web-based stated-preference data. By addressing challenges in existing SSMs, the talk will make a strong case for their applications in travel behavior modelling.
第68回土木計画学研究発表会・秋大会(企画提案型)【開催は終了いたしました】
Date
2023年11月24日(金)・25日(土)・26日(日)
Venue
東京都立大学 南大沢キャンパス
第68回土木計画学研究発表会・秋大会
第68回土木計画学研究発表会秋大会(企画提案型)の概要について,以下のとおりお知らせいたします.
- 実施期日・開催場所
実施期日:2023年11月24日(金)・25日(土)・26日(日)
開催場所:
・ベルサール西新宿(24日)
・東京都立大学 南大沢キャンパス(25日・26日)
- 開催校ウェブサイト
会場へのアクセスや懇親会などの情報は,開催校ウェブサイトにて発信いたします.
- 参加申込みについて
発表会に参加される方(発表者,一般聴講者,オーガナイザー)は,土木学会行事参加申込ホームページから参加登録を行ってください.
参加登録後,参加費:一般5,940円,学生2,970円をご請求いたします.これには発表会講演集CD-ROMの代金も含まれます.
支払いはコンビニエンスストア払い,もしくは,クレジットカード払いのみ受け付けております.お支払い頂いた参加費は返金できませんのでご注意ください.
事前参加申込の締切は11月19日(日)です.来場者の管理を行うために,できるだけ事前の参加登録をお願いいたします.
締切日を過ぎてからの参加登録は,行事当日に会場にて受付いたします.当日現金払いでの申込は受付いたしませんのでご了承ください.当日受付分は,後日にコンビニエンスストア払い,もしくは,クレジットカード払いにて支払いを行っていただきます.
- 発表プログラム・大会スケジュール
・プログラム内容は変更される可能性がございます.
・大会参加者には発表会前に論文をHPよりダウンロードできるようにいたします.
○11月24日(金)
10:00~13:00 エクスカーション
・詳細と申込方法は開催校ウェブサイトをご覧ください.
https://www.ip68.tokyo/event
15:00~16:00 委員会報告(ベルサール西新宿1階ホール)
16:00~17:30 招待講演(ベルサール西新宿1階ホール)
・土木学会賞 論文賞:河瀬 理貴(東京工業大学)「商業ロジスティクス最適化から見た人道支援ロジスティクスにおける救援物資在庫モデルの展望」
・土木学会賞 論文奨励賞:中西 航(金沢大学)「データ規模とモデル選択に関する一考察: 区間別 Fundamental Diagram 推定を例に」
・ベルサール西新宿へのアクセスは公式サイトをご覧ください.
https://www.bellesalle.co.jp/shisetsu/shinjuku/bs_nishishinjuku/access/
・委員会報告と招待講演はベルサール西新宿における会場参加,および,Zoomウェビナーによるオンライン参加が可能です.
・会場参加とオンライン参加のどちらも事前登録が必要です.研究発表会の参加登録とは別に行う必要がございます.
・会場参加をご希望の方の登録先(座席数に限りがございます):https://www.jsce.or.jp/events/form/4023912
・オンライン参加をご希望の方の登録先:https://www.jsce.or.jp/events/form/4023913
・オンライン参加の登録をされた方には,ZoomウェビナーへのURLを送信いたします.
・24日には企画セッション・スペシャルセッションは行いません.
○11月25日(土)
9:00~18:15 企画・スペシャルセッション(東京都立大学 南大沢キャンパス)
19:15~ 懇親会(京王プラザホテル八王子)
・懇親会への参加は任意です.懇親会の会費は発表会の参加費には含まれません.
・懇親会に関する情報と申込方法は,開催校ウェブサイトをご覧ください.
https://www.ip68.tokyo/event
○11月26日(日)
9:00~16:30 企画・スペシャルセッション(東京都立大学 南大沢キャンパス)
- 発表要領
下記リンク先のPDFファイルをご参照ください.
- 論文提出方法
論文の募集・投稿は終了しました.
- 土木学会論文集D3(土木計画学)特集号への投稿資格について
企画論文部門へ期限までに投稿された論文のうち,土木学会論文集D3の投稿の手引に従った形式(ただし英文要旨は任意)で執筆され,かつ2ページ以上の分量である論文については,土木計画学研究・講演集に掲載される論文として見なされ,土木学会論文集D3(土木計画学)特集号(以下,特集号と表記する)への投稿資格が得られます.論文タイトルと要旨のみで構成されており本文が記載されていないなど、定められた形式に従っていない原稿は,秋大会運営小委員会の判断により,土木計画学研究・概要集に掲載されません.その場合,土木学会論文集D3(土木計画学)特集号への投稿資格は与えられませんのでご注意ください.ただし,特集号への投稿資格を満たさない投稿論文であっても、企画論文部門セッションで発表することは可能です.
また,論文投稿されたにも関わらず実際には秋大会にて発表されていない論文,およびSS部門へ投稿された論文についても,特集号への投稿資格はありません.詳しくは,計画学ホームページをご覧下さい.
https://jsce-ip.org/publications-journals/d3/
- 論文投稿料について
企画部門の発表会投稿料は,講演1件につき5,940円です.発表会に参加するためには,別途参加登録が必要となりますのでご注意ください.SS部門は,1セッションにつき,9,900円(参加費別)です.なお,オーガナイザーによる採否決定(2023年9月1日(金))後のキャンセルは,一切認められません.発表(講演)を辞退されても,発表会投稿料として料金を請求させて頂きますので十分にご注意ください.
- CPDについて
▼ CPD受講証明を必要とされる方へ
本研究発表会は,土木学会継続教育CPDプログラムの認定を受けております.受講証明書をご希望の方は,現地会場の受付にて申請をお願いいたします.
建設系CPD協議会加盟団体CPDシステム利用者は,各団体のルールに沿って,CPD単位の申請をお願い致します.他団体へCPD単位を登録する場合は,その団体の登録のルールに則って行われます.単位が認定されるかどうかは,直接その団体にお問合せください.
- 問い合わせ先
土木計画学研究委員会秋大会運営小委員会
e-mail: keikaku68@jsce.or.jp
※土木計画学研究委員会HP http://www.jsce.or.jp/committee/ip/index.htm
#107 30年先を見据えた交通計画
Date
2023年10月3日、10月26日
Venue
中央大学3号館14階セミナー室A,B会議室(31403,31404)
NO.107 30年先を見据えた交通計画
土木計画学ワンデイセミナー 30年先を見据えた交通計画
1. 開催日時:
PARTⅠ:2023年10月 3日(火) 10:00-15:00
PARTⅡ:2023年10月26日(木) 10:00-17:00
2. 場所:
中央大学3号館14階セミナー室A,B会議室(31403,31404)
3. 定員:
80名
4. 参加費の有無:有
3000円(1回の支払いでPARTⅠ、PARTⅡの双方に参加できます)
5. タイトル:
PARTⅠ:30年先を見据えた交通計画 30年先に今の交通は何が変わるのか?
PARTⅡ:30年先の交通はどのようになるのか?(これから進むべき課題を議論)
6. 開催主旨:
本ワンデイセミナーは,2020年度より承認され活動を行っている「新しいモビリティサービスやモビリティツールの展開を前提とした交通計画論の包括的研究小委員会」が企画したセミナーである.本ワンデイセミナーは,小委員会で取り組んだ「将来の30年先の交通計画の再構築すべき方向性」に関する検討結果に基づき,30年先を見据えた、交通計画がどの様な方向に進むのか、あるいは進むべきかの考え方を示す。また、そのために、国土交通省の政策をおさらいしたうえで将来の交通の方向性について議論する.
また、その中で公共交通及びその周辺にかかわる交通計画の様々な地域課題や個別課題である、モビリティ・マネジメント、情報技術、シェアリング、小規模交通手段の交通計画などの方向性を議論する。さらに、新しい技術や計画論シェアリング、パーソナルモビリティの行方、ITSやMaaSなどの展望と方向性も議論する
なお,本ワンデイセミナーの対象者は,地域公共交通政策にかかわる自治体・国担当者,交通事業者,コンサルタント,研究者を想定しているが,興味を持たれる方は,だれでも参加可能としたい.
7. プログラム(敬称略)<8月25日現在の案、変更可能性あり>:
〇PARTⅠ:2023年10月3日(木)
1.はじめに 10:00~10:20
開会の挨拶 秋山 哲男(仮称新ブキャナン小委員会委員長・中央大学研究開発機構教授)
小委員会の取り組みと交通通政策・交通計画の課題
2.交通政策・交通計画の様々な課題 10:20~11:00
●コーディネーター・コメンテーター:秋山 哲男
2.1 住民参加:交通計画・計画技術における住民参加と情報技術等
猪井 博登 (富山大学 都市デザイン学部 准教授)
2.2 パーソナルな交通手段のシェアリングと多様な人の利用形態
吉田 長裕(大阪公立大学 大学院工学研究科 准教授)
2.3 バス・デマンド交通などの小規模公共交通の計画
竹内 龍介(中央大学研究開発機構)
3.地域課題+新しい交通マネジメントの提案 11:00~11:50
●コーディネーター:菅原 宏明 (八千代エンジニヤリング㈱ 技術創発研究所 副所長)
●コメンテーター:喜多 秀行 (神戸大学 名誉教授)
地域課題
3.1 観光:沖縄のツーリズム戦略とインフラと公共公通
神谷 大介 (琉球大学 工学部 工学科社会基盤デザインコース・教授)
3.2 大都市郊外:大都市郊外の都市形成と交通計画
有吉 亮(名古屋大学 未来社会創造機構 モビリティ社会研究所 社会的価値研究部門 特任准教授)
3.3 過疎地域・人口低密度地域:人口低密度地域の交通計画の在り方
吉田 樹(福島大学 経済経営学類 准教授(経済経営学類担当)
前橋工科大学 学術研究院 特任准教授(クロスアポイントメント)
3.4 人口低密度地域の交通事業者協同運行の可能性を求めて―日南町を例に-
秋山 哲男(中央大学研究開発機構教授)
藤田 光宏 (八千代エンジニヤリング(株)事業統括本部 国内事業部 道路・交通部)
休憩11:50~13:20
4.情報と人の安全の交通 13:20~14:00
●コーディネーター:中村 文彦(東京大学 大学院新領域創成学研究科 特任教授)
●コメンテーター:竹内 龍介(中央大学研究開発機構准教授)
4.1 自動運転情報技術による外部不経済の内部化と安全運転向上
小路 泰広(中央復建コンサルタンツ㈱東京本社 計画系部門 事業創生グループ)
4.2 情報技術を導入した交通計画:キャンパスMaaSの実証的研究を通して
菅原 宏明 (八千代エンジニヤリング㈱ 技術創発研究所 副所長)
4.3 視覚障害者のモビリティと安全
稲垣 具志 (東京都市大学 建築都市デザイン学部 都市工学科 准教授)
5.討論 今回の議論の総括と次回に向けて 14:00~14:45
●コーディネーター:秋山 哲男(中央大学)、菅原 宏明(八千代エンジニヤリング㈱)
●コメンテーター:
全体の総括 喜多 秀行(神戸大学 名誉教授) 10分
中村 文彦(東京大学) 10分
6.閉会の挨拶 中村 文彦:(仮称新ブキャナン小委員会委員長
東京大学 大学院新領域創成学研究科 特任教授) 14:45
〇PARTⅡ:2023年10月26日(木) 10:00- 17:00
Ⅰ.はじめに 10:00~10:20
開会の挨拶 委員長 中村 文彦 (仮称新ブキャナン小委員会委員長)
(東京大学 大学院新領域創成学研究科 特任教授)
30年先を見据えた、交通計画がどの様な方向に進むのか、あるいは進むべきかの考え方を示す。
2.交通計画の考え方と将来展望 10:20~12:00
●コーディネーター:中村 文彦 (仮称新ブキャナン小委員会委員長・東京大学)
●コメンテーター:喜多 秀行 (神戸大学名誉教授)
移動と交通計画への問い?
2.1 30年後の交通計画のために今何をしなければならないか?
中村 文彦 (東京大学)
2.2 人はなぜ移動するのか?
大森 宣暁(宇都宮大学 地域デザイン科学部 社会基盤デザイン学科 教授)
情報を含むモビリティの在り方?
2.3 モビリティ新時代の都市交通計画へ:新しいアプローチを展望する
高見 淳史 (仮称新ブキャナン小委員会副委員長)
(東京大学大学院 工学系研究科 都市工学専攻 准教授)
2.4 ITSの経緯と展望
平沢 隆之 (高知大学 医学部 客員講師)
2.5 マーケッティング分野におけるICTの影響の実態とその形態
鈴木 克典 (北星学園大学 経済学部 経営情報学科 教授)
環境への対応をどうするか?
2.6 気候変動下における交通計画の在り方
室町 泰徳 (東京工業大学 環境・社会理工学院 教授)
昼食12:00~13:30
3.国土交通省における交通計画 13:30~14:30
●コーディネーター:竹内 龍介(中央大学研究開発機構准教授)
3.1 「地域のくらしを創るサステイナブルな 地域交通の実現に向けて」
墳﨑 正俊 (国土交通省 総合政策局 地域交通課長)
3.2 「MaaSを中心とする新しいモビリティサービス」
齋藤 喬 (国土交通省 総合政策局 モビリティサービス推進課長)
3.3 「地域交通の方向性」
森 哲也 (国土交通省 自動車局旅客課長)
休憩15分 14:45~16:00
4. ディスカッション:これからの交通をどのように考えるか? 14:45~16:30
●コーディネーター:秋山 哲男(中央大学)、中村 文彦(東京大学)
討論者:これからの交通は?
宇都宮 浄人(関西大学経済学部教授) 15分
原田 昇 (中央大学 理工学部教授) 15分
喜多 秀行 (神戸大学名誉教授) 15分
5.閉会の挨拶 秋山 哲男(中央大学・仮称新ブキャナン小委員会委員長) 16:30
17:00~18:30 懇親会
8. 参加申込:以下のフォームにて,申し込んでください
#16 攻めの計画を支える制度・評価とその実践(2023年・年次学術講演会)
Date
2023年9月15日
Venue
広島大学 東広島キャンパス工学部講義棟 B114
攻めの計画を支える制度・評価とその実践
特別セッション 攻めの計画を支える制度・評価とその実践
2023年9月15日(金) 10:40 〜 12:00 IV-3 (広島大 東広島キャンパス工学部講義棟 B114)
座長:小池 淳司(神戸大学)
[IV-154] 実効性のある計画策定に向けたプロセス・組織論
*神田 佑亮1 (1. 呉工業高等専門学校)
キーワード:VUCA、ビジョン形成、土木計画、計画論、パブリックビジネス
[IV-155] 広島県地域公共交通ビジョンの策定について
*平井 健二6、柴田 益良1、藤井 剛1、渡邉 一成2、伊藤 雅3、神田 佑亮4、力石 真5 (1. 広島県地域政策局交通対策担当、2. 福山市立大学大学院都市経営学研究科、3. 広島工業大学工学部工学部環境土木工学科、4. 呉工業高等専門学校、5. 広島大学大学院先進理工系科学研究科、6. 復建調査設計株式会社)
キーワード:地域公共交通計画、ビジョン、地域・経済の共創、ベーシックインフラ、適散・適集社会
[IV-156] 中海・宍道湖8の字ネットワーク整備の期待と課題
*伊藤 高1、近藤 弘嗣1、佐藤 啓輔2 (1. 国土交通省、2. 復建調査設計株式会社)
キーワード:道路事業の価値、ビジネス展開、地域の目標値
[IV-157] バンディットアルゴリズム的思考に基づく計画プロセスに関する考察
*力石 真1 (1. 広島大学)
キーワード:VUCA、計画プロセス、バンディットアルゴリズム的思考、探索と活用、両利きの経営
[IV-158] 地域交通計画でのビジョンと運用 -自転車活用推進計画を例に
*鈴木 美緒1 (1. 東海大学)
キーワード:自転車交通、計画目標、評価手法
#15 科学的知識の不定性と土木の実践(2023年・全国大会研究討論会)
Date
2023年9月11日
Venue
オンライン
科学的知識の不定性と土木の実践
令和5年度土木学会全国大会・研究討論会『科学的知識の不定性と土木の実践』
https://youtu.be/1uSVQsIUFWA
不確実な将来に対しての計画策定,計画分野の専門家の在り方など,土木計画学研究発表会とはひと味違う講演内容となっておりますので,ぜひご覧いただければと思います.
研究討論会『科学的知識の不定性と土木の実践』
概要:土木計画の実践においては,中長期的な視座に立った政策判断が求められる.中長期の将来を事前に予見することは原理的に困難であることから,その判断はVUCA(Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity)環境下のものとならざるを得ない.現時点で持ちうる科学的知識をあますところなく活かして行われた計画策定であっても,その妥当性を不断に問い続け,必要に応じて修正を重ねる,いわば「科学的知識の不定性を念頭に置いた実践展開」が求められている.
本セッションでは,土木の実践における科学的知識の役割を改めて問い直し,その不定性について議論を深め,VUCA環境に正面から向き合った実践展開のあり方について討議する.
討論会構成(敬称略):
1. 話題提供
・藤垣裕子(東京大学)
・家田仁(政策研究大学院大学)
・多々納裕一(京都大学)
・小池淳司(神戸大学)
・大西正光(京都大学)
2. パネルディスカッション
モデレーター:多々納裕一(京都大学)
パネラー:藤垣裕子(東京大学)/家田仁(政策研究大学院大学)/
小池淳司(神戸大学)/大西正光(京都大学)
#225 Property Value Capture as a Mechanism for Public Transport Financing in the Philippines
Date
2023年8月3日
Venue
Webinar (Zoom)
Webinar “Property Value Capture as a Mechanism for Public Transport Financing in the Philippines”
Webinar “Property Value Capture as a Mechanism for Public Transport Financing in the Philippines”
Date: 3 August 2023, Wednesday (1:00 – 3:00pm, Philippine Standard Time).
Program:
12:45 – 1:00 pm
Welcome Remarks – Dr. Jun Castro, Director, National Center for Transportation Studies
1:10 – 1:40
Keynote Talk by Prof. Shishir Mathur, Professor, San Jose State University, California, United States; Author of Innovation in Public Transport Finance: Property Value Capture (Routledge, 2016)
With Q&A
1:40 – 1:55
Transit Oriented Development and Property Value Capture in Japan
Prof. Hironori Kato, University of Tokyo
1:55 – 2:25
Presentations by panelists: Possible pathways for the implementation of Property Value Capture (PVC) as a Mechanism for Public Transport Financing in the Philippines
“Making PVC work in the Philippines: Perspective of a railway company”
Juan Alfonso, President/CEO, Light Rail Manila Corporation
“Making PVC work in the Philippines: Perspective of a real estate developer”
Francis Adrian Viernes, Assistant Vice President and Chief Data Scientist, Megaworld
“Making PVC work in the Philippines: Perspective of a government agency”
Leonel de Velez, Assistant Secretary, Department of Transportation
2:25 – 2:45
Panel Discussion and Q&A
Panel members:
Shishir Mathur, Professor, San Jose State University (optional)
Hironori Kato, Professor, University of Tokyo
Juan Alfonso, CEO and President, Light Rail Manila Corporation
Francis Adrian Viernes, Assistant Vice President – Chief Data Scientist, Head of Data Analytics / Data Science, Megaworld
Leonel Cray De Velez, Assistant Secretary for Planning and Project Development – Department of Transportation
Moderator: Dr. Varsolo Sunio
2:45 – 2:50
Synthesis / Closing Remarks
Raphael IV Abraham Hizon, Earthauz, Inc.
This webinar should be of interest to local government units, national government agencies, transit agencies, real estate developers, transport corporations, financial institutions, property appraisers and assessor, etc.
#224 Historical and current urban design and its impact on children's travel
Date
2023年6月23日
Venue
京都大学 吉田キャンパス 総合研究4号館 共通4
Historical and current urban design and its impact on children's travel
Historical and current urban design and its impact on children’s travel
Date: June 23 (Fri.), 2024. 15:00-17:40
Venue 京都大学 吉田キャンパス 総合研究4号館 共通4
(38番の建物 https://www.kyoto-u.ac.jp/ja/archive/prev/access/campus/map6r_y)
Program:
15:00 – 15:30 Owen Waygood (Polytechnique Montréal)
“Planning for children’s independent travel”
15:30 – 16:00 Sylvia He (The Chinese University of Hong Kong)
“Neighborhood features, out-of-home physical activities and public health: Using Google Street View images and survey to inform the planning and design of age-friendly neighborhoods”
16:00 – 16:30 Uno Haruka (Tokyo University of Science)
“Traffic Safety Measures for Children on Residential Streets in Japan”
16:30 – 16:50 David Hölzel (The University of Dortmund)
“Social and Environmental Influences on Children’s Everyday Mobility in Dortmund, Germany”
16:50 – 17:10 Goto Taiga(University of Tsukuba)
“TBA”
17:10 – 17:40 Nakao Satsohi (Kyoto University)
” Japanese history on traffic safety for children influenced by motorization “
#223 Special seminar on EV in Hong Kong
Date
2023年6月19日
Venue
IP lab meeting room (on the third floor of Engineering Building No.11, Hongo Campus, The University of Tokyo)
Special seminar on EV in Hong Kong
Special seminar on EV in Hong Kong
1) Time and day: 1:00pm-1:45pm (Japan Standard Time), June 19 (Monday), 2023
2) Place (in-person): IP lab meeting room (on the third floor of Engineering Building No.11, Hongo Campus, The University of Tokyo)
3) Web link to online meeting: https://u-tokyo-ac-jp.zoom.us/j/87670893950?pwd=REVWS3BnYlRKQnpoZnlobGwvUVVodz09
4) Presenter: Dr. Sylvia He (Associate Professor, Urban Studies Programme, Department of Geography and Resource Management, The Chinese University of Hong Kong)
5) Presentation:
Title: Electrification of private cars in Hong Kong: EV adoption, charger accessibility, and the spatial planning of charging infrastructure
Abstract: Electrification of the transport sector is an important strategy to achieve carbon neutrality. Over the past few years, we have witnessed the momentum of transitioning from ICE cars to electric cars in different parts of the world, however, cities are facing various challenges and obstacles during the electrification process. In this seminar, one of the densest cities in the world – Hong Kong – will be presented, based on several recent publications and works in progress of my research lab. First, we will examine key determinants of EV adoption, based on the findings from a questionnaire survey in Hong Kong and Denmark. Among these critical factors is charger accessibility, which we will differentiate by objective, perceived, and prospective measures. Then we will develop a methodology framework and a location-allocation model to incorporate consumer preferences and land use constraints into the spatial planning of public EV charging infrastructure. Lastly, some works in progress using new and emerging data will be briefed at the end.
6) Charge: free
7) Language: English only
活動記録2022-2023
最新の情報は,小委員会webページをご参照ください.
- 第11回小委員会(2023/6/1(木)17:00-19:00)
- 今後の活動方針
- 運営会議(2023/4/14(金)10:00-11:30)
- 第66回土木計画学研究発表会・秋大会(企画提案型)琉球大学千原キャンパス(2022/11/13(日)時間帯8(13:15-14:45),時間帯9(15:00-16:30) 「4 革新的技術の都市・地域への導入に伴う合意形成上の課題(1)(2)」セッション
- デジタル社会の実現に向けた新たなインフラ整備における市民合意形成上の課題, 矢嶋宏光((株)三菱総合研究所)・小瀬木祐二・柴田立
- スマートシティの「データ」に関連するELSIの整理, 松浦正浩(明治大学公共政策大学院)・TRA MY NGUYEN THI・標葉隆馬
- 中国における社会信用システムの支持構造とプライバシーの価値:評価対象行動別の比較, Lulu Zhang(東北大学大学院)・青木俊明
- 新しいモビリティの公園への導入からみる地方都市への展開可能性, 安藤良輔((公財)豊田都市交通研究所)・小林秀平・高桑俊康・川澄奈美
- コネクテッドされた公共空間での移動ルールに対する合意形成とエンベロープ理論の意義, 屋井鉄雄(東京工業大学)・Lubing Zou
- 都市・地域での革新的技術の導入に対する一般市民と専門家の意識のズレ, 西堀泰英(大阪工業大学)・野田和樹・寺部慎太郎
- 将来の不確実性を考慮した地域計画の計画プロセス, 石神孝裕((一財)計量計画研究所)・稲原宏・石井良治・磯野昂士
- 交通分野の技術革新が経済活動の空間分布に与える影響:空間経済モデルを活用したシナリオ分析, 杉本達哉(八千代エンジニヤリング(株))・高山雄貴・高木朗義
- 交通計画における若年無関心層の関心を喚起する手法の検討, 松尾澪(東京理科大学大学院)・寺部慎太郎・柳沼秀樹・海野遥香・鈴木雄
- 第10回小委員会(2022/05/20(金)13:00-15:00)14名参加
- 谷口綾子:「クルマ」と「自動化するクルマ」に対する社会的受容
- 伊原隼人:水害を経験した市町村における減災型水害対策の策定経緯に関する研究:-計画論と技術論の観点から-
- 秋大会企画テーマの応募案
- 今後の活動方針,とりまとめに向けた委員への宿題
#222 Travel behavior analysis of the elderly in China
Date
2023年3月20日
Venue
Room 206 at Engineering Building 8th North, Nagoya University and Zoom
Travel behavior analysis of the elderly in China
Theme: Travel behavior analysis of the elderly in China
Speaker: Prof. Shengchuan Zhao, Professor at School of Transportation and Logistics, Dalian University of Technology
Date and time: 2023/4/20 (Th), 10:30-12:00
Place: Room 206 at Engineering Building 8th North, Nagoya University and Zoom
Abstract: The rapid demographic shift towards an aging society in China will bring more challenges to meeting the travel needs of older adults, especially the heterogeneity and differences in backgrounds, health, and subjective perceptions of them making it even harder. Walking, as a primary travel mode and physical activity for seniors in China, is important for them to keep involved in social life and maintain active and wellbeing while aging. Studies on the walking behavior of older adults have been focusing on realized journeys, but the research on the unmet walking needs has received insufficient attention. Moreover, most studies treated older adults as a homogeneous group. As such, this study examines how socio-demographic and built environment variables affect the unmet walking needs of older adults considering the unobserved heterogeneity by relying on subjective predictors of walking. The unmet walking needs are defined as the gaps between expected and actual walking frequencies. This is done by employing a hybrid approach integrating latent class analysis (LCA) and a zero-inflated Poisson (ZIP) regression model based on data collected from 533 older adults over 60 in China in 2021. Results of LCA show that three latent segments can be identified, i.e., Enthusiastic Walking Respondents with Excellent Health (EWEH), Positive Walking Respondents with Languishing Health (PWLH), and Fair Walking Respondents with Languishing Health (FWLH). The results of the ZIP regression model indicate that age, gender, income, elevator, and distances to the nearest bus stop are the relatively contributing factors to unmet walking needs for both three classes. Moreover, built environment factors, such as access to bus stops and distances to the nearest leisure facility, have the most significant influence on EWEH class. The findings of this study will offer insights for effective policies and interventions to build an age-friendly environment.
国土強靱化定量的脆弱性評価委員会・活動記録
国土強靱化定量的脆弱性評価委員会
- 2023年2月27日(月) 2022年度第1回委員会
- 2023年3月20日(月) 2022年度第2回委員会
- 2023年3月24日(金) 2022年度報告書
- 2023年8月17日(木) 2022年度第1回委員会
- 2023年10月17日(火) 2022年度第2回委員会
- 2023年11月27日(月) 2022年度第3回委員会
- 2023年12月21日(木) 2022年度第4回委員会
- 2024年3月8日(金) 2023年度国土強靱化定量的脆弱性評価・報告書(中間とりまとめ)
#106 権利と効率のストック効果の理論と実践
Date
2023年3月27日
Venue
土木学会講堂(JR四ツ谷駅より徒歩3分)
NO.106 権利と効率のストック効果の理論と実践
土木計画学ワンデイセミナー 権利と効率のストック効果の理論と実践
■日時: 2023年3月27日(月)13:30~16:30
■主催: 権利と効率のストック効果に関する研究小委員会(委員長:小池淳司)
■場所: 土木学会講堂(JR四ツ谷駅より徒歩3分)
■定員:対面:40名
オンライン(Zoom):500名
※対面とオンラインのハイブリッド形式
■参加費: 無料
■セミナーの趣旨:
土木計画学の研究小委員会として活動してきました「権利と効率のストック効果に関する研究小委員会(委員長:小池淳司)」の活動成果および国土交通省の新道路技術会議の技術研究開発制度により取り組んでいる「権利と効率のストック効果に基づく社会的意思決定方法と実用的なストック効果計測手法の開発」の取り組み状況について,政策評価実務の現状をふまえながら議論します.
■セミナーの主な対象者:
社会資本整備の評価実務に関心のある研究者・実務者・行政職員等の皆様の参加をお待ちしております.
■プログラム:
1.セミナーの開催趣旨
・小池淳司(神戸大学)
2.話題提供
・井上圭介(国交省道路局):国交省道路局の事業評価について
・小池淳司(神戸大):権利と効率のストック効果とは何か?
・瀬谷創(神戸大):権利から考える計画手法について
・山田順之(鹿島建設):権利からみた各国の政策(X-minute city構想)について
・佐藤啓輔(復建調査設計):効率の観点からの事業評価改善方針について
3.議論
■参加申込方法:土木学会ホームページからお申込みください。
オンライン参加の申し込み
「https://www.jsce.or.jp/events/form/4022021」
対面参加の申し込み
「https://www.jsce.or.jp/events/form/402202」
■CPD単位:2.9単位
対面参加の方は行事終了後に受付にてお渡しいたします。オンライン参加の方は、CPD受講証明発行用アンケートに回答していただくことで発行させていただきます。
ZoomURLの配信と共に、申請用のURLをお送りいたしますので、こちらから申請をお願いいたします。
※建設系CPD協議会加盟団体CPDシステム利⽤者は、各団体のルールに沿って、CPD単位の申請をお願い致します。
※他団体へCPD単位を登録する場合は、その団体の登録のルールに則って行われます。単位が認定されるかどうかは、直接その団体にお問合せください。
【セミナー当日の動画】
https://www.dropbox.com/s/qo0bvdies51uhf9/GMT20230327-041942_Recording_1920x1080.mp4?dl=0
#105 地域公共交通プライシングの新提案 -運賃設定にまつわる固定観念を越えて-
Date
2023年 3月16日
Venue
東京理科大学神楽坂キャンパス1号館 17階記念講堂
No. 105 地域公共交通プライシングの新提案 -運賃設定にまつわる固定観念を越えて-
土木計画学ワンデイセミナー 「地域公共交通プライシングの新提案 -運賃設定にまつわる固定観念を越えて-」
■日時: 2023年 3月16日(木) 14:00-16:00
■主催: 土木計画学研究委員会 公共交通プライシング研究小委員会
■場所: 東京理科大学神楽坂キャンパス1号館 17階記念講堂
・神楽坂キャンパスまでのアクセス
https://www.tus.ac.jp/access/kagurazaka_campus/
・神楽坂キャンパス付近の情報
https://www.tus.ac.jp/tuslife/campus/kagurazaka/
■定員: 100名(会場参加)※ 対面 + Web開催(ハイブリッド開催)
■参加費: 無料(事前申込制)
■セミナーの趣旨:
本ワンデイセミナーは,第61回土木計画学研究発表会にて設立が承認された「公共交通プライシング研究小委員会」が企画したセミナーである.本ワンデイセミナーは,小委員会で取り組んだ「地域公共交通のプライシングのあり方」に関する検討結果に基づき,サービス水準を考慮したプライシングの方法を提案し,実際の適用に結び付けることを目的とする.
地域公共交通はコロナ後も乗客数が以前の水準まで戻らないと言われる一方,乗務員不足や燃料高騰などで費用がかさみ,公的補助増加なしには維持できなくなっている.そのため,地域にとって必要なサービス水準を精査した上で,その供給に必要な費用を,だれがどれだけ負担するかを検討する過程で乗客の運賃を決めていくというアプローチを提案する.これによって,地域ニーズに合った公共交通サービスを関係者の合意によって実現することが可能となり,自治体の努力義務化となった地域公共交通計画の作成においても必要不可欠な方法論となる.
■セミナーの主な対象者:
地域公共交通政策にかかわる自治体・国担当者,交通事業者,コンサルタント,研究者を想定しているが,興味を持たれる方は,だれでもご参加ください.
■プログラム:
14:00-14:05 開会挨拶,趣旨説明(既存運賃制度の問題点)
宮崎 耕輔(公共交通プライシング研究小委員会 幹事長,香川高専教授)
14:05-14:35 地域公共交通プライシングに関する我々の考え方
<サービス水準設定を起点とした運賃設定の枠組み
〜協議運賃制度の活用を念頭において〜>
加藤 博和(公共交通プライシング研究小委員会 委員長,名古屋大院教授)
<サービス水準設定の考え方>
喜多 秀行(神戸大学名誉教授)
<(仮)地域公共交通の運賃設定の理論的検討>
大井 尚司(大分大学教授)
<(仮)海外の運賃設定に学ぶ>
遠藤 俊太郎((一財)交通経済研究所)
14:35-14:50 ディスカッション
<熊本での実践を踏まえた本提案の評価>
今釜 卓哉(九州産交バス)
太田 恒平(トラフィックブレイン)
<いくつかの地域での実践を踏まえた本提案の評価>
何 玏((一財)計量計画研究所)
<(仮)本提案に対するコメント>
正司 健一(神戸大学名誉教授)
14:50-16:00(質疑応答)
■申込方法:土木学会ホームページ「本部主催行事の参加申込」にてお申込み下さい.
以下のフォームにて,3/10(金) 17:00までに申し込んでください.
https://forms.gle/V5g4RMP57iFcwGmJ7
オンライン参加を希望の方は,3/15(水)までに,申し込みいただ
いたメールアドレス宛に,聴講用URLのご案内をいたします.
■締切日: 2023/3/10(金) 17:00
※本セミナーはCPDプログラムとして登録を予定しています
#221 The 7th UTokyoIP-CUTI Special Seminar
Date
2023年2月13日
Venue
オンライン(Zoom)
The 7th UTokyoIP-CUTI Special Seminar
1) Time and day: 4:00pm-5:30pm (Japan Standard Time), February 13 (Monday), 2023
2) Place: Zoom meeting room (https://u-tokyo-ac-jp.zoom.us/j/88101614989?pwd=OFY2djIwU1VUZnRjOHltQ2kyYnpZdz09)
3) Presentation
Title: The role of ride-hailing services during COVID-19 in Indonesia
Abstract: Millions of people’s activities have been disrupted by the 2019 coronavirus. As an alternative to out-of-home activities, online activities have significantly risen. Due to this phenomenon, our presentation will explore the travel behavior change during the pandemic and understand how ride-hailing services support in-home activities in Indonesia. The use of ride-hailing services for online shopping with same-day delivery services become an interesting point that will be explored in our presentation
4) Short bio of presenter
Muhammad Zudhy Irawan is an associate professor of transportation planning and modeling in the Department of Civil and Environmental Engineering, Universitas Gadjah Mada, Indonesia. He holds a doctoral degree from Kyushu University, Japan. His research interests are related to travel behavior, traffic simulation, and decision-making process.
5) Charge: free
6) Language: English only
7) Participation: Please contact Ms Tomoko Samukawa (samukawa@ip.civil.t.u-tokyo.ac.jp) for joining this seminar, but you can join the seminar even without pre-registration.
#220 The 6th UTokyoIP-CUTI Special Seminar
Date
2023年2月2日
Venue
オンライン(Zoom)
The 6th UTokyoIP-CUTI Special Seminar
1) Time and day: 1:00pm-2:30pm (Japan Standard Time), February 2nd (Thursday), 2023
2) Place: Zoom meeting room (https://u-tokyo-ac-jp.zoom.us/j/86742542338?pwd=RmpwT0E4cGJmVE81RytQU201aWcxUT09)
3) Presentation
Title: Analyzing transport transition issues from the perspective of justice using multi-criteria mapping method
Abstract: In this presentation, I apply the concept of justice and its dimensions (distributive, procedural, recognition, cosmopolitan and restorative) to transitions in public transportation systems. I also introduce the multi-criteria mapping (MCM) method (Coburn and Stirling, 2019), which was originally developed for the appraisal of contested visions. I demonstrate the applicability of both the concept and the method to the three cases of ongoing transport system transition in the Philippines, namely the (non–)legitimation of motorcycle taxis, the formalization of jeepney and the implementation of high-priority bus system. I attempt to unpack the (in)justice issues arising from these transition initiatives. Finally, I argue for the need to pay due attention to the ethical aspects and justice issues of transitions, which, being sources of tension, conflict and discontent, may powerfully resist the hoped-for sustainable transitions.
Keywords: Just transition; transport justice; sustainability transition; global south
References:
Sunio, V. (2021). Unpacking justice issues and tensions in transport system transition using multi-criteria mapping method. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 96, 102887.
Sunio, V., Ugay, J. C., Li, C. W., Liwanag, H. J., & Santos, J. (2023). Impact of Public Transport Disruption on Access to Healthcare Facility and Well-being During the Covid-19 Pandemic: A Qualitative Case Study in Metro Manila, Philippines. Case Studies on Transport Policy, 100948.
4) Short bio of presenter
Dr. Varsolo Sunio is affiliated with the Philippines’ Department of Science and Technology (DOST) as an S&T Fellow II (for transport and logistics) and a visiting researcher at The University of Tokyo. He also holds (or has held) appointments as a research fellow at the University of Asia and the Pacific, De La Salle University, Ateneo de Manila University, and the University of Macau. He finished his doctorate degree in Urban Management at Kyoto University and earned degrees from the National University of Singapore, University of the Philippines, and the Ateneo de Manila University. He previously worked as part of the data science team of the Philippines’ Department of Transportation (DoTr), the information technology team of Accenture, and the Supply Chain Department of Makati Medical Center. He has published papers on transportation issues in the developing country context, covering themes such as equity and justice, access and well-being, sustainable transitions, and financing of informal transport. His works appear in Transportation Research Part A, D and F, International Journal of Sustainable Transportation, Transport Policy, Research in Transportation Economics, Research in Transportation Business & Management, etc. He is also a regular reviewer for several transportation journals. He is a member of Transportation Science Society of the Philippines (TSSP), National Research Council of the Philippines (NRCP) and Analytics Association of the Philippines (AAP). His personal website is: https://sites.google.com/uap.asia/varsolo-sunio/
5) Charge: free
6) Language: English only
7) Participation: Please contact Ms Tomoko Samukawa (samukawa@ip.civil.t.u-tokyo.ac.jp) for joining this seminar, but you can join the seminar even without pre-registration.
#219 The 5th UTokyoIP-CUTI Special Seminar
Date
2023年1月23日
Venue
オンライン(Zoom)
The 5th UTokyoIP-CUTI Special Seminar
1) Time and day: 4:00pm-5:30pm (Japan Standard Time), January 23 (Monday), 2022
2) Place: Zoom meeting room (https://u-tokyo-ac-jp.zoom.us/j/89737816643?pwd=WmVUOTZMNCttY3RiN2VJU21iNXVZUT09)
3) Presentation
Title: Use of Ride Hailing Services in Metro Manila, Bangkok, and Hanoi: A Comparison
Abstract: The study compared the use of the ride hailing services (RHS) in three (3) Southeast Asian cities, namely, Metro Manila, Bangkok, and Hanoi, during the Covid-19 pandemic period. It attempted to zero in on the varying ways by which citizens in these cities availed of RHS in 2020. A similar set of questionnaire survey form was administered, albeit differently; it was administered online in Metro Manila, while it was done face-to-face in Bangkok and Hanoi. The differing method of survey administration may have affected the representativeness of the samples. Nevertheless, similarities and dissimilarities are presented regarding the personal characteristics of RHS users and their usage of RHS in these three cities during the time of the pandemic.
4) Short bio of presenter
Dr. Alexis M. Fillone is a Professor of the Civil Engineering Department, De La Salle University, Manila. He earned his Bachelor of Science in Civil Engineering Degree (Cum Laude) from Central Philippine University, Iloilo City, his Master of Engineering (Transportation) at the Asian Institute of Technology (AIT), Bangkok, Thailand and his PhD in Urban and Regional Planning at the School of Urban and Regional Planning (SURP), University of the Philippines, Diliman, Philippines. He was a former president of the Transportation Science Society of the Philippines (TSSP). He has around 30 years of experience as a teacher in the field of transportation planning and traffic engineering and currently mentors several Master and PhD students at De La Salle University, Manila. He also has more than 20 years of experience in transport research focusing on travel behavior analysis, travel demand modeling, public transport planning, and traffic impact studies as well as consultancy work with the government and the private sector. He has published several articles in SCOPUS and ISI-listed journals. Aside from being a registered Civil Engineer, he is also a registered Environmental Planner.
5) Charge: free
6) Language: English only
7) Participation: Please contact Ms Tomoko Samukawa (samukawa@ip.civil.t.u-tokyo.ac.jp) for joining this seminar, but you can join the seminar even without pre-registration.
第67回土木計画学研究発表会・春大会(自由投稿型)【開催は終了いたしました】
Date
2023年6月3日(土)–4日(日)
Venue
福岡大学七隈キャンパス
第67回土木計画学研究発表会・春大会(自由投稿型)
実施要領
開催の概要は次の通りです.
- 実施期日:2023年6月3日(土)・4日(日)
- 開催場所:福岡大学七隈キャンパス(対面開催)
- 開催場所へのアクセス・一時保育・会議室の予約等のご案内は,開催校ウェブサイト および 会場案内 (PDF) をご参照ください.
- 台風による影響につきまして:交通機関の運休・遅延等により,発表セッションの時間までに現地到着が困難となった場合は春大会運営小委員会 ( keikaku67@jsce.or.jp ) までお問い合わせください.
プログラム
- 印刷用プログラム [PDF(6/2版)]
- 誤り等がございましたら keikaku67@jsce.or.jp までお問い合わせください.
- 講演論文事前公開サイトの発表情報が発表のキャンセル等も考慮した最新版です.
- 詳細プログラムの会場での当日配布はございません.必要な場合は事前に印刷してご持参ください.
発表要領
発表者の皆様は,発表要領 (PDF) を熟読の上ご準備ください.
参加申込み
本研究発表大会への事前参加申し込みは締め切りました.会場にて当日参加申し込みを受け付けます.
- 一般聴講者・オーガナイザーを含め,発表会に参加される方は全員参加登録が必要です.ただし,論文投稿フォームから論文を投稿した発表者は学会事務局が参加登録しますのでご自身での参加登録手続きは必要ありません.
- 参加費は一般 6,000 円,学生 3,000 円です.
- 当日受付分についての参加費請求は発表会終了後に請求メールを送付します(クレジット・コンビニエンスストア決済).現地現金払いはできません.
講演申込み(論文投稿)
論文投稿料
論文投稿料は講演1件につき 6,000 円です.投稿後に講演を辞退された場合であっても,論文投稿料を請求させていただきますのでご留意ください.
論文投稿システム
本研究発表大会への論文投稿は締め切りました.多くの投稿をいただきありがとうございました.
- 論文投稿期間:2023年2月1日(水)〜3月10日(金) 17:00
- 後述するように,発表希望分野・発表希望形式を選択していただきます.
- 講演原稿は土木学会論文集と同一の書式をご利用ください(ただし英文要旨は任意).
- 締切時刻までは,投稿原稿の確認・差し替えが可能です.
- 締切間際に投稿が集中すると予期せぬトラブルが発生する可能性があります.締切間際の投稿は避けてください.
- 土木学会論文集の書式に準じていないもの,期限後に投稿されたものは受理できません.
- 発表申込内容と原稿の内容が違う場合であってもそのまま掲載されます.投稿時に十分ご確認ください.
- 論文を投稿した発表者は,学会事務局が参加登録を行いますので上述の参加申込みをする必要はありません.ご自身で参加申込をした場合,キャンセル・返金できませんのでご注意ください.
- なお,講演申込システムにおける「会員種別」とは土木学会の会員種別を指します.
発表希望分野の分類について
以下から発表希望分野を選択してください.なお,プログラム編成上の都合により第一希望に添えない場合があります.
- 発表希望分野Ⅰ(特別論文セッション)
充実した議論を実現するための「特別論文セッション」を実施します.特別論文セッションでは,最大で30編程度を採択し,論文内容を踏まえたコメントに基づいた議論を行います.- 投稿論文数・論文内容により,発表希望分野IIIでの発表となる場合があります.
- 1件当たりの持ち時間は45分です(発表25分・コメンテータによるコメント10分・討議10分).
- 特別論文セッションでの発表を希望される方は,8ページ以上の論文を投稿する必要があります.
- 発表者は投稿時に希望するコメンテータを伝えることができます.
- 発表希望分野II(手法等分野横断的区分)
研究対象ごとの発表区分(下記,発表希望分野III)に加えて,研究で用いた方法論に注目した分野横断的区分でセッションを構成します.分野横断的区分セッションで発表を希望される場合には,以下の5つから選択いただけます.さらに,ご希望の司会兼コメンテータを伝えることができ,これらの情報を参考に専門性の高い研究者への司会依頼を行うなどを検討します.なお,適切なセッションを組めない場合には,発表希望分野Ⅰのセッションでの発表になります.- 新分析手法:まだ適用事例の少ない統計的手法(例:機械学習的分析手法)や記述的研究(例:物語研究)などの有効性等を議論する研究
- 理論モデリング:実現象の理論的なモデリング,情報科学やゲーム理論などを駆使した手法について議論する研究
- 統計分析解釈:一般的な統計分析の考察が重要な位置を占めており,その内容や妥当性について重点的に議論する研究
- 海外事例:海外事例について集中的に議論したい研究
- その他:重点的に議論したい分野横断的内容があればそのキーワードを直接書いていただくことも可能です.
- 発表希望分野III(研究対象区分)
発表希望分野I・IIに当てはまらない発表については,下記の5分野から希望順に2つ選択し,キーワードから最大4つのキーワードを選んでください.適当なキーワードがない場合,投稿者によるキーワードを1つだけ加えてください.- A. 計画論・計画情報:計画基礎論,計画手法論,システム分析,調査論,公共事業評価法,財源・制度論,プロジェクト構想,施工計画・管理,維持管理計画,意識調査分析,計画情報,情報処理,市民参加,GIS,リモートセンシング,測量,環境計画,防災計画,河川・水資源計画,ライフライン計画・設計,地球環境問題
- B. 地域・都市・景観:国土計画,地域計画,都市計画,地区計画,住宅立地,産業立地,人口分布,地価分析,土地利用,市街地整備,再開発,景観,公園・緑地,観光・余暇,空間設計,イメージ分析,土木史
- C. 交通現象分析:発生交通,目的地選択,交通手段選択,経路選択,出発時刻選択,活動分析,時間利用,交通行動調査,交通意識分析,交通行動分析,自動車保有・利用,駐車需要,交通ネットワーク分析,土地利用・交通・環境統合モデル,観光・余暇行動
- D. 交通基盤計画:総合交通計画,地区交通計画,公共交通計画,歩行者・自転車交通計画,道路計画,鉄道計画,空港・港湾計画,ターミナル計画,駐車場計画,物流計画
- E. 交通運用管理:交通流,交通容量,サービス水準,交通制御,交通管理,交通安全,交通情報,交通環境,公共交通運用,交通弱者対策,水上交通,空港管理,交通量計測,TDM,ITS,モビリティマネジメント(MM)
発表形式について
口頭発表・ポスター発表の希望を選択してください.なお,会場の都合によりご希望に添えない場合があります.
土木学会論文集D3(土木計画学)特集号への投稿について
本研究発表会で発表された論文のうち,一定の条件を満足する論文については,土木学会論文集D3(土木計画学)特集号への投稿資格が与えられます.詳しくは,論文募集要項を参考にしてください.
優秀ポスター賞について
ポスターセッションで発表された研究のうち,発表時点における学生(博士学生含む)については,優秀ポスター賞の選考対象となります.表彰は学会2日目のランチョンミーティングにおいて実施されます.本年度の受賞者は こちら (PDF) の皆さんになります.おめでとうございます.
CPD受講証明を必要とされる方へ
- 本研究発表会は土木学会継続教育CPD (Continuing Professional Development) プログラムの認定を受けております(JSCE23-0483, JSCE23-0484,1日毎に認定・1日7.5単位).受講証明書をご希望の方は現地会場の受付にて申請してください.
- 建設系CPD協議会加盟団体CPDシステム利用者は,各団体のルールに沿ってCPD単位の申請をお願いします.他団体へCPD単位を登録する場合はその団体の登録のルールに則って行われます.単位が認定されるかどうかは直接その団体にお問合せください.
注意事項
- 原則として口頭発表・ポスターセッションの全てについて対面で実施する予定であり,Web 配信は提供しません.
- 参加費の請求書払には対応していません.論文投稿料については請求書払が可能です.
- 論文投稿フォームから論文を投稿した発表者は,学会事務局が参加登録を行いますので上述の参加申込みをする必要はありません.ご自身で参加申込をした場合,キャンセル・返金できませんのでご注意ください.
- 参加費には土木計画学研究・講演集代も含まれます.参加登録時にIDを発行し,発表会前に原稿をウェブサイトよりダウンロードできるようにします.事前申込をされた方には発表会前までに講演集CD-ROMをお送りする予定です.
- 行事参加費の決済(クレジットカード決済・コンビニエンスストア決済)完了後の返金はできません.参加費に含まれるもの(講演集CD-ROM等)は大会に参加されなかった場合でもお送りします.
- 講演集CD-ROMは数に限りがあり,当日参加申込の場合にはお渡しできない場合があります.
- ランチョンミーティングを含め,昼食の提供はありません.食堂等については 開催校 Web サイト の案内を参照してください.
問い合わせ先
土木計画学研究委員会春大会運営小委員会
e-mail: keikaku67@jsce.or.jp
#218 The 4th UTokyoIP-CUTI Special Seminar
Date
2022年12月19日
Venue
オンライン(Zoom)
The 4th UTokyoIP-CUTI Special Seminar
1) Time and day: 4:00pm-5:30pm (Japan Standard Time), December 19 (Monday), 2022
2) Place: Zoom meeting room (https://u-tokyo-ac-jp.zoom.us/j/86183190905?pwd=MTZaVzY4Umg4UERJL1hrQ3lva1Jqdz09)
3) Presentation
Title: Motorization Pattern and Private Vehicle Dependence in Asian Developing Countries
Abstract: In many developing countries, rapid motorization has been ongoing where owners of private vehicles tend to rely on their own vehicles for making trips. Although the ownership in developing cities is lower than that in developed cities, the excessive dependence on private vehicles has caused serious road traffic congestion, accidents, and negative environmental impacts in those cities. They require the mitigation of people’s dependency on private vehicles, including both private cars and motorcycles. This study investigates the private-vehicle-dependent behavior mainly in Asian developing countries. The presentation contains the topics: 1) review of motorization progress pattern and its influential factors based on statistical data of registered private vehicles in major Asian cities; 2) empirical analysis of private-vehicle dependency with mobility gaps between car/motorcycle owners and non-owners, using the JICA’s person-trips surveys; and 3) identification of factors affecting private-vehicle-dependent travel behavior, highlighting consciousness and attitude toward walkable-distance trips.
4) Short bio of presenter
Mr. Takayoshi Futose is an urban and transport consultant at ALMEC Corporation, Japan. After receiving his master’s degree from Yokohama National University, Japan, he has participated in various transport projects in developing countries, including African countries, Bangladesh, Myanmar, Philippines, and Vietnam. His main research concerns are transport survey, demand forecasting, public transport improvement, and transport planning. He is currently enrolled in the doctoral program at the graduate school of Toyo University, Japan. His doctoral research highlights the people’s private vehicle dependency in major Asian cities for contributing to urban transport planning in developing world.
5) Charge: free
6) Language: English only
7) Participation: Please contact Ms Tomoko Samukawa (samukawa@ip.civil.t.u-tokyo.ac.jp) for joining this seminar, but you can join the seminar even without pre-registration.
#217 EASTS-ITF special seminar: Prospects for Transport Decarbonisation in a rapidly changing environment
Date
2022年12月13日
Venue
一橋大学一橋講堂(人数制限あり)およびオンライン配信(Zoom)同時通訳付(英語・日本語)
EASTS-ITF special seminar: Prospects for Transport Decarbonisation in a rapidly changing environment
このたび、ITFのキム・ヨンテ事務局長の来日を機に、EASTS及びITFの主催、運輸総合研究所の共催、国土交通省の後援により、EASTS-ITF特別セミナーをハイブリッド方式で開催することになりましたので、お知らせいたします。皆様の参加をお待ちしております。
詳細:http://www.easts.info/eastsjapan/PDF_files/Programme_final_JP.pdf
登録:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScc-m0MlFrRgaGrL4iEUs0oxAjeaEV1Lu-CB2c1F-DBB6DesA/viewform
日時:2022年12月13日(火)13:30~16:00
会場:一橋大学一橋講堂(人数制限あり)
(東京都千代田区一ツ橋2-1-2 学術総合センター2階)
およびオンライン配信(Zoom)同時通訳付(英語・日本語)テーマ:激変する環境下における交通部門の脱炭素化に向けた展望
プログラム
13:30-13:40 開会挨拶
山内 弘隆(一般財団法人運輸総合研究所所長)
平岡 成哲(国土交通省国際統括官)
13:40-14:10 基調講演: ITFのアウトリーチ活動および研究活動に関する発表
ヨンテ・キム(ITF事務局長)
14:10-14:50 発表 交通の脱炭素化の未来(40分)
1.ヤリ・カウピラ(ITF事務局長室長)
「脱炭素化に向けたITFの取組み」
2.竹内 智仁(一般財団法人運輸総合研究所主任研究員)
「国際交通分野における脱炭素の実現に向けた課題」
14:50-15:55 パネルディスカッション(65分)
藤原 章正(EASTS-Japan会長/広島大学教授)
ヨンテ・キム(ITF事務局長)
ヤリ・カウピラ(ITF事務局長室長)
竹内 智仁(一般財団法人運輸総合研究所主任研究員)
<モデレータ> 花岡 伸也(EASTS-Japan事務局長/東京工業大学教授)
15:55-16:00 閉会挨拶
兵藤 哲朗(EASTS事務局長/東京海洋大学教授)
(参考)
○国際交通フォーラム(ITF)の概要
OECDにおける政府間組織で、2006年、欧州の交通大臣が集うECMT(欧州運輸大臣会合)から、グローバルな組織に改組する形で設置されました(現在64か国が加盟)。交通政策に関するハイレベルかつ自由な意見交換を行うとともに、交通に関する調査研究活動を行っています。年1回の交通大臣会合(ITFサミット:近年はライプチヒにて開催)に各国の交通担当大臣、企業経営者、有識者等が参加しています。また、年2回開催される交通運営理事会には各国の政策責任者等が参加しています。
#216 Introduction of Road Technology and Policy Making - International Joint Seminar of VJU and NILIM -
Date
2022年11月25日
Venue
オンライン(Zoom)
Introduction of Road Technology and Policy Making - International Joint Seminar of VJU and NILIM -
This is an announcement of online international seminar on technology and policy of Japan’s road, which is organized jointly by Vietnam Japan University (VJU) and National Institute for Land and Infrastructure Management, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, Japan. This event is held online from 15:00-17:20 (Japan Standard Time) on November 25 (Friday), 2022. This seminar aims to introduce the Japan’s road technology and policy making mainly to international students in Asian region including Japan. The details are shown in an attached file. Please find it. We hope you will join this seminar and engage in this important conversation. If you have any questions on this seminar, do not hesitate to contact Prof. Hironori Kato (Co-director of Master program in Civil Engineering, VJU, kato@civil.t.u-tokyo.ac.jp) and Prof. Shinichi Takeda (JICA long-term expert at VJU, takeda.s@vju.ac.vn). Thank you.
1) Time and day: 15:00-17:20 (Japan Standard Time), Nov 25 (Fri), 2022
2) Place: Zoom meeting room (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehj-_C–AcXKcer71EaTVRCBbBTVu-_xuiu5H0YwVLseudhQ/viewform)
Please have a look at the attached files for the details.
FinalVersion_Flyer_Introduction of road technology and policy making
【プログラム確定版】日越大学・国総研ジョイントセミナー
#215 The 3rd UTokyoIP-CUTI Special Seminar
Date
2022年12月5日
Venue
オンライン(Zoom)
The 3rd UTokyoIP-CUTI Special Seminar
1) Time and day: 4:00pm-5:30pm (Japan Standard Time), December 5 (Monday), 2022
2) Place: Zoom meeting room (https://u-tokyo-ac-jp.zoom.us/j/87281677470?pwd=c3VmZlFxMDJXakVhME1kNit2NDFWQT09)
3) Presentation
– Title: Ride-Hailing Service Adoption and Local Context in Motorcycle-Based Societies: Case Study in Hanoi, Vietnam
– Abstract: The ride-hailing service (RHS) has emerged as a major form of daily travel in many Southeast Asian cities where motorcycles are extensively used. This study aims to analyze the local context in motorcycle-based societies, which may affect the establishment of travelers’ choice set after the appearance of RHSs. In particular, it empirically compares three types of choice-set structures in the context of urban travel mode choice by estimating standard logit and nested logit models to test six hypotheses on the associations of RHS adoption with its determinants. Revealed preference data of 449 trips from both RHS users and non-RHS users were collected through a face-to-face interview-based questionnaire survey in Hanoi, Vietnam, in December 2020. The results of model estimations revealed: (1) a substitutional effect for two-wheelers but not for four-wheelers, (2) a significant positive influence of car ownership on car RHS adoption but not on motorcycle RHS adoption, (3) significantly high sensitivity to travel time of motorcycle RHS but not of car RHS, (4) a significant negative effect of traffic congestion on car RHS adoption but an insignificant one on motorcycle RHS adoption, and (5) a significant positive association of an individual’s experience in using a smartphone with car RHSs but insignificant association with motorcycle RHSs. Our findings suggest that transportation policies of RHS motorcycles should be different from those of RHS cars because of the heterogeneity in travel behaviors of RHS users between them. They also indicate that the transition from motorcycles to cars as well as the difference in service availability among different types of RHSs should be incorporated into the development of transportation policies in Southeast Asian cities.
4) Short bio of presenter
Assoc. Prof. Nguyen Hoang-Tung is currently a researcher at University of Transport and Communications, Vietnam. He obtained a Ph.D. in Civil & Environmental Engineering, Saitama University, Japan in 2014. He worked as a research associate at Saitama University and as an invited lecturer at Vietnam Japan University, Vietnam. He has more than 15 year experience in the academic and industrial fields of the transport sector. He was involved in numerous transport projects in Vietnam and Japan, mainly as an in-house consultant for the World Bank, the Asian Development Bank, and Japan International Cooperation Agency. His major interest is a green transportation system and public-private partnerships. He and his co-authors were awarded the best research paper by the International Association of Traffic and Safety Sciences (IATSS) in 2020.
5) Charge: free
6) Language: English only
7) Participation: Please contact Ms Tomoko Samukawa (samukawa@ip.civil.t.u-tokyo.ac.jp) for joining this seminar, but you can join the seminar even without pre-registration.
#214 International Seminar "Refugees and Migrants in the International Society with Disasters"
Date
2022年11月26日
Venue
ハイブリッド(東京大学・Zoom)
International Seminar "Refugees and Migrants in the International Society with Disasters"
We will hold an international seminar at the 4th annual symposium of the URBAN Re-DESIGN STUDIES UNIT on Nov. 26, 2022. The seminar will be held in English, and we welcome international students and researchers. You can join it online or onsite (Hongo Campus, the University of Tokyo). Please take a look at the following for more details.
Seminar theme: Refugees and Migrants in the International Society with Disasters
Seminar website: http://dss.bin.t.u-tokyo.ac.jp/symposium/symposium_2022/#international
Date and Time: 15:35-17:00 (JST) on November 26 (Saturday), 2022
Seminar Objective:
As the SDG slogan “Leave no one behind” suggests, it is crucial to ensure that no one is left behind, even minorities, during the disaster relief and recovery phases. This seminar will focus on those who may be vulnerable due to cultural and religious differences: migrants and refugees. This seminar aims to share examples of post-disaster issues, support, and recovery efforts for immigrants and refugees in Japan and abroad. Since internationalization is expected to progress further, this seminar will provide an opportunity to consider the challenges that may arise from future disasters in Japan, and the support and reconstruction that will contribute to reducing these challenges.
Speakers:
1. Mohammad Moinuddin (Osaka University)
Title: Potential of foreign nationals during disasters: with reference to two mosques in Osaka, Japan
He will talk about the disaster relief activities of Islamic mosques, the daily activity hubs for foreign residents in Japan.
2. Miko Maekawa (Sasakawa Peace Foundation)
Title: TBD
She will talk about environmental migrants in Pacific Island countries.
3. Mio Sato (International Organization for Migration)
Title: TBD
She will talk about Afghan refugees in Pakistan and the relief efforts toward them.
Coordinators: Hitomu Kotani (Kyoto University) and Riki Honda (University of Tokyo)
Language: English
Fee: Free
Registration form: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdowMg68TeO1ZXz8ZwxJU_ns2lcsggW0DsB7F_QXMxnAv7Dvw/viewform
If you have any questions, please contact the coordinator: Dr. Hitomu Kotani (kotani.hitomu.5c@kyoto-u.ac.jp).
#213 The 2nd UTokyoIP-CUTI Special Seminar
Date
2022年11月7日
Venue
オンライン(Zoom)
The 2nd UTokyoIP-CUTI Special Seminar
We will conduct a special seminar, in which Dr. Phathinan Thaithatkul (Chulalongkorn University) is invited to make a special presentation about a case study on mobility of elderly people in Thailand. This event is held online from 4:00pm-5:30pm (Japan Standard Time), November 7 (Monday). We hope you will join us for the event and engage in this important conversation. The details are shown as follows. Thank you.
[2nd UTokyoIP-CUTI Special Seminar]
1) Time and day: 4:00pm-5:30pm (Japan Standard Time), November 7 (Monday), 2022
2) Place: Zoom meeting room (https://u-tokyo-ac-jp.zoom.us/j/83729974339?pwd=TmFUdVZjWHRRNURUUFBEellsOGwrUT09)
3) Presentation
Title: Mobility, Activities, and Happiness in Old Age: Case of the Elderly in Bangkok
Abstract:
Thailand’s population is rapidly ageing, making it crucial that policy makers understand how to support the welfare of the elderly community. Using the metric of Subject Well-Being (SWB) — a marker overall happiness — our study investigates the links between SWB and senior citizens’ mobility, travel behaviors, and activities outside of the home with the aim of better understanding which factors contribute to higher quality of life for the elderly. We conducted a survey of the elderly in Bangkok, Thailand and derived descriptive statistics and performed a Latent Class Analysis and ordered logistics regression to understand these relationships. We found that active elderly was likely to have higher level of the SWB than inactive elderly. Public transport use and Out-of-home activities engagement were associated with active elderly’s SWB in Thailand. Recommendations for policy makers include improved design of public transport services for the elderly and expanded fare reduction pricing through state welfare for senior citizens.
4) Short bio of presenter
Dr. Phathinan Thaithatkul is a researcher at Transportation Institute, Chulalongkorn University, Thailand. She received her bachelor’s and master’s degrees from King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Thailand, and doctoral degree from Tokyo Institute of Technology, Japan. She has experience working as a project researcher in Center for Spatial Information Science, the University of Tokyo, Japan. Her research interest covers urban mobility and transport planning. Her research focuses on the emerging mobile technology and urban mobility, e.g., ride-hailing services, ride-sharing services, and shared mobility services. She has been involved in an international research project on ride-hailing services. She also has experience in providing consulting services for Department of Land Transport in Thailand. Her consulting services cover the regulation framework for urban mobility.
5) Charge: free
6) Language: English only
7) Participation: Please contact Ms Tomoko Samukawa (samukawa@ip.civil.t.u-tokyo.ac.jp) for joining this seminar, but you can join the seminar even without pre-registration.
#212 International seminar on "assessing the navigation error characteristics of residents and tourists during evacuation"
Date
2022年10月14日
Venue
Higashi-Hiroshima Campus, Hiroshima University
International seminar on "assessing the navigation error characteristics of residents and tourists during evacuation"
[International seminar on “assessing the navigation error characteristics of residents and tourists during evacuation”]
Date & time: 16:00-17:00, October 14, 2022
Venue: IDEC large conference room, Higashi-Hiroshima Campus, Hiroshima University
Presenter: Dr. Yuval Hadas (Senior Lecturer, Department of Management, Bar-Ilan University, Israel)
Tittle: Assessing the navigation error characteristics of residents and tourists during evacuation – a combined simulation and virtual reality approach
Abstract: During evacuation, the evacuees are required to follow the fastest and safest path to the designated evacuation site. However, navigation errors due to lack of knowledge, signage presence and the evacuee behavior are affecting the evacuation efficiency. For that, it is imperative to assess these navigation errors and to develop an optimization model in order to increase the evacuation reliability by improving the guidance at key intersections. This is done by minimizing the difference between the deterministic shortest path and the stochastic shortest path with the stochasticity associated with the selection of an arc at each node, and the behavior of the evacuee. For that, we developed two components: 1) a MATSim based evacuation model, a random (or probabilistic) walk, in which the evacuees are dynamically selecting their next road section probabilistically, and 2) a virtual reality (VR) navigation challenge which investigate the decision-making during evacuation.
Contact: chikaraishim@hiroshima-u.ac.jp (Makoto Chikaraishi, Hiroshima University)
#211 The 1st UTokyoIP-CUTI Special Seminar
Date
2022年10月24日
Venue
オンライン(Zoom)
The 1st UTokyoIP-CUTI Special Seminar
We will conduct a special seminar, in which Dr. Saksith Chalermpong (Chulalongkorn University) is invited to make a special lecture about online food delivery in Bangkok, Thailand. This event is held online from 4:00pm-5:30pm (Japan Standard Time), October 24 (Monday). We hope you will join us for the event and engage in this important conversation. The details are shown as follows. Thank you.
[1st UTokyoIP-CUTI Special Seminar]
1) Time and day: 4:00pm-5:30pm (Japan Standard Time), October 24 (Monday), 2022
2) Place: Zoom meeting room (https://u-tokyo-ac-jp.zoom.us/j/89842877944?pwd=VDgzSFVjR0doMXMyTDgxcjNqSjlCQT09; Meeting ID: 898 4287 7944; Passcode: 458770)
3) Presentation
Title: Consumers’ Spatial Attributes and Their Effects on Online Food Delivery Usage and Travel: Empirical Evidence from Bangkok, Thailand
Abstract:
This presentation gives an outline and findings of our recent paper. In this paper, we examine how consumers’ spatial attributes affect OFD adoption and usage frequency, by testing innovation-diffusion (ID) and accessibility-efficiency (AE) hypotheses. OFD usage data were collected by questionnaire surveys in Bangkok and analyzed by logistic and zero-truncated negative binomial regressions. Spatial attributes that were analyzed included the level of urbanization, transit accessibility, and availability of food outlets. The results from the OFD adoption model supported the ID hypothesis, but those from the OFD usage frequency model provided partial support for the AE hypothesis. Our results implied that while the effects of consumers’ spatial attributes on OFD usage via improved accessibility might be mixed, consumers’ locations played a critical role in explaining OFD use behaviors via diffusion of innovation.
4) Short bio of presenter
Dr. Saksith Chalermpong is Associate Professor in Civil Engineering at Chulalongkorn University, where he teaches transport engineering, planning, and policy. He has also served as Associate Director of Chulalongkorn University Transportation Institute since 2018. His research interests include urban transport planning, public and informal transport, and equality issues in transport policy. He has published extensively in the field of transport, and has provided consulting services for several government agencies in Thailand, including Department of Land Transport, Office of Transport Planning and Policy, and Bangkok Mass Transit Authority. Chalermpong received his bachelor’s degree in civil engineering from Chulalongkorn University, his master’s degree from MIT, and his doctoral degree from UC Irvine, both in the field of transport. His research on informal transportation in Bangkok with Apiwat Ratanawaraha was awarded an Excellent Research Award of Chulalongkorn University in 2018.
5) Charge: free
6) Language: English only
7) Participation: Please contact Ms Tomoko Samukawa (samukawa@ip.civil.t.u-tokyo.ac.jp) for joining this seminar, but you can join the seminar even without pre-registration.
【第10回調査データ追加】「新型コロナウイルスに関する行動・意識調査」の実施と結果報告(速報)について【2023年9月14日更新】[Supplemental Data from the 10th Survey] Conducting the “COVID-19 Behavior and Attitude Survey” and Report of Results (Preliminary Report) [Updated September 14, 2023]
「新型コロナウイルスに関する行動・意識調査」の実施と結果報告(速報)
Carrying Out the “COVID-19 Behavior and Attitude Survey” and Report on Its Results (Preliminary Report)
Go To English Page
土木計画学研究委員会では,このたびの新型コロナウイルス感染症(COVID-19)
また,調査結果(単純集計表,クロス集計表)や調査のローデータについては,利用条件を満たしていればどなたでも利用していただけます。以下の手順に従って,ダウンロードして下さい。
調査目的
「パンデミックに対する被害軽減/レジリエンス確保」実践に貢献しうる,新型コロナウイルス感染症の拡大,および政府からの国民社会経済活動自粛要請に伴う交通・都市活動,社会活動,経済活動に対するインパクトの把握,および,それらを踏まえたあるべき国土・都市計画,産業構造政策,交通物流政策についての提案を行うための基礎データの収集
企画
(公社)土木学会 土木計画学研究委員会
調査
手法:Web調査(協力:株式会社サーベイリサーチセンター)
時期:
第1回 2020年5月21日~24日
第2回 2020年10月9日~19日
第3回 2021年1月22日~28日
第4回 2021年8月20日~29日
第5回 2021年12月9日~17日
第6回 2022年2月18日~24日
第7回 2022年6月21~28日
第8回 2022年8月1~9日
第9回 2022年12月15~23日
第10回 2023年7月14~25日
調査結果
速報のため結果は修正されることがあります。以下からダウンロードしてください。
報告書(全体版)<Link>
報告書(概要版)<Link>
資料<Link>
パネル(2回分)項目集計結果<Link>
パネル(3回分)項目集計結果<Link>
パネル(4回分)項目集計結果<Link>
パネル(5回分)項目集計結果<Link>
パネル(6回分)項目集計結果<Link>
パネル(7,8回分)項目集計結果<Link>
パネル(9回分)項目集計結果<Link>
New! パネル(10回分)項目集計結果<Link>
データのダウンロード(2023年9月14日第10回調査データ追加)
利用条件
(1)集計結果の各ファイルは無償でダウンロードできます。
(2)申請者が集計結果の各ファイルをそのまま複製して第三者に譲渡、又は転貸することを禁じます。
(3)法律、政令、規則、省令その他すべての法令および条例等の法規に違反する目的・手段・方法で利用することを禁じます。また、他人の権利を侵害する目的・手段・方法での利用及び公序良俗に反するような利用についても禁じます。
(4)申請者は、集計結果の各ファイルの使用に起因して第三者に損害を与え、又は第三者と紛争が生じたときは、損害を賠償し又は紛争を解決しなければならなりません。
(5)申請者は、得られた成果等には出典を明記して下さい。(土木計画学研究委員会「新型コロナウイルスに関する行動・意識調査」)
ローデータ・単純集計表・クロス集計表(性別/年代別/地方別/職業別)
第1回調査
質問票(xlsx)<Link>
ローデータ(xlsx)<Link>
単純集計表(xlsx)<Link>
クロス集計表(性別)(xlsx)<Link>
クロス集計表(年代別)(xlsx)<Link>
クロス集計表(地方別)(xlsx)<Link>
クロス集計表(職業別)(xlsx)<Link>
第2回調査
質問票(xlsx)<Link>
ローデータ(xlsx)<Link>
単純集計表(xlsx)<Link>
クロス集計表(性別)(xlsx)<Link>
クロス集計表(年代別)(xlsx)<Link>
クロス集計表(地方別)(xlsx)<Link>
クロス集計表(職業別)(xlsx)<Link>
サンプル回収状況(xlsx)<Link>
第3回調査
質問票(xlsx)<Link>
ローデータ(xlsx)<Link>
単純集計表(xlsx)<Link>
クロス集計表(性別)(xlsx)<Link>
クロス集計表(年代別)(xlsx)<Link>
クロス集計表(地方別)(xlsx)<Link>
クロス集計表(職業別)(xlsx)<Link>
サンプル回収状況(xlsx)<Link>
第4回調査
質問票(xlsx)<Link>
ローデータ(xlsx)<Link>
単純集計表(xlsx)<Link>
クロス集計表(性別)(xlsx)<Link>
クロス集計表(年代別)(xlsx)<Link>
クロス集計表(地方別)(xlsx)<Link>
クロス集計表(職業別)(xlsx)<Link>
サンプル回収状況(xlsx)<Link>
第5回調査
質問票(xlsx)<Link>
ローデータ(xlsx)<Link>
単純集計表(xlsx)<Link>
クロス集計表(性別)(xlsx)<Link>
クロス集計表(年代別)(xlsx)<Link>
クロス集計表(地方別)(xlsx)<Link>
クロス集計表(職業別)(xlsx)<Link>
サンプル回収状況(xlsx)<Link>
第6回調査
質問票(xlsx)<Link>
ローデータ(xlsx)<Link>
単純集計表(xlsx)<Link>
クロス集計表(性別)(xlsx)<Link>
クロス集計表(年代別)(xlsx)<Link>
クロス集計表(地方別)(xlsx)<Link>
クロス集計表(職業別)(xlsx)<Link>
サンプル回収状況(xlsx)<Link>
第7回調査
質問票(xlsx)<Link>
ローデータ(xlsx)<Link>
単純集計表(xlsx)<Link>
クロス集計表(性別)(xlsx)<Link>
クロス集計表(年代別)(xlsx)<Link>
クロス集計表(地方別)(xlsx)<Link>
クロス集計表(職業別)(xlsx)<Link>
サンプル回収状況(xlsx)<Link>
第8回調査
質問票(xlsx)<Link>
ローデータ(xlsx)<Link>
単純集計表(xlsx)<Link>
クロス集計表(性別)(xlsx)<Link>
クロス集計表(年代別)(xlsx)<Link>
クロス集計表(地方別)(xlsx)<Link>
クロス集計表(職業別)(xlsx)<Link>
サンプル回収状況(xlsx)<Link>
第9回調査
質問票(xlsx)<Link>
ローデータ(xlsx)<Link>
単純集計表(xlsx)<Link>
クロス集計表(性別)(xlsx)<Link>
クロス集計表(年代別)(xlsx)<Link>
クロス集計表(地方別)(xlsx)<Link>
クロス集計表(職業別)(xlsx)<Link>
サンプル回収状況(xlsx)<Link>
第10回調査
質問票(xlsx)<Link>
ローデータ(xlsx)<Link>
単純集計表(xlsx)<Link>
クロス集計表(性別)(xlsx)<Link>
クロス集計表(年代別)(xlsx)<Link>
クロス集計表(地方別)(xlsx)<Link>
クロス集計表(職業別)(xlsx)<Link>
サンプル回収状況(xlsx)<Link>
※第1回から第10回の調査データは「ローデータ」の「Monitor_ID」で紐づいています。
#14 VUCA 時代の土木計画学(2022年・年次学術講演会)
Date
2022年9月15日
Venue
京都大学 吉田南1号館 1共33
VUCA 時代の土木計画学
特別セッション VUCA 時代の土木計画学
2022年9月15日(木) 10:40 〜 12:00 IV-3 (吉田南1号館 1共33)
座長:兵藤 哲朗(東京海洋大学)
[IV-66] 経済モデルから定義される国難級災害
*小池 淳司1 (1. 神戸大学大学院工学研究科)
キーワード:国難級災害、経済的被害、DSCGEモデル
[IV-67] VUCA時代の土木計画学についての試論
*瀬谷 創1 (1. 神戸大学)
キーワード:VUCA、インフラ投資、共通シナリオ、p値、個別効果
[IV-68] 空間経済モデルを用いた計量分析
*高山 雄貴1 (1. 金沢大学)
キーワード:空間経済学、反実仮想実験
[IV-69] VUCA時代の土木計画学における「無知」とのつきあい方
*羽鳥 剛史1 (1. 愛媛大学)
キーワード:VUCA、土木計画論、無知、buzz
[IV-70] VUCA時代における土木計画学への視座を得るための一考察
*力石 真1、伊地知 恭右2 (1. 広島大学、2. (一社)北海道開発技術センター)
キーワード:VUCA、守破離、集団的知性、ビジョン、土木計画学
[IV-71] 英国の社会資本整備計画に関する一考察
*佐藤 啓輔1 (1. 復建調査設計株式会社)
キーワード:社会資本整備計画、英国、事業評価
[IV-72] 都市整備へのアジャイルアプローチの適用〜栃木県小山市の事例〜
*淺見 知秀1,2 (1. 小山市、2. 筑波大学システム情報工学研究群)
キーワード:アジャイル、都市整備、公共空間活用、ウォーカブル、公共交通利用促進
[IV-73] 先を見通せない時代にビジョンを描ける社会の実現に向けて
*神田 佑亮1 (1. 呉工業高等専門学校)
キーワード:VUCA、土木計画、ビジョン形成、新規事業、パブリックビジネス
#13 VUCA 時代の土木計画学(2022年・全国大会研究討論会)
Date
2022年9月15日
Venue
京都大学 吉田南1号館 1共33
VUCA 時代の土木計画学
研究討論会「VUCA時代の土木計画学」
オーガナイザー:小池淳司
1. 変動性 [volatility]と統計学(神戸大学大学院・瀬谷創)
2. 不確実性 [Uncertainty]と土木計画学(京都大学防災研究所・大西正光)
3. 複雑性 [Complexity]とモデル分析(広島大学大学院・力石真)
4. 曖昧性 [Ambiguity]と計画論(神戸大学大学院・小池淳司)
5. VUCA時代の土木計画学への期待(北海道開発技術センター・伊地知恭右)
動画はこちら:
[前半] https://youtu.be/Rrm7i3ki2_Y
[後半] https://youtu.be/R3q7kNH34mY
ポストコロナにおける鉄道分野の技術・政策の役割・展望
ポストコロナにおける鉄道分野の技術・政策の役割・展望
2020年以降の新型コロナウイルス感染症の流行によるテレワークの普及や外出の自粛等は,鉄道事業の収益に大きな影響を及ぼしており,各事業者においては,経営改善に向けた様々な施策が展開されています.また,DX(デジタルトランスフォーメーション)の活用やCN(カーボンニュートラル)への対応,激甚化する自然災害の対策など,取り組むべき課題も多く存在しています.
#8 早稲田大学まちづくりシンポジウム2022 郊外住宅地の経年優化
Date
2022年7月24日
Venue
早稲田大学井深大記念ホール
[オンライン併用]
早稲田大学まちづくりシンポジウム2022 郊外住宅地の経年優化
■日時・会場
2022年7月24日(日)10:00~17:00
早稲田大学 井深大記念ホール[オンライン併用]
詳細については、下記のリーフレットをご覧ください。
東京2020大会の交通・輸送に関する各種データの提供について
東京2020大会の交通・輸送に関する各種データの提供について
2022年5月
東京都
はじめに
東京2020大会の交通マネジメントの取組の成果を取りまとめる過程で、交通輸送技術検討会の学識委員等から、蓄積されたデータを研究者等と共有し、今後の研究・施策展開に役立てていくべきとご示唆をいただいています。
この度、大会期間の交通動向の分析等の研究に活用できるよう、関係機関の皆様にご協力を頂き、東京2020大会期間の交通・輸送に関する各種データを東京都が集約し、学会※に所属する研究者にデータ提供を行うことが可能となりました。
なお、データ利用にあたっては、希望する旨を事務局に連絡するとともに、下記に定める注意事項に同意いただき、別添の「データ取扱いに関する同意書」を提出いただく必要があります。
詳しくは、「データ提供概要書」を参照ください。
※公益社団法人 土木学会、公益社団法人 日本都市計画学会、一般社団法人 交通工学研究会の3団体
ご利用にあたっての注意事項等
- 申請者が各データファイルをそのまま複製して第三者に譲渡、又は転貸することを禁じます。
- 法律、政令、規則、省令その他すべての法令および条例等の法規に違反する目的・手段・方法で利用することを禁じます。また、他人の権利を侵害する目的・手段・方法での利用及び公序良俗に反するような利用についても禁じます。
- 申請者は、各データファイルの使用に起因して第三者に損害を与え、又は第三者と紛争が生じたときは、損害を賠償し又は紛争を解決しなければなりません。
- 申請者は得られた成果等を公表する際に、東京2020大会データ提供事務局に掲載内容等を事前に連絡するとともに、出典を明記しなければなりません。
申請方法
データ提供の申請の際には、次の2点の電子データを東京2020大会データ提供事務局まで電子メール(E-Mail: tokyo2020@ibs.or.jp)にてご提出ください。
申請受付期間
2022年5月16日(月)~2022年7月29日(金)
留意事項
- サイズの大きなデータは、ネットワーク経由でのデータ提供が困難であるため、HDDやSSDによる受け渡しとなります。受け渡しに使用するHDDやSSDは、申請者にご用意いただき、発送・返送に係る実費は申請者にご負担いただきます。受け渡し方法は、申請が受理され次第、事務局から電子メールでご連絡いたします。
- データ提供事務は、ベストエフォートでの対応となります。申請が集中した場合等には、データ提供までに時間を要することがありますので、予めご承知おきください。
- データ提供事務局へのお問合せは、電子メール(E-Mail: tokyo2020@ibs.or.jp)でお願いいたします。
ご利用にあたっての連絡先
東京都 東京2020大会データ提供事務局
(一般財団法人 計量計画研究所 研究本部内 担当: 加藤、矢部、毛利)
E-Mail: tokyo2020@ibs.or.jp
TEL: 03-3268-9911(代)
第66回土木計画学研究発表会・秋大会(企画提案型)【開催は終了いたしました】
Date
2022年11月11日(金)・12日(土)・13日(日)
Venue
琉球大学 千原キャンパス及び那覇市ぶんかテンブス館
第66回土木計画学研究発表会・秋大会(企画提案型)
※開催は終了いたしました.参加された方々を始め,関係された皆さまに改めて感謝申し上げます.ありがとうございました.
● 実施期日・開催場所・実施要領
実施期日:2022年11月11日(金)・12日(土)・13日(日)
開催場所:琉球大学千原キャンパス及び那覇市ぶんかテンブス館
実施要領:PDFファイル
・開催場所へのアクセスに関する情報は,以下の開催校ウェブサイトにおいて公開しております.
https://www.jsce-ip.okinawa/
● 参加申込みについて
発表会に参加される方(発表者,一般聴講者,オーガナイザー)は全員参加登録が必要です.
参加費は一般6,000円,学生3,000円です.
事前参加申込は10月30日(日)に締め切りました.
以降のお申し込みは,行事当日に会場にて受付いたします.
現地現金払いでの申込は受付しない予定となっておりますのでご了承ください.
当日受付分は、発表会終了後に請求メールをお送りいたします.
○注意事項
・参加費には発表会講演集代も含まれます.参加登録時にIDを発行し,それにより発表会前に原稿をウェブサイトよりダウンロードできるようにいたします.
・事前申込をされた方には,発表会前までに講演集CD-ROMをお送りする予定です.
・行事参加費の決済(クレジットカード決済・コンビニエンスストア決済)完了後は,キャンセル及び変更等による返金を一切お受けいたしません.
・参加費に含まれるもの(講演集CD-ROM等)は,当日ご欠席の場合でもお送りいたしますのでご了承ください.
・講演集CD-ROMは数に限りがございますので,当日参加申込の場合にはお渡しできない場合がございます.
● 発表プログラム・大会スケジュール
・論文投稿時に発行されたIDにより発表会前(10月下旬を予定)に論文をHPよりダウンロードできるようにいたします.
○11月11日(金)
9:00~12:00 エクスカーション(⾸⾥城公園および周辺,定員は30名,事前予約が必要)
・詳細と予約方法は開催校HPをご覧ください.
https://www.jsce-ip.okinawa/about.php
14:00~15:00 委員会報告(那覇市ぶんかテンブス館4F テンブスホールおよびZoomウェビナー)
15:00~16:00 招待講演(那覇市ぶんかテンブス館4F テンブスホールおよびZoomウェビナー)
・⼟⽊学会賞 論⽂賞:星野裕司(熊本⼤学)「⼟⽊デザインに関する哲学的試論」
・⼟⽊学会賞 論⽂奨励賞:渡辺万紀子(株式会社富山市民プラザ)「街路空間における中間領域の類型とその評価に関する研究」
・委員会報告と招待講演はテンブスホールにおける会場参加,および,Zoomウェビナーによるオンライン参加が可能です.
・会場参加とオンライン参加のどちらも事前登録が必要です.研究発表会の参加登録とは別に行う必要がございます.
・会場参加をご希望の方の登録先(座席数に限りがございます):https://www.jsce.or.jp/events/form/4022912
・オンライン参加をご希望の方の登録先:https://www.jsce.or.jp/events/form/4022911
・オンライン参加の登録をされた方には,後日,ZoomウェビナーへのURLを送信いたします.
・11日には企画セッション・スペシャルセッションは行いません.
・本大会では懇親会は行いません.
○11月12日(土)
9:00~18:15 企画・スペシャルセッション(琉球大学千原キャンパス)
○11月13日(日)
9:00~18:15 企画・スペシャルセッション(琉球大学千原キャンパス)
● 発表要領
下記リンク先のPDFファイルをご参照ください.
● 開催校ウェブサイト
会場へのアクセスなどの情報は,以下の開催校ウェブサイトにて発信いたします.
https://www.jsce-ip.okinawa/
● 論文提出方法
論文提出は2022年9月30日(金)24時に締め切りました.
● 土木学会論文集D3(土木計画学)特集号への投稿資格について
企画論文部門へ期限までに投稿された論文のうち,土木学会論文集D3の投稿の手引に従った形式(ただし英文要旨は任意)で執筆され,かつ2ページ以上の分量である論文については,土木計画学研究・講演集に掲載される論文として見なされ,土木学会論文集D3(土木計画学)特集号(以下,特集号と表記する)への投稿資格が得られます.論文タイトルと要旨のみで構成されており本文が記載されていないなど、定められた形式に従っていない原稿は,秋大会運営小委員会の判断により,土木計画学研究・概要集に掲載されません.その場合,土木学会論文集D3(土木計画学)特集号への投稿資格は与えられませんのでご注意ください.ただし,特集号への投稿資格を満たさない投稿論文であっても、企画論文部門セッションで発表することは可能です.
また,論文投稿されたにも関わらず実際には秋大会にて発表されていない論文,およびSS部門へ投稿された論文についても,特集号への投稿資格はありません.詳しくは,計画学ホームページをご覧下さい.
http://www.jsce.or.jp/committee/ip/monograph/file/journal-s-tebiki.pdf
● 論文投稿料について
企画部門の発表会投稿料は,講演1件につき6,000円です.発表会に参加するためには,別途参加登録が必要となりますのでご注意ください.SS部門は,1セッションにつき,10,000円(参加費別)です.なお,オーガナイザーによる採否決定(2022年9月2日(金))後のキャンセルは,一切認められません.発表(講演)を辞退されても,発表会投稿料として料金を請求させて頂きますので十分にご注意ください.
● CPDについて
▼ CPD受講証明を必要とされる方へ
本研究発表会は,土木学会継続教育CPDプログラムの認定を受けております.
受講証明書をご希望の方は,現地会場の受付にて申請をお願いいたします.
11月11日(金)の委員会報告・招待講演にオンライン参加される方には,ZoomウェビナーのURLをお送りする際に,受講証明書の申請フォームを合わせてお送りいたしますので,このフォームから申請をお願いいたします.
建設系CPD協議会加盟団体CPDシステム利用者は,各団体のルールに沿って,CPD単位の申請をお願い致します.
他団体へCPD単位を登録する場合は,その団体の登録のルールに則って行われます.
単位が認定されるかどうかは,直接その団体にお問合せください.
● 問い合わせ先
土木計画学研究委員会秋大会運営小委員会
e-mail: keikaku66@jsce.or.jp
※土木計画学研究委員会HP http://www.jsce.or.jp/committee/ip/index.htm
#104 空間統計モデルの展望(応用地域学会令和2年度坂下賞受賞記念)
Date
2022年1月31日 →延期のため日程確定次第お知らせ
Venue
広島大学工学部内大教室
NO.104 空間統計モデルの展望(応用地域学会令和2年度坂下賞受賞記念)
空間統計モデルの展望(応用地域学会令和2年度坂下賞受賞記念)
■主催:広島大学交通研究グループ
■後援:土木学会中国支部(申請中),応用地域学会(申請中)
■開催日時:2022年4月15日13:00~14:10
■場所:広島大学工学部内大教室
■定員:50名/オンライン配信あり
■参加費:無料
■開催趣旨:
空間統計分析は,地理情報と紐づいた様々なビッグデータを統計的に処理する基礎技術であり,今後ますますの応用や発展が期待されます.
瀬谷創先生は,空間統計分析の第一人者として研究業績を蓄積され,現在も第一線でご活躍中です.
先生は上記の業績が認められて,応用地域学会より令和2年度坂下賞を授賞されました.
このワンデーセミナーは,その記念講演の内容を土木学会関係者に広く共有し,この分野への研究者,特に若手研究者への情報を提供する目的で開催します.
■セミナーの主な対象者:土木計画学で空間統計分析に関心のある方
■プログラム:
13:00-14:00/瀬谷創先生講演
14:00-14;10/質疑
■申込方法:
以下のformsにてご連絡ください.
https://forms.office.com/r/m9UZggqGBC
■その他特記事項:
来校の方とは,引き続き広島大学交通研究グループとの研究会を開催します.
活動記録
革新的技術導入における合意形成研究小委員会
最新の情報は,小委員会webページをご参照ください.
- 第11回小委員会(2023/6/1(木)17:00-19:00)
- 今後の活動方針
- 運営会議(2023/4/14(金)10:00-11:30)
- 第66回土木計画学研究発表会・秋大会(企画提案型)琉球大学千原キャンパス(2022/11/13(日)時間帯8(13:15-14:45),時間帯9(15:00-16:30) 「4 革新的技術の都市・地域への導入に伴う合意形成上の課題(1)(2)」セッション
- デジタル社会の実現に向けた新たなインフラ整備における市民合意形成上の課題, 矢嶋宏光((株)三菱総合研究所)・小瀬木祐二・柴田立
- スマートシティの「データ」に関連するELSIの整理, 松浦正浩(明治大学公共政策大学院)・TRA MY NGUYEN THI・標葉隆馬
- 中国における社会信用システムの支持構造とプライバシーの価値:評価対象行動別の比較, Lulu Zhang(東北大学大学院)・青木俊明
- 新しいモビリティの公園への導入からみる地方都市への展開可能性, 安藤良輔((公財)豊田都市交通研究所)・小林秀平・高桑俊康・川澄奈美
- コネクテッドされた公共空間での移動ルールに対する合意形成とエンベロープ理論の意義, 屋井鉄雄(東京工業大学)・Lubing Zou
- 都市・地域での革新的技術の導入に対する一般市民と専門家の意識のズレ, 西堀泰英(大阪工業大学)・野田和樹・寺部慎太郎
- 将来の不確実性を考慮した地域計画の計画プロセス, 石神孝裕((一財)計量計画研究所)・稲原宏・石井良治・磯野昂士
- 交通分野の技術革新が経済活動の空間分布に与える影響:空間経済モデルを活用したシナリオ分析, 杉本達哉(八千代エンジニヤリング(株))・高山雄貴・高木朗義
- 交通計画における若年無関心層の関心を喚起する手法の検討, 松尾澪(東京理科大学大学院)・寺部慎太郎・柳沼秀樹・海野遥香・鈴木雄
- 第10回小委員会(2022/05/20(金)13:00-15:00)14名参加
- 谷口綾子:「クルマ」と「自動化するクルマ」に対する社会的受容
- 伊原隼人:水害を経験した市町村における減災型水害対策の策定経緯に関する研究:-計画論と技術論の観点から-
- 秋大会企画テーマの応募案
- 今後の活動方針,とりまとめに向けた委員への宿題
見学会(2022/03/10(木)15:00-16:30)
柏の葉アーバンデザインセンター(UDCK)
特別講演会・第9回小委員会(2022/01/06(木)15:00-16:30)23名参加
大阪大学コミュニケーションデザイン・センター 教授 八木絵香先生 「科学技術と社会の関係を考えるー対話の可能性と限界ー」
第64回土木計画学研究発表会・秋大会(企画提案型)オンライン(2021/12/3(金)時間帯3(13:00-14:30),時間帯4(14:45-16:15)) 「52土木計画の質的研究(w/合意形成・場のデザイン・都市経営)(1)(2)」セッション
特別講演会・第8回小委員会(2021/11/12(金) 10:00-11:30)25名参加
大阪大学社会技術共創研究センター 准教授 標葉隆馬 先生 「先端科学技術の社会へのより良い導入のために-フレーミングの多様性を理解する」
第7回小委員会(2021/10/29(金) 10:00-12:00)16名参加
第6回小委員会(2021/9/27 15:30-17:30)18名参加
第5回小委員会(2021/8/4 13:30-15:30)20名参加
第4回小委員会(2021/6/18 13:00-15:00)17名参加 スペシャルセッションの再討議
これより前は,準備会としての活動.
第3回小委員会(2021/5/11 13:00-14:30)スペシャルセッションの再討議
第2回小委員会(2021/4/8 13:00-15:00)スペシャルセッションの再討議
第1回小委員会(2021/3/3 10:00-12:00)スペシャルセッションの再討議
第62回土木計画学研究発表会(秋大会:企画提案型)スペシャルセッション SS7:革新的技術の都市・地域への導入に伴う合意形成上の課題(2020/11/15)
第60回土木計画学研究発表会(秋大会:企画提案型)スペシャルセッション SS7:破壊的イノベーションと社会的合意形成(2019/11/30)
お知らせ
革新的技術導入における合意形成研究小委員会
- 最新の情報は,小委員会webページをご参照ください.
- 見学会(2022/03/10(木)15:00-16:30)
- 柏の葉アーバンデザインセンター(UDCK)
- 特別講演会・第9回小委員会(2022/01/06(木)15:00-16:30)23名参加
-
-
- 大阪大学コミュニケーションデザイン・センター 教授 八木絵香先生 「科学技術と社会の関係を考えるー対話の可能性と限界ー」
社会的にコンフリクトのある科学技術の問題について,意見や利害の異なる人同士が対話・恊働する場の企画, 運営,評価についてご講演いただきます.
-
- 約40分のご講演+質疑応答.Zoomによるオンライン会議
-
- 特別講演会・第8回小委員会(2021/11/12(金) 10:00-11:30)25名参加
-
- 大阪大学社会技術共創研究センター 准教授 標葉隆馬 先生 「先端科学技術の社会へのより良い導入のために-フレーミングの多様性を理解する」
約40分のご講演+質疑応答.Zoomによるオンライン会議
-
革新的技術導入における合意形成研究小委員会
サンプルテキスト
第65回土木計画学研究発表会・春大会(自由投稿型)【開催は終了いたしました】
Date
2022年6月4日(土)・5日(日)
Venue
オンライン開催(担当:広島大学)
第65回土木計画学研究発表会・春大会(自由投稿型)
※開催は終了いたしました。参加された方々を始め、関係された皆さまに改めて感謝申し上げます。ありがとうございました。
2022.06.05:「優秀ポスター賞」を公開
2022.06.03:「当日参加申込について」を公開
2022.06.03:「会場へのアクセス」を公開
2022.06.03:「ポスターセッションについて」の「第65回土木計画学研究発表会ポスターセッションについて」を更新
2022.06.01:「ポスターセッションについて」にデモ用サイトへのリンクを追記
2022.05.31:会場情報付の「プログラム」を公開
2022.05.31:「ポスターセッションについて」を公開
2022.05.29:「口頭発表セッションについて」(発表者・司会者・聴講者)を公開
2022.05.27:「事前参加申込について」を更新
2022.05.19:「CPD受講証明を必要とされる方へ」を公開
2022.05.19:「ポスターファイルの提出について」を公開
2022.05.11:「事前参加申込について」を公開
2022.05.09:司会者・コメンテーター情報付の「プログラム」を公開
2022.04.06:「プログラム」を公開
2022.03.06:「オンライン開催について」を公開
2022.02.01:「土木計画学研究発表会(春大会)講演申込ページ」を公開
2022.01.15:「会告」を公開
▼優秀ポスター賞
ポスターセッションでの審査により、優秀ポスター賞が下記のファイルの通りに決定いたしました。後日、受賞者の方々には大会運営小委員会からご連絡いたします。
本セミナーは、土木学会継続教育CPDプログラムですが、オンラインでの開催であり、受講証明書を発行するにあたり、実地でのセミナーと異なる手続きが必要です。
- 受講証明書をご希望される方は、必ずセミナー終了後、下記Googleフォームより取得の申請をお願いいたします。
https://forms.gle/oUPQN9szHvVkdZ3G6【締切:6月17日(金)】 - 受講証明書を発行するにあたって、「受講証明発行用アンケート(受講して得られた学びや所見を100文字以上で記載していただく等)」をご提出いただくことが必要です。
- 建設系CPD協議会加盟団体CPDシステム利用者は、各団体のルールに沿って、CPD単位の申請をお願いいたします。
- 他団体へCPD単位を登録する場合は、その団体の登録のルールに則って行われます。単位が認定されるかどうかは、直接その団体にお問い合わせください。
第65回土木計画学研究発表会では当日の参加申込についても受け付けます。下記のフォームから申し込んでください。オンライン開催のため、特例として参加費は無料です。 また、講演集CD-ROMの配布はありません。
フォームに入力・送信後、Zoom・SpatialChatのパスコードが表示されますので、そのパスコードを用いてアクセスしてください。メールアドレスを入力していただきますが、パスコード等のメール送信はされません。入力・送信後に表示される画面を必ず記録しておいてください。なお、参加番号は研究発表会終了後に配信されます。
第65回土木計画学研究発表会・当日参加申込フォーム
口頭発表セッション、ポスターセッション、ランチョンミーティングへのアクセスは下記のミーティングID・URLをご利用ください。なお、パスコードは講演者・司会者・事前参加申込者にメールで配布されたものをご利用ください。また、システムの都合上、各会場には定員がございます。申し訳ありませんが、あらかじめご了承ください。
口頭発表セッション(各会場の定員は300名です)
第1会場 885 7931 0498 https://us02web.zoom.us/j/88579310498第2会場 851 6279 6545 https://us02web.zoom.us/j/85162796545第3会場 870 5630 6324 https://us02web.zoom.us/j/87056306324第4会場 861 9395 5180 https://us02web.zoom.us/j/86193955180第5会場 826 1937 8369 https://us02web.zoom.us/j/82619378369第6会場 825 3289 2121 https://us02web.zoom.us/j/82532892121第7会場 836 9256 9610 https://us02web.zoom.us/j/83692569610第8会場 893 8068 6663 https://us02web.zoom.us/j/89380686663第9会場 826 5324 4975 https://us02web.zoom.us/j/82653244975
ポスターセッション(SpatialChat;Room1-1〜Room2-9の定員は各50名、会場全体での定員は500名です)
https://spatial.chat/s/ip65spring
上記URLからアクセス後、ポスターセッション1(9:00〜10:30)はRoom1-1〜1-9、ポスターセッション2(10:40〜12:10)はRoom2-1〜Room2-9に移動してください。
また、氏名の入力にご注意ください。デフォルトで氏名が「ポスターセッション|第65回・・・」となっている場合があります。その際は上書きしての変更をお願いします。
SpatialChat(ポスターセッション)にログインできない場合、ブラウザの履歴を削除してからお試しください。
ランチョンミーティング(会場の定員は300名です)
-
833 3131 6621 https://us02web.zoom.us/j/83331316621
ランチョンミーティングは6月5日(日)の昼休み(12:10〜13:25)に開催いたします。
事前公開オンサイト
https://onsite.gakkai-web.net/jsce/ip_sp/time_table.html
講演集、プログラム等を閲覧することができます。ID・PWは講演者・司会者・事前参加申込者にメールで配布されたものをご利用ください。
プログラム概要・会場へのアクセス情報・ポスターセッションの会場を含めたプログラムを公開しました。Zoom等のパスコードは講演者・司会者・事前参加申込者の方にメールで配信しております。
- 第65回土木計画学研究発表会プログラム(5月31日版)【PDF】
※ポスターセッションで発表される方はご自分の発表場所をご確認ください。
第65回土木計画学研究発表会の口頭発表セッションはZoomを利用します。Zoomの利用方法や口頭発表セッションでの注意事項(司会者・コメンテータ・発表者・聴講者)については、以下のファイルを参照してください。
第65回土木計画学研究発表会のポスターセッションはSpatial Chatを利用します。Spatial Chatの利用方法については、以下のファイルを参照してください。※ポスターセッションはSpatialChat内でポスター掲示場所が分かれております。プログラムで発表場所の確認をお願いいたします。
- 第65回土木計画学研究発表会ポスターセッションについて【PDF】(6月3日更新)
p.3の「参加者情報の入力」、p.8の「仮のポスターセッション会場の公開」を更新しました。
※デフォルトで氏名が「ポスターセッション|第65回・・・」となっている場合があります。その際は上書きしての変更をお願いします。
追記
ポスターセッションのデモ用サイトを公開しました。以下のサイトはいずれも同じ内容です。デモ用サイトは5名までの人数制限がありますので、混雑している場合は空いているサイトをお試しください。また、空きがない場合は時間をずらしての利用など、ご協力をお願いいたします。
デモ用サイト①:https://spatial.chat/s/ip65testデモ用サイト②:https://spatial.chat/s/ip65test2デモ用サイト③:https://spatial.chat/s/ip65test3
※デモ用サイトはパスコードを設定していませんが、実際のポスターセッション会場へのアクセスにはパスコードの入力が必要です。
追記
聴講参加者の受付締切を6月2日(木)まで延長いたします。ただし、先着順としておりました講演集CD-ROMは予定配布数に達しましたので、郵送はございません。申し訳ありませんが、ご了承ください。
参加申込は土木学会の本部主催行事の参加申込のページ(https://www.jsce.or.jp/event/active/information.asp)からご登録ください。なお、今大会から発表者の方も参加登録が必要となります(講演集CD-ROMは参加申込がなくても送付されます)。
聴講参加者の受付締切は5月28日(土) 6月2日(木)、参加費はオンライン開催に伴う特例で一般、学生ともに無料です。
以下の参加申込書をダウンロードし、必要事項を記入した上で土木学会行事担当宛にFAXをお送りいただくことでも、参加申込は可能です。締切等はウェブサイトからの申込の場合と同じです。
・参加申込書(http://www.jsce.or.jp/event/active/form.pdf)
注意事項
5月23日(月)以降にご登録いただいた場合、講演集CD-ROMの送付は学会終了後となります。また、講演集CD-ROMは数に限りがあるため、先着順となりますことをご了承ください。講演集CD-ROMは予定数に達しました。
▼ポスターファイルの提出について ※ポスターファイルの提出は終了しました。ご協力、ありがとうございました。
ポスターセッションで講演される方は6月2日(木)正午までに、ポスターのファイルを提出してください。詳細は以下のファイルをご参照ください。
春大会ポスターファイルの提出について【PDF】
▼オンライン開催について
第65回土木計画学研究発表会は広島大学を会場とした対面での開催を予定していました。しかしながら、新型コロナウィルスの感染拡大状況を踏まえて、オンラインでの開催に変更することになりました。
昨年12月に開催された秋大会において、本大会を対面開催で予定していることを公表しましたが、開催3ヶ月前を目途に、新型コロナウィルスの感染拡大状況から開催方法について検討することにもなっておりました。現在、感染者数が高止まりになって、今後はオミクロン株の亜種であるステルス変異株の拡大も懸念されること、まん延防止措置が延長される都道府県も出ていることから、対面での開催の見通しが立たなく、対面開催を断念することといたしました。
久しぶりの対面開催を楽しみにされていた方も多いのではないかと思います。大変申し訳ありませんが、このような状況下で判断を下したことをご理解いただければ幸いです。
なお、3月6日(日)を締切とした講演申込をおこなっておりますが、講演申込ページからは講演申込を取り下げることも可能です。また、3月7日以降にプログラム編成作業に入りますが、その際に申込者の方々には登録されたメールアドレスに、発表をキャンセルする場合の対応方法についてご連絡する予定です。
第63回土木計画学研究発表会と同様に、口頭発表セッションはZoom、ポスターセッションはSpatial Chatを用いて開催いたします。大会の開催・運営方法については、開催が近くなりましたら改めてご連絡いたします。また、オンライン開催へと変更となりますが、発表1件につき一般・学生ともに6,000円である投稿料の変更はございません。
▼講演の申込 ※講演申込は終了いたしました。
土木計画学研究発表会(春大会)講演申込ページ
※上記のリンクから講演を申し込んでください。なお、講演申込に際して、下記の会告を十分にご確認ください。講演申込・原稿送信締め切りは2022年3月6日(日) 17:00です。
第65回土木計画学研究発表会の開催方法について
第65回土木計画学研究発表会は広島大学を会場とし、対面での開催を予定しています。ただし、新型コロナウィルス感染症の感染対策として、ポスターセッションはオンライン(Spatial Chatを予定)での開催とします。広島大学に来訪し、ポスターセッションに参加される方は宿泊先もしくは広島大学(当該時間帯は会場を開放する予定)からアクセスしていただくことになります。なお、今後の新型コロナウィルス感染症の感染拡大状況によっては、開催方法全体を変更する可能性があります。あらかじめご承知おきください。
講演用論文
発表会の当日に十分な時間で充実した議論を行い、更なる研究の発展や学術論文等への取りまとめに繋げることが本発表会の特色です。このため、「具体的に議論したい点(研究の新規性や枠組み、データ、モデルや結論の妥当性、今後の発展性や疑問点など)」を明記して申込みしていただきます。話題性、速報性のある論文や、調査・計画、技術検討等の事例報告も歓迎します。提出された講演用論文は、原則として無審査で掲載されますが、お断りすることもあります。
発表希望分野については、通常の発表希望分野Ⅲと並行して、発表希望分野Ⅰ(特別論文セッション)及び発表希望分野Ⅱ(手法等分野横断的区分)での発表希望もお願いしています。こちらへの応募もよろしくお願いします。
また、ポスターセッション、および「優秀ポスター賞」の表彰を実施いたします。受賞対象は、投稿時点における学生です。博士後期課程の学生を含ますが、博士後期課程の学生については発表時点においても学生である方に限ります。
口頭発表とポスターでの発表のどちらを希望するかを選んで申込んでいただきます(口頭発表およびポスターでの発表のいずれも、2023年に発刊予定の「土木学会論文集D3(土木計画学),Vol.78-5」への投稿対象となります)。
※2023年に発刊予定の「土木学会論文集D3(土木計画学),Vol.78-5」への投稿には、
①第62〜65回の土木計画学研究・講演集に掲載されている
②研究発表会において、著者により当該論文の発表が行われている(発表が行われていない、または著者以外によって発表された論文は投稿不可)
③第62回・第64回の土木計画学研究・講演集に掲載された論文は企画論文部門へ投稿され、土木学会論文集D3の投稿の手引きに従った形式(ただし英文要旨は任意)で執筆され、かつ2ページ以上の文量である
ことが必要となりますので、あらかじめご了承ください。
なお、Vol.78-5への投稿期限は2022年6月の予定となります。
※2019年度より土木計画学研究発表会春大会と秋大会の実施内容の一部が入れ替わるのに伴い、土木学会論文集D3の投稿・発刊時期、対象となる発表論文等に大幅な変更がございました。詳しくは、土木学会論文集D3・特集号(土木計画学研究・論文集)投稿の手引きにてご確認ください。
講演の申込み
(1) 申込みの手続きおよび注意点
2022年2月1日(火)~3月6日(日)17時までの期間内に、土木計画学研究発表会(春大会)講演申込みページ申込画面より、講演申込と講演原稿の投稿を同時に行ってください。原稿のファイル形式はPDF形式のみ受付けます。 原稿は「講演原稿執筆要領」に従ってご執筆ください。締切日当日までは、投稿した原稿の確認、差し替えが可能ですが、締切日以降は、原稿の差し替えは受け付けられません。十分、ご注意ください。投稿時に、必ず申込内容が正しいか、PDFを取り違えての投稿がないか、申込内容とPDFのタイトル等の差異がないかなどをご確認ください。申込み期間の締切り間際に投稿が集中しますと、予期せぬ事態によりサーバーがダウンし受付ができなくなる恐れがあります。締切り間際の投稿は極力避けていただくようお願いいたします。
なお、講演原稿執筆要領に準じていないもの、および期限後に投稿されたものは受理できません。必ず所定の原稿を期間内にWEB上にて投稿してください。
間違えたファイルを提出した場合や申込内容とPDFの内容が違う場合であっても、そのまま掲載されますので、ご注意ください。
(2) 発表希望分野
(i) 発表希望分野Ⅰ(特別論文セッション)
充実した議論を実現するための、「特別論文セッション」を実施いたします。特別論文セッションでは、論文内容を踏まえたコメントに基づいた議論を行います。ただし、投稿論文数(最大で30編程度)、論文内容により、発表希望分野IIIでの発表となる場合もあります。
・1件当たりの持ち時間は、発表25分、コメンテーターによるコメント10分、討議10分の計45分とします。
・特別論文セッションでの発表を希望される方は、8ページ以上の論文を投稿することが必要です。
・発表者は投稿時にコメンテーター希望者を伝えることができます。
(ii) 発表希望分野II(手法等分野横断的区分)
従来の研究対象ごとの発表区分に加えて、研究で用いられている方法論に注目した分野横断的区分でのセッションを実施します。分野横断的区分セッションで発表を希望される場合には、今回は以下の5つから選択いただけます。さらに、そのセッションの司会兼コメンテーターでご希望の先生がいればご記入いただけます。これらの情報を参考に、専門性の高い先生への司会依頼を行うなどの検討を行う予定です。ただし、適切なセッションを組めない場合には、上記の発表希望分野Ⅰの従来型のセッションでの発表になります。
・新分析手法(まだ適用事例の少ない統計的手法(例.機械学習的分析手法)や記述的研究(例.物語研究)などの有効性等を議論したい研究)
・理論モデリング(実現象の理論的なモデリング、情報科学やゲーム理論などを駆使した手法について議論したい研究)
・統計分析解釈(一般的な統計分析の考察が重要な位置を占めており、その内容や妥当性について重点的に議論したい研究)
・海外事例(海外の事例的研究として集中的に議論したい研究)
・その他、重点的に議論したい分野横断的内容があればそのキーワードを直接書いていただくことも可能
(iii) 発表希望分野III(研究対象区分)
申し込みに際して、発表希望分野を下記の5つの発表分野から希望順に2つ選んでください。また、キーワードにつきましては、同キーワード欄の中から最大4つ選んでください。なお、適当なキーワードが見つからない場合は、投稿者の判断によるキーワードを1つだけ加えてください。
発表希望分野
| 発表希望分野 | キーワード |
| A 計画論・計画情報 | 計画基礎論、計画手法論、システム分析、調査論、公共事業評価法、財源・制度論、プロジェクト構想、施工計画・管理、維持管理計画、意識調査分析、計画情報、情報処理、市民参加、GIS、リモートセンシング、測量、環境計画、防災計画、河川・水資源計画、ライフライン計画・設計、地球環境問題 |
| B 地域・都市・景観 | 国土計画、地域計画、都市計画、地区計画、住宅立地、産業立地、人口分布、地価分析、土地利用、市街地整備、再開発、景観、公園・緑地、観光・余暇、空間設計、イメージ分析、土木史 |
| C 交通現象分析 | 発生交通、目的地選択、交通手段選択、経路選択、出発時刻選択、活動分析、時間利用、交通行動調査、交通意識分析、交通行動分析、自動車保有・利用、駐車需要、交通ネットワーク分析、土地利用・交通・環境統合モデル、観光・余暇行動 |
| D 交通基盤計画 | 総合交通計画、地区交通計画、公共交通計画、歩行者・自転車交通計画、道路計画、鉄道計画、空港・港湾計画、ターミナル計画、駐車場計画、物流計画 |
| E 交通運用管理 | 交通流、交通容量、サービス水準、交通制御、交通管理、交通安全、交通情報、交通環境、公共交通運用、交通弱者対策、水上交通、空港管理、交通量計測、TDM、ITS、モビリティマネジメント(MM) |
(3) 発表形式
口頭発表とポスターでの発表のどちらを希望するかを選んでいただきます。なお、会場の都合でご希望に添えない場合もありますので予めご了承下さい。
(4) 投稿料(本大会からの変更あり)
講演1本につき投稿料として一般・学生ともに6,000円を請求いたします。請求は5月末頃となります。振込手数料は各自でご負担願います。本大会から投稿料と大会参加費を別に請求することにいたしました。大会参加費は一般6,000円、学生3,000円として、大会参加受付時に改めてお申し込みいただきます。ご注意ください。本大会のオンライン開催に伴い、特例として参加費は学生、一般ともに無料となりました。ただし、参加登録は必要となりますので、改めてご登録ください。→<事前参加申込>
講演原稿執筆要領
講演原稿の書式・形式は、土木学会論文集のものに準じています。下記の作成例やサンプルファイルをご利用ください。講演原稿では、英文アブストラクトの記入は任意です。その他書式・形式についての詳細は土木学会論文集の原稿作成の手引き等をご参照ください。なお、「土木学会論文集D3(土木計画学), Vol.78-5」への投稿の際には英文アブストラクトは必要です。
原稿作成例やサンプルファイルは土木学会論文集編集委員会の各種書式のページを参照してください。
お問合せ先
土木計画学研究委員会大会運営小委員会(春大会担当:岸,日野,小澤)
E-mail:keikaku65@jsce.or.jp
#103 「津波に対する海岸保全施設整備計画のための技術ガイドライン」セミナー
Date
2021年10月29日
Venue
ミーティング or ウェビナー
NO.103 「津波に対する海岸保全施設整備計画のための技術ガイドライン」セミナー
■日時: 2021年10月29日(金)13:30~17:30
■主催: 公益社団法人 土木学会(海岸工学研究委員会・土木計画学研究委員会)
■場所: ミーティング or ウェビナー
■定員: 500名
■参加費: 無料
■開催趣旨:
土木学会では,2014年10月に減災アセスメント小委員会を発足させ,津波防災・減災について,対象津波の設定のみならず,まちづくりの観点も踏まえて,「豊かで安全なまちづくり」の具体的な手順を検討してきました.
今般,その成果として「津波に対する海岸保全施設整備計画のための技術ガイドライン」が完成しましたので,本セミナーを通してその内容を報告致します。
■プログラム:
13:30~ 開会挨拶 国土交通省水管理・国土保全局 局長 井上智夫
13:35~ 主旨説明 京都大学防災研究所 教授 多々納裕一
13:50~ 第1編 手順編 国土交通省水管理・国土保全局 海岸室長 奥田晃久
14:10~ 質疑応答
(休憩)
14:30~ 第2編 方法編 概説 関西大学環境都市工学部 准教授 安田誠宏
14:40~ 確率的津波水位の設定とcoRaL法 関東学院大学理工学部 准教授 福谷陽
15:10~ 粘り強さを加味した越流計算および被害計算 中央大学理工学部 教授 有川太郎
15:30~ 質疑応答
(休憩)
15:50~ 経済効率性照査 東北大学大学院情報科学研究科 教授 河野達仁
16:10~ 統計的生命価値とリスクプレミアム 京都大学防災研究所 准教授 藤見俊夫
16:20~ 第3編 実施編 ケーススタディ 株式会社建設技術研究所 牛木賢司
16:40~ 魅力あるまちづくりと両立させるには 宮崎大学地域資源創成学部 講師 尾野薫
17:00~ 質疑応答
17:20~ 閉会挨拶 東京海洋大学 教授 岡安章夫
司会 名古屋工業大学 教授 北野利一
■申込方法:土木学会ホームページ「本部主催行事の参加申込」にてお申込み下さい.
土木学会ウェブサイト(http://www.jsce.or.jp/event/active/information.asp)
■資料配布:
プレスリリース(2021.7.21)
津波に対する海岸保全施設整備計画のための技術ガイドライン(2021.6)
■関連情報:
海岸工学研究委員会
#12 土木計画学における政策と実践(2021年・年次学術講演会)
Date
2021年9月9日
Venue
オンライン
土木計画学における政策と実践
土木計画学における政策と実践I
2021年9月9日(木) 09:30 〜 10:50 IV-1 (Room15)
座長:小池 淳司(神戸大学)
[IV-01] 公共財としてではない社会基盤の価値
〇小池 淳司1 (1.神戸大学大学院工学研究科)
キーワード:社会基盤、価値、評価手法
[IV-02] 土木計画は人間の愚かさにどう向き合うのか
〇田中 皓介1 (1.東京理科大学)
キーワード:IoT、Society5.0、人工知能、スマートシティ、行動変容
[IV-03] 建設コンサルタントの実務経験を通した実践知に関する一考察
〇松本 浩和1、岡 英紀2、近藤 和宏3 (1.地域未来研究所、2.計量計画研究所、3.ライテック)
キーワード:土木計画、実践、建設コンサルタント、知の共有化
[IV-04] 東京都市圏物資流動調査の『実践力』
〇兵藤 哲朗1 (1.東京海洋大学)
キーワード:東京都市圏物資流動調査、物流拠点、実践
土木計画学における政策と実践Ⅱ
2021年9月9日(木) 11:10 〜 12:30 IV-1 (Room15)
座長:藤井 聡(京都大学)
[IV-05] 土木学会論文集D4(土木計画学:政策と実践)創刊に向けて
〇藤原 章正1 (1.広島大学)
キーワード:土木計画、実践的研究、土木計画学の両義性
[IV-06] モビリティやまちの改善における実践議論の必要性〜理想と現実のギャップを埋める〜
〇神田 佑亮1 (1.呉工業高等専門学校)
キーワード:土木計画実践、条件不利環境、政策マネジメント
[IV-07] 「実」から見た「学」
〇原 文宏1、伊地知 恭右1 (1.一般社団法人北海道開発技術センター)
キーワード:実務、学、物語
「津波に対する海岸保全施設整備計画のための技術ガイドライン」の公表について
「津波に対する海岸保全施設整備計画のための技術ガイドライン」の公表について
土木学会では,2014年10月に減災アセスメント小委員会を発足させ,津波防災・減災について,対象津波の設定のみならず,まちづくりの観点も踏まえて,「豊かで安全なまちづくり」の具体的な手順を検討してきました.今般,その成果として「津波に対する海岸保全施設整備計画のための技術ガイドライン」が完成し,公開の運びとなりましたのでお知らせ致します。
詳しくは,こちらをご覧ください。
土木学会論文集 D3特別企画「土木計画学:政策と実践」 投稿・査読委員募集
本特別企画は,現在準備・企画提案中の土木学会論文集の新カテゴリー「土木計画学:政策と実践」の前身として,土木学会論文集D3編集小委員会(轟委員長)が発行するものです。この企画は,土木計画学分野の研究においてその黎明期に強調されていた「土木計画の実践・政策についての研究」の論文の活性化を目指す,いわば原点回帰を企図した企画であります。皆様の積極的な投稿をお待ちしております。
詳しくは,こちらをご覧ください。
土木学会論文集D3・特集号(土木計画学研究・論文集)の論文募集(6月7日~18日17時まで)
土木学会論文集D3・特集号(土木計画学研究・論文集)の論文募集(6月7日~18日17時まで)
土木計画学研究委員会では,「土木学会論文集D3(土木計画学),Vol.77,No.5(土木計画学研究・論文集 第39巻)」(2022年4月発行予定)への投稿論文を募集します.土木計画学研究・講演集で発表された講演用論文の内容をさらに充実させた論文を,奮ってご投稿下さい.
詳しくは,こちらをご覧下さい。
第64回土木計画学研究発表会・秋大会(企画提案型)実施要領 【開催は終了しました】
Date
2021年12月3日(金)・4日(土)・5日(日)
Venue
オンライン(Zoom)形式 (開催協力校 福島大学)
第64回土木計画学研究発表会・秋大会 実施要領 【開催は終了しました】
第64回 土木計画学研究発表会・秋大会(企画提案型)実施要領
1.実施期日: 2021年12月3日(金)・4日(土)・5日(日)
2.開催場所: オンライン(Zoom)形式 (開催協力校 福島大学)
3.大会プログラム(スケジュール)
・ 大会プログラム(スケジュール)を公開します.
プログラムPDFファイル(2021年11月1日版)はこちら
・ 論文投稿時に発行されたIDにより発表会前(11月下旬を予定)に論文をHPよりダウンロードできるようにいたします.
4.土木学会論文集D3(土木計画学)特集号への投稿資格について
企画論文部門へ期限までに投稿された論文のうち,土木学会論文集D3の投稿の手引に従った形式(ただし英文要旨は任意)で執筆され,かつ2ページ以上の分量である論文については,土木計画学研究・講演集に掲載される論文として見なされ,土木学会論文集D3(土木計画学)特集号(以下,特集号と表記する)への投稿資格が得られます.論文タイトルと要旨のみで構成されており本文が記載されていないなど、定められた形式に従っていない原稿は,秋大会運営小委員会の判断により,土木計画学研究・概要集に掲載されません.その場合,土木学会論文集D3(土木計画学)特集号への投稿資格は与えられませんのでご注意ください.ただし,特集号への投稿資格を満たさない投稿論文であっても、企画論文部門セッションで発表することは可能です.
また,論文投稿されたにも関わらず実際には秋大会にて発表されていない論文,およびSS部門へ投稿された論文についても,特集号への投稿資格はありません.詳しくは,計画学ホームページをご覧下さい.
http://www.jsce.or.jp/committee/ip/monograph/file/journal-s-tebiki.pdf
5.論文投稿料について
企画部門の発表会投稿料(参加費を含む)は,講演1件につき一般12,000円,学生9,000円です.SS部門は,1セッションにつき,10,000円(参加費別)です.なお,オーガナイザーによる採否決定(2020年8月7日(金))後のキャンセルは,一切認められません.発表(講演)を辞退されても,発表会投稿料として料金を請求させて頂きますので十分にご注意ください.
6.参加申込みについて
参加登録(発表者以外の方):次の土木学会行事参加申し込みホームページ(こちら)より,ご登録ください.
聴講参加者の受付締切は12月1日(水),参加費は特例で一般,学生とも無料です.
11月27日(土)以降にお申込みいただいた場合は,発表会当日までに講演集CD-ROMが届かない可能性がございます.また,講演集CD-ROM については数に限りがございますので,先着順となりますことご了承ください.
なお,発表者(企画部門)は自動的に登録されていますので,あらためての参加登録は不要です.
スペシャルセッションのオーガナイザー,発表者の方は,参加登録が必要です.
7.CPDについて ▼ CPD受講証明を必要とされる方へ 本セミナーは、土木学会継続教育CPDプログラムですが、オンラインでの開催であり、 受講証明書を発行するにあたり通常の実地でのセミナーと異なる手続きが必要です。 受講証明書をご希望される方は、必ずセミナー終了後、下記Googleフォームより取得の申請をお願いいたします。 https://forms.gle/W7z1ZKyXxP1rwXNg7 受講証明書を発行するにあたって、「受講証明発行用アンケート(受講して得られた学びや所見を100文字以上で記載していただく等)」を ご提出していただくことが必要です。 建設系CPD協議会加盟団体CPDシステム利用者は、各団体のルールに沿って、CPD単位の申請をお願い致します。 他団体へCPD単位を登録する場合は、その団体の登録のルールに則って行われます。 単位が認定されるかどうかは、直接その団体にお問合せください。
8.問い合わせ先
土木計画学研究委員会秋大会運営小委員会
e-mail: keikaku64@jsce.or.jp
※土木計画学研究委員会HP http://www.jsce.or.jp/committee/ip/index.htm
参考:各種スケジュールのまとめ
●企画論文部門
企画テーマの応募 2021年6月18日(金)まで 【終了しました】
発表希望者の論文題目・概要の登録 2021年6月25日(金)~2021年7月23日(金)【終了しました】
オーガナイザーによる採否決定期間 2021年8月6日(金)~2021年8月27日(金)【終了しました】
発表希望者への採否通知期間 2021年8月30日(月)~9月3日(金)【終了しました】
論文投稿 2021年10月1日(金)まで【終了しました】
●スペシャルセッション(SS) 部門
テーマの申請 2021年6月18日(金)まで【終了しました】
発表者の決定 2021年8月6日(金)まで【終了しました】
第63回土木計画学研究発表会・春大会(自由投稿型)【開催は終了いたしました】
Date
2021年6月5日(土)・6日(日)
Venue
オンライン開催(担当:東北大学)
第63回土木計画学研究発表会・春大会(自由投稿型)
※開催は終了いたしました。参加された方々を始め、関係された皆さまには改めて感謝申し上げます。ありがとうございました。
2021.06.06:「優秀ポスター賞」を公開
2021.06.04:「会場へのアクセス」を公開
2021.06.02:プログラムを更新
2021.05.29:「口頭発表セッションについて」を公開
2021.05.24:「ポスターセッションについて」を公開
2021.05.18:「CPD受講証明を必要とされる方へ」を公開
2021.05.12:「事前参加申込について」を公開
2020.12.17:「会告」を公開
▼優秀ポスター賞
ポスターセッションでの審査により、優秀ポスター賞が下記のファイルの通りに決定いたしました。おめでとうございます。後日、受賞者の方々には大会運営小委員会からご連絡いたします。
・第63回土木計画学研究発表会優秀ポスター賞 【PDF】
口頭発表セッションの会場、ポスターセッションの会場、ランチョンミーティングへのアクセスは下記のミーティングID・URLをご利用ください。なお、パスワードは配布されたものをご利用ください。また、システムの都合上、各会場には定員がございます。大変申し訳ありませんが、あらかじめご了承ください。
・口頭発表セッション(Zoom)
第1会場:843 9245 9526 https://us02web.zoom.us/j/84392459526
第2会場:823 2313 9073 https://us02web.zoom.us/j/82323139073
第3会場:870 6414 2554 https://us02web.zoom.us/j/87064142554
第4会場:839 0063 8705 https://us02web.zoom.us/j/83900638705
第5会場:873 0390 9423 https://us02web.zoom.us/j/87303909423
第6会場:875 8163 9626 https://us02web.zoom.us/j/87581639626
第7会場:812 2377 4604 https://us02web.zoom.us/j/81223774604
第8会場:813 1110 2731 https://us02web.zoom.us/j/81311102731
第9会場:840 0556 9665 https://us02web.zoom.us/j/84005569665
※各会場の定員は300名です。
・ポスターセッション(SpatialChat)
https://spatial.chat/s/ip63spring
上記URLからアクセス後、ポスターセッション1(9:00~10:30)はRoom1-1~1-6、ポスターセッション2(10:40~12:10)はRoom2-1~2-6にご移動ください。
※各部屋(Room1-1~2-6)の定員は50名です。
・ランチョンミーティング(Zoom)
ランチョンミーティングは6月6日(日)の昼休み(12:10~13:20)に実施いたします。
307 643 0984 https://us02web.zoom.us/j/3076430984
プログラム概要・会場へのアクセス情報・ポスターセッションの会場を含めたプログラムを公開しました。(2021年6月2日)
・第63回土木計画学研究発表会プログラム(6月2日版)【PDF】
※ポスターセッションで発表される方はご自分の発表場所をご確認ください。
第63回土木計画学研究発表会の口頭発表セッションはZoom(https://zoom.us/jp-jp/meetings.html)を利用します。Zoomの利用方法や口頭発表セッションでの注意事項(司会者・コメンテータ・発表者・聴講者)については、以下のファイルを参照してください。
・第63回土木計画学研究発表会口頭発表セッション注意事項(5月29日版) 【PDF】
・第63回土木計画学研究発表会Zoom使い方マニュアル(5月28日版) 【PDF】
第63回土木計画学研究発表会のポスターセッションはSpatial Chat(https://spatial.chat/)を利用します。Spatial Chatの利用方法については、以下のファイルを参照してください。※ポスターセッションはSpatialChat内でポスター掲示場所が分かれております。6月2日に公開されたプログラムで発表場所の確認をお願いいたします。
・第63回土木計画学研究発表会(春大会)ポスターセッションについて 【PDF】
参加申込(発表者以外の方)は土木学会の本部主催行事の参加申込のページ(http://www.jsce.or.jp/event/active/information.asp)からご登録ください。発表者の方は自動的に登録されていますので、改めての参加申込は不要です。
聴講参加者の受付締切は6月2日(水)、参加費は特例で一般、学生ともに無料です。
以下の参加申込書をダウンロードし、必要事項を記入して土木学会宛にお送りいただくこと(FAXまたは郵送)でも、参加申込は可能です。締切および参加費はウェブサイトからの申込の場合と同じです。
・参加申込書 (http://www.jsce.or.jp/event/active/form.pdf)
注意事項
5月25日(火)以降にご登録いただいた場合、発表会当日までに講演集 CD-ROMが届かない可能性がございます。また、講演集CD-ROMについては数に限りがあるため、先着順となりますことをご了承ください。
本セミナーは、土木学会継続教育CPDプログラムですが、オンラインでの開催であり、受講証明書を発行するにあたり通常の実地でのセミナーと異なる手続きが必要です。
- 受講証明書をご希望される方は、必ずセミナー終了後、下記Googleフォームより取得の申請をお願いいたします。
https://forms.gle/GDjc6oYdatSbhQAQ6 - 受講証明書を発行するにあたって、「受講証明発行用アンケート(受講して得られた学びや所見を100文字以上で記載していただく等)」をご提出していただくことが必要です。
- 建設系CPD協議会加盟団体CPDシステム利用者は、各団体のルールに沿って、CPD単位の申請をお願い致します。
- 他団体へCPD単位を登録する場合は、その団体の登録のルールに則って行われます。単位が認定されるかどうかは、直接その団体にお問合せください。
▼ 第63回土木計画学研究発表会 講演の申込み ※講演申込は終了いたしました。
土木計画学研究発表会(春大会)講演申込ページ
※上記のリンクから講演を申し込んでください。なお、講演申込に際して、下記の会告を十分にご確認ください。
オンラインでの開催
新型コロナウィルス感染症の拡大状況について先行きが不透明かつ感染拡大防止のために求められる密とならない会場の確保が困難であるため、第63回土木計画学研究発表会は東北大学を担当校としたオンライン開催とします。詳細な実施方法は改めて連絡をいたしますが、ウェブ会議サービス「Zoom」を利用する予定です。
講演用論文
発表会の当日に十分な時間で充実した議論を行い、更なる研究の発展や学術論文等への取りまとめに繋げることが本発表会の特色です。このため、「具体的に議論したい点(研究の新規性や枠組み、データ、モデルや結論の妥当性、今後の発展性や疑問点など)」を明記して申込みしていただきます。話題性、速報性のある論文や、調査・計画、技術検討等の事例報告も歓迎します。提出された講演用論文は、原則として無審査で掲載されますが、お断りすることもあります。
発表希望分野については、通常の発表希望分野Ⅲと並行して、発表希望分野Ⅰ(特別論文セッション)及び発表希望分野Ⅱ(手法等分野横断的区分)での発表希望もお願いしています。こちらへの応募もよろしくお願いします。
また、ポスターセッション、および「優秀ポスター賞」の表彰を実施いたします。受賞対象は、投稿時点における学生です。博士後期課程の学生を含ますが、博士後期課程の学生については発表時点においても学生である方に限ります。
口頭発表とポスターでの発表のどちらを希望するかを選んで申込んでいただきます(口頭発表およびポスターでの発表のいずれも、2022年に発刊予定の「土木学会論文集D3(土木計画学),Vol.77-5」への投稿対象となります)。
※2022年に発刊予定の「土木学会論文集D3(土木計画学),Vol.77-5」への投稿には、
①第60〜63回の土木計画学研究・講演集に掲載されている
②第60回、第62〜63回の土木計画学研究・講演集に掲載されたものは、研究発表会において、著者により当該論文の発表が行われている(発表が行われていない、または著者以外によって発表された論文は投稿不可)
③第60回・第62回の土木計画学研究・講演集に掲載された論文は企画論文部門へ投稿され、土木学会論文集D3の投稿の手引きに従った形式(ただし英文要旨は任意)で執筆され、かつ2ページ以上の文量である
ことが必要となりますので、あらかじめご了承ください。
なお、Vol.77-5への投稿期限は2021年6月の予定となります。
※2019年度より土木計画学研究発表会春大会と秋大会の実施内容の一部が入れ替わるのに伴い、土木学会論文集D3の投稿・発刊時期、対象となる発表論文等に大幅な変更がございました。
詳しくは、土木学会論文集D3・特集号(土木計画学研究・論文集)投稿の手引きにてご確認ください。
講演の申込み(講演の申込は終了しました)
(1) 申込みの手続きおよび注意点
2021年2月1日(月)~3月7日(日)17時までの期間内に、土木計画学研究発表会(春大会)講演申込みページより、講演申込と講演原稿の投稿を同時に行ってください。原稿のファイル形式はPDF形式のみ受付けます。 原稿は「講演原稿執筆要領」に従ってご執筆ください。締切日当日までは、投稿した原稿の確認、差し替えが可能ですが、締切日以降は、原稿の差し替えは受け付けられません。十分、ご注意ください。投稿時に、必ず申込内容が正しいか、PDFを取り違えての投稿がないか、申込内容とPDFのタイトル等の差異がないかなどをご確認ください。申込み期間の締切り間際に投稿が集中しますと、予期せぬ事態によりサーバーがダウンし受付ができなくなる恐れがあります。締切り間際の投稿は極力避けていただくようお願いいたします。
なお、講演原稿執筆要領に準じていないもの、および期限後に投稿されたものは受理できません。必ず所定の原稿を期間内にWEB上にて投稿してください。
間違えたファイルを提出した場合や申込内容とPDFの内容が違う場合であっても、そのまま掲載されますので、ご注意ください。
(2) 発表希望分野
(i) 発表希望分野Ⅰ(特別論文セッション)
充実した議論を実現するための、「特別論文セッション」を実施いたします。特別論文セッションでは、論文内容を踏まえたコメントに基づいた議論を行います。ただし、投稿論文数(最大で30編程度)、論文内容により、発表希望分野IIIでの発表となる場合もあります。
・1件当たりの持ち時間は、発表25分、コメンテーターによるコメント10分、討議10分の計45分とします。
・特別論文セッションでの発表を希望される方は、8ページ以上の論文を投稿することが必要です。
・発表者は投稿時にコメンテーター希望者を伝えることができます。
(ii) 発表希望分野II(手法等分野横断的区分)
従来の研究対象ごとの発表区分に加えて、研究で用いられている方法論に注目した分野横断的区分でのセッションを実施します。分野横断的区分セッションで発表を希望される場合には、今回は以下の5つから選択いただけます。さらに、そのセッションの司会兼コメンテーターでご希望の先生がいればご記入いただけます。これらの情報を参考に、専門性の高い先生への司会依頼を行うなどの検討を行う予定です。ただし、適切なセッションを組めない場合には、上記の発表希望分野Ⅰの従来型のセッションでの発表になります。
・新分析手法(まだ適用事例の少ない統計的手法(例.機械学習的分析手法)や記述的研究(例.物語研究)などの有効性等を議論したい研究)
・理論モデリング(実現象の理論的なモデリング、情報科学やゲーム理論などを駆使した手法について議論したい研究)
・統計分析解釈(一般的な統計分析の考察が重要な位置を占めており、その内容や妥当性について重点的に議論したい研究)
・海外事例(海外の事例的研究として集中的に議論したい研究)
・その他、重点的に議論したい分野横断的内容があればそのキーワードを直接書いていただくことも可能
(iii) 発表希望分野III(研究対象区分)
申し込みに際して、発表希望分野を下記の5つの発表分野から希望順に2つ選んでください。また、キーワードにつきましては、同キーワード欄の中から最大4つ選んでください。なお、適当なキーワードが見つからない場合は、投稿者の判断によるキーワードを1つだけ加えてください。
発表希望分野
| 発表希望分野 | キーワード |
| A 計画論・計画情報 | 計画基礎論、計画手法論、システム分析、調査論、公共事業評価法、財源・制度論、プロジェクト構想、施工計画・管理、維持管理計画、意識調査分析、計画情報、情報処理、市民参加、GIS、リモートセンシング、測量、環境計画、防災計画、河川・水資源計画、ライフライン計画・設計、地球環境問題 |
| B 地域・都市・景観 | 国土計画、地域計画、都市計画、地区計画、住宅立地、産業立地、人口分布、地価分析、土地利用、市街地整備、再開発、景観、公園・緑地、観光・余暇、空間設計、イメージ分析、土木史 |
| C 交通現象分析 | 発生交通、目的地選択、交通手段選択、経路選択、出発時刻選択、活動分析、時間利用、交通行動調査、交通意識分析、交通行動分析、自動車保有・利用、駐車需要、交通ネットワーク分析、土地利用・交通・環境統合モデル、観光・余暇行動 |
| D 交通基盤計画 | 総合交通計画、地区交通計画、公共交通計画、歩行者・自転車交通計画、道路計画、鉄道計画、空港・港湾計画、ターミナル計画、駐車場計画、物流計画 |
| E 交通運用管理 | 交通流、交通容量、サービス水準、交通制御、交通管理、交通安全、交通情報、交通環境、公共交通運用、交通弱者対策、水上交通、空港管理、交通量計測、TDM、ITS、モビリティマネジメント(MM) |
(3) 発表形式
口頭発表とポスターでの発表のどちらを希望するかを選んでいただきます。なお、ご希望に添えない場合もありますので予めご了承下さい。
(4) 投稿料
講演1本につき投稿料(参加費含む)として一般12,000円、学生9,000円を請求いたします。2本以上投稿する方については、2本目以降の投稿料は一般・学生ともに6,000円を請求いたします。振込手数料は各自でご負担願います。
講演原稿執筆要領
講演原稿の書式・形式は、土木学会論文集のものに準じています。下記の作成例やサンプルファイルをご利用ください。講演原稿では、英文アブストラクトの記入は任意です。その他書式・形式についての詳細は土木学会論文集の原稿作成の手引き等をご参照ください。なお、「土木学会論文集D3(土木計画学), Vol.77-6」への投稿の際には英文アブストラクトは必要です。
サンプルファイル 和文(Word2000)/English(Word2000)
原稿作成例 和文(PDF)/English(PDF)
▼お問合せ先
土木計画学研究委員会大会運営小委員会(春大会担当:岸,日野,小澤)
E-mail:keikaku63@jsce.or.jp
#11 土木における実践の学(2020年・年次学術講演会)
Date
2020年9月9日
Venue
オンライン
土木における実践の学
2020年9月9日 第IV部門
土木における実践の学
座長:藤井 聡(京都大学)
[IV-54] 効率性と公平性の視点からの地域交通の性能とサービスの定義と運用の検討―大野城市コミュニティバス「まどか号」の例から―
〇松永 千晶1 (1.福岡女子大学)
キーワード:インフラ政策学、地域交通、公平性、効率性
本稿は,大野城市のコミュニティバス「まどか号」の見直し事例紹介を通じて、「地域交通の効率性と公平性を決める性能・サービスとは何か?」,「効率性と公平性を満たす地域交通サービスの最適化の方法とは?」という問いに対し,地域交通サービスを対象とし,「効率性と公平性を満たすサービスのあり方の検討」を目的としたものである.その上で,交通工学,交通計画学さらに厚生経済学や公共経済学の観点からその性能・サービスと効果を定義した上で,定量化を試みる必要性を述べたものである.
[IV-55] 利用者視点の多様性に着目した交通空間設計の実践における新たな課題
〇稲垣 具志1、秋山 哲男1 (1.中央大学)
キーワード:土木における実践の学、空間設計、利用者の多様性、道路設計、空港、ユニバーサルデザイン
公共の交通空間を設計するには空間の利用者の多様性にいかに対応することができるかが重要となる。特に移動に配慮が必要となる高齢者、障害者等を含めたすべての利用者の安全と円滑を確保するためには、設計者はそれぞれの立場における問題点やニーズをとらえ、総合的に一つの公共空間をつくることが求められる。本稿では道路空間、公共交通空間における具体例を示しながら、今後の道路空間設計における実践上の課題について示す。
[IV-56] 地域観光政策の現状と課題
〇栗原 剛1 (1.東洋大学)
キーワード:観光政策、地域観光、DMO
本稿では,インフラ政策学の研究対象のひとつである地域観光政策をとりあげ,わが国の地域で取り組まれている地域観光政策の現状と課題を整理し,今後の地域観光政策のあり方に対して問題提起することを目的とする.現状では観光政策をおこなうことで地域にどのような効果が期待されるのかを十分に検討されているとは言い難く,その点に地域観光政策の課題があると考えられる.現在,DMOには必須KPI以外のKPI設定は任意となっているが,その制度がDMOの観光政策立案・評価とミスリードしている恐れがある.そこで,観光施策一つ一つに対応するKPIを独自で設定することを求めることが有効であると考えられる.
[IV-57] 地域公共交通分野の「実践知」と対話プラットフォームの形成
〇吉田 樹1 (1.福島大学)
キーワード:地域公共交通、実践知、対話プラットフォーム
地域の交通課題を解決する手法は,場所に応じて編集しなおすことが求められ,既往の研究成果や計画技法を「そのまま」適用させることが難しく,実践に基づく研究成果が個別事例の報告に止まるケースも見られる。一方,典型的な被規制産業である地域公共交通分野は,ステークホルダーが参画する法定協議会制度が確立されており,ローカルな取り組みから「実践知」を形成することで,国全体の政策にインパクトを与え,より佳い社会に向けた漸次的な改善に寄与することも期待される。本稿は,地域公共交通に関わるローカルな取り組み事例から「実践知」とステークホルダーとの対話プラットフォームを形成するために求められる観点を検討する。
[IV-58] 実務者の視点から、土木計画学・インフラ政策学を考える
〇白水 靖郎1 (1.中央復建コンサルタンツ株式会社)
キーワード:土木計画学・インフラ政策学
土木計画・インフラ政策の実務において,定量的評価は必要条件ではあるものの十分条件ではない.また,精緻なモデル理論よりも,前提条件の考え方や勘と経験に根ざした評価が重要になるケースも多い.本稿では,建設コンサルタントという筆者の実務経験に基づき,これからの時代に求められる「土木計画学・インフラ政策学」の意義とあり方について意見を述べたい.
[IV-59] 大規模自然災害後の交通サービスマネジメントに関する実践的考察 〜平成30年7月豪雨の広島〜呉間の交通マネジメントの実践から〜
〇神田 佑亮1 (1.呉工業高等専門学校)
キーワード:大規模自然災害、交通需要マネジメント、災害時BRT、リスクマネジメント
平成30年7月の西日本豪雨災害は,広い範囲で同時に発生した土砂洪水氾濫により深刻な被害をもたらした.広島都市圏では,高速道路を含む幹線道路や鉄道が各地で寸断した.筆者らは,交通関係行政機関や公共交通事業者と連携し,全国初の「災害時BRT」をはじめとした,速達性・信頼性の高い発災後の公共交通サービスの確保をはじめとした交通マネジメントに主体的に携わった.本報告では,特に施策展開や施策展開の判断等の実践の経験から,今後の大規模自然災害後の交通障害への対応に備え,交通サービス確保に向けたマネジメントのあり方について述べる.
#10 土木と教養(2020年・年次学術講演会)
Date
2020年9月9日
Venue
オンライン
土木と教養
第IV部門 2020年9月9日
土木と教養
座長:小池 淳司(神戸大学)
[IV-60] 土木計画における数理モデル学習と教養
〇田中 皓介1 (1.東京理科大学)
キーワード:効用最大化、合理的選択理論、プライミング効果
土木計画学が目指すものは,インフラ整備を通したより善き社会の実現に資することであろう.整備するインフラが過大ないしは過小なものにならぬよう,事前にモデルによる予測を行うのであり,これまでこの分野で積み重ねられてきた費用便益分析や効用最大化理論に基づく離散選択モデルといった技術はそのための強力なツールである.そうしたツールに頼るか否かにかかわらず,適切な価値判断ができるということこそ教養である.ただし,人間の価値が単一の指標に還元することのできない複雑なものである以上,過度に単純化した価値判断は教養とはいえない.本稿は大学講義による数理モデル学習が,教養に及ぼす影響を考察するものである.
[IV-61] 教養と土木の関係性及び教養の獲得方法としての漫画に関する一考察
〇松本 浩和1 (1.株式会社地域未来研究所)
キーワード:教養、土木計画、メディア、漫画
本研究では、教養と土木の関係性について論じ、土木に関連した教養の獲得方法の考察を通じて、よりよい土木のあり方に資する知見を得ることを目的としている。様々な文献における教養の定義を整理し単なる知識ではない教養が示す広範な概念を整理するとともに、土木と教養との関係性を論じる。また教養獲得のために想定される手法と教養を獲得する対象について整理し、その一手法としての漫画の活用可能性について具体例を通して考察する。
[IV-62] 土木計画学における事実と価値
〇泊 尚志1 (1.東北工業大学)
キーワード:政策学、意思決定、事実、価値
本稿は,「土木計画・学」を改めて「政策学」の領域として捉える1)という議論に際して,この領域で求められる各種の「解」に相当するものが,事実と価値の観点からどのように理解されるべきものかという非常に基礎的なかついわば当然の議論について改めて取り上げることにより,講演時に二,三の簡単な論点を提示することをねらいとしたものである.本稿のタイトルが,その内容に対して非常に大風呂敷を広げたものになっているばかりか雑駁な内容となっているが,セッション参加者および読み手の皆様にご容赦いただきたい.
[IV-63] 教養の本質は「多様な人生経験」であり、「インフラ政策」において絶対的に不可欠である。
〇藤井 聡1 (1.京都大学大学院)
キーワード:教養、土木計画学、インフラ政策学、可能態、実現態
教養とは、単なる知識とは異なるものであり、教え養われ獲得されたものを意味する。したがって、その習得は単に学校教育だけで身につくものではなく、ありとあらゆる経験を通して獲得されるものである。そして、こうした経験があって始めて、他者の気持ちや思いを推し量ることが可能となる。したがって、道路や港湾、堤防などの我々の社会の基礎的なインフラを、その上で暮らす人々の気持ちや幸福を慮りながら作り上げていく、インフラ政策を展開するにおいて、そうした教養が必要非可決となる。さもなければ、そのインフラによって人々の暮らしや幸福が如何に変化するかを何ら理解できなくなるからである。
#9 日本経済と土木(2020年・全国大会研究討論会)
Date
2020年9月8日
Venue
オンライン
日本経済と土木
タイトル:日本経済と土木
・主題
社会資本整備に代表される公共事業のマクロ経済への影響を改めて議論し,特に,失われた20年以降のデフレ状況下におけるフロー効果・ストック効果の役割,さらに,税制・国債発行などの財政政策の関係から,より実践的な視点と、MMT等の最新の経済学の視点から,日本経済における土木の役割を改めて討議する.
・座長
藤原章正(広島大学大学院国際協力研究科教授)
・話題提供者
藤井聡(京都大学大学院工学研究科教授)
柴山圭太(京都大学大学院人間・環境学研究科准教授)
小池淳司(神戸大学大学院工学研究科教授)
田村秀男(産経新聞特別記者)
土木学会論文集D3分冊「COVID-19特別企画」投稿募集
土木学会論文集D3分冊「COVID-19特別企画」投稿募集
企画趣旨
COVID-19は、土木計画学が研究対象としてきた都市活動、交通行動、経済・産業活動に対して大きな影響をもたらした。そしてそれを通して、土木計画学における根幹テーマである、インフラ政策論、国土政策、交通政策といった「土木計画」の「あり方」に甚大な影響をもたらしている。
こうした状況を鑑みれば、土木計画学研究委員会を中心とした一つのアカデミズム・コミュニティはこのCOVID-19によって社会・経済、そして「土木計画」もたらされた多面的な影響を分析し、かつ、その影響を十分に踏まえた研究活動を実践的かつ学術的に展開していく責務を負っていると言うことができよう。
ついては,COVID-19により土木計画学に関連する領域にもたらされた影響や対応等の研究・実践などの報告・速報論文をとりまとめた特別企画を土木学会論文集D3において企画する.
スケジュール
2020年 9月 1日(火) 投稿開始
2020年 9月30日(水) 投稿締め切り
2020年10月~11月上旬 査読期間
2020年11月中旬(予定) 登載可否決定
2021年 1月(予定) 掲載
※登載可否決定・掲載時期は査読の進捗状況により遅れる可能性があります。
投稿要領
- 本企画への投稿は、⼟⽊学会論⽂集投稿システム(https://jjsce.jp/)からログイン後、「新規投稿」にお進みいただき、論⽂、報告、ノートのいずれかの投稿区分を選んでください。
- 投稿分冊は「D3分冊(土木計画学)」を選んでください。※通常の「D3分冊」と同じです。
- 投稿受付後、内容により「COVID-19特別企画」か「通常号」かを、編集委員会により判断いたしますが、見落としを防ぐために、投稿の際には担当の田中(tanaka.k(at)rs.tus.ac.jp)までご一報いただけますと幸いです(メール送信の際は(at)を@に変換ください)。
- 投稿要領、論⽂書式、査読⽅法等は⼟⽊学会論⽂集に準拠します。詳しくは、⼟⽊学会論⽂集投稿要領のページ(http://committees.jsce.or.jp/jjsce/j_post)を参照ください。
COVID-19に関する土木計画学研究発表セミナー
COVID-19に関する土木計画学研究発表セミナー
趣旨
COVID-19は、土木計画学が研究対象としてきた都市活動、交通行動、経済・産業活動に対して大きな影響をもたらした。さらには,土木計画学の根幹テーマである、インフラ政策論、国土政策、交通政策といった「土木計画」の「あり方」について根本的な再考を促しているように思われる。
こうした状況を鑑み、土木計画学研究委員会を中心とした一つのアカデミズム・コミュニティは、COVID-19によって社会・経済、そして「土木計画」にもたらされた多面的な影響を分析し、かつ、その影響を十分に踏まえた研究活動を実践的かつ学術的に展開していく責務を負っていると言えよう。
土木計画学研究委員会ではこの度、COVID-19に関する計画学研究の活性化を企図し、速報的研究も含めたオンライン発表会を開催することを企画した。
なお、本セミナーは、今後の土木計画学研究発表会などの場も含めたシリーズ開催を想定している。また、各発表は最終的に何らかの形で学術論文化し、COVID-19に立ち向かう「知識」と「知恵」として、その成果を後世に伝えたい。
土木計画学研究委員会委員長 兵藤哲朗
開催情報
日時:8月8日(日) 13:00~17:55
場所:Zoom および YouTube Live
アーカイブ動画(限定公開):https://youtu.be/tGU_Ah8KF-A
プログラム
※各発表のアブストラクトはこちら
■ 開会挨拶 兵藤哲郎委員長
■ セッション1:認知と行動 13:05~14:35 司会:藤井聡
- COVID-19に関する行動・意識の基礎的調査(資料・動画)
田中皓介・藤井聡・兵藤哲朗・藤原章正 - 新型コロナウイルスの感染リスク及び対策に関する市民の態度の研究(資料・補足資料・動画)
田中駿也・川端祐一郎・藤井聡 - リスク認知と社会的影響がCOVID-19パンデミックに対する自粛行動に及ぼす影響の分析(動画)
パラディジアンカルロス・谷口綾子・高見淳史
質疑(動画)
- 地域封鎖と住民の生活(ベトナム ソン・ロイ村封鎖事例)(資料・動画)
伊藤秀行・Vuong Thi Tuyet Trinh・横松宗太 - 日本のCOVID-19感染拡大初期段階における自発的な行動変化の調査分析とLASTアプローチによる対策の提案(動画)
張峻屹・Baraa Alhakim - 飲酒活動と幸福感:新型コロナウイルスの影響(資料・動画)
大森宣暁 - 世界交通学会COVID-19タスクフォース専門家調査結果からみた世界の感染現象、緊急対策と新常態のあり方について(資料・動画)
林良嗣・張峻屹
質疑(動画)
■ セッション2:移動と交通 14:45~16:15 司会:佐々木邦明
- モバイル空間統計による全国移動実態分析(2020年1月~5月)(資料・動画)
有村幹治・佐々木邦明・瀬谷創・塚井誠人・原祐輔・兵藤哲朗・福田大輔・円山琢也・柳沼秀樹・山口裕通・鈴木俊博・浅野礼子・斧田佳純 - 自動測定器でみた中心市街地の通行量の変化~地方都市である宇都宮市の事例~(資料・動画)
長田哲平・我妻智世・大森宣暁 - 80%移動制限は達成できたのか?-福岡市を対象とした移動データとシナリオ分析からの結論-(資料・動画)
溝上章志・栄徳洋平・高嶋裕治・船本洋司
質疑(動画)
- COVID19感染拡大と政府による自粛要請が公共交通に与える影響(資料・動画)
神田佑亮・太田恒平・牧村和彦・藤井聡・鈴木春菜・藤原章正 - COVID-19による緊急事態宣言時の国道16号線の交通量変動(動画)
萩田賢司 - COVID-19蔓延期の行動実態とその要因の日英独三カ国比較(資料・動画)
石橋拓海・谷口綾子・河合晃太郎・Giancarlos Troncoso Parady・高見淳史
質疑(動画)
■ セッション3:政策と制度 16:25~17:55 司会:小池淳司
- 新型コロナウイルス感染死による余命損失に関する研究(資料・動画)
上田大貴・田中駿也・川端祐一郎・藤井聡 - 自然災害及びパンデミック時の「命の選別」をめぐる倫理学的な課題に関する研究(資料・動画)
川端祐一郎 - 特設サイトを通じた感染防止策や運行支援策に関する情報発信~有事における国の施策を受けた地方自治体の制度設計を支援するために~(資料・動画)
井原雄人・太田恒平・諸星賢治・加藤博和
質疑(動画)
- The city-level spread of COVID-19 at its initial stages in China: An analysis of its associations with the built environment factors by reflecting spatial heterogeneity(動画)
Shuangjin Li・Shuang Ma・Junyi Zhang - 交通運輸部門におけるCOVID-19政策立案方法「PASSアプローチ」の提案とアジア・中東の都市を対象とする事例分析(動画)
張峻屹・吉田拓樹・Baraa Alhakim - 新型コロナウイルスによる交通崩壊の危機を訴えるオンラインイベント緊急開催の経緯と効果(資料・動画)
加藤博和・伊藤昌毅・井原雄人・清水弘子・太田恒平・岡村敏之・成定竜一 - コロナ社会における土木計画学の研究課題(資料・動画)
権利と効率のストック効果に関する研究小委員会
質疑(動画)
■ 閉会挨拶 白水靖郎副委員長
第 61 回土木計画学研究発表会(6月13~14日:大阪大学)中止とオンライン開催試行のお知らせ【2020年6月4日追記】
第 61 回土木計画学研究発表会(6月13~14日:大阪大学)中止とオンライン開催試行のお知らせ
オンライン開催を試行致します。詳しくはこちらをご確認ください。
~~~~~~~~~~~~~
新型コロナウイルス感染症の拡大による政府の緊急事態宣言が6月時点でどのように推移するのか見通せないことから、6/13より大阪大学で開催予定でした第61回土木計画学研究発表会の開催を中止させていただくこととなりました。
皆様方には、大変、ご迷惑をおかけいたします。また、開催校である大阪大学の関係者の皆様には開催に向けて既に多大なご苦労をおかけいたしておりましたが、よろしくご了承ください。
なお、土木計画学研究・講演集(CD-ROM)は発刊されます。論文投稿いただいた方には後日送付いたします。
発表講演集に掲載・公開された論文については、本研究発表会での講演発表が成立したものとして扱います。発表申込料の払い戻しは致しません。
従って、発表会は中止になりましたが、発表会に論文投稿されていた方の「土木学会論文集D3(土木計画学),Vol.76-5」への投稿は可能です。
参加者が集まって行う発表会は中止といたしますが、研究発表したい人、発表を聴きたい人のために、別途、zoom会議室を開設し、オンライン開催を試行します。
詳細は、後日、改めてお知らせいたします。
引き続きよろしくお願いいたします。
2020年5月13日
土木学会 土木計画学研究委員会委員長
藤原章正
第62回土木計画学研究発表会・秋大会(企画提案型)【開催は終了しました】
Date
2020年11月13日(金)・14日(土)・15日(日)
Venue
Zoomによるオンライン開催に変更
(信州大学 長野(工学)キャンパス及びJA長野県ビル)
第62回土木計画学研究発表会・秋大会(企画提案型)【zoom会場の情報,CPDについてを公開しました】【発表会プログラムを公開しました】【参加申し込みの受付を開始しました(2020年10月13日)】
第62回土木計画学研究発表会・秋大会(企画提案型)実施要領
第62回土木計画学研究発表会秋大会(企画提案型)の大会スケジュール(発表会プログラム)を公開します。
CPDについてを掲載しました。詳細は「7.CPDについて」をご覧ください。
10月13日より参加申し込みの受付を開始しました。参加費は特例で一般,学生とも無料です。詳細は「4.参加申込みについて」をご覧ください。
1.実施期日 2020年11月13日(金)・14日(土)・15日(日)
2.開催場所 Zoomによるオンライン開催
(信州大学 長野(工学)キャンパス及びJA長野県ビル より変更)
・zoom会場情報(パスワードは申込頂いた方に別途配信しています)
3.大会スケジュール
・ 発表会プログラムを公開します(2020年10月12日).
PDF(2020年11月9日版)はこちら
・ 論文投稿時に発行されたIDにより発表会前に論文をHPよりダウンロードできます.情報は申込頂いた方に別途配信しています.
・委員会報告(11/14(土)15:00~16:00):資料
4.参加申込みについて【10月13日(火)より開始しました】
参加登録(発表者以外の方):次の土木学会行事参加申し込みホームページ(http://www.jsce.or.jp/event/active/information.asp)より,ご登録ください.
聴講参加者の受付締切は11月11日(水),参加費は特例で一般,学生とも無料です.
11月7日(土)以降にお申込みいただいた場合は,発表会当日までに講演集CD-ROMが届かない可能性がございます.また,講演集CD-ROMについては数に限りがございますので,先着順となりますことご了承ください.
なお,発表者(企画部門)は自動的に登録されていますので,あらためての参加登録は不要です.
スペシャルセッションのオーガナイザー,発表者の方は,参加登録が必要です.
以下の参加申込書をダウンロードし,必要事項を記入して土木学会宛にお送りいただく(FAX,郵送)ことでも,参加登録は可能です.締切および参加費はホームページからの申し込みの場合と同じです.
参加申込書(http://www.jsce.or.jp/event/active/form.pdf)
- 事前参加申し込みに関する注意事項
・事前参加申し込みの締め切りは11月11日(水)となっております.事前申し込みをされた方には,発表会前までに,「Zoom会場URL」をお送りする予定です.
・締切日以降の事前受付はいたしません.
・お申し込み後,やむを得ずキャンセルされる場合は,必ず開催日の1週間前までに研究事業課宛にご連絡ください(担当:研究事業課 小澤,k-ozawa@jsce.or.jp, 03-3355-3559).
- 発表の要領
第62回土木計画学研究発表会(秋大会)はZOOMによるオンライン開催とします.その発表要領についてはオーガナイザーから配信させて頂きます.
5.土木学会論文集D3(土木計画学)特集号への投稿資格について
企画論文部門へ期限までに投稿された論文のうち,土木学会論文集D3の投稿の手引に従った形式(ただし英文要旨は任意)で執筆され,かつ2ページ以上の分量である論文については,土木計画学研究・講演集に掲載される論文として見なされ,土木学会論文集D3(土木計画学)特集号(以下,特集号と表記する)への投稿資格が得られます.論文タイトルと要旨のみで構成されており本文が記載されていないなど、定められた形式に従っていない原稿は,秋大会運営小委員会の判断により,土木計画学研究・概要集に掲載されません.その場合,土木学会論文集D3(土木計画学)特集号への投稿資格は与えられませんのでご注意ください.ただし,特集号への投稿資格を満たさない投稿論文であっても、企画論文部門セッションで発表することは可能です.
また,論文投稿されたにも関わらず実際には秋大会にて発表されていない論文,およびSS部門へ投稿された論文についても,特集号への投稿資格はありません.詳しくは,計画学ホームページをご覧下さい.
http://www.jsce.or.jp/committee/ip/monograph/file/journal-s-tebiki.pdf
6.論文投稿料について
企画部門の発表会投稿料(参加費を含む)は,講演1件につき一般12,000円,学生9,000円です.SS部門は,1セッションにつき,10,000円(参加費別)です.なお,オーガナイザーによる採否決定(2020年8月7日(金))後のキャンセルは,一切認められません.発表(講演)を辞退されても,発表会投稿料として料金を請求させて頂きますので十分にご注意ください.
7.CPDについて
【CPD受講証明を必要とされる方へ】 本セミナーは、土木学会継続教育CPDプログラムですが、オンラインでの開催であり、受講証明書を発行するにあたり通常の実地でのセミナーと異なる手続きが必要です。 ・受講証明書をご希望される方は、必ずセミナー終了後、下記Googleフォームより取得の申請をお願いいたします。 https://forms.gle/SbuxosLHYAuY6PV38 ・受講証明書を発行するにあたって、「受講証明発行用アンケート(受講して得られた学びや所見を100文字以上で記載していただく等)」をご提出していただくことが必要です。 ・建設系CPD協議会加盟団体CPDシステム利用者は、各団体のルールに沿って、CPD単位の申請をお願い致します。 ・他団体へCPD単位を登録する場合は、その団体の登録のルールに則って行われます。単位が認定されるかどうかは、直接その団体にお問合せください。
7.問い合わせ先
土木計画学研究委員会秋大会運営小委員会
e-mail: keikaku62@jsce.or.jp
※土木計画学研究委員会HP http://www.jsce.or.jp/committee/ip/index.htm
#210 バイオミメティックス国際セミナー
Date
2020年3月10日〜11日
Venue
大阪大学
バイオミメティックス国際セミナー
Living MateriArchitecture: 生物に学ぶ材料と建築・都市デザイン
~nmからkmのバイオミメティックス~
<3月10日(火)>
10:30~10:40 齋藤 彰 (大阪大学(工)精密科学 准教授)
開会あいさつ
10:40~11:10 岡田 明彦 (NEDO技術戦略研究センター)
社会的ニーズに基づくNEDOによる技術アプローチ
11:10~12:20 Thomas SPECK (ドイツ Univ. of Freiburg 教授)
生物に学ぶ適応材料システム:21世紀におけるスマートアーキテクチャの概念
13:30~14:30 下村 政嗣 (公立千歳科学技術大学 応用化学生物学科 教授)
バイオミメティクス:アントロポセン(人新世)における持続可能なサバイバルパラ
ダイム
14:30~15:30 酒井 敏 (京都大学 人間・環境学研究科 教授)
三次元だけでなく二次元:フラクタルの必要性
15:50~16:20
杉本 マキ (大和ハウス工業 未来共創センター 次長)
バイオミメティクスへの温故知新 ~創業者精神と現在の取り組み
16:20~17:05 飛鳥 政宏 (積水インテグレーテッドリサーチ 常務取締役)
自然から着想したアイデアで製品を革新する方法とその考え方
18:00~ 懇親会 (カフェテリア 匠 / 吹田キャンパス)
<3月11日(水)>
10:30~11:30 谷口 守 (筑波大学 システム情報系 教授)
生き物に学ぶ都市計画
11:30~12:40 Estelle CRUZ (フランス CEEBIOS プロジェクトマネージャー)
建築とバイオミメティクス: その文脈と機会(接点)
14:00~15:00 山本 昌仁 (たねやグループ CEO)
自然に学ぶ、たねやグループの取組み
15:20~16:05 蕪木 伸一 (大成建設 設計本部 専門設計部 部長)
都市生態系を考慮した都市再開発の実践
16:05~16:50 齋藤 彰 (阪大(工))
バイオミメティクスにおける「材料から建築へ」の橋渡し
閉会あいさつ
Borders and the Economy: Guidelines for assessing the economic impacts of border infrastructure, technology and procedures
Date
2020年3月19日(木)
Venue
京都大学桂キャンパス
<Cancelled> Borders and the Economy: Guidelines for assessing the economic impacts of border infrastructure, technology and procedures
重要:本国際セミナーは中止となりました。
Important: This international seminar is cancelled
Date: 15:00-17:00, March 19 (Thursday), 2020
Venue: 172 Lecture room, First floor, C-Cluster C1 Building, Katsura Campus, Kyoto University
(https://www.kyoto-u.ac.jp/en/access/katsura?set_language=en)
Presenter: Prof. Dr. William P. Anderson (Professor and Director of Cross-Border Institute (CBI), University of Windsor)
Abstract:
Why are cost and delay incurred as goods cross international borders an economic problem? The standard answer is that by increasing the effective cost of imports relative to domestic goods they have the same effect as tariffs: they reduce the economic gains that would otherwise arise from cross-border trade. While this perspective is useful, it is limited because there are differences between tariffs and the costs imported by border impedance. For example, while tariffs are generally fixed and defined on an ad valorem basis, border impedance costs may be highly variable and may not discriminate between high value and low value shipments.
Quantitative assessment of the economy-wide cost of border impedance is a challenging but necessary task. For public agencies to make good decisions about investments in border infrastructure, technology and the design of border procedures, they must have good estimates of the economic impacts from either increasing or decreasing border impedance. The border between Canada and the United States is used to illustrate some of the complications involved in making such an assessment. Two general conclusions arise. The first is that assessing the impact of border impedance is an explicitly spatial problem that must take into account the geography of transport networks, border crossings, production and consumption. The second is that uncertainty about border impedance – especially about crossing time – is a critical factor, especially where a large proportion of trade is of intermediate goods in cross-border supply chains.
Results from a spatially detailed Computable General Equilibrium (CGE) model, developed and applied by the Cross-Border Institute, illustrate current best practice in assessing the broader economic effects of a reduction in border impedance. Even such a model, however, has limitations arising from inconsistency between the actual dynamics of cross-border integration and the underlying general equilibrium theory and assumptions. New developments in Quantitative Spatial Economics (QSE) hold the promise of making estimates that are more comprehensive and better grounded in real economic processes.
Special seminar about climate change and London underground at UTokyo
Date
2020年2月13日
Venue
東京大学本郷キャンパス
Special seminar about climate change and London underground at UTokyo
We will conduct a special seminar, in which Ms. Sarah Victoria Greenham is invited to make a special talk about climate change and London underground. This event is held at Hongo Campus, the University of Tokyo from 4:00pm-5:00pm, February 13 (Thursday). We hope you will join us for the event and engage in this important conversation. The details are shown as follows. Thank you.
1) Time and day: 4:00pm-5:00pm, February 13 (Thursday), 2020
2) Place: Seminar room of International Project Lab., Third floor, Engineering Building No.11, Hongo Campus, The University of Tokyo (https://www.u-tokyo.ac.jp/content/400020145.pdf)
3) Presentation
– Title: Climate change and the extreme heat related impacts on the London Underground infrastructure
– Abstract:
Rail infrastructure is particularly vulnerable to extreme weather events, and damage to rail networks results in negative socioeconomic consequences such as reduced work productivity due to loss of access to commuting. The world’s oldest subway system, the London Underground (LU), operated by Transport for London (TfL) identified that extreme heat impacts the network now, and is likely to increase in future. However, previous studies are limited to passenger comfort on the deep tube and do not focus on infrastructure or a significant proportion of the network, which is in fact above ground. This research therefore aims to investigate whether causality can be determined between extreme heat events and infrastructure failure on the LU network, in order to understand the risks posed by future climate change and extreme heat events in the United Kingdom. Building on previous research using 2011-2016 data (accepted, awaiting publication), this research synthesises 2006-2018 data in greater depth, from UK Met Office archives, LU environmental observations and LU fault data with UKCP18 climate projections. Statistical tests identify the conditions, sites and assets on the LU most vulnerable to extreme heat and consequently likely to cause maximum disruption to customers in future. Preliminary findings identified a difference in surface level and deep tunnel environmental conditions and thus expect a difference in the characteristics of faults and delays accumulated. Increase in surface temperatures in the future as indicated by UKCP18 are expected to exacerbate these; scenario dependent. Results will provide TfL with quantitative information to support the business case for appropriately designed and placed climate change adaptation activity. This will ultimately help keep London moving, while simultaneously protecting a vital cultural asset to the United Kingdom.
4) Short bio of presenter
Ms Sarah Victoria Greenham is a second-year PhD student at the University of Birmingham, Department of Civil Engineering. Her PhD study is supervised by Dr Andrew Quinn & Dr Emma Ferranti at the University of Birmingham. She holds an MSc in Climate Change and Sustainability from Brunel University London, and a BSc(Hons) in Urban Planning from University College London (UCL). Sarah has worked with industry since commencing her Master’s Thesis in 2018, primarily with Transport for London (TfL), and is currently in Japan for a 2-month research fellowship with JR RTRI’s Heat and Air flow laboratory, funded by an EU project (RISEN). Last summer, Sarah was also in Japan, awarded a research fellowship under the JSPS Summer Program. She spent 2 months on a research and cultural exchange for international PhD students at The University of Tokyo’s International Project Laboratory. She and her supervisors also participate in knowledge exchange sessions between UK-based infrastructure operators (e.g. Highways England, Network Rail, Thames Water), with the aim of sharing climate change adaptation developments and best practices.
5) Charge: free
6) Language: English only
7) Participation: Please contact Ms Tomoko Samukawa (samukawa@ip.civil.t.u-tokyo.ac.jp) for joining this seminar, but you can join the seminar even without pre-registration.
CSIS Seminar "Emerging Mobility Systems: Theory and Data"
Date
24th Jan, 2020
2020年1月24日
Venue
FUJI SOFT AKIBA PLAZA 7F EX room
富士ソフト秋葉プラザ 7F EXルーム
CSIS Seminar "Emerging Mobility Systems: Theory and Data"
DATE&TIME: 24th Jan 2020 13:30 – 17:30
PLACE: FUJI SOFT AKIBA PLAZA 7F EX room (富士ソフト秋葉プラザ 7F EXルーム)
https://www.fsi.co.jp/akibapla
ABSTRACT: Emerging mobility systems, such as connected and automated vehicles and mobility-as-a-service, are changing our mobility. In this seminar, we discuss theories and data infrastructure that support these systems, in order to show visions on future mobility systems with various modes and various scales. The topics are mathematical theories on ride-sourcing and ride-sharing services, data mining and urban computing, and transport hub service design.
PROGRAM
13:30 – 13:50 Opening
Dr. Takahiko KUSAKABE
Assistant Professor, Center for Spatial Information Science, The
University of Tokyo, Japan
13:50 – 14:40 Supply Management of On-Demand Ride-Hailing Services
Invited Speaker: Mr. Zhengtian XU
Ph.D. Candidate, Department of Civil and Environmental Engineering,
University of Michigan, USA
14:40 – 15:30 Mechanism Design of Transportation Services for the
Automated Vehicle-era
Invited Speaker: Dr. Yusuke HARA
Postdoctoral Associate, Singapore-MIT Alliance for Research and
Technology (SMART), Singapore
Coffee Break
15:45 – 16:25 Urban human mobility analysis based on public
transportation smart card data
Dr. Takashi Nicholas MAEDA
Postdoctoral Researcher, The Center for Advanced Intelligence Project,
RIKEN, Japan
16:25 – 17:05 Joint optimization of SAV operation and infrastructure design
Dr. Toru SEO
Assistant Professor, Department of Civil and Environmental
Engineering, The University of Tokyo, Japan
17:05 – 17:45 A Deep Reinforcement Learning-Based Intelligent
Intervention Planning Framework for Real-Time Proactive Road Safety
Management
Dr. Ananya ROY
Project Researcher, Center for Spatial Information Science, The
University of Tokyo, Japan
17:45 – 17:50 Closing Remarks
第61回土木計画学研究発表会・春大会(自由投稿型)
Date
2020年6月13日(土)・14日(日)
Venue
オンライン開催試行 大阪大学吹田キャンパス
第61回土木計画学研究発表会・春大会(自由投稿型)
第 61 回土木計画学研究発表会・春大会(自由投稿型)のオンライン開催にむけて
2020/6/4 土木計画学研究委員会・大会運営小委員会 寺部慎太郎
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため,第61回土木計画学研究発表会(自由投稿型・春大会)の参加者が集まって行う発表会は中止しますが,研究発展のため,オンライン開催を試行します.
ここで,試行としたのは,準備期間に余裕がなく,オンライン開催に参加できない論文発表者,司会者・コメンテーターが多数いるため,またオンラインでの発表や議論がうまくできない可能性があるためです.ただし,研究発表したい人,議論に参加したい人,研究を聞きたい人には,ぜひ参加していただきたいです.なお,聴講希望者は,参加登録が必要です.以下(http://www.jsce.or.jp/event/active/information.asp)からお願い致します.Web版のプログラム及び発表原稿のURLを事前にメールにてお送りするとともに,講演集(CD-ROM)を郵送します.
- オンライン開催の情報ページ(http://committees.jsce.or.jp/ip/node/9)
1.研究発表会に係る基本事項
- 土木計画学研究・講演集(CD-ROM)を発刊し,発表講演集に掲載・公開された論文については,本研究発表会での講演発表が成立したものとして扱います.
- 発表会に論文投稿した方の「土木学会論文集D3(土木計画学),76-5」への投稿は可能です.
- オンラインの口頭発表は義務ではありません.
- 発表申込料の払い戻しはしません.
- 口頭発表の時間帯(6/13土曜日13:25-18:15,6/14日曜日9:00-18:15)に,ウェブ会議サービス「Zoom」の会議室を8つ開設し,プログラム通りに進行します.
- 論文投稿された方(ポスター発表も含みます),聴講参加登録された方には, Zoom会議室にアクセスできる,ミーティングIDとパスワードを事前に知らせます.
- 論文発表者,司会者・コメンテーターは,参加するセッションの開始時刻までにZoom会議室にアクセスし,オンラインで論文発表をして下さい.
- 論文発表者が現れない場合,その時間は何も行わず,発表順番は変更したり詰めたりしないで下さい.
- 司会者・コメンテーターが現れない場合,その場の参加者や発表者が協力して司会をして下さい.
- ポスターセッションは開催しません.また,優秀ポスター表彰も実施しません.
- ランチョンミーティング(第2日:6月14日(日)昼休み(12:20-13:20))は開催します.
資料:委員会報告・藤原委員長退任のご挨拶
2.口頭発表をする論文発表者皆様へ
- オンラインの口頭発表は義務ではありません.発表したい方が参加して下さい.
- 自分が発表する日時,セッション会場,発表番号を,プログラムで確認して下さい.
- 発表当日までに,パワーポイントプレゼンテーションを準備し,Zoom会議室での発表練習をして下さい.開催数日前に,接続確認ができるようなZoom会議室を案内します.
- 発表当日は,発表するセッションの開始時刻までにZoom会議室にアクセスし,オンラインで論文発表をして下さい.
- 自分のPCの画面共有を行いながら,自分で操作して発表して下さい.
- Zoom会議室の使い方や注意事項は後日案内します.
- オンライン開催の情報ページ(http://committees.jsce.or.jp/ip/node/9)
3.司会者・コメンテーター皆様へ
- オンラインの参加は義務ではありません.無理のない範囲で参加して下さい.
- 参加される場合は,例年通り,参加登録をお願いします.
- http://www.jsce.or.jp/event/active/information.aspからお願い致します.Web版のプログラム及び発表原稿のURLを事前にメールにてお送りするとともに,講演集(CD-ROM)を郵送します.
- 自分が担当する日時,セッション会場を,プログラムで確認して下さい.
- 担当セッションの開始時刻までにZoom会議室にアクセスし,司会をして下さい.
- コメントなどを画面表示する場合には,自分のPCの画面共有をして下さい.
- Zoom会議室の使い方や注意事項は後日案内します.
- オンライン開催の情報ページ(http://committees.jsce.or.jp/ip/node/9)
4.論文共著者皆様へ
- 論文発表者でない場合,聴講参加登録をして下さい.Zoom会議室にアクセスできる,ミーティングIDとパスワードを事前に知らせます.
- http://www.jsce.or.jp/event/active/information.aspからお願い致します.Web版のプログラム及び発表原稿のURLを事前にメールにてお送りするとともに,講演集(CD-ROM)を郵送します.
- 口頭発表者の発表を補助して下さい.
- セッションに司会者・コメンテーターが現れない場合,その場の参加者と協力して司会をして下さい.
5.聴講参加登録者皆様へ
- Zoom会議室にアクセスできる,ミーティングIDとパスワードを事前に知らせます.
- 口頭発表の時間帯に,自由にZoom会議室に出入りして,研究発表を聞いて下さい.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
第 61 回土木計画学研究発表会の中止のお知らせ
新型コロナウイルス感染症の拡大による政府の緊急事態宣言が6月時点でどのように推移するのか見通せないことから、6/13より大阪大学で開催予定でした第61回土木計画学研究発表会の開催を中止させていただくこととなりました。
皆様方には、大変、ご迷惑をおかけいたします。また、開催校である大阪大学の関係者の皆様には開催に向けて既に多大なご苦労をおかけいたしておりましたが、よろしくご了承ください。
なお、土木計画学研究・講演集(CD-ROM)は発刊されます。論文投稿いただいた方には後日送付いたします。
発表講演集に掲載・公開された論文については、本研究発表会での講演発表が成立したものとして扱います。発表申込料の払い戻しは致しません。
従って、発表会は中止になりましたが、発表会に論文投稿されていた方の「土木学会論文集D3(土木計画学),Vol.76-5」への投稿は可能です。
参加者が集まって行う発表会は中止といたしますが、研究発表したい人、発表を聴きたい人のために、別途、zoom会議室を開設し、オンライン開催を試行します。
詳細は、後日、改めてお知らせいたします。
引き続きよろしくお願いいたします。
2020.05.13
土木学会土木計画学研究委員会委員長
藤原章正
▼ 第61回土木計画学研究発表会 会告(以下の通り)
発表プログラム
発表セッション時間割
講演用論文
発表会の当日に十分な時間で充実した議論を行い、更なる研究の発展や学術論文等への取りまとめに繋げることが本発表会の特色です。このため、「具体的に議論したい点(研究の新規性や枠組み、データ、モデルや結論の妥当性、今後の発展性や疑問点など)」を明記して申込みしていただきます。話題性、速報性のある論文や、調査・計画、技術検討等の事例報告も歓迎します。提出された講演用論文は、原則として無審査で掲載されますが、会場の制約等によってお断りすることもあります。
発表希望分野については、通常の発表希望分野Ⅲと並行して、発表希望分野Ⅰ(特別論文セッション)及び発表希望分野Ⅱ(手法等分野横断的区分)での発表希望もお願いしています。こちらへの応募もよろしくお願いします。
また、ポスターセッション、および「優秀ポスター賞」の表彰を今年度も実施いたします。受賞対象は、投稿時点における学生です。博士後期課程の学生を含ますが、博士後期課程の学生については発表時点においても学生である方に限ります。
口頭発表とポスターでの発表のどちらを希望するかを選んで申込んでいただきます(口頭発表およびポスターでの発表のいずれも、2021年に発刊予定の「土木学会論文集D3(土木計画学),Vol.76-5」への投稿対象となります)。
※2021年に発刊予定の「土木学会論文集D3(土木計画学),Vol.76-5」への投稿には、
①第61回の土木計画学研究・講演集に掲載され、文量が2ページ以上の論文である
②研究発表会において、著者により当該論文の発表が行われている(発表が行われていない、または著者以外によって発表された論文は投稿不可)
ことが必要となりますので、あらかじめご了承ください。
なお、Vol.76-5への投稿期限は2020年6月の予定となります。
※2019年度より土木計画学研究発表会春大会と秋大会の実施内容の一部が入れ替わるのに伴い、土木学会論文集D3の投稿・発刊時期、対象となる発表論文等に大幅な変更がございました。
詳しくは、土木学会論文集D3・特集号(土木計画学研究・論文集)投稿の手引きにてご確認ください。
講演の申込み
(1) 申込みの手続きおよび注意点
2020年2月1日(土)~3月8日(日)17時までの期間内に、
土木計画学研究発表会(春大会)講演申込みページ申込画面より、講演申込と講演原稿の投稿を同時に行ってください。原稿のファイル形式はPDF形式のみ受付けます。 原稿は「講演原稿執筆要領」に従ってご執筆ください。締切日当日までは、投稿した原稿の確認、差し替えが可能ですが、締切日以降は、原稿の差し替えは受け付けられません。十分、ご注意ください。投稿時に、必ず申込内容が正しいか、PDFを取り違えての投稿がないか、申込内容とPDFのタイトル等の差異がないかなどをご確認ください。申込み期間の締切り間際に投稿が集中しますと、予期せぬ事態によりサーバーがダウンし受付ができなくなる恐れがあります。締切り間際の投稿は極力避けていただくようお願いいたします。
なお、講演原稿執筆要領に準じていないもの、および期限後に投稿されたものは受理できません。必ず所定の原稿を期間内にWEB上にて投稿してください。
間違えたファイルを提出した場合や申込内容とPDFの内容が違う場合であっても、そのまま掲載されますので、ご注意ください。
(2) 発表希望分野
(i) 発表希望分野Ⅰ(特別論文セッション)
充実した議論を実現するための、「特別論文セッション」を実施いたします。特別論文セッションでは、論文内容を踏まえたコメントに基づいた議論を行います。ただし、投稿論文数(最大で30編程度)、論文内容により、発表希望分野IIIでの発表となる場合もあります。
・1件当たりの持ち時間は、発表25分、コメンテーターによるコメント10分、討議10分の計45分とします。
・特別論文セッションでの発表を希望される方は、8ページ以上の論文を投稿することが必要です。
・発表者は投稿時にコメンテーター希望者を伝えることができます。
(ii) 発表希望分野II(手法等分野横断的区分)
従来の研究対象ごとの発表区分に加えて、研究で用いられている方法論に注目した分野横断的区分でのセッションを実施します。分野横断的区分セッションで発表を希望される場合には、今回は以下の5つから選択いただけます。さらに、そのセッションの司会兼コメンテーターでご希望の先生がいればご記入いただけます。これらの情報を参考に、専門性の高い先生への司会依頼を行うなどの検討を行う予定です。ただし、適切なセッションを組めない場合には、上記の発表希望分野Ⅰの従来型のセッションでの発表になります。
・新分析手法(まだ適用事例の少ない統計的手法(例.機械学習的分析手法)や記述的研究(例.物語研究)などの有効性等を議論したい研究)
・理論モデリング(実現象の理論的なモデリング、情報科学やゲーム理論などを駆使した手法について議論したい研究)
・統計分析解釈(一般的な統計分析の考察が重要な位置を占めており、その内容や妥当性について重点的に議論したい研究)
・海外事例(海外の事例的研究として集中的に議論したい研究)
・その他、重点的に議論したい分野横断的内容があればそのキーワードを直接書いていただくことも可能
(iii) 発表希望分野III(研究対象区分)
申し込みに際して、発表希望分野を下記の5つの発表分野から希望順に2つ選んでください。また、キーワードにつきましては、同キーワード欄の中から最大4つ選んでください。なお、適当なキーワードが見つからない場合は、投稿者の判断によるキーワードを1つだけ加えてください。
発表希望分野
| 発表希望分野 | キーワード |
| A 計画論・計画情報 | 計画基礎論、計画手法論、システム分析、調査論、公共事業評価法、財源・制度論、プロジェクト構想、施工計画・管理、維持管理計画、意識調査分析、計画情報、情報処理、市民参加、GIS、リモートセンシング、測量、環境計画、防災計画、河川・水資源計画、ライフライン計画・設計、地球環境問題 |
| B 地域・都市・景観 | 国土計画、地域計画、都市計画、地区計画、住宅立地、産業立地、人口分布、地価分析、土地利用、市街地整備、再開発、景観、公園・緑地、観光・余暇、空間設計、イメージ分析、土木史 |
| C 交通現象分析 | 発生交通、目的地選択、交通手段選択、経路選択、出発時刻選択、活動分析、時間利用、交通行動調査、交通意識分析、交通行動分析、自動車保有・利用、駐車需要、交通ネットワーク分析、土地利用・交通・環境統合モデル、観光・余暇行動 |
| D 交通基盤計画 | 総合交通計画、地区交通計画、公共交通計画、歩行者・自転車交通計画、道路計画、鉄道計画、空港・港湾計画、ターミナル計画、駐車場計画、物流計画 |
| E 交通運用管理 | 交通流、交通容量、サービス水準、交通制御、交通管理、交通安全、交通情報、交通環境、公共交通運用、交通弱者対策、水上交通、空港管理、交通量計測、TDM、ITS、モビリティマネジメント(MM) |
(3) 発表形式
口頭発表とポスターでの発表のどちらを希望するかを選んでいただきます。なお、会場の都合でご希望に添えない場合もありますので予めご了承下さい。
(4) 投稿料
講演1本につき投稿料(参加費含む)として一般12,000円、学生9,000円を請求いたします。2本以上投稿する方については、2本目以降の投稿料は一般・学生ともに6,000円を請求いたします。振込手数料は各自でご負担願います。
講演原稿執筆要領
講演原稿の書式・形式は、土木学会論文集のものに準じています。下記の作成例やサンプルファイルをご利用ください。講演原稿では、英文アブストラクトの記入は任意です。その他書式・形式についての詳細は土木学会論文集の原稿作成の手引き等をご参照ください。なお、「土木学会論文集D3(土木計画学), Vol.75-6」への投稿の際には英文アブストラクトは必要です。
サンプルファイル 和文(Word2000)/English(Word2000)
原稿作成例 和文(PDF)/English(PDF)
お問合せ先
土木計画学研究委員会大会運営小委員会(春大会担当:橋本,氏原,小澤)
E-mail:keikaku61@jsce.or.jp
特別研究会 Special Research Seminar
Date
2020年1月17日(金)18:55~20:25
January 17, 2020 (Friday) 18:55-20:25
Venue
明治大学駿河台キャンパス アカデミーコモン9階 309E教室
Meiji University, Academy Common Bldg., 9th Floor, Room 309E
特別研究会 Special Research Seminarトランジション・マネジメントとその実践 Transition Management and its Practice
講演者 (Presenter):ダーク・ローバック教授,エラスムス大学/オランダトランジション研究所 (Prof. Derk Loorbach, Erasmus University/Dutch Research Institute for Transition (DRIFT))
日時 (Date/Time):2020年1月17日(金)18:55~20:25 (January 17, 2020 (Friday) 18:55-20:25)
場所 (Venue):明治大学駿河台キャンパス アカデミーコモン9階 309E教室 (Meiji University, Academy Common Bldg., 9th Floor, Room 309E)
概要 (Abstract):
地球温暖化による気候変動が、これからの世界、特に将来世代に深刻な影響をもたらすことが危惧されています。その影響を人類が乗り越えていくためには、目前の課題を解決するだけでなく、社会経済システムの抜本的なトランジション(移行・転換・変革)が必要です。今回は、持続可能な社会に向けたトランジションの研究と実践で第一人者のダーク・ローバック教授をオランダからお迎えし、その概念、方法論、そして実践についてお話を伺います。
Impacts of climate change following the unstoppable global warming will surely affect our future generations around the world. In order to minimize the impact, quick-fix solutions are insufficient. Systemic transition to sustainable socioeconomic systems are needed. We will invite Professor Derk Loorbach, who is a pioneer in the research and practice of accelerating transitions.
その他 (Notes):
- 講義は英語で行われます。日英逐次通訳あり。
- Lecture will be delivered in English. Transition between English/Japanese will be provided.
- 主催:明治大学専門職大学院ガバナンス研究科 松浦研究室(※科研費助成研究「我が国の自転車通行システムの整序化へのコンセンサス形成戦略研究課題」の一環で行います)
- Organized by Prof. Masa Matsuura (Meiji University, Graduate School of Governance Studies)
- 参加費無料、研究者や学生のみなさんの積極的な参加をお待ちしています。参加希望者は次のURL (https://matsuura-lab.org/derk2020)からご登録願います。
- No fee. Looking forward to the active participation of researchers and students. If you want to join the seminar, please register using the form available at: https://matsuura-lab.org/derk2020
#7 ワンデイセミナー100回記念シンポジウム「土木計画学とは何か?~そのアイデンティティと今後の発展を考える~」
Date
2020年4月1日
Venue
土木学会 2階 講堂
※ネット同時配信あり
ワンデイセミナー100回記念シンポジウム「土木計画学とは何か?~そのアイデンティティと今後の発展を考える~」
土木計画学研究委員会が取り組んできた学問を「土木計画学」と呼称するとした場合、その「土木計画学」の展開・発展を100回のワンデイセミナーを中心に振り返り、それを通して、「土木計画学」とは一体何なのか、すなわち、「土木計画学」と呼ばれるものの輪郭、あるいは「土木計画学」のアイデンティティを探る。これを通して、本研究委員会メンバー各位が従事する「土木計画学研究」が一体何であるのかについての自認・自覚を改めて鮮明化・明確化し、それを通して本委員会活動の活性化、「土木計画学」の学問的発展を企図する。その上で、広く世間一般に自らを名乗り、アイデンティティの伝達を企図する際に、いかなる「フレーム」(枠組み)が効果的であるのかを考え、これを通して本委員会活動のさらなる発展を企図する。
動画
当日の様子はこちらからご覧いただけます →YouTube
プログラム(資料1:式次第)
1.基調報告:「土木計画学」の内実と拡がりを振り返る
本シンポジウムの趣旨(50周年シンポジウムを踏まえて)資料2
ワンデイセミナーの振り返り 資料3-1:要点 資料3-2:リスト 資料3-3:メモ
「土木計画学の成立と背景」「初期シンポジウム」等の紹介 資料4
2.講演:「土木計画学」創立時の議論を振り返る
高橋裕先生インタビュー(動画・資料5:文字起し)
天野光三先生インタビュー(動画・資料6:文字起し)
3.討議「土木計画学のフレーミングを考える」
藤原委員長( 資料8)、藤井幹事長(資料7)、小池幹事(資料10)、佐々木前幹事長(資料9)
日程
2020年4月1日(水)15時~18時 ※当初より3時間早まりました
会場
土木学会 2階 講堂 および ネット配信 ※コロナ対策で変更になりました
参加申込
たくさんのご参加、ご視聴ありがとうございました。
CPD
本シンポジウムは「土木学会継続教育(CPD)プログラム」として認定されています(3.0単位)。
なお、ネット参加の場合にも、視聴途中に複数回表示されるPWを入力することで、CPDの受講証明を発行することができます。
※新型コロナ対策
本シンポジウムの開催事務局であります土木計画学研究委員会の幹事会執行部では、折りからの新型コロナウイルス対策の関係で、本シンポジウムの開催について検討を重ねました。政府からはイベントについては19日公表の専門家会議の声明を参照いただきたいという指針が提示されており、そしてその専門家会議では、社会経済活動への影響にも配慮しつつ、自粛の可能性も含めて感染リスクを最小化する努力をしてもらいたいという声明になっています。
今、こうした政府声明、および、専門家会議の見解を「実質的な自粛要請」と捉え、全国のイベント・会合開催において、万一の事を考えて自粛するというケースが散見される状況にございます。しかし専門家会議の見解は、それぞれの学校行事やイベントの必要性と、感染拡大のリスクとを比較衡量し、十分に「感染リスクによる公益縮小期待値」が「行事・イベント開催による公益拡大期待値」を下回る程に最小化できるなら、自粛することなく開催することを要請するものとなっていると解釈できます。したがって、あらゆるイベントを一律に自粛する姿勢はむしろ、政府声明・専門家会議の見解から乖離しており、そうした一律的自粛が全国で累積すれば公益が大きく毀損することとなるというのが、専門家会議と政府の見解であると解釈できます。
ついては、「公益の増進」を目指す事を旨とする土木計画学研究の委員会幹事会執行部では、本研究委員会の存在意義を念頭に置きつつ、そうした専門家会議・政府要請の趣旨を踏まえ、本シンポジウムを開催することの社会的意義・必要性と感染拡大リスクの双方を見据えた上で審議いたしました結果、土木学会が提供する「ネット配信機能」も併用しつつ、感染リスクを最小化する対策を十分に行うことで開催することが、より望ましい帰結をもたらし得るものと判断いたしました。
そもそも今回のシンポジウムは、土木計画学の意義を、その設立時の議論を踏まえた上で改めて見直し、それを構成員間で共有することで、我々土木計画学の研究発展と、研究者の公益貢献性をさらに拡大させることを目指すものであり、適切な格好で本シンポジウムで開催できれば、十分な公益性の確保が期待されます。一方で、シンポジウム開催にあたっては、専門家会議が要請する「密閉」「密集」「近距離での会話」という3条件の「重なり」を回避する感染症対策(徹底的な換気、参加者を限定させることで密集状況を回避し、会話時の距離確保)を徹底することで、万一のリスクをその開催意義よりも十分に小さい水準に最小化できることが期待できます。
ついては、開催にあたり、「ライブ動画配信」も同時に行うこととし、ご参加申し込みいただいた皆様方に、「ネット参加」「会場参加」の二つの選択肢を提示しつつ、下記のような格好で本イベントの開催意義向上と共に、感染リスクの最小化にご協力いただく格好で開催する運びとなりました。
1)当日は、ライブ動画配信を行います。それに伴い、当初から会場を変更し、当該施設がある土木学会講堂にて、開催いたします。
2.)土木学会講堂の会場の都合で、誠に恐縮ですが開催時刻を午後3時~午後6時に変更いたします(午後6時開始の予定であったところ、3時間時間を早めました)。
3)「密集」するリスクを極力最小化するため、ご参加者各位に「ネット参加」か「会場参加」かのいずれかを選択いただきます。なお、ネット参加の皆様におかれましても、1)事前の講演資料の配付、2)当日、ならびに、事前資料をご覧頂いた上での事前での質問等のメール受付、等を実施します。
4)なお、感染リスクの最小化を記するため、(重症化リスクの高い)「60歳以上の参加者、基礎疾患をお持ちの方、妊婦」の皆様方ならびに「こうした方々と同居等をされている方々」には、ネット参加をお願いしています。同じく、ご所属の組織の組織的な方針にて、イベント参加や遠方への出張の自粛が要請されている方々もまた、ネット参加をお願いしています。その他、シンポジウム参加、および、その前後の移動機会などでの感染リスクを勘案し、参加とりやめを希望する方にはネット参加をお願いしています。
5)なお、会場の都合で、「密集」を回避するという趣旨で、会場参加者の上限を60名としています。ついては、会場参加希望者が60名に達した段階で、それ以降の参加希望者はネット参加をお願いしています。
6)当日のシンポジウムの様子は、アーカイブ化し、事後にもご覧いただけるようにしたいと存じます。
7)会場では、専門家会議が要請する「密閉」「密集」「近距離での会話・発声」の「三つの重なり」を回避すると同時に、接触感染リスクを最小化するため、以下のような配慮をいたします(注)。
・窓を開けることで換気を徹底いたします(ついては、参加者は必要に応じてコート等を着用ください)。
・入り口にて、入室前後にアルコール消毒液での手洗いをお願いします。
・参加者の座席の間隔を可能な限り空けさせていただきます。
・可能な限りマスクの着用をお願いします。また、発言時は、マスク、あるいは、ハンカチ等で口を覆いください。
・飛沫感染のリスクを回避するため、講演者と座席の間に一定の距離を確保いたします。
(注:専門家会議は、この三つの条件の一つだけでも整理しなければ、それだけで感染リスクが大幅に低減することが示唆されています。そして、ここに記載の取り組みを全て行えば、三つの重なりだけでなく、三条件の全ての成立を回避できる可能性が高まり、仮に潜在的に感染する方がおられたとしても、その感染リスクを極めて0に近い水準に低減することが可能となると期待されます)
8)また、開催日までの間に、政府、あるいは、開催地であります東京都からイベント自粛についての新たな方針等が示された場合、それを踏まえて上記の開催方針を見直すケースもありますこと、ご了承願えると幸いです。
以上
#206 Special seminar about urban planning in Vietnam at UTokyo
Date
2019年12月3日
Venue
Seminar room of International Project Lab., Third floor, Engineering Building No.11, Hongo Campus, The University of Tokyo
Special seminar about urban planning in Vietnam at UTokyo
We will conduct a special seminar, in which Dr. Kien TO is invited to make a special lecture about urban planning in Vietnam. This event is held at Hongo Campus, the University of Tokyo from 5:30pm-7:00pm, December 3 (Tuesday). We hope you will join us for the event and engage in this important conversation. The details are shown as follows. Thank you.
1) Time and day: 5:30pm-7:00pm, December 3 (Tuesday), 2019
2) Place: Seminar room of International Project Lab., Third floor, Engineering Building No.11, Hongo Campus, The University of Tokyo (https://www.u-tokyo.ac.jp/content/400020145.pdf)
3) Presetnation
– Title: Urban Planning in Vietnam Then and Now
– Abstract:
As Southeast Asia’s fastest developing country and one of the world’s fastest emerging economies, urbanization in Vietnam has been progressing very rapidly, especially in the two largest cities, Hanoi and Ho Chi Minh City. This talk provides an overview asa well as insights into urban planning in Vietnam across different historical eras, taking Hanoi – the cradle of Vietnam’s urban development – as the main case. The 100-year-old capital city is also the oldest one in Southeast Asia with many different historical layers reflecting changing eras. The first part of the talk reviews the past “millennium” urban development from the feudal era through the French colony th the socialist central planning system until Doi Moi (economic reform in 1986). The second part focuses on the contemporary urban development in post-Doi Moi era under the so-called “Market-oriented socialist” System. In this period, urban planning and development are controlled by government central planning, yet strongly driven by capitalist forces, with emerging trends, challenges and prospects as reflected in Hanoi asa well as Ho Chi Minh City. Fiercer economic competition, environmental and climate change threats, depleted resources and accumulated problems of three fast-growth decades have compelled the metropolises to innovate, take a more participatory approach, and find new development strategies, catalysts and momentum to sustain their development towards smarter and sustainable growth in the future.
4) Short bio of presenter
Dr. Kien TO is Senior Urban Planner and Project Manager affiliated with Tokyo-based Eight-Japan Engineering Consultants Inc. Besides practicing, he is an independent researcher and educator in Architecture, Urban Design and Planning with a 20-year academic track record and a strong focus on Asia. Educated in Japan, Germany, and Vietnam, Dr. Kien has worked in Japan, Singapore and Vietnam. He has researched and published on various sustainability, urban liveability, hyper-urbanization and historical conservation, and gives lectures and talks internationally. He gains empirical knowledge through extensive field-based research and projects in collaboration with local communities and authorities across Asia. In Singapore, he co-founded Opportunity Lab and Social Urban Research Group based at Singapore University of Technology and Design. He also initiated and co-chaired SUTD Go-Green Committee, and participated in a number of environmental as well as social activities in Singapore. He also served as a Resource Person at the Singapore Institute of Architects Sustainability Committee. Although active abroad, Dr. Kien always keeps a close connection with his home country Vietnam and is an active member of Vietnam Urban Planning and Development Association. He is involved in various professional and academic activities in Vietnam and writes a number of articles published in Vietnamese prominent urbanism and architecture journals as well as popular newspapers.
5) Charge: free
6) Language: English only
7) Participation: Please contact Ms. Tomoko Samukawa (samukawa@ip.civil.t.u-tokyo.ac.jp) for joining this seminar, but you can join the seminar even without pre-registration.
#205 物流分野におけるAIS等の船舶動静データの活用に関する国際セミナー
Date
2019年12月18日
Venue
東京大学 工学部3号館 423,424講義室
物流分野におけるAIS等の船舶動静データの活用に関する国際セミナー
従来,AIS(自動船舶識別装置)は船舶同士の衝突回避や不審船の探知に用いられていましたが,近年,海上物流の推計や海運経済の分析等への活用についても国内外で検討が進められています.この国際セミナーでは,AIS等の船舶動静データを海上物流の推計や海運経済の分析に活用している海外の研究者を招聘し,国海の研究者・実務者も交えた講演やパネルディスカッションを通じて,今後の物流・海運・造船分野におけるAIS等の海上物流ビッグデータの活用について考えてみたいと思います.ご関心をお持ちの多数の方々のご参加をお待ちしております.
― 記 ―
開催日時:2019年 12月18日 (水) 13:30-17:40
場所:東京大学 工学部3号館 423,424講義室(東京大学本郷キャンパス内)
参加費:無料,要事前登録
使用言語:英語
主催:日本船舶海洋工学会 S-18ストラテジー研究委員会 (AIS等の船舶動静ビッグデータの物流・海運・造船分野における活用に関する検討委員会),日本海運経済学会
共催:東京大学,広島大学
プログラム:
13:30-13:40 開会の挨拶(東京大学 青山和浩教授)
第一部 <講演> (司会:広島大学 和田祐次郎特任講師)
13:40-14:20 Still looking for the holy grail: The ups and downs of AIS-based research (Prof. Roar Adland, NHH Norwegian School of Economics)
14:20-15:00 Improving Bulk Ship Positioning Strategy with Individual Ship Movement Data (Assist. Prof. Yang Dong, The Hong Kong Polytechnic University)
15:00-15:25 Port-based estimation of global shipping pattern of dry bulk and tanker cargo by AIS and vessel movement database and its application (柴崎隆一准教授,東京大学)
15:25-15:50 Regional Disintegration in South Asia: Evidence from the end of the British Empire on Maritime Networks (坪田建明研究員,アジア経済研究所)
15:50-16:10 休憩
16:10-17:30
第二部 <パネルディスカッション> (モデレーター:柴崎隆一准教授)
パネリスト: Prof. Roar Adland, Assist. Prof. Yang Dong, Assist. Prof. Bai Xiwen (Tsinghua University), 和田祐次郎特任講師,岩佐竜至様(商船三井),前田佳彦様(MTI)
・各企業・大学の取り組み事例の紹介(発表10分)
・海外ゲストからのコメント
・フロアからの質疑
17:30-17:40 閉会の挨拶 (福知山公立大学 篠原正人教授)
18:00-20:00 懇親会 (ルヴェソンヴェール本郷) 懇親会費:5,000円/人
場所: 〒113-0033 東京都文京区本郷6-16-4 フォーレスト本郷内 レストラン
ご参加のお申し込みは,12月9日(月)までに下記連絡先までお願い致します.セミナー終了後,懇親会も予定しています.こちらにもぜひご参加ください.お手数ですが,懇親会への参加希望についても併せてご連絡をお願い致します.
問い合わせ・申込先: 和田 祐次郎 (広島大学 大学院工学研究科)
TEL:082-424-7779 FAX:082-422-7194
E-mail: waday@hiroshima-u.ac.jp
会場までのアクセス: https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/about/campus-guide/map01_02html
https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/about/campus-guide/map01_01.html
懇親会会場(ルヴェソンヴェール本郷)までのアクセス(スタッフがご案内いたします):
#204 Open seminar for LUTI modeling in the assessment of SDGs and QoL
Date
2019年10月10日
Venue
Institute of Industrial Science, University of Tokyo
Open seminar for LUTI modeling in the assessment of SDGs and QoL
以下の要領で、ミュンヘン工科大学からRolf Moeckel博士、Kasetsert大学からVarameth Viciensan博士をお招きし、土地利用交通マイクロシミュレーションモデルに関するセミナーを開催します。
Date: 14:00-17:00, October 10th, 2019
Venue: Block As, As311-312 Conference Room, Institute of Industrial Science, University of Tokyo, Komaba Campus (4-6-1 Komaba, Meguro, Tokyo 153-8505, Japan)
Access: https://www.iis.u-tokyo.ac.jp/en/access/
Google Maps: https://goo.gl/maps/uN255EUs1QFD59KCA
Co-host: DAAD-JSPS JRP (“Are sustainable development goals within reach? Development of a microsimulation urban model to test policies for a sustainable future”), SATREPS (“Smart Transport Strategy for Thailand 4.0”).
Objective: Provide findings from the research projects in DAAD-JSPS JRP and SATREPS, discuss the LUTI modeling method, procedure, implementation, application and implication to the practice.
Schedule:
14:00-14:15 Opening remark (Masanobu Kii)
14:15-15:00 Application of Microsimulation modeling (Rolf Moeckel)
15:00-15:45 LUTI model in Bangkok metropolitan area (Varameth Viciensan)
15:45-16:00 Coffee break
16:00-16:45 Earth observation and spatial analysis for urban modeling (Hiroyuki Miyazaki)
16:45-17:00 Closing remark (Masanobu Kii)
ご参加を希望される方は、9月27日金曜日までに、紀伊(kii@eng.kagawa-u.ac.jp)までご連絡いただければ幸いです。
#203 Real-time control for transit systems with transfers
Date
2019年10月8日
Venue
京都大学桂キャンパス Cクラスター C1-312(C1棟会議室3)
Real-time control for transit systems with transfers
日時:10月8日(火)16:00~17:30
場所:京都大学桂キャンパスCクラスター C1-312(C1棟会議室3)
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/access/campus/map6r_k.htm
講師: Prof. Tomer Toledo, Israel Institute of Technology (Technion), Israel
題目: Real -time control for transit systems with transfers
詳細は,下記をご覧ください.
参加を希望される方は,シュマッカー(schmoecker@trans.kuciv.kyoto-u.ac.jp)までご連絡いただければ大変ありがたく存じます.どうぞよろしくお願いいたします.
Abstract: We report on research to develop a real-time simulation-based control framework that attempts to coordinate the eperations of multiple transit lines simultaneously to allow smoother transfers and to maintain service regularity. The control actions, which include holding and change speed, are set as the solution of an optimization problem with the objective to minimize total passengers’ time in the system within a prediction horizon. The prediction horizon is defined by a number of downstream stops and subsequent buses. The predictions made include the arrival and departure times of vehicles at downstream stops and the passenger demands they are expected to serve. The model is demonstrated with a simulation-based case study of three lines of the BRT system in Haifa, Israel. The results show the system’s potential to reduce the total passengers’ time.
Bio: Dr. Tomer Toledo is an Associate Professor in the Faculty of civil and Environmental Engineering and the Head of the Transportation Research Institute at the Technion-Israel Institute of Technology. His research interests are in the areas of driver behavior, traffic modeling and simulation, intelligent transportation system and transportation network analysis. He is an Research Part C and Transportation Research Record.
#202 Seminar on short-term prediction for the next generation transport management
Date
2019年9月20日
Venue
Meeting Room 3, Suekawa Memorial Hall, Ritsumeikan University, Kyoto
Seminar on short-term prediction for the next generation transport management
The CASE (Connected, Automonous, Shared, and Electric) mobility will greatly change transport servises. One illustrative example is self-driving vehicles with multiple functions such as ride-sharing, e-coomerce, and logistics, which would enrich our daily lives. Various personalized services would be offered based on the enormous data from vehicles mobile phones, etc. At the same time, such big and real-time data would also change transport management systems drastically together with the rapid development of relevant methodologies.
One of the key common ingredients for a better mobility service and its management systems is the short-term prediction of transport conditions: an accurate short-term prediction of OD demand and travel time would be needed for a better ride-sharing service, while a better short-term prediction of traffic states using real-timedata would significantly improve dynamic traffic control and management systems. One of the emerging and promising approaches for a better short-term prediction is a machine learning approach. Appliactions of machine learning techniaues in the field of transportation have been increasing rapidly in the last couple of years. These studies have empirically shown higher prediction accuracy compared to traditional methods, opening up further possibiilties of providing new transport services as well as data-driven traffic control and management.
This seminar aims to identify unique challenges in the application of machine learning techniques to the short-term prediction, explore further possibilities ot applying deep learning techniques to transport issues, and identify potential bottlenecks in utilizing them in practice. Following a special lecture of the use of tree search and deep neural networks by Dr. Yoshizoe, two keynote lectures will be delivered by Dr. Chris van Hinsbergen and Dr. Adam Pel on the state of the art for short-term traffic prediction in Netherlands. We will then have presentation from researchers and practitioners on their ongoing works and discuss the possible future research directions and practical applications.
Date and time: 10:00-17:30 on September 20, 2019
Venue: Meeting Room 3, Suekawa Memorial Hall, Ritsumeikan University, Kyoto
9 Kinugasa Himurocho, Kita-ku, Kyoto, 603-8484
(Map: https://goo.gl/maps/N2GrysfoJnb9YHaX9)
Capacity: 40 persons
Registration: Please send your name and affiliation to Makoto Chikaraishi
(chikaraishim@hiroshima-u.ac.jp)
Note: The application will be closed as soon as the number of applicants reaches the capacity.
Program
Project Introduction and Special Lecture
Organizer: Yasuhiro Shiomi (Ritsumeikan Unievrsity)
10:00-10:15: Introduction of research project
“Short-term travel demand prediction and comprehensive transport demand management”
by Makoto Chikaraishi (Hiroshima University)
10:15-10:30: A brief overview of the application of machine learning models in the field of transportation
by Varun Varghese (Hiroshima University)
10:30-11:30: Special Lecture: Solving Problems Using Tree Search and Deep Neural Networks
by Kazuki Yoshizoe (Leader of Search and Parallel Computing Unit, RIKEN Center for Advanced Intelligence Project)
11:30-13:00: Lunch break
Keynote Lectures
Organizer: Makoto Chiakaraishi (Hiroshima University)
13:00-14:00: Keynote lecture 1: Traffic Theory & Decision Forests for prediction of local traffic patterns
by Adam Pel (Associate professor, Delft University of Technology)
14:00-15:00: Keynote lecture 2: The Neural Cell Transmission Model
by Chiris van Hinsbergen (Co-Founder & Developer, Fileradar)
15:00-15:20: Coffee break
State-of-the-Art Research and Practice
Organizer: Varun Varghese (Hiroshima University)
15:20-15:50: Traffic Congestion Control by Vehicle Trajectory Estimation
by Masaaki Ishihara (Hanshin Expressway Company Limited)
15:50-16:20: Short-Term Traffic State Prediction Using the LSTM Framework: A Case Study in Kamakura City
by Daisuke Fukuda (Tokyo Institute of Technology)
16:20-16:50: Toyota’s activities in MaaS
by Takahiro Shiga (Toyota Motor corporation)
16:50-17:20: Driver’s Behavior in Ride-hailing Service
by Junji Urata (The University of Tokyo)
17:20-17:30: Closing
#201 Special seminar about high-speed rail project in India at UTokyo
Date
2019年9月17日
Venue
Seminar room of International Project Lab., The University of Tokyo
Special seminar about high-speed rail project in India at UTokyo
1) Time and day: 5:30pm-7:00pm, September 17 (Tuesday), 2019
2) Place: Seminar room of International Project Lab., Third floor, Engineering Buidling No.11, Hongo Campus, The University of Tokyo
(https://www.u-tokyo.ac.jp/content/400020145.pdf)
3) Presentation
-Title: Inside of the Mumbai-Ahmedabad High Speed Rail Project, India’s first High-Speed Rail with Japan’s Shinkansen System
-Abstract:
India’s first high speed rail line is planned under the Mumbai-Ahmedabad High Speed Rail (MAHSR) Project. The ipmlementation of the project with use of Japanese high speed rail technologies (i.e. the SHINKANSEN system) and experiences, was cofirmed at the Japan-India Summit Meeting (December 2015). Japan International Cooperation Agency (JICA) has been providing and facilitating various types of support such as those for the detailed design of the project, dispatch of experts, conducting training in Japan, and providing ODA loans for the construction of training facilities and the MAHSR line itself. Tenders have started for both the construction of the training facilities and the main line, and intensive discussion are being held every day amongst the experts of India and Japan. Ms. Momoko Furuhashi was dispatched to the India Office of JICA from 2016 to 2019, where she first looked after road and water sector of India, and afterwards becoming officer in charge for the High Speed Rail. In the seminar she will introduce how JICA is supporting the implementation of the MAHSR, and will share her personal experience of working on the mega project.
4) Short bio of presenter
Ms. Momoko Furuhashi has just completed her tenure as a representative in the India Office of the Japan International Cooperation Agency (JICA) in mid-September 2019. She has mainly been in charge of implementation management and formulation of grant aid and Official Development Assistance (ODA) projects for transport infrastructure, namely roads, bridges and airports in the JICA HQs. The projects were located in various countries such as the Socialist Republic of Vietnam Democratic Republic of the Congo, Islamic Republic of Afghanistan, and the Republic of Mozambique.
5) Charge: free
6) Language: English only
7) Participation: Please cotact Ms. Tomoko Samukawa (samukawa@ip.civil.t.u-tokyo.ac.jp) for joining this seminar, but you can join the seminar even without pre-registration.
#200 東京大学・同済大学国際共同セミナー
Date
2019年8月5日
Venue
東京大学本郷キャンパス
Special Joint Seminar of UTokyo and Tongji University
1) Time and day: 10:00am-12:00am, August 5 (Monday), 2019
2) Place: Lecture room No.13, Department of Civil Engineering, Ground floor, Engineering Building No.1, Hongo Campus, The University of Tokyo (https://www.u-tokyo.ac.jp/content/400020145.pdf)
3) Schedule
– Opening remarks: TBD (The University of Tokyo)
– Presentation 1: Quality of life assessment of Shanghai and Guangzhou based on multi-source data source (Dr. Xiao LUO, Associate Professor, Tongji University)
-Presentation 2: The information system of multimodal transportation in Shanghai (Dr. Lijuan SHI, Lecturer, Tongji University)
– Presentation 3: Transportation investment and its impacts on regional economics: Evidences from Japan (Prof. Hironori KATO, The University of Tokyo)
4) Short bios of invited presenters
– Luo Xiao, Ph.D. is Associate Professor of Tongji University, Master Tutor, Secretary-General of Tongji-WCTRS World Transport Research Center. Mainly engaged in low-carbon transportation, built environment assessment, data mining and big data application in urban planning and transport policy. He graduate from Nagoya University in Japan in 2013 under the supervision of Prof. Yoshitsugu HAYASHI, who is ex-President of the World Transport Congress and full member of Rome Club. As the moderator/main participant, he have completed some projects on the application of low-carbon transportation and big data technology in urban and transportation research. He have good experience in international cooperation and landing of domestic projects in big-data low-carbon cities and smart transportation. He published more than 20 academic papers, including more than 10 SCI/SSCI papers, served as the editorial board of SSCI magazine Technological Forecasting and Social Change on the theme of “Smart City and Quality of Life”.
– Dr. Shi Lijuan serves as a lecturer in the department of comprehensive transportation information engineering and control in the school of traffic and transportation engineering at Tongji University. She had been a visiting scholar at the university of Wisconsin-Madison of civil engineering from 2009.8 to 2010.8. Her research area is integrated traffic and transportation informatization, automatic train control system, safety and reliability theory and technology. She has been engaged in the planning, designing and developing standards of intelligent transportation system of Shanghai, such as Shanghai traffic and transportation comprehensive information platform, Pudong new area traffic management information system, Shanghai expressway network toll collection and monitoring system, and Yangtze river delta comprehensive transportation information sharing and collaborative platform. She as a major participant in now conducting a research on a program of Comprehensive Support Technology for Railway Network Operation, which is funded by Ministry of Science and Technology of China. She is on the committee of Shanghai highway association. She has published almost 20 technical papers in journal and proceedings.
5) Charge: free
6) Language: English
7) Participation: Please contact Ms. Tomoko Samukawa (samukawa@ip.civil.t.u-tokyo.ac.jp) for joining this seminar.
#199 応用一般均衡分析と交通分析の統合に関する研究小委員会 国際セミナー
Date
2019年7月16日
Venue
神戸大学六甲第一キャンパス 経済経営研究所新館 2階会議室
応用一般均衡分析と交通分析の統合に関する研究小委員会 国際セミナー
日時:7/16(火)13:20-14:50
場所:神戸大学六甲第一キャンパス 経済経営研究所 2階会議室
アクセスマップ:http://www.kobe-u.ac.jp/guid/access/rokko/rokkodai-dai1.html
報告1: Jos van OMMEREN (アムステルダム自由大学)
The Congestion Relief Benefit of Public Transit: Evidence from Rome
備考: 神戸大学経済経営研究所交通政策研究部会及び経済経営研究所RIEBセミナー共催,JSPS外国人研究者招聘事業
準備のため,下記に参加登録をお願いいたします。
#198 Special seminar about bike planning in Maryland, USA at UTokyo
Date
2019年7月9日
Venue
Seminar room of International Project Lab., Third floor, Engineering Building No.11, Hongo Campus The University of Tokyo
Special seminar about bike planning in Maryland, USA at UTokyo
1) Time and day: 5:00pm-6:00pm, July 9 (Tuesday), 2019
2) Place: Seminar room of International Project Lab., Third floor, Engineering Building No.11, Hongo Campus, The University of Tokyo (https://www.u-tokyo.ac.jp/content/400020145.pdf)
3) Presentation
– Title: GIS Analysis for Bike Planning with Consideration for Level of Streets and Energy Consumption: A Case from Montgomery Country, Maryland, USA
– Abstract: Bike planning has become an important part of local transportation planning in urbanized areas in the US. Within it, Geographic Information Systems (GIS) are used in a variety of tasks, ranging from simple mapping to advanced analysis. In this talk, I will discuss the application of GIS analysis that incorporates two important factors that cyclists experience on roads: (a) stress to travel through street built environment and (b) changes in burden in biking due to topography. While the level of stress (LOS) is used to select street segments that are appropriate for different levels of cyclists, biking energy consumption, in addition to distance, is used as travel impedance to take into account the effects of slopes and street intersections. The integration of these two factors in conventional allows planners to enhance the capability in spatial analysis. The integrated GIS analysis methods are used to select for bike infrastructure improvements in coming years in Montgomery County, Maryland in the USA.
4) Short bio of presenter
Dr Hiroyuki (Hiro) Iseki is Associate Professor of Urban Studies and Planning at University of Maryland, College Park. He also has an appointment at the National Center for Smart Growth Research & Education (NCSG). His research focuses on balancing efficiency, effectiveness, and equity in the provision of mobility and accessibility with special attentions to transportation, land use, and the diversity of needs among different socioeconomic groups. Iseki’s pas projects include the development of direct transit demand models using origin-destination trip data, the analysis of variances in perceptions of transit service quality by user’s demographic characteristics and trip characteristics, public private partnerships in transportation financing and transit service, and equity in transit finance. Iseki has published his work in a range of transportation and planning journals, including Transportation Research Part A: Policy and Practice, Transport Reviews, Research in Transportation Economics, Transport Policy, Journal of the Transportation Research Board, Journal of Public Transportation, Computers, Environment and Urban Systems, and Journal of Planning Education and Research.
5) Charge: free
6) Language: English + Japanese
7) Participation: Please contact Ms Tomoko Samukawa (samukawa@ip.civil.t.u-tokyo.ac.jp) for joining this seminar, but you can join the seminar even without pre-registration.
#197 アジア交通学会 国際セミナー
Date
2019年7月10日
Venue
東京海洋大学 品川キャンパス 白鷹館1階
The Future of Transportation in Eastern Asia at the era of MaaS and Big Data
「MaaS・ビッグデータ時代のアジアの交通を考える」
The emergence of diverse services, such as MaaS, Bigdata, Sharing mobility, AI, and Auto-Drive, with new technologies indicates a major turning point in the transportation field.
There is great interest in the development of new technologies in Asia in the future.
EASTS invites young transportation researchers and tries to discuss the future of transportation in Asia.
Date: 10th, July, 2019
Venue: Hakuyo Hall, Shinagawa Campus, Tokyo University of Marine Science and Technology (東京海洋大学・品川キャンパス 白鷹館)
Program
13:00-13:10 Opening remarks by Tetsuro Hyodo, Treasurer of EASTS
13:10-14:00 Keynote Speech “Big data for Transportation Survey and Planning” by Jaehak Oh, Chair of EASTS ISC, President of Korean Institute of Transport
14:00-14:25 “Current issue and future challenge of shared mobility in Australia” by Meng Li (Australia)
14:25-14:50 “User Perception on Autonomous Vehicle (AV) Based Mobility-on-Demand (MOD) Services in Singapore” by Ghim Ping Ong (Singapore)
15:05-15:30 “Road Traffic Safety Challenges and Opportunities in Taiwan” by Kun-Feng Wu (Taiwan)
15:30-15:55 “MaaS: a path for creating MaaS in Bangkok” by Sorawit Narupiti (Thailand)
16:00-17:30 Panel Discussion “Future of Transportation in Eastern Asia”
Coordinator: Shinya Hanaoka, Deputy Secretary General of EASTS
Panelist: Yulong Pei (China)
Tri Tjahjono (Indonesia)
Sungwon Lee (Korea)
Nguyen Hoang Tung (Vietnam)
Karl B. N. Vergel (Philippines)
17:30-17:45 Closing remarks by Tetsuo Yai, President of EASTS
As for the detailed program, please access the following URL
プログラムについては下記URLをご参照ください.
http://easts.info/news_file/EASTS_JICA_2019July10.pdf
Please apply for participation at the URL below.
参加申し込みは以下のURLからお願いいたします.
http://easts.info/application/seminar2019/
是非、お近くの留学生にもお声がけ頂ければ幸いです.
#196 土木計画学研究委員会・EASTS-Japan共催国際セミナー International Seminar
Date
2019年7月8日
Venue
Seminar room 4, Tokyo University of Science, Dept. of Civil Engineering (Noda campus, Building No.5, 1st floor)
土木計画学研究委員会・EASTS-Japan共催国際セミナー International Seminar
All students and researchers interested in these studies are welcome to join this seminar. You don’t need to e-mail me before coming.
事前連絡は不要ですので直接会場にお越しください.
1) Main topic
“A new approach for bikeshed analysis with consideration of topography, street connectivity, and energy consumption” (地形,街路の接続性,燃料消費を考慮した,新しい自転車需要圏の分析)
2) Sub topic
“The determinants of travel demand between rail stations: A direct transit demand model using multilevel analysis for the Washington D. C. Metrorail system” (鉄道需要の決定要因:ワシントンDC地下鉄におけるマルチレベル分析を用いた重要モデル)
Date: July 8 (Monday), 2019, 5:00-6:00 pm
Place: Seminar room 4, Tokyo University of Science, Dept. of Civil Engineering (Noda campus, Building No.5, 1st floor) 東京理科大学理工学部土木工学科ゼミ室(4) (野田キャンパス5号館1F)
http://www.tus.ac.jp/info/campus/noda.html
Speaker: Dr. Hiroyuki (Hiro) Iseki, Associate Professor of Urban Studies and Planning at University of Maryland, College Park
Source 1)
A new approach for bileshed analysis with consideration of topography, street connectivity, and energy consumption
Computers Environment and Urban System 48: 166-177, November 2014
In recent years, bike planning has gained the attention of planners and the public as a sustainable and active mode of transportation that can reduce traffic congestion, vehicle emissions, and health risks. Following the success of public bikesharing program in cities in France and Canada, multiple US cities have initiated similar programs. With this background, spatial analysis has been applied to produce heat maps of bike-travel demand, and identify suitable areas for bikeshare infrastructure. Existing research considers a variety of factors, such as resident demographics, land use, street types, and availability of bike facilities and transit services. However, few studies fully account for topography and street connectivity. The study proposes a method to combine topography and presence of intersections with estimates of energy used to bike, and incorporate the resulting travel-impedance factor, as well as street connectivity, into a spatial analysis. Using the case in Montgomery Couty, Maryland, USA, where elevation and street connectivity differ substantially among neighborhoods, this study shows how the size and shape of bikesheds (or bike demand catchment area) originating from the proposed light rail stations vary in the analysis with or without taking into account these critical factors. The analysis results have significant implications for various bike planning efforts using spatial analysis.
Source 2)
The determinants of travel demand between rail stations: A direct transit demand model using multilevel analysis for the Washington D. C. Metrorail system
Transportation Research Part A: Policy and Practice Volume 116, October 2018, Pages 635-649
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0965856416306966
In this study, we developed a time-of-day Origin-Destination Direct Transit Demand Model (OD-DTDM) that uses fare-card data from the Washington DC Metrorail system, applying a multilevel (or hierarchical) model to address the statistical problem due to the presence of groups or cluster of observations. We examine the research questions: (1) what are the determinants of transit demand between the origin and destination stations in the DC Metrorail system by time of day? and (2) what are the magnitudes of impacts that land use factors, as well as factors of fares and travel time of other modes, have on transit demand vary by time of day? To address statistical complexities intorduced by the fact that each station represents both an origin and a destination, we applied multilevel (or hierarchical) modeling techniques. Using these techniques, we found that the number of households and the number of jobs within a walkshed serve as trip generating and attracting factors, respectively, in the AM peak period, but with higher positive coefficients for jobs; these two factors reverse their roles in the PM peak period. Other variables with substantial effects on ridership include transit fares per mile, travel time between OD-stations by car and by bus, parking capacity, the level of feeder bus service, and train service levels. While these findings are not surprising, the time-of-day OD-DTDM provides more detailed information regarding the determinants of transit demand with temporal variation, and enables transit planners and managers to adopt policies and plans, such as transit oriented development, fare structure, and service levels, more fine-tuned for each origin and destination pair and by time of day.
#195 The effects of the 2013 floods on German road freight traffic
Date
2019年6月27日
Venue
Seminar room S-519D Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University
The effects of the 2013 floods on German road freight traffic
Date: June 27 (Thursday) 15:00-17:00
Place: Seminar room S-519D Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University
Title: The effects of the 2013 floods on Germany’s road freight tra
Speaker: Julio Fournier, Doctoral Student, German Institute for Economic Research (DIW Berlin)
Abstract: This article quantifies the consequence of the 2013 floods on heavy vehicle’s traffic in Germany by using automatic traffic counter (ATC) data to locate affected roads and measure the stringency of the damage. The research design treats each counter as an independent time series and endogenously identifies shocks to determine the effects and dates on which the flood affected each counter. Results show a cumulative negative effect on average weekly freight traffic volumes. Although the largest number of shocks happened along the highway (Bundesstraßen) network with an overall positive effect, motorways (Autobahns) experienced larger shocks with an overall negative effect. The most affected regions were the states of Bavaria and Saxony-Anhalt, with Rosenheim (Bavaria) being the district with the largest traffic losses and Rottal-Inn (Bavaria) the one with the largest gains. Understanding the effect of repetitive meteorological events on the road network is relevant for the formulation of policies aiming to improve resilience and recovery.
#194 The 10th International Seminar on Urban Transport, Tourism and Travel Behavior Analysis
Date
2019年8月22日
Venue
Hokkaigakuen Institute for Northeast Asia Studies (HINAS), Sapporo, Japan
The 10th International Seminar on Urban Transport, Tourism and Travel Behavior Analysis
We are very delightful to make the third announcement of the 10th International Seminar on Urban Transport, Tourism and Travel Behavior Analysis 2019. The one-day seminar will be held, Friday, August 23, from 8:30 AM to 6:10 PM at the HINAS (Hokkaigakuen Institute for Northeast Asia Studies) in Sapporo. In this seminar we commemorate the 10th anniversary of our seminar and really expect to have stimulating exchange with participants as we could exprience at the previous seminars.
Let us hereby introduce the outline of the 10th International Seminar. Prof. T. Tamura, Hokkai School of Commerce (HSC) is a host professor of our tenth seminar and we will surely provide a fulfilling one-day seminar with enjoyable semianr dinner on Friday and an impressive tour to Otaru on Saturday.
Coming Sapporo seminar is scheduled to consist of 4 keynotes, 16 research reports and an inclusive discussion. See the attached program and you can find that all of participants from China, around 20 professors have already been resistered and assigned to the timetable with presenting their titiles.
On the other hand, in case of participants from Japan, presenters have been completely registered but general participants have already got their registrations.
Meanwhile, we sincerely hope that our seminar will have a great opportunity to deepen mutural understanding and exchange between China and Japan. We are looking forward to get together at the 10th anniversary seminar in Sapporo this August.
INFORMATION
Key dates:
– Sending Registraton form (for general participants) Deadline: July 22
– Sending Presentation Material (for presenters) Due: July 22
– Sending Seminar Program (Final version) Until: August 1
– Seminar Srarts At: 8:30 am August 23
REGISTRATION & SEMINAR TOUR CHARGES
For domestic participants:
Regular Registration (with lunch and seminar dinner): 12,000 Yen
Regular Registration + Seminar Tour (with lunch): 15,000 Yen
For domestic participants (only (graduate) students):
Regular Registration (with lunch and seminar dinner): 6,000 Yen
Regular Registration + Seminar Tour (with lunch): 8,000 Yen
CONTACT US
For further information of the seminar, please contact:
Secretariat of The 10th International Seminar in Sapporo 2019
KAZUO NISHII, Professor of UMDS
3-1, Gakuen-Nishi-Machi, Nishi-ku, Kobe, 651-2188, JAPAN
E-mail address: Kazuo_Nishii@red.umds.ac.jp
Phone: +81-(0)78-796-4852
第102回土木計画学ワンデイセミナー「健康まちづくりの実践的展開」
第102回土木計画学ワンデイセミナー「健康まちづくりの実践的展開」
健康まちづくり研究小委員会では、生涯を通して健康を実感できるまちづくりを具体的な研究フィールドにおいて進め、まちづくりと健康の関係に関わる実データ収集、そのデータの集計・分析・提示・目標設定による人々の行動への影響、まちづくり手法としてのエリアマネジメントのあり方などを盛り込んだ総合的な研究を進めてきた。
特に、健康まちづくり計画の側面について、①健康を増進・維持するための人々の「行動のあり方」、②それを支える環境としての「都市のあり方」、③両者を効果的につなげる「社会システムデザイン」に分類した。第1回のワンデイセミナーでは、それぞれの視点から健康まちづくりの方向性を検討した。個々の視点についての代表的な研究成果について報告した。また、国土交通省、厚生労働省、地方自治体を招いて健康まちづくりに関する議論を行った。
第2回のワンデイセミナーでは、これらの成果を踏まえて、健康まちづくりの「実践に向けての課題」を議論する。
開催日:2019年10月30日(水)12:50~17:30
会 場:関西大学 千里山キャンパス 尚文館 マルチメディアAV大教室
■プログラム(司会:秋山委員長)
・12:50~13:10 開会挨拶・第1回報告(秋山委員長)
・13:10~13:40 報告①:尾崎平氏(関西大学)
「スマートヘルシ倶楽部の取り組みについて」
・13:40~14:10 報告②:藤生慎氏(金沢大学)
「国民健康保険データベースを用いた健康まちづくり」
・14:10~14:40 報告③:柳原崇男氏(近畿大学)
「高齢者の健康維持における外出と交通の役割」
<休憩>
・15:00~15:30 講演①:吹田市 健康医療審議監 舟津謙一氏
「北大阪健康医療都市(健都)のまちづくりについて」
・15:30~16:00 講演②:高石市 保健福祉部 スマートウェルネス推進班 班長 舩冨学氏
「スマートウェルネスシティの推進について」
<休憩>
・16:20~17:25 ワークショップ・ディスカッション(森栗茂一氏)
報告者・講演者(一般参加者の質疑応答に基づくディスカッション)
・17:25~17:30 閉会挨拶(北詰幹事長)
■参加費 無料
■参加申し込み
下記のページより申し込みをお願いします。
https://forms.gle/zRVFsySrVW9cw83f7
申込をされた方は下記ページより「実践的な健康まちづくりに関してセミナーで議論して欲しい課題」を記載して下さい。
https://forms.gle/dzeoEcBv8MAifhVW6
■会場案内
関西大学 千里山キャンパス
〒564-8680 大阪府吹田市山手町3-3-35
阪急電鉄 千里線 関大前駅下車 徒歩10分
詳細は以下のWebをご参照ください。
http://www.kansai-u.ac.jp/global/guide/access.html
■問い合わせ先
関西大学 環境都市工学部 井ノ口 弘昭
E-mail: hiroaki@inokuchi.jp
Tel./FAX 06-6368-0964
#102 健康まちづくりの実践的展開
Date
2019年10月30日
Venue
関西大学 千里山キャンパス 尚文館 マルチメディアAV大教室(大阪府吹田市山手町3-3-35)
土木計画学ワンデイセミナー NO.102 健康まちづくりの実践的展開
土木計画学ワンデイセミナー「健康まちづくりの実践的展開」
■主催:
土木学会土木計画学研究委員会「健康まちづくり研究小委員会」
■共催:
関西大学先端科学技術推進機構「健康まちづくりオープンイノベーションにおける合意形成と意思決定研究グループ」
■趣旨:
健康まちづくり研究小委員会では、生涯を通して健康を実感できるまちづくりを具体的な研究フィールドにおいて進め、まちづくりと健康の関係に関わる実データ収集、そのデータの集計・分析・提示・目標設定による人々の行動への影響、まちづくり手法としてのエリアマネジメントのあり方などを盛り込んだ総合的な研究を進めてきた。
特に、健康まちづくり計画の側面について、①健康を増進・維持するための人々の「行動のあり方」、②それを支える環境としての「都市のあり方」、③両者を効果的につなげる「社会システムデザイン」に分類した。第1回のワンデイセミナーでは、それぞれの視点から健康まちづくりの方向性を検討した。個々の視点についての代表的な研究成果について報告した。また、国土交通省、厚生労働省、地方自治体を招いて健康まちづくりに関する議論を行った。
第2回のワンデイセミナーでは、これらの成果を踏まえて、健康まちづくりの「実践に向けての課題」を議論する。
■開催日:
2019年10月30日(水)12:50~17:30
■会場:
関西大学 千里山キャンパス 尚文館 マルチメディアAV大教室
〒564-8680 大阪府吹田市山手町3-3-35
阪急電鉄 千里線 関大前駅下車 徒歩10分
詳細は以下のWebをご参照ください。
http://www.kansai-u.ac.jp/global/guide/access.html
■プログラム(司会:秋山委員長):
12:50~13:10 開会挨拶・第1回報告(秋山委員長)
13:10~13:40 報告①:関西大学 尾崎平氏
「スマートヘルシ倶楽部の取り組みについて」
13:40~14:10 報告②:金沢大学 藤生慎氏
「国民健康保険データベースを用いた健康まちづくり」
14:10~14:40 報告③:近畿大学 柳原崇男氏
「高齢者の健康維持における外出と交通の役割」
15:00~15:30 講演①:吹田市 健康医療審議監 舟津謙一氏
「北大阪健康医療都市(健都)のまちづくりについて」
15:30~16:00 講演②:高石市 保健福祉部 健幸づくり課 スマートウェルネス推進班 班長 舩冨学氏
「スマートウェルネスシティの推進について」
16:20~17:25 ワークショップ・ディスカッション(森栗茂一氏)
報告者・講演者・一般参加者の質疑応答に基づくディスカッション
17:25~17:30 閉会挨拶(北詰幹事長)
■参加費:
無料
■参加申し込み
下記のページより申し込みをお願いします。
https://forms.gle/zRVFsySrVW9cw83f7
また、申込をされた方は、下記ページより「実践的な健康まちづくりに関してセミナーで議論して欲しい課題」を記載して下さい。
https://forms.gle/dzeoEcBv8MAifhVW6
#8 土木計画学とダイバーシティ(2019年・年次学術講演会)
Date
2019年9月14日
Venue
香川大学幸町キャンパス 幸町北4号館 432講義室
土木計画学とダイバーシティ
土木計画学とダイバーシティ
2019年9月4日(水) 08:40 〜 10:10 IV-2 (幸町北4号館 432講義室)
座長:佐々木 葉(早稲田大学)
[IV-60] 計画の仕事におけるダイバーシティとは —ニューヨークの状況をもとに考えるー
*佐々木 葉1 (1. 早稲田大学)
キーワード:ダイバーシティ、都市地域計画、働き方、キャリアデザイン、ニューヨーク
都市・地域計画分野の仕事におけるダイバーシティについて、その意義と概念の整理を、ニューヨークにおけるヒアリング調査をもとに行った。ヒアリングはPratt Institute の教授からアメリカにおけるプランニングの専門性の特徴、就職状況などについて、またNY市に勤務しており、American Plannning Associationにおけるダイバーシティ委員会の活動を行っている若手にその活動と自身のキャリアデザインについて行った。これらを元に、計画というそもそも多様で複雑な社会を相手にした思考と実践には,単に属性のダイバーシティのみでなく,多義的なそれが重要という結論を得た
[IV-61] 旅行時間価値とダイバーシティ
*藤原 章正1 (1. 広島大学大学院国際協力研究科)
キーワード:ダイバーシティ、自己−他者−公共世界、多次元的計画
中山間地域に運行する貨客混載サービスの旅行時間価値を事例として取り上げ,「自己−他者−公共世界」観にもとづいて、土木計画におけるダイバーシティの意味の再考察を試みる。
[IV-62] 新たな時代に対応した土木計画学の役割 -多様化する社会ニーズに対応したダイバーシティ・マネジメント-
*毛利 雄一1 (1. 一般財団法人計量計画研究所)
キーワード:土木計画学、ダイバーシティ、Society5.0
高齢者問題,地域格差問題,エネルギー・環境問題等々の様々な国土,地域,都市の社会課題も顕在化され,一人一人の嗜好と行動の結果である個人の幸福と社会全体の福利との調和的な関係が維持される政策展開や制度設計が必要とされる.土木計画学は,この個人と社会の調和を図り,より善い社会へ導くための学問としての役割は大きい.本論文では,これらの状況を踏まえ,今後の新たな時代に対応した土木計画学の役割について,多様化する社会ニーズに対応したダイバーシティ・マネジメントという視点から論じることとする.
[IV-63] ダイバーシティの反面教師
*谷口 綾子1 (1. 国立大学法人 筑波大学)
キーワード:ダイバーシティ
本稿の目的は,土木計画学研究に携わる方々に「ダイバーシティとは何か」という答えのない問の解をご検討いただくにあたり,陥ってはいけない反面教師となり得る事例を二つ,何が正解かわからない事例を一つ紹介し,そうならないための打開策を検討することである.具体的には,筆者が体験した三つのエピソードを紹介し,それらへの対処を検討することを通じて,土木計画学のダイバーシティを考える一助としたい.
[IV-64] 移動制約者の社会活躍を担保する道路デザインに向けた課題 ―生活道路における視覚障害者の歩行誘導の視点から―
*稲垣 具志1 (1. 日本大学)
キーワード:ダイバーシティと土木計画、視覚障害者、生活道路、歩行誘導、交通安全
都市における社会活動の多くの場面において安全で円滑な移動が保障されることは,きわめて基本的で重要な視点である.昨今議論が盛んなダイバーシティ推進に関する取り組みの中では,多方面において高齢者や障害者をはじめとした移動制約者が社会で活躍するための社会環境をつくることが求められている.本稿では,整備に関して様々な制約の強い生活道路における視覚障害者の歩行を取り上げ,交通安全施設等の路面表示のユニバーサルな活用方法について言及し,道路デザインにおけるダイバーシティの課題を考察する.
[IV-65] ESGの視点からみた建設・運輸業界におけるダイバーシティの現状と課題
*松永 千晶1 (1. 九州大学大学院)
キーワード:ダイバーシティ、土木計画、ESG、企業価値、持続可能性、サステナブル投資
我が国でも建設・運輸関連業界のみならずあらゆる業界において,ダイバーシティへの取り組みが重要視されている.ダイバーシティとは社会的背景から生じる必然ではなく,企業戦略として考えるという意識チェンジが必要とされている.一方で,企業価値を高める戦略にとって昨今注目を集めるのが,企業の持続可能性の評価指標として注目されるESGに対する取り組みや,それに基づくESG投資(責任投資,サステナブル投資とも言う)である.以上より本稿では,BloombergのESG情報開示スコアを用いて土木計画とダイバーシティの問題,特に建設・運輸関連企業における現状と課題について述べるものである.
#193 Special seminar about bus operation in Bangkok at UTokyo
Date
2019年6月3日
Venue
Hongo Campus, The University of Tokyo
Special seminar about bus operation in Bangkok at UTokyo
Time and day: 1:00pm-3:00pm, June 3 (mon), 2019
Place: Seminar room of International Project Lab., Third floor, Engineering Building No.11, Hongo Campus, The University of Tokyo
https://www.u-tokyo.ac.jp/content/400020145.pdf
Presentation
– Title: Opetational Models, Drivers’ Compensation, and Bus Service Quality in Bangkok
– Abstract:
This paper explores how operational models and compensation methods are associated with bus drivers’ incentives and consequently bus service quality and safety in Bangkok. We cross-analyze data on bus drivers’ compensation collected from a structured interview survey with data on passenger complaints and bus accidents compiled from governmental databases. We find that private joint-service operators provide their drivers with far less compensation and benefits than the state-owned operator. The private operators also tie drivers’ compensation and benefit levels to the numbers of working hours and trips, especially on routes where private operators can compete freely. These compensation methods incentivize drivers to work long hours beyond what is permitted by law, inducing fatigue and potential accidents. The key policy implication is that the bus policy aiming to improve service quality and safety should improve drivers’ compensation and working conditions.
Short bio of presenter
Saksith Chalermpong is Associate Professor in Civil Engineering at Chulalongkorn University, where he teaches transport engineering, planning, and policy. He also serves as Deputy Director of the Transportation Institute, Chulalongkorn Univeristy. His research interests include urban transport planning, public and informal transport, and equality issues in transport policy. He has published extensively in the field of transport, and has provided consulting services for several government agencies in Thailand, including Department of Land Transport, Office of Transport Planning and Policy, and Bangkok Mass Transit Authority. Dr. Chalermpong received his bachelor’s degree in civil engineering from Chlalongkorn University, his master’s degree from MIT, and his doctoral degree from UC Irvine, both in the field of transport.
Charge: free
Language: English only
Participation: Please contact Ms. Tomoko Samukawa (samukawa@ip.civil.t.u-tokyo.ac.jp) for joining this seminar, but you can join the seminar even without pre-regstration.
第60回土木計画学研究発表会・秋大会(企画提案型)
Date
11月29日(金):エクスカーション
11月30日(土)・12月1日(日)・2日(月):研究発表会
Venue
富山大学五福キャンパス及び富山県内各市町村会場
第60回土木計画学研究発表会・秋大会(企画提案型)の概要
第60回土木計画学研究発表会秋大会(企画提案型)の概要について、以下のとおりお知らせいたします。
【第60回土木計画学研究発表会・秋大会(企画提案型)の概要】
実施期日:2019年11月29日(金):エクスカーション,11月30日(土)・12月1日(日)・2日(月):研究発表会
開催場所: 富山大学五福キャンパス及び富山県内各市町村会場
実施要領 (PDFファイル)
発表プログラムを公開しました(2019年11月22日更新)
10/21 更新事項
1) ポスターセッションのコアタイムを記載しました。
2) 発表辞退による発表順の変更を修正しました。
11/8 更新事項
1) サテライトセッションの会場・セッション時間帯を追記しました。
11/22 更新事項
1)「12月 2日 時間帯 1, 8:45-10:15」のセッションについて、各セッションの1番の発表が、本来の最終発表者の下に重複して表示されている誤りを修正しました。
開催校ウェブサイトを公開しました(随時更新中)
開催校ウェブサイト
開催校ウェブサイトモバイルページ
(モバイルページはPCのブラウザーでも閲覧して頂けます)
エクスカーション・講演・懇親会・チュートリアルセッション・若手研究者の集いなどの案内・申し込み情報は、モバイルページで随時発信しています。
●企画論文部門・スペシャルセッション(SS)部門
企画論文部門は、オーガナイザーを公募し提案された企画テーマでの論文公募を行い、口頭発表またはポスター形式での発表を行うものです。SS部門は、原則として既存の研究小委員会が主催して、研究討議・意見交換を中心にセッションを構成するもので、本大会では12 セッションを限度とします。
・企画論文部門のセッション一覧はこちら
・企画論文投稿 (論文投稿 2019年10月4日(金)正午締切)【終了しました】
・SS講演原稿投稿(2019年10月4日(金)正午締切)【終了しました】
●スケジュール
○企画論文部門
企画テーマの応募 2019年6月14日(金)まで【終了しました】
発表希望者の論文題目・概要の登録 2019年6月21日(金)~2019年7月26日(金)【終了しました】
オーガナイザーによる採否決定期間 2019年8月9日(金)~2019年8月30日(金)【終了しました】
発表希望者への採否通知期間 2019年9月2日(月)~9月6日(金)【終了しました】
論文投稿 2019年10月4日(金)まで【終了しました】
○スペシャルセッション(SS) 部門
テーマの申請 2019年6月14日(金)まで【終了しました】
発表者の決定 2019年8月9日(金)まで 【終了しました】
発表の要領
口頭発表セッションでは,聴講者用にレジュメ50部をご用意の上,各セッション会場にて配布してください.
12月1日(日)に実施する各市町村会場には,レジュメ60部をご用意ください.なお,オーガナイザーから別途指示があった場合はそれに従ってください.
(1)講演時間
セッションの時間は,発表件数に応じて異なります.発表時間・発表方法・セッション運営についてはオーガナイザーの指示に従ってください.
(2)講演打ち合わせ
セッション開始10分前に各発表会場に集合し,オーガナイザーとセッションの進め方に関する打ち合わせを行って下さい.
(3)発表時の使用機器について
各発表会場には,液晶プロジェクターとディスプレイケーブルを準備します(OHP,スライドは使用できません).11月30日の富山大学会場、及び12月2日の県民会館会場では,HDMI、RGBの接続が可能です.各市町村会場の設備については,後日公開いたします. なお,ノートPCは各自で持参してください. 各発表会場に設置されている液晶プロジェクタヘの接続は,各発表者の責任にて行ってください.セッションが円滑に進行するようにご準備のご協力をお願い致します.
(4)ポスターセッション
プログラムで「ポスター」と表示されたセッションは,オーガナイザーにより,ポスター発表形式でのセッションを指定されたセッションです.セッション運営の方法については,各セッションのオーガナイザーにお問い合わせください.
ポスターのサイズは,A0(縦)を上限としてご用意ください.なお,ポスター用のパネル,貼り付け用文具につきましては開催校より提供する予定です.
参加登録
参加登録(発表者以外の方):次の土木学会行事参加申し込みホームページhttp://www.jsce.or.jp/event/active/information.aspより,ご登録ください.
聴講参加者の受付は10月7日(月)から,締切は11月14日(木),参加費は一般6,000円,学生3,000円です.
※当初締切を11月23日(土)と公開いたしましたが, 前倒しとなっております.
なお,発表者(企画部門)は自動的に登録されていますので,あらためての参加登録は不要です.オーガナイザー,スペシャルセッションの発表者の方は,参加登録が必要です.
以下の参加申込書をダウンロードし,必要事項を記入して土木学会宛にお送りいただく(FAX/郵送)ことでも,参加登録は可能です.締切および参加費はホームページからの申し込みの場合と同じです.
参加申込FAX用紙 http://www.jsce.or.jp/event/active/form.pdf
事前参加申し込みに関する注意事項
・参加申し込みの締切は11月14日(木)となっております.申し込みをされた方には,発表会前までに,「参加券」,「請求書」等をお送りする予定です.
・本行事の参加費支払いは事前入金制となっておりますので,申込みフォームの「当日払い」,「現金持参」は選択しないでください.
・締切日以降の事前受付はいたしません.締切日を過ぎてからのお申し込みは,行事当日に会場にて受付いたします.
・お申し込み後,やむを得ずキャンセルされる場合は,必ず開催日の1週間前までに土木学会研究事業課宛にご連絡ください(担当:研究事業課 小澤,k-ozawa[a]jsce.or.jp, [a]=>@,03-3355-3559).ご連絡がない場合は,参加費を徴収させて頂きますので予めご了承ください.
●土木学会論文集D3(土木計画学)特集号への投稿資格について
企画論文部門へ期限までに投稿された論文のうち、土木学会論文集D3の投稿の手引に従った形式(ただし英文要旨は任意)で執筆され、かつ2ページ以上の分量である論文については、土木計画学研究・講演集に掲載される論文として見なされ、土木学会論文集D3(土木計画学)特集号(以下、特集号と表記する)への投稿資格が得られます。論文タイトルと要旨のみで構成されており本文が記載されていないなど、定められた形式に従っていない原稿は,大会運営小委員会の判断により,土木計画学研究・概要集に掲載されません。その場合、土木学会論文集D3(土木計画学)特集号への投稿資格は与えられませんのでご注意ください。ただし、特集号への投稿資格を満たさない投稿論文であっても、企画論文部門セッションで発表することは可能です。
また、論文投稿されたにも関わらず実際には大会にて発表されていない論文、およびSS部門へ投稿された論文についても、特集号への投稿資格はありません。詳しくは、計画学ホームページをご覧下さい。
http://www.jsce.or.jp/committee/ip/monograph/file/journal-s-tebiki.pdf
●論文投稿料について
企画部門の発表会投稿料(参加費を含む)は,講演1件につき一般12,000円,学生9,000円です.SS部門は,1セッションにつき,10,000円(参加費別)です.なお,オーガナイザーによる採否決定(2019年8月9日(金))後のキャンセルは,一切認められません.発表(講演)を辞退されても,発表会投稿料として料金を請求させて頂きますので十分にご注意ください.
●チュートリアルセッションの実施について
今大会でも、土木計画学研究委員会主催の下、下記のチュートリアルセッションを開催いたします。多くの学部生・大学院生・社会人・研究者の方の参加をお待ちしております。
・日時:2019年11月29日(金)13:30~16:30
・会場:大学コンソーシアム富山 研修室1
(富山市新富町 1-2-3 CiCビル5階,富山駅徒歩3分)
http://www.consortium-toyama.jp/siseturiyou.html
・参加無料
・内容:「合意形成の心理実験:心理実験の基礎と“誰がなぜゲーム”を用いた実験体験」
13:30 – 13:45 土木計画における心理実験の活用意義 青木俊明(東北大学)
13:45 – 15:45 誰がなぜゲーム体験 野波 寛(関西学院大学)
15:45 – 16:00 休憩
16:00 – 16:30 質疑応答
・概要
本企画では、合意形成研究を行っている社会心理学者を招き、ステークホルダー間の模擬討議を通して合意形成を目指す「参加体験型ゲーム」の1つである“誰がなぜゲーム(WWG)”を実施する。参加者には、実際にWWGを体験してもらい、心理実験の手法の基礎を習得してもらうことを目的とする。
※筆記用具をご持参ください。また,当日参加も可能ですが、資料用意の関係上、事前にお申し込みをしていただければ幸いです。
・チュートリアルセッション事前申し込み先
チュートリアルセッションに参加を希望される方は、11月27日(水)正午までに、チュートリアルセッション専用申し込みフォームにて氏名、所属、連絡先をご連絡下さい。※こちらの申し込みフォームは、研究発表会の申し込みフォームではありません。
●秋大会運営に関する問合せ先
土木計画学大会運営小委員会 秋大会部会
e-mail: keikaku60@jsce.or.jp
スマート・プランニング実践セミナー(@北陸)
地⽅開催企画 第4弾「スマート・プランニング実践セミナー(@北陸)」
司会:羽藤英二氏パネラー:東京大学 浦田淳司氏富山大学 金山洋一氏國學院大学 児玉千絵氏福井市 國枝都市戦略部長 [資料2]
スマート・プランニング実践セミナー(@北陸)
地⽅開催企画 第4弾「スマート・プランニング実践セミナー(@北陸)」
#192 The Value of slow travel by Prof. Stephen Greaves
Date
2019年5月10日
Venue
Room 206, IDEC, Hiroshima University
The Value of slow travel by Prof. Stephen Greaves
Date & Time: May 10, 14:30-15:30
Place: Room 206, IDEC, Hiroshima University
Name: Stephen Greaves
Affiliation: The University of Sydney
Bio: Stephen Greaves is a Professor in Transport Management in the Institute of Transport & Logistics Studies (ITLS) at the University of Sydney. He has previously Director of the Business School Doctoral studies program (2014-2017). Stephen’s research interests are focused around the health/environmental/safety impacts of transport, new vehicle technologies including electric vehicles and autonomous vehicles, and innovative travel data collection methods using the latest technologies. He has 125 refereed publications, including 43 in international journals, and has held three major ARC grants. He also provides expert advice and media commentary on a range of transport-related issues and was co-chair of a major international coference on survey methods held in Australia in 2014.
Presentation title: The value of slow travel: Economic appraisal of cycling projects using the logsum measure of consumer surplus
Abstract: Walking and cycling have clear benefts for users, even though they may be slower than other transport modes. However, these user benefits could be undervelued using traditional economic appraisal, in which speed increases or travel time savings are highly valued. This paper explores the use of the logsum measure of consumer surplus for valuing the user benefits of new active transport infrastructure, using new separated cycleways in Sydney (Australia) as a case study. The results suggest the value of user benefits can be significant – of a similar order of magnitude to the estimated value of the public health benefits – and it becames more pronounced as cycleways are intergrated into a connected network. The method could be used to inform transportation investment policy decisions in other jurisdictions, where suitable travel survey data are available.
#191 土木計画学研究委員会・EASTS-Japan 共催国際セミナー(International Seminar)
Date
2019年4月25日
Venue
Seminar room (1), Tokyo University of Science, Dept. of Civil Engineering (Noda campus, Building No. 5, 1st floor)
土木計画学研究委員会・EASTS-Japan 共催国際セミナー(International Seminar)
Title: Enjoy Biking in Taipei: Using, Planning and Assessing (台北における自転車利用の時空間パターン,自転車道のネットワークデザイン,利用可能性評価について)
Date: April 25 (Thursday), 2019, 5:00-6:00pm
Place: Seminar room (1), Tokyo University of Ssience, Dept. of Civil Engineering (Noda campus, Building No.5, 1st floor) 東京理科大学理工学部土木工学科ゼミ室 (1) (野田キャンパス5号館1階)
Presenter: Professor Jen-Jia Lin (林楨家 教授), Department of Geography, National Taiwan University, Taiwan (国立台湾大学地理学科)
Abstract:
Biking is a green and active travel mode that consumers minimal energy, limited pollution, and accompanies physical activites. Taipei City government has deployed numerous biking-promotion schemes since 2009; however, because of very limited knowledge about biking in literature, a portion of the promotion schemes were developed in unprofessional ways and their effectiveness need further improvements. To fill the research gaps, attention toward to biking studies has been increasing in the past decade in Taiwan. I would like to briefly introduce three recent works in my lab, which are related to spatiotemporal patterns of public bike uses, bikeway network design model and area-wide bikeability assessment method. All of the works are empirically based on Taipei context, and their details can be found in the following articles.
Lin, J. J. and Liao, R. Y. (2016), Bikeway network design model for recreational bicycling in scenic areas, Networks and Spatial Economics, 16 (1): 9-31.
Lin, J. J. and Wei, Y. H. (2018), Assessing area-wide bikeability: A grey analytical network process, Transportation Research Part A: Policy and Practice, 113: 381-396.
Liu, H. C. and Lin, J. J. (2019), Associations of built environments with spatiotemporal patterns of public bicycle use, journal of Transport Geography, 74: 299-312.
Anyone who is interesting in biking research is welcome to attend the seminar and all commnets and questions will be appreciated.
Keywords: Biking, Spatiotemporal nanalysis, Network design problem, Bikeability assessment
#190 Special seminar on land use and transport in UK at UTokyo
Date
2019年4月18日
Venue
Hongo Campus, The University of Tokyo
Special seminar on land use and transport in UK at UTokyo
Time and day: 5:00pm-6:00pm, April 18 (Thursday), 2019
Place: Seminar room of International Project Lab., Third floor, Engineering Building No.11, Hongo Campus, The University of Tokyo
https://www.u-tokyo.ac.jp/content/400020145.pdf
Presentation
– Title: Findings from the UK National Travel Survey Data that are cogent to new land use and transport infrastructure developments
– Abstract:
This short talk summarises the methods and findings from our studies using the UK National Travel Survey data. The methods deployed include those of structural equation modelling and latent cluster analysis for indentification of travel behavioural patterns, and those of integrated economic, land use, built form and passenger travel modelling for predicting travel demand changes in the medium and long term. The insights from the findings have been used to support our recent predictive modelling work on balancing jobs, housing, and travel in the suburbs and exurbs of London (especially for the Cambridgeshire and Peterborough Mayoral Authority), and for the UK as a whole (at the UK2070 Commission in its inquiry into regional inequality and a long term plans for action). The Cambridge team is currently engaging with national travel survey teams in Germany and the Netherlands.
Short bio of presenter
Dr. Ying Jin is a Reader in Architecture and Urbanism at University of Cambridge Department of Architecture. He has been working on land use planning, transport modelling and urban design in the UK since 1992, and since 2013 leading the research group on cities and transport at the Martin Centre for Architectural and Urban Studies, which if a leading institution in the UK in creating and using predictive models for cities and multimodal transport systems. Ying Jin’s work has increasing incorporated the social and political dynamics in transport and urban planning. He became an inaugural Visiting Fellow at the Bennett Institute for Public Policy, Univerdsity of Cambridge in 2018.
Charge: free
Language: English only
Participation: Please contact Ms. Tomoko Samukawa (samukawa@ip.civil.t.u-tokyo.ac.jp) for joining this seminar, but you can join the seminar even without pre-regstration.
#189 Special seminar about travel-based multitasking at UTokyo
Date
2019年4月18日
Venue
Hongo Campus, The University of Tokyo
Secial seminar about travel-based multitasking at UTokyo
Time and day: 2:00pm-3:00pm, April 18 (Thur), 2019
Place: Seminar room of International Project Lab., Third floor, Engineering Building No.11, Hongo Campus, The University of Tokyo
(https://www.u-tokyo.ac.jp/content/400020145.pdf)
Presentation
– Title: Satiation in Travel-Based Multitasking: A Case Study from Mumbai, India
– Abstract:
Multitasking is an essential aspect of an individual’s overall activity participation and time allocation behavior, and travel is one of the few activities which provides the scope for natural multitasking. This study (1) analyzed the effect of parameters on multitasking choice which reflect the heterogeneity of urban settings in a developing country scenario, and (2) evaluated the existence of satiation and estimated it for different multitasking activities. A travel diary survey was conducted of 1,123 individuals residing in both formal and informal housing across the city of Mumbai, capturing information on their multitasking during travel behavior. A multiple discrete-continuous extreme value model was formulated testing the effect of parameters and estimating satiation in alternatives. Findings suggest that travel characteristics, individual and household socioeconomic characteristics, and access to information and communication technology (ICT) are important indicators affecting multitasking during travel. In addition, along with access to ICT, certain other socioeconomic characteristics such as gender, occupation type, and poor living conditions affected the participation in ICT-based multitasking activities, indicating the linkages between digital and social divide. Findings on satiation showed a glaring mismatch between participation and preference. Although the participation and time allocation in doing no activity were the highest, the levels of satiation were observed to be lower for sleeping/snoozing/resting activities and mos ICT-based multitasking alternatives. This indicated that if a suitable setting is provided, individuals prefer to participate in other activities rather than performing no activity.
Short bio of presenter
Varun Varghese is a Postdoctoral Researcher at the Infrastructure Planning and Urban Risk Management lab at Hiroshima University. He is currently working on the application of advanced machine learning techniques for transportation planning and management. He is a Civil Engineer and he finished his Ph.D. from the Centre for Urban Science and Engineering, Indian Institute of Technology Bombay, India. For his Ph.D. thesis, he worked on indentifying the interrelationships between ICT, travel behavior, and activity participation behavior in Mumbai, India.
Charge: free
Language: English only
Particiapation: Please contact Ms. Tomoko Samukawa (samukawa@ip.civil.t.u-tokyo.ac.jp) for joining this seminar, but you can join the seminar even without pre-registration.
#188 A special lecture of Applied Geographic Information Science
Date
2019年3月27日
Venue
東北大学 青葉山新キャンパス 環境科学研究科 本館 4F 講義室2
A special lecture of Applied Geographic Information Science
Date: 15:00-17:00, March 27, 2019
Venue: 東北大学 青葉山新キャンパス 環境科学研究科 本館4階講義室2
(キャンパスマップ:http://www.tohoku.ac.jp/map/ja/?f=AY_J22)
Title: Geographically Weighted Regression with flexible choices of distance metrics
Speaker: Dr. Lu Binbin, Wuhan University, China
Abstract:
Geographically Weighted Regression (GWR) has been developed as a local technique to investigation spatial nonstationarity in data relationships. GWR is calibrated with data whose influence decays with distance, distances that are commonly defined as straight line or Euclidean. However, the complexity of our real world that the scope of possible distance metrics is far larger than the trasitional Euclidean choice. In this talk, GWR with flexible choices of distance metrics will be presented, i.e. using Euclidean distance and non-Euclidean distance metrics. Furthermore, variatons in spatial relationships within a GWR model might also very in intensity with respect to location and direction. This assertion has led to extensions of GWR with parameter-specific distance metrics (PSDM GWR).
#187 Space-Time GIS for Human Dynamics Research
Date
2019年3月25日
Venue
東京大学工学部14号館8階会議室
Space-Time GIS for Human Dynamics Research
Date: 16:00-17:30, March 25, 2019
Venue: 東京大学工学部14号館8階会議室(http://www.due.t.u-tokyo.ac.jp/contact/)
Title: Space-Time GIS for Human Dynamics Research
Speaker:
Shih-Lung Shaw, Ph.D.
Alvin and Sally Beaman, Professor & Arts and Sciences Excellence Professor,
Department of Geography, University of Tennessee, Knoxville
Abstract:
Due to widespread use of location-aware technology, information and communication technology (ICT) and mobile technology, there have been many important changes to how people carry out their activities and interactions that hace important implications to future transportation systems and services. With the unprecedented data collection of a wide range of human activities and the environments, we now have opportunities to gain insights of human dynamics in a space-time context. In the meantime, we also face many challenges of using geographic information science (GIScience) to properly support human dynamics research. This presentation will share some examples of our work in developping a space-time geographic information system (GIS) for human dynamics research, followed by a critical review of the limitations of conventional GIS and a proposed new GIScience framework to support human dynamics research in a hybrid physical-virtual space that includes four different conceptualizations for space.
About the speaker:
Dr. Shih-Lung Shaw is Alvin and Sally Beaman Professor and Arts and Sciences Excellence Professor of Geography at the University of Tennessee, Knoxville. His research interests cover GIS for transporation, space-time GIS, time geography, transportaton planning and modeling, and human dynamics. His recent research has focused on space-time analytics of human dymamics in a hybrid physical-virtual world based on various types of individual tracking data. Dr. Shaw is an elected Fellow of the American Association for Advancement of Science (AAAS) and a recipient of the Edward L. Ullman Award fro Outstanding Contributions to Transportation Geography from the Association of American Geographers (AAG). He served as Interim Associate Provost for International Education and Head of the Department of Geography at the University of Tennessee. He is the current Chair of the Research Committee of the University Consortium for Geographic Information Science (UCGIS), lead editor of Spriger’s Human Dynamics in Smart Cities book series, and editorial board member of International journal of Geographical Information Science, Journal of Transport Geography, Travel Behaviour and Society, among others.
Contact:
国立環境研究所 有賀敏典
Email: ariga.toshinori@nies.go.jp
当日参加も受け付けますが、資料準備の都合上、事前にご一報いただけると助かります。皆様のご参加をお待ちしております。
#186 Using big data for modelling human decision making
Date
2019年3月20日
Venue
京都大学桂キャンパスCクラスター C1-117 (C1棟会議室1)
Using big data for modelling human decision making
日時:3月20日(水) 15:00-16:30
場所:京都大学桂キャンパスCクラスター C1-117(C棟会議室1)
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/access/campus/map6r_k.htm
講師:Prof. Stephane Hess, University of Leeds, UK
題目:Using big data for modelling human decision making
Abstract: Traditional data sources like household surveys are expensive to collect and sueveys are thus not conducted at regular enough intervals nor do they collect samples large enough to be representative or reliable for complex model estimation. On the other hand, very large streams of data are collected automatically from people every day, most notably in the form of mobile phone records and smart card data. While such data sourves have been used extensively for visualisarion or even in machine learning, their use in traditional transport modelling is still in its infancy. This presentation presents some ground-breaking work in this area, showing how smartcard, GPS and mobile phone data can be exploited for modelling a veriety of transport decisions and producing meaningful results. The presentation also looks at some of the steps required to make the data usable for analysis. The talk will provide a methodological overview meant to stimulate discussion. Part of the talk will also be a range of application studies, among others on tourism and evacuation modelling.
About the speaker: Stephane Hess is Professor of Choice Modelling in the Institute for Transport Studies and Director of the Choice Modelling Cntre at the University of Leeds. He is also Honorary Professor in Choice Modelling in the Institute for Transport and Logistices Studies at the University of Sydney, Honorary Professor of Modelling Behaviour in Africa at the University of Cape Town. His area of work is the analysis of human decision making using advanced mathematical models. He has made contoributions to the state of the art in the specification, estimation and interpretation of such models, as well as in facilitating the transition of ideas and approaches across disciplines. Together with his research team at the Choice Modelling Centre, he is setting the research agenda in applying choice modelling in new fields, including education, lifestyle choices, social (network) interactions and joint decision making. Advanced choice models require high quality data, and Hess and his team are leading the field in exploring and exploring novel data sources, with numerous applications using “big data”. Hess has published over 100 peer reviewed journal papers, and his work is highly cited, with a Scopus H-index of 28 (google scholar H-index of 45). HIs cotributions have been recognised for example by the 2017 ICMC award for the most innvative application of chice modelling, the 2014 Outstanding Young Member of the Transporation Research Board (TRB) award for exceptional achievements in transportation research, policy, or practice, the 2010 Fred Burggraf award handed out by the Transportation Research Board and the 2005 Eric Pas award for the best PhD thesis in the area of travel behaviour modelling. He is also the founding editor in chief of the Journal of Choice Modelling and the founder and steering committee chair of the International Choice Modelling Conference.
参加申し込み先: Jan-Dirk Schmöcker (PhD), Associate Professor
Department of Urban Management, Kyoto University
C1-2-436, Katsura Nishikyo-ku, Kyoto 615-8540, Japan
Tel : +81-75-383-3234, Fax: +81-75-383-3236
schmoecker@trans.kuciv.kyoto-
http://trans.kuciv.kyoto-u.ac.
#185 MEILI an open source alternative to collect travel diary with smartphone: Lessons from Stockholm and progress
Date
2019年3月18日
Venue
Seminar room, the 2nd floor of Midorigaoka Bldg. 5, O-okayama campus, Tokyo Institute of Technology
MEILI an open source alternative to collect travel diary with smartphone: Lessons from Stockholm and progress
1) Datetime: 11:00am-0:00pm, March 18 (Mon.), 2019
2) Place: Seminar room, the 2nd floor of Midorigaoka Bldg. 5, O-okayama campus, Tokyo Institute of Technology
3) Presentation
Speaker: Professor Yusak Susilo (KTH)
https://www.kth.se/profile/yusak
Outline:
The increased interest in the automation of travel diary collection, together with the ease of access to new artificial intelligence methods led scientists to explore the prerequisites to the automatic generation of travel diaries. One of the most promising methods for this automation relies on collecting GPS traces of multiple users over a period of time, followed by asking the users to annotate their collected data by specifying the base entities for a travel diary, i.e., trips and triplegs. This led scientist on one of two paths: either develop an in-house solution for data collection and annotation, which is usually an undocumented prototype implementation limited to few users, or contract an external provider for the development, which results in additional costs. This paper provides a third path: an open-source highly modular system for the collection and annotation of travel diaries of multiple users, named MEILI. The paper discusses the architecture of MEILI with an emphasis on the data model, which allows scientists to implement and evaluate their methods of choice for the detection of the following entities: trip start/end, trip destination, trip purpose, tripleg start/end, and tripleg mode. Furthermore, the open source nature of MEILI allows scientists to modify the MEILI was successfully trialed in multiple case studies in Stockholm and Gothenburg, Sweden between 2014 and 2017.
Reference: https://doi.org/10.1016/j.compenvurbsys.2018.01.011
We will conduct a special seminar, in which Prof. Yusak Susilo, a Professor in Transport Analysis and Policy at the Royal Institute of Technology (KTH) is invited to make a mini-seminar about an open-source Apps. for collecting travel behavior data named “MEILI” and its applications.
Participation: Please contact Daisuke Fukuda (fukuda@plan.cv.titech.ac.jp) for joining this seminar
#184 Special seminar about autonomous bus service at UTokyo
Date
2019年3月18日
Venue
Seminar room of International Project Lab., Third floor, Engineering Building No.11, Hongo Campus, The University of Tokyo
Special seminar about autonomous bus service at UTokyo
1) Time and day: 5:00pm-6:30pm, March 18 (Mon), 2019
2) Place: Seminar room of International Project Lab., Third floor, Engineering Building No.11, Hongo Campus, The University of Tokyo (https://www.u-tokyo.ac.jp/con
3) Presentation
– Title: Lessons from Autonomous Bus Service Deployment on a Public Road in Stockholm
– Abstract:
An EZ10 autonomous bus has been deployed in Stockholm public road from January 2018 for six months period. The service connected Kista metro station with major offices and university in Kista Science City. The focus of the deployment is the feasibility to use such service as a last mile transport option. The current service is operated between 7:00 and 18:00, with some exceptions for exceptional conditions. Until May 2018, the service has been used by 10000 passengers and logged 2000km kilometres. This project serves as the first step to understand the effects and challenges of the real AVs for shared services deployment from both technical and also to the societal, users and system perspectivest. This knowledge will important to design future deployment and pilots, to create a system that is sustainable and working from societal, environmental and economical perspective in Swedish context.
This particular presentation focuses on the users’ acceptance towards the AV service from two perspectives:
1. Acceptance and responses of the potential users and users of semi-autonomous bus service.
2. Reaction and adaptation of other road users to semi-autonomous bus running on public road.
Three-waves of panel survey among more than 500 users were deployed over the six-month period. The survey was designed to capture the longitudinal changes of attitudes, acceptance, and expectation of commuters and residents in appreciating and adopting (or use) this new public transport service. A series of psychological (attitudes, preferences and perceptions) questions, which are derived from Modified Theory of Reasoned Action, were deployed in February 2018, April 2018 and June 2018. Each survey wave includes about 30 minutes of questionnaire.
4) Short bio of presenter
Yusak O. Susilo is a Professor in Transport Analysis and Policy at the Royal Institute of Technology. His main research interest lies in the intersection between transport and urban planning, transport policy, decision making processes and behavioural interactions modelling. He received his doctoral degree from the Department of Urban Management, Kyoto University, Japan. He has been/is a principal investigator (PI) and co-investigator (co-I) in various international and national projects, including developed an open-source smartphone based travel diary collector app, MEILI, which has been deployed in 5 different cities at 3 different continents around the globe, and evaluating the impacts of autonomous buses deployment as a public transport service in a mixed public roads in Stockholm. He is currently serving as a board member of the International Association for Travel Behaviour Research (IATBR) and an associate editor of Transportation, European Transport Research Review and Journal of Transport and Health.
5) Charge: free
6) Language: English only
7) Participation: Please contact Ms Tomoko Samukawa (samukawa@ip.civil.t.u-tokyo.a
8) Others: If you have some questions, please let me know them. My e-mail address is kato@civil.t.u-tokyo.ac.jp.
#183 The Future of Urban Transportation in Cairo-the Opportunity and Challenge
Date
2019年3月18日
Venue
東京大学工学部14号館144講義室
The Future of Urban Transportation in Cairo-the Opportunity and Challenge
Speaker
Prof. Dr. Ahmed I. Mosa, Professor of Transportation planning, The German University in Cairo & the British University in Cairo, Co- Founder and Managing Director of MASARAT consultancy
Abstract
Cairo is the 10th largest metropolis in the world with population reached 20 million and around 28 million trips/ year. Despite the high congestion in Egypt, the private car ownership rate actually remains among the lowest worldwide at approximately 50 cars per 1000 inhabitant. Even at the level of Greater Cairo Region (GCR), the most congested urban agglomerate, the rate has only recently reached approx. 100 cars/1000 inhabitants, yet it continues to rise. With regards to formal sector bus services, they have suffered an erosion of market share. Currently, around 2700 buses are working in Cairo; nearly 50% of the fleets are beyond residual life. The informal sector on the other hand (predominantly microbuses), on the other hand, appear to have achieved a very strong role in terms of road-based public transport services absorbing near 8.1 million journeys per day at present. Existing mobility systems in Cairo are close to breakdown. In 2015, the average time an urban dweller spends in traffic jams recorded 300 hours per year, three times more than the Figure in 2010. The cost of Congestion is estimated at 8 Billion $US/ Year, only in Greater Cairo Area. Delivering urban mobility will require more and more resources. Growth in urban travel needs is fast outpacing the evelopment of transport infrastructure, the need of the hour is to identify business strategies that enable sustainable integrated urban mobility. Therefore, a new economic landscape is needed to provide stakeholders with an array of opportunities to exploit, in the quest towards integrated mobility.
About a speaker
Dr. Mosa is the co-founder of MASARAT Consultancy Company that focuses on transportation, mobility, market research and investment platform. Dr. Mosa worked as the director of UITP MENA Center for Transport Excellence in Dubai where he oversees various research projects on various topics related to sustainable public transport. Mosa received a Master’s of Science and a Doctorate of Philosophy in Transportation Engineering from the University of Tokyo-Japan. As a Professor of transportation planning at the German University in Cairo, Nile University and the British university In Cairo, Mosa taught courses related to traffic engineering and transportation and participated in curriculum development and other special committees. Also before joining the UITP, he worked as the assistant to the Minister of Transportation in Egypt, and he is the founder of the Transportation Center
of Excellence at the Ministry of Transport in Egypt. Mosa established the center, supervising a team of researchers, and maintaining international and local relations with organizations and institutes such as JICA, World Bank and AFD. He was responsible for reviewing and updating the existing transportation models for Cairo (CREATS Transport model) and Egypt (MINITS) and developing transportation plans on the national, regional, international and cross-borders level including work on Egypt’s Bus Rapid Transit (BRT) systems and the master plans for Greater Cairo Region, national freeways road network and logistic centers. Dr. Mosa has over 16 years of experience that combine research/academic knowledge and practical experience. He won several awards, as well as authored and co- authored more than 40 papers in leading journals, conferences/workshops presentations and technical reports.
#101 子育てしやすく子どもにやさしいまちづくり~地域と子育て~
Date
2019年3月16日
Venue
東京大学工学部14号館141講義室(東京都文京区本郷7-3-1)
第101回 土木計画学ワンデイセミナー
「子育てしやすく子どもにやさしいまちづくり~地域と子育て~」
■主催:公益社団法人 土木学会 土木計画学委員会
■共催:公益財団法人 交通エコロジー・モビリティ財団
■企画:子育てしやすく子どもにやさしいまちづくり研究小委員会
■日時:2019年3月16日(土)13:30-17:30
■場所:東京大学工学部14号館141講義室(東京都文京区本郷7-3-1)
■定員:80名
■参加費:無料
■開催趣旨:
人口減少、少子高齢社会に直面する我が国において、子育てしやすく子どもにやさしいまちづくりが求められている。近年、バリアフリー法等の整備により、道路や公共交通、公共施設や商業施設などのバリアフリー化が進められ、一昔前と比べると子ども連れで外出しやすい環境が整ってきた。一方、子ども・子育て支援新制度の導入等、子育てしながら働きやすい環境の整備も進められている。さらに、子ども自身が安全・安心に外出できる環境の整備が重要な課題である。本ワンデイセミナーでは、土木計画学および他分野の研究者、行政、民間、NPOなど、多様な立場の方々が一堂に会し、これまでの研究成果の一部の報告と、最近の我が国の取り組みに関する報告をもとに、子育てしやすく子どもにやさしいまちづくりの方向性について、特に地域と子育てという視点から幅広く議論を行うことを目的とする。
■プログラム:
総合司会:青野 貞康(うつのみや市政研究センター)
13:30-13:35 開会挨拶
13:35-14:35 講演・報告(I)
1.「子育てコミュニティ構築に資する保育施設整備の方法」
後藤 智香子(東京大学)
2.「幼児向け公共交通教育で子ども達が得るもの」
神田 佑亮(呉工業高等専門学校)
3.「地域における子どもの諸活動と発育を考える」
吉城 秀治(福岡大学)
14:35-14:50 質疑応答
14:50-15:00 休憩
15:00-16:00 講演・報告(II)
4.「子どもの社会力向上を促す親子の生活環境の評価」
松村 暢彦(愛媛大学)
5.「子ども・子育て支援新制度と子ども・子育てをめぐる現状について」
島田 あかね(内閣府子ども子育て本部)
6.「子ども連れで外出しやすい環境整備の取り組み」
高橋 紀夫(国土交通省総合政策局)
16:00-16:15 質疑応答
16:15-16:30 休憩
16:30-17:45 パネルディスカッション
テーマ:地域と子育て
パネリスト:遠藤 俊太郎(交通経済研究所)
大島 隆(西日本鉄道)
松田 妙子(せたがや子育てネット 代表理事)
大野 慶太(全国子育てタクシー協会 会長)
司会:大森 宣暁(宇都宮大学)
17:45-17:50 閉会挨拶
18:00-19:30 懇親会@222アーバンコモンズ(参加費:1,000円)
■お申込み:大森(nobuaki[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp)宛て、「お名前」、「ご所属」、「懇親会参加のご希望」をご記入の上、3月11日(月)頃までにお申し込み下さい。(メールアドレスの[at]は@に変えてください。)
■お子様の保育サービス(無料)の実施を検討しております。ご希望の方は、セミナー申込みと合わせてご相談下さい。
国際セミナー「International Seminar on Integration of Spatial Computable General Equilibrium and Transport Modeling」を開催しました.
International Seminar on Integration of Spatial Computable General Equilibrium and Transport Modeling
日程:2019年3月14日
場所:神戸大学ブリュッセルオフィス
#100 「国土・県土整備の技術と実践」-人口減少・交流時代に真に必要なインフラ整備を考える- 沖縄会場
Date
2019年3月7日
Venue
ホテルオーシャン 大会議室場 ジェード(沖縄県那覇市安里2-4-8)
NO.100 土木計画学セミナー「国土・県土整備の技術と実践」-人口減少・交流時代に真に必要なインフラ整備を考える- 沖縄会場
土木計画学セミナー 「国土・県土整備の技術と実践」
-人口減少・交流時代に真に必要なインフラ整備を考える- 沖縄会場
■日時: 2019年3月7日(木)13:00~16:55
■主催: 公益社団法人 土木学会(担当:土木計画学研究委員会)
■後援: 内閣府沖縄総合事務局
■場所: ホテルオーシャン 3階 大会議室場 ジェード(http://www.hotelocean.jp/access.html)
■定員: 80名(申込者多数の場合は先着順)
■参加費: 無料(事前申込制)
■セミナーの趣旨:
自治体等の計画においては,多面的なストック効果を踏まえた公共インフラの包括的な社会的意義についての理解が不十分であったり、B/Cに代表される各種の評価技術についての理解が不十分であったりすることから、適切なインフラの整備や運用が阻害されるケースがしばしば見受けられます.こうした問題の改善を企図し、インフラ政策についての基礎的な考え方や知識をセミナー形式で学ぶ機会を、それらを専門に扱う土木学会(土木計画学)から講師を派遣する形で提供するとともに,沖縄におけるインフラ政策・地域政策の方向性や具体のインフラ整備事例について地元の講師からご講演をいただきます.本セミナーを通して,基礎的な評価技術の適正な理解に加えて、真に必要な土木・公共事業とは何かなどについて考え,より深い理解につながるきっかけとなることを企図しています.
■セミナーの主な対象者:
総合事務局開発部関係機関、県、基礎自治体等の主要自治体のインフラ関係部局の担当者,事業評価部局の担当者,コンサルタントなど,土木計画にかかわる実務の方を主な対象としていますが、研究者の皆様やこれから社会人になる学生の皆様のご参加も歓迎いたします。
■プログラム:
1.開会あいさつ:13:00~13:05 (12:40開場)
2.講義:13:05~15:35
1)インフラ政策の総論:京都大学大学院 教授 藤井聡
2)費用便益分析とストック効果:神戸大学大学院 教授 小池淳司
3)エビデンスに基づく政策形成支援の基礎と応用:早稲田大学 教授 佐々木邦明
3.離島・観光振興の課題と地域政策:15:45~16:40 琉球大学 准教授 神谷大介
4.全体の質疑応答:16:40~16:50
5.閉会挨拶:16:50~16:55
※セミナー終了後,会場にて関連書籍の販売がございます.
■申込方法: 土木学会ホームページ「本部主催行事の参加申込」にてお申込み下さい.
土木学会ウェブサイト(http://www.jsce.or.jp/event/active/information.asp)
■締切日: 2019年3月3日(日)
※本セミナーは「土木学会継続教育(CPD)プログラム」に 認定されています(4.0単位,JSCE19-0135)
#99 「国土・県土整備の技術と実践」-人口減少・交流時代に真に必要なインフラ整備を考える- 北海道会場
Date
2019年3月4日
Venue
TKP札幌駅カンファレンスセンター(札幌市北区北7条西2丁目9)
NO.99 土木計画学セミナー「国土・県土整備の技術と実践」-人口減少・交流時代に真に必要なインフラ整備を考える- 北海道会場
土木計画学セミナー 「国土・県土整備の技術と実践」
-人口減少・交流時代に真に必要なインフラ整備を考える- 北海道会場
■日時: 2019年3月4日(月)13:00~16:55
■主催: 公益社団法人 土木学会(担当:土木計画学研究委員会)
■後援: 国土交通省北海道開発局
■場所: TKP札幌駅カンファレンスセンター カンファレンスルーム2B
(http://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/cc-sapporo-eki/access/)
■定員: 80名(申込者多数の場合は先着順)
■参加費: 無料(事前申込制)
■セミナーの趣旨:
自治体等の計画においては,多面的なストック効果を踏まえた公共インフラの包括的な社会的意義についての理解が不十分であったり、B/Cに代表される各種の評価技術についての理解が不十分であったりすることから、適切なインフラの整備や運用が阻害されるケースがしばしば見受けられます.こうした問題の改善を企図し、インフラ政策についての基礎的な考え方や知識をセミナー形式で学ぶ機会を、それらを専門に扱う土木学会(土木計画学)から講師を派遣する形で提供するとともに,北海道におけるインフラ政策・地域政策の方向性や具体のインフラ整備事例について地元の講師からご講演をいただきます.本セミナーを通して,基礎的な評価技術の適正な理解に加えて、真に必要な土木・公共事業とは何かなどについて考え,より深い理解につながるきっかけとなることを企図しています.
■セミナーの主な対象者:
開発局関係機関、道、基礎自治体等の主要自治体のインフラ関係部局の担当者,事業評価部局の担当者,コンサルタントなど,土木計画にかかわる実務の方を主な対象としていますが、研究者の皆様やこれから社会人になる学生の皆様のご参加も歓迎いたします。
■プログラム:
1.開会あいさつ:13:00~13:05 (12:40開場)
2.講義:13:05~15:35
1)インフラ政策の総論:京都大学大学院 教授 藤井聡
2)権利と効率のストック効果 ―予測と予定の計画論―:神戸大学大学院 教授 小池淳司
3)エビデンスに基づく政策形成支援の基礎と応用:早稲田大学 教授 佐々木邦明
3.地域政策からみた北海道のインフラ整備:15:45~16:40 北海道大学公共政策大学院 特任教授 石井吉春
4.全体の質疑応答:16:40~16:50
5.閉会挨拶:16:50~16:55
※セミナー終了後,会場にて関連書籍の販売がございます.
■申込方法:土木学会ホームページ「本部主催行事の参加申込」にてお申込み下さい.
土木学会ウェブサイト(http://www.jsce.or.jp/event/active/information.asp)
■締切日: 2019年2月27日(水)
※本セミナーは「土木学会継続教育(CPD)プログラム」に 認定されています(4.0単位,JSCE19-0126)
#182 日欧国際共同セミナー International Seminar on Integration of Spatial Computable General Equilibrium and Transport Modeling
Date
2019年3月14日
Venue
ベルギー,ブリュッセル,神戸大学ブリュッセルオフィス
日欧国際共同セミナー International Seminar on Integration of Spatial Computable General Equilibrium and Transport Modeling
応用一般均衡分析と交通分析の統合に関する研究小委員会では,日欧国際共同セミナー International Seminar on Integration of Spatial Computable General Equilibrium and Transport Modeling を,下記日程・会場にて開催します.
日程:2019年3月14日(終日)
場所:ベルギー,ブリュッセル,神戸大学ブリュッセルオフィス
http://www.office.kobe-u.ac.jp/ipiep/kubec/index.html
参加者:CGE分析,交通モデル分析,ロジスティクスを専門とする研究者(主に欧州,日本から)
※参加者については募集および調整中ですが,現時点では,SCEG研究分野のパイオニアである Johannes Bröcker氏 (Kiel University),物流モデリングをご専門とされChairman of WCTR Scientific Committee も務められている Lori Tavasszy (TU Delft) のご参加が決定しています.
本セミナーへの参加をご希望・ご検討される方は,石倉 (iskr@tmu.ac.jp) までお知らせください.
ご不明な点については,お気軽にお問い合わせください.
第59回土木計画学研究発表会春大会
Date
2019年6月8日(土)・9日(日)
Venue
名城大学 ナゴヤドーム前キャンパス
第59回土木計画学研究発表会・春大会
会告について
▼ 第59回土木計画学研究発表会 会告(以下の通り)
講演用論文
発表会の当日に十分な時間で充実した議論を行い、更なる研究の発展や学術論文等への取りまとめに繋げることが本発表会の特色です。このため、「具体的に議論したい点(研究の新規性や枠組み、データ、モデルや結論の妥当性、今後の発展性や疑問点など)」を明記して申込みしていただきます。話題性、速報性のある論文や、調査・計画、技術検討等の事例報告も歓迎します。提出された講演用論文は、原則として無審査で掲載されますが、会場の制約等によってお断りすることもあります。
発表希望分野については、通常の発表希望分野Ⅲと並行して、発表希望分野Ⅰ(特別論文セッション)及び発表希望分野Ⅱ(手法等分野横断的区分)での発表希望もお願いしています。こちらへの応募もよろしくお願いします。
また、ポスターセッション、および「優秀ポスター賞」の表彰を今年度も実施いたします。受賞対象は、投稿時点における学生です。博士後期課程の学生を含ますが、博士後期課程の学生については発表時点においても学生である方に限ります。
口頭発表とポスターでの発表のどちらを希望するかを選んで申込んでいただきます(口頭発表およびポスターでの発表のいずれも、2020年に発刊予定の「土木学会論文集D3(土木計画学),Vol.75-6」への投稿対象となります)。
※2020年に発刊予定の「土木学会論文集D3(土木計画学),Vol.75-6」への投稿には、
①第59回の土木計画学研究・講演集に掲載され、文量が2ページ以上の論文である
②研究発表会において、著者により当該論文の発表が行われている(発表が行われていない、または著者以外によって発表された論文は投稿不可)
ことが必要となりますので、あらかじめご了承ください。
なお、第59回土木計画学研究発表会にて発表した論文は、
Vol.75-6(2019 年 6 月投稿)
Vol.76-5(2020 年 6 月投稿)
のいずれの論文集にも投稿可能ですが、
Vol.75-6(2019 年 6 月投稿)への投稿期限は6月21日(金)となります。
※2019年度より土木計画学研究発表会春大会と秋大会の実施内容の一部が入れ替わるのに伴い、土木学会論文集D3の投稿・発刊時期、対象となる発表論文等に大幅な変更がございます。
詳しくは、土木学会論文集D3・特集号(土木計画学研究・論文集)投稿の手引きにてご確認ください。
講演の申込み
(1) 申込みの手続きおよび注意点
2019年2月1日(金)~3月10日(日)17時までの期間内に、
土木計画学研究発表会(春大会)講演申込みページ申込画面より、講演申込と講演原稿の投稿を同時に行ってください。原稿のファイル形式はPDF形式のみ受付けます。 原稿は「講演原稿執筆要領」に従ってご執筆ください。締切日当日までは、投稿した原稿の確認、差し替えが可能ですが、締切日以降は、原稿の差し替えは受け付けられません。十分、ご注意ください。投稿時に、必ず申込内容が正しいか、PDFを取り違えての投稿がないか、申込内容とPDFのタイトル等の差異がないかなどをご確認ください。申込み期間の締切り間際に投稿が集中しますと、予期せぬ事態によりサーバーがダウンし受付ができなくなる恐れがあります。締切り間際の投稿は極力避けていただくようお願いいたします。
なお、講演原稿執筆要領に準じていないもの、および期限後に投稿されたものは受理できません。必ず所定の原稿を期間内にWEB上にて投稿してください。
間違えたファイルを提出した場合や申込内容とPDFの内容が違う場合であっても、そのまま掲載されますので、ご注意ください。
(2) 発表希望分野
(i) 発表希望分野Ⅰ(特別論文セッション)
充実した議論を実現するための、「特別論文セッション」を実施いたします。特別論文セッションでは、論文内容を踏まえたコメントに基づいた議論を行います。ただし、投稿論文数(最大で30編程度)、論文内容により、発表希望分野IIIでの発表となる場合もあります。
・1件当たりの持ち時間は、発表25分、コメンテーターによるコメント10分、討議10分の計45分とします。
・特別論文セッションでの発表を希望される方は、8ページ以上の論文を投稿することが必要です。
・発表者は投稿時にコメンテーター希望者を伝えることができます。
(ii) 発表希望分野II(手法等分野横断的区分)
従来の研究対象ごとの発表区分に加えて、研究で用いられている方法論に注目した分野横断的区分でのセッションを実施します。分野横断的区分セッションで発表を希望される場合には、今回は以下の5つから選択いただけます。さらに、そのセッションの司会兼コメンテーターでご希望の先生がいればご記入いただけます。これらの情報を参考に、専門性の高い先生への司会依頼を行うなどの検討を行う予定です。ただし、適切なセッションを組めない場合には、上記の発表希望分野Ⅰの従来型のセッションでの発表になります。
・新分析手法(まだ適用事例の少ない統計的手法(例.機械学習的分析手法)や記述的研究(例.物語研究)などの有効性等を議論したい研究)
・理論モデリング(実現象の理論的なモデリング、情報科学やゲーム理論などを駆使した手法について議論したい研究)
・統計分析解釈(一般的な統計分析の考察が重要な位置を占めており、その内容や妥当性について重点的に議論したい研究)
・海外事例(海外の事例的研究として集中的に議論したい研究)
・その他、重点的に議論したい分野横断的内容があればそのキーワードを直接書いていただくことも可能
(iii) 発表希望分野III(研究対象区分)
申し込みに際して、発表希望分野を下記の5つの発表分野から希望順に2つ選んでください。また、キーワードにつきましては、同キーワード欄の中から最大4つ選んでください。なお、適当なキーワードが見つからない場合は、投稿者の判断によるキーワードを1つだけ加えてください。
発表希望分野
| 発表希望分野 | キーワード |
| A 計画論・計画情報 | 計画基礎論、計画手法論、システム分析、調査論、公共事業評価法、財源・制度論、プロジェクト構想、施工計画・管理、維持管理計画、意識調査分析、計画情報、情報処理、市民参加、GIS、リモートセンシング、測量、環境計画、防災計画、河川・水資源計画、ライフライン計画・設計、地球環境問題 |
| B 地域・都市・景観 | 国土計画、地域計画、都市計画、地区計画、住宅立地、産業立地、人口分布、地価分析、土地利用、市街地整備、再開発、景観、公園・緑地、観光・余暇、空間設計、イメージ分析、土木史 |
| C 交通現象分析 | 発生交通、目的地選択、交通手段選択、経路選択、出発時刻選択、活動分析、時間利用、交通行動調査、交通意識分析、交通行動分析、自動車保有・利用、駐車需要、交通ネットワーク分析、土地利用・交通・環境統合モデル、観光・余暇行動 |
| D 交通基盤計画 | 総合交通計画、地区交通計画、公共交通計画、歩行者・自転車交通計画、道路計画、鉄道計画、空港・港湾計画、ターミナル計画、駐車場計画、物流計画 |
| E 交通運用管理 | 交通流、交通容量、サービス水準、交通制御、交通管理、交通安全、交通情報、交通環境、公共交通運用、交通弱者対策、水上交通、空港管理、交通量計測、TDM、ITS、モビリティマネジメント(MM) |
(3) 発表形式
口頭発表とポスターでの発表のどちらを希望するかを選んでいただきます。なお、会場の都合でご希望に添えない場合もありますので予めご了承下さい。
(4) 投稿料
講演1本につき投稿料(参加費含む)として一般12,000円、学生9,000円を請求いたします。2本以上投稿する方については、2本目以降の投稿料は一般・学生ともに6,000円を請求いたします。振込手数料は各自でご負担願います。
講演原稿執筆要領
講演原稿の書式・形式は、土木学会論文集のものに準じています。下記の作成例やサンプルファイルをご利用ください。講演原稿では、英文アブストラクトの記入は任意です。その他書式・形式についての詳細は土木学会論文集の原稿作成の手引き等をご参照ください。なお、「土木学会論文集D3(土木計画学), Vol.75-6」への投稿の際には英文アブストラクトは必要です。
サンプルファイル 和文(Word2000)/English(Word2000)
原稿作成例 和文(PDF)/English(PDF)
お問合せ先
土木計画学研究委員会大会運営小委員会(春大会担当:橋本,氏原,林)
E-mail:keikaku59@jsce.or.jp
#98 成果報告会:多様なビッグデータを活用した道路技術研究開発
Date
2019年2月22日
Venue
東京大学 武田先端知ビル 武田ホール(〒113-0032 東京都文京区弥生2-11-16)
NO.98 成果報告会:多様なビッグデータを活用した道路技術研究開発
第98回 土木計画学ワンデイセミナー 【2019.02.12 申込方法追記】
「成果報告会:多様なビッグデータを活用した道路技術研究開発」
■主催: 神戸大学大学院工学研究科市民工学専攻 井料研究室
広島大学工学部第四類社会基盤環境工学プログラム 地域環境計画学研究室
東京工業大学環境・社会理工学院土木・環境工学系 福田研究室
■後援: 国土交通省道路局(予定,調整中)
■開催主旨:
国土交通省道路局の新道路技術開発(http://www.mlit.go.jp/road/tech/index.html)で行われている三つの特定課題(ETC2.0,自動運転,観光AI)について,各プロジェクトリーダーの先生より研究概要のご紹介を頂くと共に,今後の多様なビッグデータを活用した道路技術研究開発の方向性についてのパネルディスカッションを行う.また,横浜国立大学上席特別教授の藤野陽三先生より,主にハード分野におけるAI・ビッグデータ活用の展望についての基調講演を賜る.
■プログラム(仮)
13:00 オープニング
福田大輔(東京工業大学大学院准教授)
13:05 招待講演
藤野陽三(横浜国立大学先端科学高等研究院上席特別教授,東京大学名誉教授):
「インフラメンテナンス・マネジメントにおけるAI・ビッグデータ活用の展望」
13:40 特定課題 “ETC2.0を含む多様なビッグデータ活用” 最終年度成果報告
井料隆雅(神戸大学大学院教授):
「蓄積車両軌跡データの効率的活用のための階層型データベースの構築」
福田大輔(東京工業大学大学院准教授):
「ETC2.0プローブ情報等を活用した“データ駆動型”交通需要・空間マネジメントに関する研究開発」
塚井誠人(広島大学大学院准教授):
「複数のデータを活用した道路のストック効果の計測技術の再構築」
14:55 休憩
15:05 特定課題 “自動運転社会の実現に必要な道路インフラについて” 二年度報告
有村幹治(室蘭工業大学大学院准教授):
「自動運転と道の駅を活用した生産空間を支える新たな道路交通施策に関する研究開発」
原田 昇(東京大学大学院教授):
「対流型地域圏における自動走行システム普及に向けた新たな道路ストック評価手法」
15:45 特定課題 “AIを活用した交通分析・予測・マネジメント手法の開発” 初年度報告
力石 真(広島大学大学院准教授):
「AI技術に基づく短期交通予測手法と総合的な交通需要マネジメントの研究開発」
桑原雅夫(東北大学大学院教授):
「交通流理論とAI学習による非日常の発見とアラート発信」
布施孝志(東京大学大学院教授):
「学習型モニタリング・交通流動予測に基づく観光渋滞マネジメントについての研究開発」
16:30 休憩
16:45 パネルディスカッション「多様なビッグデータを活用した道路技術研究開発の展望」
塚井誠人[オーガナイザー]
水野宏治(国土交通省道路局企画課評価室長),井料隆雅,福田大輔,桑原雅夫
17:50 クロージング
井料隆雅(神戸大学大学院教授)
18:00 懇親会
■ 申込方法 【2019.02.12 追記】
参加される方は下記Google Formよりお申込ください.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzIbKy6OvQRRvTona0zfThk5c141mDpcj3Eu7wL_D4btkl9Q/viewform?vc=0&c=0&w=1
Google Formへアクセスできない方はk.sakai [at mark] port.kobe-u.ac.jp(事務局:神戸大学井料研究室 坂井)まで下記フォームにてお申込みください.
—–【申込フォームここから】—-
氏名:
所属:
メールアドレス:
懇親会参加の有無:
—–【申込フォームここまで】—–
#181 The Future of Urban Transportation in Cairo-the Opportunity and Challenge
Date
2019年2月18日
Venue
東京大学工学部14号館144講義室
The Future of Urban Transportation in Cairo-the Opportunity and Challenge
Title: The Future of Urban Transportation in Cairo- the Opportunity and
Challenge
Speaker: Prof. Dr. Ahmed I. Mosa, Professor of Transportation planning, The German University in Cairo & the British University in Cairo, Co- Founder and Managing Director of MASARAT consultancy
Abstract:
Cairo is the 10th largest metropolis in the world with population reached 20 million and around 28 million trips/ year. Despite the high congestion in Egypt, the private car ownership rate actually remains among the lowest worldwide at approximately 50 cars per 1000 inhabitant. Even at the level of Greater Cairo Region (GCR), the most congested urban agglomerate, the rate has only recently reached approx. 100 cars/1000 inhabitants, yet it continues to rise. With regards to formal sector bus services, they have suffered an erosion of market share. Currently, around 2700 buses are working in Cairo; nearly 50% of the fleets are beyond residual life. The informal sector on the other hand (predominantly microbuses), on the other hand, appear to have achieved a very strong role in terms of road-based public transport services absorbing near 8.1 million journeys per day at present. Existing mobility systems in Cairo are close to breakdown. In 2015, the average time an urban dweller spends in traffic jams recorded 300 hours per year, three times more than the Figure in 2010. The cost of Congestion is estimated at 8 Billion $US/ Year, only in Greater Cairo Area. Delivering urban mobility will require more and more resources. Growth in urban travel needs is fast outpacing the evelopment of transport infrastructure, the need of the hour is to identify business strategies that enable sustainable integrated urban mobility. Therefore, a new economic landscape is needed to provide stakeholders with an array of opportunities to exploit, in the quest towards integrated mobility.
About a speaker:
Dr. Mosa is the co-founder of MASARAT Consultancy Company that focuses on transportation, mobility, market research and investment platform. Dr. Mosa worked as the director of UITP MENA Center for Transport Excellence in Dubai where he oversees various research projects on various topics related to sustainable public transport. Mosa received a Master’s of Science and a Doctorate of Philosophy in Transportation Engineering from the University of Tokyo-Japan. As a Professor of transportation planning at the German University in Cairo, Nile University and the British university In Cairo, Mosa taught courses related to traffic engineering and transportation and participated in curriculum development and other special committees. Also before joining the UITP, he worked as the assistant to the Minister of Transportation in Egypt, and he is the founder of the Transportation Center
of Excellence at the Ministry of Transport in Egypt. Mosa established the center, supervising a team of researchers, and maintaining international and local relations with organizations and institutes such as JICA, World Bank and AFD. He was responsible for reviewing and updating the existing transportation models for Cairo (CREATS Transport model) and Egypt (MINITS) and developing transportation plans on the national, regional, international and cross-borders level including work on Egypt’s Bus Rapid Transit (BRT) systems and the master plans for Greater Cairo Region, national freeways road network and logistic centers. Dr. Mosa has over 16 years of experience that combine research/academic knowledge and practical experience. He won several awards, as well as authored and co- authored more than 40 papers in leading journals, conferences/workshops presentations and technical reports.
#97 健康政策と都市構造を考えたまちづくりの展開方策
Date
2019年1月28日
Venue
土木学会講堂(〒160-0004 東京都新宿区四谷1丁目 外濠公園内)
健康政策と都市構造を考えたまちづくりの展開方策
第97回土木計画学ワンデイセミナー
「健康政策と都市構造を考えたまちづくりの展開方策」
■日時:2019 年 1 月28 日(月)10:30 – 17:00
■場所:土木学会講堂(東京都新宿区四谷一丁目 外濠公園内)
■参加費:無料
■主催: 土木学会土木計画学研究委員会 健康まちづくり研究小委員会
■共催: 関西大学先端科学技術推進機構 エコメディカルな社会システム構築研究グループ
■参加申し込み:
土木学会 イベント申込ページから登録をお願いします
http://www.jsce.or.jp/event/active/information.asp
■開催概要:
生涯を通して健康に過ごせるライフスタイルが望まれており、それをまちで支える取組みが進んでいる。日常の健康への欲求や健康寿命の増進へのニーズが高まる市民やマーケット拡大に期待する企業だけでなく、それによる社会保障政策費用の削減の必要性が高まる政府にとっても喫緊の課題となっている。しかし、このような課題は、医療・保健分野にとどまらず、総合的なまちづくりの観点から進める必要がある。世界的にみても、Healthy City の取組みに見られるように注目され、さらなる段階への飛躍が期待されている。健康まちづくり研究小委員会では、このような背景から、生涯を通して健康を実感できるまちづくりを具体的な研究フィールドにおいて進め、まちづくりと健康の関係に関わる実データ収集、そのデータの集計・分析・提示・目標設定による人々の行動への影響、まちづくり手法としてのエリアマネジメントのあり方などを盛り込んだ総合的な研究を進めてきた。
健康まちづくり計画の側面について、①健康を増進・維持するための人々の「行動のあり方」、②それを支える環境としての「都市のあり方」、③両者を効果的につなげる「社会システムデザイン」に分類する。ここでは、それぞれの視点から健康まちづくりの方向性を検討する。本セミナーにおいては、個々の視点についての代表的な研究成果について報告する。また、国土交通省、厚生労働省、地方自治体を招いて健康まちづくりに関する議論を行う。
■プログラム:
10:30~ 開会挨拶:小委員会委員長 秋山孝正(関西大学)
10:45~ 報告1 (G1:行動論):谷口綾子氏(筑波大学)
11:15~ 報告2 (G2 :都市論):藤生慎氏(金沢大学)
11:45~ 報告3 (G3 :社会システム論):柳原崇男氏(近畿大学)
12:15~ 休憩
13:30~ 講演1:楠田幹人氏(国土交通省 都市局 都市計画課長)
14:00~ 講演2:吉田啓氏(厚生労働省 保険局 医療介護連携政策課)
14:30~ 講演3:久住時男氏(新潟県見附市長)
15:00~ 休憩
15:10~ パネルディスカッション
コーディネーター:小委員会副委員長 谷口守(筑波大学)
楠田幹人氏(国土交通省 都市局 都市計画課長)
吉田啓氏(厚生労働省 保険局 医療介護連携政策課)
久住時男氏(新潟県見附市長)
森栗茂一氏(大阪大学)
16:50~ 閉会挨拶:小委員会幹事長 北詰恵一(関西大学)
健康まちづくり研究小委員会ワンディセミナー
健康まちづくり研究小委員会ワンディセミナー
タイトル「健康政策と都市構造を考えたまちづくりの展開方策」
・日時:2019(平成30)年1月 28日(月) 10:30~17:00
・場所:土木学会講堂
生涯を通して健康に過ごせるライフスタイルが望まれており、それをまちで支える取組みが進んでいる。日常の健康への欲求や健康寿命の増進へのニーズが高まる市民やマーケット拡大に期待する企業だけでなく、それによる社会保障政策費用の削減の必要性が高まる政府にとっても喫緊の課題となっている。しかし、このような課題は、医療・保健分野にとどまらず、総合的なまちづくりの観点から進める必要がある。世界的にみても、Healthy City の取組みに見られるように注目され、さらなる段階への飛躍が期待されている。健康まちづくり研究小委員会では、このような背景から、生涯を通して健康を実感できるまちづくりを具体的な研究フィールドにおいて進め、まちづくりと健康の関係に関わる実データ収集、そのデータの集計・分析・提示・目標設定による人々の行動への影響、まちづくり手法としてのエリアマネジメントのあり方などを盛り込んだ総合的な研究を進めてきた。
健康まちづくり計画の側面について、①健康を増進・維持するための人々の「行動のあり方」、②それを支える環境としての「都市のあり方」、③両者を効果的につなげる「社会システムデザイン」に分類する。ここでは、それぞれの視点から健康まちづくりの方向性を検討する。本セミナーにおいては、個々の視点についての代表的な研究成果について報告する。また、国土交通省、厚生労働省、地方自治体を招いて健康まちづくりに関する議論を行う。
・プログラム
10:30~ 開会挨拶:小委員会委員長 秋山孝正(関西大学)
10:45~ 報告1 (G1:行動論):谷口綾子氏(筑波大学)
11:15~ 報告2 (G2 :都市論):藤生慎氏(金沢大学)
11:45~ 報告3 (G3 :社会システム論):柳原崇男氏(近畿大学)
12:15~ 休憩
13:30~ 講演1:楠田幹人氏(国土交通省 都市局 都市計画課長)
14:00~ 講演2:吉田啓氏(厚生労働省 保険局 医療介護連携政策課)
14:30~ 講演3:久住時男氏(新潟県見附市長)
15:00~ 休憩
15:10~ パネルディスカッション
コーディネーター:小委員会副委員長 谷口守(筑波大学)
楠田幹人氏(国土交通省 都市局 都市計画課長)
吉田啓氏(厚生労働省 保険局 医療介護連携政策課)
久住時男氏(新潟県見附市長)
森栗茂一氏(大阪大学)
16:50~ 閉会挨拶:小委員会幹事長 北詰恵一(関西大学)
活動記録:スマート・プランニング実践セミナー(@高知市)
スマート・プランニング実践セミナー(@高知市)
地方開催企画 第3弾「スマート・プランニング実践セミナー(@高知市)」
主催:土木計画学スマート・プランニング研究小委員会
日時:2019年1⽉11⽇(金)10:30-17:15
(午前の部:10:30-12:00 午後の部:13:00-17:15)
開催地:高知県高知市(高知県自治会館第1会議室)
概要:
スマート・プランニングは,Wi-FiやGPSといったさまざまな交通関連データを活用し,そこから得られる「行動データ」をもとに,利用者の暮らしと事業者の事業活動を同時に計画するための(施設計画・交通計画・土地利用計画を包含する)新たな都市計画に向けた計画手法であり,今後の都市計画・まちづくりの切り札として大いに期待されています.今後,多くの都市で導入されていくには,各地の実務者がスマート・プランニングに関する様々なスキルを取得することが重要となります.本セミナーでは、主にコンサルタント職員等の実務者を対象として,甲府市の取組みを事例に,スマート・プランニングの調査計画を立案するためのスキル習得を目指します.
プログラム:次第
【午前の部】
・スマート・プランニング概要説明 [資料1]
・事例紹介(岡山市・神戸市)[資料2] [資料3]
【午後の部】
・高知市取組み概要説明(高知市)[資料4]
・まちなか⾒学会 [資料5]
・基調講演
①羽藤英二氏(東京⼤学)
②坂本淳氏(高知大学)
③西内裕晶氏(高知工科大学)
・ワークショップ [資料6] [資料7] [資料8] [資料9]
・講評・閉会挨拶(研究⼩委員会)
スマート・プランニング実践セミナー(@高知市)
スマート・プランニング実践セミナー(@高知市)
地⽅開催企画 第3弾「スマート・プランニング実践セミナー(@高知市)」
⼟⽊計画学スマート・プランニング研究⼩委員会では、地⽅開催企画の第3弾として「スマート・プランニング実践セミナー(@高知市)」を開催します。
参加を希望される⽅は、以下のフォームよりお気軽に申し込みください。
【定員50名程度 ※先着順】(午前の部、午後の部のみでも承ります)
※事前申し込み制、〆切 1/7(月) 17:00
<申し込みフォーム>
宛先:hqt-smapla-seminar@ml.mlit.go.jp
件名:【スマート・プランニング実践セミナー申し込み】
本⽂:①参加者⽒名 ②所属
=============================================
地⽅開催企画 第3弾「スマート・プランニング実践セミナー(@高知市)」
主催:⼟⽊計画学スマート・プランニング研究⼩委員会
⽇時:2019年1⽉11⽇(金)10:30-17:15
(午前の部:10:30-12:00 午後の部:13:00-17:15)
開催地:高知県高知市(高知県自治会館第1会議室)
参加費:無料
概要:
スマート・プランニングは、Wi-FiやGPSといったさまざまな交通関連データを活⽤し、そこから得られる「⾏動データ」をもとに、利⽤者の暮らしと事業者の事業活動を同時に計画するための(施設計画・交通計画・⼟地利⽤計画を包含する)新たな都市計画に向けた計画⼿法であり、今後の都市計画・まちづくりの切り札として⼤いに期待されています。今後、多くの都市で導⼊されていくには,各地の実務者がスマート・プランニングに関する様々なスキルを取得することが重要となります。本セミナーでは、主に自治体やコンサルタント職員等の実務者を対象として、高知市の取組みを事例に、スマート・プランニングの調査計画を⽴案するためのスキル習得を⽬指します。
プログラム:
【午前の部】
・スマート・プランニング概要説明
・事例紹介(岡山市・神戸市)
【午後の部】
・開会挨拶(研究⼩委員会)
・高知市取組み概要説明(高知市)
・まちなか⾒学会
・基調講演
①羽藤英二氏(東京⼤学)
②坂本淳氏(高知大学)
③西内裕晶氏(高知工科大学)
・ワークショップ
・講評・閉会挨拶(研究⼩委員会)
=============================================
#96 空間的応用一般均衡分析と交通プロジェクトのストック効果
Date
2019年1月8日
Venue
土木学会講堂(〒160-0004 東京都新宿区四谷1丁目 外濠公園内)
空間的応用一般均衡分析と交通プロジェクトのストック効果
第96回 土木計画学ワンデイセミナー 「空間的応用一般均衡分析と交通プロジェクトのストック効果」
「応用一般均衡分析と交通分析の統合に関する研究小委員会」(委員長 小池淳司(神戸大学))では,下記の要領にて第96回ワンデイセミナーを開催いたします.
■日時:2019年1月8日(火),10:30-
■会場:土木学会講堂
■主催:応用一般均衡分析と交通分析の統合に関する研究小委員会
■申込:
参加ご希望の方は,以下のリンクからオンラインにてお申込みください.
https://goo.gl/forms/r3psDHwYMzRZXZKt2
※上記リンクへのアクセスができない場合には,参加者のお名前とご所属を,本小委員会幹事長の石倉(iskr@tmu.ac.jp)までお知らせください. 記
■プログラム
10:30 開会
10:35 第一部,講演
・権利と効率のストック効果:小池淳司(神戸大学)
12:00 休憩
13:00 第二部,SCGE 分析と実務への活用
・産業別生産額変化の事後比較によるSCGE 分析の推計精度:右近崇(三菱UFJ リサーチ&コンサルティング)
・ストック効果最大化にむけたSCGEモデルの活用方法:佐藤啓輔(復建調査設計)
・SCGE モデルの概要と設計・計算法の基礎(セミナー参加者限定で,簡易なSCGE モデルの計算過程を入力済みのMS-Excelファイルを配布します):石倉智樹(首都大学東京)
15:00 休憩
15:30 第三部,関連分野の研究フロンティア
(以下の題目は今後変更される可能性もあります)
・集積の経済を考慮したSCGE 分析:高山雄貴(金沢大学)
・リニア中央新幹線の影響と地域差:平松燈(近畿大学)
・SCGE モデルによる地域別生産性の推定:瀬木俊輔(京都大学)
17:30 セミナー総括:小池淳司(神戸大学)
ワンデイセミナー「空間的応用一般均衡分析と交通プロジェクトのストック効果」を開催しました
ワンデイセミナー「空間的応用一般均衡分析と交通プロジェクトのストック効果」を開催しました
本研究小委員会の主催するワンデイセミナーを開催しました.
概要は以下のとおりです.
第96回 土木計画学ワンデイセミナー 「空間的応用一般均衡分析と交通プロジェクトのストック効果」
日時:2019年1月8日(火),10:30-
場所:土木学会講堂
主催:応用一般均衡分析と交通分析の統合に関する研究小委員会
プログラム
10:30 開会
10:35 第一部,講演
・権利と効率のストック効果:小池淳司(神戸大学)
12:00 休憩
13:00 第二部,SCGE 分析と実務への活用
・産業別生産額変化の事後比較によるSCGE 分析の推計精度:右近崇(三菱UFJ リサーチ&コンサルティング)
・ストック効果最大化にむけたSCGEモデルの活用方法:佐藤啓輔(復建調査設計)
・SCGE モデルの概要と設計・計算法の基礎(セミナー参加者限定で,簡易なSCGE モデルの計算過程を入力済みのMS-Excelファイルを配布します):石倉智樹(首都大学東京)
15:00 休憩
15:30 第三部,関連分野の研究フロンティア
(以下の題目は今後変更される可能性もあります)
・集積の経済を考慮したSCGE 分析:高山雄貴(金沢大学)
・リニア中央新幹線の影響と地域差:平松燈(近畿大学)
・SCGE モデルによる地域別生産性の推定:瀬木俊輔(京都大学)
17:30 セミナー総括:小池淳司(神戸大学)
International Seminar on Integration of Spatial Computable General Equilibrium and Transport Modeling
International Seminar on Integration of Spatial Computable General Equilibrium and Transport Modeling
日程:2019年3月14日
場所:神戸大学ブリュッセルオフィス
【重要】2019年度から土木計画学研究発表会と土木学会論文集(土木計画学)特集号が変わります!
2019年度から土木計画学研究発表会が変わります!土木学会論文集(土木計画学)特集号も変わります!
2019年度から土木計画学研究発表会と土木学会論文集(土木計画学)特集号が変わります!
詳しくはこちらのPDFをご確認下さい。
#180 Street Management Integrating Places and Public Transportation in Southeast Asian Cities - The Case of City Center of Khon Kaen City, Thailand -
Date
2019年1月10日
Venue
横浜にぎわい座 のげシャーレ(小ホール)
Street Management Integrating Places and Public Transportation in Southeast Asian Cities - The Case of City Center of Khon Kaen City, Thailand -
横浜国立大学 交通と都市研究室主催にて,ミニ国際シンポジウム(英語発表)を開催いたします.このシンポジウムでは,タイ国コンケン大学との共同プロジェクトの成果報告をベースに,成長の著しい東南アジア地方都市の今後の街路及び交通施策のあり方について議論いたします.ゲストコメンテーターとして,大阪市立大学 吉田長裕准教授,埼玉大学 小嶋文准教授をお招きします.
日時:2019年1月10日(木)18:30~20:30(18:00開場)
場所:横浜にぎわい座 のげシャーレ(小ホール)
横浜市中区野毛町3丁目110番1号
プログラム:
18:30-18:35 挨拶・趣旨説明
18:35-18:55 東南アジア地方都市の街路空間とモビリティ (横浜国立大学 中村文彦教授)
18:55-19:05 「場 (Place)」の機能とストリートマネジメント (横浜国立大学 三浦詩乃)
19:05-19:35 タイ・コンケン市での街路プロジェクト
1) 地域学生のためのメインストリートプロジェクト (横浜国立大学チーム)
2) メインストリートにおける社会実験のあり方への提言 (コンケン大学 Nayatat Tonmitr講師)
3) 住まいやすい中規模都市化に向けたコンケン市のストリートモビリティ (コンケン大学 Pattamapom Wongwiriya講師)
4) コンケン市郊外部の路上マーケットの利用実態と類型 (コンケン大学 Pornnarong Charnnuwong准教授)
19:35ー20:05 ゲストからのコメント
1) 大阪市立大学 吉田長裕准教授
2) 埼玉大学 小嶋文准教授
20:05-20:25 ディスカッションおよびQ&A
20:25-20:30 総括・閉会
申込方法:以下のリンクからオンラインにてお申込みください.
https://goo.gl/forms/uvU0jn5xVRhiyR3T2
※上記リンクへのアクセスができない場合には,参加者のお名前とご所属を,専用メールアドレスkkctuel2019@gmail.com までお知らせください.
#178 国際セミナー New Mobility and Society Combining Autonomous Driving Technology and Sharing Service
Date
2018年11月30日
Venue
東京工業大学キャンパス・イノベーションセンター多目的室3
国際セミナー New Mobility and Society Combining Autonomous Driving Technology and Sharing Service
開催の主旨:それほど遠くない将来,自動運転技術とシェアリングが融合した個人間カーシェアリングサービスが実現すると思われる.そのような新たなサービスの提供は,自動車利用はもちろんのこと,従来のように個別に提供されてきた公共交通サービスの形態や役割を大きく変えるであろう.また,駐車場などの交通インフラは言うに及ばず,都市構造さえ大きく変え得ると考えられる.本国際学術セミナーでは,自動運転技術とシェアリングが融合したモビリティサービスとそれが実現した社会のあり方について,海外の新鋭研究者の基調講演に加えて,学術研究者,自動運転・ITS推進組織,企業経営コンサルタントから提言を頂くと共に,我が国の最新の研究発表,意見交換を行う.
日時:2018年11月30日(金)10:00~17:00
場所:東京工業大学キャンパス・イノベーションセンター多目的室3
所在地:〒108-0023 東京都港区芝浦3-3-6
TEL:03-5440-9020
主催:熊本大学交通まちづくり研究室
共催:土木学会土木計画学研究委員会
国土交通省国土技術総合政策研究所
協賛:一般財団法人計量計画研究所
言語:英語
プログラム
午前 10:00~12:35
1. Opening remarks
2. Keynote Speech: Research Frontiers in Autonomous Driving and Shared-Mobility (Prof. Schott Eric Le Vine, Assistant Professor, New York State University)
3. Automated driving for universal services; Japanese approach (天野 肇 氏/Mr. Hajime Amano,ITS Japan 専務理事/President and CEO, ITS Japan)
4. The Rising and Realization of Intelligent Mobility (周 磊 氏/Mr. Lei Zhou,デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 執行役員/Partner at Monitor Deloitte/Deloitte Tohmatsu Consulting LLC)
5. Intelligent Mobility Technology Development for Sharing Economy (福島 正夫 氏/Mr. Masao Fukushima,株式会社オートモーティブテクノロジーエンジニアリングサービス部技術顧問,ITS Technical Consultant, Engineering Service Department, Nissan Automotive Technology Co., Ltd)
午後 13:30~17:00
6. 研究者による先端研究発表
(1) Consumer preference for alternative free-floating carsharing fleet management mechanisms (Prof. Scott Eric Le Vine, Assistant Professor, New York State University)
(2) On the characteristics of car sharing users (山本 俊行 先生/Prof. Toshiyuki Yamamoto, Professor, Nagoya University)
(3) Endogenous market penetration dynamics of connected and automated vehicles: Transport-oriented model and its paradox (瀬尾 亨 先生/Prof. Toru Seo, Assistant Professor, The University of Tokyo)
(4) Adoption of dynamic ridesharing system under influence of information on social network (Mr. Phathinan Thaithatkul, A project researcher at Center for Spatial Information Science, The University of Tokyo)
(5) Dynamic Taxi-Pooling Service Experiment in Nagoya (金森 亮 先生/Prof. Ryo Kanamori, Research Associate Professor, Nagoya University)
(6) Social acceptance of autonomous vehicles in Japan and UK: focused on risk perception and trust (谷口 綾子 先生/Prof. Ayako Taniguchi, Associate Professor, University of Tsukuba)
(7) Mobility and society combining autonomous driving technology and sharing services (溝上 章志 先生/Prof. Shoshi Mizokami, Professor, Kumamoto University)
7. Closing remarks
連絡先:熊本大学大学院先端科学研究部 溝上 章志
TEL:096-342-3541
e-mail:smizo@gpo.kumamoto-u.ac.jp
#179 Innovation in shared mobility and planning
Date
2018年11月29日
Venue
The University of Yokyo Hongo Campus, Engineering Building 14 Room 802 (8F)
Innovation in shared mobility and planning
Date: November 29th 2018
Time: 15:00 – 17:00
Place: The University of Tokyo Hongo Campus, Engineering Building 14 Room 802 (8F)
Schedule:
15:00 – 15:05 Introduction
15:05 – 15:55 Keynote presentation: ” Innovation in shared mobility and planning”
Presenter: Dr. Scott Le Vine
15:55 – 16:25 “Network planning problem for shared-mobility with stochastic demand”
Presenter: Dr. Sachiyo Fukushima, Research Associate, The University of Tokyo
16:25 – 16:55 “”Metro-MaaS”, an Integrated Mobility Service Concept for Magacities”
Presenter: Dr. Yohei Fujigaki, Research Associate, The University of Tokyo
16:55 – 17:00 Wrap-up
Places are limited, so if you interested in participating, please send an e-mail to
gtroncoso@ut.t.u-tokyo.ac.jp and urata@bin.ut.t.u-tokyo.ac.jp with your name and affiliation.
第9回研究小委員会を開催しました.
第9回研究小委員会を開催しました.
場所:大分大学(土木計画学研究発表会 秋大会)
議事
1.今後の予定について
・ワンデイセミナーの開催
・国際セミナーの開催
・土木学会論文集特集企画について
第58回土木計画学研究発表会・秋大会
第58回土木計画学研究発表会・秋大会
招待講演(11/23(金),15:55~17:15)
特別講演(11/23(金),15:05~15:50)
発表プログラム
災害調査報告(11/23(金),13:30~15:00)
大分特別セッション(現地視察,1,2)(11/24(土)午前)
発表要領
事前参加申込みについて
CD-ROM版講演集の配布について
チュートリアルセッションの開催(ネットワークと行列情報の分析)
14:45-15:45 固有値による分解と非負値行列因子分解 山口裕通(金沢大学)
16:00-17:30 交通ネットワーク均衡分析とその演習 中山晶一朗(金沢大学)
- 本案内時点から11月6日(火)ご登録分までは,土木計画学研究委員会関連小委員会および論文集編集委員会等土木学会関係会議の予約を先行して受け付けます(無料).下記の予約枠から必要な分をご予約ください.ご用意できる会議室数(調整中)の範囲内で,ご参加予定者数に応じて会議室を割り当てます.満室の場合にはその旨を返答致しますのでご容赦願います.
- 上記以外の予約も本案内時点から受け付けます(有料)が,11月7日(水)以降に,前項と同様にご参加予定者数に応じて会議室を割り当てます.満室の場合にはその旨を返答致しますのでご容赦願います.なお,1枠(30分)当たり1,000円(税込)を頂戴いたします.お申込み内容は,大会幹事から予約確定メールをお送りした時点で成立するものとし,変更・取消は不可と致しますので,ご注意ください.なお,発表申込みや聴講申込みと同様に,研究発表会後に請求書を送付致します.振込手数料等は各自でご負担願います.
- いずれも,会議室のお申し込み締め切りは11月21日(水)です.その後も受け付けは致しますが,返答が著しく遅くなる場合がありますのでご了承願います.
- お申込:こちらのフォームからお申し込みください.https://goo.gl/forms/f6LYGDmWv7KqKTzg2
予約枠(大会1日目,11/23(金)は設定なし)
- 大会2日目,11/24(土):下記のうち(1)~(17)
- 大会3日目,11/25(日):下記のうち(1)~(14)
- (1) 9:00~9:30
- (2) 9:30~10:00
- (3) 10:00~10:30
- (4) 10:45~11:15
- (5) 11:15~11:45
- (6) 11:45~12:15
- (7) 12:15~12:45
- (8) 12:45~13:15
- (9) 13:15~13:45
- (10) 13:45~14:15
- (11) 14:15~14:45
- (12) 15:00~15:30
- (13) 15:30~16:00
- (14) 16:00~16:30
- (15) 16:45~17:15
- (16) 17:15~17:45
- (17) 17:45~18:15
お問合せ先
会告について
講演用論文
講演の申込み
発表希望分野
| 発表希望分野 | キーワード |
| A 計画論・計画情報 | 計画基礎論、計画手法論、システム分析、調査論、公共事業評価法、財源・制度論、プロジェクト構想、施工計画・管理、維持管理計画、意識調査分析、計画情報、情報処理、市民参加、GIS、リモートセンシング、測量、環境計画、防災計画、河川・水資源計画、ライフライン計画・設計、地球環境問題 |
| B 地域・都市・景観 | 国土計画、地域計画、都市計画、地区計画、住宅立地、産業立地、人口分布、地価分析、土地利用、市街地整備、再開発、景観、公園・緑地、観光・余暇、空間設計、イメージ分析、土木史 |
| C 交通現象分析 | 発生交通、目的地選択、交通手段選択、経路選択、出発時刻選択、活動分析、時間利用、交通行動調査、交通意識分析、交通行動分析、自動車保有・利用、駐車需要、交通ネットワーク分析、土地利用・交通・環境統合モデル、観光・余暇行動 |
| D 交通基盤計画 | 総合交通計画、地区交通計画、公共交通計画、歩行者・自転車交通計画、道路計画、鉄道計画、空港・港湾計画、ターミナル計画、駐車場計画、物流計画 |
| E 交通運用管理 | 交通流、交通容量、サービス水準、交通制御、交通管理、交通安全、交通情報、交通環境、公共交通運用、交通弱者対策、水上交通、空港管理、交通量計測、TDM、ITS、モビリティマネジメント(MM) |
(3) 発表形式
口頭発表とポスターでの発表のどちらを希望するかを選んでいただきます。なお、会場の都合でご希望に添えない場合もありますので予めご了承下さい。
(4) 投稿料
講演1本につき投稿料(参加費含む)として一般12,000円、学生9,000円を請求いたします。2本以上投稿する方については、2本目以降の投稿料は一般・学生ともに6,000円を請求いたします。振込手数料は各自でご負担願います。
講演原稿執筆要領
講演原稿の書式・形式は、土木学会論文集のものに準じています。下記の作成例やサンプルファイルをご利用ください。講演原稿では、英文アブストラクトの記入は任意です。その他書式・形式についての詳細は土木学会論文集の原稿作成の手引き等をご参照ください。なお、「土木学会論文集D3(土木計画学), Vol.75-6」への投稿の際には英文アブストラクトは必要です。
サンプルファイル 和文(Word2000)/English(Word2000)
原稿作成例 和文(PDF)/English(PDF)
お問合せ先
土木計画学研究委員会大会運営小委員会(春大会担当:橋本,氏原,林)
E-mail:keikaku59@jsce.or.jp
活動記録:スマート・プランニング実践セミナー(@山形市)
スマート・プランニング実践セミナー(@山形市)
地方開催企画 第2弾「スマート・プランニング実践セミナー(@山形市)」
主催:土木計画学スマート・プランニング研究小委員会
日時:2018年11月14日(水)13:30-17:15
開催地:山形県山形市(中央公民館大会議室)
概要:
スマート・プランニングは,Wi-FiやGPSといったさまざまな交通関連データを活用し,そこから得られる「行動データ」をもとに,利用者の暮らしと事業者の事業活動を同時に計画するための(施設計画・交通計画・土地利用計画を包含する)新たな都市計画に向けた計画手法であり,今後の都市計画・まちづくりの切り札として大いに期待されています.今後,多くの都市で導入されていくには,各地の実務者がスマート・プランニングに関する様々なスキルを取得することが重要となります.本セミナーでは、主にコンサルタント職員等の実務者を対象として,甲府市の取組みを事例に,スマート・プランニングの調査計画を立案するためのスキル習得を目指します.
プログラム:次第
1. 開会挨拶 研究小委員会委員長 原田昇(東京大学)
2. 山形市取組み概要説明(山形市)[資料1] [資料2] [資料3] [資料4]
3. まちなか見学会
4. 基調講演
① 国土交通省都市局 都市計画調査室 [資料5]
② 羽藤英二氏(東京大学)[資料6]
③ 吉田朗氏(東北芸術工科大学)
5. ワークショップ [資料7] [資料8]
6. 講評・閉会挨拶(研究小委員会)
※資料4の駐車場配置図は2018.5現在のものであり最新版ではありません.
スマート・プランニング実践セミナー(@山形市)
スマート・プランニング実践セミナー(@山形市)
地⽅開催企画 第2弾「スマート・プランニング実践セミナー(@山形市)」
⼟⽊計画学スマート・プランニング研究⼩委員会では、地⽅開催企画の第2弾として「スマート・プランニング実践セミナー(@山形市)」を開催します。
参加を希望される⽅は、以下のフォームよりお気軽に申し込みください。【定員50名程度 ※先着順】
※事前申し込み制、〆切 11/2(金) 17:00
<申し込みフォーム>
宛先:hqt-smapla-seminar@ml.mlit.go.jp
件名:【スマート・プランニング実践セミナー申し込み】
本⽂:①参加者⽒名 ②所属
=============================================
地⽅開催企画 第2弾「スマート・プランニング実践セミナー(@山形市)」
主催:⼟⽊計画学スマート・プランニング研究⼩委員会
⽇時:2018年11⽉14⽇(⽔)13:30-17:15
開催地:山形県山形市(中央公民館大会議室)
参加費:無料
概要:
スマート・プランニングは、Wi-FiやGPSといったさまざまな交通関連データを活⽤し、そこから得られる「⾏動データ」をもとに、利⽤者の暮らしと事業者の事業活動を同時に計画するための(施設計画・交通計画・⼟地利⽤計画を包含する)新たな都市計画に向けた計画⼿法であり、今後の都市計画・まちづくりの切り札として⼤いに期待されています。今後、多くの都市で導⼊されていくには,各地の実務者がスマート・プランニングに関する様々なスキルを取得することが重要となります。本セミナーでは、主に自治体やコンサルタント職員等の実務者を対象として、山形市の取組みを事例に、スマート・プランニングの調査計画を⽴案するためのスキル習得を⽬指します。
プログラム:
・開会挨拶(研究⼩委員会委員長 原田昇氏(東京大学))
・山形市取組み概要説明(山形市)
・まちなか⾒学会
・基調講演
①国土交通省都市局
②羽藤英二氏(東京⼤学)
③吉田朗氏(東北芸術工科大学)
・ワークショップ
・講評・閉会挨拶(研究⼩委員会)
=============================================
#177 TSU Seminar: Optimization in Transport Systems
Date
2018年11月8日
Venue
東京工業大学大岡山キャンパス 緑が丘6号館1階緑が丘ホール
TSU Seminar: Optimization in Transport Systems
TSU Seminar: Optimization in Transport Systems
13:30-13:40 Opening address, Prof. Yasuo Asakura (Tokyo Tech)
13:40-15:00
Utility Maximising Spanning Trees: An Application to the Sydney Harbour Ferry System
Prof. Mike Bell, Institute of Transport and Logistics Studies (ITLS), University of Sydney Business School
15:00-15:30 Break
15:30-17:30
Considerations of Sustainability in Transportation – A Case for Multi-Objective Optimisation
Prof. Matthias Ehrgott, Dept. of Management Science, Lancaster University Management School
Prof. Judith Wang, School of Civil Eng. and Institute for Transport Studies, University of Leeds
スマート・プランニング講習会
スマート・プランニング講習会
スマート・プランニング講習会
#176 土木計画学研究委員会・EASTS-Japan 共催国際セミナー (International Seminar)
Date
2018年10月29日
Venue
東京理科大学理工学部土木工学科ゼミ室(4) (野田キャンパス5号館1F)
土木計画学研究委員会・EASTS-Japan 共催国際セミナー (International Seminar)
土木計画学研究委員会・EASTS-Japan 共催国際セミナー (International Seminar)
「KeeChoo Choi 教授を招いた特別セミナー」
日時: 2018 年 10 月 29 日(月)10:30 – 11:30
会場: 東京理科大学理工学部土木工学科ゼミ室(4) (野田キャンパス5号館1F)
http://www.tus.ac.jp/info/campus/noda.html
題目: Public Transportation Reform in Korea: Half Success and New Agendas
講演者:Prof. KeeChoo Choi, (韓国 Ajou University 交通工学科教授/韓国交通学会会長)
お問い合わせ:
東京理科大学土木工学科 寺部慎太郎
Shintaro TERABE (terabe@rs.noda.tus.ac.jp)
Tokyo University of Science, Dept. of Civil Engineering
第8回研究小委員会を開催しました.
第8回研究小委員会を開催しました.
日時:2018年10月23日(火)14:00-17:00
場所:神戸大学梅田インテリジェントラボラトリ
議事
・話題提供:小池淳司(神戸大学)
「権利と効率のストック効果」
・今後の予定ほか
#175 土地利用交通モデルに関する国際セミナー
Date
2018年9月28日
Venue
同志社大学寒梅館
土地利用交通モデルに関する国際セミナー
日時:2018年9月28日(金曜日)17~19時
会場:同志社大学寒梅館
Summary:
In this seminar, a Land Use Transport Integrated Micro-Simulation (LUTI-MS) model is explained by the developer team from Technical University of Munich, and its application to the SDGs assessment is discussed with participants.
SDGs can be assessed based on the observed indices corresponding to the targets. Those indices have inter-relationship each other that have to be taken into account for the effective policy making to achieve the SDGs. Furthermore, the SDGs agenda pledges to “leave no one behind”. Therefore analysis of interrelationship among the various targets as well as the wide variety of impacts on diverse individuals, not the average impact, will be needed.
Microsimulation can be a suitable approach for these analytical requirements.
In this seminar, we discuss the applicability of LUTI-MS model to the SDGs target assessment especially for the targets related with urban transportation.
Through this discussion, we intend to create useful knowledge for future SDGs research in the urban transport field.
Program:
17:00-17:10 Introduction (Kii, Kagawa University)
17:10-17:30 LUTI-MS model framework (Prof. Dr. Rolf Moeckel, TUM)
17:30-18:00 Components of LUTI-MS model: MatSim/MITO/SILO
(Dr. Moreno, Dr. Lorca, Mr. Kühnel, TUM)
18:00-18:20 SDGs targets and applicability of LUTI-MS model(Kii)
18:20-19:00 Discussion
#174 シュリンキングシティ日米研究交流セミナー名古屋2018
Date
2018年9月22日
Venue
名城大学ナゴヤドーム前キャンパス南館
シュリンキングシティ日米研究交流セミナー名古屋2018
趣旨:人口減少が都市に与える空間変容、コミュニティや生活の質など社会的持続性への影響、それらに対する政策、計画、デザインに関して、アメリカと日本の研究者から報告してもらう。これによって、両国の独自性・特性と共通性を理解するとともに、我が国の人口減少都市の将来、対応策について、理解を深める。
会場:名城大学ナゴヤドーム前キャンパス南館、名古屋市東区矢田南4-102-9
https://www.meijo-u.ac.jp/about/campus/dome.html
1. 9月22日(土)13:30~17:00
研究集会「日本とアメリカのシュリンキングシティ:実態・政策・マネジメント」
日本とアメリカのシュリンキングシティに関する報告を4名の研究者から行ってもらい、それを元に討議を行います。
報告者:
野澤 千絵(東洋大学教授)
黒瀬 武史(九州大学大学院准教授)
吉武 俊一郎(株式会社吉武都市総合研究所代表取締役)
矢吹 剣一(東京大学特任研究院、アーバンデザインセンター坂井ディレクター)
※上記の4名にディスカッサー(吉田 友彦・立命館大学教授、藤井 康幸・静岡文化芸術大学教授)が加わり議論をします。
会場:名城大学ナゴヤドーム前キャンパス南館DS401教室
言語:日本語
2. 9月23日(日)13:00~17:00
シンポジウム「シュリンキングシティを超えて―日本とアメリカの人口減少都市の実態・政策・対応―」
アメリカと日本からそれぞれ2名の専門家に参加してもらい、講演とパネルディスカッションを行います。
講演者:
アラン・マラーク(センター・フォーコミュニティ・プログレス/シニアフェロー)
テリー・シュワルツ(ケント州立大学クリーブランド・アーバン・デザイン・コラボレイティブ/ディレクター)
饗庭 伸(首都大学東京教授)
浅野 純一郎(豊橋技術科学大学大学院教授)
※パネルディスカッションでは、講演者4名にコーディネーター(服部 圭郎・龍谷大学教授)が加わり議論をします。
会場:名城大学ナゴヤドーム前キャンパス南館DSホール(DS101)
言語:英語(同時通訳付き)
※両日とも参加費無料
※資料準備の都合上、事前に下記より参加申し込み下さい。
https://goo.gl/forms/hFKxRDcuWOx3kwKI3
主催:シュリンキングシティ研究会(代表:海道 清信・名城大学都市情報学部教授)
後援:都市住宅学会、日本都市計画学会、計画行政学会、都市環境デザイン学会、日本建築学会東海支部、名城大学
※なお、本セミナーは、科研費基盤研究B「シュリンキングシティにおける空間変化と計画的対応策の日米欧比較研究と提案」助成研究活動の一環で実施し、大林財団、大幸財団の支援を得ています。
2018年度 航空交通システム研究会・見学会
2018年度 航空交通システム研究会・見学会
#7 土木と観光 in 北海道(2018年・年次学術講演会)
Date
2018年8月29日
Venue
北海道大学札幌キャンパス 情報科学研究棟 A13教室
土木と観光 in 北海道

平成30年度土木学会全国大会研究討論会
土木と観光 in 北海道
概要
大会:平成30年度土木学会全国大会
- 開会・趣旨説明:太田恒平(トラフィックブレイン 代表取締役社長)
- 話題提供1)観光ビッグデータ分析
太田恒平 - 話題提供2)鉄道
後藤靖子(九州旅客鉄道 取締役監査等委員) - 話題提供3)北海道のモビリティ・地域づくり
原文宏(北海道開発技術センター 理事) - 話題提供4)観光、交通の学識
清水哲夫(首都大学東京 都市環境科学研究科観光科学域 教授) - 討論
- 閉会挨拶
講演内容紹介
太田恒平(座長 トラフィックブレイン 代表取締役社長)
経路検索データ、訪日外国人の移動履歴データを用いた、地方創生・交通事業のための観光分析の事例や、公共交通オープンデータ整備の経験に基づく問題提起を行います。

後藤靖子(九州旅客鉄道 取締役監査等委員)新幹線による観光需要喚起、「ななつ星」などそれ自体が目的になるような観光列車など、九州における交通と観光の共栄についてご講演いただきます。

原文宏(北海道開発技術センター )シーニックバイウェイ・サイクルツーリズム・インフラツーリズムなど観光資源としての道路・土木と、北海道ならではの話題についてご講演いただきます。

清水哲夫(首都大学東京 都市環境科学研究科観光科学域 教授)
交通と観光の両分野にまたがる研究からの知見、観光統計データ整備の必要性や課題等についてご講演いただきます。
#173 The 11th International BinN Research Seminar
Date
2018年8月7日
Venue
東京大学 工学部14号館222教室, Faculty of Engineering Building #14, Room #222
The 11th International BinN Research Seminar
Seminar Program: the 11th International BinN Research Seminar
Date: 1500-1700, 7th of August, 2018
Venue: Faculty of Engineering Building No.14, room No.222, the University of Tokyo
Title: “Modeling and analysis of ride-sourcing systems and latest trend of transportation research”
Speaker: Yafeng Yin, Ph.D. Professor, Department of Civil and Environmental Engineering, University of Michigan, Ann Arbor
For an application: Eiji HATO, hato@bin.t.u-tokyo.ac.jp
#172 34th Tokyo Tech TSU Seminar: Resililence thinking in transport planning: Transport, air quality, health and resilience
Date
2018年8月1日
Venue
東京工業大学 緑ヶ丘1号館 2F 206-B号室, Room 206-B, 2F, Midorigaoka Build. No. 1, Ookayama Campus, Tokyo Institute of Technology
34th Tokyo Tech TSU Seminar: Resililence thinking in transport planning: Transport, air quality, health and resilience
Date: August 1st (Wed.) 2018
Time: 9:00 – 10:30 Venue: Room 206-B, 2nd floor of Midorigaoka Building No.1 at Ookayama Campus
Speaker: Prof. Judith Wang (the University of Leeds, UK)
Title: “Resilience tinking” in transport planning: Transport, air quality, health and resilience
Details are shown at,
http://www.transport-titech.jp/seminar_visitor.html
#171 The ROLE of zakat in the provision of housing for the POOR AND needy muslims IN MALAYSIA
Date
2018年7月30日
Venue
京都大学桂キャンパスC1棟 312会議室
The ROLE of zakat in the provision of housing for the POOR AND needy muslims IN MALAYSIA
2018年7月30日(月)16:00-18:00
Asst. Prof. Dr. Sharina Farihah Hasan
(Department of Quantity Surveying, Kulliyyah of Architecture and Environmental Design, International Islamic University Malaysia)
The ROLE of zakat in the provision of housing for the POOR AND needy muslims IN MALAYSIA
Zakat is one of the key instruments that address the socio-economic well-beings of needy Muslims. In terms of approach zakat has specific style as prescribed in the Al-Quran and Al-Hadiths. It is observed that the most critical problem currently facing the Muslims in Malaysia is the lack of access to decent and affordable housing for the low and middle income families especially those living in the urban areas. Zakat institutions in Malaysia have been playing their roles in assisting the poor and needy Muslims through the various assistance schemes. Specific housing assistance includes building new house, rental assistance, repairs, deposit for new house, etc.
京都大学桂キャンパスC1棟 312会議室
#170 東京大学・フランス国立土木学校(ENPC)共同国際セミナー
Date
2018年6月26日
Venue
東京大学本郷キャンパス工学部3号館32番教室(東京都文京区本郷7-3-1)
東京大学・フランス国立土木学校(ENPC)共同国際セミナー
【東京大学・フランス国立土木学校(ENPC)共同国際セミナー】
・日時:2018年6月26日(火)9:30 – 12:00
・場所:東京大学本郷キャンパス工学部3号館32番教室(東京都文京区本郷7-3-1)
・スケジュール(予定)
9:30-9:35am:開会の挨拶(Prof. Eiji HATO, Head of Department of Civil Engineering, The University of Tokyo)
セッション1:「インフラとファイナンス」
9:35-10:10am
Prof. Michel LYONNET du MOUTIER (Professor at Ecole Nationale des Ponts et Chaussées and Professor Emeritus at University of Paris)
“Financial Innovation in Mobility: Project Finance and Toll Motorways in Europe”
10:10-10:45am
Prof. Hironori KATO (Professor at Department of Civil Engineering, The University of Tokyo)
“Infrastructure Finance in Japan”
セッション2:「イノベーションマネジメントと価値創造」
10:45-11:20am
Prof. Dominique JACQUET (Professor of Financial Strategy, Ecole Nationale des Ponts et Chaussées)
“Value Migration and Innovation Capabilities Transfer in the Car Industry”
11:20-11:55am
Prof. Gento MOGI (Associate Professor at Department of Technology Management for Innovation, The University of Tokyo)
“BEV or FCV; consequence of the dissemination of either personal mobility”
11:55-12:00am:閉会の挨拶(TBD)
・言語:英語のみ
・参加費:無料
スマート・プランニング通信 Vol.3
スマート・プランニング通信 Vol.3
第57回土木計画学研究発表会・春大会@東京工業大学にて、 スペシャルセッション「スマート・プランニングの活用と実践」を開催しました。
詳しくはこちらのPDFをご覧下さい。
第57回土木計画学研究発表会(春大会)企画セッション「航空交通システムの進化と分析技術(1)(2)」
第57回土木計画学研究発表会(春大会)企画セッション「航空交通システムの進化と分析技術(1)(2)」
第57回土木計画学研究発表会・春大会
第57回土木計画学研究発表会・春大会
第57回土木計画学研究発表会(春大会)の概要
土木計画学研究委員会は下記の概要で第57回土木計画学研究発表会(春大会)を開催いたします.
実施期日 2018年6月9日(土)・10日(日)
開催場所 東京工業大学(大岡山キャンパス)
実施要領 (PDFファイル)
発表確定プログラム(2018年6月1日更新,会場名入り)
※やむを得ない辞退等により暫定プログラムからの変更がございます。最新の発表時間帯について、必ずご確認をお願いいたします。
(※6/1追記:2日目第1~2セッション、第5会場OS52に一部変更があります。)
●企画論文部門・スペシャルセッション(SS)部門
企画論文部門は、オーガナイザーを公募し提案された企画テーマでの論文公募を行い、口頭発表またはポスター形式での発表を行うものです。SS部門は、原則として既存の研究小委員会が主催して、研究討議・意見交換を中心にセッションを構成するもので、本大会では12 セッションを限度とします。
●スケジュール
○企画論文部門
発表希望者の論文題目・概要の登録 2017年12月8日(金)~2018年2月2日(金)【終了しました】
・企画論文部門のセッション一覧はこちら
オーガナイザーによる採否決定期間 2018年2月16日(金)~2018年3月9日(金) 【終了しました】
論文投稿 2018年4月27日(金)正午まで ○スペシャルセッション(SS) 部門
発表者の決定 2018年3月9日(金)まで
(2018年4月27日(金)正午締切)
発表の要領
口頭発表セッションでは,聴講者用にレジュメ50部をご用意の上,各セッション会場にて配布して下さい.
(1)講演時間
セッションの時間は,発表件数に応じて異なります.発表時間・発表方法・セッション運営についてはオーガナイザーの指示に従ってください.
(2)講演打ち合わせ
セッション開始10分前に各発表会場に集合し,オーガナイザーとセッションの進め方に関する打ち合わせを行って下さい.
(3)発表時の使用機器について
各発表会場には,液晶プロジェクターとディスプレイケーブル(RGB)を準備します(OHP,スライドは使用できません).なお,ノートPCは各自で持参して下さい. 各発表会場に設置されている液晶プロジェクタヘの接続は,各発表者の責任にて行って下さい.セッションが円滑に進行するようにご準備のご協力をお願い致します.
(4)ポスターセッション
ポスター用のパネル(A0縦),貼り付け用文具につきましては開催校より提供する予定です.
参加登録
参加登録(発表者以外の方):次の土木学会行事参加申し込みホームページより,ご登録ください.
聴講参加者の受付は4月20日(金)から,締切は5月29日(火),参加費は一般6,000円,学生3,000円です.なお,発表者(企画部門)は自動的に登録されていますので,あらためての参加登録は不要です.オーガナイザー,スペシャルセッションの発表者の方は,参加登録が必要です.
以下の参加申込書をダウンロードし,必要事項を記入して土木学会宛にお送りいただく(FAX/郵送)ことでも,参加登録は可能です.締切および参加費はホームページからの申し込みの場合と同じです.
参加申込書(PDF)
事前参加申し込みに関する注意事項
・参加申し込みの締切は5月29日(火)となっております.申し込みをされた方には,発表会前までに,「参加券」,「請求書」等をお送りする予定です.
・本行事の参加費支払いは事前入金制となっておりますので,申込みフォームの「当日払い」,「現金持参」は選択しないでください.
・締切日以降の事前受付はいたしません.締切日を過ぎてからのお申し込みは,行事当日に会場にて受付いたします.
・お申し込み後,やむを得ずキャンセルされる場合は,必ず開催日の1週間前までに研究事業課宛にご連絡ください.ご連絡がない場合は,参加費を徴収させて頂きますので予めご了承ください.
●土木学会論文集D3(土木計画学)特集号への投稿資格について
企画論文部門へ期限までに投稿された論文のうち、土木学会論文集D3の投稿の手引に従った形式(ただし英文要旨は任意)で執筆され、かつ2ページ以上の分量である論文については、土木計画学研究・講演集に掲載される論文として見なされ、土木学会論文集D3(土木計画学)特集号(以下、特集号と表記する)への投稿資格が得られます。論文タイトルと要旨のみで構成されており本文が記載されていないなど、定められた形式に従っていない原稿は,春大会運営小委員会の判断により,土木計画学研究・概要集に掲載されません。その場合、土木学会論文集D3(土木計画学)特集号への投稿資格は与えられませんのでご注意ください。ただし、特集号への投稿資格を満たさない投稿論文であっても、企画論文部門セッションで発表することは可能です。
また、論文投稿されたにも関わらず実際には春大会にて発表されていない論文、およびSS部門へ投稿された論文についても、特集号への投稿資格はありません。詳しくは、計画学ホームページをご覧下さい。
https://jsce-ip.org/wp-content/uploads/2019/03/journal-s-tebiki-2.pdf
●論文投稿料について
企画部門の発表会投稿料(参加費を含む)は,講演1件につき一般12,000円,学生9,000円です.SS部門は,1セッションにつき,10,000円(参加費別)です.なお,オーガナイザーによる採否決定(2018年3月9日(金))後のキャンセルは,一切認められません.発表(講演)を辞退されても,発表会投稿料として料金を請求させて頂きますので十分にご注意ください.
●春大会運営に関する問合せ先
土木計画学大会運営小委員会 春大会部会
e-mail: keikaku57@jsce.or.jp
企画セッション・第7回委員会
企画セッション・第7回委員会
「OS37:健康まちづくりに向けた実践的アプローチ」
会場:第1会場(W321)
講演件数:9件 (5件+4件)
第7回研究小委員会を開催しました.
第7回研究小委員会を開催しました.
日時:2018年6月9日(月) 16:45-18:30
場所:東京工業大学 W831会議室(西8号館)
議事
・研究小委員会での発表資料アーカイブについて
・ERSAスペシャルセッション,2018年8月28日-31日,於:アイルランド, Corkについて
・今後の活動予定(論文集特集企画,書籍出版計画,等)
スマート・プランニングスペシャルセッション@土木計画学春大会 ~スマート・プランニングの活用と実践~
スマート・プランニングスペシャルセッション@土木計画学春大会 ~スマート・プランニングの活用と実践~
#6 宇沢弘文の社会的共通資本を再考する
Date
2018年5月28日
Venue
土木学会講堂
宇沢弘文の社会的共通資本を再考する
企画趣旨
宇沢弘文氏(1928-2014)は、数学者、経済学者として様々な分野で影響を与えてきた。特に、土木分野においては、「自動車の社会的費用」、「地球温暖化の経済学」、そして「社会的共通資本」の著作はその時代の政策研究、論議に大きな影響を与えた。
このシンポジウムでは、「宇沢弘文の研究」の第一人者の帝京大学の小島寛之教授を迎え、宇沢弘文の思想と理論について解説していただく。また、藤井聡教授、小池淳司教授から公共政策論、土木計画論の立場から社会的共通資本に関連する話題を提供していただく。
さらに、基調講演、話題提供を受けて、全体討議をすることにより、「宇沢弘文の社会的共通資本」を再考するものである。
〇シンポジウム開催の趣旨 大石久和(土木学会会長) 13:00-13:30
<基調講演>
〇「宇沢弘文の思想と理論」 小島寛之(帝京大学教授) 13:30-14:30
休憩 14:30-14:40
〇「社会的共通資本と土木」 藤井聡(京都大学教授) 14:40-15:20
<講演2>
〇「公共事業評価と社会的共通資本」小池淳司(神戸大学教授) 15:20-16:00<全体討論> 16:00-16:50
進行:藤井聡(京都大学教授)
(小島教授、大石会長、小池教授も登壇)
<閉会の挨拶> 16:50-17:00
〇占部まり(宇沢国際学館)(予定)
■問い合わせ先
公益社団法人 土木学会 研究事業課
林 淳二
E-mail j-hayashi@jsce.or.jp
講演資料
〇シンポジウム開催の趣旨 大石久和(土木学会会長) 13:00-13:30
<基調講演>
〇「宇沢弘文の思想と理論」 小島寛之(帝京大学教授) 13:30-14:30
<講演1>
〇「社会的共通資本と土木」 藤井聡(京都大学教授) 14:40-15:20
<講演2>
〇「公共事業評価と社会的共通資本」小池淳司(神戸大学教授) 15:20-16:00
#169 Special Seminar at The University of Tokyo: Analyzing the influence of Aberrant Driving Behaviors on traffic safety and efficiency
Date
2018年5月14日
Venue
Seminar Room of International Project Lab (Third floor of Engineering Building No.11, Hongo Campus)
Special Seminar at The University of Tokyo: Analyzing the influence of Aberrant Driving Behaviors on traffic safety and efficiency
1. Presenter: Prof. SHI Jing, Dr. E., PE, APEC E, Department of Civil Engineering, Tsinghua University, Beijing China
2. Theme: Analyzing the influence of Aberrant Driving Behaviors on traffic safety and efficiency
3. Date:1:30pm to 3:00pm, May 14 (Mon) 2018
4. Venue:Seminar Room of International Project Lab (Third floor of Engineering Building No.11, Hongo Campus)
5. Abstract: China has not yet become a mature automobile society, although its automobile industry is developing rapidly. The specific performance is the universal existence of aberrant driving behaviors. Aberrant driving behavior refers to the drivers’ behavior in driving which violates other traffic participants’ benefit, endangers the safety of themselves or others, including driving traffic violations and usually called bad habits in traffic. Aberrant Driving Behaviors are prevalent in China but have not attracted as much attention from researchers. Traffic accidents may be caused by frequently occurred aberrant driving behaviors. However, in the research, we found that aberrant driving behaviors not only threaten the traffic safety, but also may reduce traffic efficiency. The presentation will introduce the latest quantitative analysis methods and relative research results of aberrant driving behaviors.
57th Spring Conference, 2018
Date
June 9th – June 10th, 2018
Venue
@ Tokyo Institute of Technology
57th JSCE Spring Conference Overview
The council of JSCE conference will hold the 57th JSCE conference (spring session) according to the overview described below.
Date: June 9th (Saturday), 10th (Sunday) 2018
Location: Tokyo Institute of Technology (Ookayama Campus)
- Project development department. Special session (SS) department.
The project development department will invite the organizer who will set the project theme, under which the theses will be collected from the public, and they will give oral presentations or presentations using posters. The SS department will be sponsored by the existing subcommittee as a rule, and hold a session centered around research discussions/exchange of opinions, bringing it to a total of 12 sessions at the conference. Furthermore, there will be a maximum of 10 parallel sessions by the project development department and SS department.
- Schedule
○Project Development Department
Registration of overview and thesis subject of prospective presenters 12/8 2017 (Friday) ~2018 2/2 (Friday) [Finished]
・List of project development department session here
・Project development thesis submission page here
Acceptance period by the organizer 2/16 2018 (Friday) ~3/9 2018 (Friday)
Thesis submission until 4/27 2018 (Friday) noon
○Special session (SS) department
Decision of presenter until 3/9 2018 (Friday)
- Procedure of project development department hereafter
Prospective presenter:
Step 1. Through HP (http://www.jsce-ip.com/conference/index.html?id=27) specify the first session of choice and submit thesis presentation. Thereafter, the result of thesis presentation acceptance will be announced from the office to the prospective presenters.
Step 2. In the case of having the presentation selected, submit the thesis via the Web by the deadline.
Please note that depending on the presentation acceptance, there is a possibility that the applicant will be asked to cancel the presentation registration or give a presentation as other than the first preferred session.
Organizer:
Through the Web (the URL, password, etc. will be sent via mail thereafter) the presentation overview will be checked and the presentation acceptance will be decided on. The acceptance will take place from 2/16 (Friday) to 3/9 (Friday) 17:00.
※Number of sessions for themes concerning the project development thesis department will be decided at the spring session subcommittee.
Where there are many presentation theses, schedule will be managed through the use of such things as poster sessions. The requirement for setting up a session is that there are more than 5 presentation theses, and when the number of presentation applicants per thesis is under 5, that theme will as a rule be abolished. However, when the organizer of another project development thesis department adjusts and joins together themes, it shall not be obstructed.
- JSCE thesis collection D3 (infrastructure planning and management) On the submission qualification for special issue
Out of the theses that were submitted by the deadline to the project development department, it is to be written accordingly to the format following the submission rules of JSCE thesis collection D3 (English abstract is optional), and for theses exceeding 2 pages will be regarded as theses to be published through JSCE research and lecture collection, and will be qualified to submit to JSCE thesis collection D3 (JSCE) special issue (referred henceforth as special issue). Drafts that are not written in accordance with the stipulated format, such as drafts submitted only with thesis title and abstract and without the main body, will be judged by the spring conference subcommittee to not be included in the JSCE research and lecture collection. Please be warned that in such cases, qualification for submission to the JSCE thesis collection D3 (JSCE) special issue will not be given. However, even if the submitted thesis does not qualify for submission to the special issue, it is still possible to present at the the project development department session. Furthermore, theses not presented at the spring conference in spite of having been submitted, and theses submitted to the SS department, will not be qualified for submission to the special issue. For more details please visit the JSCE homepage.
http://www.jsce.or.jp/committee/ip/monograph/file/journal-s-tebiki.pdf
On thesis submission fee
The submission fee for the project development conference (including participation fee) is 12,000 yen per 1 lecture, 9,000 yen for students. 10,000 yen (not including participation fee) per session for SS department. Cancellation after the acceptance decision by the organizer (3/9 2018 (friday)) will not be allowed. Even in the case of declining to present (lecture), you will be charged the presentation submission fee.
Contact regarding spring conference
JSCE Subcommittee Spring Conference
e-mail: keikaku57@jsce.or.jp
#95 土木の『領域』再考と社会的実効性ある学会活動の展開 -土木計画学の視点から-
Date
2018年4月18日
Venue
土木学会講堂(〒160-0004 東京都新宿区四谷1丁目 外濠公園内)
土木の『領域』再考と社会的実効性ある学会活動の展開 -土木計画学の視点から-
#94 都市間旅客交通ワンデーセミナー -都市間旅客交通の基礎的特徴とデータ-
Date
2018年3月30日
Venue
日本大学理工学部駿河台キャンパス1号館4階141教室
都市間旅客交通ワンデーセミナー -都市間旅客交通の基礎的特徴とデータ-
■タイトル:都市間旅客交通ワンデーセミナー -都市間旅客交通の基礎的特徴とデータ-
■開催日時: 2018/03/30(金) 13:00 – 18:00
■場所:日本大学理工学部駿河台キャンパス1号館4階141教室
https://www.cst.nihon-u.ac.jp/campus/surugadai/
■定員:150名
■参加費の有無:無料
■開催主旨:
都市間の長距離旅客交通には,交通発生の非日常性・大きな季節変動・旅客が持つ情報の不完備性・需要薄によるサービス供給制約・複数のサービスの複合利用による複雑なネットワーク効果など,長距離・低頻度の旅行であることに起因する特徴が多く存在する.しかし,これらの特徴によって,都市間旅客交通の全体像を把握するデータを取得することは,非常に高コストであった.
一方で,近年活用が可能となったWebアンケートや携帯電話位置情報データであれば,近年は膨大なサンプルの情報を比較的容易に得ることができ,都市間旅客交通についてもこれまで得られなかったデータを入手することが可能となってきた.それに伴い,新たな分析方法論が必要となるとともに,これまでと異なる視点からネットワーク・サービスの設計が可能となりつつあると期待される.
そこで,本セミナーでは,都市間旅客交通の基礎的な特徴を再整理(第一部)したうえで,新しいデータの活用に取り組んだ研究を含む最新の研究成果と幹線旅客交通に関する実務的な課題を共有する(第二部)ことによって,政策課題の 発掘と研究課題の深化を図るものである.とくに,第一部ではこれから都市間旅客交通に関連する研究に取り組もうとする学生の参加を,第二部には都市間旅客交通に関連する実務に関わる方々が参加し討議に参加いただくことを期待します.
■プログラム:
第一部(13:00 – 15:00): 都市間旅客交通の基礎的な特徴
> 奥村誠(東北大学) 「仮題:都市間旅客交通サービス設計の基礎」
> 山口裕通(金沢大学) 「仮題:日本の都市間旅客交通需要の時系列面の特徴」
第二部(15:30 – 18:30): 我が国の都市間旅客交通データのフロンティアと,実務への展開
> 塚井誠人(広島大学) 「仮題:Web調査による都市間旅行データの特徴」
> 福田大輔・鈴木新(東京工業大学) 「仮題:複数データの融合による日別・旅行目的別都市間旅客流動量推計」
> ほか,全国幹線旅客純流動調査など,都市間旅客交通データに関連する内容で数件を予定
■参加登録
https://goo.gl/forms/k2nAzUzCGn8YEjzv2
■問い合わせ
山口裕通(金沢大学)
hyamaguchi@se.kanazawa-u.ac.jp
#93 地域アセットマネジメントの実装へ向けて ー地域ニーズに応じたインフラ管理とはー
Date
2018年3月29日
Venue
土木学会講堂(〒160-0004 東京都新宿区四谷1丁目 外濠公園内)
地域アセットマネジメントの実装へ向けて ー地域ニーズに応じたインフラ管理とはー
【開催案内】土木計画学ワンデイセミナー NO.93 地域アセットマネジメントの実装へ向けて ー地域ニーズに応じたインフラ管理とはー
【開催案内】土木計画学ワンデイセミナー NO.93 地域アセットマネジメントの実装へ向けて ー地域ニーズに応じたインフラ管理とはー
日時
2018年3月29日
場所
土木学会講堂(〒160-0004 東京都新宿区四谷1丁目 外濠公園内)
#168 Mini-Workshop: Big Data and Transportation Dynamics
Date
2018年3月19日
Venue
TKPガーデンシティ御茶ノ水のカンファレンスルーム2D
Mini-Workshop: Big Data and Transportation Dynamics
場所:TKPガーデンシティ御茶ノ水のカンファレンスルーム2D
地図:
詳細:
申込URL:
※席が限られています.
13:30 – 14:00 Opening (Introduction of the project)
Dr Takahiko Kusakabe
Assistant Professor
Spatial Infromation Science Center, the Universiy of Tokyo
14:00 – 14:30 “Application of Activity-Besed Simulator MATSIM for
Tokyo Metrpolitan Area”
Dr Takuma Mitani
Project Assistant Professor
Spatial Infromation Science Center, the Universiy of Tokyo
14:30 – 15:00 “Day-to-day dynamics of ridesharing system based on user
rational behavior”.
Dr Phathinan Thaithatkul
Project Researcher
Spatial Infromation Science Center, the Universiy of Tokyo
15:05 – 15:30 “Intentional Removals of Nodes and Links to Avoid Gridlock”
Mr Kashin Sugishita
Doctoral candidate
Tokyo Institute of Technology
15:30 – 15:55 “Departure Time and Mode Choice in Urban Cities with
Bottleneck Congestion and Crowding Cost”
Mr. Takao Dantsuji
Doctoral candidate
Tokyo Institute of Technology
15:55 – 16:30 “Considering Overtaking and Passenger Boarding Behaviour
in Bus Holding to Reduce Bus Bunching”
Dr Ronghui Liu
Associate Professor & Director of International Activities
Institute for Transport Studies, University of Leeds
#164 International Seminar on Integration of Spatial Computable General Equilibrium and Transport Modelling
Date
2018年3月14日
Venue
神戸大学ブリュッセルオフィス
International Seminar on Integration of Spatial Computable General Equilibrium and Transport Modelling
ベルギーにて海外研究者との共同セミナーを開催しました
ベルギーにて海外研究者との共同セミナーを開催しました
INTERNATIONAL SEMINAR ON
INTEGRATION OF SPATIAL COMPUTABLE GENERAL EQUILIBRIUM
AND TRANSPORT MODELLING
– Economic modeling and application for urban policy –
Seminar Outline
Date March-14th, 2018
Venue Kobe University Brussels European Centre (KUBEC),
(Boulevard de la Plaine 5 Pleinlaan, 5th floor Bruxelles 1050 Brussel)
Host Kobe University & TU Delft
Chairs Professor Atsushi KOIKE, Kobe University
Professor Lori Tavasszy, TU Delft
Conference Program
March 14th
9:30-9:40 Opening Address
Atsushi Koike (Kobe University)
9:45-10:45 Session 1
Hajime Seya (Kobe University), Hedonic approach for preference measurement in land use planning
Sander Onstein (TU Delft): Factors determining spatial logistics decisions
Atsushi Koike (Kobe University): Ethics for numerical analysis
10:45-11:15 Coffee Break
11:15-12:15 Session 2
Tomoki Ishikura (Tokyo Metropolitan University): Impact of volcanic ash fall to commodity flow and freight transport network: WIP report
Gonçalo Correia (TU Delft), Agent based model for land use-transport interaction
12:15-13:15 Lunch Break
13:15-14:15 Session 3
Christophe Heyndrickx (Transport & Mobility Leuven): Urban Spatial General Equilibrium Model
Toshimori Otazawa (Kobe University): Cause and effect analysis of transport investments
Lori Tavasszy (TU Delft): Logistics sprawl of the Randstad region – some measurements
14:15-14:30 Closing Remarks
Lori Tavasszy (TU Delft)
Atsushi Koike (Kobe University)
March 15th
9:00-12:00 Academic meeting for future cooperation
「健都」健康・医療のまちづくりシンポジウム
「健都」健康・医療のまちづくりシンポジウム
【「健都」健康・医療のまちづくりシンポジウム(ご案内)】
北大阪健康医療都市(以下「健都」という。)では、2018年春には健康増進広場が、同年秋には市立吹田市民病院、駅前複合商業施設がオープンする予定であり、2019年夏には国立循環器病研究センターのオープンが控えるなど、各施設が順次開設され、いよいよ「健都」のまちが動き始めようとしています。
今後「健都」においては、「健康づくり」と「医療イノベーション」の2つの観点を結び付けていくことで、新たなライフスタイルの提案、地域の活力創出などの好循環につなげていく必要があり、「健都」においてどのような好循環につなげていくかについて、このシンポジウムで模索します。
■日 時:2018年3月10日(土)13:00-15:40
■場 所:関西大学千里山キャンパス「ソシオAVホール」
(大阪府吹田市山手町3-3-35 阪急千里線「関大前」駅下車すぐ)
■主 催:国立循環器病研究センター・吹田市・摂津市・関西大学
■後援(予定):近畿厚生局・近畿経済産業局・大阪府・大阪商工会議所・吹田商工会議所・摂津市商工会
■参加費:無料
■定 員:400名
■プログラム:
*パネルディスカッション
コーディネーター
関西大学 環境都市工学部教授 北詰 恵一
パネリスト
国立循環器病研究センター 予防健診部長 宮本 恵宏
医薬基盤・健康・栄養研究所 身体活動研究部部長 宮地 元彦
吹田市 健康医療審議監 舟津 謙一
NPO法人摂津まるごとプロジェクト 理事長 新田 昌恵
パナソニック株式会社 関西渉外室部長 増森 毅
関西大学 副学長 吉田 宗弘
*特別講演
講演者
近畿経済産業局長 森 清
■詳細・申込:http://www.kansai-u.ac.jp/renkei/event/detail.php?i=364
「健都」健康・医療のまちづくりシンポジウム
「健都」健康・医療のまちづくりシンポジウム
#165 Dynamic Risk Management of Transport Networks: Theory and Observation
Date
2018年3月7日
Venue
神戸大学梅田インテリジェントラボラトリ Umeda intelligent laboratory of Kobe University
Dynamic Risk Management of Transport Networks: Theory and Observation
・開催場所:「神戸大学梅田インテリジェントラボラトリ」
(梅田ゲートタワー 8階
(8th floor of Umeda gate tower, see
13:00-13:15 Opening (introduction to the project),
by Masao Kuwahara, Tohoku University
13:15-14:15 Challenges and opportunities in static and dynamic traffic assignment,
by Hillel Bar-gera, Ben-Gurion University of the Negev (Israel)
14:15-15:00 Group decision modelling approach to analyze response behavior of household travel survey,
by Takuya Maruyama, Kumamoto University
15:00-15:20 (break)
15:20-15:50 Continuum car-following model for capacity drop at sag and tunnel bottlenecks,
by Kentaro Wada, The University of Tokyo
15:50-16:20 Interactive probe person survey system,
by Takahiko Kusakabe, The University of Tokyo
16:20-16:40 Departure time choice equilibrium model considering the destination characteristics,
by Katsuya Sakai, Kobe University
16:40-17:00 An optimization approach for dynamic strategy of evacuation and picking-up behavior to respond to tsunami risk,
by Junji Urata, Kobe University
#166 Unsteady behavior modelling in damaged networks
Date
2018年2月28日
Venue
Seminar Room A, 4th Floor Building 1 at UT, Hongo Campus
Unsteady behavior modelling in damaged networks
Unsteady behavior modelling in damaged networks
2018.2.28-3.2
Program Committee:
Eiji Hato (University of Tokyo) , Schlomo Bekhor (Israel Technion),
Tomer Toledo (Israel Technion), Junji Urata (Kobe University),
Hideki Yaginuma (Tokyo Science University),
Keiichiro Hayaka
wa (TOYOTA Central Research Lab.) ,
Kayoko Hara (Nissan Motor Co.),
Giancarlos Troncoso Parady (University of Tokyo)
スマート・プランニング通信 Vol.2
スマート・プランニング通信 Vol.2
地方開催企画第1弾として,スマート・プランニング実践セミナー(@甲府市)を開催しました.
詳しくはこちらのPDFをご覧下さい。
#167 Inferring Travel Patterns and Social Life from Mobile Phone Data. Review of Case Studies and Future Challenges
Date
2018年2月21日
Venue
京都大学桂キャンパスCクラスター C1-312(C1棟会議室3)
Inferring Travel Patterns and Social Life from Mobile Phone Data. Review of Case Studies and Future Challenges
スマート・プランニング実践セミナー(@甲府市)
スマート・プランニング実践セミナー(@甲府市)
地方開催企画 第1弾「スマート・プランニング実践セミナー(@甲府市)」
①「都市交通調査の高度化について」(国土交通省都市局 都市計画調査室)[資料3]
②「さあ山梨でスマプラを始めよう」佐々木邦明(山梨大学)[資料4]
#91 「国土・県土整備の技術と実践」 -人口減少・交流時代に真に必要なインフラ整備を考える- 九州会場
Date
2018年2月13日
Venue
第三博多偕成ビル 4階会議室(福岡市博多区博多駅南1-3-6)
「国土・県土整備の技術と実践」 -人口減少・交流時代に真に必要なインフラ整備を考える- 九州会場
土木計画学セミナー 「国土・県土整備の技術と実践」
-人口減少・交流時代に真に必要なインフラ整備を考える- 九州会場(土木学会CPDプログラム)
日 時 2018年2月13日(火)13:00~17:05
主 催 公益社団法人 土木学会(担当:土木計画学研究委員会)
後援 国土交通省九州地方整備局
場 所 第三博多偕成ビル 4階会議室(http://www.t-kaisei.co.jp/property/hakata_rental_3.html)
定 員 140名(申込者多数の場合は先着順)
参加費 無料(事前申込制)
セミナーの趣旨
自治体等の計画においては,多面的なストック効果を踏まえた公共インフラの包括的な社会的意義についての理解が不十分であったり、B/Cに代表される各種の評価技術についての理解が不十分であったりすることから、適切なインフラの整備や運用が阻害されるケースがしばしば見受けられます.こうした問題の改善を企図し、インフラ政策についての基礎的な考え方や知識をセミナー形式で学ぶ機会を、それらを専門に扱う土木学会(土木計画学)から講師を派遣する形で提供するとともに,九州地域におけるインフラ政策・地域政策の方向性や具体のインフラ整備事例について地元の講師からご講演をいただきます.本セミナーを通して,基礎的な評価技術の適正な理解に加えて、真に必要な土木・公共事業とは何かなどについて考え,より深い理解につながるきっかけとなることを企図しています.
セミナーの主な対象者
・整備局関係機関、県、基礎自治体等の主要自治体のインフラ関係部局の担当者,事業評価部局の担当者,コンサルタントなど,土木計画にかかわる実務の方を主な対象としていますが、研究者の皆様やこれから社会人になる学生の皆様のご参加も歓迎いたします。
講習会内容 プログラム
1.開会あいさつ:13:00~13:05 (12:40開場)
2.講義:13:05~16:00
1)インフラ政策の総論:京都大学教授 藤井聡
2)費用便益分析とストック効果:神戸大学教授 小池淳司
3)エビデンスに基づく政策形成支援:山梨大学教授 佐々木邦明
3.九州におけるインフラ整備について:16:00~16:50 福岡大学教授 辰巳浩
4.全体の質疑応答16:50~17:00
5.閉会挨拶:17:00~17:05
※セミナー終了後,会場にて17:20まで,関連書籍の販売がございます.
申込方法 土木学会ホームページ「本部主催行事の参加申込」にてお申込み下さい.
土木学会ウェブサイト(http://www.jsce.or.jp/event/active/information.asp)
申込締切日 2018年2月9日(金)
*本セミナーは「土木学会継続教育(CPD)プログラム」に 認定されています(4.0単位,JSCE17-1302)
#92 大災害に道路ネットワークはどう備えるか? ~道路防災機能評価の新たな展開?~
Date
2018年2月5日
Venue
香川県高松市 高松サンポート合同庁舎低層棟アイホール 2F
大災害に道路ネットワークはどう備えるか? ~道路防災機能評価の新たな展開?~
#90 「国土・県土整備の技術と実践」 -人口減少・交流時代に真に必要なインフラ整備を考える- 東北会場
Date
2018年1月31日
Venue
TKPガーデンシティ仙台勾当台 ホール2(仙台市青葉区国分町3丁目6番1号 仙台パークビル)
「国土・県土整備の技術と実践」 -人口減少・交流時代に真に必要なインフラ整備を考える- 東北会場
第6回研究小委員会を開催しました.
第6回研究小委員会を開催しました.
第6回 応用一般均衡分析と交通分析の統合に関する研究小委員会
日時:2018年1月29日(月) 16:00-18:30
場所:首都大学東京 秋葉原サテライトキャンパス
議事
1.研究小委員会での発表資料アーカイブについての諸連絡および活動計画に関する諸連絡
2.話題提供:東山洋平 氏 (日本大学 博士後期課程)
3.次回の日程調整
#89 「国土・県土整備の技術と実践」 -人口減少・交流時代に真に必要なインフラ整備を考える- 中部会場
Date
2018年1月23日
Venue
ウインクあいち 1204室(名古屋市中村区名駅4丁目4-38)
「国土・県土整備の技術と実践」 -人口減少・交流時代に真に必要なインフラ整備を考える- 中部会場
#163 Roles of Universities and Academic Societies in Infrastructure Engineering in Vietnam and Japan
Date
2018年1月20日
Venue
Room 415 – 416, My Dinh Campus of Vietnam Japan University
Roles of Universities and Academic Societies in Infrastructure Engineering in Vietnam and Japan
“Roles of Universities and Academic Societies in Infrastructure Engineering in Vietnam and Japan”
Organized by Vietnam Japan University (VJU)
Supported by Japan Society of Civil Engineers (JSCE), Vietnam Construction Association, and Vietnam Bridge and Road Association (VIBRA)
- Objectives
– To discuss the roles of universities and academic societies in infrastructure engineering in Vietnam and Japan among Vietnamese professional associations, universities, and private firms together with Japan Society of Civil Engineers (JSCE) and Vietnam Japan University (VJU);
– To explore future collaboration and to expand human network between Vietnam and Japan on academic research and education in the field ofinfrastructure engineering; and
– To examine the expected role of VJU in the field of infrastructure engineering.
- Time and venue
– Time: 08:00am -1:00pm, Jan. 20th (Sat.), 2018;
– Venue: Room 415 – 416, My Dinh Campus of Vietnam Japan University (Luu Huu Phuoc Street, My Dinh 1, Hanoi).
- Agenda
08:00 – 08:20 Introduction of Vietnam Japan University (VJU)
08:20 – 08:40 Academic training & research activities of Master Program for Infrastructure Engineering (MIE), VJU
08:40 – 09:20 Activities of Japan Society of Civil Engineers (JSCE) and its Hanoi Center
09:20 – 09:40 Coffee-break
09:40 – 10:20 Activities of two associations in the field of Infrastructure Engineering in Vietnam
10:20 – 11:00 Expectations from business communities to universities and associations
11:00 – 12:00 Panel Discussion
12:00 – 13:00 Lunch
#87 「3次元モデルが変えるまちづくりの計画論」
Date
2018年1月12日
Venue
弘済会館(東京都千代田区 麹町 5−1) 4階 楓
「3次元モデルが変えるまちづくりの計画論」
第87回ワンデイセミナー「3次元モデルが変えるまちづくりの計画論」
・主催:土木計画学研究委員会 土木計画分野における3次元モデルの活用に関する研究小委員会
・日時:平成30年1月12日(金) 13:00-17:30
・会場:弘済会館(東京都千代田区 麹町 5−1) 4階 楓
・土木学会ウェブサイト(http://www.jsce.or.jp/event/active/information.asp)にて参加申込のこと(先着70名まで)、参加費無料
・開催趣旨:
CIM(Construction Information Modeling)の普及推進とともに、単体の社会基盤施設から地域の空間構成に到るまで、3次元モデルを利用する機会が増えてきている。しかし、建設プロジェクトサイクルの上流にある計画策定のプロセスにおいては十分に活用されているとは言い難い。本ワンデイセミナーでは、公共計画の立案などに関わる実務家ならびに3次元モデルに係る教育を行おうとする大学等教員を対象として最新の取り組み,他国の状況などを紹介し、パネルディスカッションを通じて3次元モデルが計画プロセスを変える可能性とその障害、制約を打開する方策案を示す。
・プログラム:
13:00-13:15 開会の挨拶~CIM概説/秀島栄三(名工大)
13:15-13:35 宇都宮のまちづくりにおける3次元モデル(仮)/長田哲平(宇都宮大)
13:35-13:55 石巻市復興事業へのCIM活用/大元守(石巻市)
13:55-14:15 道路設計への3次元モデルの適用とVRへの展開/蒔苗耕司(宮城大)
14:15-14:35 合意形成過程への適用事例(仮)/藤澤泰雄(八千代エンジニアリング)
14:35-14:55 CIMによる建設技術者育成の新たな試み/大屋誠(松江工専)
15:20-16:20 タイでのCIMの展開/Veerasak Likhitruangsilp(チュラロンコン大)
16:25-17:25 パネルディスカッション/鈴木温(名城大)・赤星健太郎(内閣府)・大西正光(京都大)・鈴木美緒(東京大)
17:25-17:30 閉会の挨拶/蒔苗耕司(宮城大)
・本セミナーは土木学会認定CPD(継続教育)プログラムです。
#162 31st Tokyo Tech TSU Seminar: Towards integrated urban design and simulation of autonomous vehicles: Engaging mobility @ Future Cities Laboratory
Date
2018年1月9日
Venue
東京工業大学 緑が丘5号館 2F 小会議室 2F,Small Meeting Room, Midorigaoka Build. #5, Ookayama Campus, Tokyo Institute of Technology
31st Tokyo Tech TSU Seminar: Towards integrated urban design and simulation of autonomous vehicles: Engaging mobility @ Future Cities Laboratory
#88 地域アセットマネジメント確立に向けて(第1回JAAM研究発表会内で開催)
Date
2017年12月19日
Venue
日本橋ライフサイエンスビル9階会議室(〒103-0023 東京都中央区日本橋本町2-3-11)
地域アセットマネジメント確立に向けて(第1回JAAM研究発表会内で開催)
日 時 2017年12月19日(火) 10:00~19:00
#161 Measuring Economic Resilience to Natural Disasters and Terrorism
Date
2017年12月14日
Venue
京都大学 防災研究所 大会議室 S519D
Measuring Economic Resilience to Natural Disasters and Terrorism
日時:12月14日 16:00-17:30
場所:京都大学 防災研究所 大会議室 S519D
宇治市五ケ庄 最寄駅:JR黄檗(奈良線)、京阪黄檗
講師: Prof. Adam Rose
Price School of Public Policy and Center for Risk and Economic Analysis of Terrorism Events (CREATE), University of Southern California
講演題目:Measuring Economic Resilience to Natural Disasters and Terrorism
要旨:
Resilience is a powerful strategy for reducing losses from disasters. Its unique character pertains to how best to recover economic activity after a disaster has struck. This can be done by using remaining resources as effectively as possible and accelerating the repair and reconstruction of the capital stock. This presentation will focus on recent advances in measuring economic resilience in a variety of contexts, such as electricity outages, seaport disruptions, hurricanes, and earthquakes. Results of recent survey research will be presented and their implications for development of an economic resilience index will be described. A broader benefit-cost analysis framework will be explained for making resource allocation decisions, including trade-offs between (pre-event) mitigation and (post-event) resilience.
第5回研究小委員会を開催しました
第5回研究小委員会を開催しました
第5回 応用一般均衡分析と交通分析の統合に関する研究小委員会
日時:2017年11月20日(月) 14:00-17:00
場所:金沢大学 サテライトプラザ 2階 講義室
1. 話題提供
・佐藤啓輔,右近崇,片山慎太郎:SCGEを活用したストック効果最大化に向けた検討事例紹介
・山崎雅人:アイスバーグ型SCGEとアクセシビリティ型SCGEの便益分布特性の違い
・石倉智樹:空間的応用一般均衡モデルにおける輸送費の扱いと交通投資プロジェクト評価
#160 Making route choice and traffic flow models more realistic
Date
2017年11月7日
Venue
神戸大学六甲台第2キャンパス 自然科学総合研究棟3号館1階125室
Making route choice and traffic flow models more realistic
– Speaker: Dr. Adam J Pel, TU Delft, the Netherlands
– Title: “Making route choice and traffic flow models more realistic, but not more complex”
– Venue: Room 125, Science & Technology Research Building No. 3, 1F
– Place : Rokkodai 2nd Campus, Department of Engineering, Kobe University.
http://www.kobe-u.ac.jp/en/
In this seminar I will talk about route choice models and traffic flow models as these are used in road network modelling. Road network models simulate drivers’ behaviour and how their decisions are both based on, and collectively lead to, the emerging traffic flows and congestion conditions.
I will present several existing types of models, from basic to complex, and discuss their underlying assumptions on traffic behaviour and their suitability for various modelling applications. I will present in more detail a few recent studies at Delft University of Technology on: a route choice model that incorporates dynamic rerouting behaviour; a static traffic flow model that incorporates ‘dynamic’ traffic flow congestion; and a first-order traffic flow model that incorporates some second-order traffic flow phenomena.Bio:
Dr. Adam Pel is Assistant Professor at Delft University of Technology in the Netherlands. His main research field is the resilience of road transport systems. Pel’s research group studies, on the one hand how stochastics, uncertainty, dynamics and disruptions affect transport systems, including emergencies and evacuations, and on the other hands how network design, contingency planning, and mobility and traffic management can be strategically used to increase resiliency. In his research, he often uses network modelling as research method. These models are used to assess the dynamic performance of road transport systems regarding: human factors, infrastructure, services, technologies, policies, control measures and information flows. Pel’s research group develops models for more behavioural realism, faster computation, better use of (new) data, higher precision and accuracy. Furthermore, Pel works part-time at Fileradar, a university-spinoff company, where he is lead engineer for Fileradar’s predictive data analytics, used for traffic monitoring, information and control.
第56回土木計画学研究発表会・秋大会
Date
2017年11月3日(金)~5日(日) ※チュートリアルセッション:11月2日(木)/三陸地域の現地視察:11月5日(日)セッション終了後~6日(月)
Venue
岩手大学 上田キャンパス
開催校ホームページ
第59回土木計画学研究発表会・春大会
招待講演(11/4(土),14:00~15:30)
清水 英範氏(東京大学)「山尾庸三が臨時建築局総裁に就任した経緯に関する研究」
大澤 実氏(東北大学)「集積経済モデルの数理解析とその周辺」
特別講演(11/4(土),15:40~16:10)
発表プログラム
発表要領
参加申込み
会告について
講演用論文
講演の申込み
発表希望分野
| 発表希望分野 | キーワード |
| A 計画論・計画情報 | 計画基礎論、計画手法論、システム分析、調査論、公共事業評価法、財源・制度論、プロジェクト構想、施工計画・管理、維持管理計画、意識調査分析、計画情報、情報処理、市民参加、GIS、リモートセンシング、測量、環境計画、防災計画、河川・水資源計画、ライフライン計画・設計、地球環境問題 |
| B 地域・都市・景観 | 国土計画、地域計画、都市計画、地区計画、住宅立地、産業立地、人口分布、地価分析、土地利用、市街地整備、再開発、景観、公園・緑地、観光・余暇、空間設計、イメージ分析、土木史 |
| C 交通現象分析 | 発生交通、目的地選択、交通手段選択、経路選択、出発時刻選択、活動分析、時間利用、交通行動調査、交通意識分析、交通行動分析、自動車保有・利用、駐車需要、交通ネットワーク分析、土地利用・交通・環境統合モデル、観光・余暇行動 |
| D 交通基盤計画 | 総合交通計画、地区交通計画、公共交通計画、歩行者・自転車交通計画、道路計画、鉄道計画、空港・港湾計画、ターミナル計画、駐車場計画、物流計画 |
| E 交通運用管理 | 交通流、交通容量、サービス水準、交通制御、交通管理、交通安全、交通情報、交通環境、公共交通運用、交通弱者対策、水上交通、空港管理、交通量計測、TDM、ITS、モビリティマネジメント(MM) |
(3) 発表形式
口頭発表とポスターでの発表のどちらを希望するかを選んでいただきます。なお、会場の都合でご希望に添えない場合もありますので予めご了承下さい。
(4) 投稿料
講演1本につき投稿料(参加費含む)として一般12,000円、学生9,000円を請求いたします。2本以上投稿する方については、2本目以降の投稿料は一般・学生ともに6,000円を請求いたします。振込手数料は各自でご負担願います。
講演原稿執筆要領
講演原稿の書式・形式は、土木学会論文集のものに準じています。下記の作成例やサンプルファイルをご利用ください。講演原稿では、英文アブストラクトの記入は任意です。その他書式・形式についての詳細は土木学会論文集の原稿作成の手引き等をご参照ください。なお、「土木学会論文集D3(土木計画学), Vol.75-6」への投稿の際には英文アブストラクトは必要です。
サンプルファイル 和文(Word2000)/English(Word2000)
原稿作成例 和文(PDF)/English(PDF)
事前参加申込みについて
CD-ROM版講演集の配布について
スケジュールと内容
お問合せ先
土木計画学研究委員会大会運営小委員会(春大会担当:橋本,氏原,林)
E-mail:keikaku59@jsce.or.jp
第4回研究小委員会を開催しました.
第4回研究小委員会を開催しました.
第4回 応用一般均衡分析と交通分析の統合に関する研究小委員会
日時:2017年11月2日(木) 17:40-18:00
場所:いわて県民情報交流センター
(所属および敬称略)
議事.今後の予定について
・次回研究小委員会:11月20日午後,於:金沢大学
・日蘭(日欧)セミナー,2018年3月(予)於:ベルギー,ブリュッセル
・土木計画学研究発表会春大会,企画論文セッション,SS,
2018年6月9日-10日,於:東京工業大学
・ERSAスペシャルセッション,2018年8月28日-31日,於:アイルランド, Cork
チュートリアルセッションを開催しました.
チュートリアルセッション(空間・経済・統計分析)
日時 2017年11月2日(木)
13:30–14:00 土木計画学における理論研究とは 小池淳司(神戸大学・教授)
14:00–15:00 空間統計学入門 瀬谷創(神戸大学・准教授)
15:15–16:15 統計的因果推論 織田澤利守(神戸大学・准教授)
16:30–17:30 応用一般均衡分析 小池淳司(神戸大学・教授)
会場 いわて県民情報交流センター
(岩手県盛岡市盛岡駅西通1丁目7番1号,JR盛岡駅徒歩4分)
#159 29th Tokyo Tech TSU Seminar: Traffic Management in the Era of Vehicle Automation and Communication Systems (VACS)
Date
2017年10月16日
Venue
東京工業大学 大岡山キャンパス 緑が丘6号館 Midorigaoka Build. #6, Ookayama Campus, Tokyo Institute of Technology
29th Tokyo Tech TSU Seminar: Traffic Management in the Era of Vehicle Automation and Communication Systems (VACS)
#158 The 9th International BinN Seminar: Behavior Model and Optimization
Date
2017年10月14日
Venue
東京大学 工学部一号館 15号教室
The 9th International BinN Seminar: Behavior Model and Optimization
Behavior Model and Optimization
Prof. Michel Bierlairel (EPFL)
#6 DIVERSITYの視点から見直そう:土木計画学における研究と教育(2017年・年次学術講演会)
Date
2017年9月11日
Venue
九州大学伊都キャンパス センター2号館2203
DIVERSITYの視点から見直そう:土木計画学における研究と教育
平成29年度土木学会全国大会 研究討論会 <九州大学>
共催: ダイバーシティ推進委員会
※ 言語:日本語(一部英語可)
座長: Giancarlos Troncoso Parady(東京大学)、中道 久美子(東京工業大学)
プログラム:
開会・趣旨説明: Giancarlos Troncoso Parady(東京大学)、中道 久美子(東京工業大学)
話題提供者:
藤原 章正(広島大学)/留学生指導・
Jan-Dirk Schmocker(京都大学)/
谷口 綾子(筑波大学)/女性から見た土木計画学における教育・研究
村山 顕人(東京大学)/異分野から見た国際研究・教育
松尾 美和(神戸大学)/海外研究経験のある女性から見た研究・教育
Wisetjindawat Wisinee(名古屋工業大学)/女性外国人から見た研究・
閉会挨拶: 屋井鉄雄(東京工業大学/EASTS会長)
場所:九州大学伊都キャンパス センター2号館2203(福岡市西区元岡744)
http://www.jsce.or.jp/
#154 留学生のための特別サマーセミナー「大都市の鉄道と地域開発2017」
Date
2017年9月7日
Venue
Hongo campus, The University of Tokyo
留学生のための特別サマーセミナー「大都市の鉄道と地域開発2017」
留学生のための特別サマーセミナー「大都市の鉄道と地域開発2017」 募集要項
この度、下記の通り、東京大学大学院(社会基盤学専攻)、政策研究大学院大学並びに JR東日本、東京メトロ、東急電鉄、三井不動産、海外鉄道技術協力協会の共同で、留学生のための特別サマーセミナー「大都市の鉄道と地域開発2017」を開催いたします。特に東京を題材として、市街地がどのように都市鉄道を使いながら発展してきたのか、またそれを支えているのはどのような技術やシステムなのかについて、トップクラスの専門家や実務者等による総合的な講義に加え、ターミナル駅や都市開発事例の見学なども通じて、日本で学ぶ留学生を中心とする学生諸君に学んでもらおうというものです。
奮ってご応募くださいますよう、お待ち申し上げております。
都市鉄道セミナー実行委員会委員長
政策研究大学院大学
教授 家田 仁
記
1.スケジュール
2017年9月7日(木)~9月8日(金)の1泊2日、詳細は下記をご覧ください。
http://www.trip.t.u-tokyo.ac.jp/urbanrailseminar/TentativeSchedule2017.pdf
2.参加者の負担金
・資料代として3,000円を申し受けます。
・9月7日の懇親会費及び宿泊費(但し主催者側が用意したホテルに滞在する場合に限る)は主催者側が負担します。
・それ以外の食事代と交通費は自己負担とします。
3.募集定員
日本の大学の大学院で学んでいる留学生30名、日本人大学生・大学院生10名を定員とします。
4.応募資格
応募資格のある学生は、交通や都市・国土プロジェクトの計画や実施など総合的工学、経済・政策系の学問、機械工学・電気工学など個別工学を専門分野としている学生のうち、以下の条件を満たしている方とします。
・日本の大学或いは大学院に所属していること。
・日本の大学或いは大学院に所属する教員の指導を受けていること。
・下記「8」の注意事項の全てについて同意できること。
5.募集期間と応募方法
・募集期間は2017年6月30日(金)23:59 JST までとします。
・応募者はこちらの応募書類を全て記入し、下記連絡先までメールで送付してください。日本人応募者は日本語を使用しても構いません。
http://www.trip.t.u-tokyo.ac.jp/urbanrailseminar/ApplicationFormSSSIS2017.docx
6.参加者の審査
・応募者多数が予想されるため、応募書類によって審査をさせていただき、参加者を選考します。
・審査にあたっては、各主催組織メンバーからなる審査委員会を設けます。
・審査の視点は、都市鉄道や地域開発に関する基礎知識、セミナー参加の動機、将来従事したい仕事とします。
7.参加者の決定と連絡
2017年7月18日(火)までに、全応募者に参加の可否をメールにて連絡します。
8.注意事項
・9月7日の夜の宿泊場所は主催者側で用意するため、手配は必要ありません。ただし、東京近郊在住の場合、宿泊を遠慮していただく場合があります。
・暑い時期ですのでクールビズで結構ですが、節度ある服装をお願いします。
・各自の責任で適切な傷害保険に加入していることを前提とします。
・参加が不可能になった場合は8月7日までに必ず連絡してください。それ以降のキャンセルは認めません。
・その他、主催者の指示には従ってください。
9.使用言語
原則として英語とします。
10.連絡先
都市鉄道セミナー実行委員会
委員長 家田 仁 (東京大学・政策研究大学院大学、教授)
副委員長 加藤 浩徳 (東京大学、教授)
副委員長 中井 雅彦 (JR東日本、常務取締役)
副委員長 山村 明義 (東京メトロ、専務取締役)
副委員長 城石 文明 (東急電鉄、取締役・執行役員・鉄道事業本部長)
副委員長 山川 秀明 (三井不動産、開発企画部長)
問合せ先e-mail: urbanrailseminar@trip.t.u-tokyo.ac.jp
(加藤浩徳、森川想・東京大学)
第3回研究小委員会を開催しました.
第3回研究小委員会を開催しました.
第3回 応用一般均衡分析と交通分析の統合に関する研究小委員会
日時:2017年8月18日(金) 13:30-16:00
場所:神戸大学梅田インテリジェントラボラトリ
出席者:小池,織田澤,佐藤,瀬谷,山本,瀬木,高山,平松,寺西,右近,片山,石倉(所属および敬称略)
話題提供
・山本浩道(三菱重工/神戸大学)「家計の異質性を考慮したCUEモデルの開発」
概要:
アジア・ASEANでのCUEモデルへの要請として,推定精度の高さや,家計の社会経済的属性が多様な地域への適用性が求められている.CUEモデルの立地モデルおよび交通モデルの各段階において,社会経済属性によってモデルパラメータの異質性を考慮した場合のモデルを構築し,神戸市を事例としてモデル出力結果への影響を分析した.
・瀬木俊輔(京都大学)「CGEモデルにおける貨物輸送費用の表現と実装に関する考察,ほか」
概要:
SCGEモデルにおいて輸送サービスをモデル化するための理論的枠組みについて,データの利用可能性を考慮しつつ方法論を整理した.
一地域閉鎖経済を対象として,貨物輸送費削減効果を評価するための理論モデルを構築し,その効果を解析的に示した.輸送サービス供給を明示したモデルと氷塊輸送型モデルとの類似性と差異を示した.
ほか,食品の在庫管理費用を考慮した商店の立地分析に関する研究および補償原理に関する考察について話題提供があった.
その他:次回日程調整など
本研究小委員会に関係する今後のイベント:
ERSA2017スペシャルセッション,8/30@フローニンゲン大学
土木計画学研究発表会(秋大会),11/3-5@岩手大学
チュートリアルセッション,11/2@いわて県民情報交流センター(JR盛岡駅徒歩4分)
研究小委員会+懇親会:11/2夕方(チュートリアルセッション後)に開催予定
日蘭(日欧)セミナー,2018年3月予定
2017年度 第2回「ITSとインフラ・地域・まちづくり」小委員会
2017年度 第2回「ITSとインフラ・地域・まちづくり」小委員会
日時:2017年8月3日(木) 15:00~17:10
場所:土木学会AB会議室
第12回日本モビリティ・マネジメント会議(福岡県福岡市)
第12回日本モビリティ・マネジメント会議(福岡県福岡市)
第十二回日本モビリティ・マネジメント会議(JCOMM)開催のお知らせ
我が国におけるMM施策が、今後も効果的・広範に推進されることを目指して、行政、大学、コンサルタント、市民団体等のMM関係者が一堂に会する日本モビリティ・マネジメント会議(JCOMM)を下記の要項にて開催いたします。
■ 開催日 2017年7月28日(金)・29日(土)
■ 会場 福岡県福岡市 アクロス福岡
■ 主催 (一社)日本モビリティ・マネジメント会議
■ 概要 概要等の詳細は決定次第掲載いたします。なお、プログラム概要は以下を予定しております。
※28日:午前は開催地企画、午後からJCOMMセッション
※29日:終日JCOMMセッション
http://www.jcomm.or.jp
#86 スマート・プランニングの活用と今後の展望
Date
2017年7月22日
Venue
東京大学工学部14号館,141教室(1階)
スマート・プランニングの活用と今後の展望
第86回ワンデイセミナー「スマート・プランニングの活用と今後の展望」
第86回ワンデイセミナー「スマート・プランニングの活用と今後の展望」
「都市-交通計画の未来」羽藤英二(東京大学)[資料2-1]「さあ始めよう,スマートプランニング」関信郎(国土交通省) [資料2-2]
岡山市 是友修二(岡山市) [資料3-1]神戸市 杉本保男(神戸市) [資料3-2]熊本市 溝上章志(熊本大学) [資料3-3]
データ同化から,Wi-FiやGPSを用いた最新の都市流動調査の可能性と街路空間の再配分やストリートマネジメント,駅まち空間の新時代に向けた新たな都市計画手法の可能性と今後の課題を議論します.
コーディネータ:羽藤英二(東京大学)パネリスト: 佐々木邦明(山梨大学) [資料4-1]
伊藤香織(東京理科大) [資料4-2]越智健吾(国土交通省) [資料4-3]三島功裕(神戸市) [資料4-4]石神孝裕(IBS) [資料4-5]
#155 28th Tokyo Tech TSU Seminar: Solving Path Problems in Network Traffic Assignment
Date
2017年7月13日
Venue
東京工業大学 大岡山キャンパス 緑が丘6号館 Midorigaoka Build. #6, Ookayama Campus, Tokyo Institute of Technology
28th Tokyo Tech TSU Seminar: Solving Path Problems in Network Traffic Assignment
Date:13th July (Thu.) 2017
Time:14:00 – 17:00
http://www.transport-titech.jp/seminar_visitor.html
Lecture 1
Title:Another Alternative to Dial’s Logit Assignment Algorithm on All Acyclic Paths
Speaker:Dr. Takeshi Nagae (Tohoku University) and Shin-ichi Inoue (The Institute of Behavioral Sciences)
Lecture 2
Title:Why does proportionality matter in traffic assignment and how to achieve it?
Speaker:Prof. Yu (Marco) Nie (Northwestern University)
Abstract for Lecture 2:
The proportionality condition has been widely used to produce a unique path flow solution in the user equilibrium traffic assignment problem. In this talk I will first explain why proportionality offers a conceptually simple, practically viable and computationally efficient approach to determining a path flow solution that approximately conforms to the principle of entropy maximization. I will then address two hitherto open questions: (1) whether and to what extent does the proportionality condition accord to real travel behavior; and (2) how to develop an efficient algorithm that guarantees finding a solution to satisfy the proportionality condition strictly? To answer the first question, we mine a large taxi trajectory data set to obtain millions of route choice observations, and uncover hundreds of valid paired alternative segments (PAS) from the data. The results obtained by performing linear regression analysis and chi-square tests show that the majority of the PASs tested (up to 85%) satisfy the proportionality condition at a reasonable level of statistical significance. To answer the second question, we propose a novel algorithm. It alternates between constructing an origin-based and a destination-based bush representation of user equilibrium solutions, and iteratively solves the entropy maximization subproblem defined for each bush. Thanks to the special structure of bushes, these subproblems can be solved efficiently. The proposed algorithm thus obviates enumerating all UE paths or collecting a set of paired alternative segments (PAS) to cover them. We prove that the algorithm ensures convergence to a solution that perfectly satisfies the proportionality condition in general networks. The proposed algorithm solves the problem much faster than the known alternatives, with a speedup of 3 – 8 times on large networks.
Short Bio. of Dr. Yu (Marco) Nie:
Dr. Marco Nie is currently an Associate Professor of Civil and Environmental Engineering at Northwestern University. He received his B.S. in Structural Engineering from Tsinghua University, his M.Eng. from National University of Singapore and his Ph.D. from the University of California, Davis. Dr. Nie’s research covers a variety of topics in the areas of transportation systems analysis, transportation economics, sustainable transportation and traffic flow theory and simulation. Dr. Nie is currently a member of TRB committee on Transportation Network Modeling (ADB30). He also serves as an Associate Editor for Transportation Science, an Area Editor for Networks and Spatial Economics, and is a member of the Editorial Advisory Board for Transportmetrica-B and Transportation Research Part B. Dr. Nie’s research has been supported by National Science Foundation, Transportation Research Board, US Department of Transportation, US Department of Energy, and Illinois Department of Transportation.
#157 Multi-gated perimeter traffic flow control of monocentric cities
Date
2017年7月7日
Venue
Room C2-301, Department of Engineering, Kobe University
Multi-gated perimeter traffic flow control of monocentric cities
– Speaker: Dr. Konstantinos Ampountolas, Glasgow University, UK
– Title: “Multi-gated perimeter traffic flow control of monocentric cities”
– Venue: Room C2-301, Department of Engineering, Kobe University.
#156 The 8th of International BinN Research Seminar “Dynamic Behavior Analysis and Clustring in Unsteady Networks”
Date
2017年7月5日
Venue
Room 409, Building #1, the University of Tokyo
The 8th of International BinN Research Seminar “Dynamic Behavior Analysis and Clustring in Unsteady Networks”
The 8th International BinN Research Seminar “Dynamic Behavior Analysis in Unsteady Networks” will be held on July 5th 2015. As keynote speakers, we will invite Dr. Konstantinos Ampountolas from University of Glasgow. Dr. Dr. Konstantinos Ampountolas is currently doing research on network analysis and in the seminar, keynote lectures would focus on functional distributional algorithm for clustering heterogeneous traffic networks using spatiotemporal data. In addition, we discuss about new approaches of unsteady behavioral modeling with two researchers’ presentation.
Program
Ashwini Venkatasubramaniama,b,c, Ludger Eversa, and Konstantinos Ampountolas*, School of Mathematics & Statistics, Urban Big Data Centre (UBDC) http://ubdc.ac.uk University of Glasgow, UK
Title:
Functional distributional clustering of traffic networks for spatio-temporal data
Abstract:
Clustering analysis provides a selection of a finite collection of templates that well represent, in some sense, a large collection of data. Nowadays clustering has many applications in engineering, computer science, social and life sciences, due to the availability of large volumes of data from user-generated content and emerging infrastructure-based sensors. In this talk, we present a functional distributional algorithm for clustering heterogeneous traffic networks using spatiotemporal data. The proposed algorithm seeks to identify spatially contiguous clusters in Manhattan-like grid networks and has the ability to accommodate temporal data with bi-modal characteristics. The algorithm draws on a measure of distance that utilises (cumulative distribution) functions of observations rather than functions of clusters. We describe methods to determine the optimal number of clusters within a hierarchical agglomerative clustering framework. This helps to evaluate the similarity between distinct identified clusters and “true” clusters to measure the algorithm’s performance. Results demonstrate that the proposed functional distributional clustering algorithm has a greater ability to efficiently identify clusters compared to functional only and temporal only algorithms. On-going work on dynamic clustering seeks to identify clusters that change over time.
Sachiyo Fukuyama
Department of Civil Engineering, University of Tokyo
Title: Network analysis for urban planning based on the historical development process
Abstract:
We propose a method of network analysis to figure out the spatial structure and characteristics of urban districts, which are assumed to be important for efficient urban planning and renovation. We use a simple index that reflect route choice behavior for analyzing road networks in the periods before behavioral surveys started. For a case study, we apply the method to the historical networks of the old city of Barcelona and find the relation between the streets of high centrality and the placement of open spaces.
Eiji Hato and Samal Dharmarathna*
Department of Civil Engineering, University of Tokyo
*Presenter
Title:
Unsteady travel behavior under uncertainty in densified networks
Abstract:
Understanding the travellers’ behavior under uncertainty is essential to minimize the congestion and maintain the service level of densified networks during unexpected events such as earthquakes or extreme weather events. During such events, drivers’ pre-trip decisions are get disturbed and it becomes quite obvious to assume that their cognition and decision-making mechanisms are more myopic as the network condition is likely to be stochastic. But still there is some space that drivers could use their spatial knowledge on the network to choose the route.
This on-going study tries to cope with both these concepts by using the generalized recursive logit (GRL) model and compare the differences, by using the probe taxi data collected in Tokyo during the period of Great East Japan Earthquake occurred on 11th March 2011 and torrential rain occurred on 23rd July 2013. Gridlock phenomena has occurred in Tokyo for the first time, after the earthquake due to the temporary shutdown of the metropolitan expressway and all railways for checking purposes. The behavior of the sequential discount rate which generalize the drivers’ decision making dynamics and represent the degree of spatial recognition of network as a parameter is compared along with other parameters such as travel time and right turn dummy within the event by using similar data collected exactly one week before and after the earthquake respectively on 04th and 18th of March 2011. During the event of torrential rain, some of the links that has under passes and depressions were inundated and the cars or taxies couldn’t move across. Hence the travellers’ use such routes under normal circumstances had to choose alternative routes. In this case also, the aforementioned parameters were estimated and compared within the event by using the similar data collected exactly one week after the event on 30th July 2013. In addition, we would like to present the comparison of parameters between the two events as well.
国際海運経済学会(IAME)京都大会の開催
国際海運経済学会(IAME)京都大会の開催
http://web.apollon.nta.co.jp/iame2017/index.html
#152 Lecture Series on "Future Urban Mobility and Public Transportation -Challenges and Values-"
Date
2017年6月26日
Venue
熊本大学,国土技術政策総合研究所,東京大学生産技術研究所
Lecture Series on "Future Urban Mobility and Public Transportation -Challenges and Values-"
#153 How can the Taxi Industry Survive the Tide of Ridesourcing? Evidence from Shenzhen, China
Date
2017年6月20日
Venue
京都大学桂キャン パスCクラスター C1-314(C1棟会議室3)
How can the Taxi Industry Survive the Tide of Ridesourcing? Evidence from Shenzhen, China
第55回土木計画学研究発表会・春大会
Date
2017年6月10日(土)・11日(日)
Venue
愛媛大学
第55回土木計画学研究発表会・春大会
土木計画学研究委員会は下記の概要で第55回土木計画学研究発表会(春大会)を開催いたします.
実施要領 (PDFファイル)
発表暫定プログラム(確定版2017年5月29日更新)(概要版,詳細版)
企画論文部門・スペシャルセッション(SS)部門
企画論文部門は,オーガナイザーを公募し提案された企画テーマでの論文公募を行い,口頭発表またはポスター形式での発表を行うもので,本大会では55セッションが開催されます.SS部門は,既存の研究小委員会等が主催して,研究討議・意見交換を中心にセッションを構成するもので,本大会では全体セッション1件を含む15セッションが開催されます.また,企画論文部門・SS部門の並行セッションは最大12会場を予定しております.
展示ブース
スケジュール
企画論文部門
スペシャルセッション(SS) 部門
発表の要領
聴講者用にレジュメ50部をご用意の上,各セッション会場にて配布して下さい.
論文投稿料について
企画部門の発表会投稿料(参加費を含む)は,講演1件につき一般12,000円,学生9,000円です.SS部門は,1セッションにつき,10,000円(参加費別)です.なお,論文題目・概要の登録(2016年2月5日(金))後のキャンセルは,一切認められません.発表(講演)を辞退されても,発表会投稿料として料金を請求させて頂きますので十分にご注意ください.
参加登録
参加登録(発表者以外の方):次の土木学会行事参加申し込みホームページより,ご登録ください.
事前参加申し込みに関する注意事項
土木学会論文集D3(土木計画学)特集号への投稿資格について
http://www.jsce.or.jp/committee/ip/monograph/file/journal-s-tebiki.pdf
春大会運営に関する問い合わせ先
土木計画学研究委員会大会運営小委員会
e-mail: keikaku55@jsce.or.jp
第2回委員会開催のお知らせ
第2回委員会開催のお知らせ
日時:2017年6月10日(土)18:30-20:00(90分)
-第55回土木計画学研究発表会@愛媛大学
場所:愛媛大学会議室2(共通講義棟A(受付・発表会場) 4F 講44)
次第(案)
1.情報共有
2.今後の予定
3.その他
2017年度 第1回「ITSとインフラ・地域・まちづくり」小委員会
2017年度 第1回「ITSとインフラ・地域・まちづくり」小委員会
日時:2017年6月10日(土) 12:40~13:20
場所:愛媛大学 共通講義棟A 講44
#85 これからの空港と次世代航空交通システムの進化
Date
2017年5月26日
Venue
日本大学駿河台キャンパス1号館151教室(千代田区神田駿河台1-8-14)
これからの空港と次世代航空交通システムの進化
第2回研究小委員会を開催しました
第2回研究小委員会を開催しました
日時:2017年5月18日(木) 14:00-16:00
場所:神戸大学(工学部棟 C2-202教室)
参加者:小池,織田澤,瀬谷,山崎(雅),山本,瀬木,高山,平松,土屋,右近,片山,石倉
●話題提供1:高山雄貴(金沢大学)
集積の外部性を考慮した応用一般均衡モデルに関する研究の報告
Globalな分散力とLocalな分散力がもたらす都市人口集積パターン
日本における県別,都市雇用圏別での人口変化の理論的予測と実績の比較
都市階層原理とランクサイズルールに関する実証と考察
●話題提供2:平松燈(近畿大学)
交通モデルと地域経済モデルの相互作用モデルに関する研究報告
九州新幹線開業による九州各県における経済効果の分析
観光産業に特に着目
新幹線開業による交通一般化費用低下を交通モデルにより表現し,地域経済モデルでは旅行財の費用低下として経済均衡変化を導出.旅行需要変化として交通モデルにフィードバックし,相互作用モデルとして構成
●次回の研究小委員会
日時:8月18日(金)午後
場所:神戸大学
話題提供者:山本,瀬木
参考:
土木計画学研究発表会(春大会)
6/10(土)15:00-16:30,スペシャルセッション「インフラのストック効果は計測可能か」
6/10(土)16:45-18:30,企画論文セッション「空間経済分析」
5月18日に第2回研究小委員会を開催します
5月18日に第2回研究小委員会を開催します
日時:2017年5月18日(木) 14:00-16:00
場所:神戸大学(工学部棟 C2-202教室)
話題提供者:高山雄貴(金沢大学),平松燈(近畿大学)
2016年度
2016年度
・第84回土木計画学ワンデイセミナー「少子高齢社会における子育てしやすいまちづくり~都市のバリアと心のバリア~」(2017年3月4日(土)@東京大学工学部14号館)
・第4回小委員会(2016年11月5日(土)@長崎大学)
・Qサポネット主催 子連れお出かけ支援シンポジウム「ふくおかを日本一子連れでお出かけがしやすいまちにするには何が必要か?~子連れでお出かけがしやすい・支える・見守るまちづくりを考える~」共催(2016年11月3日(木・祝)@福岡)
・第3回小委員会(2016年10月28日(金)@文教大学湘南キャンパス)
・文京区視察会&第2回小委員会(2016年6月9日(木)16:00~19:00@文京区青少年プラザb-lab&東京大学工学部14号館)
・第1回小委員会(2016年5月29日(日)@北海道大学工学部)
2015年度
2015年度
・世田谷区区民版子ども子育て会議主催 第1回せたがや子ども・子育て楽(学)会 共催(2016年3月12日(土)@せたがや がやがや館)
・第5回小委員会(2016年3月8日(火)17:00~19:00@土木学会A会議室)
・第78回土木計画学ワンデイセミナー「少子高齢社会における子育てしやすいまちづくり~親の視点と子どもの視点~」(2016年2月20日(土)@東京大学工学部14号館)
・第4回小委員会(2015年11月22日(日)10:45~11:30@秋田大学手形キャンパス)
・杉並区児童館視察会&第3回小委員会(2015年10月6日(火)14:00~17:00@杉並)
・第2回小委員会(2015年8月20日(木)18:00~20:00@土木学会D会議室)
・第1回小委員会(2015年6月7日(日)13:45~15:15@九州大学伊都キャンパス)
・福岡市の中心市街地における子育て支援に関する視察会(2015年6月5日(金)14:00~17:40@福岡)
2014年度
2014年度
・第75回土木計画学ワンデイセミナー「少子高齢社会における子育てしやすいまちづくり~大都市と地方都市、都心と郊外、どちらが子育てしやすいか?~」(2015年3月14日(土)@土木学会講堂)
・第4回小委員会(2015年2月18日(水)18:00~19:30@土木学会A会議室)
・第3回小委員会(2014年11月2日(日)10:30~12:00@鳥取大学工学部)
・第2回小委員会(2014年9月3日(水)18:00~20:00@東京大学工学部14号館)
・松戸市子育て関連施設視察会&第1回小委員会(2014年8月1日(金)13:30~17:40@松戸)
委員の公募について
委員の公募について
土木計画学研究委委員会「ITSとインフラ・地域・まちづくり研究小委員会」
委員追加公募のお知らせ
(締切:2017(平成29)年5月31日)
(本公募は終了いたしました)
平成28年度より設置している標記小委員会について、委員の追加公募を行います。
●委員会名:「ITSとインフラ・地域・まちづくり研究小委員会」
●小委員長: 清水 哲夫(首都大学東京 教授)
●活動期間:平成29(2017)年6月~平成31(2019)年11月
●活動趣旨:
土木学会では1999年から現在まで,ITS研究開発に関する委託業務を実施し,ITS施策の方向性に対して提言を行うとともに,各地のフィールドにおいて防災・減災,交通安全など土木学会ならではのニーズ指向の地域ITS実践研究を実施してきた.
しかし,成功・失敗要因の学術的な特定が進んでいないこと,ITSを地域に導入する事業スキームが標準化されていないこと,少子高齢化・人口減少対応,地方創生,観光振興,まちづくり,コミュニティー形成,インフラ維持管理の多様な分野でITSに対する新たなニーズの可能性があること,など,地域ITS実践研究の継続が必要である.
本小委員会の活動目的は,全国の土木計画学研究者ネットワークを活用して,地域における上記分野でのITSへのニーズを広範に把握すること,国内外の従来の地域ITSの成果と課題を分析して実践に向けた事業化手法を提案すること,であり,最終成果として地域ITS実践マニュアル(仮称)を作成する計画である.
●活動方法:年2回程度の委員会(計画学研究発表会時)およびWGによる活動
●応募条件:小委員会の目的をご理解いただき,小委員会への出席等,活発な活動をしていただける方
●応募方法:参加を希望される方は,メールにて、本文に下記を明記の上,メール件名を「【公募申込】ITSとインフラ・地域・まちづくり研究小委員会 委員申込」とし,末尾の応募先までE-mailをお送り下さい。折り返しご連絡を差し上げます.
①氏名
②年齢
③所属
④連絡先住所
⑤電話番号
⑥E-mailアドレス
●留意事項:本研究活動は、実導入や実施を視野に入れた価値ある研究を目指しております。そのため、委員になっていただいた方には、調査や研究協力をお願いすることがありますので、ご了解のうえ申し込みいただければ幸いです。
●応募締切:2017(平成29)年5月31日(水)
●備考:旅費・交通費は支給されません
土木計画学研究発表会(春大会)にて平成29年度の第1回小委員会(キックオフ)を実施予定
●応募先・その他問合せ先:
公益社団法人土木学会 技術推進機構 中島 TEL:03-3355-3502 Mail:k-nakajima [at] jsce.or.jp
[at]を”@”に置き換えてください
#151 Lean Sustainable Logistics -Sustainable Performance Measurement in Sugar Industry-
Date
2017年5月10日
Venue
東京工業大学大岡山キャンパス石川台4号館地下B02-05
Lean Sustainable Logistics -Sustainable Performance Measurement in Sugar Industry-
小委員会活動
小委員会活動
第1回委員会 (2014年10月12日13:00~15:00,東京大学本郷キャンパス)
委員紹介,主旨説明,話題提供:残余のリスク(佐藤海岸工学委員長)
第2回委員会(2014年11月13日9:00~11:00,ウインクあいち)
話題提供:海岸をめぐる制度の現状(井上),土木計画学視点からみた減災アセスメント研究の課題について(羽藤)
第3回委員会(2015年1月20日13:00~15:00,土木学会)
話題提供:海岸工学における外力の確率評価(安田),費用便益分析と動学的不整合(河野)
第4回委員会(2015年3月27日13:00~17:00,土木学会)
話題提供:実務的な防潮堤設計,土地利用規制の課題等(井上),現場の視点からみた防潮堤の外部性について(平野)
第5回委員会(2015年6月7日18:00~20:00,ハミングバード貸会議室)
話題提供:防潮堤整備水準の設定のための方法論(藤見)
第6回委員会(2015年7月28日10:00~13:00,土木学会)
話題提供:防潮堤と土地利用の議論のための基本モデルの提案(横松)
議題:防潮堤高さの決め方について,東日本大震災5周年シンポジウムについて
第7回委員会(2015年9月19日15:00~18:30,京都大学東京オフィス)
話題提供:確率論的津波リスク評価と津波リスクの定量化(福谷),
確率的すべり分布モデルを用いた津波被害の不確実性評価(安田),
不確実性の評価についての紹介,耐震設計の課題(本田)
議題:津波の生起確率関数の考え方,津波フラジリティについて
第8回委員会(2015年12月19日15:00~18:00,東京海洋大学)
話題提供:均衡土地利用について(高木)
第1回幹事会(2016年1月14日15:00~19:00,東京海洋大学)
第9回委員会(2016年3月15日10:00~13:00,関西大学東京センター)
議題:海岸防災・減災対策決定プロセス,ケーススタディについて
第10回委員会(2016年9月7日15:00~17:00,東北大学)
第3回幹事会(3月5日@東北大東京分室)
第11回委員会(2017年3月31日11:00~14:00,キャンパスプラザ京都)
・津波リスクに対応した企業立地・人口の変化分析(河野)
・地震のスケーリング則を考慮した津波水位の確率評価(安田)
・ロジックツリーを用いた津波水位の確率論的評価(福谷)
・確率台風モデルを援用した高潮の確率論的評価(安田)
第12回委員会(2017年5月8日16:00~20:00,東北大学東京分室)
・ロジックツリーを用いた津波水位の確率論的評価(福谷)
・松崎町を対象とした浸水および避難シミュレーション(宇野)
・確率台風モデルを用いた高潮の確率評価(田島)
第13回委員会(2017年8月10日14:00~17:00,東北大学東京分室)
・徳島都市圏における津波防災まちづくりに関する研究紹介(山中)
・差分の差分の分析の他地域への展開と防潮堤整備効果の計測(河野)
現地視察および意見交換(2017年9月18日(月・祝)~19日(火),阿南市)
海岸工学講演会前日シンポジウム(2017年10月24日18:00~20:00,北海道大学フロンティア応用科学研究棟 鈴木章ホール)
タイトル「津波減災と最適海岸防護施設-津波ハザードの適切評価と後背地の経済・人口変化予測」
第14回委員会(2017年10月25日10:00~13:00,TKP札幌駅カンフェレンスセンター
・ 砂浜のレクリエーション価値と堤防嵩上げによる損失の推計(安田)
第15回委員会(2017年12月26日15:00~18:00,東北大学東京分室)
・津波リスク変化に応じた企業立地・人口の変化の把握方法
・防護施設の影響に関する進捗
第16回委員会(2018年3月29日14:00~17:00,ウィングス京都)
・費用便益分析を用いた最適防潮堤高さの設定方法(安田)
第17回委員会(2018年5月25日15:00~18:00,関西大学東京センター)
・防潮提高の違いによる企業立地移動と人口移動(河野,牛木)
第18回委員会(2018年9月11日14:00~17:00,関西大学東京センター)
・津波避難行動における認知的不協和特性の地域間の違い(河野)
・津波発生時の沿岸域住民の避難行動に関するアンケート調査(計画)(安田)
・津波防災公園の平時価値推計のための公園利用状況調査(計画)(安田)
現地視察および意見交換(2018年11月4日~5日,和歌山県串本町,那智勝浦町)
第3回地域アセット実装小委員会 研究会
第3回地域アセット実装小委員会 研究会
第55回土木計画学 春大会にて,
第3回地域アセット実装小委員会 研究会を開催します.
【主な内容】
・メンバーの活動共有
・議論
#5 土木計画学ハンドブック出版記念シンポジウム
Date
2017年4月28日
Venue
土木学会講堂
土木計画学ハンドブック出版記念シンポジウム
主催:土木学会土木計画学研究委員会
日時:平成29年4月28日 15:00-18:00
CPD:土木学会認定CPDプログラム 2.7単位 (認定番号 JSCE17-0214)
【趣旨】
土木計画学研究委員会では,委員会設立50周年を記念して,土木計画学ハンドブック出版事業運営小委員会(小委員長:小林潔司京都大学教授)を立ち上げ,土木計画学の分野における研究成果をとりまとめた「土木計画学ハンドブック」を編纂してまいりました.このたび,ハンドブック発刊を記念したシンポジウムを開催することとなりました.シンポジウムではハンドブックの理念や概要についてご紹介すると共に,その内容を踏まえた将来の研究・実践活動に関する展望を議論します.
【プログラム(案)】
15:00 開会・あいさつ
屋井鉄雄 土木計画学研究委員会 委員長
15:20 計画学の実践化に向けて
小林潔司 土木計画学ハンドブック出版事業運営小委員会 委員長
16:10ハンドブックの概要
多々納裕一 土木計画学ハンドブック出版事業運営小委員会 幹事長
堤盛人(筑波大学)・松島格也(京都大学)
16:30 パネルディスカッション –今後の研究・実践活動にむけて–
登壇者: 伊藤正秀(国総研),奥村誠(東北大学),吉井稔雄(愛媛大学),白水靖郎(中央復建コンサルタンツ)
司会 赤羽弘和 土木計画学ハンドブック運営小委員会 幹事
17:40 おわりに
藤原章正 土木計画学研究委員会 副委員長
【参加申込】
土木学会ホームページhttp://www.jsce.or.jp/event/active/information.aspからお申し込み下さい.
※当日の会場では,「土木計画学ハンドブック」を,土木学会員の特別価格(定価27,000円の
ところ24,300円(税込み))にて展示販売を行います.
#150 Lecture Series on " Future Urban Mobility and Public Transportation -Challenges and Values- "
Date
2017年4月25日
Venue
広島大学,神戸大学,東京工業大学,東北大学
Lecture Series on " Future Urban Mobility and Public Transportation -Challenges and Values- "
#149 Public transport spatiotemporal analysis with reduced data sources availability
Date
2017年4月18日
Venue
京都大学桂キャンパスCクラスター C1-312(C1棟会議室3)
Public transport spatiotemporal analysis with reduced data sources availability
#148 Integration of Active Mobility and Public Transport in Taipei
Date
2017年4月5日
Venue
東京工業大学 蔵前会館 手島精一記念会議室
Integration of Active Mobility and Public Transport in Taipei
ベルギーにて海外研究グループとの共同セミナーを開催しました.
ベルギーにて海外研究グループとの共同セミナーを開催しました.
INTERNATIONAL SEMINAR ON INTEGRATION OF SPATIAL COMPUTABLE GENERAL EQUILIBRIUM AND TRANSPORT MODELLING – Economic modeling and application for urban policy –
1 Introduction
While so far in transport modelling the assumptions concerning product markets and labor markets have been rudimentary, also in economic geography models connection to the transport system models is done with little detail. Integrating economic geography models with transportation models still requires progress in
– The understanding of behavioral principles of the two subsystems:
– Mathematical modelling of joint passenger/freight systems,
– Estimation approaches for combined models
– Applications at global, national, regional and urban scale.
– Economic evaluations of transport projects in Europe and Asia.
The contributors will present recent development of this fields and further discussion. Different modelling issues will be introduced by speakers (origin of the problem, state of the art, solution paths, work needed) and discussed in the seminar.
2. Seminar Outline
Date March-28th, 2017
Venue Kobe University Brussels European Centre (KUBEC),
(Boulevard de la Plaine 5 Pleinlaan, 5th floor Bruxelles 1050 Brussel)
Host Kobe University & TU Delft
Chairs Professor Atsushi KOIKE, Kobe University
Professor Lori Tavasszy, TU Delft
3. Conference Program
March 28th
10:30-10:40 Opening Address
Lori Tavasszy (TU Delft)
10:45-12:15 Session 1
Contributors:
Atsushi Koike (Kobe University)
Lori Tavasszy (TNO/TU Delft)
Toshimori Otazawa (Kobe University)
12:15-13:30 Lunch Break
13:30-14:30 Session 2
Contributors:
Koen Mommens (Free University Brussels)
Hajime Seya (Kobe University)
14:30-15:00 Short Break
15:00-16:30 Session 3
Contributors:
Ronald Halim (TU Delft)
Tomoki Ishikura (Tokyo Metropolitan University)
16:30-16:40 Closing Remarks
Atsushi Koike (Kobe University)
#147 Disaster Adaptation Investment with Inter- and Intra-port Competition and Cooperation
Date
2017年3月27日
Venue
京都大学桂キャンパスCクラスター C1-2棟 3階 314会議室
Disaster Adaptation Investment with Inter- and Intra-port Competition and Cooperation
地域アセット実装小委員会 研究会開催報告
地域アセット実装小委員会 研究会開催報告
#146 22nd Tokyo Tech TSU Seminar Transport Policies in Asia: Cases from Sri Lanka and Indonesia
Date
2017年3月16日
Venue
東京工業大学大岡山キャンパス石川台4号館地下B02-05
22nd Tokyo Tech TSU Seminar Transport Policies in Asia: Cases from Sri Lanka and Indonesia
健康・医療のまちづくりシンポジウム
健康・医療のまちづくりシンポジウム
日時:3月11日(土) 13:00~15:30
場所:関西大学 千里山キャンパス 第3学舎4号館 ソシオAV大ホール
内容
基調講演「国立健康・栄養研究所の健都移転による健康長寿まちづくりへの貢献」
米田悦啓 氏(国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 理事長)
パネルディスカッション「『健都』から始まる機能連携による新たな価値創造」
http://www.kansai-u.ac.jp/calendar/archives/2017/03/post_1243.html
研究会を開催しました.
研究会を開催しました.
日時:平成29年3月9日(木曜)~10日(金曜)
場所:神戸大学(六甲大第2キャンパス),C3-203(9日),C1-202(10日)
【話題提供者】
3月9日(木曜)
13:00~14:00 鳥取大学 桑野将司
14:00~15:00 名城大学 鈴木温
15:15~16:15 埼玉大学 大窪和明
16:15~16:45 東北工業大学 泊尚志
16:45~17:45 神戸大学 織田澤利守
3月10日(金曜)
10:00~11:00 神戸大学 地主遼史(博士後期1年生,研究経過発表会)
11:00~12:00 豊橋技術科学大学 松尾幸二郎
13:00~14:00 香川大学 中村一樹
14:00~15:00 広島大学 塚井誠人
15:00~16:00 首都大学東京 石倉智樹
International Workshop on Mobilities and Urban Policy
International Workshop on Mobilities and Urban Policy
The International Workshop on Mobilities and Urban Policy “Domestic Migration and its Consequences: Comparisons between Japan and China” was held at Graduate School for International Development and Cooperation (IDEC), Hiroshima University. This was sponsored by two research funds (Principal Researcher: Junyi Zhang): Grants-in-Aid for Scientific Research (B), JSPS (26303003: Trend of urbanization caused by rural migrant workers under the New China Urbanization Policy and its impacts on low-carbon urban development) and Grants-in-Aid for Scientific Research (A), JSPS (15H02271: Interdisciplinary research on policies promoting young people’s migration to and permanent residence in local cities). This workshop was also supported by the Committee of Infrastructure Planning and Management, Japan Society of Civil Engineers (JSCE). The program is show below.
Venue: IDEC, Hiroshima University
10:00 ~ 10:10 Welcome Remarks
10:10 ~ 11:10 Keynote Speech
Anming ZHANG, Prof., The University of British Columbia, Canada; Visiting Prof., IDEC, Hiroshima University, Japan
Connectivity of intercity transportation in China: A multi-modal and network approach
11:10 ~ 11:30 Studies on China (1)
Junyi ZHANG, Prof., Mobilities & Urban Policy Lab, IDEC, Hiroshima University
Review of China’ new-type urbanization policy
11:30 ~ 12:00 Studies on China (2)
Ying JIANG, Special Postdoctoral Researcher, Mobilities & Urban Policy Lab, IDEC, Hiroshima University
Rural migrant workers, future residence, and energy consumption under the influence of China’ new-type urbanization policy
12:00 ~ 13:30 Lunch time
13:30 ~ 14:00 Studies on China (3)
Linghan ZHANG, Doctoral Candidate, Mobilities & Urban Policy Lab, IDEC, Hiroshima University
Urban and Rural Connections: A case study on rural tourism in China
14:00 ~ 15:00 Book review: Moderated by Junyi ZHANG
Life-oriented Behavioral Research for Urban Policy (Springer; Editor: Junyi Zhang)
15:00 ~ 15:30 Studies on Japan (1)
Junyi ZHANG, Prof., Mobilities & Urban Policy Lab, IDEC, Hiroshima University
Domestic migration and public policies in Japan: A longitudinal analysis based on a discrete choice model with spatial context dependency
15:30 ~ 16:00 Studies on Japan (2)
Weiyan ZONG, Doctoral Candidate, Mobilities & Urban Policy Lab, IDEC, Hiroshima University
Internal migration and life choices in Japan: An analysis based on an extension of the theory of planned behavior
16:00 ~ 16:30 Studies on Japan (3)
David PEREZ BARBOSA, Doctoral Candidate, Mobilities & Urban Policy Lab, IDEC, Hiroshima University
High school students’ future life choices associated with social exclusion: A case study in Hiroshima Prefecture
16:30 ~ 17:10 Studies on Japan (4)
Hajime SEYA, Assoc. Prof., Graduate School of Engineering, Kobe University
A spatial analysis on net migration in Hyogo Prefecture
17:10 ~ 17:50 Studies on Japan (5)
Zhenjiang SHEN, Prof., Graduate School of Natural Science and Technology, Kanazawa University
Development of agent-based model for simulation on residential mobility affected by downtown regeneration policy
17:50 ~ 18:00 Closing remarks
#143 International Workshop on Mobilities and Urban Policy: Domestic Migration and its Consequences: Comparisons between Japan and China
Date
2017年3月8日
Venue
広島大学東広島キャンパス
International Workshop on Mobilities and Urban Policy: Domestic Migration and its Consequences: Comparisons between Japan and China
#145 Small International Workshop on Advanced Choice Modelling
Date
2017年3月6日
Venue
東京工業大学 創造プロジェクト館 1F 大会議室
Small International Workshop on Advanced Choice Modelling
#84 少子高齢社会における子育てしやすいまちづくり~都市のバリアと心のバリア~
Date
2017年3月4日
Venue
東京大学工学部14号館144講義室
少子高齢社会における子育てしやすいまちづくり~都市のバリアと心のバリア~
総合司会:青野貞康(計量計画研究所) 13:30-13:35 開会挨拶 13:35-15:50 講演・報告 1.「幼児同乗用自転車における思考発話法の効果」松村 暢彦(愛媛大学) 2.「日本の子どもの交通行動の変遷とその社会的影響」谷口 綾子(筑波大学) 3.「地下鉄駅内外の空間バリアがベビーカー利用者の駅アクセスに与える影響」丹 羽 由佳理(森記念財団都市整備研究所) 質疑応答(14:35-14:50) 4.「行政サービスが子育て世帯の居住地選択に与える影響分析」岡本 英晃(交通 エコロジー・モビリティ財団) 5.「「住み続けられる国土」と子育て」高柳 百合子(国土交通省国土政策局総合 計画課) 質疑応答(15:30-15:40) 15:40-16:00 休憩 16:00-17:10 パネルディスカッション テーマ:子育てしやすいまちの実現のために パネリスト:秋山 哲男(中央大学、日本福祉のまちづくり学会長) 杉浦 美奈(政策研究大学院大学) 北方 真起(Wa-Life Labo代表) 有賀 敏典(国立環境研究所) 司会:大森 宣暁(宇都宮大学) 17:10-17:15 閉会挨拶 17:30-19:00 懇親会@222アーバンコモンズ ※保育サービス(無料)あり
#144 Dynamic Risk Management of Transport Network - Social Interaction, Monitoring and Simulation
Date
2017年3月4日
Venue
東京工業大学_緑ヶ丘ホール
Dynamic Risk Management of Transport Network - Social Interaction, Monitoring and Simulation
地域づくりに資するITS等の活用に関する意見交換会(沖縄 第2回)
地域づくりに資するITS等の活用に関する意見交換会(沖縄 第2回)
日時:2017年3月3日(金) 15:30~17:30
場所:沖縄総合事務局
#83 これからの交通事故リスクマネジメント
Date
2017年3月2日
Venue
日本大学駿河台キャンパス1号館131教室
これからの交通事故リスクマネジメント
第1回研究小委員会を開催しました.
第1回研究小委員会を開催しました.
第1回応用一般均衡分析と交通分析の統合に関する研究小委員会
日時:2017年2月14日(火) 14時~16時
場所:神戸大学(自然科学3号館125号室)
参加者:
小池淳司,石倉智樹,織田澤利守,瀬谷創,山崎雅人,山本浩道,瀬木俊輔,高山雄貴,平松燈,佐藤啓輔
議事:
1.小池委員長より研究小委員会の趣旨ならびに活動方針に関する説明
2.フリーディスカッション
#142 航空輸送と高速鉄道
Date
2017年2月10日
Venue
神戸大学梅田インテリジェントラボラトリ
航空輸送と高速鉄道
講演会「まちづくりのVR その活用を考える」
講演会「まちづくりのVR その活用を考える」
日時:2月3日(金)15:00~
場所:関西大学 千里山キャンパス
先端機構 2階 2-1会議室
「まちづくりのVR その活用を考える」
パナソニック株式会社 エコソリューションズ社
コンサルティング事業グループ
環境計画VR推進チーム
長濱 龍一郎 氏
自転車利用環境向上会議2016@静岡
自転車利用環境向上会議2016@静岡
第2回モビリティ・マネジメント教育普及推進セミナー(JCOMMセミナー2017 in 滋賀)
第2回モビリティ・マネジメント教育普及推進セミナー(JCOMMセミナー2017 in 滋賀)
ITSミニンシンポジウム
ITSミニンシンポジウム
日時:2017年1月24日(火) ~25日(水)
場所:TKP市ヶ谷カンファレンスセンター、土木学会
ITSは地域の課題・ニーズにどう応えるか
~まちづくり、みちづくりにITSや最新技術はいかに役立つか?~
以下の韓国の研究者2名を招へいし議論を行なった。
Dr. Wonho Kim, Director, The Seoul Institute
Dr. Back Jin Lee, Research Fellow, Korea Research Institute for Human Settlement (KRIHS)
シンポジウム「エコメディカルな社会システム構築」
シンポジウム「エコメディカルな社会システム構築」
日 時:平成29年1月20日(金) 15:15~17:10
開催場所:関西大学 千里山キャンパス 100周年記念会館 第1会議室
(阪急千里線 関大前駅下車)
〔講 演〕
「世界の健康医療・健康長寿社会をリードする未来医療健康都市関西の創造」
講師:井垣 貴子 氏
(株式会社 健康都市デザイン研究所/株式会社 HRJ 代表取締役社長
/一般社団法人 医療国際化推進機構 理事・事務局長)
「日常「歩く」ことから捉えた健康まちづくりのための地区別評価」
北詰 恵一 教授
講演会「健幸ポイントとまちづくり」
講演会「健幸ポイントとまちづくり」
日 時:平成29年1月10日(火) 13:30~15:00
開催場所:関西大学 千里山キャンパス 学術フロンティア・コア3階会議室
(阪急千里線 関大前駅下車 徒歩約15分)
〔講 演〕 「健幸ポイントとまちづくり」
高石市スマートウェルネス推進室
室長 舩冨 学 氏
専門図書の出版 Life-oriented Behavioral Research for Urban Policy (Springer)
専門図書の出版 Life-oriented Behavioral Research for Urban Policy (Springer)
On January 2017, the book “Life-oriented Behavioral Research for Urban Policy”, Edited by Prof. Junyi Zhang, was formally published by Springer. This is the first book in literature to present a general picture of life choice research from the interdisciplinary perspective.
Even though various dialogues between different disciplines occur here and there, unfortunately, behavioral disciplines with truly interdisciplinary features could not be found in literature for supporting urban policy decisions, which are usually associated with various life domains. The life-oriented approach argues that people’s various life choices, being attributable to quality of life (QOL), are interrelated of each other. In other words, one life choice may not only results from other life choice(s), but also affect other life choice(s). Such interdependencies are essential to understand human decisions.
This book aims to present the life-oriented approach as one of the “common languages” to facilitate the “talk” between different stakeholders for improving people’s QOL.
The life-oriented approach also provides a fundamental theory for supporting research on young people.
地域アセット実装小委員会 研究会開催報告
地域アセット実装小委員会 研究会開催報告
2016年12月15日に第1回地域アセット実装小委員会 研究会を開催しました.
主な議題
・メンバーの活動共有
・研究会の方針,進め方協議
#141 Developing High-Speed Rail Hubs with Metro Extensions and Land Leases: Evidence from Wuhan, China
Date
2016年12月13日
Venue
東京大学本郷キャンパス工学部11号館
Developing High-Speed Rail Hubs with Metro Extensions and Land Leases: Evidence from Wuhan, China
地域づくりに資するITS等の活用に関する研究 -『地域における課題・ニーズ』に関する有識者アンケート
地域づくりに資するITS等の活用に関する研究 -『地域における課題・ニーズ』に関する有識者アンケート
土木学会では,この15年に渡って地域の交通をより賢くするためのITS研究を実施してきました.その活動は主として道路空間での渋滞解消や交通安全対策などが中心でした.
交通は地域の多様な活動を下支えするものであり,ITSは道路空間だけに限らず,公共交通空間やまち・地域空間でも積極的に課題解決に貢献し,さらには防災・医療・少子高齢化など地域が抱える多様な社会問題の解決にも貢献したいと考えております.
この問題意識に基づき,平成28年11月に土木計画学研究委員会内に「ITSとインフラ・地域・まちづくり研究小委員会」(研究代表者:清水哲夫首都大学東京教授)を設置いたしました.
小委員会ではITSの多様なニーズを把握し,新たな研究の可能性を模索するために,地域で多様な活動を展開されている有識者の方々に,日常の業務で解決が求められる課題について,幅広にご意見を伺いたいと考えております.
回答は以下のURLからお願いできれば幸いでございます.
(当面常時回答可能な状態にいたしますが)期限は2017年1月10日と設定しております.
http://committees.jsce.or.jp/opcet/its/enq2016
ご多用の折,はなはだご迷惑かと存じますが,ご協力をお願い申し上げます.
地域づくりに資するITS等の活用に関する意見交換会(京都)
地域づくりに資するITS等の活用に関する意見交換会(京都)
日時:2016年12月6日(火) 16:00~18:00
場所:TKP京都四条烏丸カンファレンスセンター
#140 メガシティにおける道路ネットワーク交通マネジメント
Date
2016年12月1日
Venue
御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター Room C
メガシティにおける道路ネットワーク交通マネジメント
地域づくりに資するITS等の活用に関する意見交換会(北海道)
地域づくりに資するITS等の活用に関する意見交換会(北海道)
日時:2016年11月29日(火) 13:30~15:30
場所:TKP札幌カンファレンスセンター
土木計画学春大会の企画論文募集(健康まちづくりのための社会システムデザインの展開)
土木計画学春大会の企画論文募集(健康まちづくりのための社会システムデザインの展開)
土木計画学春大会の企画論文を募集しますので、積極的な投稿をお願い致します。
第55回土木計画学研究発表会・春大会
実施期日:2017年6月10日(土)・11日(日)
実施場所:愛媛大学
発表希望者の論文題目・概要の登録 2016年12月9日(金)~2017年2月3日(金)
オーガナイザーによる採否決定期間 2017年2月17日(金)~2017年3月10日(金)
論文投稿 2017年4月28日(金)まで
部門テーマ名(日本語): 健康まちづくりのための社会システムデザインの展開
部門テーマ名(英語): The development of social system design for healthy cities
主オーガナイザー: 秋山 孝正
部門テーマ概要(日本語):
わが国は、平均寿命・健康寿命ともに世界最高水準であり、長寿健康社会を形成している。全国的にも、医療・健康を主体とする未来志向型のまちづくりの具現化を目指して、スマートウエルネスシティなどのさまざまな取り組みが進展している。ここでは、健康まちづくりにおける実践的な課題を取り上げる。すなわち、①基本的な都市構造・土地利用・インフラ構成、②健康まちづくりのシステム構成・社会制度、③住民参画・自律的な健康増進の推進、④都市のアクティビティ・健康コミュニティの形成などの具体的事例を取り上げる。最終的に、これらの議論を踏まえて、健康まちづくりのための社会システムデザインの基本事項を整理する。
部門テーマ概要(英語):
The healthy longevity society is created in Japan with the world longest average lifespan as well as healthy lifespan. Many activities such as smart wellness city have been known to develop future oriented medical and healthy cities. The practical issues in wellness city development are discussed in the session. The topics with practical examples are summarized as follows: (1) urban structure, land use, infrastructure, (2) urban system development, social systems, (3) participation by residents, autonomous health promotion (4) urban healthy activities, healthy life community. According to the above discussion, the fundamental elements of social system design for development of wellness cities.
#82 土木計画学における空間・経済・統計分析セミナー
Date
2016年11月25日
Venue
神戸大学六甲台第2キャンパス工学部LR棟501室
土木計画学における空間・経済・統計分析セミナー
#135 Carlos Daganzo 教授講演会(京都)
Date
2016年11月25日
Venue
ホテル日航プリンセス京都・ローズ
Carlos Daganzo 教授講演会(京都)
ワンデイセミナー「土木計画学における空間・経済・統計分析セミナー」を開催しました
ワンデイセミナー「土木計画学における空間・経済・統計分析セミナー」を開催しました
会場 神戸大学六甲台第2キャンパス自然科学総合研究棟3号館
日時 2016年11月25日(金)
10:25–10:30 主催者挨拶
10:30–12:00 空間統計学入門 瀬谷創(神戸大学・准教授)
13:00–14:30 統計的因果推論 織田澤利守(神戸大学・准教授)
15:00–16:30 空間的応用一般均衡分析 小池淳司(神戸大学・教授)
参加者:62名
#134 Carlos Daganzo 教授講演会(東京)
Date
2016年11月24日
Venue
東京工業大学,緑ヶ丘キャンパス,緑ヶ丘6号館1F緑ヶ丘ホール
Carlos Daganzo 教授講演会(東京)
地域アセットマネジメント実装イベント②
地域アセットマネジメント実装イベント②
岐阜県中津川市神坂地域におけるインフラ協働点検の実施を実施しました.
#139 Workshop on Frontiers of Multi-Hazard Mitigation Strategies in Urban Areas
Date
2016年11月7日
Venue
Room No.211, Lecture Hall 2, Yokohama National University (Campus Map N4-3)
Workshop on Frontiers of Multi-Hazard Mitigation Strategies in Urban Areas
第54回土木計画学研究発表会・秋大会
第54回土木計画学研究発表会・秋大会
土木計画学研究委員会は下記の概要で2016年の秋期における土木計画学研究発表会(秋大会)を開催します。
発表プログラム
プログラム(司会者確定版,2016.10.06. updated)
発表要領
参加申込
Web(事前申込〆切:2016年10月20日.講演申し込みをされた方は事前参加申込を行う必要はありません.)
事前参加申込注意事項(必ずお読みください)
会告について
講演用論文
発表会の当日に十分な時間で充実した議論を行い、更なる研究の発展や学術論文等への取りまとめに繋げることが本発表会の特色です。このため、「具体的に議論したい点(研究の新規性や枠組み、データ、モデルや結論の妥当性、今後の発展性や疑問点など)」を明記して申込みしていただきます。話題性、速報性のある論文や、調査・計画、技術検討等の事例報告も歓迎します。提出された講演用論文は、原則として無審査で掲載されますが、会場の制約等によってお断りすることもあります。
今発表会では、試行的に、通常の発表希望分野Ⅲと並行して、発表希望分野Ⅰ(特別論文セッション)及び発表希望分野Ⅱ(手法等分野横断的区分)での発表希望もお願いしています。こちらへの応募もよろしくお願いします。
なお、ポスターセッションを今年度も実施いたします。口頭発表とポスターでの発表のどちらを希望するかを選んで申込んでいただきます(口頭発表およびポスターでの発表のいずれも、「土木学会論文集D3(土木計画学), Vol.73, No.5(土木計画学研究・論文集34巻)」への投稿対象となります)。
※2017年発行予定の「土木学会論文集D3(土木計画学), Vol.73, No.5(土木計画学研究・論文集34巻)」及びそれ以降の巻への投稿には、
① 投稿時点から過去2年以内の土木計画学研究・講演集に掲載され、文量が2ページ以上の論文である
② 研究発表会において、著者により当該論文の発表が行われている(発表が行われていない,または著者以外によって発表された論文は投稿不可)ことが必要となりますので、あらかじめご了承ください。
講演の申込み
(1) 申込みの手続きおよび注意点
2016年7月1日(金)~7月31日(日)17時までの期間内に、
土木計画学研究発表会(秋大会)講演申込みページ申込画面より、講演申込と講演原稿の投稿を同時に行ってください。原稿のファイル形式はPDF形式のみ受付けます。 原稿は「講演原稿執筆要領」に従ってご執筆ください。締切日当日までは、投稿した原稿の確認、差し替えが可能ですが、締切日以降は、原稿の差し替えは受け付けられません。十分、ご注意ください。投稿時に、必ず申込内容が正しいか、PDFの取り違えての投稿がないか、申込内容とPDFのタイトル等の差異がないかなどをご確認ください。申込み期間の締切り間際に投稿が集中しますと、予期せぬ事態によりサーバーがダウンし受付ができなくなる恐れがあります。締切り間際の投稿は極力避けていただくようお願いいたします。
なお、講演原稿執筆要領に準じていないもの、および期限後に投稿されたものは受理できません。必ず所定の原稿を期間内にWEB上にて投稿してください。
間違えたファイルを提出した場合や申込内容とPDFの内容が違う場合であっても、そのまま掲載されますので、ご注意ください。
(2) 発表希望分野
(i) 発表希望分野Ⅰ(特別論文セッション)
今回の秋大会では、充実した議論を実現するための、「特別論文セッション」を実施いたします。特別論文セッションでは、論文内容を踏まえたコメントに基づいた議論を行います。ただし、投稿論文数(最大で30編程度)、論文内容により、発表希望分野IIIでの発表となる場合もあります。
・1件当たりの持ち時間は、発表25分、コメンテーターによるコメント10分、討議10分の計45分とします。
・特別論文セッションでの発表を希望される方は、8ページ以上の論文を投稿することが必要です。
・発表者は投稿時にコメンテーター希望者を伝えることができます。
(ii) 発表希望分野II(手法等分野横断的区分)
従来の研究対象ごとの発表区分に加えて、研究で用いられている方法論に注目した分野横断的区分でのセッション構成を検討しています。分野横断的区分セッションで発表を希望される場合には、今回は以下の5つから選択いただけます。さらに、そのセッションの司会兼コメンテーターでご希望の先生がいればご記入いただけます。これらの情報を参考に、専門性の高い先生への司会依頼を行うなどの検討を行う予定です。ただし、適切なセッションを組めない場合には、上記の発表希望分野Ⅰの従来型のセッションでの発表になります。
・新分析手法(まだ適用事例の少ない統計的手法(例.機械学習的分析手法)や記述的研究(例.物語研究)などの有効性等を議論したい研究)
・理論モデリング(実現象の理論的なモデリング、情報科学やゲーム理論などを駆使した手法について議論したい研究)
・統計分析解釈(一般的な統計分析の考察が重要な位置を占めており、その内容や妥当性について重点的に議論したい研究)
・海外事例(海外の事例的研究として集中的に議論したい研究)
・その他、重点的に議論したい分野横断的内容があればそのキーワードを直接書いていただくことも可能
(iii) 発表希望分野III(研究対象区分)
申し込みに際して、発表希望分野を下記の5つの発表分野から希望順に2つ選んでください。また、キーワードにつきましては、同キーワード欄の中から最大4つ選んでください。なお、適当なキーワードが見つからない場合は、投稿者の判断によるキーワードを1つだけ加えてください。
発表希望分野
| 発表希望分野 | キーワード |
| A 計画論・計画情報 | 計画基礎論、計画手法論、システム分析、調査論、公共事業評価法、財源・制度論、プロジェクト構想、施工計画・管理、維持管理計画、意識調査分析、計画情報、情報処理、市民参加、GIS、リモートセンシング、測量、環境計画、防災計画、河川・水資源計画、ライフライン計画・設計、地球環境問題 |
| B 地域・都市・景観 | 国土計画、地域計画、都市計画、地区計画、住宅立地、産業立地、人口分布、地価分析、土地利用、市街地整備、再開発、景観、公園・緑地、観光・余暇、空間設計、イメージ分析、土木史 |
| C 交通現象分析 | 発生交通、目的地選択、交通手段選択、経路選択、出発時刻選択、活動分析、時間利用、交通行動調査、交通意識分析、交通行動分析、自動車保有・利用、駐車需要、交通ネットワーク分析、土地利用・交通・環境統合モデル、観光・余暇行動 |
| D 交通基盤計画 | 総合交通計画、地区交通計画、公共交通計画、歩行者・自転車交通計画、道路計画、鉄道計画、空港・港湾計画、ターミナル計画、駐車場計画、物流計画 |
| E 交通運用管理 | 交通流、交通容量、サービス水準、交通制御、交通管理、交通安全、交通情報、交通環境、公共交通運用、交通弱者対策、水上交通、空港管理、交通量計測、TDM、ITS、モビリティマネジメント(MM) |
(3) 発表形式
口頭発表とポスターでの発表のどちらを希望するかを選んでいただきます。なお、会場の都合でご希望に添えない場合もありますので予めご了承下さい。
(4) 投稿料
講演1本につき投稿料(参加費含む)として一般12,000円、学生9,000円を請求いたします。2本以上投稿する方については、2本目以降の投稿料は一般・学生ともに6,000円を請求いたします。振込手数料は各自でご負担願います。
講演原稿執筆要領
講演原稿の書式・形式は、土木学会論文集のものに準じています。下記の作成例やサンプルファイルをご利用ください。講演原稿では、英文アブストラクトの記入は任意です。その他書式・形式についての詳細は土木学会論文集の原稿作成の手引き等をご参照ください。なお、「土木学会論文集D3(土木計画学), Vol.75-6」への投稿の際には英文アブストラクトは必要です。
サンプルファイル 和文(Word2000)/English(Word2000)
原稿作成例 和文(PDF)/English(PDF)
お問合せ先
土木計画学研究委員会大会運営小委員会(春大会担当:橋本,氏原,林)
E-mail:keikaku59@jsce.or.jp
問合先
土木計画学研究委員会・学術小委員会 E-mail:keikaku54@jsce.or.jp
以下の該当する部分を熟読のうえ、手続きを取っていただけますようお願いいたします。
#6 秋大会企画「実践と研究を接続する」
Date
2016年11月4日
Venue
長崎大学中部講堂
#6 秋大会企画「実践と研究を接続する」
土木計画学秋大会50周年記念企画「実践と研究を接続する」
日時:2016年11月4日 13:00-14:30
場所:長崎大学中部講堂
土木計画学50周年記念シンポジウムの議論を受けて,土木計画学を代表する研究者が,
優れた実践・リサーチを生み出す場をこれまでどのようにつくってきたか,そして
これからどうつくっていくのかについて議論し,これからの土木計画学の方向性を探る.
また,4回にわたる関連行事の総括を行う.
司会:藤原章正 (土木計画学研究委員会副委員長/広島大学)
(1)はじめに
屋井鉄雄(土木計画学研究委員会委員長/東京工業大学)
(2)これまでの50周年関連行事の活動報告と今後への提言
これまでの3つの50周年記念行事での成果や議論を振り返りながら,今後の土木計画学の活動密度を更に高めるための提言を行なう.
若手特命チーム(塚井・大西・山口・原),プレゼンター:山口敬太(京都大学) 発表資料
(3)今後の土木計画学を考えるパネルディスカッション (60分)
土木計画学50周年関連イベントの総括や若手研究者からの提言を参照しながら,
現場に基づく理論・理論に基づく実践を進めて行くために,これまで自分たちが
どのような取り組みを行なってきたかの発表を行い,土木計画学における研究・
実践スタイルとその課題について議論する.そして,産学官すべての立場が今後
どのように活動を行なうべきか,土木計画学を希望する学生や若手技術者,中堅・
シニアの研究者・技術者はどのようにして土木計画学を盛り上げて行く必要があるか
について,フロアも含めて議論する.
塚井誠人(広島大学,若手特命チーム) 発表資料1
青木俊明(東北大学) 発表資料2
毛利雄一(一般財団法人 計量計画研究所) 発表資料3
(4)総括
羽藤英二(土木計画学研究委員会幹事長/東京大学)
2016春〜2016秋までの活動記録
2016春〜2016秋までの活動記録
■活動記録
第2回自転車通行システム研究会(16名参加)
日 時 2016年7月11日(月) 16:30-20:45
場 所 日本大学理工学部駿河台キャンパス 5号館2階524会議室
16:30-18:00 研究会
山中英生 研究の進め方 10分
話題提供 研究内容の共有 各20分程度 4名
18:30-20:45 勉強会
自転車の行動改善にむけた勉強会
行動分析学の考え方(仮題)講演 杉山尚子先生(星槎大学)
自転車の行動改善ミニワークショップ
こども自転車国際WS&セミナー
ワークショップ(国内3カ所開催)
尼崎10/9(21名)
京都10/10(21名)
金沢10/16(23名)
セミナー(国内4カ所開催)
大阪10/9(17名)
京都10/10(30名)
東京10/13(50名)
金沢10/16(12名)
#138 Karima Kourtit 博士 (スウェーデン王立工科大学) 特別講演会
Date
2016年10月12日
Venue
北海学園大学山鼻キャンパス3号館3階 3A教室
Karima Kourtit 博士 (スウェーデン王立工科大学) 特別講演会
#81 超高齢社会2020に向けた移動権に関するセミナー
Date
2016年10月8日
Venue
ハロー貸会議室西新宿駅前(東京都新宿区西新宿6-12-7 ストーク新宿1F)
超高齢社会2020に向けた移動権に関するセミナー
#133 Sustainable Land Use and Transport Planning for High-Density City
Date
2016年10月8日
Venue
東京工業大学,緑ヶ丘キャンパス,緑ヶ丘6号館1F
Sustainable Land Use and Transport Planning for High-Density City
#136 Moshe Ben-Akiva 教授講演会(名古屋)
Date
2016年9月28日
Venue
名駅モリシタ名古屋駅前中央店 7階の第2+3会場
Moshe Ben-Akiva 教授講演会(名古屋)
#5 土木計画学50周年記念シンポジウム「土木計画学の未来 〜理論に基づく実践、現場に根ざした理論〜」
Date
2016年9月26日
Venue
東京大学弥生講堂一条ホール
土木計画学50周年記念シンポジウム「土木計画学の未来 〜理論に基づく実践、現場に根ざした理論〜」
土木計画学50周年記念シンポジウム
土木計画学の未来 〜理論に基づく実践、現場に根ざした理論〜
シンポジウム資料集 PDF
土木計画学研究委員会は、「土木技術者の活動範囲において、土木に関する計画の分野がきわめて重要なる事態に鑑み、土木計画のあるべき姿、その問題点を検討し、あわせて計画に関する調査、研究を行うこと」を目的として昭和41(1966)年に設立され、今日に至っています。以降、社会基盤整備とその需要予測や費用便益分析、景観デザイン、まちづくりとその合意形成に関する活動等の幅広い分野において、理念や方法・手順の研究とその社会実装としての実践を行ってきました。今年は土木計画学研究委員会かが設立されてから50周年となる記念すべき節目となる年です。
そこで、土木計画学50周年を記念し、土木計画学の未来を考える50周年記念シンポジウムを開催致します。開催にあたって、土木計画学50周年記念事業実行委員会(委員長:桑原雅夫、副委員長:久保田尚)を設立し、「土木計画学の未来~理論に基づく実践、現場に根ざした理論~」をテーマとして、土木計画学の理論と実践のかたちを辿り、語り合い、描くことで、土木計画学のこれからを皆様とともに考える機会とします。第1部では、長年にわたって日本の土木計画学と関わりの深いマサチューセッツ工科大学のBen-Akiva教授を基調講演にお迎えし、これまでの土木計画学の成果や社会の中で果たしてきた役割を辿ります。第2部では、土木計画学やその関連分野において研究と実践の第一線で活躍されてきた先生方から、優れた実践・研究を下支えしてきた実践哲学について語って頂きます。第3部では、土木計画学の若手研究者が中心となって、理論に基づく実践と現場に根ざした理論の両輪を実現する土木計画学の未来を描きます。土木計画学の今日的課題と各研究者のもつ問題意識を共有し、これからの土木計画学が向かうべき方向性とそのためのアクションについて、フロアとともに議論します。是非ご参加ください。
会 場: 東京大学弥生講堂一条ホール
プログラム
第1部:「辿る」
1984年の土木学会論文集において招待論文を寄せられるなど、長年にわたって日本の土木計画学と関わりの深いマサチューセッツ工科大学のBen-Akiva教授を基調講演にお迎えし、土木学会の100年ビジョンとの関連性や社会の中での土木計画学の役割・期待などについて議論することで、これまでの土木計画学の成果や社会の中で果たしてきた役割を辿ります。
10:00~10:05 開会の辞 桑原雅夫(東北大教授、土木計画学50周年記念事業委員長)
10:05〜10:10 挨拶 田代民治(土木学会会長)
10:10~10:50 基調講演:リサーチと実践 Moshe Ben-Akiva (MIT教授)
10:50〜11:20 これまでの土木計画学-土木学会100周年を超えて- 屋井鉄雄(東京工業大教授)
11:30〜12:15 社会の中での土木計画学のあり方
パネルディスカッション司会:久保田尚(埼玉大教授)
パネリスト:森昌文(国土交通省技監)
中井雅彦 (JR 東日本 常務取締役)
藤井聡(京都大教授)
第2部:「語らう」
これまで土木計画学やその関連分野において、研究と実践の第一線で活躍されてきた先生方から優れた実践・研究を下支えしてきた実践哲学について語って頂きます。
4名の先生方の講演の中から、土木計画学のこれからを描くための輪郭を浮かび上がらせます。
13:30〜13:55 土木計画学の成果と課題 森地茂(政策研究大学院大教授)
13:55〜14:20 戦略的まちづくりの時代 内藤廣(建築家・東京大名誉教授)
14:30〜14:55 土木計画学を取り巻く環境と未来 小林潔司(京都大教授)
14:55〜15:20 国際的視点と実践・リサーチ 藤野陽三(横浜国立大上席特別教授)
第3部:「描く」
土木計画学の若手研究者が中心となって、理論に基づく実践と現場に根ざした理論の両輪を実現する土木計画学の未来を描きます。土木計画学の今日的課題と各研究者がもつ問題意識を共有するために、各研究者のこれまで/これからの研究を土木計画学の理論と実践の1つのかたちとして位置付け、これからの理論と実践の研究スタイルを模索します。そして、これからの土木計画学が向かうべき方向性とそのためのアクションについて、パネルディスカッションの中でフロアとともに議論します。
企画:若手特命チーム (塚井誠人(広島大准教授)・大西正光(京都大准教授)・
山口敬太(京都大助教)・原祐輔(東北大助教))
15:40〜15:50 本セッションの企画意図と土木計画学の現状認識 若手特命チーム
15:50〜16:05 理論-実践の両輪を目指して 力石真(広島大特任准教授)
16:05〜16:20 理論-実践の両輪を目指して 松田曜子(長岡技術科学大准教授)
16:20〜16:35 理論-実践の両輪を目指して 瀬谷創(神戸大准教授)
16:35〜16:50 理論-実践の両輪を目指して 若手特命チーム
16:50〜17:50 パネルディスカッション
パネリスト: 赤松隆(東北大教授)
多々納裕一(京都大教授)
上記プレゼンター17:50〜18:00 閉会の辞 屋井鉄雄(土木計画学研究委員会委員長)
18:20〜 懇親会 @弥生講堂アネックス
#137 7th International BinN Seminar
Date
2016年9月25日
Venue
東京大学工学部1号館15番教室
7th International BinN Seminar
#80 災害時対応~復興支援と災害調査-熊本地震の経験を踏まえて-
Date
2016年9月17日
Venue
岐阜大学サテライトキャンパス(岐阜スカイウイング37 東棟4階)
災害時対応~復興支援と災害調査-熊本地震の経験を踏まえて-
英文専門図書の出版予定: Life-oriented Behavioral Research for Urban Policy
英文専門図書の出版予定: Life-oriented Behavioral Research for Urban Policy
A book titled “Life-oriented Behavioral Research for Urban Policy” will be published soon by Springer (editor: Prof. Junyi Zhang, Hiroshima University) (in press)
Summary
This book presents a life-oriented approach, which is an interdisciplinary methodology proposed for cross-sectoral urban policy decisions such as transport, health, and energy policies. Improving people’s quality of life (QOL) is one of the common goals of various urban policies on one hand, while QOL is closely linked with a variety of life choices on the other. The life-oriented approach argues that life choices in different domains (e.g., residence, neighborhood, health, education, work, family life, leisure and recreation, finance, and travel behavior) are not independent of each other, and ignorance of and inability to understand interdependent life choices may result in a failure of consensus building for policy decisions. The book provides evidence about behavioral interdependencies among life domains based on both extensive literature reviews and case studies covering a broad set of life choices. This work further illustrates inter-behavioral analysis frameworks with respect to various life domains, along with a rich set of future research directions. This book deals with life choices in a relatively general way. Thus, it can serve not only as a reference for research, but also as a textbook for teaching and learning in varied behavior-related disciplines.
Unique Selling Points
– Presents a series of life-oriented behavioral studies for public policies by linking them with the quality of life mainly in an urban context
– Provides extensive literature reviews about how interdependent life choices have been captured in different disciplines
– Introduces new empirical evidence of behavioral interdependencies within and across life domains based on a broad set of life-choice data
– Illustrates inter-behavioral analysis frameworks with respect to various life domains (e.g., such as migration, job, residence, travel, health, leisure and tourism, energy consumption)
Contents
Chapter 1 Life-oriented Approach (Junyi ZHANG)
Chapter 2 Empirical Evidence of Behavioral Interdependencies across Life Choices (Yubing XIONG, Junyi ZHANG)
Chapter 3 Lifestyles and Life Choices (Veronique Van ACKER)
Chapter 4 The Car-dependent Life (Junyi ZHANG, Masashi KUWANO, Makoto CHIKARAISHI, Hajime SEYA)
Chapter 5 Household Energy Consumption Behavior (Biying YU, Junyi ZHANG)
Chapter 6 ICT-dependent Life and Its Impacts on Mobility (Giovanni CIRCELL)
Chapter 7 Health-related Life Choices (David PÉREZ BARBOSA, Junyi ZHANG)
Chapter 8 Life-oriented Tourism Behavior Research (Linghan ZHANG, Lingling WU, Junyi ZHANG)
Chapter 9 Influence of Land Use and Transport Policies on Women’s Labor Participation and Life Choices (Yubing XIONG, Junyi ZHANG)
Chapter 10 Mobility of the Elderly (Makoto CHIKARAISHI)
Chapter 11 Risky Behaviors in Life: A Focus on Young People (Ying JIANG, Junyi ZHANG)
Chapter 12 Adaptation of Behavior to Overcome Natural Disasters (Qing-Chang LU, Junyi ZHANG, Lingling WU, A.B.M. Sertajur RAHMAN)
Chapter 13 Mobility Biographies and Mobility Socialisation – New Approaches to an Old Research Field (Joachim SCHEINER)
Chapter 14 Biographical Interactions over the Life Course: Car Ownership, Residential Choice, Household Structure, and Employment/Education (Biying YU, Junyi ZHANG)
Chapter 15 Household Time Use Behavior Analysis: A Case Study of Multidimensional Timing Decisions (Junyi ZHANG, Harry TIMMERMANS)
Chapter 16 Models of Behavioral Change and Adaptation (Soora RASOULI, Harry TIMMERMANS)
Chapter 17 Behavioral Changes in Migration Associated with Jobs, Residences, and Family Life (Junyi ZHANG, Yubing XIONG, Ying JIANG, Nobuhito TANAKA, Nobuaki OHMORI, Ayako TANIGUCHI)
Chapter 18 Future Perspectives of the Life-oriented Approach (Junyi ZHANG)
#4 土木学会全国大会研究討論会「土木計画学50年の研究成果 -実践とリサーチの観点から-」
Date
2016年9月9日
Venue
東北大学川内北キャンパス C棟102教室
土木学会全国大会研究討論会「土木計画学50年の研究成果 -実践とリサーチの観点から-」
土木計画学50年の研究成果 -実践とリサーチの観点から-
http://www.jsce.or.jp/taikai2016/campus.html
(東北大学川内北キャンパス、地下鉄東西線「川内駅」下車徒歩1分)
http://committees.jsce.or.jp/zenkoku/
Six International Conference on Transportation Research (TLOG 2016)の開催
Six International Conference on Transportation Research (TLOG 2016)の開催
2016.9.7-9の3日間で,台湾の国立交通大学(新竹市)において表記会議が開催され,Prof. Bellによる基調講演,パネルディスカッション,academic trackとpractical trackを併せ61件の一般発表,および見学会(台北新港,桃園空港貨物ターミナル,物流センター)が行われました.
会議HP↓
http://tlog2016.conf.tw/site/Page.aspx?pid=901&sid=1082&lang=en
なお,次回は2018年夏または秋に大連海事大学(中国)にて開催予定です.
#132 Freight data collection and sensing: some research prospects
Date
2016年8月25日
Venue
東京大学本郷キャンパス工学部11号館 3階国際プロジェクト研究室セミナールーム
Freight data collection and sensing: some research prospects
#131 Developing effective O-D flow estimation/updating using traffic counts: Results and research prospects
Date
2016年8月12日
Venue
京都大学桂キャンパスCクラスター C1-312(C1棟会議室3)
Developing effective O-D flow estimation/updating using traffic counts: Results and research prospects
#130 Collaborating Research, Business(Industrial), Administration, Teaching into better transport environment
Date
2016年7月28日
Venue
Room 332, Building No.3, Kagurazaka Campus, Tokyo University of Science
Collaborating Research, Business(Industrial), Administration, Teaching into better transport environment
#128 An Infrastructure Based Approach Toward Connected Automated Vehicle-Highway System
Date
2016年7月25日
Venue
Lecture Room No.14, Engineering Building No.1, Hongo Campus The University of Tokyo
An Infrastructure Based Approach Toward Connected Automated Vehicle-Highway System
ウィスコンシン大学のRan Bin教授をお招きして,米国におけるインフラベースのITSに関するご講演をいただきます.詳細は,以下の通りです.ご関心のある方は是非ともご参加ください.
- 日時:2016年7月25日(月)16:30-18:00
- 場所:東京大学本郷キャンパス工学部1号館
(http://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/cam01_04_02_j.html)1階14号教室 - 発表タイトル:An Infrastructure Based Approach Toward Connected Automated Vehicle-Highway System (発表内容の概略については,英文をご覧ください)
- Ran Bin教授について:1986年に清華大学を卒業後,1989年に東京大学で修士号取得し,その後イリノイ大学シカゴ校でPhDを取得.MITやカリフォルニア大学バークレー校に滞在した経験もある.現在,ウィスコンシン大学マディソン校においてITSプログラムのディレクターをしている.専門は,動的交通ネットワークモデル,交通シミュレーション,交通情報システムなど.詳細は,英文をご覧下さい.
- 言語:英語
- 参加費用:無料
- お問い合わせ:
東京大学大学院工学系研究科 羽藤英二教授(hato[@]civil.t.u-tokyo.ac.jp)
東京大学大学院工学系研究科 加藤浩徳教授(kato[@]civil.t.u-tokyo.ac.jp)
We invite you to a special international seminar on ITS where Professor Ran Bin, Professor and Director of ITS Program at the University of Wisconsin at Madison, will make a short talk about the infrastructure-based ITS in the United States. Anybody who is concerned with his talk can join it. The details are shown below. Please contact Prof. Hironori Kato (kato[@]civil.t.u-tokyo.ac.jp) for more details.
- Time and day: From 4:30pm to 6:00 pm on July 25 (Monday), 2016
- Place: Lecture Room No.14, Engineering Building No.1, Hongo Campus The University of Tokyo (Campus map is available at http://www.u-tokyo.ac.jp/en/index.html)
- Presentation Title: “An Infrastructure Based Approach Toward Connected Automated Vehicle-Highway System”
- Abstract:
Internet companies and auto makers have been focusing on developing a vehicle-centric platform for connected vehicle and autonomous driving. This presentation presents an alternative approach, which is infrastructure based and could be more cost-effective and reliable. This presentation will discuss various definitions of Connected and Automated Vehicle-Highway System. In developing these systems in the next few decades, the active roles of transportation planning, design and management agencies and organizations will be presented. In addition, this presentation will discuss about the system architecture, major technologies, and the roadmap to achieve the four levels of automation and connectivity defined by the US DOT in 2015. The system designs, R&D efforts, challenges, and international collaboration will be discussed as well.
- About Professor Ran Bin:
Dr. Bin Ran is a Professor and Director of ITS Program at the University of Wisconsin at Madison. He also served as the Director of the Traffic Operations and Safety Lab (TOPS) at the University of Wisconsin at Madison. Dr. Ran holds the title of National Distinguished Expert in China. Dr. Ran is also the Director for Southeast University – University of Wisconsin Joint Research Institute on Internet of Mobility, which is an international collaborative effort between China and US.
Dr. Ran is an expert in dynamic transportation network models, traffic simulation and control, traffic information system, Internet of Mobility, and Connected Automated Vehicle-Highway System. He has led the development and deployment of various traffic information systems and technologies in the US and China. He has trained younger generations of professors and experts in traffic engineering and Intelligent Transportation Systems (ITS) in the US, China, Korea, and other countries.
Dr. Ran is the author of two leading textbooks on dynamic traffic networks. He has co-authored more than 130 journal papers and more than 220 referenced papers at national and international conferences. He co-authored 6 books on intelligent highways in China. He holds 3 US patents and 10 Chinese patents, and has a few patents pending in the US and China. He is an associate editor of Journal of Intelligent Transportation Systems. He is the Founding President of North America Chinese Overseas Transportation Association (NACOTA, currently named as Chinese Overseas Transportation Association or COTA) from 1996 to 1998.
Earlier in his career, Dr. Ran held positions at the Massachusetts Institute of Technology and the University of California at Berkeley. He is active in the Transportation Research Board and Intelligent Transportation Society of America. Dr. Ran received his PhD from the University of Illinois at Chicago in 1993, his MS from the University of Tokyo in 1989, and his BS from Tsinghua University in 1986.
- Language: English
- Fee: Free of charge
- Contact: Professor Eiji Hato, The University of Tokyo (hato[@]civil.t.u-tokyo.ac.jp) or Professor Hironori Kato, The University of Tokyo (kato[@]civil.t.u-tokyo.ac.jp)
#129 Influences of Intercity Transportation on Economic Development
Date
2016年7月19日
Venue
東京大学本郷キャンパス工学部11号館3階国際プロジェクト研究室セミナールーム
Influences of Intercity Transportation on Economic Development
Seminar on Smart and Connected Communities
Seminar on Smart and Connected Communities
Time:
15:00 – 17:00, July 15, 2016
Topic:
Toward Smart and Connected Communities: Challenges and Opportunities in Transportation
(abstract: see below)
Lecturer:
Prof. Yinhai Wang, University of Washington, USA
Venue:
Large Meeting Room, Graduate School for International Development and Cooperation, Hiroshima University
///////////////////////////////////////////////////////
Abstract:
Transportation involves human, infrastructure, vehicle, and environmental interactions and is therefore a very complicated system. Transportation activities are found affecting public health, air quality, sustainability, etc., and thus tie to everyone’s daily life and are critical for achieving goals of smart and connected communities. Traditionally, transportation has been studied through classical methods, typically with ideal assumptions, limited data support, and poor computing resources. While the theories (such as traffic flow and driver behavior models) developed through these efforts provide valuable insights in understanding transportation-related issues, they are often ineffective in large-scale transportation system analysis with massive amount of data from various sources. With recent advances in sensing, networking, and computing technologies, more and more cities and communities have launched their smart cities/communities plans to improve quality of life, sustainability, efficiency, and productivity. Sensor networks are fundamental elements of smart cities and the data they produce have the potential of generating the intelligence needed to make urban transportation smarter. We expect that many new transportation-related data and computational resources will become available in the smart cities context. These new assets are likely to bring in new opportunities to understand transportation systems better and address those critical transportation issues in a faster, more accountable, and more cost-effective way. To take advantage of these big data, a new theoretical framework and its supporting platform are clearly needed to integrate the quickly growing massive amount of data, typically from numerous sources of varying spatial and temporal characteristics, into the large-scale transportation problem solving and decision making processes. Efforts along this line are likely to form up a new subject area, namely e-science of transportation, in the years to come. Through his talk, the speaker will share his vision and pilot research on extracting transportation big data streams from the smart cities sensor networks and demonstrate the values of these data in large-scale system analysis and decision support through an online regional-map-based data platform named Digital Roadway Interactive Visualization and Evaluation Network (DRIVE Net).
Short bio of the lecturer:
Dr. Yinhai Wang is a professor in transportation engineering and the founding director of the Smart Transportation Applications and Research Laboratory (STAR Lab) at the University of Washington (UW). He also serves as director for Pacific Northwest Transportation Consortium (PacTrans), USDOT University Transportation Center for Federal Region 10. Dr. Wang has a Ph.D. in transportation engineering from the University of Tokyo (1998) and a master’s degree in computer science from the UW. Dr. Wang’s active research fields include traffic sensing, smart transportation systems, e-science of transportation, transportation safety, etc.
Dr. Wang has actively involved in numerous research projects and received over $53 million of research funds as principal investigator over the past fifteen years. He has published over 110 peer-reviewed journal articles, three edited books, one book chapter, and nearly 50 peer-reviewed conference papers. To disseminate research findings, he has delivered over 120 invited talks and nearly 200 other academic presentations.
Dr. Wang serves as a member of the Transportation Information Systems and Technology Committee and Highway Capacity and Quality of Service Committee of the Transportation Research Board (TRB). He is currently on the Board of Governors for the ASCE Transportation & Development Institute and a member of the steering committee for the IEEE Smart Cities. He was an elected member of the Board of Governors for the IEEE ITS Society from 2010 to 2013. Additionally, Dr. Wang is associate editor for three journals: Journal of ITS, Journal of Computing in Civil Engineering, and Journal of Transportation Engineering. He was the winner of the ASCE Journal of Transportation Engineering Best Paper Award for 2003. He was also a conference co-chair for the 2015 IEEE International Smart Cities Conference to be held in Guadalajara, Mexico from October 25 to 28 2015.
#127 International seminar on disaster management and humanitarian logistics
Date
2016年7月15日
Venue
Rohm Plaza, Katsura Campus, Kyoto University
International seminar on disaster management and humanitarian logistics
Application: Please send an email to Qureshi.aligu.4c[@]Kyoto-u.ac.jp
Audience: The seminar is open to general public, academia, and practitionersProgram:
9:30-9:40 Eiichi Taniguchi (Kyoto University)
Welcome
9:40-10:20 Eiichi Taniguchi (Kyoto University)
Humanitarian logistics in disasters
10:20-11:00 Russell G. Thompson (University of Melbourne)
Transport modelling for improved disaster management
11:00- 11:20 Break
11:20-12:00 Benny Chen (University of Melbourne)
Intelligent Disaster Decision Support System (IDDSS) and Transport
12:00- 13:30 Lunch
13:30-14:10 Jan-Dark Schmoecker (Kyoto University)
Analysing Evacuation Decisions with Data from the 2011 Great East Japan earthquake
14:10-14:50 Arash Kavani (University of Melbourne)
Modelling for Traffic Management after disasters
14:50-15:30 Rubel Das (Tohoku University)
Analysis of different relief distribution strategies during limited information environment
15:30-15:40 Russell G. Thompson (University of Melbourne)
Closing remarks
#126 Toward Smart and Connected Communities: Challenges and Opportunities in Transportation
Date
2016年7月15日
Venue
Large Meeting Room, 1F, IDEC, Hiroshima University
Toward Smart and Connected Communities: Challenges and Opportunities in Transportation
講演会「健康経営とまちづくりへの展開」
健康まちづくり研究小委員会ワンディセミナー
#79 開発途上国の交通に関するセミナー International Seminar on Transportation in Developing Countries
Date
2016年6月13日
Venue
JICA市ヶ谷ビル セミナールーム
開発途上国の交通に関するセミナー International Seminar on Transportation in Developing Countries
#125 開発途上国の交通に関するセミナー International Seminar on Transportation in Developing Countries (ワンデイセミナー No.79)
Date
2016年6月13日
Venue
JICA市ヶ谷ビル セミナールーム
開発途上国の交通に関するセミナー International Seminar on Transportation in Developing Countries (ワンデイセミナー No.79)
#124 Transport Modeling in the Era of Cloud Computing and Big Data
Date
2016年5月31日
Venue
東京工業大学大岡山キャンパス石川台4号館B02-05会議室
Transport Modeling in the Era of Cloud Computing and Big Data
2016年度土木計画学研究委員会 第1回国際セミナー(通算 第124回国際セミナー)Transport Modeling in the Era of Cloud Computing and Big Data
日時:2016年5月31日(火) 9:00-12:00 (8:30受付開始)
場所:東京工業大学大岡山キャンパス石川台4号館B02-05会議室(地下1階)
http://www.titech.ac.jp/maps/ookayama/
使用言語:英語
セミナー概要:
– Latest in our flagship product Cube, a comprehensive toolbox for transport and land use planning
(Cubeの紹介と交通・土地利用計画への適用)
– New innovative tools by integrating Cube with GIS, Cloud computing, and Big Data Analytics for accessibility analysis and public transport planning, operations and management.
(公共交通計画のためのCubeとGIS,クラウドコンピューティング,ビッグデータの統合ツールの紹介)
プログラム:
08:30 – 09:00 Registration
09:00 – 09:10 Opening Remarks by Professor Shinya Hanaoka
09:10 – 09:20 Welcome Remarks and Introduction of Citilabs ? Mr. Luke Cheng
09:20 – 10:30 Self Introduction
09:30 – 10:30 Cube ? Transportation and Land Use Solutions ? Mr. Luke Cheng
10:30 – 10:45 Coffee Break
10:45 – 11:45 Harnessing Big Data for Better Public Transport Planning & Operations ? Mr. Luke Cheng
11:45 – 12:00 Q&A
12:00 – 13:00 Lunch time (Lunch Box)
参加申込み方法:
件名を「5月31日Cubeセミナー参加希望」として,本文にお名前・ご所属をご記入の上,以下のアドレスにお送りください。
参加費は無料です。弁当も準備しておりますので,弁当希望の有無をお知らせください。
会場の定員になり次第,お申込みを終了させて頂くことがございます。
Mr. Luke Cheng: lcheng[at]citilabs.com(英語のみ)
川崎智也:kawasaki[at]ide.titech.ac.jp
※[at]を@に変換してください.
第3回研究会
第3回研究会
1. 趣旨説明 張峻屹 広島大学
① 全国の視点からみた地方定住政策
今野水己 三菱総合研究所インフラマネジメントグループリーダー
(1) 地方創生に関する全国の動き(2) 地方版総合戦略(3) 地方版総合戦略の政策パッケージ(4) 地方版総合戦略の事業とKPI(5) 生涯活躍のまちづくり(6) 地方創生事業の検討状況
② 地方の視点:北海道における計画的な国土交通行政の推進に関わる近時の 状況について
澤野宏 国土交通省北海道開発局広報室・広報企画官
(1) 北海道総合開発計画(2) 国土形成計画等と北海道総合開発計画の関係(3) これまでの北海道総合開発計画の推移(4) 今回の計画の策定の背景(5) 今回の計画の概要(6) 全国のトレンドを踏まえた国土交通行政に関する具体的な取り組みの実例(7) 北海道の最新の諸計画の紹介
③ 海外の視点:ドイツの地方都市におけるquality of life :フライブルク市を事例に
フンク・カロリン 広島大学大学院総合科学研究科教授
ドイツでは、人口100万人以上の都市が4カ所と少なく、「大都市」と言われる人口10万人の都市が76カ所存在している。(1) ドイツの地域計画や行政構成の仕組み:独自 性の強い地方都市(2) Urban AuditとしてのQuality of Life 調査の都市政策や地 域計画での活用(3) ドイツの地方都市の生活環境と課題(4) フライブルク市の都市政策に影響する要因、 市民アンケート調査結果からみた課題、環境、教育と文化に関連する政策、環境モデル地区などを紹介する。
#4 熊本地震報告会
Date
2016年5月29日
Venue
北海道大学・工学部
熊本地震報告会
#3 春大会企画セッション「若手研究者によるフロンティアの発見 -土木計画学50周年に寄せて-」
Date
2016年5月29日
Venue
北海道大学・工学部
春大会企画セッション「若手研究者によるフロンティアの発見 -土木計画学50周年に寄せて-」
- 時間:14:45-15:20
- 会場:第 53 回土木計画学研究発表会・第1会場
- 若手研究者によるフロンティアの発見 原祐輔(東北大)
- 景観・計画・歴史研究のフロンティアと実践 山口敬太(京都大)
- 春大会のセッションタイトルに見る土木計画学の現状 塚井誠人(広島大)
- 討議・まとめ 久保田尚副委員長(埼玉大)
第53回土木計画学研究発表会・春大会
第53回土木計画学研究発表会・春大会
第53回土木計画学研究発表会(春大会)は終了いたしました.
ご参加いただき,ありがとうございました.
5月27日の羽田空港でのトラブルによる対応について
※ 聴講の事前申し込みをされた方で,5月27日の羽田空港でのトラブルの影響により,やむを得ず参加をキャンセルされ,かつ,講演集CD-ROMのご送付を希望されない方は,5月30日(月)以降に事務局 林(j-hayashi@jsce.or.jp)までご連絡ください.
また,同トラブルのために発表ができなかった場合,その旨を記した理由書ととも投稿いただければ,特集号への論文投稿を受理することといたします.
土木学会論文集D3(土木計画学)特集号への投稿資格について
企画論文部門へ期限までに投稿された論文のうち、土木学会論文集D3の投稿の手引に従った形式(ただし英文要旨は任意)で執筆され、かつ2ページ以上の分量である論文については、土木計画学研究・講演集に掲載される論文として見なされ、土木学会論文集D3(土木計画学)特集号(以下、特集号と表記する)への投稿資格が得られます。論文タイトルと要旨のみで構成されており本文が記載されていないなど、定められた形式に従っていない原稿は,春大会運営小委員会の判断により,土木計画学研究・概要集に掲載されません。その場合、土木学会論文集D3(土木計画学)特集号への投稿資格は与えられませんのでご注意ください。ただし、特集号への投稿資格を満たさない投稿論文であっても、企画論文部門セッションで発表することは可能です。
また、論文投稿されたにも関わらず実際には春大会にて発表されていない論文、およびSS部門へ投稿された論文についても、特集号への投稿資格はありません。
詳しくは、計画学ホームページをご覧下さい。
https://jsce-ip.org/wp-content/uploads/2019/03/journal-s-tebiki.pdf
実施要領
企画論文部門・スペシャルセッション(SS)部門
企画論文部門は、オーガナイザーを公募し提案された企画テーマでの論文公募を行い、口頭発表またはポスター形式での発表を行うものです。SS部門は、既存の研究小委員会等が主催して、研究討議・意見交換を中心にセッションを構成するもので、本大会では12 セッションを限度とします。また、企画論文部門・SS部門の並行セッションは最大10 会場を想定しております。
公共政策デザインコンペ部門
公共政策デザインコンペは、学生グループまたは学生個人(2016年2 月28 日時点)を対象に「われわれを取り巻く社会環境における問題を自ら発見し、その問題の背景を熟考し、これを含めた社会を改善するための手立て(公共政策)の提案」を募集し、プレゼンテーションならびにポスター展示による発表を競うものです。優秀な作品には、北村記念賞、土木計画学委員会賞が授与されます。
なお、本コンペは、「これからのまちづくりを担う学生諸君の若い力をはぐくむ」ことを目的に掲げ、2006年から開催して一定の成果をあげて参りました。この間、黒川先生、岡田先生ならびに歴代委員長の先生方に審査員をお引き受けいただき、黒川賞、岡田賞、北村賞などの賞を授与して参りましたが、このたび岡田先生のご退職を機にコンペの内容を見直すこととなりました。そのため、現行方式によるコンペは2016年の開催までとします。
申込要領など詳細については公共政策デザインコンペウェブページhttp://www.jsce.or.jp/committee/ip/events/design_compe/about.htmlをご覧ください.
展示ブース
○ブース開設場所と開設期間
開設場所は,発表会会場に隣接する教室に展示スペースを設置する予定です.開設期間は発表会開催期間(2016年5月28日(土)・29日(日))とします.
※ ただし,申し込みが5件程度に満たない場合はブースの開設を中止します.
○展示ブースの内容
展示ブースは2.5m幅のスペースを確保します.60cm×40cmの教室机6個で構成される180cm×80cmの展示物スペースを使用可能です.椅子も提供可能です.電源は1つのブースに対して2か所提供しますが,延長コードは提供しません.
○出展費用
ブース出展の費用は1件10万円とします(原則として1社1ブースの出展に限ります.).
○出展申し込み方法
以下の情報を明記して,e-mailにて土木計画学研究委員会春大会運営小委員会(keikaku53@jsce.or.jp)宛てにお申し込み下さい.
1) 会社/機関名,2) 代表者名,3) 連絡先(e-mail/電話番号),4) 出展内容の概要(日本語300字/英語150 words程度)
○申し込み期限
2016年2月5日(金)17時まで.ただし,申し込み受付件数が10件となり次第,受け付けを終了します.
スケジュール
○企画論文部門
発表希望者の論文題目・概要の登録: 2015年12月11日(金)~ 2016年2月5日(金)
オーガナイザーによる採否決定期間: 2016年2月19日(金)~ 2016年3月11日(金)
論文投稿: 2016年3月24日(金)~ 2016年4月22日(金)まで
○スペシャルセッション(SS) 部門
発表者の決定: 2016年3月11日(金)まで
○公共政策デザインコンペ
応募受付: 2016年3月11日(金)まで
ポスター提出: 2016年5月6日(金)まで
企画論文部門の今後の流れ
○発表希望者
ステップ1:HP(https://www.gakkai-web.net/gakkai/jsce/ip_sp/)を通して,第一および第二希望のセッションを明記し論文発表を申し込む.(発表希望セッションの申し込みは,第一希望のみでも可能ですが,できるだけ第二希望の登録もおすすめします.)続いて,事務局より発表希望者へ,論文発表採否結果が連絡される.
ステップ2:発表が採択された場合は,期日までに論文をWebから投稿する.なお,発表採否の状況によっては,第一および第二希望セッション以外のセッションで発表をお願いする可能性があることをご承知おきください.
○オーガナイザー
Web(URLやパスワード等は後日メールにて送付)を通して,発表概要を確認して発表採否を決定する.第一希望採否は2月19日(金)から2月26日(金)17時までに行う.第一希望のセッションで採択されなかった論文については,事務局より論文発表の第二希望のセッションオーガナイザーへ,採否決定を依頼する.第二希望採否は2月27日(土)から3月11日(金)17時までに行う.
なお,今回より,セッションの運営要領が以下の通りに変更されておりますのでご注意ください.
※変更事項:
企画論文部門において、一論文の発表時間は最小で15分を確保することとする。発表論文の多いセッションについては、ポスターセッションを併用するなどして、討議時間を確保するよう調整を行う。
セッションの成立要件は発表論文が4本以上であることとし、1つの企画論文部門テーマへの発表希望者数が4本に満たない場合には、原則として当該テーマは廃止される。ただし、他の企画論文部門テーマのオーガナイザーとの調整によりテーマを統合することは妨げない。
論文投稿料について
企画部門の発表会投稿料(参加費を含む)は,講演1件につき一般12,000円,学生9,000円です.SS部門は,1セッションにつき,10,000円(参加費別)です.なお,論文題目・概要の登録(2016年2月5日(金))後のキャンセルは,一切認められません.発表(講演)を辞退されても,発表会投稿料として料金を請求させて頂きますので十分にご注意ください.
春大会運営に関する問合せ先
土木計画学研究委員会春大会運営小委員会
e-mail: keikaku53@jsce.or.jp
#123 自転車の死傷者を減らすための挑戦:自転車利用王国オランダの教訓
Date
2016年3月15日
Venue
大阪駅前第二ビル6F 大阪市立大学梅田サテライト104教室
自転車の死傷者を減らすための挑戦:自転車利用王国オランダの教訓
The 14th International Seminar of Committee of Infrastructure Planning and Management, JSCE in FY2015
2015年度土木計画学研究委員会 第14回国際セミナー(通算 第123回国際セミナー)
自転車の死傷者を減らすための挑戦:自転車利用王国オランダの教訓
■大阪
日時:2016年3月15日(火) 18:00?20:00
場所:大阪駅前第二ビル6F 大阪市立大学梅田サテライト104教室(定員43名)
〒530-0001 大阪市北区梅田1-2-2-600
http://www.gscc.osaka-cu.ac.jp/access/
主催:交通科学研究会
協力:土木学会土木計画学研究委員会自転車政策研究小委員会、自転車活用推進研究会
参加費:1000円(資料代)
参加申込:https://goo.gl/R1iG77
お問い合わせ:大阪市立大学吉田までメールでお願いします。
yoshida[at]eng.osaka-cu.ac.jp
※※[at]を@に変換してください。
■東京
日時:2016年4月1日(金) 18:00?20:00
場所:ライフ・クリエーション・スペース OVE南青山(定員60名)
〒107-0062 東京都港区南青山3-4-8 KDXレジデンス南青山 1F
http://www.ove-web.com/minamiAoyama/#shopMap
主催:自転車活用推進研究会
協力:土木学会土木計画学研究委員会自転車政策研究小委員会
参加費:会員:1000円 非会員:2000円
参加申込:http://cyclists.jp/seminar/20160401.html
お問い合わせ:自転車活用推進研究会事務局までメールでお願いします。
info@cyclists.jp
■セミナーの概要(東京・大阪共通):
趣旨:
本セミナーでは、自転車利用王国のオランダにおける交通安全の様々な取り組みと新たな課題について、オランダから講師をお招きして、最新事例の共有を図りたいと思います。
(ご講演は英語で逐次通訳あり)
講師:
ディベラ トゥイスク 女史
ディベラ トゥイスク女史は、英キール大学で心理学・社会学専攻し、蘭グローニンゲン大学大学院では実験心理学/人間工学を修了。その後、グローニンゲンの交通研究所、TNOを経て、オランダ交通安全研究所(SWOV)にて交通安全に関わる研究に従事。SWOVでの20年間に、初心運転者 novice drivers, 事故分析 accident analyses, トレーニング training, ヒューマンファクター human factors, ナチュラリスティックな運転とサイクリング Naturalistic driving and cycling, 自転車交通行動 cycling behaviour等の研究に従事してきました。OECDではYoung drivers the road to safety (OECD-ECMT, 2006)の編集に関わり、最近では、研究所で自転車研究のコーディネーターをつとめており、EUのUDRIVEプロジェクトにも参画しています。最新の著書は「Protecting Pre-License Teens from Road Risk」。
題目:
自転車の死傷者を減らすための挑戦:自転車利用王国オランダの教訓
概要:
オランダは、世界の中でも自転車にやさしい国の一つで、7.5km以下のすべてのトリップの約1/3の分担率となっています。加えて、中学生は自動車と同程度の距離を自転車で移動しています。自転車利用時のリスクは、自動車利用時に比べて約4倍ほど高リスクであると推定されていますが、それでもオランダは世界の中でももっとも安全な国の一つです。
発表では、自転車を保護するために有効であることが示されている施策を扱います。また、交通安全教育の役割とその効果についても含んでいます。多くの成功経験の一方で、オランダは現在、過去10年間で自転車の重傷者が増加するという、新たな課題に直面しています。さらに、高齢化、自転車促進策、電動バイクや高速電動アシスト自転車の利用、自動運転の向けた技術的開発は、今後数年間の安全レベルに影響をもたらす可能性があります。関連する研究の成果や教訓について示したいと思います。
Title:
Challenges in reducing bicycle casualties with high volume cycle use:
lessons from the Netherlands
Presenter:
Dr. Divera Twisk, Bicycle Research Coordinator , Stichting
Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV)
Abstract:
The Netherlands is one of the friendlies countries for cycling in the world, with cycling accounting for about one third of all trips under 7.5 km. In addition young adults in secondary schools travel almost as far a distance by bicycle as by car. Although cycling is estimated to be about four times riskier than car travel, the Netherlands is still one of the safest countries in the world.
This presentation deals with the measures that have shown to be effective in protecting cyclists. It also addresses the role of road safety education and its effects. Despite successes the Netherlands has also been faced with new challenges now that serious injuries among cyclists have been steadily rising in the last decade. Further, an aging society, policies to stimulate cycling, the use of e-bikes and speed pedelecs, and technical developments towards self-driving cars may affect safety levels in the years to come. Results from relevant studies and lessons learnt will be presented.
(English to Japanese consecutive interpreting will be provided.)
#122 災害の根本原因を探る
Date
2016年2月22日
Venue
京都大学防災研究所 連携研究棟 3階 大セミナー室
災害の根本原因を探る
The 13th International Seminar of Committee of Infrastructure Planning and Management, JSCE in FY2015
2015年度土木計画学研究委員会 第13回国際セミナー(通算 第122回国際セミナー)
災害の根本原因を探る
日時:2016年2月22日(月) 15:00?17:30
場所:京都大学防災研究所 連携研究棟 3階 大セミナー室
講師・題目:
(1)Subhajyoti Samaddar:
The Process Mechanism of Community Based Disaster Management:
An Experience and Evaluation of a Participatory Flood Risk Mapping Exercise
(2)Irasema Alc?ntara Ayala:
Forensic Investigations of Disasters (FORIN): a closer look to disasters
概要:
メキシコ自治大学地理学研究所から当研究所に客員教授としてご滞在いただいているIrasema Alc?ntara Ayala先生と昨年10月から特定准教授としてご着任いただいているSubhajyoti Samaddar先生にご講演をいただく機会を上記のように設けました.
Irasema先生は,国際科学連合(ISCU)と国連防災計画(UN-ISDR)が共同して立ち上げている災害リスク統合研究(IRDR)において、災害原因究明プログラム(FORIN)の主査を務め、災害の根本原因に迫る研究を主導して来られています.今回のご講演では,このプロジェクトにおける哲学や方法論,主要な成果等に関してご講演いただきます.
また,Subhajyoti Samaddar先生は,コミュニティー防災の研究者で,バングラディシュ,インド・ムンバイ,ガーナなどでフィールドを持ち,地域住民が減災に主体的に取り組むことを可能にする条件の解明やそのための仕組みづくりなどに取り組んでおられます.
減災のための条件を考究し,そのための方法を議論することのできる貴重な機会となると思いますのでどうぞご参集ください.
#78 少子高齢社会における子育てしやすいまちづくり~親の視点と子どもの視点~
Date
2016年2月20日
Venue
東京大学工学部14号館141講義室
少子高齢社会における子育てしやすいまちづくり~親の視点と子どもの視点~
土木計画学ワンデイセミナー NO.78
少子高齢社会における子育てしやすいまちづくり~親の視点と子どもの視点~
日時:2016年2月20日(土) 13:30-17:30
場所:東京大学工学部14号館141講義室(東京都文京区7-3-1)
http://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/cam01_04_15_j.html
http://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/map01_02_j.html
定員:80名
参加費:無料
主催:土木学会 土木計画学研究委員会(少子高齢社会における子育てしやすいまちづくり研究小委員会)
■開催趣旨
人口減少、少子高齢社会に直面する我が国において、子育てしやすいまちづくりが求められている。近年、バリアフリー法等の整備により、道路や公共交通、公共施設や商業施設などのバリアフリー化が進められ、一昔前と比べると子ども連れで外出しやすい環境が整ってきた。一方、子ども・子育て支援新制度の導入等、子育てしながら働きやすい環境の整備も進められている。さらに、子ども自身が安全・安心に外出できる環境の整備が重要な課題である。本ワンデイセミナーでは、土木計画学および他分野の研究者、行政、民間、NPOなど、多様な立場の方々が一堂に会し、これまでの研究成果の一部の報告と、最近の我が国の取り組みに関する報告をもとに、子育て中の親の視点と子どもの視点の双方から、地域特性に応じた子育てしやすいまちづくりの方向性について幅広く議論を行うことを目的とする。
■プログラム
13:30-13:35 開会挨拶
13:35-15:50 講演・報告
1.「子どもの道路横断時の判断特性」稲垣具志(日本大学)
2.「街区公園と街路の一体的なリデザインとネットワーク化」川本義海(福井大学)
3.「中心市街地における子連れ回遊特性」吉城秀治(福岡大学)
4.「東京都内における幼児乗せ自転車利用の実態」上田真紀子(八千代エンジニヤリング)
5.「幼児世代のバス外出の課題とMMによる緩和のアプローチ」神田佑亮(京都大学)
質疑応答(15:15-15:30)
6.「子ども連れで外出しやすい環境整備の取り組み」国土交通省総合政策局安心生活政策課
7.「コンパクトシティと子育て支援の連携に向けて」国土交通省都市局都市計画課
質疑応答(15:50-16:00)
16:00-16:15 休憩
16:15-17:25 パネルディスカッション
テーマ:子育てしやすいまちの実現のために
パネリスト:遠藤俊太郎(運輸調査局)
楠田悦子(モビリティコンサルタント)
正田小百合(杉並区立桃井第五小学校 学校支援本部「The絆」)
真鍋陸太郎(東京大学)
司会:大森宣暁(宇都宮大学)
17:25-17:30 閉会挨拶
17:45-19:00 懇親会
※懇親会参加費は1,000円です。
※お申込み:大森(nobuaki[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp)宛て、「お名前」、「ご所属」、「懇親会参加のご希望」をご記入の上、2月15日(月)頃までにお申し込み下さい([at]を@に変換してください)。
※お子様の保育サービス(無料)の実施を検討しております。ご希望の方は、セミナー申込みと合わせてご相談下さい。
関西大学先端科学技術シンポジウム 健康まちづくりのためのソーシャルデザイン講演会(共催)
関西大学先端科学技術シンポジウム 健康まちづくりのためのソーシャルデザイン講演会(共催)
An International Workshop on Young People’s Life Choices and Travel Behavior
An International Workshop on Young People’s Life Choices and Travel Behavior
Our subcommittee organized this international workshop at the 95th Annual Meeting of Transportation Research Board, Washington D.C. (The Walter E. Washington Convention Center), January 10-14, 2016.
#121 Building Information Modeling (BIM) for Modern Construction Management
Date
2016年1月7日
Venue
京都大学 桂キャンパス Cクラスター 173号室
Building Information Modeling (BIM) for Modern Construction Management
The 12th International Seminar of Committee of Infrastructure Planning and Management, JSCE in FY2015
2015年度土木計画学研究委員会 第12回国際セミナー(通算 第121回国際セミナー)
Building Information Modeling (BIM) for Modern Construction Management
日時:2016年1月7日(木) 13:00?16:15(途中15分休憩)
場所:京都大学 桂キャンパス Cクラスター 173号室
講師:Veerasak Likhitruangsilp准教授(タイ・チュラロンコン大学)
題目:Building Information Modeling (BIM) for Modern Construction Management
趣旨:コンピューターによる設計図面の作成を可能にしたBIMは設計の正確性を高めるのみならず,BIMで作成した設計図が契約図書の一部を構成するようになりつつあり,プロジェクト・マネジメントのプラクティスにも変革を迫っている. BIMをベースとしたプロジェクトマネジメントを教える大学が世界的に増加する一方,わが国ではその重要性に対する認識が普及しているとは言いがたい状況にある.本特別講演会では,BIMによる建設マネジメントの研究に精力的に取り組むVeerasak Likhitruangsilp先生から,最先端の研究内容とともに,今後の展望についてお話いただく予定である.
#77 持続可能かつ住みやすい都市を創る都市物流システム
Date
2016年1月6日
Venue
土木学会講堂
TKP札幌駅カンファレンスセンター(札幌市北区北7条西2丁目9)
持続可能かつ住みやすい都市を創る都市物流システム
土木計画学ワンデイセミナー NO.77
持続可能かつ住みやすい都市を創る都市物流システム
日時:2016年1月6日(水)10:00-16:45
場所:土木学会講堂(東京都新宿区四谷一丁目外濠公園内)
http://www.jsce.or.jp/contact/map.shtml
参加費:無料
主催:土木学会 土木計画学研究委員会(持続可能かつ住みやすい都市を創るスマートロジスティクス研究小委員会)
■開催趣旨
持続可能かつ住みやすい都市を創るための都市物流システムは、今後の都市の発展の基盤となるプラットフォームを提供できる。 すべてのモノやコトがインターネットでつながるIoT時代を迎えて、物流の効率性のみならず、環境、エネルギー、安全、健康、生活の質に配慮した都市物流システムの構築に向けて、課題とその解決策、今後の展望について議論を行う。
なおこのワンデーセミナーでは、土木計画学以外の情報工学の専門家を招いて議論を深める。
■プログラム
10:00-10:05 開会の辞(谷口栄一、京都大学大学院工学研究科教授)
10:05-10:30 都市物流システムに関する新しい方向(谷口栄一、京都大学大学院工学研究科教授)
10:30-11:00 日本の物流政策(小原宏朗、国土交通省道路局企画課道路経済調査室課長補佐)
11:00-11:30 ETC2.0を活用した大型車交通マネジメント(池田武司、国土交通省道路局道路交通管理課車両通行対策室専門官)
11:30-12:00 人工知能はビジネスをどう変えるか
(矢野和男、日立製作所研究開発グループ技師長/東京工業大学大学院総合理工学研究科 連携教授)
12:00-13:00 昼食
13:00-13:30 ネットワーク型デジタコと物流プローブ分析サービス(島田孝司、(株)富士通交通・道路データサービス社長)
13:30-14:00 東京都市圏物資流動調査よりみた貨物車の動き(岡英紀、一般財団法人計量計画研究所社会基盤研究室研究員)
14:00-14:30 最近の物流動向からみた物流拠点立地の動向と対応策(萩野保克、一般財団法人計量計画研究所研究部次長)
14:30-14:45 休憩
14:45-15:15 中心市街地における端末物流の現状と対策?東京都市圏物資流動調査「端末物流対策の手引き」より?
(高橋淳一、(株)日本能率協会総合研究所交通・まちづくり研究部)
15:15-15:45 海外の都市物流マネジメントに関する事例(今西芳一、(株)公共計画研究所社長)
15:45-16:15 コンテナターミナル陸側の混雑特性と改善策
(元野一生、内閣府/京都大学経営管理大学院特命准教授、古市正彦、京都大学経営管理大学院特定教授)
16:15-16:45 物流研究のこれから(兵藤哲郎、東京海洋大学教授)
■連絡先:このワンデーセミナーに参加希望の方は下記までご連絡ください。
中村有克
京都大学大学院工学研究科都市社会工学専攻
nakamura[at]kiban.kuciv.kyoto-u.ac.jp
※[at]を@に変換してください。
#120 ポートランドのまちづくり:エコ・リバブルシティに向けたまちづくりの基盤
Date
2015年12月18日
Venue
岡山大学国際交流会館(18), 西川アゴラ(19)
ポートランドのまちづくり:エコ・リバブルシティに向けたまちづくりの基盤
The 11th International Seminar of Committee of Infrastructure Planning and Management, JSCE in FY2015
2015年度土木計画学研究委員会 第11回国際セミナー(通算 第120回国際セミナー)
ポートランドのまちづくり:エコ・リバブルシティに向けたまちづくりの基盤
※本講演会は環境省総合研究推進費「エコ・リバブルシティの都市構造モデルの構築とその計画論に関する研究(研究代表者 氏原岳人・岡山大)」のキックオフシンポジウムとして開催致します。
日時:12月18日(金)14:00-17:00
場所:岡山大学国際交流会館
内容:ポートランド市における都市計画の役割 ~より良い空間づくりのための挑戦とその条件~
講師:Ethan Seltzer 氏(ポートランド州立大学教授)
環境にやさしくて住みやすいエコ・リバブルシティとして世界的に有名なポートランド都市圏の都市計画に最も精通しているEthan Seltzer先生をお招きして、都市計画が環境や住みやすさにどのような貢献をしたのかをお話いただきます。
日時:12月19日(土)14:00-17:00
場所:西川アゴラ (岡山市中心部)
内容:ポートランド市の都市計画40年史 ~ポートランドの将来像を再想像する~
講師:Ethan Seltzer 氏(ポートランド州立大学教授)
ポートランド都市圏の40年史についてお話いただきます。ポートランドがなぜ世界的に認められる都市になったのか、そのポイントを説明いただきます。Ethan Seltzer教授や参加者の方々とのディスカッションを通じて、日本版エコ・リバブルシティの方向性を探ります。
主催:岡山大学
共催:環境省、岡山市
※エコ・リバブルシティとは、低炭素でかつ住みやすい都市のことです。私たちの研究グループでは環境省の支援のもと、エコ・リバブルシティ実現に向けた取組みを進めています。
第52回土木計画学研究発表会・秋大会
Date
2015年11月21日(土)~23日(月・祝)
Venue
秋田大学 手形キャンパス
第52回土木計画学研究発表会・秋大会
土木計画学研究委員会は下記の概要で2015年の秋期における土木計画学研究発表会(秋大会)を開催します。
講演用論文
発表会の当日に十分な時間で充実した議論を行い、更なる研究の発展や学術論文等への取りまとめに繋げることが本発表会の特色です。このため、「具体的に議論したい点(研究の新規性や枠組み、データ、モデルや結論の妥当性、今後の発展性や疑問点など)」を明記して申込みしていただきます。話題性、速報性のある論文や、調査・計画、技術検討等の事例報告も歓迎します。提出された講演用論文は、原則として無審査で掲載されますが、会場の制約等によってお断りすることもあります。
今発表会では、試行的に、通常の発表希望分野Ⅰと並行して、発表希望分野Ⅱ(手法等分野横断的区分)での発表希望もお願いしています。こちらへの記入もよろしくお願いします。
なお、ポスターセッションを今年度も実施いたします。口頭発表とポスターでの発表のどちらを希望するかを選んで申込んでいただきます(口頭発表およびポスターでの発表のいずれも、「土木学会論文集D3(土木計画学), Vol.72, No.5(土木計画学研究・論文集33巻)」への投稿対象となります)。
※2016年発行予定の「土木学会論文集D3(土木計画学), Vol.72, No.5(土木計画学研究・論文集33巻)」及びそれ以降の巻への投稿には、
① 投稿時点から過去2年以内の土木計画学研究・講演集に掲載され、文量が2ページ以上の論文である
② 研究発表会において、著者により当該論文の発表が行われている
ことが必要となりますので、あらかじめご了承ください。
問合先
土木計画学研究委員会・学術小委員会 E-mail:keikaku52@jsce.or.jp
以下の該当する部分を熟読のうえ、手続きを取っていただけますようお願いいたします。
講演の申込み
(1) 申込みの手続きおよび注意点
2015年7月3日(金)~7月31日(金)17時までの期間内に、 土木計画学研究発表会(秋大会)講演申込みページ申込画面より、講演申込と講演原稿の投稿を同時に行ってください。原稿のファイル形式はPDF形式のみ受付けます。 原稿は「講演原稿執筆要領」に従ってご執筆ください。締切日当日までは、投稿した原稿の確認、差し替えが可能ですが、締切日以降は、原稿の差し替えは受け付けられません。十分、ご注意ください。投稿時に、必ず申込内容が正しいか、PDFの取り違えての投稿がないか、申込内容とPDFのタイトル等の差異がないかなどをご確認ください。申込み期間の締切り間際に投稿が集中しますと、予期せぬ事態によりサーバーがダウンし受付ができなくなる恐れがあります。締切り間際の投稿は極力避けていただくようお願いいたします。
なお、講演原稿執筆要領に準じていないもの、および期限後に投稿されたものは受理できません。必ず所定の原稿を期間内にWEB上にて投稿してください。
間違えたファイルを提出した場合や申込内容とPDFの内容が違う場合であっても、そのまま掲載されますので、ご注意ください。
(2) 発表希望分野
(i) 発表希望分野Ⅰ(研究対象区分)
申し込みに際して、発表希望分野を下記の5つの発表分野から希望順に2つ選んでください。また、キーワードにつきましては、同キーワード欄の中から最大4つ選んでください。なお、適当なキーワードが見つからない場合は、投稿者の判断によるキーワードを1つだけ加えてください。
発表希望分野
| 発表希望分野 | キーワード |
| A 計画論・計画情報 | 計画基礎論、計画手法論、システム分析、調査論、公共事業評価法、財源・制度論、プロジェクト構想、施工計画・管理、維持管理計画、意識調査分析、計画情報、情報処理、市民参加、GIS、リモートセンシング、測量、環境計画、防災計画、河川・水資源計画、ライフライン計画・設計、地球環境問題 |
| B 地域・都市・景観 | 国土計画、地域計画、都市計画、地区計画、住宅立地、産業立地、人口分布、地価分析、土地利用、市街地整備、再開発、景観、公園・緑地、観光・余暇、空間設計、イメージ分析、土木史 |
| C 交通現象分析 | 発生交通、目的地選択、交通手段選択、経路選択、出発時刻選択、活動分析、時間利用、交通行動調査、交通意識分析、交通行動分析、自動車保有・利用、駐車需要、交通ネットワーク分析、土地利用・交通・環境統合モデル、観光・余暇行動 |
| D 交通基盤計画 | 総合交通計画、地区交通計画、公共交通計画、歩行者・自転車交通計画、道路計画、鉄道計画、空港・港湾計画、ターミナル計画、駐車場計画、物流計画 |
| E 交通運用管理 | 交通流、交通容量、サービス水準、交通制御、交通管理、交通安全、交通情報、交通環境、公共交通運用、交通弱者対策、水上交通、空港管理、交通量計測、TDM、ITS、モビリティマネジメント(MM) |
(3) 発表形式
口頭発表とポスターでの発表のどちらを希望するかを選んでいただきます。なお、会場の都合でご希望に添えない場合もありますので予めご了承下さい。
(4) 投稿料
講演1本につき投稿料(参加費含む)として一般12,000円、学生9,000円を請求いたします。2本以上投稿する方については、2本目以降の投稿料は一般・学生ともに6,000円を請求いたします。振込手数料は各自でご負担願います。
講演原稿執筆要領
講演原稿の書式・形式は、土木学会論文集のものに準じています。下記の作成例やサンプルファイルをご利用ください。講演原稿では、英文アブストラクトの記入は任意です。その他書式・形式についての詳細は土木学会論文集の原稿作成の手引き等をご参照ください。なお、「土木学会論文集D3(土木計画学), Vol.75-6」への投稿の際には英文アブストラクトは必要です。
サンプルファイル 和文(Word2000)/English(Word2000)
原稿作成例 和文(PDF)/English(PDF)
お問合せ先
土木計画学研究委員会大会運営小委員会(春大会担当:橋本,氏原,林)
E-mail:keikaku59@jsce.or.jp
発表プログラムについて
参加申込
Web (事前申込〆切:2015年11月6日.講演申し込みをされた方は事前参加申込を行う必要はありません.)
#119 Perspectives on the organization of home life, workforce participation and spatio-temporal behaviour by Women and Men in Qu?bec, Canada
Date
2015年11月17日
Venue
広島大学大学院国際協力研究科大会議室
Perspectives on the organization of home life, workforce participation and spatio-temporal behaviour by Women and Men in Qu?bec, Canada
The 10th International Seminar of Committee of Infrastructure Planning and Management, JSCE in FY2015
2015年度土木計画学研究委員会 第10回国際セミナー(通算 第119回国際セミナー)
Perspectives on the organization of home life, workforce participation and spatio-temporal behaviour by Women and Men in Qu?bec, Canada
Program:
Time: 12:50-18:00, November 17, 2015
Venue: 広島大学大学院国際協力研究科大会議室(1階)
Please refer to the map here.
■Speakers:
Martin E. H. Lee-Gosselin
Emeritus Professor, Graduate School of Planning, Laval University, Qu?bec City, Canada
Visiting Professor, Imperial College London
H?l?ne Lee-Gosselin
Professor, Department of Management, Business School, Laval University, Qu?bec City, Canada
Incumbent, Chaire Claire-Bonenfant femmes-savoir-soci?t?s (Laval University’s Research Chair on Women, Knowledge and Society)
■Summary of Seminar
The seminar will be jointly animated by the two speakers, drawing on a variety of research traditions, including gender studies, organisational psychology, activity and travel behaviour analysis, longitudinal data collection and analysis, and gaming-simulation. There will be three parts to the seminar:
a) Lectures providing contextual information from longitudinal national and provincial statistics, over up to 30 years, on the evolution of workforce participation by different household structures, and from an in-depth, 3-wave longitudinal panel survey of decision-making by individuals and households about the spatio-temporal organisation of their activities and travel.
b) A period of guided exchange among seminar participants on the scope and potential of emerging data collection methods, notably as concerns life-oriented approaches and the observation of individual, household and agency decision-making. Particular reference will be made to the use of ICTs to observe, and potentially influence, mobility behaviour in the interests of transport safety and system performance.
c) An open discussion on the implications of insights and inferences from research in these areas, and on the identification of leading problem areas, appealing research designs, new and improved methods, and promising public policy levers.
■Sponsored by
Grants-in-Aid for Scientific Research (A), Japan Society for the Promotion of Science (JSPS)
Principal researcher: Prof. Junyi Zhang, Hiroshima University
Project period: 2015.04~2019.03
Project title: Interdisciplinary research on policies promoting young people’s migration to and permanent residence in local cities
https://sites.google.com/site/lifeorientedbehavior/app-young-people
#118 International Seminar on City Logistics and Freight Transport
Date
2015年11月12日
Venue
Jinyu Hall, Kyoto University, Katsura Campus
International Seminar on City Logistics and Freight Transport
The 9th International Seminar of Committee of Infrastructure Planning and Management, JSCE in FY2015
2015年度土木計画学研究委員会 第9回国際セミナー(通算 第118回国際セミナー)
International Seminar on City Logistics and Freight Transport
Program:
Date: 12-13 November 2015
Venue: Jinyu Hall, Kyoto University, Katsura Campus
Please refer to the map here(English, Japanese).
Day 1 Program (Thursday, 12th November 2015)
930 – 1000 Registration
Session 1
1000 – 1010 Welcome; Prof. Eiichi Taniguchi, Kyoto University
Welcome; Prof. Satoshi Fujii, Head of Department of Urban Management, Kyoto University
1010 – 1040 Presentation 1: Paradigm change for city logistics; Prof. Eiichi Taniguchi, Kyoto University
1040 – 1110 Presentation 2: City Logistics: past, present and future; Associate Prof. Russell Thompson, The University of Melbourne
1110 – 1140 Presentation 3: Developing a freight strategy in London: Challenges and lessons learned 1985-2015; Prof. Michael Browne, The University of Gothenburg
1140 – 1200 Discussion
Lunch 1200-1330
Session 2
1330 – 1400 Presentation 4: Freight demand management; Prof. Jose Holguin-Veras, Rensselaer Polytechnic Institute
1400 – 1430 Presentation 5: Business continuity management methodologies for port logistics; Prof. Kenji Ono, Kyoto University
1430 – 1450 Discussion
1450 – 1700 Technical visit
Day 2 Program (Friday, 13th November 2015)
Session 3
1000 – 1030 Presentation 6: Social Impact of “team pickup/delivery” on Last Mile Parcel Delivery Network; Prof. Toshinori Nemoto, Hitotsubashi University, Prof. Katsuhiko Hayashi, Ryutsu Keizai University, Mr. Kosuke Miyatake, Hitotsubashi University
1030 – 1100 Presentation 7: City planning and freight – Searching for intersections; Associate Prof. Kazuya Kawamura, University of Illinois
1100 – 1130 Presentation 8: Vehicle routing models in humanitarian logistics; Associate Prof. Ali G. Qureshi, Kyoto University
1130 – 1150 Discussion
Lunch 1150-1400
Session 4
1400 – 1430 Presentation 9: 25 years of city logistics in the Netherlands; Dr. Johan Visser, Delft University of Technology
1430 – 1500 Presentation 10: Framework for citywide road freight transport management; Dr. Yoshikazu Imanishi, Public Planning and Policy Studies
1500 – 1520 Discussion
1520 – 1530 Concluding Remarks; Prof. Michael Browne, The University of Gothenburg
1530 – 1630 Technical Tour
Application:Please send an email to Qureshi.aligu.4c[@]Kyoto-u.ac.jp
Free to attend
The seminar is open to general public, academia, and practitioners.
#117 The 5th International Seminar on Integration of Spatial Computable General Equilibrium and Transport Modeling
Date
2015年10月15日
Venue
神戸大学百年記念館六甲ホール
The 5th International Seminar on Integration of Spatial Computable General Equilibrium and Transport Modeling
The 8th International Seminar of Committee of Infrastructure Planning and Management, JSCE in FY2015
2015年度土木計画学研究委員会 第8回国際セミナー(通算 第117回国際セミナー)
The 5th International Seminar on Integration of Spatial Computable General Equilibrium and Transport Modeling
Program:
日時:平成27年10月15日(木),16日(金)
場所:神戸大学百年記念館六甲ホール
(地図:http://www.kobe-u.ac.jp/guid/access/rokko/rokkodai-dai2.html)
1日目:10月15日(木) Octorber 15th
10:00-11:30 Morning Lecture(■実務者向け,日本語セッション)
小池淳司(神戸大学) Atsushi Koike (Kobe University)
「交通投資のストック効果計測」
“Assessing Economic impacts of Transport Investment”(in Japanese)
13:00-13:30 開会挨拶 Opening Address
Lori Tavasszy (TNO/TU Delft)
13:30-14:30 基調講演 Keynote Lecture
Johaness Brocker (Kiel University)
“TBA”
14:50-16:20 セッション1:国際物流 (Global freight flows)
柴崎隆一(国土交通省国土技術政策総合研究所)
「海運・陸運インターモーダル輸送ネットワークにおける国際物流モデリング」
Ryuichi Shibasaki (NILIM)
“Modeling of international freight flow on worldwide intermodal network including both maritime and land shipping and its application”
Kees Ruijgrok (University of Tilburg)
「減速運航が国際物流ネットワークの最適化に及ぼす影響」
“Slow steaming and its effects on international freight network optimization”
田邊怜(東京大学 博士後期課程)
Satoshi Tanabe (University of Tokyo)
「国際交通インフラ整備の影響評価モデル:中央アジアにおける貿易と物流に着目して」
“Impact Assessment Model of International Transportation Infrastructure Development: Focusing on Trade and Freight Traffic in Central Asia”
16:40-17:40 セッション2:貿易と経済 (Trade & Economic Modeling)
瀬木俊輔(京都大学)
「カナダ・アメリカ国境における待ち時間削減の経済効果:応用一般均衡モデルと越境交通の統合」
Shunsuke Segi (Kyoto University)
“Economic Impacts of Reduced Wait Time at Canada-US Border Crossing: Integrating CGE Model and Cross-Border Transportation“
Lori Tavasszy (TNO/TU Delft)
「サプライチェーンにおける外部費用の内部化がもたらす効果について」
“Effects of internalization of external costs of supply chains”
18:00-20:00 Participants Meeting (invitation only)
2日目:10月16日(金) Octorber 16th
10:00-11:00 セッション3:ロジスティクスと交通 (Logistics and Transport Modeling)
円山 琢也(熊本大学)
「トリップ・チェイン型均衡配分モデルを用いた長期的な交通需要予測」
Takuya Maruyama (Kumamoto University)
“Long-Term Travel Forecasting using Trip-Chain-Based User Equilibrium Model”
Igor Davydenko (TNO):
「物流モデルにおけるロジスティクス・チェーン」
“Logistics Chains in Freight Transport Modeling”
11:20-12:20 セッション4:直接・間接効果 (Direct and Indirect Effects)
Euijune Kim (Seoul National University)
「鉄道整備が地域経済に及ぼす影響:鉄道・高速道路ネットワークのマイクロシミュレーションを利用した空間一般均衡アプローチ」
“Impact of Railroad Investments on Regional Economies: an Approach of Spatial CGE Model with a Microsimulation Module of Railroad and Highway Networks”
石倉 智樹 (東京首都大学)
「多国多地域型応用一般均衡モデルと国際・国内交通基盤整備の評価」
Tomoki Ishikura (Tokyo Metropolitan University)
“Transnational Interregional CGE Model and Assessment of International and Intranational Transport Development”
12:30-14:00 昼食
14:00-15:00 セッション5:災害マネジメント1(Disaster Management I)
奥山 恭英 (北九州市立大学)
「阪神淡路大震災後の神戸経済」
Yasuhide Okuyama (University of Kitakyushu)
“Rise and Fall of the Kobe Economy from the 1995 Earthquake”
山崎雅人(名古屋大学)
「自然災害による経済被害評価のための多地域動学応用一般均衡モデル」
Masato Yamazaki (Nagoya University)
“A multi-regional dynamic CGE model for assessing the economic impacts of natural disasters”
15:20-16:20 セッション6:災害マネジメント2 (Disaster Management II)
Olga Ivanova (PBL, Netherlands Environmental Assessment Agency)
「EU圏域における異常気象による間接被害評価のための空間応用一般均衡モデル」
“Using EU-wide SCGE model for the assessment of indirect impacts of past climate extreme events”
織田澤 利守(神戸大学)
「産業の過剰集積による災害脆弱性と交通減災施策」
Toshimori Otazawa (Kobe University)
“ Industrial Location and Vulnerability to Natural Hazards”
16:40-17:10 Closing Remarks
#5 復興と土木:対話できる社会基盤と新たな国土デザインを考える(2015年・年次学術講演会)
Date
2015年9月18日
Venue
岡山大学 津島キャンパス 文法経講義棟 12番講義室(会場名:V-3)
#5 復興と土木:対話できる社会基盤と新たな国土デザインを考える
平成27年度土木学会全国大会 研究討論会 <岡山大学>
題目:復興と土木:対話できる社会基盤と新たな国土デザインを考える
(土木計画学研究委員会・海岸工学委員会)
概要:海岸工学と社会基盤計画の視点から,東日本大震災における工学と土木の専門家の様々な学会活動を振り返った上で,特に地域社会と社会基盤の対話について海岸工学と土木計画の視点から考えたい.さらに防潮堤と地域の関係に着目し,防潮堤の高さの見直しから,海岸施設と地域環境の保全の実情やランドスケープデザインまで,新たな国土デザインの方向性を議論する.
座 長:
羽藤 英二(東京大学大学院工学系研究科教授)
話題提供者:
磯部 雅彦(土木学会前会長)
佐藤 慎司(海岸工学委員長)
家田 仁 (東大・政策研究大学院大学教授)
石川 幹子(中央大学教授)
日時: 9月18日(金) 16:20~18:20
場所: 岡山大学 津島キャンパス
文法経講義棟 12番講義室(会場名:V-3)
#115 The 8th Japan-China Joint Seminar on Sustainable Management of Cities and Regions under Disaster and Environmental Risks
Date
2015年8月22日
Venue
Kusunoki Kaikan Hall, Kurokami Campus, Kumamoto University
The 8th Japan-China Joint Seminar on Sustainable Management of Cities and Regions under Disaster and Environmental Risks
The 6th International Seminar of Committee of Infrastructure Planning and Management, JSCE in FY2015
2015年度土木計画学研究委員会 第6回国際セミナー(通算 第115回国際セミナー)
The 8th Japan-China Joint Seminar on Sustainable Management of Cities and Regions under Disaster and Environmental Risks
Date: August 22-24, 2015 9:00-18:00
Venue: Kusunoki Kaikan Hall, Kurokami Campus, Kumamoto University
BACKGROUND AND SCOPE
Fulfilling energy demands is an inevitable issue in cities and regions all over the world. It is essential to establish a proper system to manage and govern limited enery resources to achieve sustainable society. However, cities and regions are threaten by environmental and disastrous risks that will disrupt economic and social activities in cases. It is a critical issue to establish robust and resilient society against such risks. Against such a background, the seminar aims to deepen an understanding of urban and regional management schemes and policies that enable us to live in cities and regions with limited resources threaten by environmental and disastrous risks. Such schemes and policies are applicable (in cases, exchangeable) among cities and regions. In this sense, the seminar provides an opportunity to exchange opinions on schemes or policies to sustain cities and regions in different social and cultural context.
OBJECTIVES
Key objectives of the seminar are:
? To discuss sustainable cities and regions threaten by disaster/environmental risks
? To discuss sustainable management of basic human needs, such as water, foods and energy
? To broad a network among sustainable cities and regions all over the world
Topics of interest in the seminar includes
1. Methodologies for disaster/environmental risk analysis and management
2. Methodologies for modeling of social vulnerability, including social, human and production capital
3. Policy analysis of disaster and environmental risk management
4. Methodologies for community-based disaster and environmental risk management
5. Methodologies for dealing with critical infrastructure against disaster/environmental risks
6. Infrastructural planning and management for sustainable management of cities and regions
7. Methodologies for flood risk management
8. Other issues related with the seminar theme
DISTINGUISHED SPEAKERS
Prof. Norio OKADA (Kwansai Gakuin University)
Prof. Asao ANDO (Tohoku University)
WHO SHOULD ATTEND THE CONFERENCE?
We are pleased to welcome all researches, practitioners and students interested in the above objectives.
LANGUAGE
The official language of the conference is English.
ORGANISING BODIES
The Implementation Research and Education System Center for Reducing Disaster Risk (IRESC), Kumamoto University
#116 第5回国際研究BinNセミナー(BinN International Research Seminar #5)
Date
2015年8月11日
Venue
Room. 429 at Faculty of Engineering Bldg. 14, The University of Tokyo (Hongo Campus)
第5回国際研究BinNセミナー(BinN International Research Seminar #5)
The 7th International Seminar of Committee of Infrastructure Planning and Management, JSCE in FY2015
2015年度土木計画学研究委員会 第7回国際セミナー(通算 第116回国際セミナー)
第5回国際研究BinNセミナー(BinN International Research Seminar #5)
“Modeling for evaluation of new urban transit and recent innovation in data-service technologies”
Host:
JSPS Kaken S/A by Kuwahara, M.(Tohoku Univ) and Hato, E.(UT)
Organizer: Yaginuma, H.(UT)
The 5th International BinN Research Seminar will be held on Tuesday Aug. 11th 2015. As keynote speakers, we will invite Dr. Oded Cats from TU Delft and Dr. Jan-Dirk Schm?cker from Kyoto University. Dr. Cats is currently doing research on agent-based dynamic public transit modeling. In this seminar, the keynote lectures will focus on developed dynamic model and its application to real network. In addition, we will discuss new approaches to new urban mobility modeling considering recent innovation of technologies. .
Program:
Date: Aug 11th (Tue.) 2015, 2:00 pm – 5:00 pm
Venue: Room. 429 at Faculty of Engineering Bldg. 14, The University of Tokyo (Hongo Campus)
2:00 pm – 2:45 pm
Keynote Lecture 1: “An agent-based approach to modelling public transport dynamics”
Oded Cats (TU Delft)
* Brief bio can be founded below.
2:45 pm – 3:30 pm
Keynote Lecture 2: “Smart transit systems for even smarter travellers”
Jan-Dirk Schm?cker (Kyoto Univ.)
3:45 pm – 4:30 pmm
Research Presentation 1
“Innovative ITS Approaches for Control of Large-Scale Urban Networks”
Mehdi Keyvan-Ekbatani (TU Delft)
** Brief bio can be founded below.
4:30 pm – 5:00 pm
Research Presentation 2
“Demand control management for one-way car sharing system focus on the imbalance between demand and supply”
Nodoka Kasahara (Tokyo Univ.)
After party:
After party will probably take place around The University of Tokyo in the evening.
Application:yaginuma[at]civil.t.u-tokyo.ac.jp (mail to Hideki YAGINUMA)
Free to attend
The symposium is open to public.
You can see information about past seminars here.
* Brief Bio:
Dr. Oded Cats is an Assistant Professor in Public Transport Operation at the Department of Transport and Planning at Delft University of Technology in the Netherlands and part-time at KTH Royal Institute of Technology in Sweden. Oded holds a dual-PhD from KTH and Technion – Israel Institute of Technology. He is a member of the US Transport Research Board committee on Transit Management and Performance and Public Transportation Marketing and Fare Policy. His areas of expertise include the dynamics of public transport operations and demand, multimodal urban networks and simulation modelling and the impacts of reliability, congestion, disruptions and information on passengers’ decisions. His research activities are geared to support transport agencies and operators’ decision making.
** Brief Bio:
Dr. Mehdi Keyvan-Ekbatani is a post-doctoral researcher at the Department of Transport and Planning, Delft University of Technology, the Netherlands. In 2013, he received his PhD degree in Real-Time Urban Traffic Control from Dynamic Systems and Simulation Laboratory (DSSL), Technical University of Crete, Greece. DSSL is among the leading institutions in Intelligent Transportation Systems (ITS); the lab was awarded with the IEEE ITS Institutional Lead Award in 2011. In 2012, he visited Urban Transport Systems Laboratory (LUTS), Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL), Switzerland as a visiting scholar. He was the recipient of a scholarship for his PhD from NEARCTIS (Network of Excellence for Advanced Road Cooperative Traffic management in the Information Society), by European Commission (2010-2013). In 2012, he received the Best Paper Award at the European Transportation Research Arena. In addition, he was also a finalist for the Eltis Award Europe 2012. Dr. Keyvan-Ekbatani is the recipient of the 2014 IEEE ITSS Best Ph.D. Dissertation Award. His main research interests include: Traffic flow theory, traffic control, transportation systems, driving behaviour modelling and public transport systems.
#2 2015北海道道路国際シンポジウム -人間社会とリスク-
Date
2015年8月10日
Venue
京王プラザホテル札幌
2015北海道道路国際シンポジウム -人間社会とリスク-
と き: 2015年8月10日(月)13:00-17:30
ところ: 京王プラザホテル札幌 (北海道札幌市中央区北5条西7丁目2?1)
参加国数 4カ国(日本含む)
参加者数 日本在住:合計334名
■開催概要
土木学会土木計画学委員会は2016年に設立50周年を迎えることとなり、 その記念行事の一環として、この度北海道に於いて国際シンポジウムを企画いたしました。 周知のとおり土木学会は2014年に創立100周年を迎え、従来の学会員の満足度向上を改め、 「市民の満足度向上」を目標に掲げて活動を行っております。 この流れに沿って、本国際シンポジュ-ムの目的は、交通と災害をテ-マとする 世界的な研究者を北海道に招いて、「人間社会とリスク」という市民に身近なタイトルで 学会から市民へ世界の潮流と新しいものの考え方を発信するものです。
■主催 2015北海道道路国際シンポジウム実行委員会
(北海道大学、北見工業大学、室蘭工業大学、公益社団法人土木学会土木計画学研究委員会、国立研究開発法人 土木研究所 寒地土木研究所、一般社団法人北海道開発技術センタ-、一般財団法人北海道道路管理技術センタ-、一般財団法人北海道建設技術センター)
■プログラム
13:00-13:15 開会挨拶
13:15-15:25
13:15-14:55 人間社会とリスク(海外の事例)
Michael G.H.Bell (University of Sydney)
Michael A.P. Taylor (University of South Australia)
Henry X. Liu (University of Michigan)
William H.K. Lam (The Hong Kong Polytechnic University)
Agachai Sumalee (King Mongkut’s Institute of Technology)
14:55-15:25 わが国への示唆
円山琢也(熊本大学)
内田賢悦(北海道大学)
倉内文孝(岐阜大学)
(休憩 15:25-15:45)
15:45-17:15 パネルディスカション「防災と交通 -人間社会とリスク-」
朝倉康夫(東京工大)
山田菊子(東京工大)
加藤哲平(北海道大学、博士課程)
北海道開発局
北海道
17:15-17:30 閉会挨拶
■ポスターはこちら
■講演資料・講演録を以下からダウンロードできます.
Michael G.H.Bell (University of Sydney)
Michael A.P. Taylor(University of South Australia)
Henry X. Liu (University of Michigan)
William H.K. Lam (The Hong Kong Polytechnic University)
円山琢也(熊本大学)
内田賢悦(北海道大学)
倉内文孝(岐阜大学)
講演録
International Workshop on the Life-oriented Approach for Transportation Studies
International Workshop on the Life-oriented Approach for Transportation Studies
Our subcommittee organized this international workshop at the IATBR’2015 Conference, Windsor, UK, July 19-23, 2015. The program is shown as follows:
July 20 (Monday), 16:00 ~ 18:00
(1) 16:00~16:10 Introduction of the workshop
Prof. Junyi ZHANG, Hiroshima University
(2) 16:10~16:40 Keynote Speech: Consumption and happiness
Prof. Ruut VEENHOVEN, Emeritus Professor of Erasmus University Rotterdam; Director of the World Database of Happiness and a founding editor of the Journal of Happiness Studies
(3) 16:40~16:50 Discussion on the Keynote Speech
Assoc. Prof. Dick ETTEMA, Utrecht University
(4) 16:50~17:10 Raising Big Questions (1): Lifestyle based activity-travel behavior analysis
Assis. Prof. Veronique VAN ACKER, University of Amsterdam
(5) 17:10~17:20 Discussion on the talk by Assis. Prof. Veronique VAN ACKER
Prof. Kay W. AXHAUSEN, IVT, ETH Zurich
(6) 17:20~18:00 Open discussion
July 22 (Wednesday), 11:00 ~ 13:00
(1) 11:00~11:05 Summary of discussion on July 20
Prof. Junyi ZHANG, Hiroshima University
(2) 11:05~11:25 Resource Paper: Understanding changing travel behavior
over the life course: Contributions from biographical research
Assoc. Prof. Joachim SCHEINER, Dortmund University of Technology
Assoc. Prof. Kiron CHATTERJEE, University of the West of England
(3) 11:25~11:35 Discussion on the Resource Paper
Prof. Patricia L. MOKHTARIAN, Georgia Institute of Technology
(4) 11:35~11:55 Raising Big Questions (2): Choice context in travel behavior models
Prof. Konstadinos G. GOULIAS, University of California, Santa Barbara
(5) 11:55~12:05 Discussion on the talk by Prof. Konstadinos G. GOULIAS
Prof. Donggen WANG, Hong Kong Baptist University
(6) 12:05~12:15 Discussant to the whole workshop
Prof. Martin LANZENDORF, Goethe University Frankfurt
(7) 12:15~13:00 Open discussion
#114 High Speed Rail and the demand for speed: a sustainability issue (名古屋大学持続的共発展教育研究センターセミナー)
Date
2015年7月8日
Venue
Engineering-Bldg. #8, Room#102, Nagoya University
High Speed Rail and the demand for speed: a sustainability issue (名古屋大学持続的共発展教育研究センターセミナー)
The 5th International Seminar of Committee of Infrastructure Planning and Management, JSCE in FY2015
2015年度土木計画学研究委員会 第5回国際セミナー(通算 第114回国際セミナー)
Education and Research Center for Sustainable Co-Development Seminer
High Speed Rail and the demand for speed: a sustainability issue
Date: July 8 (Wed), 2015 10:30-12:00
Venue: Engineering-Bldg. #8, Room#102, Nagoya University
Lecturer: Prof. Yves Crozet
(the Laboratory of Economy of the Transport (LET), Lumi?re University Lyon 2)
キックオフ会議・第一回研究会
キックオフ会議・第一回研究会
「市民生活行動学」は地方創生と若者生活に関する研究の根拠理論の1つとして位置づけられている。当該図書の解説を通じて、地方創生を考える新しい視点の提示を試みたい。
演題:「東京」に出る若者たち―仕事・社会関係・地域間格差講演者:日本女子大学人間社会学部・石黒格准教授(演題の図書(ミネルヴァ書房,2012年9月)の第一著者)
演題:地方創生と若者の移住・定住に関する鳥取県の取り組み講演者:鳥取県地域振興部とっとり暮らし支援課 前田康博様
#113 第4回国際研究BinNセミナー(BinN International Research Seminar #4)
Date
2015年6月13日
Venue
Room. 429 at Faculty of Engineering Bldg. 14, The University of Tokyo (Hongo Campus)
第4回国際研究BinNセミナー(BinN International Research Seminar #4)
The 4th International Seminar of Committee of Infrastructure Planning and Management, JSCE in FY2015
2015年度土木計画学研究委員会 第4回国際セミナー(通算 第113回国際セミナー)
第4回国際研究BinNセミナー(BinN International Research Seminar #4)
“Dynamic modeling based on bounded rationality to understand diversifying travel behavior”
Host:
JSPS Kaken S/A by Kuwahara, M.(Tohoku Univ) and Hato, E.(UT)
The 4th International BinN Research Seminar “Dynamic modeling based on bounded rationality to understand diversifying travel behavior” will be held on Saturday June 13th 2015. As keynote speakers, we will invite Dr. Theo Arentze from Eindhoven University of Technology and Prof. Morikawa from Nagoya University. Dr. Arentze is currently doing research on dynamic activity-based modeling involving human cognition and learning. In this seminar, the keynote lectures will focus on bounded rationality in individual decision making, and its implications for policy making. In addition, two invited researchers will discuss new approaches to disaggregate behavioral modeling.
Summary:
Although much progress has been made over the years, the basis of current transport models is still the rational-agent model. This traditional view is regarded to lead to numerous biases in the description of human behavior. In this seminar, new approaches to travel behavior modeling based on bounded rationality are discussed, particularly focusing on how to accurately represent the decision making context and process. In addition, this seminar aims at discussing about methods for integrating new data and technologies into models.
Program:
Date: June 13th (Sat.) 2015, 1:30 pm – 5:00 pm
Venue: Room. 429 at Faculty of Engineering Bldg. 14, The University of Tokyo (Hongo Campus)
1:30 pm – 2:30 pm
Keynote Lecture 1: “The role of bounded rationality in travel choice behavior and implications for transport modeling”
Theo Arentze (Eindhoven University of Technology)
* This lecture’s abstract and Dr. Connors brief bio can be found below.
2:45 pm – 3:30 pm
Keynote Lecture 2: “Bounded Rationality in Travel Behavior Modeling”
Takayuki Morikawa (Nagoya University)
3:40 pm – 4:20 pm
Research Presentation 1
“Modeling shopping behavior in a neighborhood with endogenous representation of retail attractiveness”
Makoto Chikaraishi (Hiroshima University)
4:20 pm – 5:00 pm
Research Presentation 2
“Choice set generation of pedestrian route choice using data distribution of walking behavior in urban space”
Sachiyo Fukuyama (National Institute for Land and Infrastructure Management)
After party:
After party will probably take place around the University of Tokyo in the evening.
Application:oyama[at]bin.t.u-tokyo.ac.jp (mail to Yuki OYAMA)
Free to attend
The symposium is open to public.
* You can see information about past seminars here.
Title & Abstract
“The role of bounded rationality in travel choice behavior and implications for transport modeling”
Understanding people’s activity-travel behaviour is critical for effective policy making in urban and transport planning. Traditionally, transport models play an important role as a tool for forecasting and policy evaluation. Although much progress has been made over the years, the basis of current transport models is still the rational-agent model. Recent experimental research in psychology and behavioural economics show that this traditional view on behaviour is severely misguided. Numerous biases, which stem from heuristics people use in judgment and decision making, have been revealed. In the presentation I discuss what the known biases in (travel) choice behaviour are, what there implications are for policy making and how they can be taken into account in new approaches to travel behaviour modelling. I argue that a prerequisite for incorporating bounded rationality in transport models is that the current cross-sectional basis is replaced by a longitudinal, dynamic approach. First steps in this direction have recently been made and are supported by new GPS-based survey technologies which allow collection of activity-travel behavior data for longer periods of time. Although dynamic models offer appealing new perspectives, they also raise new issues when it comes to implementation in large-scale simulation systems and application in practice. Only recently the new approach is being explored and experience to date is limited to small-scale prototype systems. I will review approaches in the area of dynamic activity-based models for large-scale micro-simulation and discuss theoretical and computational issues as well as first experiences.
Brief Bio:
Dr. Theo Arentze is associated professor of Urban Planning at the Eindhoven University of Technology. His research interests include activity-based modelling, discrete choice modelling, agentbased modelling, human cognition/learning, and traveller information systems for application in transportation and urban planning. The main focus of his research is to increase behaviour realism in models of spatial choice behaviour of individuals and households in urban environments. The results of his research find application in large-scale simulation systems of urban processes. An example is the Albatross model which has defined a new state-of-the-art in travel demand modelling. He is involved as principle researcher, supervisor or project leader in a constant stream of PhD, Postdoc and EU projects on these topics. He is member of the editorial board of several international peerreviewed journals and acts as an ad-hoc reviewer and program committee member for many journals, conferences and research foundations in transportation, planning, geography and consumer research.
第51回土木計画学研究発表会・春大会
第51回土木計画学研究発表会・春大会
土木計画学研究委員会は下記の概要で第51回土木計画学研究発表会(春大会)を開催いたします.
企画論文部門は、オーガナイザーを公募し提案された企画テーマでの論文公募を行い、口頭発表またはポスター形式での発表を行うものです。SS部門は、既存の研究小委員会等が主催して、研究討議・意見交換を中心にセッションを構成するもので、本大会では12 セッションを限度とします。また、企画論文部門・SS部門の並行セッションは最大10 会場を想定しております。
企画部門およびSSオーガナイザー申込 <終了しました>
たくさんのご応募ありがとうございました。
公共政策デザインコンペは、学生グループまたは学生個人(2015年2 月28 日時点)を対象に「われわれを取り巻く社会環境における問題を自ら発見し、その問題の背景を熟考し、これを含めた社会を改善するための手立て(公共政策)の提案」を募集し、プレゼンテーションならびにポスター展示による発表を競うものです。優秀な作品には、以下の賞が授与されます。 岡田賞(主として実践的取組を評価:賞金5万円)、北村記念賞(主として構想力を評価:賞金5万円)、土木計画学委員会賞(賞金5万円)
○企画論文部門
企画テーマの応募:2014年11月11日(火)(予定)~2014年11月28日(金)
発表希望者の論文題目・概要の登録:2014年12月12日(金)~2015年2月6日(金)企画論文部門のセッション一覧はこちら
企画論文投稿ページはこちら
オーガナイザーによる採否決定期間:2015年2月20日(金)~2015年3月13日(金)(予定)
論文投稿:2015年4月24日(金)まで
○スペシャルセッション(SS) 部門
テーマの申請 2014年11月11日(火)(予定)~2014年11月28日(金)
発表者の決定 2015年3月13日(金)まで
○公共政策デザインコンペ
応募受付 2015年3月13日(金)まで
ポスター提出 2015年5月8日(金)まで
応募申込みページはこちら
実施要領はこちら
発表プログラム(概略版)
発表プログラム(詳細版:1日目)
発表プログラム(詳細版:2日目)
<発表プログラムの注意事項>
・今後,若干の修正が入る可能性があります.
・並行するセッションにおいて発表者およびオーガナイザーが重複しないように作成されています.ただし,連名者については並行セッションでの重複が生じる場合がありますが,ご了承ください.
※企画論文セッション「ITS(高度道路交通システム)」は,電子情報通信学会ITS研究会との併催となっております.これらのセッション会場に隣接する会場にて,電子情報通信学会ITS研究会も同時開催されており,参加費は無料とのことです.ご興味のある方は,こちらへのご参加もご検討ください.研究会情報は,こちらからご覧いただけます.
参加登録(発表者以外の方):次の土木学会行事参加申し込みホームページより,ご登録ください.
聴講参加者の受付締切は5月27日(水),参加費は一般6,000円,学生3,000円です.
なお,発表者(企画部門,公共政策デザインコンペ部門(5名以内))は自動的に登録されていますので,あらためての参加登録は不要です.
スペシャルセッションのオーガナイザーの方は,参加登録が必要です.
以下の参加申込書をダウンロードし,必要事項を記入して土木学会宛にお送りいただく(FAX,郵送)ことでも,参加登録は可能です.締切および参加費はホームページからの申し込みの場合と同じです.
参加申込書(PDF / MS-Word)
事前参加申し込みに関する注意事項
・事前参加申し込みの締め切りは5月27日(水)となっております.事前申し込みをされた方には,5月末までに,「参加券」,「請求書」等をお送りする予定です.
・本行事の参加費支払いは事前入金制となっておりますので,申込みフォームの「当日払い」,「現金持参」は選択しないでください.
・締切日以降の事前受付はいたしません.締切日を過ぎてからのお申し込みは,行事当日に会場にて受付いたします.
・お申し込み後,やむを得ずキャンセルされる場合は,必ず開催日の1週間前までに研究事業課宛にご連絡ください.ご連絡がない場合は,参加費を徴収させて頂きますので予めご了承ください.
★聴講者用にレジュメ50部をご用意の上,各セッション会場にて配布して下さい.
(1)講演時間
セッションの時間は,すべて90分です.
発表時間等は基本的にオーガナイザーの指示に従ってください.
(2)講演打ち合わせ
セッション開始10分前に各発表会場に集合し,オーガナイザー・司会者および会場担当者とセッションの進め方に関する打ち合わせを行って下さい.
(3)発表時の使用機器について
各発表会場には,液晶プロジェクターとディスプレイケープルを準備します(OHP,スライドは使用できません).なお,ノートPCは各自で持参して下さい. 各発表会場に設置されている液晶プロジェクタヘの接続は,各発表者の責任にて行って下さい.セッションが円滑に進行するようにご準備のご協力をお願い致します.
(4)ポスターセッション
プログラム(概略版や詳細版)のセッション名の横に(P)が入っているセッションは,オーガナイザーにより,ポスター発表形式でのセッションを指定されたセッションです.ポスターのみによる発表とするか,あるいはプロジェクターでの発表を併用するかなどは,各セッションのオーガナイザーにお問い合わせください.
ポスターセッションの際に利用されるパネル,貼り付け用文具等は,オーガナイザーの責任によりご準備ください.開催校からは提供されませんのでご注意ください.
当該年度の1~2月に募集を行う土木学会論文集D3(土木計画学)・特集号(以下「特集号」と表記)への投稿資格が与えられるのは、以下の①、②の両条件を満たす場合に限られます。
① 規定の応募方法に従って企画論文部門*に投稿された発表会前原稿のうち、文量が2ページ以上の論文であること。
② 研究発表会において、著者により当該論文の発表が行われている**こと。
* 特集号への投稿資格を満たさない論文でも、企画論文部門セッションで発表すること自体は可能です。なお、SS部門への投稿論文については、特集号への投稿資格はありません。
** 発表がキャンセルされた場合、たとえ①の条件を満たしていても特集号への投稿資格はありません。また、著者以外の第三者による代理発表がなされた場合も投稿資格はありません。
詳しくは、計画学ホームページをご覧下さい。
http://www.jsce.or.jp/committee/ip/monograph/file/journal-s-tebiki.pdf
土木計画学研究委員会春大会運営小委員会
e-mail: keikaku51@jsce.or.jp
土木学会事務局
林 淳二 e-mail: j-hayashi@jsce.or.jp Tel:03-3355-3559
https://jsce-ip.org/
#111 Special Seminar Series on Transportation Planning and Travel Behavioral Analysis (Axhausen教授を囲む会)
Date
2015年5月28日
Venue
Meeting Room of International Project Lab., 3rd floor of Engineering Building No.11, Hongo Campus, The University of Tokyo
Special Seminar Series on Transportation Planning and Travel Behavioral Analysis (Axhausen教授を囲む会)
The 2nd International Seminar of Committee of Infrastructure Planning and Management, JSCE in FY2015
2015年度土木計画学研究委員会 第2回国際セミナー(通算 第111回国際セミナー)
Special Seminar Series on Transportation Planning and Travel Behavioral Analysis
交通計画・交通行動分析の連続国際セミナー(Axhausen教授を囲む会)
日本語版
1. 主催者:加藤浩徳(東京大学),福田大輔(東京工業大学)
2. 後援:土木学会土木計画学研究委員会
3. 開催趣旨:本年4月より7月まで,スイス連邦工科大学(ETH)チューリッヒ校のKay Axhausen教授が,東京大学の客員研究員として滞在されています.Axhausen教授は,Transportation誌の編集長を務めるなど,交通計画・交通行動分析の分野で世界的に広く知られる研究者です(詳しくはこちら).せっかくの機会ですので,Axhausen教授にご参加いただいて,交通計画・交通行動分析に関わる国際セミナーを連続で開催します(Axhausen教授は,全ての回に出席される予定です).皆様のご参加をお待ちしております.
4. 場所:東京大学・本郷キャンパス工学部11号館 3階国際プロジェクト研究室会議室(113-8656 東京都文京区本郷7-3-1)
5. 参加費:無料(参加人数を知りたいので,参加を希望される方は,事前に加藤までご連絡願います.)
6. 言語:英語のみです.
7. その他:終了後に簡単な懇親会を開催する予定です.
8. スケジュール(案)
第1回 5月28日(木)16:00-18:00
1. Kay Axhausen (ETH, Zurich): Social Network and Transportation
2. 加藤浩徳(東京大学):Recent Issues of Urban Rail Network in Tokyo
第2回 6月4日(木)16:00-18:00
1. 山本俊行(名古屋大学): Analysis on Battery Charging Behavior of Electric Vehicles
2. Giancarlos Troncoso(東京大学): The Effect of Social Networks and Personality Traits on Out-of-home Leisure Activity Generation: A Case Study of Fukuoka, Japan
第3回 6月12日(金)16:00-18:00
1. 小早川悟(日本大学): Parking Management System in Japan, Current and Future Perspective
2. 佐々木邦明(山梨大学): Real-time Adjustment of Parameters in a Traffic Simulator
第4回 6月19日(金)16:00-18:00
1. 大森宣暁 (宇都宮大学): Recent Trends in Travel Time Use: Impacts of Mobile ICTs
2. 松尾美和 (早稲田大学): Efficiency and Effectiveness of Rural Bus Transit in the US
第5回 6月25日(木)16:00-18:00
1. 日下部貴彦(東京工業大学): Continuous Travel Behaviour Data Collection from Smart Devices
2. 羽藤英二・大山雄己(東京大学): Trip Chain Analysis using Probe Data Collected Through Mobile Phones
第6回 7月3日(金)16:00-18:00
1. 大口敬(東京大学): Impact of ACC Introduction for Alleviating Motorway Bottlenecks
2. 清水哲夫(首都大学東京): Tourism Policies, Data and Researches in Japan
第7回 7月16日(木)17:00-19:00
1. 福田大輔(東京工業大学): Development of Hyperpath-based Risk-averse Route Guidance System and its Verification by a Field Experiment
2. 米崎克彦(運輸調査局): Overview of Air Transport Policy in Japan
English version
1. Organizers: Prof Hironori Kato (The University of Tokyo) and Dr Daisuke Fukuda (Tokyo Institute of Technology)
2. Support: Infrastructure Planning Committee, JSCE
3. Purpose: Professor Kay Axhausen from ETH (Swiss Federal Institute of Technology), Zurich has been staying at the University of Tokyo as Visiting Professor from April to July, 2015. He is a well-known transportation researcher, for example the editor-in-chief of Transportation (see more details here). Then we organize a series of seminars regarding transportation planning and travel behavioral analysis where Professor Axhausen join and discuss together. At each seminar two presenters will give short talks. Anyone who is concerned with the seminars is invited. Please contact Professor Hironori Kato for your participation.
4. Location: Meeting Room of International Project Lab., 3rd floor of Engineering Building No.11, Hongo Campus, The University of Tokyo
5. Language: English
6. Contact: Professor Hironori Kato
7. Other: Small networking-party will be held after each seminar.
8. Schedule
Seminar 1: 16:00-18:00 May 28 (Thursday)
1. Prof Kay Axhausen (ETH, Zurich): Social Network and Transportation 2. Prof Hironori Kato (The University of Tokyo):Recent Issues of Urban Rail Network in Tokyo
Seminar 2: 16:00-18:00 June 4 (Thursday)
1. Prof Toshiyuki Yamamoto (Nagoya University): Analysis on Battery Charging Behavior of Electric Vehicles
2. Dr Giancarlos Troncoso (The University of Tokyo): The Effect of Social Networks and Personality Traits on Out-of-home Leisure Activity Generation: A Case Study of Fukuoka, Japan
Seminar 3: 16:00-18:00 June 12 (Friday)
1. Prof Satoru Kobayakawa (Nihon University): Parking Management System in Japan, Current and Future Perspective
2. Prof Kuniaki Sasaki (University of Yamanashi): Real-time Adjustment of Parameters in a Traffic Simulator
Seminar 4: 16:00-18:00 June 19 (Friday)
1. Prof Nobuaki Ohmori (Utsunomiya University): Recent Trends in Travel Time Use: Impacts of Mobile ICTs
2. Dr Miwa Matsuo (Waseda University): Efficiency and Effectiveness of Rural Bus Transit in the US
Seminar 5: 16:00-18:00 June 25 (Thursday)
1. Dr Takahiko Kusakabe (Tokyo Institute of Technology): Continuous Travel Behaviour Data Collection from Smart Devices
2. Prof Eiji Hato & Yuki Oyama: Trip Chain Analysis using Probe Data Collected Through Mobile Phones
Seminar 6: 16:00-18:00 July 3 (Friday)
1. Prof Takashi Oguchi (The University of Tokyo): Impact of ACC introduction for Alleviating Motorway Bottlenecks
2. Prof Tetsuo Shimizu (Tokyo Metropolitan University): Tourism Policies, Data and Researches in Japan
Seminar 7: 17:00-19:00 July 16 (Thursday)
1. Dr Daisuke Fukuda (Tokyo Institute of Technology): Development of Hyperpath-based Risk-averse Route Guidance System and its Verification by a Field Experiment
2. Dr Katsuhiko Yonezaki (Institute of Transportation Economics): Overview of Air Transport Policy in Japan
#112 Global Economy and the Emerging Role of India (第9回グローバルビジネス講演会)
Date
2015年5月23日
Venue
Case Study Room, 3F Reserhc Bldg No.2, Graduate School of Management, Kyoto University
Global Economy and the Emerging Role of India (第9回グローバルビジネス講演会)
The 3rd International Seminar of Committee of Infrastructure Planning and Management, JSCE in FY2015
2015年度土木計画学研究委員会 第3回国際セミナー(通算 第112回国際セミナー)
Global Economy and the Emerging Role of India (第9回グローバルビジネス講演会)
Date: May 23 (Sat), 2015 14:45-16:15
Venue: Case Study Room, 3F Reserhc Bldg No.2, Graduate School of Management, Kyoto University
Organizer:Research in Bisiness Administrattion, Graduate School of Management, Kyoto University
Detailed informaion is shown here.
Lecture: Moving People.Connecting Neighbourhoods: The 20 Minute City
Lecture: Moving People.Connecting Neighbourhoods: The 20 Minute City
Dr. Janet Stanley (The University of Melbourne) & Prof. John Stanley (The University of Sydney)
15:00 – 17:00, April 24 (Friday)
Small Meeting Room of IDEC (1F), Graduate School for International Development and Cooperation, Hiroshima University
#110 Current Issues and Future Prospect of Locally Adapted, Modified and Advanced Transportation (LAMAT) in Developing Countries
Date
2015年4月20日
Venue
Royal Blue Hall, TokyoTech Front
Current Issues and Future Prospect of Locally Adapted, Modified and Advanced Transportation (LAMAT) in Developing Countries
The 1st International Seminar of Committee of Infrastructure Planning and Management, JSCE in FY2015
2015年度土木計画学研究委員会 第1回国際セミナー(通算 第110回国際セミナー)
The 14th TSU Seminar
“Current Issues and Future Prospect of Locally Adapted, Modified and Advanced Transportation (LAMAT) in Developing Countries”
「開発途上国におけるパラトランジットの現状と将来」
Date: April 20 (Mon), 2015 13:00-16:45
Venue: Royal Blue Hall, TokyoTech Front (Oookayama 2-12-1, Meguroku, 1520033, Tokyo)
Organizer: TokyoTech Transport Studies Unit (TSU)
Support: Infrastructure Planning Committee, JSCE, Eastern Asia Society for Transportation Studies, and Association for Planning and Transportation Studies
Detailed informaion is shown here (in English and Japanese).
#76 幹線旅客交通のフロンティア
Date
2015年3月27日
Venue
土木学会講堂
幹線旅客交通のフロンティア
土木計画学ワンデーセミナー NO.76 幹線旅客交通のフロンティア 企画:都市間旅客交通研究小委員会((公社)土木学会 土木計画学研究委員会) 本小委員会については,http://strep.main.jp/modules/pico3/index.php?content_id=25をご覧ください. 参加費:無料 趣旨:日本は,世界でも稀な高密度の幹線交通網を実現した国土を有している. 質の高い幹線輸送手段はわが国の経済活動を支える上で重要なばかりで なく, 今後の発展が見込まれる東南アジア,インド,南米等においても,日本で蓄積さ れた幹線交通網整備の知見が注目を集めている.このセミナー は,幹線旅客交 通に関する実務的な課題と最新の研究成果を共有することによって,政策課題の 発掘と研究課題の深化を図るものである. 日時:3月27日(金) 10:30 ? 17:30 場所:土木学会講堂(160-0004 東京都新宿区四谷一丁目外濠公園内) タイムテーブル案 (カッコ内は所属,敬称略) 1030 to 1035 塚井誠人(広島大学):本セミナーの趣旨 1035 to 1120 春名幸一(JR西日本)「(仮)北陸新幹線への期待」 1120 to 1205 新倉淳史(運政研)「都市間交通に関する統計~全国幹線旅客純流動調査の展望」 昼食75分 1320 to 1405 竹林幹雄(神戸大学)「航空輸送と高速鉄道の共存における課題」 1405 to 1450 金子雄一郎(日本大学)「震災時の都市間交通特性とネットワークの脆弱性評価」 休憩15分 1505 to 1550 柴田宗典(鉄道総研)「多目的最適化による都市間交通のサービス供給計画」 1550 to 1635 山口裕通(東北大学)「都市間旅行回数分布の経年変化と将来予測」 休憩15分 1650 to 1710 奥村誠(東北大学)「(仮)研究と実務の融合に向けて」 司会:塚井誠人(広島大学) お問い合わせ先:塚井誠人
#109 「アジアにおける持続可能な交通(EST)」公開国際シンポジウム
Date
2015年3月19日
Venue
名古屋大学 東山キャンパス 環境総合館 1階 レクチャーホール
「アジアにおける持続可能な交通(EST)」公開国際シンポジウム
The 16th International Seminar of Committee of Infrastructure Planning and Management, JSCE in FY2014
2014年度土木計画学研究委員会 第16回国際セミナー(通算 第109回国際セミナー)
「アジアにおける持続可能な交通(EST)」公開国際シンポジウム
“Public Symposium on Environmentally Sustainable Transport (EST) in Asia”
日時:2015年3月19日(木) 13:00 – 17:00
場所:名古屋大学 東山キャンパス 環境総合館 1階 レクチャーホール
共 催:名古屋大学大学院環境学研究科附属持続的共発展教育研究センター (SusCoDe)、国際連合地域開発センター(UNCRD)
対 象:科学者、研究者、民間企業、行政機関、ご関心のある一般の方
言 語:英語(日本語同時通訳あり)
参加費:無料
申 込:以下のアドレスに氏名・所属先・メールアドレスをご記入の上、事前にお申し込みください。
estasia[at]ercscd.env.nagoya-u.ac.jp
※※[at]と@に変換してください。
プログラム
13:00 – 13:20 開会の辞
13:20 – 13:45 「アジアEST地域フォーラムの成果」 (UNCRD)
13:45 – 14:10 基調講演「バンコク2020宣言を越えて」(名古屋大学・共発展センター)
パネルディスカッション
14:10 – 15:20 セッション1:「統合されたEST政策とレジリエンス(社会の復元力)」
15:20 – 15:30 休憩
15:30 – 16:40 セッション2:「PPP-ESTのための戦略的金融・投資」
16:40 – 16:50 まとめ(UNCRD、共発展センター)
16:50 – 17:00 閉会の辞
共発展センター・ウェブサイト:
http://ercscd.env.nagoya-u.ac.jp/jpn/announcements/event/est.html
#75 少子高齢社会における子育てしやすいまちづくり ~大都市と地方都市、都心と郊外、どちらが子育てしやすいか?~
Date
2015年3月14日
Venue
土木学会講堂
少子高齢社会における子育てしやすいまちづくり ~大都市と地方都市、都心と郊外、どちらが子育てしやすいか?~
土木計画学ワンデーセミナー NO.75
少子高齢社会における子育てしやすいまちづくり~大都市と地方都市、都心と 郊外、どちらが子育てしやすいか?~
日時:2015年3月14日(土)
場所:土木学会講堂(東京都新宿区四谷一丁目外濠公園内)
http://www.jsce.or.jp/contact/map.shtml
定員:120名
参加費:無料
○開催主旨:
人口減少、少子高齢社会に直面する我が国において、子育てしやすいまちづくり が求められている。近年、バリアフリー法等の整備により、道路や公共交通、公 共施設や商業施設などのバリアフリー化が進められ、一昔前と比べると子ども連 れで外出しやすい環境が整ってきた。しかし、例えば大都市ではベビーカーで公 共交通を利用する際に、周囲の乗客とコンフリクトが生じるなどの課題も指摘さ れている。一方、保育所待機児童の問題をはじめ、子育てしながら働きやすい環 境の整備も重要な課題である。本ワンデイセミナーでは、土木計画学および他分 野の研究者、行政、民間、NPOなど、多様な立場の方々が一堂に会し、これまで の研究成果の一部の報告と、最近の我が国の関連制度の報告をもとに、大都市と 地方都市、都心と郊外など、地域特性に応じた子育てしやすいまちづくりの方向 性について幅広く議論を行うことを目的とする。
○プログラム:
13:30-13:35 開会挨拶
13:35-15:45 報告
1.「東京都市圏パーソントリップ調査における子育て世帯の交通行動特性」石 神孝裕(IBS)
2.「北部九州圏パーソントリップ調査における子育て世帯の交通行動特性」辰 巳浩(福岡大学)
3.「ライフサイクルステージに着目した自動車利用と外出活動との関係性~高 松市の事例~」宮崎耕輔(香川高専)
4.「子育て意識の世代間ギャップ」谷口綾子(筑波大学)
質疑応答(14:45-15:00)
5.「公共交通機関等におけるベビーカー利用に関する協議会について」松原淳 (交通エコロジー・モビリティ財団)
6.「立地適正化計画と子育て」高柳百合子(国土交通省都市局)
7.「子ども・子育て支援新制度について」海老敬子(松戸市)
質疑応答(15:35-15:45)
15:45-16:00 休憩
16:00-17:25 パネルディスカッション
テーマ:子育てしやすいまちの実現のために
パネリスト:長野博一(荒川区)
松田妙子(せたがや子育てネット)
西本由紀子(神戸女子大学)
寺内義典(国士舘大学)
宮崎耕輔(香川高専)
司会:大森宣暁(宇都宮大学)
17:25-17:30 閉会挨拶
17:45-19:00 懇親会
※懇親会参加費は1,000円です。
※お申込み:大森(nobuaki[at]cc.utsunomiya-u.ac.jp)宛て、「お名前」、「ご所 属」、「懇親会参加のご希望」をご記入の上、3月10日(火)頃までにお申し込み 下さい。
※※[at]と@に変換してください。
※小学校3年生までの保育サービス(無料)の実施を検討しております。ご希望の 方は、セミナー申込みと合わせてご相談下さい。
#74 交通関連ビッグデータは土木計画の研究と実務に何をもたらすか?
Date
2015年3月9日
Venue
東京工業大学蔵前工業会館内 「くらまえホール」
交通関連ビッグデータは土木計画の研究と実務に何をもたらすか?
土木計画学ワンデーセミナー NO.74
交通関連ビッグデータは土木計画の研究と実務に何をもたらすか?
日時:2015年3月9日(月曜日) 9:30~18:00
場所:東京工業大学蔵前工業会館内 「くらまえホール」
〒152-0033 目黒区大岡山2丁目12-1(東急目黒線・大井町線大岡山駅徒歩1分)
http://www.somuka.titech.ac.jp/ttf/access/index.html
定員:200名(定員になり次第締め切り)
参加費:無料
申し込み方法:土木学会 行事申し込みWEB よりお申し込み下さい(行事コード:40402)
http://www.jsce.or.jp/event/active/information.asp
主催:(公益社団法人)土木学会・土木計画学研究委員会・交通関連ビッグデータの社会への実装研究小委員会
共催:(一般社団法人)交通工学研究会
■開催趣旨
交通に関わるデータの収集技術は,近年,質・量共に飛躍的に高度化・深度化したが,得られたビッグデータの利活用方法や,計画体系への適切な導入方法についての議論は十分ではない.これらのデータの特性と限界に関する理解を深めた上で,既存調査に対する代替可能性や,新たな政策課題分析への適用可能性を明らかにすることが喫緊の課題である.本セミナーでは,このような問題意識で発足した2年間の本小委員会での議論や成果を報告すると共に,交通関連ビッグデータを研究している研究者や実務で取り扱っている方々をお招きして,関連する最新の知見の紹介や,交通関連ビッグデータの今後の展望について,研究者・実務者双方の視点から検討する.
■詳細 http://www.plan.cv.titech.ac.jp/fukudalab/big-data0309/
お問い合わせ先:
小委員会事務局長 東京工業大学 福田大輔(fukuda[at]plan.cv.titech.ac.jp )
※[at]と@に変換してください。
#108 第3回国際研究BinNセミナー(BinN International Research Seminar #3)
Date
2015年3月4日
Venue
Room. 411 at Faculty of Engineering Bldg. 1, The University of Tokyo (Hongo Campus)
第3回国際研究BinNセミナー(BinN International Research Seminar #3)
The 15th International Seminar of Committee of Infrastructure Planning and Management, JSCE in FY2014
2014年度土木計画学研究委員会 第15回国際セミナー(通算 第108回国際セミナー)
第3回国際研究BinNセミナー(BinN International Research Seminar #3)
“Network configuration and multi-scale behavior analysis”
Host:
Grant-in-Aid for Scientific Research S (Principle Investigator: Masao Kuwahara)
“Dynamic risk management of transportation networks using mobile system monitoring”
Group 3 Dynamic network management
Co-host: Committee of Infrastructure Planning and Management
The 3rd International BinN Research Seminar “Network configuration and multi-scale behavior analysis” will be held on March 4th 2015. The keynote speaker will be Dr. Richard Connors from the Institute for Transport Studies (University of Leeds). Dr. Connors is currently doing research on network equilibrium and topological configuration of transportation networks. His lecture will focus on understanding how network configuration impacts performance. In addition, two researchers will discuss their research regarding travel behavior and the recognition of behavioral space.
Summary:
The optimal spatial scale of analysis of travel behavior differs given the target behavior of interest. As a result, modelling travel behavior in micro, meso and macro scale is necessary to adequately analyze and evaluate transportation networks. In addition, scale aggregation is sometimes necessary not only to match the scale at which spatial recognition is conducted by individuals, but also to reduce calculation costs. This seminar aims at deepen the discussion regarding the relationship between spatial configuration and travel behavior in a multi-scale framework.
Program:
Date: March 4th 2015, 9:30am – 11:30am
Venue: Room. 411 at Faculty of Engineering Bldg. 1, The University of Tokyo (Hongo Campus)
9:30 am – 10:30 am
Keynote Lecture: “Ensemble Analysis of Transport Networks”
Richard Connors (Institute for Transport Studies, University of Leeds)
* This lecture’s abstract and Dr. Connors brief bio can be found below.
10:30 am – 11:00 am
Research Presentation 1
“Experimental study of driving behaviour of personal mobility vehicles”
Miho Iryo-Asano (The University of Tokyo)
11:00 am – 11:30 am
Research Presentation 2
“A joint estimation model of destination choice and evacuation timing: Case study of Kesennuma City”
Giancarlos TRONCOSO (The University of Tokyo)
Application:gtroncoso[at]bin.t.u-tokyo.ac.jp (mail to Giancarlos TRONCOSO)
Free to attend
The symposium is open to public.
* You can see information about past seminars here.
Title & Abstract
”Ensemble Analysis of Transport Networks”
How does the topological configuration of a transport network impact upon its performance? Answering this question is difficult because the space of all possible transport networks is large (of high dimension). Moreover, each network in this space could have flows arising from a high dimensional space of all possible demand matrices. Nevertheless, we seek to answer this question by bringing together characterisations of the topology, structural properties and spatial embedding of transport networks. We adopt an approach from Network Science and generate ensembles of synthetic road-like networks in order to systematically test performance as a function of topology. Here I set out a methodology and highlight the research questions that need to be considered within this process of generating synthetics networks, grouping them into ensembles and analysing their performance.
Brief Bio:
Dr Richard Connors is a senior research fellow at ITS-Leeds, UK. He has published research on a range of transport problems, including models for network equilibrium, bi-level network design, quasi-dynamic traffic assignment, network reliability and predictive accident models. Richard’ s current research considers characteristics of urban systems that arise from the spatial configuration of transportation infrastructure. The aim, in the context of transport systems, is to understand how network configuration impacts upon network performance, to what extent universal features emerge and can be identified in such systems, and hence how to establish methods to model urban evolution on the aggregate scale that consistently represent the underlying networked infrastructures. This research framework comprises work on: the analytic aggregation of network equilibrium models; network evolution algorithms; empirical ensemble analysis of synthetic planar networks; multi-objective optimisation of urban spatial evolution.
#107 International workshop on context and social interactions in activity and travel decisions
Date
2015年3月4日
Venue
Large Meeting Room (1F), Graduate School for International Development and Cooperation, Hiroshima University
International workshop on context and social interactions in activity and travel decisions
The 14th International Seminar of Committee of Infrastructure Planning and Management, JSCE in FY2014
2014年度土木計画学研究委員会 第14回国際セミナー(通算 第107回国際セミナー)
International workshop on context and social interactions in activity and travel decisions (The 3rd IWATS)
Time: 9:00-19:00, March 4 (Wednesday)
Venue: Large Meeting Room (1F), Graduate School for International Development and Cooperation, Hiroshima University
Language: English
Free of charge and open to the public, but need to register via e-mail
Program:
[9:00-9:10] Opening remarks
Opening remarks [Akimasa Fujiwara, Hiroshima University]
[9:10-11:10] Session 1: Local interactions in different contexts (Moderator: Makoto Chikaraishi)
Influences of home-workplace configuration and motorcycle ownership on two-worker households’ task allocation in Hanoi, Vietnam / Tran Minh Tu, Makoto Chikaraishi, Junyi Zhang, Akimasa Fujiwara (Hiroshima University)
The Role of subjective social norms on students car purchase intention / Prawira Fajarindra Belgiawan (Kyoto University), Jan-Dirk Schm?cker (Kyoto University), Maya Abou-Zeid (American University Beirut), Joan Walker (University California at Berkeley), Satoshi Fujii (Kyoto University)
Analysis of social interactions in evacuation behaviors using a structural estimation / Junji Urata, Eiji Hato (The University of Tokyo)
[11:10-11:30] Break
[11:30-12:30] Keynote 1
Survey challenges, modelling challenges [Kay Axhausen, ETH Z?rich]
[12:30-13:30] Lunch
[13:30-14:30] Keynote 2
Context-sensitive behavior analysis and life-oriented approach: Re-visiting residential self-selection issues [Junyi Zhang, Hiroshima University]
[14:30-14:50] Break
[14:50-16:50] Session 2: Social interactions and mechanism design (Moderator: Hajime Seya)
Transportation service auction mechanism for preference elicitation / Yusuke Hara (Tohoku University)
Analysis of driver’s interaction on highways with structural estimation / Atsushi Ito, Hideki Yaginuma, Eiji Hato (The University of Tokyo)
Spatially explicit land-use scenarios and urban resilience / Yoshiki Yamagata (National Institute for Environmental Studies), Hajime Seya (Hiroshima University), Murakami Daisuke (Tsukuba University)
[16:50-17:10] Break
[17:10-18:30] Session 3: Interactions in long-term planning contexts (Moderator: Makoto Tsukai)
An analysis of intermodal competition on intercity transportation network / Kazuaki Okubo (Saitama University)
Modelling and estimating positive demand feedback processes / Jan-Dirk Schm?cker (Kyoto University)
[18:30-19:00] Discussion
#106 Prof. William P. Anderson講演会
Date
2015年2月26日
Venue
京都大学桂キャンパスCクラスター C1-2棟 3階 314会議室
Prof. William P. Anderson講演会
The 13th International Seminar of Committee of Infrastructure Planning and Management, JSCE in FY2014
2014年度土木計画学研究委員会 第13回国際セミナー(通算 第106回国際セミナー)
Prof. William P. Anderson講演会
日時:2月26日(木)15:00~17:00(4限)
場所:京都大学桂キャンパスCクラスター C1-2棟 3階 314会議室
http://www.t.kyoto-u.ac.jp/ja/access/katsura
参加費:無料
言語:英語
講師:Prof. William P. Anderson (Director, Cross-Border Institute, University of Windsor)
題目:The Border and the Ontario Economy
概要:Ontario is Canada’s largest province in terms of both population and GDP. It accounts for about half of Canada-US trade, which is still the largest bilateral trade relationship in the world. The great majority of trade is in manufactured goods, many of which are intermediate goods moving between production facilities in cross-border supply chains. Border costs have a negative impact on the efficiency of these supply chains and the production systems they support.
Costs at the Canada-US border are substantial for a number of reasons. NAFTA is not a customs union, so substantial documentation is required even on goods that cross duty-free. There are inconsistent product regulations and health inspections are often repeated on each side of the border. Geography dictates that crossings are limited to a small number of rivers that connect the Great Lakes, so traffic congestion is common. The terrorist attacks of September 11, 2001 led to heightened security measures that have increased the cost and time of border crossings for both goods and people.
This presentation will summarize research on border costs and their economic impacts. It will also review policy initiatives directed at making borders more efficient, with emphasis on reducing border inspections through enhanced supply chain security.
#105 Urban transport in Medellin, Colomnbia and China
Date
2015年2月5日
Venue
横浜国立大学土木工学棟2階セミナー室
Urban transport in Medellin, Colomnbia and China
The 12th International Seminar of Committee of Infrastructure Planning and Management, JSCE in FY2014
2014年度土木計画学研究委員会 第12回国際セミナー(通算 第105回国際セミナー)
Urban transport in Medellin, Colomnbia and China
日時:2015年 2月 5日(木) 10:00~12:00
場所:横浜国立大学土木工学棟2階セミナー室
参加費:無料
言語:英語
講演者:Prof. Ian Salmiento and Prof. Shengchuan Zhao
プログラム:
10:00-10:40
1. Urban transport in Medellin, Colombia by Prof. Ian Salmiento
10:40-11:20
2. Urban transport in China by Prof. Shengchuan Zhao
11:20-12:00
3. Free Discussion
#73 震災20年をむかえた災害研究のこれまでとこれから~土木計画学の視点から
Date
2015年1月23日
Venue
デザイン・クリエイティブセンター神戸KIITO3階303会議室
震災20年をむかえた災害研究のこれまでとこれから~土木計画学の視点から
土木計画学ワンデーセミナー NO.73
震災20年をむかえた災害研究のこれまでとこれから~土木計画学の視点から
日時:2015年1月23日(金)10:00-16:00
場所: デザイン・クリエイティブセンター神戸KIITO3階303会議室
(〒651-0082 兵庫県神戸市中央区小野浜町 1-4)
定員:100名
参加費:無料
主催:土木学会 土木計画学研究委員会
■開催趣旨
阪神淡路大震災から20年をむかえ,土木計画学における災害に関する研究活動の これまでの成果を俯瞰しつつ,今後,どのような研究が必要となるか,また,土 木計画学がその研究活動を通じて防災や減災にどのように貢献できるのかをより 長期的かつ学術的な視点に立って議論することを目的とする.このために,特 に,若手研究者の方に研究発表の時間を設け,最新の研究成果に関する情報提供 と意見交換を行う場を提供する.
■プログラム
10:00-10:20 趣旨および震災後20年の土木計画を振り返る:小池淳司(神戸大 学大学院教授)
10:20-11:00 「TBA」:桑原雅夫(東北大学大学院教授)
11:10-11:50 「TBA」:多々納裕一(京都大学防災研究所教授)
若手研究者 研究セッション
13:00-13:30 広島土砂災害と新聞報道の時系列:赤池美奈(広島大学大学院修 士課程)
13:30-14:00 巨大地震に対する応用一般均衡分析の可能性と課題:山崎雅人 (名古屋大学減災連携研究センター助教)
14:00-14:30 地域における避難時間最小化のための動的流入制御:浦田淳司 (東京大学大学院工学研究科博士課程)
14:30-15:00 東日本大震災時の行動データが明らかにする避難行動の傾向:原 祐輔(東北大学 助教)
15:00-15:30 A joint estimation of destination choice and evacuation timing during tsunami disasters:
A case study of the Great East Japan Earthquake:Giancarlos Troncoso Parady(東京大学復興デザイン研究体特任研 究員)
15:30-16:00 全体コメント・全体討議:井料隆雅(神戸大学大学院教授)
#104 Prof. Sagara講演会
Date
2015年1月14日
Venue
京都大学防災研究所大会議室(S-519D)
Prof. Sagara講演会
The 11th International Seminar of Committee of Infrastructure Planning and Management, JSCE in FY2014
2014年度土木計画学研究委員会 第11回国際セミナー(通算 第104回国際セミナー)
Prof. Sagara講演会
日時:2015年 1月14日(水) 15:00~17:00
場所:京都大学防災研究所大会議室(S-519D)
参加費:無料
言語:英語
講演者:Dr. Saut Sagala (Assistant Professor, Institute of Technology Bandung (IIB), Indonesia)
講演タイトル: Tourists’ Risk Perception and Preparedness to Potential Tsunami: Case Study from Sanur Area, Denpasar, Bali (旅行者のリスク認知と懸念される津波に対する備え:バリ島デンパサール,サヌア地域におけるケーススタディ)
講演概要:This research is part of a larger research umbrella SANREST which stands for Sanur Resilience to Tsunami. Sanur is one of a popular beach areas and tourist resorts in Bali. Despite it’s attraction for tourism sector, some tourism areas in Bali are prone to tsunami disasters. Therefore, it is important to assess the resilience of communities, tourists and local government to tsunami disasters. Currently, only limited literature explores tourist’s understanding (perception) and their preparedness towards disasters. In this particular session, we seek for the information how tourists understand about potential disasters that might occur in the tourism areas. We explore and apply common indicators used when assessing risk perception and preparedness to disasters. In general, tourists have had information or exposed to previous disasters. Nonetheless, we found that only a small number of tourists have prepared information about the potential disasters in Sanur and what to do in case disaster occurs. This implies that equiping enough information and preparedness measures would be very important to ensure tourists’ safety.
#103 超高齢社会の社会インフラと交通に関する国際セミナー
Date
2015年1月14日
Venue
中央大学後楽園キャンパス 5号館 1階 36号室
超高齢社会の社会インフラと交通に関する国際セミナー
The 10th International Seminar of Committee of Infrastructure Planning and Management, JSCE in FY2014
2014年度土木計画学研究委員会 第10回国際セミナー(通算 第103回国際セミナー)
超高齢社会の社会インフラと交通に関する国際セミナー
日時:2015年 1月14日(水) 10:00受付開始
場所:中央大学後楽園キャンパス 5号館 1階 36号室
参加費:無料
主催:中央大学研究開発機構、土木計画学研究委員会「移動権の考え方に基づく移動環境の整備・評価に関する研究小委員会(山田委員長)」、日本福祉のまちづくり学会「国際委員会(北川委員長)」「地域福祉交通委員会(吉田委員長)」「オリ・パラ委員会(秋山委員長)」
セミナーの概要:この度、土木計画学研究委員会と日本福祉のまちづくり学会、中央大学、ロンドン大学(UCL)の3者の合同で国際セミナーを開催する運びとなりました。海外やオリンピック・パラリンピックの最近の話題、車いすとモビリティに関する研究、高齢者・障害者の交通に関する研究、などが主要テーマです。詳しくはこちらをご覧ください。
#72 航空輸送に関する高度なモデル化と統計分析手法の政策への応用:手法論と政策論
Date
2015年1月12日
Venue
土木学会講堂
航空輸送に関する高度なモデル化と統計分析手法の政策への応用:手法論と政策論
土木計画学ワンデーセミナー NO.72
航空輸送に関する高度なモデル化と統計分析手法の政策への応用:手法論と政策論
日時:1月22日(木)
場所: 土木学会講堂(東京都新宿区四谷一丁目 外濠公園内)
定員:120名
参加費:無料 ※既に定員に達しております。
主催:土木学会 土木計画学研究委員会
後援:一般財団法人 運輸政策研究機構
■開催趣旨
90年代以降,世界的な規模で航空輸送における規制緩和・自由化が進行し,輸送市場は拡大の一途にあるといえる.このような中で,従来の商慣習に囚われない,新しいビジネスモデルを携えて市場に登場した航空会社も少なくない.LCCをはじめとする新しいビジネスモデルの登場は,航空輸送市場を活性化する一方で,市場構造がより複雑となった.現在のように,市場構造が複雑化した中では,「利用者(需要側)」行動だけではなく,サービスの供給側である「キャリア」側の行動,さらには空港管理者の行動も考慮されることが必要であろう.また効率的な運用のためにはそのガバナンスも検討する必要があろう.技術論的には需要予測の精緻化だけではなく,管理運営システムそのもののデザインについても検討されるべき事項が多々存在する.
本セミナーでは以上のような問題意識に基づき,航空輸送に関わる需要モデルや政策評価の最新の話題を紹介するとともに,航空輸送の現状とその問題点について研究者・実務者双方からの視点で検討する.
■プログラム
10:00 開会の挨拶 竹林幹雄(神戸大学)
10:05 研究小委員会の成果報告 竹林幹雄(神戸大学)
10:20-12:30 成果報告事例
1. 「ゲートウェイ空港の運営政策 -2面市場アプローチ-」
大西正光(京都大学)
2. 「日本とアジアのLCCの将来」
花岡伸也(東京工業大学)
3. 「国内線LCC参入による航空需要インパクト分析 – 関西~新千歳路線を対象に」
石倉智樹(首都大学東京)
4. 「サウスウエスト航空の戦略変化」
村上英樹(神戸大学)
13:40-14:20 特別講演
「わが国の航空交通政策について昨今考えること」
家田仁(東京大学・政策研究大学院大学)
14:20-16:00 パネルディスカッション テーマ「空港民営化の現状と課題」
登壇者 花岡伸也(東京工業大学),大西正光(京都大学)
河田敦弥(国土交通省航空局 空港経営改革推進室長)
阿部純哉(みずほ総合研究所 公共アドバイザリー部PPP事業推進室主任研究員)
モデレーター 竹林幹雄(神戸大学)
16:00 閉会の挨拶 花岡伸也(東京工業大学)
#71 自転車利用環境計画の進展と課題
Date
2015年1月10日
Venue
土木学会講堂
自転車利用環境計画の進展と課題
土木計画学ワンデーセミナー NO.71
自転車利用環境計画の進展と課題
日時:1月10日(土)10:00-16:45
場所: 土木学会講堂(東京都新宿区四谷一丁目 外濠公園内)
参加費:土木学会・自転車活用推進研究会会員 3000円 非会員 4000円 学生 1000円
テキスト(事例集CD)を含む(事例集のみの販売:2000円)
参加申込:こちらからお願いします。(自転車活用推進研究会会員の方は備考に会員である事を記入してください。)
主催:土木学会 土木計画学研究委員会 (自転車政策研究小委員会)
共催:自転車活用推進研究会
■開催趣旨
安全で快適な時点利用環境創出ガイドライン(国土交通省・警察庁,2012年11月),自転車利用環境整備のためのキーポイント(道路協会,2013年6月),この指針にしたがった自転車利用環境計画の策定が各自治体で進んでいます.本セミナーでは,これらの計画事例の紹介と,継続的整備に向けた課題を共有します。なお,土木学会計画学研究委員会の自転車政策研究小委員会において製作した多様な自転車通行空間の事例集(CD-ROM)の増補版をテキストとして配布します.
■プログラム案
午前の部 10:00-12:00
1 ガイドラインにおける自転車ネットワーク計画が目指すもの 30分
屋井 鉄雄(東京工業大学・教授)
2 自転車安全利用条例の策定状況 30分
元田 良孝(岩手県立大学・教授)
3 ガイドラインに示された交差点整備の効果計測事例について 30分
海老沢 綾一(警視庁交通部交通規制課)
4 自転車利用環境計画の課題と施策 ―海外との比較― 30分
古倉 宗治(三井住友トラスト基礎研究所・研究理事)
午後の部 13:00-16:30
5 自転車ネットワーク計画の策定状況 30分
小林 寛(国土技術政策総合研究所・主任研究官)
6 自転車利用計画の策定事例の特徴 20分×4+10分 進行総括 金 利昭(茨城大学・教授)
1)宮崎市のネットワーク計画の特徴 鈴木 美緒(東京工業大学・助教)
2)金沢市の計画づくりとその成果 三国 成子(地球の友・金沢)
3)堺市の自転車利用環境計画の特徴 吉田 長裕(大阪市立大学・准教授)
4)東京における取り組みとその課題 小林 成基(自転車活用推進研究会・事務局長)
休憩 20分
7 ミニパネルディスカッション「継続的整備に向けた課題と展望」 70分
進行 山中 英生(徳島大学・教授)
+ 上記発表者による討議
16:30-17:30 名刺交換会:会場にて開催します.
(飲み物+菓子付き 実費500円) 当日会場にて申し込みください.
#102 Professor D. Marc Kilgour講演会
Date
2014年11月17日
Venue
京都大学防災研究所大会議室(S-519D)
Professor D. Marc Kilgour講演会
The 9th International Seminar of Committee of Infrastructure Planning and Management, JSCE in FY2014
2014年度土木計画学研究委員会 第9回国際セミナー(通算 第102回国際セミナー)
Professor D. Marc Kilgour講演会
日時:2014年11月17日(月) 15:00-17:00
場所:京都大学防災研究所大会議室(S-519D)
参加費:無料
言語:英語
講演者:Professor D. Marc Kilgour (Department of Mathematics, Wilfrid Laurier University)
講演タイトル: Fair Division: Old and New.
講演概要:Often, group decision and negotiation can be broken down into two processes: ? ascertaining the relative preferences of the parties, and then ? using preference information to find an allocation making each party “reasonably” happy. This talk concentrates on the second problem: Assuming some information about preferences, can an allocation that meets certain fairness criteria be selected? If so, how? For example, an allocation is envy-free if each participant feels that his or her portion is at least tied for best ? and therefore does not envy anyone else. A prototype procedure for fair division between two persons is “I Cut, You Choose,” (ICYC), for splitting a divisible (continuous) good between two people. ICYC is assessed, and various improvements and extensions introduced. ICYC also lies at the heart of certain procedures for the allocation of indivisible items, particularly in situations with very limited information about preferences. One special case has been identified in which there is an elegant, easy-to-compute solution. Fair division procedures and principles are, in principle, fundamental! to procedural approaches to allocation and interest negotiation. Their relevance to problems in economics, computer science, operations research, management, and politics is discussed.
#101 Professor Tim McDaniels講演会
Date
2014年11月13日
Venue
京都大学防災研究所大会議室(S-519D)
Professor Tim McDaniels講演会
The 8th International Seminar of Committee of Infrastructure Planning and Management, JSCE in FY2014
2014年度土木計画学研究委員会 第8回国際セミナー(通算 第101回国際セミナー)
Professor Tim McDaniels講演会
日時:2014年11月13日(木) 15:30-17:00
場所:京都大学防災研究所大会議室(S-519D)
参加費:無料
言語:英語
講演者:Professor Tim McDaniels (University of British Columbia)
講演タイトル: Building risk communication among interdependent groups for self-organizing efforts to improve disaster resilience
講演概要:This presentation is concerned with the transition from risk communication to resilience communication, a term used by Professor Hayashi and colleagues. I discuss how self-organizing efforts among interdependent groups can serve as a basis for self-organizing efforts (a crucial aspect of building resilience in any complex system). I use two examples to show that the concepts are relevant at many levels of social organization. At one extreme, I discuss risk communication among the interdependent infrastructure systems in a region, based on a case study in Vancouver, BC. At another extreme, I discuss efforts in Japan by the Disaster Rescue Stockyard, in Nagoya, to build disaster resilience among neighbors in small rural or semi-urban areas of Japan. The results point to a new paradigm for risk communication, or more accurately, resilience communication, to enhance mutual efforts to work with peers to build resilience without the aid of governments, aside for organizational support.
第50回土木計画学研究発表会・秋大会
Date
2014年11月1日(土)~3日(月・祝)
Venue
鳥取大学
第50回土木計画学研究発表会・秋大会
会告について
▼ 第50回土木計画学研究発表会・秋大会 会告(以下の通り)
講演用論文
発表会の当日に充実した議論を行うということが、本発表会の特色です。このため、講演の申し込みに際して、「土木計画学への貢献」と「議論したい点」を明記していただきます。話題性、速報性のある論文や、調査・計画、技術検討等の事例報告も歓迎します。提出された講演用論文は、原則として無審査で掲載されますが、会場の制約等によってお断りすることもあります。
なお、ポスターセッションを今年度も実施いたします。口頭発表とポスターでの発表のどちらを希望するかを選んで申込んでいただきます(口頭発表およびポスターでの発表のいずれも、「土木学会論文集D3(土木計画学),Vol.71,No.5(土木計画学研究・論文集32巻)」への投稿対象となります)。
2015年発行予定の「土木学会論文集D3(土木計画学),Vol.71,No.5(土木計画学研究・論文集32巻)」及びそれ以降の巻への投稿には、投稿時点から過去2年以内の土木計画学研究・講演集に掲載され,かつ土木計画学研究発表会で発表されたものである必要がありますので、あらかじめご了承ください。
問合先
土木計画学研究委員会・学術小委員会 E-mail:keikaku50@jsce.or.jp
以下の該当する部分を熟読のうえ、手続きを取っていただけますようお願いいたします。
講演の申込み
(1) 申込みの手続きおよび注意点
2014年7月4日(金)~8月1日(金)17時までの期間内(予定)に、 土木計画学委員会ホームページを使って、講演申込と講演原稿の投稿を同時に行ってください。原稿のファイル形式はPDF形式のみ受付けます。 原稿は「講演原稿執筆要領」に従ってご執筆ください。今回より、論文投稿の締切日以降の原稿の確認期間を設けないこととなりました。締切日当日までは、投稿した原稿の確認、差し替えが可能ですが、締切日以降は、原稿の差し替えは受け付けられません。十分、ご注意ください。投稿時に、必ず申込内容が正しいか、PDFの取り違えての投稿がないか、申込内容とPDFのタイトル等の差異がないかなど確認ください。申込み期間の締切り間際に投稿が集中しますと、予期せぬ事態によりサーバーがダウンし受付ができなくなる恐れがあります。締切り間際の投稿は極力避けていただくようお願いいたします。
なお、原稿の提出がないもの、講演原稿執筆要領に準じていないもの、および期限後に投稿されたものは受理できません。必ず最終原稿を期間内にWEB上にて投稿してください。 間違えたファイルを提出した場合や申込内容とPDFの内容が違う場合であっても、そのまま掲載されますので、ご注意ください。
(2) 発表希望分野
申し込みに際して、発表希望分野を下記の5つの発表分野から希望順に2つ選んでください。また、キーワードにつきましては、同キーワード欄の中から最大4つ選んでください。なお、適当なキーワードが見つからない場合は、投稿者の判断によるキーワードを1つだけ加えてください。
発表希望分野
| 発表希望分野 | キーワード |
| A 計画論・計画情報 | 計画基礎論、計画手法論、システム分析、調査論、公共事業評価法、財源・制度論、プロジェクト構想、施工計画・管理、維持管理計画、意識調査分析、計画情報、情報処理、市民参加、GIS、リモートセンシング、測量、環境計画、防災計画、河川・水資源計画、ライフライン計画・設計、地球環境問題 |
| B 地域・都市・景観 | 国土計画、地域計画、都市計画、地区計画、住宅立地、産業立地、人口分布、地価分析、土地利用、市街地整備、再開発、景観、公園・緑地、観光・余暇、空間設計、イメージ分析、土木史 |
| C 交通現象分析 | 発生交通、目的地選択、交通手段選択、経路選択、出発時刻選択、活動分析、時間利用、交通行動調査、交通意識分析、交通行動分析、自動車保有・利用、駐車需要、交通ネットワーク分析、土地利用・交通・環境統合モデル、観光・余暇行動 |
| D 交通基盤計画 | 総合交通計画、地区交通計画、公共交通計画、歩行者・自転車交通計画、道路計画、鉄道計画、空港・港湾計画、ターミナル計画、駐車場計画、物流計画 |
| E 交通運用管理 | 交通流、交通容量、サービス水準、交通制御、交通管理、交通安全、交通情報、交通環境、公共交通運用、交通弱者対策、水上交通、空港管理、交通量計測、TDM、ITS、モビリティマネジメント(MM) |
(3) 発表形式
口頭発表とポスターでの発表のどちらを希望するかを選んでいただきます。なお、会場の都合でご希望に添えない場合もありますので予めご了承下さい。
(4) 投稿料
講演1本につき投稿料(参加費含む)として一般12,000円、学生9,000円を請求いたします。2本以上投稿する方については、2本目以降の投稿料は一般・学生ともに6,000円を請求いたします。振込手数料は各自でご負担願います。
講演原稿執筆要領
講演原稿の書式・形式は、土木学会論文集のものに準じています。下記の作成例やサンプルファイルをご利用ください。講演原稿では、英文アブストラクトの記入は任意です。その他書式・形式についての詳細は土木学会論文集の原稿作成の手引き等をご参照ください。なお、「土木学会論文集D3(土木計画学), Vol.75-6」への投稿の際には英文アブストラクトは必要です。
サンプルファイル 和文(Word2000)/English(Word2000)
原稿作成例 和文(PDF)/English(PDF)
お問合せ先
土木計画学研究委員会大会運営小委員会(春大会担当:橋本,氏原,林)
E-mail:keikaku59@jsce.or.jp
→事前参加申込注意事項(必ずお読みください)
#100 第2回国際研究BinNセミナー(BinN International Research Seminar #2)
Date
2014年9月27日
Venue
Room. 15 at Faculty of Engineering Bldg. 1, The University of Tokyo(Hongo Campus)
第2回国際研究BinNセミナー(BinN International Research Seminar #2)
The 7th International Seminar of Committee of Infrastructure Planning and Management, JSCE in FY2014
2014年度土木計画学研究委員会 第7回国際セミナー(通算 第100回国際セミナー)
第2回国際研究BinNセミナー(BinN International Research Seminar #2)
“Advanced activity model for capturing dynamic changes”
Host:
Grant-in-Aid for Scientific Research S (Principle Investigator: Masao Kuwahara)
“Dynamic risk management of transportation networks using mobile system monitoring”
Group 3 Dynamic network management (Seminar planning: Junji Urata)
Co-host: Committee of Infrastructure Planning and Management
The 2nd International BinN Research Seminar “Advanced activity model for capturing dynamic changes” will be held on September 27th and 28th. We invite Prof. Shlomo Bekhor, who belongs to Israel Institute of Technology and studies on transportation planning, network optimization and behavioral models. Prof. Bekhor will lecture about an advanced behavior modelling and an activity-based model on Sept 27. Three young researchers will talk about their recently studies about behaviors with observations, built environments and interactions on Sept 28 and discuss with Prof. Bekhor and audiences.
Summary:
In this decade, activity-based models based on a series of choices have become progressively popular. Activity-based models are able to illustrate and evaluate personal activities and their traffic environments. The models have been implemented for various policy applications. For the highly precise application, activity-based models integrate with accurate observations and predictions of traffic states under dynamic situation. We try to develop an advanced activity model based on previous researches. In this seminar, we want to discuss about the direction of advanced activity theory.
Program:
Date:
Keynote Lecture – Saturday, September 27, 2014, 10:30am – noon
Early Bird Session – Sunday, September 28, 2014, 0:30pm – 2pm
Venue: Room. 15 at Faculty of Engineering Bldg. 1, The University of Tokyo(Hongo Campus)
http://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/cam01_04_02_j.html
Sept 27, 10:30 am – noon
Keynote Lecture: Shlomo Bekhor (Israel Institute of Technology)
“Stability analysis of activity-based models: case study of the Tel Aviv transportation model”
Sept 28, 0:30 pm – 2 pm
Early Bird Session
1. “Transportation system monitoring method by using probe vehicles that observe other vehicles”
Toru Seo (Tokyo Institute of Technology)
2. “The built environment-travel behavior connection: A propensity score approach under a continuous treatment regime”
Giancarlos TRONCOSO (The University of Tokyo)
3. “Modelling the contraction of local interaction using dynamic programming under a heavy rain disaster”
Junji Urata (The University of Tokyo)
Application:urata[at]bin.t.u-tokyo.ac.jp (mail to Junji URATA)
Free to attend
The symposium is open to public.
Those who wish to attend are asked to submit to me (urata[at]bin.t.u-tokyo.ac.jp)
URL: http://bin.t.u-tokyo.ac.jp/I-BinN-S/index.html
* this site has the report of the last seminar.
#99 持続可能な都市開発のモデル分析に関するシンポジウム
Date
2014年9月19日
Venue
日本大学理工学部駿河台キャンパス1号館121会議室
持続可能な都市開発のモデル分析に関するシンポジウム
The 6th International Seminar of Committee of Infrastructure Planning and Management, JSCE in FY2014
2014年度土木計画学研究委員会 第6回国際セミナー(通算 第99回国際セミナー)
持続可能な都市開発のモデル分析に関するシンポジウム
ウイーン工科大学・交通研究所・交通計画・交通工学研究センターのG?nter Emberger教授を迎えして、持続可能な都市開発のモデル分析に関するシンポジュウムを開催します。シンポジュウムでは、先生を中心に開発されたMARS(Metropolitan Activity Relocation Simulator)注)を紹介して頂くとともに、日本とタイの研究者から持続可能な都市開発あるいは低炭素都市開発に関連するアクセシビリティーの研究やシステム・ダイナミックスを用いた分析の動向を紹介して頂き、持続可能な都市開発の分析の方向性に関して討議を行います。
日時:9月19日(金) 13:00~17:30
場所:日本大学理工学部駿河台キャンパス1号館121会議室
言語:英語
主催:日本大学大学院理工学研究科交通研究センター、日本環境共生学会、システム・ダイナミックス学会日本支部
共催:EASTS-Japan(2014年度第2回EASTS-Japan共催セミナー)、土木計画学国際小委員会(土木計画学国際セミナー)
申込(連絡先):9月17日(水)までに氏名、所属をご連絡ください。
日本大学理工学部交通システム工学科 石坂哲宏 office@j-s-d.jp
プログラム
13:00-13:05 開会の挨拶 日本大学理工学部教授・システム・ダイナミックス学会日本支部事務局長 福田 敦
13:05-14:35 特別講演「Outline of Metropolitan Activity Relocation Simulator and its application」
ウイーン工科大学交通研究所教授 G?nter Emberger
14:35-16:45 休憩
14:45-15:10 講演「マイクロシミュレーションモデルを用いた世帯立地のダイナミックスと都市政策評価」
名城大学理工学部准教授 鈴木 温
15:10-15:35 講演「人口減少下にある都市の持続可能性に関する実証分析:札幌・帯広都市圏のケース」
室蘭工業大学 大学院工学研究科准教授 有村 幹治
15:35-16:00 講演 Change of Land Use in Bangkok due to Accessibility Improvement」
カセサート大学工学部准教授 Varameth Vichiensan
16:00-16:20 講演「我が国の都市分析におけるシステムダイナミックスモデルの系譜」
日本大学理工学部助教 石坂 哲宏
16:20-16:30 休憩
16:30-17:20 パネルディスカッション
【コーディネーター】
名古屋大学工学部教授・日本環境共生学会会長 林 良嗣
【パネラー】
ウイーン工科大学交通研究所教授 G?nter Emberger
カセサート大学工学部准教授 Varameth Vichiensan
名城大学理工学部准教授 鈴木 温
室蘭工業大学 大学院工学研究科准教授 有村 幹治
17:20-17:30 閉会の挨拶
専修大学商学部教授・システム・ダイナミックス学会日本支部会長 内野 明
注)システム・ダイナミックスを用いて開発された動学的土地利用・交通モデル、ヨーロッパをはじめとする多くの都市において土地利用計画・交通計画の戦略的分析に適用されている。これまで以下の都市で適用された;イギリスのエジンバラ、リーズ、ゲーツヘッド、オーストリアのウイーン、ザルツブルグ、アイゼンシュタット、ノルウェーのオスロ、トロンハイム、フィンランドのヘルシンキ、スウェーデンのストックホルム、スペインのマドリード、ブラジルのポートアレグロ、米国のワシントンDCベトナムのホーチミン、タイのウボンラチャタニ、チェンマイ。
#97 Analysis of Firm Location and Relocation around Maryland andWashington, DC Metro Rail Stations
Date
2014年7月19日
Venue
東京大学本郷キャンパス・工学部11号館3階国際プロジェクト研究室会議室
Analysis of Firm Location and Relocation around Maryland andWashington, DC Metro Rail Stations
The 4th International Seminar of Committee of Infrastructure Planning and Management, JSCE in FY2014
2014年度土木計画学研究委員会 第4回国際セミナー(通算 第97回国際セミナー)
Title: Analysis of Firm Location and Relocation around Maryland andWashington, DC Metro Rail Stations
題目:メリーランド州およびワシントンDCの地下鉄駅周辺における企業立地・立地変更に関する分析
Abstract
Transportation investments can have substantial impacts on the location of social and economic activities by changing the overall level of accessibility. Changes in the amount and location of activities lead to different levels of economic development among locations. Particularly, transit oriented development (TOD) has been touted as a catalyst to stimulate local economic development and increase property values, as well as integrating transportation and land use, promoting mixed land uses, and making transit and pedestrian travel more viable. While a few studies have found that rail transit proximity and TOD are associated with a higher concentration of firms and employment in particular industries, such as finance, insurance, and real estate (FIRE) industries, and these claims need more evidence based on solid empirical research.
We have been working to examine the impacts of rail station investments on the geographic distribution of firms in selected industries with a strong presence in the region, including FIRE industries. We are currently working on a descriptive analysis part that seeks to address three key questions about the effects of station proximity: 1) What is the overall distribution of firms in relation to metro station locations? 2) What industries, if any, are more likely to locate near transit stations? 3) Whether Metro station openings have a substantial effect on the distribution of firms across the region? 4) Does a new transit station result in a net gain of firms within the station proximity and for the region or does it merely redistribute existing firms?
We apply GISs, statistics, and economic development analysis method to examine the National Establishment Time Series (NETS) dataset within the Washington DC region (comprising Washington, DC, Montgomery and Prince George’s Counties in Maryland and covering the 66 stations of Washington Metropolitan Area Transit Authority (WMATA) Metro service). The NETS dataset contains longitudinal and cross-sectional firm-level data for the years 1990 – 2010, which allow us to look at changes in number of firms within relatively small geographic areas around Metro stations, several of which were constructed during the 21 year period. The NETS dataset also provides firm-level relocation information for the same time period to assess firm movement within and outside of the study area as they relate to transit stations. (Please note that this study is working in progress, and I will present results that we have obtained so far.)
講演者:Dr Hiroyuki Iseki, Assistant Professor, School of Architecture, Planning & Preservation, University of Maryland, College Park(メリーランド 大学カレッジパーク校講師)
日時:2014年6月19日(木)18:30-20:00
場所:東京大学本郷キャンパス・工学部11号館3階国際プロジェクト研究室会議室
(工学部11号館へのアクセスは,http://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/cam01_04_12_j.htmlをご覧ください.)
言語:英語
参加手続き:無料です.事前に以下の連絡先まで,連絡をお願いします.ただし,当日の突然参加も大歓迎です.
連絡・問い合わせ先:加藤浩徳(kato@civil.t.u-tokyo.ac.jp)
#98 第一回国際研究BinNセミナー(BinN International Research Seminar #1)
Date
2014年7月12日
Venue
東京大学工学部14号館 144番教室
第一回国際研究BinNセミナー(BinN International Research Seminar #1)
The 5th International Seminar of Committee of Infrastructure Planning and Management, JSCE in FY2014
2014年度土木計画学研究委員会 第5回国際セミナー(通算 第98回国際セミナー)
第一回国際研究BinNセミナー(BinN International Research Seminar #1) “Dynamic Travel Behavior Modelling for Evacuation”
主催:
科研基盤S:移動体観測に基づく交通ネットワークの動的リスクマネジメント(代表:桑原雅夫)
グループ3 動的ネットワーク運用方策の構築(セミナー企画:浦田淳司)
日時:2014年7月12日 (土) 13時30分~17時
場所:東大本郷キャンパス工学部14号館 144番教室
概要:東日本大震災の甚大な被害への対策,また将来の東海・東南海地震に備え て,日本では各地で避難研究・避難対策を行われている.同時に,海外でもスマ トラ沖地震やハリケーンカトリーナ以降,避難研究・対策が注目を集めている. また,今後の防災計画にむけ,住民の避難行動の解明や情報技術を用いた避難交 通マネジメント,人/情報/交通の減災ネットワークデザインが必要とされる. 今回,TU Delftで避難行動研究の若手研究者であるDr. Pelをお招きして,避難 行動モデリングの現在とこれからについて議論したい.限られた時間の中で突発的 な判断・行動が必要な状況下での最善の避難には,動的な予測と制御が必要とな る.そのためには,これまで蓄積された日常の交通行動研究を下敷きにした非日 常の交通行動研究が求められる.本セミナーでは,今後の避難行動研究の理論の 方向性について深堀した議論を展開したい.
https://sites.google.com/site/dynamicriskmanagement/home/activity
Program:
Date: Saturday, July 12, 2014, 1:30pm – 5:00pm
Venue: Room. 144 at Faculty of Engineering Bldg. 14, The University of Tokyo(Hongo Campus) http://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/cam01_04_15_j.html
1:30pm – 3:00pm
“Route choice Behavior and Optimal traffic management in Evacuation”
Key Note Lecture:Adam Pel (TU Delft)
– A review of dynamic route choice model in evacuation
– Route choice model including information and compliance
– Optimal traffic management in evacuation
3:15pm – 4:00pm
Research Presentation 1 “Directions of evacuation traffic (Tentative)” Takamasa IRYO (Kobe University)
4:05pm – 4:50pm
Research Presentation 2 “A Dynamic Discrete Choice Model of Collective Behaviors incorporated in Spatial Reference Group under Disaster Situation” Junji URATA (The University of Tokyo)
4:50pm – 5:00pm
Closing
Application:urata[at]bin.t.u-tokyo.ac.jp (mail to Junji URATA) Free to attend The symposium is open to public. Those who wish to attend are asked to submit to me (urata[at]bin.t.u-tokyo.ac.jp)
#96 High Speed Railway in the Asia and Urban Development around Station Areas
Date
2014年7月4日
Venue
政策研究大学院大学 1階 想海樓ホール(東京都港区六本木7-22-1)
High Speed Railway in the Asia and Urban Development around Station Areas
High Speed Railway in the Asia and Urban Development around Station Areas ―International Comparison Study―
国際シンポジウム「アジアにおける新幹線と駅周辺の都市開発 -国際比較分析-」
主催 政策研究大学院大学
共催 アジア交通学会 EASTS (Eastern Asia Society for Transportation Studies)
後援 一般財団法人 運輸政策研究機構
日時 2014年7月4日 13:30-17:00
場所 政策研究大学院大学 1階 想海樓ホール(東京都港区六本木7-22-1)
————————————–
プログラムなどの詳細は http://www.easts.info/announce20140606.html をご参照ください.
参加無料です.
参加申し込みは,上記のプログラムなどの詳細ページの中にある[Application form] をダウンロードして,ご記入いただき指定のアドレスにお送りください.
#95 1st International Workshop on Utilizing Transit Smart Card Data for Service Planning
Date
2014年7月2日
Venue
長良川国際会議場 国際会議室
1st International Workshop on Utilizing Transit Smart Card Data for Service Planning
会議名:1st International Workshop on Utilizing Transit Smart Card Data for Service Planning
日時:2014年7月2,3日
場所:長良川国際会議場 国際会議室
参加者数(予定):40名程度(うち海外からの出席者15名程度)
参加費:5,000円(資料代含む.当日現金にて徴収いたします.)
主催:「第1回サービス設計のための公共交通スマートカードデータの活用に関する国際ワークショップ」実行委員会
共催:岐阜大学工学部社会基盤工学科
※実行委員会メンバー
倉内文孝(岐阜大学教授) 実行委員長
Schmoecker, Jan-Dirk(京都大学工学研究科准教授)
嶋本寛(宮崎大学准教授)
宇野伸宏(京都大学経営管理研究院准教授)
中村俊之(京都大学工学研究科助教)
山崎浩気(京都大学工学研究科助教)
第49回土木計画学研究発表会・春大会
Date
2014年6月7日(土)・8日(日)
Venue
東北工業大学
第49回土木計画学研究発表会・春大会
土木計画学研究委員会は下記の概要で第49回土木計画学研究発表会(春大会)を開催いたします.
発表プログラム(概略版)
発表プログラム(詳細版:1日目)
発表プログラム(詳細版:2日目)
<発表プログラムの注意事項>
・今後,若干の修正が入る可能性があります.
・並行するセッションにおいて発表者およびオーガナイザーが重複しないように作成されています.ただし,連名者については並
行セッションでの重複が生じる場合がありますが,ご了承ください.
※企画論文セッション「ITS(高度道路交通システム)」は,電子情報通信学会ITS研究会との併催となっております.これらのセッション会場に隣接する会場にて,電子情報通信学会ITS研究会も同時開催されており,参加費は無料とのことです.ご興味のある方は,こちらへのご参加もご検討ください.研究会情報は,以下のリンクからご覧いただけます. http://www.ieice.org/~its/
参加登録(発表者以外の方):以下の土木学会行事参加申し込みホームページより,ご登録ください.
( http://www.jsce.or.jp/event/active/information.asp)
聴講参加者の受付締切は5月28日(水),参加費は一般6,000円,学生3,000円です.
なお,発表者(企画部門,公共政策デザインコンペ部門(5名以内))は自動的に登録されていますので,あらためての参加登録は不要です.
以下の参加申込書をダウンロードし,必要事項を記入して土木学会宛にお送りいただく(FAX,郵送)ことでも,参加登録は可能です.締切および参加費はホームページからの申し込みの場合と同じです.
参加申込書(PDF / MS-Word)
申込書送付先:
※土木学会研究事業課(担当:林 淳二)
〒160-0004 東京都新宿区四谷1丁目(外濠公園内)
TEL:03-3355-3559 / FAX:03-5379-0125
E-mail j-hayashi@jsce.or.jp
・事前参加申し込みの締め切りは5月28日(水)となっております.事前申し込みをされた方には,5月末までに,「参加券」,
「請求書」等をお送りする予定です.
・本行事の参加費支払いは事前入金制となっておりますので,申込みフォームの「当日払い」,「現金持参」は選択しないでくだ
さい.
・締切日以降の事前受付はいたしません.締切日を過ぎてからのお申し込みは,行事当日に会場にて受付いたします.
・お申し込み後,やむを得ずキャンセルされる場合は,必ず開催日の1週間前までに研究事業課宛にご連絡ください.ご連絡がな
い場合は,参加費を徴収させて頂きますので予めご了承ください.
★聴講者用にレジュメ50部をご用意の上,各セッション会場にて配布して下さい.
(1)講演時間
セッションの時間は,すべて90分です.
発表時間等は基本的にオーガナイザーの指示に従ってください.
(2)講演打ち合わせ
セッション開始10分前に各発表会場に集合し,オーガナイザー・司会者および会場担当者とセッションの進め方に関する打ち合わせを行って下さい.
(3)発表時の使用機器について
各発表会場には,液晶プロジェクタとディスプレイケープルを準備します(OHP,スライドは使用できません).なお,ノートPCは各自で持参して下さい. 各発表会場に設置されている液晶プロジェクタヘの接続は,各発表者の責任にて行って下さい.セッションが円滑に進行するようにご準備のご協力をお願い致します.
(4)ポスターセッション
プログラム(概略版や詳細版)のセッション名の横に(P)が入っているセッションは,オーガナイザーにより,ポスター発表形式でのセッションを指定されたセッションです.ポスターのみによる発表とするか,あるいはプロジェクターでの発表を併用するかなどは,各セッションのオーガナイザーにお問い合わせください.
ポスターセッションの際に利用されるパネル,貼り付け用文具等は,オーガナイザーの責任によりご準備ください.開催校からは提供されませんのでご注意ください.
企画論文部門へ期限までに投稿された論文のうち、土木学会論文集D3の投稿の手引に従った形式(ただし英文要旨は任意)で執筆され、 かつ2ページ以上の分量である論文については、土木計画学研究・講演集に掲載される論文として見なされ、 土木学会論文集D3(土木計画学)特集号(以下、特集号と表記する)への投稿資格が得られます. 論文タイトルと要旨のみで構成されており本文が記載されていないなど、定められた形式に従っていない原稿は, 春大会運営小委員会の判断により,土木計画学研究・概要集への掲載を行わない上, 土木計画学研究・概要集への掲載が条件になっている土木学会論文集D3(土木計画学)特集号への投稿資格は与えられません. 特集号への投稿資格を満たさない投稿論文であっても、企画論文部門セッションで発表することは可能です. SS部門へ投稿された論文については、特集号への投稿資格はありませんので、ご注意ください.
#1 土木計画学の過去,現在,未来:土木計画学50周年に向けて
Date
2014年6月7日
Venue
東北工業大学
土木計画学の過去,現在,未来:土木計画学50周年に向けて
「土木計画学の過去,現在,未来:土木計画学50周年に向けて」と題する特別セッションを,第49回 土木計画学研究発表会(2014年6月7-8日,東北工業大学)の初日午前に開催しました.土木学会将来ビジョンの作成に携わっておられる屋井鉄雄教授(東京工業大学)に基調講演をお願いしました.また,森川高行教授(名古屋大学),清水英範教授(東京大学),小林潔司教授(京都大学)の先生方には,交通・測量/空間情報・土木計画の観点から,これまでの研究成果や今後の展望について話題提供していただきました.当日は約200名が会場に集い,基調講演やパネルディスカッションの内容に興味深く耳を傾けました.セッションの内容はこのページからダウンロードできますので,興味のある方はご覧ください.
今回のセッションは設立50周年(2016年)に向けての一連の企画のキックオフに位置付けられます.今後の行事については,詳細が決まり次第,本WEBサイトやip-mlにて随時情報発信してまいります.
■特別セッションの講演資料(屋井教授,森川教授,清水教授,小林教授)はこちら
■特別セッションの議論内容はこちら
#94 International Seminar on Road Networks for Earthquake Resilient Societies (ROADERS)
Date
2014年4月2日
Venue
Rakuyu Kaikan, Kyoto University
International Seminar on Road Networks for Earthquake Resilient Societies (ROADERS)
The 1st International Seminar of Committee of Infrastructure Planning and Management, JSCE in FY2014
2014年度土木計画学研究委員会 第1回国際セミナー(通算 第94回国際セミナー)
Date: 10:15-16:40, April 2, 2014
Venue: Rakuyu Kaikan, Kyoto University, Yoshidanihonmatsu-cho, Sakyoku, Kyoto 606-8501, Japan
Registration fee: Free (E-mail to register is much appreciated – joel.teo@kiban.kuciv.kyoto-u.ac.jp)
Access (Please refer to poster for details):
http://www.kyoto-u.ac.jp/en/access/getting/getting_1.htm (English)
http://www.t.kyoto-u.ac.jp/ja/access/yoshida (Japanese)
Seminar Description:
Emergency functionality and rapid recovery of road networks after a worst-case earthquake that has triggered additional hazards such as post-quake fires, landslides, tsunamis and a series of large aftershocks are vital requirements for the sustainability of any modern society, which, in the light of recent events like the Tohoku earthquake and tsunami, has not been properly addressed. This seminar will discuss the potential of post-disaster transportation needs for evacuation and humanitarian logistics operations after an extreme event and how these may lead to the identification of the most critical components and the definition of their required performance beyond their design limit (robustness). Since the assets could be mainly bridges, due to their generally large operational loss potential, the seminar will includes topics on innovative structural concepts that may be capable of providing the required robustness and speedy recovery within acceptable economic and time co! nstraints. The resilience based optimization methods for transportation and humanitarian logistics analysis will offer a rational framework for decision-making and resource allocation in addition to structural enhancements.
Programme Outline
10.15am Registration
10.30am-10.40am Opening speech (Prof. Eiichi Taniguchi)
Welcome speech (Prof. Uwe E. Dorka)
10.40am-11.10am Humanitarian Logistics
Prof. Eiichi Taniguchi (Kyoto University)
11.10am-11.40am Robustness of bridges under multiple extreme events
Prof. Uwe E. Dorka (University of Kassel)
11.45am-2.00pm Lunch
2.00pm-2.30pm Research progress in road network seismic resilience for the North-Eastern Region of Romania
Prof. Gabriela M. Atanasiu, Assoc. Prof. Florin Leon (Technical University “Gheorghe Asachi” from Ia?i)
2.30pm-3.00pm Network resilience and Osaka case study of evacuation modelling
Assoc. Prof. Jan-Dirk Schm?cker, Asst. Prof. Hiroki Yamazaki (Kyoto University)
3.00pm-3.20pm Coffee Break
3.20pm-3.50pm Methods for improving the resilience of road networks
Assoc. Prof. Russell G. Thompson (University of Melbourne)
3.50pm-4.30pm Discussion
4.30pm-4.35pm Wrap-up (Prof. Eiichi Taniguchi)
4.40pm End of Workshop
#70 東日本大震災後の交通と輸送:仙台からの報告
Date
2014年3月28日
Venue
土木学会講堂
東日本大震災後の交通と輸送:仙台からの報告
土木計画学ワンデーセミナー NO.70
東日本大震災後の交通と輸送:仙台からの報告
日時:3月28日(金)10:30-17:00(予定)
場所: 土木学会講堂(東京都新宿区四谷一丁目 外濠公園内)
定員:120名
参加費:無料,事前申し込み不要
主催:土木学会土木計画学研究委員会リスク評価に基づく道路構造物・ネットワークの耐震設計に関する合同研究小委員会
東日本大震災ロジスティック調査団(東北大学,東北工業大学,熊本大学)
東日本大震災に関する東北支部学術合同調査委員会
後援:京都大学防災研究所
■開催趣旨
土木学会リスク評価に基づく道路構造物・ネットワークの耐震設計に関する合同研究小委員会(委員長 多々納裕一京都大学教授)では,平成21年 度から道路ネットワークの耐震性に関する計画立案の必要性,道路ネットワーク の耐 震性能を与件とした道路構造物の耐震設計法の確立などをテーマとして研 究活動を行ってまいりました.この活動中に発生した東日本大震災において道 路が果たした役割とその課題は,ネットワーク計画を考えるために踏まえるべ き重要な知見です.このたび,仙台を中心に行われた調査,研究活動の成 果を 共有し,今後のネットワーク計画の在り方を議論するためにワンディセミナー 「東日本大震 災後の交通と輸送:仙台からの報告」 (案)を企画いたしました. 年度末の大変お忙しい時期ですが,多くの方々のご参加をお待ちいたします.
■プログラム
10:30-10:40 開会の挨拶 奥村 誠
1.調査・研究報告(テーマ,報告者ともに予定)
10:40-12:10
災害時の交通モニタリングと避難インフラ評価 桑原 雅夫 (東北大学)
(現場からの報告)港湾の被災復旧状況 高田 直和 (国土交通省東北地方整備局)
緊急支援物資の輸送実態と課題 福本 潤也 (東北大学)
13:40-15:40
震災時のガソリン不足問題の実態 長江 剛志 (東北大学))
東日本大震災前後の交通行動の変化 菊池 輝 (東北工業大学)
災害時の商業物流について 石井耕治・江藤和昭 (オリエンタルコンサルタンツ)
東日本大震災の間接経済被害と復興事業の経済効果 稲村 肇 (東北工業大学)
15:40-15:50 (休憩)
2.総合質疑・討論
15:50-16:50
震災時の交通とロジスティックのマネジメント 報告者一同
16:50-17:00 閉会の挨拶
備考
荒天時,自然災害時には,行事を中止させていただくことがあります.中止の場合は,報告会当日 午前7時までに 東北大学 災害科学国際研究所 奥村研究室のホームページ上(http://www.strep.main.jp)に情報を掲載します.
#69 交通まちづくり -実践のこれまでとこれから-
Date
2014年3月8日
Venue
土木学会講堂
交通まちづくり -実践のこれまでとこれから-
土木計画学ワンデーセミナー NO.69
交通まちづくり -実践のこれまでとこれから-
主催: 土木学会 土木計画学研究委員会 「交通まちづくりの実践」研究小委員会
日時: 2014年3月8日(土)10:00-16:55
場所: 土木学会講堂(東京都新宿区四谷一丁目 外濠公園内)
(地図 http://www.jsce.or.jp/contact/map.shtml)
参加費: 無料
■開催趣旨
少子高齢化・人口減少が進みつつあるわが国では、従来のような混雑緩和などの問題解決型の交通計画より、 望ましい生活像を提案する価値創造型の交通計画、持続可能な都市、都心部の活性化、楽しく歩けるまちづくりといった時代に対応した目標に貢献する交通計画が求められています。 土木学会・土木計画学研究委員会の下に設置された「交通まちづくりの実践」研究小委員会(2010年11月~、代表:東京大学教授・原田昇)は、 前身の交通まちづくり研究小委員会(2007年11月~2010年11月、同)から数えて6年あまりの間、こうした新しい交通計画=交通まちづくりのための計画手法の開発や実践展開を目指し、 活動を続けてきました。本ワンデーセミナーは小委員会活動の1つのまとめとして開催するものです。国内7都市の交通まちづくり事例の報告から、 まちのビジョンを市民に提示し合意を形成する手法、計画立案や実践に生かすためのデータ取得・調査・分析手法、計画の立案や実現を支える制度のあり方について知見を共有し、 掘り下げた討議を行うことを目的としています。併せて、今後の交通まちづくりの方向性に関し、広範な議論を行う機会にしたいと考えています。
■プログラム
<はじめに>
10:00-10:20 「交通まちづくり原論」 原田昇(東大)
<交通まちづくりの実践を知る3つの視座>
10:20-10:40 「ビジョンの構築と合意形成」 高山純一(金沢大)
10:40-11:00 「調査と分析の体系」 栄徳洋平((株)福山コンサルタント),溝上章志(熊本大)
11:00-11:20 「計画の立案と実現のための制度」 谷口守(筑波大),高見淳史(東大)
11:20-11:30 質疑応答
<交通まちづくりの実践事例に学ぶ(1)>
12:30-12:55 「金沢:トップダウンとボトムアップの融合、そして条例化によるまちづくりの継続」 高山純一(金沢大)
12:55-13:20 「札幌:都心の活性化に資する交通計画の理論と実践」 原田昇(東大)
13:20-13:45 「広島:高齢化社会の交通まちづくりを支える調査・分析への挑戦 ~需要予測からモニタリングへ」
藤原章正(広島大)
13:45-14:10 「由布:交通社会実験から10年,湯布院の観光まちづくりに活かされたこと,活かされなかったこと」
米田誠司(愛媛大)
<交通まちづくりの実践事例に学ぶ(2)>
14:25-14:50 「宇都宮:LRT導入の経緯と今後の展開」 森本章倫(宇都宮大)
14:50-15:15 「松江:多様な主体を巻き込んだ支援組織の役割 ~松江市公共交通利用促進市民会議について」
飯野公央(島根大)
15:15-15:40 「京都:南太秦学区の小さな交通まちづくり」 土井勉(京大)
<総括討議>
15:55-16:55 「交通まちづくり・実践のこれまでとこれから」 司会:羽藤英二(東大)
■参加申込
準備の都合上、下記申込フォームの所定事項をご記入のうえ、申込先メールアドレスまでお申し込みください。
—– 申込フォーム ここから —–
お名前:
ご所属:
メールアドレス:
—– 申込フォーム ここまで —–
申込先: km1day@ut.t.u-tokyo.ac.jp
#93 Perspectives of Conflict and Risk Governance
Date
2014年3月8日
Venue
京都大学宇治キャンパス きはだホール
Perspectives of Conflict and Risk Governance
The 15th International Seminar of Committee of Infrastructure Planning and Management, JSCE in FY2013
2013年度土木計画学研究委員会 第15回国際セミナー(通算 第93回国際セミナー)
Keith W. Hipel 教授 来日記念シンポジウム
日時: 2014年3月8日(土) 13:00-18:00 (受付12:30-)
会場: 京都大学宇治キャンパス きはだホール
参加料: 無料, 使用言語:英語
講演者: Keith W. Hipel 教授・カナダ・ウォータールー大学
講演題目: コンフリクトとリスク・ガバナンス研究のパースペクティブ:Perspectives of Conflict and Risk Governance
講演要旨:
本講演では、社会や国が直面する大規模かつ複雑化した様々な問題に取り組み、実効性を持ち得る ガバナンスを目指すための、”Systems of Systems” のエンジニリングデザイン法による統合的・ 適応型設計アプローチを提唱する。”Systems of Systems” の枠組みを用いることによって、参加型 アプローチによりさまざまなステークホルダーの価値観を反映しつつ、持続可能性や公平性、 レジリエンスといった目標を多精することが可能となる。
招待講演:
小林潔司教授(京都大学経営管理大学院経営研究センター長)
講演題目: 想定外リスクと計画概念
福嶋雅夫教授(南山大学情報理工学部、京都大学名誉教授)
講演題目:マルチ・リーダー・フォロワー・ゲームの最近の結果
曽道智教授(東北大学大学院情報科学研究科)
講演題目:自国市場効果について
パネルディスカッション:
複雑世界におけるコンフリクトの解決とリスクコミュニケーション
-モデル化、特性評価とコミュニケーションへの挑戦-
岡田憲夫教授(関西学院大学・災害復興制度研究所長、京都大学名誉教授)
福山 敬教授(鳥取大学)
猪原健弘教授(東京工業大学)
榊原弘之准教授(山口大学)
松田曜子准教授(関西学院大学)
講演内容の詳細につきましては、以下のwebをご参照下さい。
http://www.dpri.kyoto-u.ac.jp/web_j/contents/event_text/20140308.pdf
————————————————————
懇親会
日時: 2013年3月8日(土)18:30-
場所: レストランきはだ
会費: 3,000円
お手数ですが、会場準備のため、懇親会にご出席いただく場合は、メールにて、3/3(月)までに社会防災研究部門 山下までお申込下さい。
連絡先: yamasita@imdr.dpri.kyoto-u.ac.jp 内線 4039
————————————————————
#68 超高齢社会を支える効率的かつ信頼性の高いロジスティクスシステム
Date
2014年3月7日
Venue
東京海洋大学越中島キャンパス 越中島会館二階セミナー室
超高齢社会を支える効率的かつ信頼性の高いロジスティクスシステム
土木計画学ワンデーセミナー NO.68
超高齢社会を支える効率的かつ信頼性の高いロジスティクスシステム
主催: 土木計画学研究委員会 超高齢社会を支える効率的かつ信頼性の高いロジスティクスシステムに関する研究小委員会
日時: 3月7日(金)10:00-15:00
場所:東京海洋大学越中島キャンパス 越中島会館二階セミナー室
(地図 http://www.kaiyodai.ac.jp/info/37/39.html)
費用:\2,000 (テキスト代として)
■プログラム
10:00 開会のあいさつ
京都大学 谷口 栄一
10:05 効率的かつ信頼性の高いロジスティクス
京都大学 谷口 栄一
10:35 中山間部における買い物を支えるロジスティクス
長岡技術科学大学 佐野 可寸志
11:05 エージェントベースモデルによる緊急支援物資の配分計画
東京工業大学 花岡 伸也
13:00 「支援物資のロジスティクスに関する調査研究」について
国土交通政策研究所 松永 康司,加藤 賢
13:30 脆弱化社会における大規模災害対応ロジスティクス
京都大学 小野 憲司
14:00 大規模災害対応のロジスティクスシステム~特積み業界総掛りのプル型緊急物資輸配送~
全国物流ネットワーク協会 松永 正大
15:00 在宅医療・介護における現状と課題
日立製作所 甲斐 隆嗣
15:30 まとめ
東京海洋大学 兵藤 哲朗
#91 The 9th TSU (Transport Studies Unit) Seminar
Date
2014年2月21日
Venue
Kuramae Hall, TokyoTech Front, Oookayama 2-12-1, Meguroku, Tokyo
The 9th TSU (Transport Studies Unit) Seminar
#92 Feasibility Study of BRT in Da Nang City, Vietnam
Date
2014年2月20日
Venue
Room 1458, 5nd Floor, Building No.14, Funabashi Campus, Nihon University
Feasibility Study of BRT in Da Nang City, Vietnam
The 14th International Seminar of Committee of Infrastructure Planning and Management, JSCE in FY2013 2013年度土木計画学研究委員会 第14回国際セミナー(通算 第92回国際セミナー) 講演者:Nguyen Van Truong (Lecturer, UTC:University of Transport and Communication) 講演テーマ:Feasibility Study of BRT in Da Nang City, Vietnam 日時:2014年2月20日(木)14:00~15:00 講演後、質疑を予定。 場所:日本大学理工学部船橋校舎14号館5階1458教室 http://www.cst.nihon-u.ac.jp/campus/access.html 言語:英語 申込:参加費無料で申込みは必要ございません。当日、直接会場にお越しください。
#90 Road Safety Analysis Model Development
Date
2014年1月8日
Venue
Room 144, 2F, Faculty of Engineering Building #14, The University of Tokyo
Road Safety Analysis Model Development
The 12th International Seminar of Committee of Infrastructure Planning and Management, JSCE in FY2013 2013年度土木計画学研究委員会 第12回国際セミナー(通算 第90回国際セミナー) Date & Time: January 8, 2014 (Wed), 15:00-16:15 Venue: Room 144, 2F, Faculty of Engineering Building #14, The University of Tokyo http://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/cam01_04_15_j.html http://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/map01_02_j.html Seminar Title: Road Safety Analysis Model Development Speaker: Dr. Joon-Ki Kim (Korea Research Institute for Human Settlements (KRIHS)) Abstract: 現在、韓国の道路政策は、道路の新設?拡張は止めて、道路の線形や施設を改良して、安全性を向上させて、効率的に運営することができる方向に進んでいる。道路の安全性向上事業を効果的に推進するためには道路の安全性を客観的かつ科学的に判断して事業を選定することと事業に伴う安全性の向上を評価することが必要である。本研究では、これらの道路の安全性の分析および評価のためのモデルを開発する目的がある。本研究の主な内容は、米国のHSM(Highway Safety Manual)を根幹として、韓国の実情に合わせて、道路の安全性を分析し、評価することができるモデルを開発することである。モデルを構築するために一般国道、総13,797 kmのうち2,879 km(20.1%)、 国の支援する地方道(日本の県道)3,879 kmのうち475km(12.2%)を対象にして、道路幾何構造、交通特性、安全施設、気象、環境などのデータを収集した。構築されたデータに基づいて、負の二項回帰分析モデル(NB:Negative binomial regression model)を構築して、これに基づいて、交通量や道路の区間延長を利用して、発生事故件数を予測する安全性能関数(SPF:Safety Performance Function)と道路幾何構造の特性等の変化に応じて、事故の発生頻度の変化を決定する事故修正係数(CMF:Crash Modification Factors)を開発した。 Language: English Contact: Nobuaki OHMORI Department of Urban Engineering The University of Tokyo TEL: +81-3-5841-6235 E-mail: nobuaki@ut.t.u-tokyo.ac.jp
#89 Wait Marketing and the City
Date
2013年11月25日
Venue
Room 144, 2F, Building #14, Faculty of Engineering, The University of Tokyo
Wait Marketing and the City
The11th International Seminar of Committee of Infrastructure Planning and Management, JSCE in FY2013
2013年度土木計画学研究委員会 第11回国際セミナー(通算 第89回国際セミナー)
Date & Time: November 25, 2013 (Mon), 14:00-15:30
Venue: Room 144, 2F, Faculty of Engineering Building #14, The University of Tokyo
http://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/cam01_04_15_j.html
http://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/map01_02_j.html
Seminar Title: Wait Marketing and the City
Speaker: Prof. Diana Derval (DervalResearch)
http://www.derval-research.com/en
Abstract:
– Urban transports: Waiting from A to B
– Tokyo: How to connect with 13 million city dwellers?
– WeChat or Angry Birds? Variations in perception of time
– Wait Marketing cases in Amsterdam, Paris, and Shanghai
Even when high-speed trains are punctual, city dwellers spend hours waiting in public transports. Applications like WeChat and games like Angry Birds help keep them entertained. How can brands, transportations, and cities, together, implement Wait Marketing strategies in order to better connect with and serve their urban audience? In this interactive session Prof. Diana Derval, researcher in physiology and sensory perception, founder of DervalResearch, and author of the books “Wait Marketing”, and “The Right Sensory Mix”- AMA-Berry best marketing book award- will explain how to make the most of our journey in the city.
Contact:
Nobuaki OHMORI
Department of Urban Engineering
The University of Tokyo
TEL: +81-3-5841-6235
E-mail: nobuaki@ut.t.u-tokyo.ac.jp
第48回土木計画学研究発表会・秋大会
Date
2013年11月2日(土)~4日(月)
Venue
大阪市立大学
第48回土木計画学研究発表会・秋大会
会告について
▼ 第48回土木計画学研究発表会・秋大会 会告(以下の通り)
講演用論文
発表会の当日に充実した議論を行うということが、本発表会の特色です。このため、講演の申し込みに際して、「土木計画学への貢献」と「議論したい点」を明記していただきます。話題性、速報性のある論文や、調査・計画、技術検討等の事例報告も歓迎します。提出された講演用論文は、原則として無審査で掲載されますが、会場の制約等によってお断りすることもあります。
なお、ポスターセッションを今年度も実施いたします。口頭発表とポスターでの発表のどちらを希望するかを選んで申込んでいただきます(口頭発表およびポスターでの発表のいずれも、「土木学会論文集D3(土木計画学),Vol.70,No.5(土木計画学研究・論文集31巻)」への投稿対象となります)。
2014年発行予定の「土木学会論文集D3(土木計画学),Vol.70,No.5(土木計画学研究・論文集31巻)」及びそれ以降の巻への投稿には、投稿時点で過去2年以内の土木計画学研究発表会での講演が必要となりますので、あらかじめご了承ください。
問合先
公益社団法人土木学会研究事業課 橋本 剛志 E-mail:hashimoto@jsce.or.jp
以下の該当する部分を熟読のうえ、手続きを取っていただけますようお願いいたします。
講演の申込み
(1) 申込みの手続きおよび注意点
2013年7月4日(木)~8月2日(金)17時までの期間内に、 土木計画学委員会ホームページを使って、講演申込と講演原稿の投稿を同時に行ってください。原稿のファイル形式はPDF形式のみ受付けます。 原稿は「講演原稿執筆要領」に従ってご執筆ください。 申込んだ論文が正しく転送されているかを確認するための期間を2013年8月5日(月)~8月7日(水)17時に設けています。講演申込み者自身で必ず確認してください。 申込み期間の締切り間際に投稿が集中しますと、予期せぬ事態によりサーバーがダウンし受付ができなくなる恐れがあります。締切り間際の投稿は極力避けていただくようお願いいたします。 なお、原稿の提出がないもの、講演原稿執筆要領に準じていないもの、および期限後に投稿されたものは受理できません。確認期間を過ぎての原稿の差し替え・修正および申し込みの取り下げには応じられません。必ず最終原稿を期間内にWEB上にて投稿してください。
投稿後、必ず申込内容が正しいか、PDFの取り違えての投稿がないか、申込内容とPDFのタイトル等の差異がないかなど確認ください。
間違えたファイルを提出した場合や申込内容とPDFの内容が違う場合であっても、そのまま掲載されますので、ご注意ください。
(2) 発表希望分野
申し込みに際して、発表希望分野を下記の5つの発表分野から希望順に2つ選んでください。また、キーワードにつきましては、同キーワード欄の中から最大4つ選んでください。なお、適当なキーワードが見つからない場合は、投稿者の判断によるキーワードを1つだけ加えてください。
発表希望分野
| 発表希望分野 | キーワード |
| A 計画論・計画情報 | 計画基礎論、計画手法論、システム分析、調査論、公共事業評価法、財源・制度論、プロジェクト構想、施工計画・管理、維持管理計画、意識調査分析、計画情報、情報処理、市民参加、GIS、リモートセンシング、測量、環境計画、防災計画、河川・水資源計画、ライフライン計画・設計、地球環境問題 |
| B 地域・都市・景観 | 国土計画、地域計画、都市計画、地区計画、住宅立地、産業立地、人口分布、地価分析、土地利用、市街地整備、再開発、景観、公園・緑地、観光・余暇、空間設計、イメージ分析、土木史 |
| C 交通現象分析 | 発生交通、目的地選択、交通手段選択、経路選択、出発時刻選択、活動分析、時間利用、交通行動調査、交通意識分析、交通行動分析、自動車保有・利用、駐車需要、交通ネットワーク分析、土地利用・交通・環境統合モデル、観光・余暇行動 |
| D 交通基盤計画 | 総合交通計画、地区交通計画、公共交通計画、歩行者・自転車交通計画、道路計画、鉄道計画、空港・港湾計画、ターミナル計画、駐車場計画、物流計画 |
| E 交通運用管理 | 交通流、交通容量、サービス水準、交通制御、交通管理、交通安全、交通情報、交通環境、公共交通運用、交通弱者対策、水上交通、空港管理、交通量計測、TDM、ITS、モビリティマネジメント(MM) |
(3) 発表形式
口頭発表とポスターでの発表のどちらを希望するかを選んでいただきます。なお、会場の都合でご希望に添えない場合もありますので予めご了承下さい。
(4) 投稿料
講演1本につき投稿料(参加費含む)として一般12,000円、学生9,000円を請求いたします。2本以上投稿する方については、2本目以降の投稿料は一般・学生ともに6,000円を請求いたします。振込手数料は各自でご負担願います。
講演原稿執筆要領
講演原稿の書式・形式は、土木学会論文集のものに準じています。下記の作成例やサンプルファイルをご利用ください。講演原稿では、英文アブストラクトの記入は任意です。その他書式・形式についての詳細は土木学会論文集の原稿作成の手引き等をご参照ください。なお、「土木学会論文集D3(土木計画学), Vol.75-6」への投稿の際には英文アブストラクトは必要です。
サンプルファイル 和文(Word2000)/English(Word2000)
原稿作成例 和文(PDF)/English(PDF)
お問合せ先
土木計画学研究委員会大会運営小委員会(春大会担当:橋本,氏原,林)
E-mail:keikaku59@jsce.or.jp
→事前参加申込注意事項(必ずお読みください)
※セッション詳細プログラムは含みません
※会場受付にて、白黒印刷の紙冊子として配布します。
※発表要領は含みません。別紙を参照して下さい。
※セッション会場の詳細配置図も含みません。
会場内の掲示を参照して下さい。
#88 国際セミナー「海外から見た日本の土木計画学,及び土木計画学研究・土木計画学研究の国際性・国際化の推進のために」
Date
2013年11月2日
Venue
Room 132, Building #1, Sugimoto Campus, Osaka City University
国際セミナー「海外から見た日本の土木計画学,及び土木計画学研究・土木計画学研究の国際性・国際化の推進のために」
The 10th International Seminar of Committee of Infrastructure Planning and Management, JSCE in FY2013
2013年度土木計画学研究委員会 第10回国際セミナー(通算 第88回国際セミナー)
[趣旨]
本セミナーは,教育・産業界だけでなく学術の視点でもグローバル人材育成や国際的に評価される研究促進が要請される中, 我が国固有の土木計画学研究が,海外の研究者にどのように評価されているのか,今後の土木計画学研究の国際性の向上と国際化の推進のための方策を議論することを目的としています.
[講演]
「海外から見た日本の土木計画学,及び土木計画学研究」
Prof. Lee (Kyonggi University, Korea)
Prof. Shengcuhan Zhao (Dalian University of Technology, China)
Dr. Varameth Vichiensan (Kasetsart University, Thailand)
[ミニシンポ]
「土木計画学研究の国際性・国際化の推進のために」
コーディネーター:
谷口栄一(土木計画学研究委員会委員長)
パネラー:
Prof. Lee (Kyonggi University, Korea)
Prof. Shengcuhan Zhao (Dalian University of Technology, China)
Dr. Varameth Vichiensan (Kasetsart University, Thailand)
福田敦(日本大学教授・土木学会国際委員長)
[日 時] 平成25年11月2日(土)13:00-15:00
[会 場]大阪市立大学 杉本キャンパス1号館132教室
[主 催] 土木学会土木計画学研究委員会 学術小委員会
#87 自転車利用環境向上国際セミナー「自転車利用環境向上のための施策 バーゼル市の取り組みから」
Date
2013年11月1日
Venue
大阪駅前第二ビル6F 大阪市立大学梅田サテライト101教室
自転車利用環境向上国際セミナー「自転車利用環境向上のための施策 バーゼル市の取り組みから」
The 9th International Seminar of Committee of Infrastructure Planning and Management, JSCE in FY2013
2013年度土木計画学研究委員会 第9回国際セミナー(通算 第87回国際セミナー)
[趣旨]
本セミナーでは、アンティエ ハンマー女史より自転車利用環境の向上を目指して取り組んでおられる スイスバーゼル市における自転車施策についてご講演を頂き、引き続き我が国の自転車施策のあり方についてパネルディスカッションを行います。
[講師]
アンティエ ハンマー女史は、ドイツのダルムシュタット工科大学とスイス連邦工科大学ローザンヌ校で都市交通計画を専門に土木工学を学び、卒業しました。 その後、交通計画の事務所や地方及び地域の行政機関、大学などの調査で、交通プランナーとして15 年以上活動しました。 2009 年からは、国際交通のプロジェクトやモビリティ・マネジメントを担当し、バーゼル市の公共事業や交通に関する部門に従事しています。http://velo-city2013.com/?page_id=5256
[日 時] 平成25年11月1日(金)15:00-17:30
[会 場] 大阪駅前第二ビル6F 大阪市立大学梅田サテライト101教室(定員75名)〒530-0001 大阪市北区梅田1-2-2-600
[主 催] 土木学会土木計画学研究委員会 自転車政策研究小委員会
[共 催] 地球の友・金沢、(特)自転車活用推進研究会
[協 力] 公益財団法人交通エコロジー・モビリティ財団
[参加費] 1000円(資料代として)
[申 込]
http://goo.gl/M5MYzq に入力してください.
[プログラム]
1.開会挨拶 山中英生 徳島大学
2.基調講演 Ms.Antje Hamme バーゼル市 「バーゼル市における自転車施策」
(通訳解説 三国千秋 北陸大学)
3.ミニパネル討議 自転車利用環境向上のための施策 ーソフトな試みに着目してー
Ms.Antje Hamme バーゼル市
三国千秋 北陸大学
三国成子 地球の友・金沢
金 利昭 茨城大学
元田良彦 岩手県立大学
小林成基 (特)自転車活用推進研究会
(進行 山中英生 徳島大学)
問い合わせ先]
自転車政策研究小委員会事務局 吉田(大阪市立大学)
yoshida@civil.eng.osaka-cu.ac.jp
#86 From Visioning to Implementation of Low-Carbon Transport in Asia
Date
2013年10月16日
Venue
CST Hall, Nihon University
From Visioning to Implementation of Low-Carbon Transport in Asia
The 8th International Seminar of the Committee of Infrastructure Planning and Management, JSCE in FY2013
2013年度土木計画学研究委員会 第8回国際セミナー(通算 第86回国際セミナー)
[Date]
1st Day: 2013 / 10 / 16(Wed) 10:00-17:30
2nd Day: 2013 / 10 / 17(Thu) 09:30-17:00
[Place]
1st Day: CST Hall, Nihon University (1-8-14 Kanda-Surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan)
2nd Day: U Thant International Conference Hall, United Nations University (5-53-70 Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo, Japan)
[Organizers]
※1 The Environment Research and Technology Development Fund (S-6-5) , the Ministry of the Environment, Japan (MOEJ)
※2 Graduate School of Environmental Studies ,Nagoya University
※3 Department of Transportation Systems Engineering, College of Science and Technology, Nihon University
[Co-Organizer]
National Institute for Environmental Studies, Japan (NIES)
Committee of Infrastructure Planning and Management, JSCE
[Language]
1st day: English Only
2nd day:Simultaneous Translation (English, Japanese)
[Registration fee]
Free
[Application]
Please email your name, affiliation, and dates of your attendance
E-mail : s65sympo@urban.env.nagoya-u.ac.jp
It is also possible to attend the symposium on the day.
[Contents]
In Asian developing countries, rapid economic growth will cause drastic emission growth, which will become significant part of future global emissions. This symposium is aimed at discussing how to design long-term measures to develop low-carbon transport systems in Asia in a leap-frog manner and in a backcasting way, decoupling economic growth with CO2 emission increase. For the discussion, we invite international experts on low-carbon development of urban transport and inter-regional transport. The symposium is sponsored by the “Low-Carbon Asia” research project, funded by Ministry of the Environment, Japan, as the Environment Research and Technology Development Fund (S6). We have sessions to discuss the outcome of the project on the transport part, “Low-Carbon Transport in Asia” (S6-5). On the 2nd day, we also have a collaborative symposium with our partners working on low-carbon development of various sectors in the “Low-Carbon Asia” project (S6).
[Program]
1st day
October 2013 (Wed) 10:00-17:30
CST-Hall, Nihon-University
10:00 – 10:20 Registration
10:20 ? 10:30 Welcome address
・Prof. Yoshitsugu Hayashi, Nagoya University, Japan
10:30-12:00 Session1-1:Visioning Low-Carbon Urban Transport Systems in Asia
・Prof. Wiroj Rujopakarn, Kasetart University, Thailand(Keynote Address)
・Prof. Yoshitsugu Hayashi, Nagoya University, Japan
・Dr. Kazuki Nakamura, Nagoya University, Japan
・Prof. Fumihiko Nakamura, Yokohama National University, Japan
13:00-15:30 Session1-2:Case Studies of Low-Carbon Urban Transport Development in Asia
・Prof. Atsushi Fukuda, Nihon University, Japan
・Dr. Varameth Vichiensan, Kasetsart University, Thailand
・Dr. Paramet Luathep, Prince of Songkla University, Thailand
・Dr. Thaned Satiennam, KhonKaen University, Thailand
・Dr. Nuwong Chollacoop, National Metal and Material Technology Centre, Thailand
・Dr. Sittha Jaensirisak, Ubon Ratchathani University, Thailand
15:50- 17:20 Session1-3:Low-Carbon Development of Inter-Regional Transport Systems in Asia
・Prof. Werner Rothengatter, Karlsruhe Institute of Technology, Germany(Keynote Address)
・Dr. Poon Thiengburanathum, Chiang-Mai University, Thailand
・Dr. Shinya Hanaoka, Tokyo Institute of Technology, Japan
・Prof. Takaaki Okuda, Nanzan University, Japan
17:20 ? 17:30 Closing Remarks
2nd day
October 2013 (Wed) 09:30-17:00
U Thant International Conference Hall, United Nations University
09:00 ? 09:30 Registration
09:30 ? 09:40 Welcome address
・Prof. Yoshitsugu Hayashi, Nagoya University, Japan
09:40 ? 12:00 Session2 : Comparison of Low-Carbon Transport Development between ASEAN and China
・Prof. Atsushi Fukuda, Nihon University, Japan
・Dr. Shinya Hanaoka, Tokyo Institute of Technology, Japan
・Prof. Pan Xiao, Tonji University, China
・Prof. Tae Oum, The University of British Colombia, Vancouver, Canada
・Mr. Cornie Huizenga, SLoCaT, Shanghai, China
・Panel Discussion (Chair : Prof. Yoshitsugu Hayashi, Nagoya University, Japan)
13:00 ? 17:00 Symposium on “Low-Carbon Asia” (S6)
※プログラムの内容等は、一部変更の可 能性があります。
【お問い合わせ先/Contact】
名古屋大学大学院 環境学研究科附属 交通・都市国際研究センター林・加藤研究室
E-mail: s65sympo@urban.env.nagoya-u.ac.jp
電話/Phone: +81-52-789-2773
【シンポジウムHP/Symposium HP】
http://www.sustrac.env.nagoya-u.ac.jp/s65sympo/
#85 International Seminar on Happiness and Urban/Transport Policies
Date
2013年10月9日
Venue
Room 144, 2F, Building #14, Faculty of Engineering, The University of Tokyo
International Seminar on Happiness and Urban/Transport Policies
The 7th International Seminar of the Committee of Infrastructure Planning and Management, JSCE in FY2013: International Seminar on Happiness and Urban/Transport Policies
2013年度土木計画学研究委員会 第7回国際セミナー(通算 第85回国際セミナー)「幸福度と都市・交通政策」
Time: 10:30 ~ 18:30, October 9, 2013
Venue: Room 144, 2F, Building #14, Faculty of Engineering, The University of Tokyo
Organizer: The Subcommittee of Citizen Life Behavior Studies, The Committee of Infrastructure Planning and Management, JSCE
[Program]
Morning session (in Japanese)
10:30~10:40 Activity Report of the Subcommittee
10:40~12:00 Reports of members’ research activities
10:40~11:10 Change of car-dependent lifestyles and its implications on policies
Toshiyuki Yamamoto, Nagoya University
11:10~11:40 Risk analysis in transport studies: Case of traffic accidents
Makoto Chikaraishi, The University of Tokyo
11:40~12:00 Discussion
12:00~13:30 Lunch
Afternoon session (in English)
13:30~13:40 Opening remarks, Junyi Zhang, Hiroshima University (Chair of the Subcommittee)
13:40~14:40 Session (1): Lifestyle, mobilities and happiness
13:40 ~14:10 Residential environment, travel behavior and life satisfaction
Yubing Xiong and Junyi Zhang, Hiroshima University
14:10~14:40 Households’ total mobilities over life course
Biying Yu, Kyoto University; Junyi Zhang, Hiroshima University
14:40~16:10 Session (2): Keynote speech
Happiness and Public Policy
Prof. Ruut Veenhoven, Emeritus Prof., Erasmus Univ. Rotterdam
Founding editor of the Journal of Happiness Studies
16:10~16:20 Break
16:20~18:30 Session (3): Happiness during travel
16:20~16:50 Troublesome behavior and the happiness during travel:
An international comparison
Nobuaki Ohmori, The University of Tokyo
16:50~17:20 Travel with children and the happiness during travel
Ayako Taniguchi, University of Tsukuba
17:20~17:50 Smile and pedestrian walking environment
Aya Kojima, Hisashi Kubota, Saitama University
17:50~18:30 Comments from Prof. Veenhoven, and discussion
18:30~ Closing remarks
申し込み,Contact:asmo@hiroshima-u.ac.jp
#84 "User-oriented measurement of travel time reliability: concepts and applications
Date
2013年9月12日
Venue
Midorigaoka 5th Building 1F Conference room, Tokyo Tech, Meguroku, Tokyo
"User-oriented measurement of travel time reliability: concepts and applications
The 6th International Seminar of Committee of Infrastructure Planning and Management, JSCE in FY2013
2013年度土木計画学研究委員会 第6回国際セミナー(通算 第84回国際セミナー)
Date: September 12, 2013 (Thursday), 17:00-18:00
Venue: Midorigaoka 5th Building 1F Conference room, Tokyo Tech, 東京工業大学創造プロジェクト館1F大会議室
http://www.plan.cv.titech.ac.jp/fukudalab/contact/
(東急大井町線緑が丘駅徒歩8分)
Seminar Title: User-oriented measurement of travel time reliability: concepts and applications
Speaker: Dr. Ioannis Kaparias
(Lecturer, City University of London)
http://www.city.ac.uk/engineering-maths/staff/dr-ioannis-kaparias
Abstract:
This study introduces a new user-oriented measure of travel time reliability for implementation in the dynamic routing algorithm of an intelligent car navigation system. The measure is based on the log-normal distribution of travel time on a link and consists of two indices corresponding to the extreme values of the distribution, such that they reflect the shortest and longest travel times that may be experienced on the link. Through a series of mathematical manipulations, the indices are expressed in terms of the characteristic values of the speed distribution on the link. An expression relating the indices of a route and the indices of the individual links forming it is derived. The accuracy of the measure is then assessed through a field experiment and the results are presented.
#4 都市再生と地下空間 -期待と展望-(2013年・年次学術講演会)
Date
2013年9月4日
Venue
日本大学生産工学部津田沼キャンパス 37号館605教室(会場名:V-4)
#4 都市再生と地下空間 -期待と展望-
平成25年度土木学会全国大会 研究討論会 <日本大学>
題目:都市再生と地下空間 -期待と展望-
(地下空間研究委員会・土木計画学研究委員会)
概要:高密度化する都市において、地下空間??残された貴重な空間て?あり、そ??活用??都市??再生においても重要な役割??果たしている。本討論会て???、各地??都市再生フ?ロシ?ェクトにおける地下街??事例を 紹介しつつ、地上空間と??連携、鉄道駅なと?インフラと??関係、快適な移動??ため??アメニティ??確保、災害時??避難行動なと?、多様な視点から地下空間へ??期待を述へ?ていたた?く。それらをもとに、今後?? 展望について総合的な議論を展開するも??のて?ある。
座 長:
渡邉 浩司 東日本旅客鉄道(株)ターミナル計画部担当部長
話題提供者:
岩倉 成志 芝浦工業大学工学部教授
粕谷 太郎 都市地下空間活用研究会主任研究員
羽藤 英二 東京大学大学院
和氣 典二 神奈川大学客員教授
日時: 9月4日(水) 16:15-18:15
場所: 日本大学生産工学部津田沼キャンパス
37号館605教室(会場名:V-4)
#83 A Behavioral Freight Transportation Modeling System
Date
2013年6月27日
Venue
Room C1-4-191 Katsura Campus, Kyoto University, Nishikyoku, Kyoto
A Behavioral Freight Transportation Modeling System
The 5th International Seminar of Committee of Infrastructure Planning and Management, JSCE in FY2013
2013年度土木計画学研究委員会 第5回国際セミナー(通算 第83回国際セミナー)
Date: June 27, 2013 (Thursday), 15:00-16:30
Venue: Room C1-4-191 Katsura Campus, Kyoto University, Nishikyoku, Kyoto 615-8540, Japan
Access:
http://www.t.kyoto-u.ac.jp/en/access/katsura (English)
http://www.t.kyoto-u.ac.jp/ja/access/katsura?set_language=ja (Japanese)
Seminar Title: A Behavioral Freight Transportation Modeling System
Speaker: Dr. Kazuya Kawamura
(Associate Professor, College of Urban Planning and Public Affairs, University of Illinois, Chicago)
http://www.uic.edu/cuppa/upp/faculty/kawamura.html
Seminar Description:
Compared against passenger travels, freight transportation is a relatively less-researched field in terms of advanced demand modeling.
The main challenges to build reliable freight demand models include lack of data, complexity of decision-making in freight system,
lack of proper validation process, etc. In the last decade, researchers around the world and the field have rapidly made advancements
in many fronts, including data collection, modeling frameworks and operational strategies. However, there are still significant gaps
in terms of our understanding of the fundamentals and the nature of freight movement systems and their behavioral decision making process.
The presentation outlines a new framework for freight transportation modeling by incorporating more detailed logistics choices into
an operational large-scale freight transportation modeling system that has been under development at the University of Illinois, Chicago.
Interested participants are encouraged to contact Dr. Joel Teo.
Contact:
Dr. Joel Teo (Program-specific Researcher)
C1-2-338 Kyoto University, Katsura,
Nishikyoku, Kyoto, Japan 615-8540
Tel. +81-75-383-3231, Fax. +81-75-950-3800
E-mail: joel.teo@kiban.kuciv.kyoto-u.ac.jp
#82 Special Seminar on International Maritime Shipping
Date
2013年6月21日
Venue
Seminar Room E&F, JSCE
Special Seminar on International Maritime Shipping
The 4th International Seminar of Committee of Infrastructure Planning and Management, JSCE in FY2013
2013年度土木計画学研究委員会 第4回国際セミナー(通算 第82回国際セミナー)
Special Seminar on International Maritime Shipping
Date & Time: June 21 (Fri.) 13:00-15:00
Venue: Seminar Room E & F, JSCE
土木学会E・F会議室(〒160-0004東京都新宿区四谷一丁目外濠公園内)
Abstract: Due to the globalization of the world economy and advancement of transport and communication technology,
international maritime shipping in each region of the world has become more interdependent. The Suez Canal and Panama Canal,
key infrastructures of maritime shipping, are also influenced by each other as well as by other factors such as world
economic trends and regional development plans. In particular, the capacity of the Panama Canal will be expanded through
construction of the third lock in 2015. Also, Arctic shipping via the Northern Sea Route (along the Russian Arctic coast)
has the potential to shorten the distance of worldwide maritime shipping, due to the melting of sea ice. This special
seminar will bring together specialists from Egypt and Japan who will provide the latest information on the current status
and future prospect of the Suez Canal, Panama Canal, and Northern Sea Route. Discussion after the presentations is also expected.
Program
1) 13:00-13:05 Greeting from Host
2) 13:05-13:40 Current Status and Future Prospect: (1) Suez Canal
Mr. Ahmed Mohammed Elmanakhly, Board Member & Transit Director, Suez Canal Authority
(スエズ運河の現状と展望:エジプト国スエズ運河庁運航部長エルマナクリ氏)
3) 13:40-14:10 Current Status and Future Prospect: (2) Panama Canal
Dr. Koji Kobune, Ides Inc.
(パナマ運河の現状と展望:Ides株式会社小舟浩治氏)
4) 14:10-14:40 Current Status and Future Prospect: (3) Northern Sea Route
Dr. Natsuhiko Otsuka, North Japan Port Consultants, Inc.
(北極海航路の現状と展望:北日本港湾コンサルタント株式会社大塚夏彦氏)
5) 14:40-15:00 Discussion
Language: English
Deadline for Application: June 17 (Mon.) (Seating Capacity: 25 people, first-come basis)
Host: Special committee for Managing and Supporting International Research Activities on Logistics, JSCE
土木学会 土木計画学研究委員会 物流に関わる国際戦略・研究活動支援事業運営小委員会
Contact:
Ryuichi SHIBASAKI, Dr. Eng.
The Overseas Coastal Area Development Institute of Japan (OCDI)
E-mail:shibasaki@ocdi.or.jp
tel: +81-3-5570-5931
(一財)国際臨海開発研究センター 柴崎隆一(運営小委員会幹事長)
#81 The 12th TSU (Transport Studies Unit) Seminar:Sharing of Research Works on Logistics Management
Date
2013年6月6日
Venue
Ookayama Campus, Ishikawadai-4 bldg., B1F, Room B02-05, Tokyo Institute of Technology, Japan
The 12th TSU (Transport Studies Unit) Seminar:Sharing of Research Works on Logistics Management
The 3rd International Seminar of Committee of Infrastructure Planning and Management, JSCE in FY2013
2013年度土木計画学研究委員会 第3回国際セミナー(通算 第81回国際セミナー)
The 12th TokyoTech TSU (Transport Studies Unit) Seminar
http://www.transport-titech.jp/
Date: June 6th. (Thu.) 2013
Time: 17:00-18:30
Venue: Tokyo Tech. Ookayama Campus, Ishikawadai-4 bldg., B1F, Room B02-05
(東工大・大岡山キャンパス 石川台4号館 地下1F B02-05室)
http://www.ide.titech.ac.jp/~hanaoka/access.jp.html
*Prior expression of interest to Assoc. Prof. Hanaoka by email would be appreciated.
email: hanaoka[at]ide.titech.ac.jp
Speaker: Prof. Tsung-Sheng Chang (張宗勝教授)
(Graduate Institute of Logistics Management, National Dong Hwa University (国立東華大学), Taiwan)
He is staying in Japan as a visiting professor of Hanaoka Lab.
He is also a specialist of OR (Operations Research).
http://faculty.ndhu.edu.tw/~ts/
Title: Sharing of Research Works on Logistics Management
Abstract:
Logistics has recently received much attention in both practical and academic fields. So far, many logistics issues have been raised and studied in academia. However, there should be many various and important real-world logistics problems that are not fully researched or that even remain unexplored. Therefore, this presentation seeks, through my sharing of some of the main logistics works in which I have or am currently engaging, to not only inspire researchers to participate in the research on logistics management, but also to help them bring forth new and interesting logistics research topics. The research works to be introduced include global logistics, distribution logistics, facility location, city logistics, hazmat logistics, natural disaster logistics, perishable products logistics, and so on.
第47回土木計画学研究発表会・春大会
Date
2013年6月1日(土)・2日(日)
Venue
広島工業大学(五日市キャンパス)
第47回土木計画学研究発表会・春大会
企画論文部門オーガナイザーおよびSSオーガナイザーの公募について(添付ファイル)
企画部門およびSSオーガナイザー申込はこちら(終了)
企画テーマ一覧
( http://www.jsce.or.jp/event/active/information.asp)
聴講参加者の受付開始は4月15日(月),締切は5月18日(金), 参加費は一般6,000円,学生3,000円です.
なお,発表者(企画部門,SS部門,公共政策デザインコンペ部門(5名以内)) はこちらで自動的に登録しますので,参加登録して頂く必要はございません.
スペシャルセッションの概要
発表プログラム(概略版)
発表プログラム(詳細版:1日目)
発表プログラム(詳細版:2日目)
<発表プログラムの注意事項>
・今後,若干の修正が入る可能性があります.
・並列セッションにおいて発表者が重複しないように組まれています.ただし,連名者については重複の場合があります.ご承知置きください.
★聴講者用にレジュメ50部をご用意の上,各セッション会場にて配布して下さい.
(1)講演時間
セッションの時間は,すべて90分です.
発表時間等は基本的にオーガナイザーの指示に従ってください.
(2)講演打ち合わせ
セッション開始10分前に各発表会場に集合し,オーガナイザー・司会者および会場担当者とセッションの進め方に関する打ち合わせを行って下さい.
(3)発表時の使用機器について
各発表会場には,液晶プロジェクタとディスプレイケープルを準備します(OHP,スライドは使用できません).なお,ノートPCは各自で持参して下さい. 各発表会場に設置されている液晶プロジェクタヘの接続は,各発表者の責任にて行って下さい.セッションが円滑に進行するようにご準備のご協力をお願い致します.
(4)ポスター併用セッション
プログラム(概略版や詳細版)のセッション名の横に(P)が入っているセッションは,ポスター併用を申し込み時に希望されたセッションです.実際に,ポスターを併用した発表を行うのか,あるいは,プロジェクターでの発表のみを行うのかなどは,各セッションのオーガナイザーにお問い合わせください.
・ 90cm×180cmのボード1枚に貼れる内容のポスターを発表会場にお持ちください.ボードは基本的に会場の床から壁に立てかけます.枚数やサイズは自由とします が数名が同時に見えるように文字の大きさ等を工夫してください.
・ ポスター掲示用のボード(3×6枚:90cm×180cm)は,各セッション会場にいる会場係が用意いたしますので,セッション開始の10分前までに会場係からお受け取りください.
・ 発表時間までにボードにポスターを貼り付けておいてください.貼り付けるための場所と文具は会場で用意いたします.
・ 発表会場では会場の壁を掲示スペースとして使いますので,そこにボードを立てかける方法で掲示してください.
・ セッションが終了しましたら,ボードをセッション会場係に返却ください.ポスターは処分してよろしければ,貼り付けたままで結構です.
#80 The 11th TSU (Transport Studies Unit) Seminar: Managing the Repositioning Problem in Bike-Sharing Systems
Date
2013年5月23日
Venue
Ookayama Campus, Midorigaoka Bldg. No. 5,Room1F, Meeting Room, Tokyo Institute of Technology, Japan
The 11th TSU (Transport Studies Unit) Seminar: Managing the Repositioning Problem in Bike-Sharing Systems
The 2nd International Seminar of Committee of Infrastructure Planning and Management, JSCE in FY2013
2013年度土木計画学研究委員会 第2回国際セミナー(通算 第80回国際セミナー)
The 11th TokyoTech TSU (Transport Studies Unit) Seminar
http://www.transport-titech.jp/
Date: May 23 (Thu.) 2013 16:00-17:30
Venue: Tokyo Institute of Technology, Ookayama Campus, Midorigaoka Bldg. No. 5, Room1F, Meeting Room
http://www.plan.cv.titech.ac.jp/fukudalab/contact/
(8 min walk from Midorigaoka station of Tokyu Ooimachi-line)
Sperker: Dr. Panagiotis Angeloudis氏
(Lecturer at Imperial College London,
Director of the Port Operations Research and Technology Centre)
http://www3.imperial.ac.uk/people/p.angeloudis
http://www3.imperial.ac.uk/portoperations
Title: Managing the Repositioning Problem in Bike-Sharing Systems
(自転車シェアシステムにおける再配置問題:ロンドンを例に)
概要:The presence of enough bicycles and free docking points to satisfy user demands in stations is a known operational issue in bicycle-sharing schemes. Empty and full stations in such systems are equally undesirable and disruptive for the operation of the network, since the former turn away potential users while the latter could not be used to terminate bicycle journeys. Repositioning practices have been used in the past to address this situation with partial success. This study introduces a new planning approach for such activities, addressing both routing and assignment aspects of bicycle repositioning using a fleet of carrier vehicles. A case study on bicycle usage patterns from a large bicycle-sharing scheme is carried out; examples are also provided that demonstrate the behaviour of the algorithm. Implementation concerns and means to improve computational performance are also discussed.
Note: Towards the end of the seminar (or privately), Dr. Panageotis could also talk about some of his ongoing work on infrastructure resilience.
#79 International Seminar on Resilient and Sustainable Road Freight Systems and Humanitarian Logistics
Date
2013年4月9日
Venue
Jin-Yu Hall, C1-2-311 Katsura Campus, Kyoto University, Nishikyoku, Kyoto 615-8540, Japan
International Seminar on Resilient and Sustainable Road Freight Systems and Humanitarian Logistics
The 1st International Seminar of Committee of Infrastructure Planning and Management, JSCE in FY2013
2013年度土木計画学研究委員会 第1回国際セミナー(通算 第79回国際セミナー)
Seminar Title: International Seminar on Resilient and Sustainable Road Freight Systems and Humanitarian Logistics
Date: 0900-1715, April 9, 2013
Venue: Jin-Yu Hall, C1-2-311 Katsura Campus, Kyoto University, Nishikyoku, Kyoto 615-8540, Japan
Access:
http://www.t.kyoto-u.ac.jp/en/access/katsura (English)
http://www.t.kyoto-u.ac.jp/ja/access/katsura?set_language=ja (Japanese)
Seminar Description:
The disparity of commercial logistics and humanitarian logistics has motivated researchers and practitioners to create leading edge solutions to handle their differences. However both the commercial and humanitarian logistics share the same effort to reach resiliency and sustainability. Commercial logistics involves the operations of storage and transporting of goods to conform to customers’ requirements while being economically efficient. In contrast, humanitarian logistics is viewed simply as a wide range of activities aimed at saving lives and eliminating the sufferings of victims in a disaster or catastrophe. In recent years, the issues related to humanitarian logistics are so complex that a multi-disciplinary approach and the sharing of information and field experiences are so important to overcome the challenges of future devastating events.
This seminar hopes to create a platform for all key stakeholders and professionals in the area of road freight systems and humanitarian logistics to share on the following subjects:
? Innovative strategies to build resilient and sustainable road and maritime freight systems
? Valuable experiences and lessons learnt from the distribution of relief goods in the aftermath of a disaster or catastrophe
? International collaborative effort in disaster response and recovery
? State of the art modeling techniques
Programme Outline
0900 Prof. Eiichi Taniguchi (Kyoto University) Welcome address
0905 Prof. Eiichi Taniguchi (Kyoto University) Humanitarian Logistics in Disasters
0945 Ms. Megumi Tsukizoe (Deputy Asst. Director, Global Env. Dept., Disaster Mgmt. Div. 2, JICA) JICA’s strategy for disaster risk management
1025 Break
1035 Dr. Russell G. Thompson (Senior Lecturer, Monash University) Increasing the Resilience of Road Freight Systems
1115 Dr. Panagiotis Angeloudis (Lecturer, Imperial College London) Resilience of Transport Infrastructure Against Flooding
1155 Lunch
1330 Mr Osamu Suzuki (President, MOL Ferry Co. Ltd.) Expected Activity of the Mega Ferry Boats When Extensive Disaster has Taken Place
1415 Prof. Kenji Ono (Kyoto University) The Possible Policy Development for Facilitating ER Operations by Ro-Ro Vessels
1500 Break
1510 Assoc. Prof. Jan-dirk Schm?cker (Kyoto University) Risk Adverse Route Planning: Which Worst Case to Consider?
1550 Mr Rubel Das (PhD. Candidate, Tokyo Institute of Technology) Agent Based Simulation Model for Humanitarian Logistics
1630 Dr. Joel Teo (Post-doc Researcher, Kyoto University) Prospects of Multi-agent Systems Models for Urban Freight and Humanitarian Logistics
1710 Dr. Russell G. Thompson (Senior Lecturer, Monash University) Closing Remarks
Contact:
Dr. Joel Teo
C1-2-338 Kyoto University, Katsura, Nishikyoku, Kyoto, Japan 615-8540 Tel. +81-75-383-3231, Fax. +81-75-950-3800
E-mail: joel.teo@kiban.kuciv.kyoto-u.ac.jp
#78 Keith W. Hipel教授(カナダ・ウォータールー大学) 特別講演会のご案内
Date
2013年3月4日
Venue
京都大学宇治キャンパス 木質ホール
Keith W. Hipel教授(カナダ・ウォータールー大学) 特別講演会のご案内
The 20th International Seminar of Committee of Infrastructure Planning and Management, JSCE in FY2012
2012年度土木計画学研究委員会 第20回国際セミナー(通算 第78回国際セミナー)
下記のように、Keith W. Hipel教授(カナダ・ウォータールー大学)による、特
別講演会を開催いたします。Keith W. Hipel教授は、社会システム工学における
先駆的な学際的研究者として世界的に著名であり、今回は、平成24年度日本学術
振興会・外国人著名研究者招へ い事業により来日されます。この機会に、長年
に渡る卓越した学術的キャリアを通して蓄積してきた知識と経験をご講演いただ
きますので、皆様方には 是非ご参加いただきたくご案内申し上げます。学生諸
子にもご周知いただければ幸いです。
また、この講演会の後、懇親会を予定しておりますので、併せてご案内申し上げ
ます。
————————————————————
特別講演会
日時:3月4日(月) 15:00?16:30
場所:京都大学宇治キャンパス 木質ホール
(以下の地図の9番の建物です.)
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/access/campus/map6r_uji.htm
講演者:Prof. Keith W. Hipel, カナダ・ウォータールー大学
講演題目: 気候変動への挑戦
Tackling Climate Change: A System of Systems Engineering Perspective
講演要旨:
気候変動に取り組む責任ある統制に向けた、Systems of Systems Engineeringの
枠組みをベースとした統合的・適応型アプローチを提唱します。System of
Systems Engineering の枠組みは、参加型アプローチを用いて様々なステークホ
ルダーの価値観を反映しつつ、持続可能性や公平性といった目標を達成すること
が可能です。セミナー 後半には、講演者が研究者・教育者として心がけている
ことについてお話しいただきます。
講演内容の詳細につきましては、下記のHPをご参考下さい。
http://www.dpri.kyoto-u.ac.jp/web_j/contents/event_text/20130304-2.pdf
問い合わせ先:京都大学防災研究所 横松(0774-38-4279)
同 山下(0774-38-4039)
————————————————————
懇親会
日時: 2013年3月4日(月)17:00 – 18:30
場所: レストランきはだ
会費: 3,000円
お手数ですが、会場準備のため、懇親会にご出席いただく場合は、メールにて、
2/27(水)までに 京都大学防災研究所 社会防災研究部門 山下 秘書までお
申込下さい。
申込先: yamasita@imdr.dpri.kyoto-u.ac.jp
————————————————————
多々納裕一 (代理送信:横松)
#77 International Workshop on Transport Networks under Hazardous Conditions
Date
2013年3月1日
Venue
永田町「砂防会館」
International Workshop on Transport Networks under Hazardous Conditions
The 19th International Seminar of Committee of Infrastructure Planning and Management, JSCE in FY2012
2012年度土木計画学研究委員会 第19回国際セミナー(通算 第77回国際セミナー)
このワークショップは,科学研究費補助金(基盤A)による「移動体シミュレー ションと連動した交通ネットワークの信頼性評価」,および,国土交通 省の道 路政策の質の向上 に資する技術研究開発「都市高速道路における突発事象時の 最適交通運用についての研究開発」の成果を報告することを狙いとし て,東京 工業大学TSU(Transport Studies Unit) が企画・開催するもので,土木学会土 木計画学研究委員会の国際セミナーを兼ねています.国内外の関連分野の研究者 に発表いただく予定ですので,お忙しい時 期ではありますが,皆様のご参加を お待ちしております.
1.日時: 2013年3月1日(金曜)~2日(土曜)
2.場所: 永田町「砂防会館」
http://www.sabo.or.jp/kaikan-annnai/bekkan.htm
3.プログラム: 東工大 Transport Studies Unit のWEB,および,下記 6.をご覧ください.
http://www.transport-titech.jp/index.html
4. 申し込み方法:
会場準備の都合上,2月15日までに,「ご所属,お名前,連絡先Email」の情報を お知らせ下さい.質問等も併せて受け付けます.
申し込み先: 朝倉康夫 asakura[at]plan.cv.titech.ac.jp
5.関連情報:
前日の2/28に,東工大TSUの国際セミナー「Challenging Issues on Transport Studies」が開催されま す.併せてご参加ください.
6.International Workshop on Transport Networks under Hazardous Conditions
Dates:1st (Friday) and 2nd (Saturday), March, 2013
Venue:Sabo-kaikan (砂防会館)
http://www.sabo.or.jp/kaikan-annnai/bekkan.htm
1st (Friday) March
09:30-10:00 Opening (Yasuo Asakura)
10:00-10:45 Approaches to Modelling Degradable Networks (Mike Bell)
10:45-11:00 Break
11:00-11:30 Estimating Vehicle Trajectories on a Motorway by Data Fusion of Probe and Detector Data (Masao Kuwahara, Takeshi Ohhata, Tsubasa Takigawa, Takeshi Imai, Koichi Abe, Kiichiro Nakamura)
11:30-12:00 Traffic Accident Risk at Designated Expressway Road Networks (Toshio Yoshii)
12:00-13:30 Lunch
13:30-14:15 Temporal and Spatial Impacts of Rainfall Intensity on Traffic Accidents in Hong Kong (William Lam)
14:15-14:35 Traffic Prediction under Accidents using Dynamic Traffic Simulation on Tokyo Metropolitan Expressway (Hiroshi Warita, Ryota Horiguchi, Yuji Tamura, Hikaru Sato)
14:35-14:55 Behavior Changes of Drivers in Traffic Jams Due to Traffic Information Provision Based on Portable Traffic Detectors (Tomoyuki Adachi) 14:55-15:15 Improvement of Travel Time Information under Incident Condition Using Prediction Model Based on Current Traffic Condition (Toshihiko Kitazawa, Dai Tamagawa, Jun Tanabe, Takeshi Hagihara, Akito Higatani)
15:15-15:30 Break
15:30-16:15 Trip-timing decisions with traffic incidents(Mogens Fosgerau)
16:15-16:40 The impact of prevailing traffic conditions on incident characteristics (Zoi Christoforou)
16:40-17:05 The Progress of Miyako Recovery Plan from Tsunami Disaster (Tetsuo Yai)
17:05-17:30 Land-use Structure and Disaster Vulnerability (Daisuke Fukuda)
Session closed by 18:00
2nd (Saturday) March
09:15-10:00 Managing Pedestrian Crowds: for First Principles to Crowd Control Strategies (Serge Hoogendoorn)
10:00-10:45 A virtual travel laboratory: New methodological ways to unravel traffic and travel behaviour under extreme conditions (Hans van Lint)
10:45-11:00 Break
11:00-11:30 Modeling the Cooperation Network Formation Process for Evacuation Systems Design in Disaster Areas with a Focus on Japanese Mega-disasters (Eiji Hato, Jun Urata)
11:30-12:00 Evacuation Dynamics and Social Interactions (Takamasa Iryo, Shingo Tsujimoto, Kazunobu Amano)
12:00-13:30 Lunch
13:30-14:15 Resilience Issues in Vulnerable Transport Networks (Seungjae Lee)
14:15-14:45 Simulation analysis of commuters unable to get home and traffic congestion at large-scale disaster in Nagoya metropolitan area (Toshiyuki Yamamoto)
14:45-15:15 Spatio-Temporal Analysis of Gasoline Shortage in Tohoku Region after Great East Japan Earthquake (Takashi Akamatsu, Takeshi Nagae)
15:15-15:30 Break
15:30-16:00 Respondents’ Attitude on Large-scale Probe Person Survey using Smartphone Apps (Takuya Maruyama)
16:00-16:30 Stochasticity of Transportation Networks: Asymptotic distribution of travel times and maximum likelihood method (Sho-ichiro Nakayama)
16:30-16:40 Closing
Session closed by 17:00
#76 TokyoTech TSU Seminar "Challenging Issues on Transport Studies"
Date
2013年2月28日
Venue
TokyoTechフロント「ロイヤルブルーホール」
TokyoTech TSU Seminar "Challenging Issues on Transport Studies"
The 18th International Seminar of Committee of Infrastructure Planning and Management, JSCE in FY2012
2012年度土木計画学研究委員会 第18回国際セミナー(通算 第76回国際セミナー)
東京工業大学TSU(Transport Studies Unit)では,以下の要領で 2月28日午後に国際セミナーを開催致します.本セミナーは,東工大 TSUに所属する各研究グループの主要研究テーマ発表,並びに, 国内外からの招聘研究者による講演によって構成されております.
特に今回は,デンマーク工科大学のモーンス フォスグロゥ教授, 並びに,京都大学の文世一教授より基調講演を行って頂くことと なっております.
年度末のお忙しい時期ではございますが,興味ある多くの方々からの ご参加をお待ち申し上げております.
TSU Seminar “Challenging Issues on Transport Studies”
1. 日時: 2013年2月28日(木曜) 13時-18時半
Date: 13:00-18:30PM, February 28 (Thu), 2013
2. 主催: 東京工業大学イノベーション研究推進体
「先端的交通研究ユニット(TSU)」
Organizer: TokyoTech Transport Studies Unit (TSU)
http://transport-titech.jp
後援: 土木学会土木計画学研究委員会(国際セミナー)
アジア交通学会
計画交通研究会
Support: Infrastructure Planning Committee, JSCE
Eastern Asia Society for Transportation Studies (EASTS)
Association for Planning and Transportation Studies (APTS)
3. 会場: TokyoTechフロント「ロイヤルブルーホール」
[〒152-0033 東京都目黒区大岡山2丁目12-1 東工大蔵前会館内]
(東急目黒線/大井町線大岡山駅 徒歩1分)
Venue: Royal Blue Hall, TokyoTech Front
[Ookayama 2-12-1, Meguro-ku, 1520033 Tokyo, Japan]
(1 minute walk from Ookayama Station,
Tokyu Meguro/Oimachi Lines)
http://www.somuka.titech.ac.jp/ttf/index.html
4. プログラム (Program, all presentations done in English)
13:00-13:05 (5 min.)
Opening Remarks / Daisuke FUKUDA (Associate Professor, TokyoTech)
13:05-13:15 (10 min.)
Activities of TSU / Tetsuo YAI (Professor, TokyoTech)
(Session 1: City, Environment and Institution)
13:15-13:35 (20 min.)
“Innovative infrastructure planning process in Japanese communicative culture”
/ Tetsuo YAI (Professor, TokyoTech)
13:35-13:55 (20 min.)
“Development of cycling simulator for traffic safety analysis”
/ Mio SUZUKI (Assistant Professor, TokyoTech)
13:55-14:15 (20 min.)
“Airport capacity expansion and mitigation of aircraft noise impacts in Tokyo metropolitan area”
/ Terumitsu HIRATA (Adjunct Associate Professor, TokyoTech)
14:15-14:35 (20 min.)
“Transport and climate change in Japan: Current status”
/ Yasunori MUROMACHI (Associate Professor, TokyoTech)
(Session 2: Safety and Security)
14:35-14:55 (20 min.)
“Real-time crash prediction model for urban expressways”
/ Dr. Moinul HOSSAIN
(Adjunct Associate Professor, University of Toronto, Canada) 14:55-15:15 (20 min.)
“Behavioural data collection for disaster risk evaluation”
/ Yasuo ASAKURA (Professor, TokyoTech) and Takahiko KUSAKABE (Assistant Professor, Tokyo Tech)
[Break]
(Session 3: Travel Time Variability)
15:30-16:10 [Special Invited Lecture 1] (40 min.)
“Economic evaluation of travel time variability”
/ Professor Mogens FOSGERAU (Technical University of Denmark)
[Note] Dr. Mogens Fosgerau is a professor of economics at Department for Transport, Technical University of Denmark. His areas of research include micro-economics and micro-econometrics applied to problems in transportation, in particular to issues concerning time, reliability and congestion. He has contributed to the econometrics of discrete choice emphasising the problem of recovering the distribution of latent variables such as the value of travel time from observed choices. He has also worked on the value of reliability, providing a foundation for this concept in scheduling preferences. His most recent research area is policies to regulate urban congestion during demand peaks. He is a founding editor of Economics of Transportation.
http://www.transport.dtu.dk/upload/institutter/dtu%20transport/cv/cv-mf.pdf http://www.sciencedirect.com/science/journal/22120122/
16:10-16:30 (20 min.)
“The value of reliability for headway-based transit in Paris”
/ Assistant Professor Nicolas COULOMBEL (Ecole des Ponts ParisTech, France)
16:30-16:50 (20 min.)
“Japanese update of the valuation of travel time variability”
/ Daisuke FUKUDA (Associate Professor, TokyoTech)
(Session 4: Aviation and International Logistics)
16:50-17:30 [Special Invited Lecture 2] (40 min.)
“Port competition and welfare effect of privatization”
/ Professor Se-il MUN (Kyoto University)
17:30-17:50 (20 min.)
“Airline-airport cooperation in liberalized aviation market”
/ Batari Saraswati (Doctoral Student, TokyoTech) and Shinya Hanaoka (Associate Professor, TokyoTech)
17:50-18:30 (40 min.)
Comprehensive Discussion and Concluding Remarks
/ Yasuo ASAKURA (Professor, TokyoTech)
5. 申し込み方法 (How to apply):
会場の準備の関係上,2月25日までに,以下のEmailまで
「ご所属,お名前,連絡先Email」 の情報をお知らせ下さい.質問等も併せて受け付けます.
申し込み先:福田大輔(fukuda[at]plan.cv.titech.ac.jp)
Please send the participant’s information (Name, affiliation, and the contact email address) to Dr. Daisuke FUKUDA (fukuda@plan.cv.titech.ac.jp). Any inquiry about the seminar are also welcomed.
6. 関連情報(Relevant information): 翌日の3月1日-2日には,TSU国際ワークショップ “Transport Networks under Hazardous Conditions” (会場:砂防会館,別途案内)も開催されますので,興味ある方は併せてご参加頂けますよう,お願い申し上げます.
International Workshop on Transport Networks under Hazardous Conditions Dates: 1st-2nd March 2013
Venue: Sabo Kaikan, Tokyo, Japan
(Address: 2-7-5, Hirakawa-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, 102-0093)
http://www.sabo.or.jp/kaikan-annnai/bekkan.htm
http://transport-titech.jp/seminar_visitor/2013/TSU-IWORKSHOP2013-01_Mar_1st.pdf
#67 自転車通行空間の設計 ~事例から学ぶ~
Date
2012年12月7日
Venue
キャンパスポート大阪 会議室D+E 大阪市北区梅田1-2-2-400 大阪駅前第2ビル4階
自転車通行空間の設計 ~事例から学ぶ~
土木計画学ワンデーセミナー NO.67
自転車通行空間の設計 ~事例から学ぶ~
土木計画学研究委員会自転車政策研究小委員会(代表:山中英生(徳島大学))では、「自転車通行空間の設計 ~事例から学ぶ~」という題目でワンディセミナーを、下記の通り開催します。8月に東京で開催された同セミナー内容を更新し、大阪で開催します。
セミナーでは、本小委員会で制作した事例集テキスト(増補版発行予定)を用いて、今後の自転車通行空間整備の方向性について情報共有を図りながら、議論する場にしたいと考えております。
自転車計画、道路設計等に携わる技術者、都市交通に関わる研究者、自転車に関心のある利用者の方など、是非この機会にご参加くださいますよう、お願い致します。
開催趣旨:
警察庁や国土交通省の検討会では、車道における自転車利用ネットワーク整備に向けて提言をまとめています。また、モデル事業や社会実験において、多様な整備事例が生まれています。
本セミナーでは、土木学会計画学研究委員会の自転車政策研究小委員会において製作しました、多様な自転車通行空間の事例集(CD-ROM版カラーPDF、主要な約40例の経緯・評価を収録)を用いて、歴史や設計上の留意点などを解説し、今後の整備方向を共有します。
主催:土木学会土木計画学研究委員会「自転車政策研究小委員会」 土木学会関西支部
共催:自転車活用推進研究会
日時:開催日:2012年12月7日(金) 午前10:30-16:30 受付開始:10:00
場所:キャンパスポート大阪 会議室D+E 大阪市北区梅田1-2-2-400 大阪駅前第2ビル4階
定員:117名(定員になり次第締め切らせて頂きます)
参加費:土木学会会員(正会員[個人]等)・土木学会関西支部賛助会員団体所属者:7,000円
学生:5,000円 その他:9,000円
・参加費に、テキスト『自転車通行空間整備・計画事例集CD』代を含みます。
・事例集CDは東京のセミナーで使用したものの一部増補版となる予定です。
・キスト『自転車通行空間整備・計画事例集CD』のみの購入も可能です。
・土木学会認定CPDプログラム
プログラム(予定):
10:30-10:35 はじめに 徳島大学 山中英生
10:35-11:05 自転車通行空間の歴史 岩手県立大学 元田良孝
11:05-11:35 自転車通行空間の設計上の留意点(仮)国土交通省 国土技術政策総合研究所 本田 肇
11:35-12:05 自転車通行空間事例集の解説 東京工業大学 鈴木美緒
昼食休憩
13:00-13:25 事例1 自転車道の事例 茨城大学 金 利昭
13:25-13:50 事例2 自転車レーンの事例 日本文理大学 吉村充功
13:50-14:15 事例3 自転車レーンの交差点 (株)日建設計シビル 大森高樹
14:15-14:40 事例4 指導帯の事例 (株)日本海コンサルタント 埒 正浩
14:40-15:05 事例5 生活道路の自転車施策 地球の友金沢 三国成子
休 憩
15:15-16:30 自転車通行空間整備の展望と質疑
座長:埼玉大学 久保田尚
コメント:徳島大学 山中英生
自転車活用推進研究会 小林成基
上記発表者からの質疑への回答
申込方法:
土木学会関西支部のサイトよりオンライン申し込みをお願い致します。
http://goo.gl/Bt545
申込締切日:11月22日(木)
申し込みに関してお願い:
定員に達し次第申込を締め切ります。また、定員に余裕がある場合は締切後も引き続きお申込を受け付けます。
問合先:
申込等に関するお問い合わせ:
541-0055 大阪市中央区船場中央2-1-4-409
土木学会関西支部「ワンディセミナー」係
TEL:06-6271-6686 FAX:06-6271-6485
企画内容に関するお問い合わせ:
自転車政策研究小委員会事務局 吉田長裕(大阪市立大学)
E-mail:yoshida@civil.eng.osaka-cu.ac.jp
#75 Transport & Planning (TU Delft) Seminar
Date
2012年11月14日
Venue
京都大学 桂キャンパス Cクラスター315号室
Transport & Planning (TU Delft) Seminar
The 17th International Seminar of Committee of Infrastructure Planning and Management, JSCE in FY2012
2012年度土木計画学研究委員会 第17回国際セミナー(通算 第75回国際セミナー)
講師:デルフト工科大学 Prof. Bart van Arem, Prof. Victor Knoop, Mr. Bernat Goni Ros他
日時:平成24年11月14日(水) 13:30 – 16:30
場所:京都大学 桂キャンパス Cクラスター315号室
プログラム:
13:30 – 14:00 Mr. Masami Yanagihara (Kyoto University)
– A Model for Transition of Latent Intentions: An Integration of Driving Phase/Regime Models
14:00 – 14:30 Dr. Yasuhiro Shiomi (Ritsumeikan University)
– Travel time measurement based on loop detectors considering lane changes
14:30 – 14:45 Coffee break
14:45 – 15:15 Mr. Bernat Goni Ros (Delft University of Technology)
– Car-following behavior at sags and its impacts on traffic flow
15:15 – 15:45 Prof. Victor Knoop (Delft University of Technology)
– Generalized macroscopic fundamental diagram in traffic
15:45 – 16:15 Prof. Bart van Arem (Delft University of Technology)
– Towards cooperative traffic management in the Netherlands
問い合せ:
参加を希望される方は,会場設営等の都合上,
立命館大学 塩見(shiomi@fc.ritsumei.ac.jp)までご一報下さい.
#74 International Seminar on Humanitarian Logistics and Emergency Management
Date
2012年11月6日
Venue
Jin-Yu Hall, Katsura Campus, Kyoto University
International Seminar on Humanitarian Logistics and Emergency Management
The 16th International Seminar of Committee of Infrastructure Planning and Management, JSCE in FY2012
2012年度土木計画学研究委員会 第16回国際セミナー(通算 第74回国際セミナー)
Seminar Title: International Seminar on Humanitarian Logistics and Emergency Management
Date: 9:00 – 16:30, November 6, 2012
Venue: Jin-Yu Hall, Katsura Campus, Kyoto University
Seminar Description:
Disasters both natural and man-made have significantly affected population across the world. Consequently, substantial efforts have been made to create societies that are disaster resilient. Humanitarian logistics being a key process towards disaster resilience, have gained significant attention from researchers and practitioners in the field. The purpose of the seminar is to bring an opportunity for multi-disciplinary researchers and practitioners to discuss and exchange ideas on:
– Past disaster experiences and lessons learnt
– Issues and challenges in humanitarian logistics
– Modeling techniques
– Emergency management, response and recovery
– Risk management strategies
The overall objective is to explore innovative yet practical research ideas that can strengthen humanitarian logistics system.
Program:
9:00 Prof. Eiichi Taniguchi (Kyoto University) Welcome Address
9:10 Prof. Eiichi Taniguchi (Kyoto University) The relief supply distribution in the Tohoku disasters
10:00 Break
10:15 Prof. Kenji Ono (Kyoto University) An impact of the east Japan great earthquake on the local and global logistics
11:05 Mr. Motohisa Abe (National Institute for Land and Infrastructure Management) Emergency relief logistics supported by the maritime sector at the East Japan Great Earthquake – operations and challenges
11:55 Lunch Break
14:00 Dr. Russell G. Thompson (Monash University) Recovery of road freight networks after disasters
14:50 Break
15:05 Dr. Rojee Pradhananga (Kyoto University) Risk management in hazardous material transportation
15:45 Mr. Andie Pramudita (Kyoto University) Application of debris collection operation after disasters model case study: Tokyo metropolitan area hazard maps
16:25 Dr. Russell G. Thompson (Monash University) Closing Remarks
Contact:
Dr. Rojee Pradhananga
C1-3-182 Kyoto-daigaku Katsura, Nishikyo-ku, Kyoto 615-8540, Japan
Tel: +81-75-383-3415 Fax: +81-75-950-3800
Email: rojee@kiban.kuciv.kyoto-u.ac.jp
第46回土木計画学研究発表会・秋大会
Date
2012年11月2日(金)~4日(日)
Venue
埼玉大学
第46回土木計画学研究発表会・秋大会
会告について
▼ 第46回土木計画学研究発表会・秋大会 会告(以下の通り)
実施期日
2012年11月2日(金)~4日(日)の3日間
実施場所
埼玉大学
講演用論文
発表会の当日に充実した議論を行うということが、本発表会の特色です。このため、講演の申し込みに際して、「土木計画学への貢献」と「議論したい点」を明記していただきます。話題性、速報性のある論文や、調査・計画、技術検討等の事例報告も歓迎します。提出された講演用論文は、原則として無審査で 掲載されますが、会場の制約等によってお断りすることもあります。
なお、ポスターセッションを今年度も実施いたします。口頭発表とポスターでの発表のどちらを希望する かを選んで申込んでいただきます(口頭発表およびポスターでの発表のいずれも、「土木学会論文集D3(土木計画学),Vol.69,No.5(土木計画学 研究・論文集30巻)」への投稿対象となります)。本秋大会の一日目は平日であり、会場の都合上、一日目はポスター発表などを主体にする予定です。多くの ポスター発表をお待ちしております。
2013年発行予定の「土木学会論文集D3(土木計画学),Vol.69,No.5(土木計画学研究・論文集30巻)」及びそれ以降の巻への投稿には、投稿時点で過去2年以内の土木計画学研究発表会での講演が必要となりますので、あらかじめご了承ください。
問合先
(社)土木学会 研究事業課 増永 克也 E-mail:masunaga@jsce.or.jp
以下の該当する部分を熟読のうえ、手続きを取っていただけますようお願いいたします。
講演の申込み
(1) 申込みの手続きおよび注意点
2012年8月3日(金)17時までの期間内に、土木計画学委員会ホームページを使って、講演申込と講演原稿の投稿を同時に行ってください。原稿のファイル形式はPDF形式のみ受付けます。 原稿は「講演原稿執筆要領」に従ってご執筆ください。 申込んだ論文が正しく転送されているかを確認するための期間を2012年8月6日(月)~8月8日(水)17時に設けています。講演申込み者自身で必ず確認してください。 申込み期間の締切り間際に投稿が集中しますと、予期せぬ事態によりサーバーがダウンし受付ができなくなる恐れがあります。締切り間際の投稿は極力避けていただくようお願いいたします。
なお、原稿の提出がないもの、講演原稿執筆要領に準じていないもの、および期限後に投稿されたものは受理できません。確認期間を過ぎての原稿の差し替え・修正および申し込みの取り下げには応じられません。必ず最終原稿を期間内にWEB上にて投稿してください。
(2) 発表希望分野
申し込みに際して、発表希望分野を下記の5つの発表分野から希望順に2つ選んでください。また、キーワードにつきましては、同キーワード欄の中から最大4つ選んでください。なお、適当なキーワードが見つからない場合は、投稿者の判断によるキーワードを1つだけ加えてください。
発表希望分野
| 発表希望分野 | キーワード |
| A 計画論・計画情報 | 計画基礎論、計画手法論、システム分析、調査論、公共事業評価法、財源・制度論、プロジェクト構想、施工計画・管理、維持管理計画、意識調査分析、計画情報、情報処理、市民参加、GIS、リモートセンシング、測量、環境計画、防災計画、河川・水資源計画、ライフライン計画・設計、地球環境問題 |
| B 地域・都市・景観 | 国土計画、地域計画、都市計画、地区計画、住宅立地、産業立地、人口分布、地価分析、土地利用、市街地整備、再開発、景観、公園・緑地、観光・余暇、空間設計、イメージ分析、土木史 |
| C 交通現象分析 | 発生交通、目的地選択、交通手段選択、経路選択、出発時刻選択、活動分析、時間利用、交通行動調査、交通意識分析、交通行動分析、自動車保有・利用、駐車需要、交通ネットワーク分析、土地利用・交通・環境統合モデル、観光・余暇行動 |
| D 交通基盤計画 | 総合交通計画、地区交通計画、公共交通計画、歩行者・自転車交通計画、道路計画、鉄道計画、空港・港湾計画、ターミナル計画、駐車場計画、物流計画 |
| E 交通運用管理 | 交通流、交通容量、サービス水準、交通制御、交通管理、交通安全、交通情報、交通環境、公共交通運用、交通弱者対策、水上交通、空港管理、交通量計測、TDM、ITS、モビリティマネジメント(MM) |
(3) 発表形式
口頭発表とポスターでの発表のどちらを希望するかを選んでいただきます。なお、会場の都合でご希望に添えない場合もありますので予めご了承下さい。
(4) 投稿料
講演1本につき投稿料(参加費含む)として一般12,000円、学生9,000円を請求いたします。2本以上投稿する方については、2本目以降の投稿料は一般・学生ともに6,000円を請求いたします。振込手数料は各自でご負担願います。
講演原稿執筆要領
講演原稿の書式・形式は、土木学会論文集のものに準じています。下記の作成例やサンプルファイルをご利用ください。講演原稿では、英文アブストラクトの記入は任意です。その他書式・形式についての詳細は土木学会論文集の原稿作成の手引き等をご参照ください。なお、「土木学会論文集D3(土木計画学), Vol.75-6」への投稿の際には英文アブストラクトは必要です。
サンプルファイル 和文(Word2000)/English(Word2000)
原稿作成例 和文(PDF)/English(PDF)
CD-ROM版講演集の配布について
CD-ROM版講演集は大会参加者全員に配布します。事前受付をされた方には郵送でCD-ROM版講演集を配布します。大会当日に受け付けされた方には、当日配布いたします。
お問合せ先
土木計画学研究委員会大会運営小委員会(春大会担当:橋本,氏原,林)
E-mail:keikaku59@jsce.or.jp
#73 Special seminar on public-private partnerships (PPPs)
Date
2012年9月19日
Venue
京都大学 吉田キャンパス 総合研究棟 2号館3階 ケーススタディ室
Special seminar on public-private partnerships (PPPs)
The 15th International Seminar of Committee of Infrastructure Planning and Management, JSCE in FY2012
2012年度土木計画学研究委員会 第15回国際セミナー(通算 第73回国際セミナー)
日時:日時:平成24年9月19日(水) 10:00 – 12:00
場所:京都大学 吉田キャンパス 総合研究棟 2号館3階 ケーススタディ室
プログラム:
10:00 – 10:05 Introduction
10:05 – 10:35 Comparative Study on PPPs around the World
Speaker: Masamitsu Onishi
Assistant Professor at Graduate School of Engineering,
Kyoto University
10:35 – 10:45 Break
10:45 – 11:30 PPP Policy and Implementation in Philippine
Speaker: Cayetano Paderanga, Jr.
Former Director-General of the National Economic and
Development Authority (NEDA),
the government of Philippine Professor at University of
Philippine
Visiting Research Fellow at Center for Southeast Asian Studies,
Kyoto University
11:30 – 12:00 Free discussion
使用言語:英語
参加申し込み:参加を希望される方は,配付資料等の準備の都合上,メールにてご一報下さい.
京都大学大学院工学研究科都市社会学専攻 大西正光
onishi.masamitsu.7e@kyoto-u.ac.jp
#3 モビリティ首都を目指すグレーターナゴヤのインフラ整備とITS(2012年・年次学術講演会)
Date
2012年9月7日
Venue
名古屋大学 東山キャンパス 工学部(工学研究科)3号館 3-321(会場名:Ⅳ-1)
モビリティ首都を目指すグレーターナゴヤのインフラ整備とITS
平成24年度土木学会全国大会 研究討論会 <名古屋大学>
題目:モビリティ首都を目指すグレーターナゴヤのインフラ整備とITS
(土木計画学研究委員会)
概要:交通の要衝であり、自動車関連産業が集積している名古屋大都市圏(グレーターナゴヤ)は、先進的モビリティの研究開発から社会実装までを世界に先駆けて行う「モビリティ首都」を目指そうとしている。本討論会では、グレーターナゴヤにおける、運輸・交通、エネルギー、環境、防災、福祉、まちづくり、経済活性化などの課題解決を念頭に、交通インフラ、情報通信インフラ、車両、デバイス、制度などのあり方と、「モビリティ首都」の考え方について議論を行う。
パネリスト:
・天野 肇 (ITS Japan 専務理事)
・菊地 春海 (国土交通省 中部地方整備局道路部長)
・杉浦 孝明 (三菱総合研究所)
・中村 英樹 (名古屋大学)
・森川 高行 (名古屋大学) <コーディネータ>
日時: 9月7日(金) 12:40~14:40
場所: 名古屋大学 東山キャンパス
工学部(工学研究科)3号館 3-321(会場名:Ⅳ-1)
http://www.jsce.or.jp/taikai2012/guidance.html#campus
参加費: 無料(会場に直接お越しください)
#72 WHAT PUBLIC SERVING PLANNERS CAN LEARN FROM MEDIATORS OF PUBLIC DISPUTES: Micropolitics and Possibilities
Date
2012年9月5日
Venue
京都大学 百周年時計台記念館 2F 会議室Ⅲ
WHAT PUBLIC SERVING PLANNERS CAN LEARN FROM MEDIATORS OF PUBLIC DISPUTES: Micropolitics and Possibilities
The 14th International Seminar of Committee of Infrastructure Planning and Management, JSCE in FY2012
2012年度土木計画学研究委員会 第14回国際セミナー(通算 第72回国際セミナー)
日時:2012年9月5日(水)13:30~15:00
場所:京都大学 百周年時計台記念館 2F 会議室Ⅲ
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/clocktower/
講演者: ジョン・フォレスター教授 コーネル大学 都市地域計画学科
講演タイトル:WHAT PUBLIC SERVING PLANNERS CAN LEARN FROM
MEDIATORS OF PUBLIC DISPUTES: Micropolitics and Possibilities
講演概要:フォレスター先生は、Planning in the Face of Power (1989)、The Deliberative Practitioner (1999)などの著作を通じ、都市計画の決定過程における対話や意思決定の実態をつぶさに観察するすることで、都市計画家の役割を、技術専門家としてだけではなく、多様な市民の調整役にまで拡大再定義された第一人者です。
http://bit.ly/vzcxcq
今回の講演会では、都市計画分野で活躍するファシリテーター・メディエーターなどの実態を長年観察してきたフォレスター先生が、公共分野での論争・紛争の解決に携わるメディエーターの経験や知識から、都市計画の専門家やプランナーが学ぶことができることは何かを、議論を通じて明らかにしていきます。
定員:30名
言語:英語
参加手続き: 参加無料・要事前登録
参加お申し込みは http://bit.ly/OqUOjM からお願いします。
連絡先:東京大学公共政策大学院 特任准教授
松浦正浩 matsuura@pp.u-tokyo.ac.jp
#71 THE CHALLENGE OF A CRITICAL PRAGMATISM:Integrating Learning and Acting through Creative Negotiations
Date
2012年9月1日
Venue
東京大学本郷キャンパス 経済学研究科 小島ホール(2階)
THE CHALLENGE OF A CRITICAL PRAGMATISM:Integrating Learning and Acting through Creative Negotiations
The 13th International Seminar of Committee of Infrastructure Planning and Management, JSCE in FY2012
2012年度土木計画学研究委員会 第13回国際セミナー
(通算 第71回国際セミナー)
日時:2012年9月1日(土)
場所:東京大学本郷キャンパス 経済学研究科 小島ホール(2階)
講演者: ジョン・フォレスター教授 コーネル大学 都市地域計画学科
講演タイトル:THE CHALLENGE OF A CRITICAL PRAGMATISM:
Integrating Learning and Acting through Creative Negotiations
講演概要: フォレスター先生は、Planning in the Face of Power (1989)、he Argumentative Turn in Policy Analysis and Planning (1993)Frank Fischerと共編)、The Deliberative Practitioner (1999)などの作を通じ、都市計画を中心とした政策形成過程におけるディスコースに目し、 対話や意思決定の実態に基づき、批判的視点から政策分析の理論を進めてきた第一人者です。
http://bit.ly/vzcxcq
今回の講演会では、対話や交渉を通じた政策形成によって、ステークホルダーのバーゲニングによる短期的な問題解決にとどまらず、内省的な学習へと発展していく過程を、「批判的プラグマティズム」の視点から、実践と理論について、お話いただきます。
対話の参与観察やインタビューなどに基づき、演繹的に理論を構築し、論文として記述し、さらに査読でアクセプトされることは、決して容易なことではありません。この課題は、質的研究に取り組む人々の世界的な課題であり、フォレスター先生も重大な関心を寄せています。そこで、フォレスター先生をまじえ、若手研究者や学生を中心に、論文執筆の課題と戦略について議論するライティング・ワークショップを同時開催します。
プログラム:
13:00~14:30 講演会
15:00~16:00 ライティング・ワークショップ
定員:40名(ワークショップ:20名)
言語:英語
参加手続き: 参加無料・要事前登録 参加お申し込みは
http://bit.ly/MzO1Bf からお願いします。
(ワークショップの参加申し込みは上記講演会と同時にお願いします)
連絡先:東京大学公共政策大学院 特任准教授
松浦正浩 matsuura@pp.u-tokyo.ac.jp
#66 自転車通行空間の設計 ~事例から学ぶ~
Date
2012年8月3日
Venue
東京工業大学 くらまえホール(蔵前会館)
自転車通行空間の設計 ~事例から学ぶ~
土木計画学ワンデーセミナー NO.66
自転車通行空間の設計 ~事例から学ぶ~
開催日:2012年8月3日(金) 午前10:00-17:00
開催場所:東京工業大学 くらまえホール(蔵前会館) 定員200名
〒152-0033 目黒区大岡山2丁目12-1 東急大井町線 大岡山駅下車1分
http://www.somuka.titech.ac.jp/ttf/access/index.html
主催:土木学会土木計画学研究委員会(自転車政策研究小委員会)
http://goo.gl/LVKbH
後援:国土交通省国土技術政策総合研究所(依頼中),自転車活用推進研究会
参加費:土木学会会員 7,000円 土木学会非会員 9,000円 学生5,000円
(テキスト:自転車通行空間整備・計画事例集CDを含む)
趣旨:
警察庁や国土交通省の検討会では,車道における自転車利用ネットワーク整備に向けて提言をまとめています。また,モデル事業や社会実験において,多様な整備事例が生まれています。本セミナーでは,土木学会計画学研究委員会の自転車政策研究小委員会において製作しました,多様な自転車通行空間の事例集(CD-ROM版カラーPDF,主要な34事例の経緯・評価を収録)を用いて,歴史や設計上の留意点などを解説し,今後の整備の方向性を共有します。
プログラム:
10:00 はじめに 徳島大学 山中英生
10:05 自転車通行空間の歴史 岩手県立大学 元田良孝
10:45 自転車通行空間の設計上の留意点(仮) 国総研(依頼中)
11:10 自転車通行空間事例集の解説 徳島大学 山中英生
11:30 事例1 自転車道 水戸 茨城大学 金 利昭
13:00 事例2 自転車レーン 尼崎市 大阪市立大学 吉田長裕
13:30 事例3 自転車レーンおよび交差点 静岡市 (株)オリエンタル
コンサルタント 竹平誠治
14:00 事例4 指導帯 世田谷区 東京工業大学 鈴木美緒
14:30 事例5 生活道路 金沢市 地球の友金沢 三国成子
15:15 質疑応答および自転車通行空間整備の展望
座長:埼玉大学 久保田尚
コメント:東京工業大学 屋井鉄雄
自転車活用推進研究会 小林成基
上記発表者からの質疑への回答
※同様の内容を大阪において12月7日に開催する予定です。紹介事例、登壇者は一部変更される可能性があり、事例集CDは増補版となる予定です。
自転車通行空間整備・計画事例集 目次:
最新の目次は以下の小委員会ホームページをご覧ください。
http://goo.gl/JVbSD
参加申込み:
土木学会行事サイトより『自転車通行空間の設計 ~事例から学ぶ~』(行事コード:40203) 「申込画面へ」をクリックしてください。法人会員、または土木学会個人会員以外の方はFAX申し込みとなります。詳細は「申込画面へ」で表示されます。
土木学会行事サイト:http://www.jsce.or.jp/event/active/information.asp
↑
申込締切:7月18日(水)
申し込みに関してお願い:
・申込締切日前に定員に達している場合がございますので予めご了承ください.
なお,締切日以降の事前受付はいたしません.但し,定員に余裕がある場合は,行事当日に会場にて受付致します.
・申込後,やむを得ずキャンセルをされる場合は,必ず開催日の5日前(土・日・祝祭日を含まず)までに研究事業課宛ご連絡ください.ご連絡がない場合は,参加費を徴収させて頂きますので予めご了承ください.
・申込をされる前にご送金頂くことはトラブルの原因となりますので固くお断り致します.
連絡先:
・申し込み等に関するお問い合わせ:
土木学会事務局研究事業課 土木学会事務局研究事業課 尾崎史治
TEL 03-3355-3559 E-mail:fumiharu-ozaki@jsce.or.jp
・企画・内容等に関するお問い合わせ:
自転車政策研究小委員会 事務局 吉田長裕(大阪市立大学)
E-mail:yoshida@civil.eng.osaka-cu.ac.jp
#62 Temporal Aggregation in Traffic Forecasting: Implications for Statistical Characteristics and Model Choice 「交通需要予測における時間的な集計:統計的な特性とモデルの選択への示唆」
Date
2012年7月10日
Venue
東京大学工学部1号館2階 社会基盤学科セミナーB室
Temporal Aggregation in Traffic Forecasting: Implications for Statistical Characteristics and Model Choice 「交通需要予測における時間的な集計:統計的な特性とモデルの選択への示唆」
The 4th International Seminar of Committee of Infrastructure Planning and Management, JSCE in FY2012
2012年度土木計画学研究委員会 第4回国際セミナー(通算 第62回国際セミナー)
・講演タイトル:Temporal Aggregation in Traffic Forecasting: Implications for Statistical Characteristics and Model Choice
(交通需要予測における時間的な集計:統計的な特性とモデルの選択への示唆)
・講演概要:
Temporal Aggregation in Traffic Forecasting: Implications for Statistical Characteristics and Model Choice Time series techniques are useful for analyzing transportation data, uncovering past trends and providing projections. Such analyses are sensitive to the temporal aggregation of the data, an issue that has been widely ignored in the transportation literature. In traffic engineering, aggregation usually equals to the average of a variable across large regular time intervals, such as 15 minutes, hours, days, months and so on. We investigate the effects of temporal aggregation on time series of traffic volume and occupancy in urban signalized arterials. Results indicate that aggregation eliminates long memory characteristics and variance heterogeneity; this leads to smoothing traffic variation and creating a time series structure that has reduced sensitivity to changes in traffic. Moreover, aggregation was found to directly affect volatility as captured by the parameters of the Generalized Auto-Regressive Conditionally Heteroskedastic (GARCH) models.
・講演者:Matthew G. Karlaftis, Associate Professor of the National
Technical University of Athens(国立アテネ工科大学准教授)
・日時:2012年7月10日(火)16:00-17:00
・場所:東京大学工学部1号館2階社会基盤学科セミナーB室
(工学部1号館へのアクセスは,http://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/cam01_04_02_j.htmlをご覧ください.)
・言語:英語
・参加手続き:無料です.事前に以下の連絡先まで,連絡をお願いします.ただし,当日の突然参加も大歓迎です.
・連絡・問い合わせ先:加藤浩徳(kato@civil.t.u-tokyo.ac.jp)
#70 Statistics and Neural Networks: Differences, Similarities, and Why Should transportationresearchers be Interested?
Date
2012年7月6日
Venue
京都大学 吉田キャンパス 本部構内 工学部3号館 講義室N3
Statistics and Neural Networks: Differences, Similarities, and Why Should transportationresearchers be Interested?
The 12th International Seminar of Committee of Infrastructure Planning and Management,
JSCE in FY2012
2012年度土木計画学研究委員会 第12回国際セミナー(通算 第70回国際セミナー)
日時:2012年7月6日(金) 16:30~18:00
会場:京都大学 吉田キャンパス 本部構内 工学部3号館 講義室N3
京都大学 吉田キャンパス:http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/access/campus/map5r.htm
本部構内 工学部3号館:http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/access/campus/map6r_y.htm
講演者: Matthew G. Karlaftis
講演題目:Statistics and Neural Networks: Differences, Similarities, and Why Should transportation researchers be Interested?
(統計的アプローチとニューラルネットワーク:その相違,共通点および交通研究者が興味を持つ理由.)
講演概要:
In the field of transportation, data analysis is probably the most important and widely used research tool available. In the data analysis universe, there are two ‘schools of thought’;
the first uses statistics as the tool of choice, while the second – one of the many methods from – Computational Intelligence. Although the goal of both approaches is the same, the two have kept each other at arm’s length.
Researchers frequently fail to communicate and even understand each other’s work. In this presentation we discuss differences and similarities between these two approaches, attempt to provide a set of insights for selecting the appropriate approach, and present three cases studies from transportation research that compare the two distinct approaches on the same set of data.
講演言語:英語
申し込み:7月4日(水)まで下記連絡先までご連絡願います。当日参加も可。
連絡・問い合わせ先:中村俊之(nakamura@trans.kuciv.kyoto-u.ac.jp)
#69 Short Term Traffic and Travel Time Forecasting: Objectives,Methods,Future Directions
Date
2012年7月5日
Venue
名古屋大学工学部8号館2階土木系会議室(210号室)
Short Term Traffic and Travel Time Forecasting: Objectives,Methods,Future Directions
The 11th International Seminar of Committee of Infrastructure Planning and Management, JSCE in FY2012
2012年度土木計画学研究委員会 第11回国際セミナー(通算 第69回国際セミナー)
日時:2012年7月5日(木)16:30-17:30
場所:名古屋大学工学部8号館2階土木系会議室(210号室)
(8号館へのアクセスはhttp://www.civil.nagoya-u.ac.jp/access.htmlをご覧ください.)
講演者:Matthew G. Karlaftis先生(国立アテネ工科大学准教授)
講演題目:Short Term Traffic and Travel Time Forecasting: Objectives, Methods, Future Directions
(交通所要時間の短期予測:目的,方法と将来動向)
講演概要:In the last two decades, the growing need for short-term prediction of traffic parameters embedded in a real-time intelligent transportation systems environment has led to the development of a vast number of forecasting algorithms.
Despite this, researchers rarely have a clear view regarding the various requirements involved in modeling short term traffic flow. We examine developments in the field by separating short-term traffic forecasting into its three basic aspects:
determination of scope, data quality, and core modeling. We critically discuss several interactions between the above parameters and offer an approach that can be used as a framework for developing successful short-term traffic and travel time forecasting models.
講演言語:英語
連絡・問い合わせ先:名古屋大学 山本俊行(yamamoto@civil.nagoya-u.ac.jp)
#68 Attitudes and Value of Time Heterogeneity
Date
2012年6月29日
Venue
東京工業大学創造プロジェクト館1F大会議室
Attitudes and Value of Time Heterogeneity
The 10th International Seminar of Committee of Infrastructure Planning and Management, JSCE in FY2012
2012年度土木計画学研究委員会 第10回国際セミナー(通算 第68回国際セミナー)
第5回東京工業大学TSU (Transport Studies Unit)セミナー http://www.transport-titech.jp/
日時:2012年6月29日(金)17:30-19:00
場所:東京工業大学創造プロジェクト館1F大会議室(東急大井町線緑が丘駅徒歩8分)
http://www.plan.cv.titech.ac.jp/fukudalab/contact/
講師:Maya Abou-Zeid氏 (American University of Beirut 講師,MIT-ITSプログラム研究員)
講演タイトル:Attitudes and Value of Time Heterogeneity (態度と時間価値異質性の関連性)
概要:
There is ample evidence showing a high level of heterogeneity of values of time among travelers.
Previous studies have represented this heterogeneity by a distribution such as lognormal whose parameters depend on covariates like income, trip purpose, and mode of travel.
We present and demonstrate a model where the distribution of the value of time also depends on attitudes towards travel. Attitudes are latent, or unobservable, and their distribution determines the conditional distribution of the value of time given the observable covariates such as income. We illustrate this model using data from a stated preferences survey. The estimation results show that as expected the median value of time increases with income and that the variability of value of time also increases with income reflecting the greater effect that the attitude towards travel has for high income groups.
参加申込:ご参加を希望される方は,資料ならびに会場の準備の都合上,6月27日(水)までに,以下までご連絡ください.
東京工業大学大学院理工学研究科 福田大輔 fukuda@plan.cv.titech.ac.jp
#66 Does Biofuel Reduce GHG Emissions from the Transport Sector? :Some Insights from Global Economic Modeling 「バイオ燃料は交通部門の地球温暖化ガスを減少させるのか?:世界経済モデルからの知見」
Date
2012年6月29日
Venue
東京大学工学部1号館社会基盤学科1階 13号講義室
Does Biofuel Reduce GHG Emissions from the Transport Sector? :Some Insights from Global Economic Modeling 「バイオ燃料は交通部門の地球温暖化ガスを減少させるのか?:世界経済モデルからの知見」
The 8th International Seminar of Committee of Infrastructure Planning and Management, JSCE in FY2012
2012年度土木計画学研究委員会 第8回国際セミナー(通算 第66回国際セミナー)
日時:2012年6月29日(金)17:00-18:30
場所:東京大学工学部1号館社会基盤学科1階13号講義室
http://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/cam01_04_02_j.html
講演者:Govinda R Timilsina博士(世界銀行シニアリサーチエコノミスト)
講演タイトル:Does Biofuel Reduce GHG Emissions from the Transport Sector?
Some Insights from Global Economic Modeling?
(バイオ燃料は交通部門の地球温暖化ガスを減少させるのか?:世界経済モデルからの知見)
言語:英語
参加手続き:無料です.事前に以下まで,連絡をお願いします.ただし,当日,突然の参加も大歓迎です.
連絡先:加藤浩徳(kato@civil.t.u-tokyo.ac.jp)
#67 Probabilistic Fusion of Vehicle Features for Re-identification and Travel Time Estimation Using Video Image Data
Date
2012年6月26日
Venue
東京工業大学・大岡山キャンパス西8号館E棟 E1001会議室
Probabilistic Fusion of Vehicle Features for Re-identification and Travel Time Estimation Using Video Image Data
The 9th International Seminar of Committee of Infrastructure Planning and Management, JSCE in FY2012
2012年度土木計画学研究委員会 第9回国際セミナー(通算 第67回国際セミナー)
日時:2012年6月26日(火) 15:00-18:00
場所:東京工業大学・大岡山キャンパス 西8号館E棟 E1001会議室
http://www.titech.ac.jp/about/campus/o_map.html?id=03
講師: Dr. Agachai Sumalee (The Hong Kong Polytechnic University)
題目:Probabilistic Fusion of Vehicle Features for Re-identification and Travel Time Estimation Using Video Image Data
プログラム詳細:
http://www.transport-titech.jp/seminar_visitor/2012/TSU-SV2012-004_June_26th.pdf
申し込み方法:
6月23日(土)までに参加申し込みフォームにてご連絡ください。
送信先:tsu-office@plan.cv.titech.ac.jp(東京工業大学 日下部貴彦)
参加申し込みフォーム:
—————————————————————
ご氏名:
ご所属:
ご連絡先:
—————————————————————
#65 Happiness and Travel Mode Switching: Comparison of Findings from two Public Transportation Experiments 「幸福度と交通手段変容の関連性」
Date
2012年6月20日
Venue
京都大学・吉田キャンパス工学部3号館2階 北棟N5講義室
Happiness and Travel Mode Switching: Comparison of Findings from two Public Transportation Experiments 「幸福度と交通手段変容の関連性」
The 7th International Seminar of Committee of Infrastructure Planning and Management, JSCE in FY2012
2012年度土木計画学研究委員会 第7回国際セミナー(通算 第65回国際セミナー)
日時 平成24年6月20日(水) 16時00分~
場所 京都大学吉田キャンパス 工学部3号館2階 北棟 N5講義室
講師:Maya Abou-Zeid 氏 (American University of Beirut 講師,MIT-ITSプログラム研究員)
講演タイトル:Happiness and Travel Mode Switching: Comparison of Findings from two Public Transportation Experiments
(幸福度と交通手段変容の関連性)
講演概要:
通勤交通を対象に,交通手段の変容と幸福度の関連性の実証分析をスイスとMITをフィールドに実施.
公共交通での通勤の試行に参加した自動車通勤者対象者に無料の公共交通利用券を渡し,その通勤の満足度、交通手段選択行動、行動意図、認識、態度について,前後で調査により確認した.
スイス,MITの事例とも,交通手段利用前後で幸福度の違いが確認された.
その後,MITでの対象者の約3分の1は、職場の駐車許可を返納した.
講演では,満足度に与える行動メカニズムを解説するとともに,スイスとMITの実証結果の相違について,参加者の特性、心理的な要因等から比較考察する.
また,無料の公共交通機関利用券を用いた交通手段変容促進方策や交通政策制度論についても述べる.
参加申し込み:
メールにて以下にご連絡ください。
京都大学大学院工学研究科
都市社会工学専攻 交通マネジメント工学講座 交通行動システム分野 神田 佑亮
kanda@trans.kuciv.kyoto-u.ac.jp
#64 Japanese ODA and Contribution to DPWH Infrastructure Development 「フィリピン共和国公共事業道路省インフラ開発における日本政府開発援助の貢献」
Date
2012年6月15日
Venue
国際協力機構(JICA)本部会議室109-110
Japanese ODA and Contribution to DPWH Infrastructure Development 「フィリピン共和国公共事業道路省インフラ開発における日本政府開発援助の貢献」
The 6th International Seminar of Committee of Infrastructure Planning and Management, JSCE in FY2012
2012年度土木計画学研究委員会 第6回国際セミナー(通算 第64回国際セミナー)
フィリピン共和国 エンカルナシオン氏 土木学会国際貢献賞受賞記念セミナー
日時:2012年6月15日(金)15:30 – 17:30
場所:国際協力機構(JICA) 本部会議室109-110
東京都千代田区二番町5-25二番町センタービル
http://www.jica.go.jp/about/structure/organization/hq.html
題目:
フィリピン共和国 公共事業道路省インフラ開発における日本政府開発援助の貢献
Japanese ODA and Contribution to DPWH Infrastructure Development
講師:ティオドロ・トリニダッド・エンカルナシオン氏(Mr.Teodoro Trinidad Encarnacion)
フィリピン共和国公共事業道路省(Department of Public Works & Highways (DPWH))元次官。
DPWH退官後もフィリピン共和国大統領に対するインフラ関連顧問、JICAフィリピン事務所諮問委員等を歴任。
我が国の技術と人材をフィリピンの開発に巧みに活用し、フィリピン共和国と我が国の友好関係の維持・発展に大いに貢献した功績が認められ、公益社団法人土木学会の平成23年度土木学会国際貢献賞を受賞。
概要:
エンカルナシオン氏はフィリピン共和国公共事業道路省(Department of Public Works & Highways (DPWH))の元次官として、JICAがDPWHと実施してきた数々のプロジェクトを総括してきました。
この度、エンカルナシオン氏が公益社団法人土木学会の平成23年度土木学会国際貢献賞を受賞することとなり、この機会を捉え、これまでのJICAとDPWHの協力の歴史・成果等を振り返り、今後の協力の在り方等を検討するための機会として、エンカルナシオン氏を講師にお招きし、セミナーを開催します。
参加申し込み・お問い合わせ先:
独立行政法人 国際協力機構(JICA) 経済基盤開発部
運輸交通・情報通信第二課 西形 康太郎
E-mail: Nishigata.Kohtaro@jica.go.jp
※お申し込み期限:2012年6月8日(金)
※人数に限りがあるため、定員に達し次第、受付を終了させていただく可能性がございますが、是非、広くご参加いただきたくよろしくお願いいたします。
西形康太郎
Nishigata Kotaro
国際協力機構(JICA)経済基盤開発部
運輸交通・情報通信第二課兼計画・調整課
03-5226-8152(直通)
#63 Comparison the airliners' productivity 「航空会社の生産性比較」
Date
2012年6月13日
Venue
東京工業大学大岡山キャンパス石川台4号館地下 B02-05室
Comparison the airliners' productivity 「航空会社の生産性比較」
The 5th International Seminar of Committee of Infrastructure Planning and Management, JSCE in FY2012
2012年度土木計画学研究委員会 第5回国際セミナー(通算 第63回国際セミナー)
第3回東京工業大学TSU (Transport Studies Unit)セミナーhttp://www.transport-titech.jp/
2012年度第1回EASTS-Japanセミナー
日時:2012年6月13日(水) 16:30-18:00
場所:東京工業大学大岡山キャンパス石川台4号館地下B02-05室
http://www.ide.titech.ac.jp/~hanaoka/access.jp.html
題目:”Comparison the airliners’ productivity”
講師:Prof. Seock-Jin Hong(洪 錫普)
Professor of Supply Chain and Transport, Bordeaux Management School, Bordeaux, France Hong教授は,仁川大学物流大学院(韓国)助教授時代に運輸政策研究所の運輸セミナーでご講演をされるなど,わが国の航空関係の研究者にもおなじみの方です.2009年より現職に異動され,欧州を拠点に,航空貨物やサプライ・チェーンの研究に従事されております.
概要:アジアを中心に市場規模が拡大しつつある,国際航空貨物市場を担う航空会社の生産性について,種々の統計や独自のアンケート調査をもとにDEAや統計解析を行い,その相違点について経営形態や地域性の観点から考察を行う.また,同時に,今,世界の航空貨物でおきつつある「変化」について,その概略を紹介し,議論の材料を提供したい.
問い合わせ先:花岡伸也
東京工業大学 大学院理工学研究科 国際開発工学専攻
TEL/FAX 03-5734-3468 hanaoka@ide.titech.ac.jp
第45回土木計画学研究発表会・春大会
Date
2012年6月2日(土)・3日(日)
Venue
京都大学(吉田キャンパス)
第45回土木計画学研究発表会・春大会
土木計画学研究委員会は下記の概要で第45回土木計画学研究発表会(春大会)を開催いたします.
参加申込書( PDF / MS-Word)
<発表プログラムの注意事項>
・今後,若干の修正が入る可能性があります.
・並列セッションにおいて発表者が重複しないように組まれています.ただし,連名者については重複の場合があります.ご承知置きください.
発表の要領
★聴講者用にレジュメ50部をご用意の上,各セッション会場にて配布して下さい.
(1)講演時間
セッションの時間は,すべて90分です.
発表時間等は基本的にオーガナイザーの指示に従ってください.
(2)講演打ち合わせ
セッション開始10分前に各発表会場に集合し,オーガナイザー・司会者および会場担当者とセッションの進め方に関する打ち合わせを行って下さい.
(3)発表時の使用機器について
各発表会場には,液晶プロジェクタとディスプレイケープルを準備します(OHP,スライドは使用できません).なお,ノートPCは各自で持参して下さい. 各発表会場に設置されている液晶プロジェクタヘの接続は,各発表者の責任にて行って下さい.セッションが円滑に進行するようにご準備のご協力をお願い致します.
(4)ポスター併用セッション
プログラム(概略版や詳細版)のセッション名の横に(P)が入っているセッションは,ポスター併用を申し込み時に希望されたセッションです.実際に,ポス ターを併用した発表を行うのか,あるいは,プロジェクターでの発表のみを行うのかなどは,各セッションのオーガナイザーにお問い合わせください.
● 90cm× 180cmのボード1枚に貼れる内容のポスターを発表会場にお持ちください.ボードは基本的に会場の床から壁に立てかけます.枚数やサイズは自由とします が数名が同時に見えるように文字の大きさ等を工夫してください.
● ポスター掲示用のボード(3×6枚:90cm×180cm)は,各セッション会場にいる会場係が用意いたしますので,セッション開始の10分前までに会場係からお受け取りください.
● 発表時間までにボードにポスターを貼り付けておいてください.貼り付けるための場所と文具は会場で用意いたします.
● 発表会場では会場の壁を掲示スペースとして使いますので,そこにボードを立てかける方法で掲示してください.
● セッションが終了しましたら,ボードをセッション会場係に返却ください.ポスターは処分してよろしければ,貼り付けたままで結構です.
#60 Public Transport in the Era of ITS 「ITS時代の公共交通」
Date
2012年5月11日
Venue
A531, Engineering Building, Gifu University (岐阜大学工学部A棟 A531室)
Public Transport in the Era of ITS 「ITS時代の公共交通」
2012年度土木計画学研究委員会 第2回国際セミナー(通算 第60回国際セミナー)
Public Transport in the Era of ITS 「ITS時代の公共交通」
Date: 11th, May, 2012 13:00 – 17:30
Venue: A531, Engineering Building, Gifu University (岐阜大学工学部A棟A531室)
Aims
The challenge of sustainability is facing calls for a shift of the demand for mobility from individual to collective means of transport.
Hence more attractive public transport systems are required, above all in urban contexts.
Since a shortage of funds for public transport is envisaged for the next years, efforts are needed to allocate money in the most effective and efficient way. Transit assignment models describe and predict the patterns of network usage by passengers, which are a fundamental input for transport planning. The models currently used do not take adequately into consideration the effects on transit operations and on passenger behaviour brought about by increasingly advanced and widespread Intelligent Transportation Systems, nor do they exploit to the full the amount of high quality data made available by such new technologies.
This deficiency can delay the realisation of the benefits of enhanced passenger information provision.
Currently the European Union is providing funding to a number of researchers to discuss how these challenges can be addressed. This workshop is aiming to bridge the gap to research conducted in Japan.
We invite interested persons to contribute or participate in this workshop. Contributions that address advances in our understanding of passenger behaviour, passenger flow modelling, processing and use of smart card data or other related topics are welcome.
Tentative list of speakers:
1.Mike Bell : Overview of COST Action TU1004 “Public transport assignment in the era of ITS”
2.Valentina Trozzi : Stop models and dynamic transit assignment
3.Achille Fonzone : A regret / bounded rationality approach for passenger route choice
4.Jan-Dirk Schmoecker : Population uptake of sustainable transport
5.Hiroshi Shimamoto and Fumitaka Kurauchi: Transit behaviour analysis using smartcard data
6.Hironori Kato: Rail demand forecasting on Tokyo Metropolitan area
7.Takahiko Kusakabe and Yasuo Asakura: Estimation of behavioural change of railway passengers using smart card data
8.Daisuke Fukuda and Hideki Yaginuma: A large scale application of a hyperpath based railway route assignment model considering congestion effects to Tokyo Metropolitan Area
9.Daisuke Fukuda and Jiangshan Ma: Hyperpath and route guidance
————————–参加票(5/7締切)————————–
参加者のお名前( )
発表の希望
あり ・ なし (どちらかを残してください.)
発表希望の場合のタイトル(英文)
( )
※希望者多数の場合には,こちらで調整させて頂きます.
Workshop後の懇親会への参加有無
する ・ しない (どちらかを残してください.)
※当日がちょうど鵜飼い開きの日ですので,鵜飼い鑑賞を計画中です.
会費は5,000円程度を予定しています.
送付先::岐阜大学 倉内文孝先生 kurauchi@gifu-u.ac.jp
———————————————————-
#61 Rescue centre location in degradable transport networks 「災害時に寸断される可能性のある交通ネットワークにおける救援センターの配置問題」
Date
2012年5月8日
Venue
京都大学桂キャンパスCクラスター 人融ホール
Rescue centre location in degradable transport networks 「災害時に寸断される可能性のある交通ネットワークにおける救援センターの配置問題」
The 3rd International Seminar of Committee of Infrastructure Planning and Management, JSCE in FY2012
2012年度土木計画学研究委員会 第3回国際セミナー(通算 第61回国際セミナー)
題目:Rescue centre location in degradable transport networks
「災害時に寸断される可能性のある交通ネットワークにおける救援センターの配置問題」
講師:Prof. Michael G H Bell
(Professor of Transport Operations and Director, PORTeC
Department of Civil and Environmental Engineering, Imperial College London)
日時:2012年5月8日 16時~18時
場所:京都大学桂キャンパスCクラスター 人融ホール
概要:Areas which are prone to natural or man-made disasters, such as earth quakes, fires, floods or attacks, are reliant on the residual transport network for the rescue of survivors. Pre-disaster planning requires assumptions about how the transport network may degrade. This paper focuses on the location of rescue centres in earth quake zones and assumes that links in mountainous areas and closer to fault lines will sustain higher levels of damage. Sichuan province is China is chosen to illustrate the problem. To facilitate a cautious approach to rescue centre location, it is assumed that the transport network is subject to attack by node-specific demons with the power to degrade one link leading out of every node. The mixed strategy Nash equilibrium for the non-cooperative zero sum game between rescuers seeking to reach population centres and the node-specific demons defines our interpretation of the worst credible case link damage probabilities, which in turn leads to pessimistic estimates of travel costs from rescue centres to population centres. These costs are used to find the best locations for a limited number of rescue centres where each has an upper limit on the maximum number of households it can cover. The rescue centre location problem is solved initially by a greedy heuristic and then by a relaxation method.
#59 「Advanced Technologies on Transport Network Systems」
Date
2012年4月3日
Venue
東京工業大学・大岡山キャンパス本館 H111
「Advanced Technologies on Transport Network Systems」
2012年度土木計画学研究委員会 第1回国際セミナー(通算 第59回国際セミナー)
「Advanced Technologies on Transport Network Systems」
日時:2012年4月3日(火) 13:00-17:00
場所:東京工業大学・大岡山キャンパス本館 H111
地図:http://www.titech.ac.jp/about/campus/o_map.html?id=03
■プログラム
13:00-14:15 William Lam (The Hong Kong Polytechnic University)
「Intelligent Transport Systems (ITS) in Hong Kong: Recent Development
and Future Applications」
14:15-14:45
Takamasa Iryo (Kobe University)
「Empirical Study on Demand Change of an Urban Expressway Caused by Incidents」
14:45-15:00 Break
15:00-17:00
Chong Wei (Tokyo Institute of Technology)
「A Statistical Approach to Traffic Estimation on Stochastic User Equilibrium Networks」
Ma Jiangshan and Daisuke Fukuda (Tokyo Institute of Technology)
「Hyperpath-Based Route Guidance」
Takahiko Kusakabe (Tokyo Institute of Technology)
「Behavioural Analysis of Smart Card Data」
Yusuke Hara and Eiji Hato(The University of Tokyo)
「Tradable Permit System for Mobility Sharing」
(プログラムの詳細はhttp://www.transport-titech.jp/seminar_visitor/2012/TSU-SV2012-002_Program_Apr_3rd.pdfをご覧下さい.)
■申し込み方法
申込先:「東京工業大学 日下部貴彦 t.kusakabe@plan.cv.titech.ac.jp」まで,下記のフォームをご返信ください.
申し込み締切:3月31日(土)
参加申し込みフォーム:
—————————————————————
ご氏名:
ご所属:
ご連絡先:
—————————————————————
#64 社会・経済リスクの下での社会資本整備の経済効果分析―応用都市経済モデルの適用と課題―
Date
2012年3月1日
Venue
土木学会講堂
社会・経済リスクの下での社会資本整備の経済効果分析―応用都市経済モデルの適用と課題―
土木計画学ワンデーセミナー No.64
『社会・経済リスクの下での社会資本整備の経済効果分析
― 応用都市経済モデルの適用と課題 ―』
■開催趣旨:
これまで,土木計画学と中心に土地利用交通相互作用モデルの名の下,交通整備が都市構造に及ぼす効果を分析する数多くの計量モデルが開発されてきた.なかでも,応用都市経済(CUE)モデルはその理論的基礎をミクロ経済学的な行動理論に依拠するという特徴を持ち,実際の社会資本整備事業の経済評価での適用を通じて実用化が進んできている.CUEモデルと同様に社会資本整備の経済評価への適用事例の多い応用一般均衡モデルと比較すると,CUEモデルはより微視的な地域・都市計画的な観点からの分析に優れ,立地・土地利用変化の分析などの描写に適している.昨今の社会・経済環境の変化に伴い,CUEモデルは,交通整備のみならず,土地利用規制,環境規制,コンパクトシティ施策など様々な政策・施策の評価への適用が期待されている.
本セミナーでは,CUEモデルに関する最近の取り組みを紹介すると共に,その課題と今後の方向性に関する議論を行うことを趣旨としている.
■主催:土木学会土木計画学研究委員会
「社会・経済リスクの下での長期的な社会基盤政策の理論研究小委員会」
■共催: RAEM-Light協議会
■日時:3月1日(木) 10時~17時予定
■場所:土木学会講堂
■定員:80名(定員になり次第締め切らせて頂きます)
■参加費:無料
■プログラム(予定)
10:00~10:05 主旨説明:堤盛人(筑波大学)
10:05~11:40 セッションI:予備的準備
10:05~10:25 「CUEモデルの意義と発展経緯」 堤 盛人(筑波大学)
10:25~11:40 「CUEモデルの構造と適用事例」 山崎 清(価値総研)
11:40~13:00 昼休み
13:00~14:30 セッションⅡ:CUEモデルの課題と展望
13:00~13:30
「CUEモデルの適用におけるデータの扱いについての課題と展望」
堤盛人(筑波大学)
13:30~14:00
「CUEモデルの実用上の課題と展望」 山崎 清(価値総研)
14:00~14:30
「CUEモデルを用いた便益評価の課題と展望」 小池 淳司(神戸大学)
14:30~14:50 休憩
14:50~16:20 セッションⅢ:CUEモデルの新たな展開
(役所・コンサルタント等の実務での現在の取り組みについて
ご紹介いただく予定です。)
16:20~16:50 総括とディスカッション
司会:小池 淳司(神戸大学)
■申込方法
下記の必要事項をご記入の上,2月22日(水)までにメールにてお申し込みください.
定員に達し,お断りさせていただく場合のみ,ご連絡させていただきます.
e-mail:CUE_seminar@fukken.co.jp
(申込内容)
件名:ワンデーセミナー申込(応用都市経済モデル)
氏名:
E-mailアドレス:
電話:
FAX:
勤務先:
所属:
※個人情報保護法に基づき,提供された個人情報は,その目的以外の用途には利用しません.
#56 ISO国際規格アセットマネジメント・セミナー
Date
2012年2月29日
Venue
都市センターホテル 606会議室
ISO国際規格アセットマネジメント・セミナー
2011年度土木計画学研究委員会 第16回国際セミナー
ISO国際規格アセットマネジメント・セミナーのご案内
アセットマネジメントに関する国際規格ISO5500xの策定作業が進められており、2014年2月を目途に発行される予定です。従来より、京都大学経営管理大学院では、ISO5500xの枠組みを踏まえ、アセットマネジメント、マネジメントシステム、ならびに、技術の普及、啓蒙活動等を行ってきました。しかしながら、日本においては、アセットマネジメントの必要性は認識されていても、そのマネジメントシステムに関する理解が不十分であったり、国際規格を如何に活用して組織の経営に反映させるのか、国際規格を如何にビジネスに繋げるのか、といった疑問が投げかけられることも少なくありません。
そこで、当大学院では、ISO/PC251アセットマネジメントの議長を務めている英国のMr. Rhys Daviesならびにアセットモニタリングを専門とするMISTRAS Group Inc.からMr. Phillip T. ColeとMr. Samuel Ternowchekをお招きして、ISO5500xの目的を深く理解するとともに、アセットマネジメントの標準化と、それを取り巻く英国、米国でのビジネス動向についてのセミナーを、下記の通り開催することと致しました。
今後のアセットマネジメントに関わる教育研究、あるいは、ビジネス戦略を検討する一助になると考えますところ、多数の皆さまに是非ご参加頂きたく、ご案内を差し上げます。
記
日 時: 2012年2月29日(水) 13:00pm~17:30pm
場 所: 都市センターホテル 606会議室
〒102-0093 東京都千代田区平河町2-4-1
Tel. 03-3265-8211
(地図http://toshicenter.co.jp/access/index.html参照)
主 催: 京都大学 経営管理大学院
共 催: 土木学会 土木計画学研究委員会
後 援: 一般社団法人 京都ビジネスリサーチセンター(KBRC)
言 語: 日本語/英語(同時通訳付き)
定 員: 100名(定員になり次第申し込みを締め切らせて頂きます)
参加料: 無料
参加登録: 以下の別紙フォームに必要事項を記載の上、uketsuke@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp
までE-Mailでお送り下さい。
別紙フォーム: http://www.jsce.or.jp/committee/ip/events/articles/registration_1116.doc
事務局担当:京都大学経営管理大学院 澤井克紀/豊嶋恵子
(問い合わせ:uketsuke@mail2.adm.kyoto-u.ac.jp, Tel.075-753-3530)
プログラム:
2012年2月29日(水) 13:00pm ~ 17:30pm
都市センターホテル 606会議室
12:30~ 受付開始
13:00~13:10 開催の挨拶
河野広隆
京都大学経営管理大学院教授
ISO/PC251国内審議委員会委員長
13:10~14:25 “We have been Managing our Assets for a long time – why do we need International Standards for Asset Management?”
Mr. Rhys Davies
Chairman of ISO/PC251 Asset Management
Managing Director, Smart Asset Management Solutions Ltd. UK
14:25~15:25 “TBD”
Mr. Phillip T. Cole
Executive Vice President, International Division
MISTRAS Group, UK
15:25~15:45 コーヒーブレイク
15:45~16:45 “On Line Asset Integrity Monitoring with Acoustic Emission Technology “
Mr. Samuel Ternowchek
Vice President, AE Business Development & Support
MISTRAS Group Inc., USA
16:45~17:30 “国際技術標準化戦略について”
小林潔司
京都大学経営管理大学院 院長
17:30 閉会
講師略歴:
Mr. Rhys Davies
Rhys Davies graduated with BEng (Hons) and MEng in Electronic Engineering from University College of North Wales in 1990 and 91. He went on to complete an MBA in 1999 and is a Chartered Engineer. Rhys has developed his career as an asset management specialist in a variety of industries including Aerospace, Defence, Rail, Telecoms,
Utilities and the Oil industry. Rhys’ roles have included systems design, consultancy, operations management and audit.
Rhys is the Chairman of the ISO Committee (PC251) developing formal International Standards for Asset Management. He has been fundamentally involved in the development of PAS 55 and was Vice Chair of the Steering Group for PAS 55:2008.
Rhys is Managing Director and Founder of Smart Asset Management Solutions Limited and has been involved with the Institute of Asset Management (IAM) in a variety of roles over 5 years, notably: IAM Council Member 2008 – 2010; IAM Patrons Representative (for Lloyd’s Register) 2005 – 2010 and various committee roles. Rhys was been a member of the Executive Committee of the Joint IET/IAM Technical Professional Network for Asset Management since January 2011.
Mr. Phillip T. Cole
Phillip Cole is Executive Vice President of Mistras Group, a company specializing in inspection and monitoring solutions, and listed on the New-York stock exchange. He has spent his career in the development and application of non-destructive testing and condition monitoring to process plant and structures in the oil and gas, process, and civil industries, and has published more than fifty papers.
Since 1980 he has primarily been involved in asset inspection and monitoring, using a diverse range of inspection and monitoring methods. He is most associated with the use of acoustic emission to monitor the structural integrity and degradation of assets. Structures monitored include suspension bridge main cables, post-tensioned concrete and steel bridges, offshore structures, and process vessels in the oil, gas, and nuclear industries. The Plant Condition Monitoring Systems division of his company specializes in asset integrity management software for refineries, which combines inspection data management and risk-based inspection methodology based on the American Petroleum Institute codes.
In the civil area university research project partners include the University of Wales, Cardiff, and CICE Loughborough University, researching steel bridge structures and corrosion of reinforcing bar in concrete. The Cardiff work on steel bridge structures was given an engineering excellence award by the Royal Society.
Phillip Cole has been a member of British Institute of NDT, European Working Group for Acoustic Emission since 1980, including a period as secretary, and a member of the codes sub-group, CEN TC 138 WG 7 for the development of European codes in acoustic emission, Technical advisor to ISO TC 135 SC09 HOIS, the prime industry forum for discussing inspection issues and utilizing improved inspection technology for applications in oil and gas.
Mr. Samuel Ternowchek
Sam Ternowchek is Vice President, On Line Asset Integrity Monitoring with the Mistras Group. In this capacity he is responsible for the company’s development of Advance NDT as it applies to On Line Asset Integrity Management. He has extensive experience in Advance NDT techniques especially acoustic emission, having participated as an engineer in the first applications of the technology to quality control at the Western Electric Company during the mid 1970’s. He participated in the start up of Physical Acoustics Corporation in 1978. He has served the company in a wide range of capacities in the intervening years. He has been active in many different Advance NDT applications within the company including guided wave technology and phased array ultrasonics. He is coordinator of the MONPAC(R) User’s Group, secretary of the CARP committee, Mistras’s representative to the AAR Tank Car Committee NDT Task Group. He is also active in API and is chairmen of the NACE Acoustic Emission committee.
He is an ASNT Fellow.
He is a graduate of Penn State University with a degree in Engineering Technology.
In total, Mr. Ternowchek has over thirty-eight (38) years of industry experience in applying Advance NDT and Acoustic Emission technology.
He has written numerous publications and has made presentations at several conferences.
Prof. Kiyoshi Kobayashi
Kiyoshi Kobayashi is Professor of Infrastructure Economics and the Dean of the Graduate School of Management of Kyoto University. He is also Professor of Planning and Management Theory of Graduate School of Engineering, Kyoto University. He is a world renowned researcher in the fields of Urban and Infrastructure Management and Economics and a recipient of several awards including the Distinguished Research Awards by Japan Society of Civil Engineers and registered as a Top 50 City Creator and Urban Expert by the Danish Ministry of Environment.
He experienced the President of the Applied Regional Science Conference and serves on the editorial boards of international journals including the American Society of Civil Engineers, and on the series editor-in-chief of the Journals of Japan Society of Civil Engineers and the Journal of Applied Regional Science.
Currently, he is a member of National Land Development Council of Japan, a committee expert on Transport Policy Council of Japan, and a coalition member of Science Council of Japan. He was an adjunct professor of 10 oversea universities and a visiting fellow of international organizations of OECE, WHO, and World Bank, etc.
He is the author and co-editor of 53 books including “Kobayashi, K.et al.(eds.) Joint Ventures in Construction, Thomas Teleford, 2009 and over 370 academic reviewed papers.
小林潔司氏は、現在、京都大学経営大学院大学院長・インフラ経済学担当教授であり、同時に京都大学大学院工学研究科都市社会工学専攻・計画マネジメント論教授を併任している。同教授は都市マネジメント、インフラマネジメント、インフラ経済学の分野で国際的に著名な研究者であり、土木学会研究業績賞、World TOP 50 City Creatorand Urban Expert (デンマーク環境大臣)を初めとして種々の受賞歴を持っている。
応用地域学会会長、アメリカ土木学会論文集副編集長を初めとした国際論文集の編集委員会委員、土木学会論文集委員長、応用地域学会論文集委員長を歴任。その間,国土交通省国土審議会,交通政策審議会委員,日本学術会議連携会員等に任命されるとともに、海外10大学の客員教授、OECD, WHO, 世界銀行等の客員研究員を経験した。
著書約50冊 (たとえば, Joint Ventures in Construction, Thomas Telford, 2009), 査読学術論文約370編を出版している.
#65 地域公共交通シンポジウムin静岡~多様な視点から「おでかけ」を考えよう~
Date
2012年2月27日
Venue
静岡駅ビル「パルシェ」7階 第1・第2・第3会議室
地域公共交通シンポジウムin静岡~多様な視点から「おでかけ」を考えよう~
土木計画学ワンデーセミナー NO.65
地域公共交通シンポジウムin静岡~多様な視点から「おでかけ」を考えよう~
持続可能な地域をつくりだすために、公共交通の確保維持改善をいかに進めるかは、実務的に重要かつ喫緊の課題であるとともに、学術的にも興味深いものとして、近年、土木計画学分野など様々なアプローチから調査研究が行われてています。
その1つとして、科学研究費補助金プロジェクト「地域公共交通サービス供給が地域住民のQOL向上に与える効果に関する研究」(代表:加藤博和・名古屋大学環境学研究科准教授)では、土木計画学分野の若手研究者が集まり、地域公共交通の社会的必要性とサービス水準の設定、そして費用効率性を高めるための運営・運行方式を選定する方法論を確立することを目的として、3年間研究を進めてきました。
本シンポジウムは、プロジェクトメンバーに加え関連研究者にもご参画をいただき、総括を行うとともに、自治体実務担当者など関係各方面へ研究成果をフィードバックすることを目的として開催いたします。
■日時:平成24年2月27日(月)13:15~16:50(開場:13:00)
■主催:国土交通省中部運輸局企画観光部、静岡運輸支局
土木学会土木計画学研究委員会
■協力:「地域公共交通サービス供給が地域住民のQOL向上に与える効果に関する研究」プロジェクト
(平成21~23年度 科学研究費補助金採択研究課題)
■場所:静岡駅ビル「パルシェ」7階 第1・第2・第3会議室
(静岡県静岡市葵区黒金町49)
※「パルシェ」はJR静岡駅の駅ビルです。
お越しの際は、公共交通機関のご利用をお願いいたします。
■内容:
・基調講演「交通基本法案をめぐる状況について(仮題)」
国土交通省総合政策局公共交通政策部 石井 昌平 参事官
・リレー講義
「交通事業者をとりまく状況」 大分大学 大井 尚司 准教授
「自治体の交通計画について」 岡山大学 橋本 成仁 准教授
「活動機会に着目した地域公共交通計画」
香川高等専門学校 宮崎 耕輔 准教授
「福祉有償運送・STSと交通計画」 大阪大学 猪井 博登 助教
「複数市町村の連携」 名古屋大学 福本雅之 技術補佐員
「住民参画~中国地方の事例」 米子工業高等専門学校 加藤 博和 准教授
「デマンド交通」 首都大学東京 吉田 樹 助教
「地域公共交通の制度活用について」 名古屋大学 加藤 博和 准教授
・パネルディスカッション
聴講者の疑問・質問をテーマに、リレー講義の講師陣が議論を行います。
■定員:120名 先着受付順
■申込方法:参加申込書を以下のホームページからダウンロードの上、所定の様式にてお申し込み下さい。
http://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/tsukuro/info/pdf/23sinpoinsizuoka.pdf
#57 アジアにおける低炭素交通システム実現方策に関する国際ワークショップ
Date
2012年2月24日
Venue
日本大学理工学部駿河台校舎1号館122教室
アジアにおける低炭素交通システム実現方策に関する国際ワークショップ
アジアにおける低炭素交通システム実現方策に関する国際ワークショップのご案内
(兼2011年度第17回土木計画学研究委員会国際セミナー)
環境省環境研究総合推進費戦略的研究開発領域(S-6)のご支援により,表題のワークショップを下記の要領で実施いたします.国内研究グループおよび海外協力メンバーによる成果を発表いたします.皆様の積極的なご参加をお待ちしております.
日時:2012年2月24日(金曜日)13:30-17:00
主催:日本大学大学院理工学研究科社会交通工学専攻 交通研究センター
会場:日本大学理工学部駿河台 校舎1号館1階122教室
東京都千代田区神田駿河台1-8-14
http://www.cst.nihon-u.ac.jp/information/surugadai.html
最寄駅 JR御茶ノ水駅、メトロ千代田線新御茶ノ水駅
言語:英語
参加費:無料
プログラム(予定):
13:30 – 13:50 Opening Session
Prof. Dr. Yoshitsugu Hayashi, Nagoya University
13:50 – 14:00 Development of Future Vision of Low Carbon Society in Khon Kaen
Prof. Dr. Atsushi Fukuda
Director of Transportation Research Center, Nihon University
14:00 – 14:10 Spatial Development and Transport toward Low-Carbon Asia
– a research plan –
Prof. Dr. Takaaki Okuda, Nagoya University
14:10 – 14:20 Optimum speed of container vessels with the reduction of
CO2 emission in maritime transport
Dr. Shinya Hanaoka, Tokyo Institute of Technology
14:20 – 14:40 -Title to be determined-
Dr. Anthony Chin Theng Heng, National University of Singapore, Singapore
14:40 – 15:00 -Title to be determined-
Dr. Viet Hung Khuat, Centre for International Research and Education Cooperation, Vietnam.
15:00 – 15:30 Coffee Break
15:30 – 15:40 Issues on BRT introduction in Developing megacities
-learning from Latin American experiences- Prof. Dr. Fumihiko Nakamura, Yokohama National University
15:40 – 16:00 “Captivity”: the Effects on transport demand forecasting
Dr. Sittha Jaensirisak, Ubon Ratchathani University, Thailand Dr. Paramet Luathep, Prince of Songkla University, Thailand
16:00 – 16:20 -Title to be determined-
Dr. Varameth Vichiensan, Kasetsart University, Thailand
16:20 – 16:40 Impact of CO2 Emission Reductions by Introducing BRT in
Metro Manila
Dr. Alexis Morales Fillone, De La Salle University, Philippines
16:40 – 17:00 Discussion Session
Moderator: Dr. Sittha Jaensirisak, Ubon Ratchathani University, Thailand
問い合わせ先:花岡伸也
東京工業大学 大学院理工学研究科 国際開発工学専攻
TEL/FAX 03-5734-3468 hanaoka@ide.titech.ac.jp
#58 「中国における港湾改革の貨物取扱量に対する影響」
Date
2012年2月22日
Venue
海事センタービル 7階 701・702会議室
「中国における港湾改革の貨物取扱量に対する影響」
2011年度土木計画学研究委員会 第18回国際セミナー
「中国における港湾改革の貨物取扱量に対する影響」
概要:中国では1978年の改革開放以降、地方分権や民営化が港湾政策にも影響を与えてきた。
本講演では、経済改革や港湾立法が港湾貨物取扱量に与えた効果を検討する。
(詳細は下記アブストラクトをご覧ください。)
発表者:Anthony Chin シンガポール国立大学准教授
日時:2012年2月22日(水)15:15-16:45
会場:海事センタービル 7階 701・702会議室
東京都千代田区麹町4-5
http://www.konnokaiji.com/map_tokyo.html
最寄駅:東京メトロ有楽町線麹町駅(2番出口より徒歩1分)
言語:英語
参加費:無料
問い合わせ先:川崎智也(日本海事センター 研究員)
TEL: 03-3263-9421
email: t-kawasaki@jpmac.or.jp
————————————————-
Political events and Ports Reforms: Testing for Structure Break in Chinese Ports Throughput Development
Dong Yang Anthony Chin Shun Chen
Abstract:
Chinese ports has been witnessed a series of international or domestic economics and political events. In addition, after China inaugurated its policy of economic reform and openness at 1978, a succession of reform measures have been introduced to ports in the subsequent thirty years. This range from decentralization, corporatization to privatization in an effort to promote the growing economy and port efficiency. This paper attempts to identify and interpret the impacts on evolution of traffic level of Chinese ports and sets out to identify the relative contributions of economic reform, political events and port legislation through applying structural break.
Findings suggest that foreign trade triggers the Chinese port throughput, especially foreign and coastal throughput. The development of port throughputs in return leads to an increase in domestic retail sales (or domestic demand) while port investment lags behind the rise of port throughput. The development of Chinese ports maritime traffics was affected by multiple shocks. The political, economic events like the Great Leap Forward affected Chinese ports throughput greatly in addition to the level of foreign trade and retail sales. The ports reform policies and infrastructure development did not have an important impact on port throughput but rather events such as China’s accession to WTO. It affirms the role of transport infrastructure as subject to derived demand, enablers and facilitators of trade and economic growth.
#54 シェアードスペースと生活支援交通の将来像
Date
2012年2月8日
Venue
キャンパスポート大阪 ルームD+E
シェアードスペースと生活支援交通の将来像
2011年度土木計画学研究委員会 第14回国際セミナー
「シェアードスペースと生活支援交通の将来像」
概要:
このたび大阪大学大学院工学研究科交通・地域計画学領域では、大阪大学-ロンドン大学合同セミナー「シェアードスペースと生活支援交通の将来像」といたしまして、ロンドン大学Nick Tyler教授、藤山講師、英国障害者交通諮問委員会の委員長Dai Powell氏をお迎えし、セミナーを開催いたします。
Nick Tyler教授はロンドン大学で土木工学を担当され、特にユニバーサルデザインで顕著な実績を残しておられます。歩行者と自動車などの複数の交通モードを分離し通行させるのではなく、同じ道路空間を共有させ、通行させることにより、良好な歩行環境を構成するというシェアードスペースの導入が欧州で進んでおります。今回は欧州で導入が進むシェアードスペースについて、事例やその効用、問題点などをご講演いただきます。
Dai Powell氏はロンドン市ハックニー区でコミュニティトランスポートという会社を運営しておられます。この会社は、バス交通を運営する部門と障害者や高齢者の生活支援交通を提供する部門からなり、バス交通の利益により、非採算である障害者や高齢者の生活支援交通を提供する社会的企業(ソーシャルエンタープライズ)を運営しておられます。また、DPTAC(英国障害者交通諮問委員会)の委員長もしておられ、障害者交通をどのように実現していくかに精通しておられます。本セミナーでは、障害者・高齢者の移動を促進する仕組みとして、ハックニーコミュニティトランスポートとDPTACについてご講演いただきます。
また、事前に、生活支援交通に関わる日英の専門家と近畿で障害者の交通に取り組んでおられ関西STS連絡会の方々とワークショップを開催し、我が国における生活支援交通をどのように拡大していくかについて議論を行います。この成果についてもセミナーでご報告し、皆様と討議をしたいと考えております。
日時:2012年2月8日(水)13:30~
場所:キャンパスポート大阪 ルームD+E
大阪市北区梅田1-2-2-400 大阪駅前第2ビル4階
http://www.consortium-osaka.gr.jp/about/access.html
プログラム:
13:30-13:35 開会挨拶:新田保次(大阪大学教授)
13:35-14:35 講演:Nick Tyler教授(University College of London ロンドン大学教授)
仮題:シェアードスペースとユニバーサルデザイン
14:35-14:45 質疑応答
14:45-14:55 休憩
14:55-15:55 講演:Dai Powell氏(英国障害者交通諮問委員会(DPTAC))
仮題:障害者・高齢者の移動を促進する仕組み DPTAC(英国障
害者交通諮問委員会)の取り組みとソーシャルエンタープライズについて
15:55-16:05 質疑応答
16:05-16:20 ワークショップ報告:秋山哲男(北星学園大学客員教授)
仮題:日本の生活支援交通の将来
16:20-16:40 討議
16:40-16:50 まとめ
定員:80名 (定員になり次第締め切らせていただきます)
参加費:無料
お申し込み、お問い合わせ:
資料の準備などの関係から、ご出席いただけます場合は、2月3日(金)までに、お名前、ご所属を下記へご連絡ください。
大阪大学大学院工学研究科地球総合工学専攻交通システム学研究室
猪井博登(助教)
TEL:06-6879-7610、7610 FAX:06-6879-7612
e-mail: application@civil.eng.osaka-u.ac.jp
#53 道路交通時間価値に関する国際セミナー
Date
2012年2月7日
Venue
東京大学山上会館大会議室
道路交通時間価値に関する国際セミナー
2011年度土木計画学研究委員会 第13回国際セミナー
「道路交通時間価値に関する国際セミナー」
日時:2012年2月7日(火) 13:00~16:30(12:30開場)
場所:東京大学山上会館大会議室 http://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/cam01_00_02_j.html
概要:
道路交通時間会研究会(代表:加藤浩徳(東京大学))は,国土交通省道路局の「道路政策の質の向上に資する技術研究開発」(新道路技術会議)の支援を受けて,2009年度より3カ年にわたり道路交通時間価値に関する研究をしてまいりました.この度,その成果を報告するとともに,リーズ大学よりMark Wardman教授をお招きして,欧州の交通時間価値研究の動向について講演をしていただきます.
交通時間価値に関心のある研究者のみならず,広く交通計画,交通政策に関心のある実務者や学生にも有益なセミナーです.本セミナーの詳細は,以下の通りです.ご関心のある方は,是非ともお誘い合わせの上,本セミナーへご参加願います.
スケジュール:
13:00 開会
13:05-14:05 Mark Wardman教授(Leeds大学)講演
「欧州の時間価値と交通サービス属性に関するメタ分析」
14:05-14:30 質疑応答
14:30-14:45 休憩
14:45-15:45 我が国の道路交通時間価値に関する研究報告
「我が国の道路交通の時間価値に関する調査報告」(加藤浩徳)
15:45-16:05 コメンテーターよりコメント
・Jan-Dirk Schmoecker准教授(京都大学)
・三古展弘准教授(神戸大学)
16:05-16:30 質疑応答
16:30 閉会
参加費:無料
言語:和英同時通訳がつきます.
申込先:参加登録・問い合わせ等:東京大学・加藤浩徳(kato@civil.t.u-tokyo.ac.jp)まで早めに連絡をお願いいたします.
#55 ヒューマニタリアンロジスティクスと非常時マネジメントに関するシンポジウム
Date
2012年2月1日
Venue
京都大学桂キャンパスCクラスター 人融ホール
ヒューマニタリアンロジスティクスと非常時マネジメントに関するシンポジウム
2011年度土木計画学研究委員会 第15回国際セミナー
ヒューマニタリアンロジスティクスと非常時マネジメントに関するシンポジウム
2011東日本大震災と津波-災害マネジメント,復旧,復興を改善するためのチャレンジと機会
日時:2012年2月1日 14時~17時半
場所:京都大学桂キャンパスCクラスター 人融ホール
主催:(独)科学技術振興機構
共催:京都大学GCOE「アジア・メガシティの人間安全保障工学拠点」
プログラム:
14:00 開会挨拶 谷口栄一教授(京都大学)
14:10 Recovery and Reconstruction: Options and cases from global best practices Dr. Sanjaya Bhatia(国際復興支援プラットホーム)
15:10 Post-disaster Humanitarian Logistics Operations after the 2011 Great East Japan Earthquake Frederico Ferreira研究員(京都大学)
15:50 Debris Collection Operation After Disasters Andie Pramudita
博士後期課程学生(京都大学)
16:20 Challenges for Humanitarian Logistics in Brazil and Sao Paulo
Hugo Yoshizaki准教授(サンパウロ大学)
17:20 閉会挨拶 谷口栄一教授
概要:In the awake of the 2011 Great East Japan Earthquake and Tsunami, academics and practitioners are faced with challenges never before experienced in the field of disasters management. The highly complex environment surrounding the response to the humanitarian crises in the Tohoku Region in Japan and the need to carefully re-design current building and urban planning practices indicate that an integrated perspective is paramount in order to reduce the risks in future disaster events.
In this backdrop, this symposium intends to bring an opportunity for multidisciplinary researchers to discuss and exchange ideas on:
・Risk Management strategies in the context of natural hazards;
・Emergency Management response and recovery;
・Reconstruction after natural disasters;
・Debris management after disasters; and
・Modeling techniques applied for disaster mitigation.
Overall, the event envisages to allow the proposal of innovative academic approaches yet readily applicable into practice due to the urgent need of effective tools for disasters mitigation, response and recovery.
#52 交通CO2排出コミュニケーションと認識の影響(Carbon Aware Travel Choice (CATCH))
Date
2011年12月21日
Venue
京都大学桂キャンパスCクラスター 2F 217室
交通CO2排出コミュニケーションと認識の影響(Carbon Aware Travel Choice (CATCH))
2011年度土木計画学研究委員会 第12回国際セミナー
「交通CO2排出コミュニケーションと認識の影響(Carbon Aware Travel Choice (CATCH))」
講師:Dr. Owen Waygood(University of the West of England)
日時:12月21日(水)16時00分~17時30分
場所:京都大学桂キャンパス Cクラスター 2F 217室
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/access/campus/map6r_k.htm
参加希望の方は,Jan-Dirk Schmoecker准教授までメールでお申し込みください。
schmoecker@trans.kuciv.kyoto-u.ac.jp
詳細は以下のファイルをご覧ください。
http://www.jsce.or.jp/committee/ip/events/articles/CATCH seminar details.pdf
—–
12th International Seminar of Committee of Infrastructure Planning and Management in FY 2011
A seminar on the CATCH project (Carbon Aware Travel Choice (CATCH): Communicating Transport CO2 and Influencing Perceptions)
Spearker: Dr. Owen Waygood (University of the West of England)
Date and Time: Dec 21, 4pm-5.30pm
Venue: Kyoto University, Katsura Campus, C Cluster, 2nd Floor, Room 217
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/access/campus/map6r_k.htm
Contact: Assoc. Prof. Jan-Dirk Schmoecker
schmoecker@trans.kuciv.kyoto-u.ac.jp
See the the following file for detail.
http://www.jsce.or.jp/committee/ip/events/articles/CATCH seminar details.pdf
#63 社会・経済リスクの下での社会資本整備の経済効果分析―応用一般均衡分析の適用と課題―
Date
2011年12月13日
Venue
国土交通省国土技術政策総合研究所 8F会議室
社会・経済リスクの下での社会資本整備の経済効果分析―応用一般均衡分析の適用と課題―
土木計画学ワンデイセミナー シリーズ第63回
社会・経済リスクの下での社会資本整備の経済効果分析
― 応用一般均衡分析の適用と課題 ―
■開催趣旨:
これまで,応用一般均衡モデルは社会資本整備の経済効果分析手法として数多くの研究および実証分析が蓄積されている.一方で,社会・経済環境の変化から,モデルに期待される役割が広がりつつある.そこで,「応用一般均衡モデルの社会資本整備評価への応用」と題し,今日的課題として,セッションI:災害による経済被害計測への応用,セッションII:マクロ計量モデルとDSGEモデル,セッションIII:独占的競争型モデルと完全競争型モデルのテーマに関する最近の取り組みを紹介すると同時に今後の方向性に関する議論を行うことを本研究会の趣旨としている.
■主催:土木学会土木計画学研究委員会
「社会・経済リスクの下での長期的な社会基盤政策の理論研究小委員会
(委員長:小林潔司)」
■共催:国土交通省国土技術政策総合研究所
神戸大学大学院工学研究科市民工学専攻
RAEM-Light協議会
■日時:12月13日(火)13時00分~17時30分
■場所:国土交通省国土技術政策総合研究所 8F会議室
〒305-0804 茨城県つくば市旭1番地 Tel.029-864-2211(代)
http://www.nilim.go.jp/japanese/location/location.htm
■定員:100名(定員になり次第締め切らせて頂きます)
■参加費:無料
~プログラム~
■はじめに:趣旨説明
■SCGEの現状と課題
・小池淳司(神戸大学)
■セッションI:災害による経済的被害計測への応用
・土屋哲(長岡技術科学大学)・多々納裕一(京都大学防災研究所)
「SCGEモデルを用いた災害リスクに対する交通ネットワークの評価」
・今野正雄(日本工営)
「東日本大震災による東北地方における波及被害の分析」
・遠香尚史(三菱UFJリサーチ&コンサルティング)・小池淳司(神戸大学)
「高速道路破断に伴う経済的影響の空間的把握 地域間IO表を用いた短期的影
響分析」
■セッションII:マクロ計量モデルとDSGEモデル
・門間俊幸(国土技術政策総合研究所)・樋野誠一(計量計画研究所)
「流動性の罠を考慮したマクロ計量モデルによる財政政策の効果分析」
・小池淳司(神戸大学)・漆谷敏和(鳥取大学)
「流動性の罠を考慮したDSGEモデルによる財政政策の効果分析」
■セッションIII:独占的競争型モデルと完全競争型モデル
・石倉智樹(首都大学東京)・小池淳司(神戸大学)・佐藤啓輔(復建調査設計)
「経済均衡モデルのモデリング方法の相違による結果の比較分析」
・土谷和之(三菱総合研究所)・大田垣聡(エムアールアイ・アソシエイツ)
「生活圏間SCGEの構築と課題 ―関東地方を事例に―」
■おわりに:総括とディスカッション
・小池淳司(神戸大学)
■お問い合わせ
復建調査設計株式会社 地域経済戦略チーム
佐藤啓輔
TEL:03-5835-2631 FAX:03-5835-2632
e-mail:keisuke.sato@fukken.co.jp
■申込方法
下記の必要事項をご記入の上,12月6日(火)までにメールにてお申し込みください.定員に達し,お断りさせていただく場合のみ,ご連絡させていただきます.
e-mail:SCGE_seminor@fukken.co.jp
(申込内容)
件名:ワンデーセミナー申込
氏名:
E-mailアドレス:
電話:
FAX:
お勤め先:
ご所属:
※個人情報保護法に基づき,提供された個人情報は,その目的以外の用途には利用しません.
#51 京都大学工学研究科低炭素都市圏政策ユニット 第4回国際シンポジウム
Date
2011年12月12日
Venue
芝蘭会館 稲盛ホール
京都大学工学研究科低炭素都市圏政策ユニット 第4回国際シンポジウム
2011年度土木計画学研究委員会 第11回国際セミナー
京都大学工学研究科低炭素都市圏政策ユニット第4回国際シンポジウム
■日時:2011年12月12日(月)13:00~16:15
■場所:芝蘭会館 稲盛ホール(京都市左京区吉田近衛町 京都大学医学部構内)
http://www.med.kyoto-u.ac.jp/siran/kotsu.htm
■参加費:無料
■プログラム:
12:30 受付開始
13:00 開会
13:00~13:10 開会の挨拶
京都大学工学研究科教授(ユニット長) 谷口栄一
13:10~14:30 基調講演1
ロンドン大学教授 Peter Jones氏
Title:Encouraging Sustainable Transport in Urban Areas:
wider approaches to transport planning and street design
※同時通訳いたします(英/日)。
14:30~14:45 休憩
14:45~16:05 基調講演2
中国交通運輸部都市交通研究センター センター長 Yulin Jiang氏
Title:Transportation Development Policy for Low-Carbon City in China
※同時通訳いたします(英/日)。
16:05~16:15 閉会
京都大学工学研究科教授(ユニット政策支援センター長) 中川 大
[申込み方法]
Eメール(sympo2011@upl.kyoto-u.ac.jp)にて、氏名(フリガナ)、所属、連絡先を明記の上、平成23年12月6日(火)までにお申込みください。
事前申込みの先着順となっております。
なお、複数名のお申込みの場合は、それぞれについて明記ください。
[お問い合わせ]
京都大学大学院 工学研究科 低炭素都市圏政策ユニット
e-mail : info@upl.kyoto-u.ac.jp
TEL: 075-231-1255 FAX: 075-231-1255
http://www.upl.kyoto-u.ac.jp/symposium/index.html
第44回土木計画学研究発表会・秋大会
Date
2011年11月25日(金)~27日(日)
Venue
11/25(金)長良川国際会議場 ・11/26(土)~27(日)岐阜大学工学部
第44回土木計画学研究発表会・秋大会
第43回土木計画学研究発表会より講演原稿の書式・形式等が変更になり、土木学会論文集と同様のものとなっております。下記の作成例やサンプルファイルをご利用ください。講演原稿では、英文アブストラクトの記入は任意です。その他書式・形式についての詳細は土木学会論文集の原稿作成の手引き等をご参照ください。
実施期日
2011年11月25日(金)~27日(日)の3日間
実施場所
長良川国際会議場(25日)、岐阜大学工学部(26~27日)
講演用論文
発表会の当日に充実した議論を行うということが、本発表会の特色です。このため、講演の申し込みに際して、「土木計画学への貢献」と「議論したい点」を明記していただきます。話題性、速報性のある論文や、調査・計画、技術検討等の事例報告も歓迎します。提出された講演用論文は、原則として無審査で掲載されますが、会場の制約等によってお断りすることもあります。
なお、ポスターセッションを今年度も実施いたします。口頭発表とポスターでの発表のどちらを希望するかを選んで申込んでいただきます(口頭発表およびポスターでの発表のいずれも、「土木学会論文集D3(土木計画学),Vol.68,No.5(土木計画学研究・論文集29巻)」への投稿対象となります)。本秋大会の一日目は平日であり、会場の都合上、一日目はポスター発表などを主体にする予定です。多くのポスター発表をお待ちしております。
2013年発行予定の「土木学会論文集D3(土木計画学),Vol.69,No.5(土木計画学研究・論文集30巻)」及びそれ以降の巻への投稿には、投稿時点で過去2年以内の土木計画学研究発表会での講演が必要となりますので、あらかじめご了承ください。
問合先
(社)土木学会 研究事業課 田中 章一 E-mail:tanaka@jsce.or.jp
以下の該当する部分を熟読のうえ、手続きを取っていただけますようお願いいたします。
講演の申込み
(1) 申込みの手続きおよび注意点
2011年8月5日(金)17時までの期間内に、土木計画学委員会ホームページを使って、講演申込と講演原稿の投稿を同時に行ってください。原稿のファイル形式はPDF形式のみ受付けます。 原稿は「講演原稿執筆要領」に従ってご執筆ください。 申込んだ論文が正しく転送されているかを確認するための期間を2011年8月8日(月)~8月10日(水)17時に設けています。講演申込み者自身で必ず確認してください。 申込み期間の締切り間際に投稿が集中しますと、予期せぬ事態によりサーバーがダウンし受付ができなくなる恐れがあります。締切り間際の投稿は極力避けていただくようお願いいたします。
なお、原稿の提出がないもの、講演原稿執筆要領に準じていないもの、および期限後に投稿されたものは受理できません。確認期間を過ぎての原稿の差し替え・修正および申し込みの取り下げには応じられません。必ず最終原稿を期間内にWEB上にて投稿してください。
(2) 発表希望分野
申し込みに際して、発表希望分野を下記の5つの発表分野から希望順に2つ選んでください。また、キーワードにつきましては、同キーワード欄の中から最大4つ選んでください。なお、適当なキーワードが見つからない場合は、投稿者の判断によるキーワードを1つだけ加えてください。
発表希望分野
| 発表希望分野 | キーワード |
| A 計画論・計画情報 | 計画基礎論、計画手法論、システム分析、調査論、公共事業評価法、財源・制度論、プロジェクト構想、施工計画・管理、維持管理計画、意識調査分析、計画情報、情報処理、市民参加、GIS、リモートセンシング、測量、環境計画、防災計画、河川・水資源計画、ライフライン計画・設計、地球環境問題 |
| B 地域・都市・景観 | 国土計画、地域計画、都市計画、地区計画、住宅立地、産業立地、人口分布、地価分析、土地利用、市街地整備、再開発、景観、公園・緑地、観光・余暇、空間設計、イメージ分析、土木史 |
| C 交通現象分析 | 発生交通、目的地選択、交通手段選択、経路選択、出発時刻選択、活動分析、時間利用、交通行動調査、交通意識分析、交通行動分析、自動車保有・利用、駐車需要、交通ネットワーク分析、土地利用・交通・環境統合モデル、観光・余暇行動 |
| D 交通基盤計画 | 総合交通計画、地区交通計画、公共交通計画、歩行者・自転車交通計画、道路計画、鉄道計画、空港・港湾計画、ターミナル計画、駐車場計画、物流計画 |
| E 交通運用管理 | 交通流、交通容量、サービス水準、交通制御、交通管理、交通安全、交通情報、交通環境、公共交通運用、交通弱者対策、水上交通、空港管理、交通量計測、TDM、ITS、モビリティマネジメント(MM) |
(3) 発表形式
口頭発表とポスターでの発表のどちらを希望するかを選んでいただきます。なお、会場の都合でご希望に添えない場合もありますので予めご了承下さい。
(4) 投稿料
講演1本につき投稿料(参加費含む)として一般12,000円、学生9,000円を請求いたします。2本以上投稿する方については、2本目以降の投稿料は一般・学生ともに6,000円を請求いたします。振込手数料は各自でご負担願います。
講演原稿執筆要領
講演原稿の書式・形式は、土木学会論文集のものに準じています。下記の作成例やサンプルファイルをご利用ください。講演原稿では、英文アブストラクトの記入は任意です。その他書式・形式についての詳細は土木学会論文集の原稿作成の手引き等をご参照ください。なお、「土木学会論文集D3(土木計画学), Vol.75-6」への投稿の際には英文アブストラクトは必要です。
サンプルファイル 和文(Word2000)/English(Word2000)
原稿作成例 和文(PDF)/English(PDF)
お問合せ先
土木計画学研究委員会大会運営小委員会(春大会担当:橋本,氏原,林)
E-mail:keikaku59@jsce.or.jp
#2 東日本大震災から学び、東海大地震に備える
Date
2011年11月25日
Venue
長良川国際会議場 メインホール「さらさ~ら」
東日本大震災から学び、東海大地震に備える
東日本大震災における我が国の様々な対応状況を分析しつつ、過去からの災害伝承や、中世以降の歴史地震、三大都市圏の形成過程を振り返り、来る東海・東南海・南海地震に備えて、現代社会のあるべき姿について、市民の皆さまとともに考える。
【開催日時】平成23年11月25日(金)9:30~12:00
【会 場】長良川国際会議場 メインホール「さらさ~ら」 参加費無料
【主 催】(社)土木学会(担当:土木計画学研究委員会)
【共 催】岐阜大学
【後 援】国土交通省中部地方整備局、国土交通省中部運輸局、
岐阜県、岐阜市、大垣市、各務原市、中津川市、
高山市、関市、下呂市、岐阜県測量設計業協会、
岐阜県建設コンサルタンツ協会、岐阜社会基盤研究所、
岐阜観光コンベンション協会
【プログラム】
総合司会:高山純一(金沢大学理工研究域教授、土木計画学研究員会学術小委員会委員長)
9:30-9:35 開会挨拶
小林潔司(京都大学経営管理大学院長、土木計画学研究委員会委員長)
9:35-10:35 基調講演「東日本大震災に学ぶ地震対策」
福和伸夫(名古屋大学大学院環境学研究科教授)
10:40-11:55 対談
対談者:福和伸夫(名古屋大学大学院環境学研究科教授)
高木朗義(岐阜大学工学部社会基盤工学科教授)
聞き手:松田曜子(NPO法人レスキューストックヤード事務局長)
11:55-12:00 閉会挨拶
八嶋厚(岐阜大学理事・副学長)
【連絡先】第44回土木計画学研究発表会実行委員会
(岐阜大学工学部社会基盤工学科内)
TEL :058-293-2447 FAX:058-293-2393
E-mail: ip44sympo@gu-rsp.org
【開催場所】〒502-0817 岐阜市長良福光2695-2
長良川国際会議場
TEL:058-296-1200 FAX:058-296-1210
#50 国際シンポジウム「環境共生のまちづくりを考える-福岡アイランドシティを事例として-」
Date
2011年11月15日
Venue
福岡大学 A棟AB01教室
国際シンポジウム「環境共生のまちづくりを考える-福岡アイランドシティを事例として-」
2011年度土木計画学研究委員会 第10回国際セミナー
国際シンポジウム「環境共生のまちづくりを考える-福岡アイランドシティを事例として-」
開催日:2011年11月15日火曜日
時間:18:30~21:00(開場18:00)
会場:福岡大学A棟AB01教室
申込不要・先着順・参加費無料・逐次通訳有り
主催:福岡大学工学部社会デザイン工学科 景観まちづくり研究室
後援:風景デザイン研究会
問い合せ先:福岡大学工学部景観まちづくり研究室(担当:高田彩乃)
〒814-0180 福岡市城南区七隈8-19-1
TEL:092-871-6631(内線6484)
FAX:092-865-6031(共通)
E-mail:td114012@cis.fukuoka-u.ac.jp
プログラム(逐次通訳有):
第1部(18:30~19:30)共同研究ワークショップ
「カリフォルニア大学バークレイ校(SAVE International)・福岡大学によるアイランドシティのまちづくり・野鳥公園のデザイン提案」
第2部(19:45~20:50)パネルディスカッション
「環境共生のまちづくりを考える」
《パネラー》
ランドルフ・T・へスター(カリフォルニア大学バークレイ校 名誉教授)
マーシャ・マクナリー(カリフォルニア大学バークレイ校 特任教授)
出口 敦(東京大学大学院 新領域創成科学研究科 教授)
(進行)柴田 久(福岡大学 工学部社会デザイン工学科 准教授)
趣旨
「環境共生」のあり方が模索される今日、豊かな自然に囲まれたここ福岡の博多湾には、世界的に貴重な野鳥「クロツラヘラサギ」が越冬地として飛来する。現在、博多湾に浮かぶ人工島福岡アイランドシティには野鳥公園の建設も予定されており、同時にアイランドシティの土地利用のあり方として、福岡の活力ある産業活動やまちづくりの方向性が模索されている。この度、米国カリフォルニア大学バークレイ校のメンバーを中心とした環境保護団体 SAVE Internationalと福岡大学景観まちづくり研究室による環境共生に関わる共同研究として、福岡アイランドシティを対象としたまちづくりと野鳥公園のデザイン考案がなされた。本シンポジウムはその成果報告と有識者によるパネルディスカッションを行い、今後の持続可能な環境共生のまちづくりについて考えてみたい。
#48 第3回「東アジアの交通統計に関するワークショップ」
Date
2011年11月15日
Venue
神戸大学深江キャンパス 梅木記念ホール
第3回「東アジアの交通統計に関するワークショップ」
2011年度土木計画学研究委員会 第8回国際セミナー
第3回「東アジアの交通統計に関するワークショップ」
国土形成計画(全国計画)に示されたシームレスアジアの実現に向けて調査研究を進めるうえで、東アジア諸国における交通統計等の整備が喫緊の課題になっています。
このため、2008年3月に第1回、2008年11月に第2回ワークショップを開催し、交通統計データの整備状況について議論した結果、交通統計の標準化、共有化の重要性が認識され、今後とるべき方向性が示されました。
今回は、過去2回のワークショップの議論をさらに深めていくため、東アジア諸国の交通統計の専門家にお集まりいただき、各国の交通統計の現状報告と自由討議を行います。
主催:国土交通省国土政策局
共催:神戸大学大学院海事科学研究科
後援:国土交通省近畿地方整備局,神戸市,EASTS IRG17
日程:2011年11月15日(火)~16日(水)
場所:神戸大学深江キャンパス梅木記念ホール
神戸市東灘区深江南町5丁目1-1
言語:英語(同時通訳はありません)
参加費:無料
プログラム・申込等の詳細は下記リンク先でご確認ください。
http://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/kokudoseisaku_tk1_000005.html
—–
8th International Seminar of Committee of Infrastructure Planning and Management in FY 2011
The Third Workshop on Transport Statistics in East Asian Countries
In order to conduct research works for realization of the concept of the Seamless Asia, which is stated in “The New National Land Sustainability Plan (National Plan)”, improvement of statistics of traffic and transportation is the major issue.
The first and the second workshops on transport statistics in East Asian counties were held in March and November 2008 and current data issues of traffic and transportation statistics were discussed. In the workshop, importance of commoditization and standardization of traffic and transportation statistics was identified, and the course of action to be taken was proposed.
This time, the presentation of country reports and free discussion for desirable transportation statistics will be organized, with experts of transport statistics from East Asian countries, in order to deepen discussions in the first and the second workshops.
Date & Venue:
15th and 16th November, 2011
Kobe University at FUKAE; UMEKI Memorial Hall
5-1-1 Fukae Minamicho, Higashi Nada-ku, Kobe City, Hyogo Prefecture
Language: English
Admission Fee: The admission to the workshop is free of charge.
See the following webpage for detail:
http://www.mlit.go.jp/en/kokudoseisaku/kokudoseisaku_fr1_000001.html
#49 国際交流公開講座「再考 コミュニティ・デザイン」
Date
2011年11月11日
Venue
福岡大学 A棟AB01教室
国際交流公開講座「再考 コミュニティ・デザイン」
2011年度土木計画学研究委員会 第9回国際セミナー
国際交流公開講座「再考 コミュニティ・デザイン」
日時:2011年11月11日(金)18:00~20:30(17:30受け付け開始)
会場:福岡大学A棟AB01教室
参加費:無料(申込み不要・先着順)
主催:福岡大学工学部景観まちづくり研究室
後援:風景デザイン研究会
開催趣旨
今日、コミュニティ・デザインに対する注目が集まっている。甚大な被害をもたらした東日本大震災、人口減少に悩む地方小都市、希薄化する地域共同体など、我が国において、これまで以上に人々のつながりを重視したまちづくりや公共空間の形成が求められている。
本公開講座では、アメリカにおけるコミュニティ・デザインの先駆者であるランドルフ・T・へスター、マーシャ・マクナリー両氏、さらに同じく日本の先駆者である土肥真人氏を迎え、コミュニティ・デザインの可能性を再考し、我が国の進むべきまちづくりの方向性を展望する。
プログラム(逐次通訳有):
18:00 開会挨拶・主旨説明
柴田 久(福岡大学准教授)
18:10 基調講演1「米国でのコミュニティ・デザインの実践」
ランドルフ・T・へスター(カリフォルニア大学バークレイ校名誉教授)
マーシャ・マクナリー(カリフォルニア大学バークレイ校特任教授)
18:50 基調講演2「我が国におけるコミュニティデザインの行方」
土肥真人(東京工業大学准教授)
19:10 休憩
19:20 パネルディスカッション
パネラー:ランドルフ・T・へスター、マーシャ・マクナリー
土肥真人
コーディネーター: 柴田 久
問合せ先:福岡大学工学部社会デザイン工学科景観まちづくり研究室
柴田 久 担当:石橋悠 (092-871-6631内線6484/hisashi@fukuoka-u.ac.jp)
#47 Andre Dantas先生 講演会
Date
2011年10月6日
Venue
京都大学桂キャンパスCクラスター 人融ホール
Andre Dantas先生 講演会
2011年度土木計画学研究委員会 第7回国際セミナー
7th International Seminar of Committee of Infrastructure Planning and Management in FY 2011
日時:2011年10月6日(木)16:00-17:30
会場:京都大学 桂キャンパス C Cluster, Jin-Yu Hall (Room 311)
講演者:Dr. Andre Dantas (National Association of Urban Transport Companies)
Presentation outline:
Dr. Andre Dantas will present the most recent initiatives on the implementation of Bus Rapid Transit (BRT) systems in Brazil. He will discuss the details of how 12 Brazilian cities are geared towards planning, managing and operating high quality public transport services.
In specific, the presentation will show the overall context of each study area and how BRT will be incorporated as part of the existing system. Also, details of the basic, executive and operation plans will be described. Dr. Dantas’ presentation is part of the National Association of Urban Transport Companies’ (NTU) initiatives to encourage the development of efficient and equitable public transport systems in Brazil.
Dr. Andre Dantas’ BIO:
Dr. Dantas is an internationally recognized professional working in strategic planning and related areas who has has acted as an expert consultant around the world. In these projects, Dr. Dantas has provided advisory services to a large variety of infrastructure-related clients.
The Urban Transportation Network Reliability Assessment Techniques in Beijing, China and the Port of Brisbane Motorway upgrade, Australia are examples of major projects in which Dr. Dantas used his modeling, economics, planning and logistics background. MWH Australia also used Andre’s services in business and service development activities. Taking advantage of his fluency in Portuguese, English, Spanish and Japanese. During his tenure at the University of Canterbury, Dr. Dantas participated in a series of applied research projects such as logistics of postal services, energy constrained transport systems and airport cities. Dr. Dantas returned to Brazil in 2010, where he has been involved in a consultancy project about the cost of rural school transport. Since 2011, Dr. Dantas is working at the National Association of Urban Transport Companies, where he leads a technical team providing assistance to over 600 bus operators throughout Brazil.
#46 Rodney Smith准教授 特別講演会
Date
2011年10月3日
Venue
京都大学 吉田キャンパス 総合研究2号館 3F ケーススタディ演習室
Rodney Smith准教授 特別講演会
2011年度土木計画学研究委員会 第6回国際セミナー
6th International Seminar of Committee of Infrastructure Planning and Management in FY 2011
日時:2011年10月3日(月)13:00-15:00
場所:京都大学 吉田キャンパス 総合研究2号館 3F ケーススタディ演習室
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/access/campus/map6r_y.htm
講演者:Rodney Smith氏(アメリカ・ミネソタ大学応用経済学部 准教授)
タイトル: “On the Flow and Stock Values of non-Market Natural Resources:
Theory and Practical Considerations”
概要:
A recent UNEP report (TEEB) concluded the current set of valuation tools is ill-equipped to measure the value of ecosystem services in macroeconomic settings. This project uses water resources in Japan to illustrate the hurdles one encounters when trying to measure the economic value of a natural asset as pervasive as water, and the steps one can take to overcome them. In telling this story, I lay out a dynamic, general equilibrium model of economic growth. With this model,
I discuss how we typically link IO data to the model, and point out (non-market) water has no role in such a framework. I suggest (a possibly obvious) remedy to this problem, and present simulation results based on 2005 Japanese IO data. I then discuss how we use the results to calculate the stock values of water over time. I conclude with a brief discussion of extending the model to accommodate ecosystem services – where an ecosystem is described by one or more dynamic stock variables.
申込み:不要
主催:京都大学経営管理大学院
共催:土木計画学研究委員会
#45 Roger Vickerman教授 講演会
Date
2011年10月3日
Venue
日本大学理工学部駿河台校舎1号館 4階141教室
Roger Vickerman教授 講演会
2011年度第4回EASTS-Japanセミナー
兼2011年度第5回土木計画学研究委員会国際セミナー
兼計画交通研究会セミナー
日時:2011年10月3日(月曜日)18:00-19:30
講師:Roger Vickerman教授
Dean of the University of Kent at Brussels
Professor of European Economics
講演テーマ:
Wider economic impacts of transport investments: issues for appraisal
講演概要:
This seminar will include an assessment of current UK practice and its use in major rail projects such as Crossrail in London and High-speed rail from North England to Scottland.
Crossrail:ロンドンを東西に横断する予定のheavy rail計画
High-speed rail:完成しているSt. PancrasからEuro Star規格の高速鉄道を北イングランド–>スコットランドへと延ばす計画
会場:日本大学理工学部駿河台校舎1号館4階141教室
東京都千代田区神田駿河台1-8-14
http://www.cst.nihon-u.ac.jp/information/surugadai.html
最寄駅 JR御茶ノ水駅、メトロ千代田線新御茶ノ水駅
参加費:無料
申込先:花岡伸也
東京工業大学 大学院理工学研究科 国際開発工学専攻
TEL/FAX 03-5734-3468 hanaoka@ide.titech.ac.jp
#44 Seminar on Transportation and Logistics for Human Security in Asian Cities
Date
2011年9月16日
Venue
京都大学桂キャンパスCクラスター 人融ホール
Seminar on Transportation and Logistics for Human Security in Asian Cities
2011年度土木計画学研究委員会第4回国際セミナー
4th International Seminar of Committee of Infrastructure Planning and Management in FY 2011
Title: “Seminar on Transportation and Logistics for Human Security in Asian Cities:
Perspective Towards Safer and Sustainable Transport Logistics”
Date: September 16, 2011 (14:00 – 17:00)
Venue: Jin-Yu Hall, C Cluster, Katsura Campus, Kyoto University
Outline: Transportation and logistics are keys to development, but are also responsible for a range of negative impacts such as the road accidents, traffic congestion and environmental degradation. Obtaining safe, secure and sustainable transportation is an immense challenge, and transport planners and managers are working hard on several policies to achieve it. For Asian cities, things have become more and more challenging due to recent unwarranted rise of traffic in all the three modes (Road, Water and Air) of transportation in these cities.
Scientific research studies can come up with innovative yet realistic approaches to deal with the challenges. But, it is also equally important to encourage public and private partnership to translate the research to field implementation.
This seminar aims at presenting
1. Scientific ideas to foster the safety, security and sustainability of the transportation and logistics schemes especially in concern to Asian cities.
2. Approaches to obtain public acceptability for implementation of such innovative ideas.
The overall objective is to create a platform for discussion among researchers in the field to exchange their knowledge, ideas and experiences that may direct towards further effective tools.
The seminar is an open seminar and all the related personnel are requested to participate.
Speakers:
Prof. Kunnawee Kanitpong (Asian Institute of Technology)
Dr. Frederico Ferreira (Kyoto University)
Dr. Rojee Pradhananga (Kyoto University)
Mr. Joel Sze Ern Teo (Kyoto University)
Ms. Batari Saraswati (Tokyo Institute of Technology)
For details contact:
Dr. Rojee Pradhananga
C1-3-182 Kyoto-daigaku Katsura, Nishikyo-ku, Kyoto 615-8540, Japan
Tel: +81-75-383-3415
Fax: +81-75-950-3800
Email:rojee@kiban.kuciv.kyoto-u.ac.jp
Reference:
http://www.jsce.or.jp/committee/ip/events/articles/invitation_is1104.pdf
#2 リスク評価に基づく道路ネットワークの耐震設計法を目指して(2011年・年次学術講演会)
Date
2011年9月7日
Venue
愛媛大学 共通教育講義棟 講21
リスク評価に基づく道路ネットワークの耐震設計法を目指して
平成23年度土木学会全国大会 研究討論会 <愛媛大学>
題目:リスク評価に基づく道路ネットワークの耐震設計法を目指して
(土木計画学委員会・地震工学委員会)
土木計画学委員会と地震工学委員会の合同設置の共同研究小委員会「リスク評価に基づく道路構造物・道路ネットワークの耐震設計研究小委員会」では、道路ネットワークの各リンクの耐震性能の設計と、リンクの要求性能を所与とした場合の個別道路構造物の耐震設計とからなる2段階の耐震設計法の体系の確立が必要であるとの認識のもとで、共同研究を進めてきた。本討論会では、リスク評価に基づいて道路ネットワークの耐震設計法を構成する際の主要な論点を整理するとともに、道路構造物および道路ネットワークの新しい耐震設計法の確立を目指して、総合的な議論を行うこととする。
座長
多々納裕一 京都大学防災研究所
澤田 純男 京都大学防災研究所
話題提供者(予定)
澤田 純男 京都大学防災研究所
中村 晋 日本大学
酒井 久和 広島工業大学
奥村 誠 東北大学東北アジア研究センター
朝倉 康夫 東京工業大学大学院工学研究科
日時:平成23年9月7日(水) 16:15-18:15
会場:共通教育講義棟 講21
#43 ヘンリック・グッドムンドソン先生(デンマーク工科大学)
Date
2011年7月7日
Venue
東京工業大学工学部創造プロジェクト館[緑が丘5号館]1F会議室
ヘンリック・グッドムンドソン先生(デンマーク工科大学)
平成23年度第3回土木計画学国際セミナー
平成23年度第2回EASTS国際セミナー
「交通における持続可能性の指標と業績測定」
ヘンリック・グッドムンドソン先生(デンマーク工科大学)
日時:2011年7月7日(木曜日) 15:00-18:30
場所:東京工業大学工学部(大岡山キャンパス)
創造プロジェクト館[緑が丘5号館]1F会議室
http://www.titech.ac.jp/about/campus/o_map.html?id=02
東急大井町線緑が丘駅徒歩8分
東急大井町線/目黒線大岡山駅徒歩15分
————————————————————————
“Indicators and performance measures of sustainability in transportation”
Sustainability has become an overarching concern for transportation policy and planning around the world. The notion of sustainability for transportation however remains poorly specified which allows many policies and practices to be identified as ‘sustainable’ whilst business as usual approaches are pursued. There is a strong need to make the notion operational for application in transportation and related fields.
The lecture will focus on the use of indicators and performance measures as key tools to make sustainability operational within the field of transportation planning and management. An indicator can be defined as a variable, or a combination of variables, being selected to represent a certain wider phenomenon or problem of interest, to support observation, communication, or intervention.
A performance measure is an indicator that is connected to organizational objectives, goals, targets, and/or practices.
The lecture will:
*Introduce the topic of sustainability in general, and in transportation (concept of present and future needs, the three dimensions, the impacts that transport has on sustainability, key principles and goals, challenges involved in defining sustainability for a subsystem such as transport)
*Introduce and define various types of indicators and performance measures, and their functions and roles for different transport planning, management and decision making applications. (definitions, types of criteria for good indicators, applications of indicators)
The lecture will shift between PowerPoint presentation, small group work sessions, and interactive plenary sessions, where results of group discussions are reported and discussed. Total duration would be around 3,5 hours.
Tentatively, the schedule could be:
*One hour lecture on the first topic, followed by 20 minutes of group discussions and 20 minutes of interactive feedback, with breaks in between, as appropriate
*One hour lecture on the second topic, followed by 20 minutes of group
discussions and 20 minutes of interactive feedback, with breaks in between as appropriate
The emphasis will be on introducing concepts and typologies; no mathematics or calculation exercises will be involved. The lecture will be based on draft chapters of a textbook currently in preparation called “Sustainability in Transportation: Making it Count”. The book is scheduled to be completed in 2012, and published by Springer.
It is intended as teaching material for transportation classes at higher education
institutions, as well as for practitioners in transport planning around the world.
The lecture could provide valuable feed-back to improve the drafting of the textbook.
Lecture Schedule:
15:00-16:00 (1) Lecture on the topic of sustainability in general, and in transportation
16:00-16:20 (1) Group Discussion
16:20-16:40 (1) Interactive Feedback
(Short break)
16:50-17:50 (2) Lecture on indicators and performance measures, and their functions and roles for different transport planning, management and decision making applications
17:50-18:10 (2) Group Discussion
18:10-18:30 (2) Interactive Feedback
18:30 Concluding Remarks
#42 ヘンリック・グッドムンドソン先生(デンマーク工科大学)
Date
2011年6月9日
Venue
東京理科大学理工学部講義棟K310
ヘンリック・グッドムンドソン先生(デンマーク工科大学)
平成23年度第2回土木計画学国際セミナー
平成23年度第1回EASTS国際セミナー
「持続可能な交通計画のための業績評価指標」
ヘンリック・グッドムンドソン先生(デンマーク工科大学)
日時:2011年6月9日(木曜日) 15:00-17:00
場所:東京理科大学理工学部(野田キャンパス)
講義棟K310
http://www.tus.ac.jp/info/access/nodcamp.html
————————
“The Use of Indicators for Sustainable Transport Planning”
by Dr. Henrik Gudmundsson
(Senior Researcher, Department of Transport, Technical University of Denmark)
[topics of lecture]
– Principles of sustainability for transport policy and planning
– Concept and examples of indicators and performance measures
– The assessment and use of appropriate indicators in transport planning and policy making
The lecture will be based on recent and ongoing research work in two European research projects. “COST Action 356, Indicators of environmental sustainability in transport: An interdisciplinary approach to methods” (http://cost356.inrets.fr), and ” POINT – The Policy Influence of Indicators”
(http://bayswaterinst.squarespace.com/), as well as one project in the US: “NCHRP 08-74, Sustainability Performance Measures for State DOTs and Other Transportation Agencies”.
————————————————————————
講義は英語で行われますが,適宜日本語解説を交えながらゆっくり進める予定です.
また,7/7にも東京工業大学にて同様のセミナーがありますので,ご都合の付かない場合には,そちらにご参加頂くのも良いかと存じます.
内容は一部重複しますが同一ではないため,別の回のセミナーとして企画しています.
————————————————————————
第43回土木計画学研究発表会・春大会
Date
2011年5月28日(土)~29日(日)
Venue
筑波大学 第三エリア(つくば市)
第43回土木計画学研究発表会・春大会
土木計画学研究委員会は下記の概要で第43回土木計画学研究発表会(春大会)を開催いたします。
<発表プログラムの注意事項>
・今後,若干の修正が入る可能性があります.
・並列セッションにおいて発表者が重複しないように組まれています.ただし,連名者については重複の場合があります.ご承知置きください.
・SSの発表者で論文投稿される方へ! 論文投稿方法が企画セッションとは違います.pdfで作成された論文を計画学委員会(keikaku43@jsce.or.jp) および秋田活版の大和田様(katsuki@kappan.co.jp)までメールに添付してお送りください.その際に,発表されるSSのセッション番号とセッション名を示してください.
発表の要領
★聴講者用にレジュメ50部をご用意の上,各セッション会場にて配布して下さい.
(1)講演時間
セッションの時間は,すべて90分です.
発表時間等は基本的にオーガナイザーの指示に従ってください.
(2)講演打ち合わせ
セッション開始10分前に各発表会場に集合し,オーガナイザー・司会者および会場担当者とセッションの進め方に関する打ち合わせを行って下さい.
(3)発表時の使用機器について
各発表会場には,液晶プロジェクタとディスプレイケープルを準備します(OHP,スライドは使用できません).なお,ノートPCは各自で持参して下さい. 各発表会場に設置されている液晶プロジェクタヘの接続は,各発表者の責任にて行って下さい.セッションが円滑に進行するようにご準備のご協力をお願い致します.
(4)ポスター併用セッション
プログラム(概略版や詳細版)のセッション名の横に(P)が入っているセッションは,ポスター併用を申し込み時に希望されたセッションです.実際に,ポスターを併用した発表を行うのか?プロジェクターでの発表のみを行うのかなどは,各セッションのオーガナイザーにお問い合わせください.
● 90cm× 180cmのボード1枚に貼れる内容のポスターを発表会場にお持ちください.ボードは基本的に会場の床から壁に立てかけます.枚数やサイズは自由としますが数名が同時に見えるように文字の大きさ等を工夫してください.
● ポスター掲示用のボード(3×6枚:90cm×180cm)は,各セッション会場にいる会場係が用意いたしますので,セッション開始の10分前までに,会場係からお受け取りください.
● 発表時間までに,ボードにポスターを貼り付けておいてください.貼り付けるための場所と文具は会場で用意いたします.
● 発表会場では,会場の壁を掲示スペースとして使いますので,そこにボードを立てかける方法で掲示してください.
● セッションが終了しましたらボードをセッション会場係に返却ください。ポスターは処分してよろしければ,貼り付けたままで結構です.
#41 Jose Holguin-Veras先生 特別講演会
Date
2011年5月23日
Venue
京都大学桂キャンパスCクラスター 314号室
Jose Holguin-Veras先生 特別講演会
2011年度土木計画学研究委員会第1回国際セミナー
Jose Holguin-Veras先生 特別講演会
日時:2011年5月23日 10時~12時
場所:京都大学桂キャンパスCクラスター 314号室
題目:WHAT PREVIOUS DISASTERS TEACH US: THE HARD LESSONS OF KATRINA
AND HAITI FOR POST-DISATER HUMANITARIAN LOGISTICS
講師:Jose Holguin-Veras 教授
Abstract
Extreme events pose serious logistical challenges to emergency and aid organizations active in preparation, response and recovery operations, as the disturbances they bring about have the potential to suddenly turn normal conditions into chaos. Under these conditions, delivering the critical supplies (e.g., food, water, medical supplies) urgently required becomes an extremely difficult task because of the severe damages to the physical and virtual infrastructures and the very limited, or non-existent, transportation capacity. In this context, the recovery process is made more difficult by the prevailing lack of knowledge about the nature and challenges of emergency supply chains. As a result, the design of reliable humanitarian logistic systems is hampered by the lack of: knowledge about the particulars of how formal and informal (emergent) supply chains operate and interact; methods to properly analyze and coordinate the flows of both priority and non-priority goods; and, in general, scientific methods to analyze logistic systems under extreme conditions.
This presentation is based on the quick response field work conducted by the author and his colleagues on New Orleans and Haiti. The presentation provides a succinct description of the key logistical issues that plagued the Katrina response, and then discusses preliminary observations concerning the response to the Port au Prince earthquake. These cases provide an example of the need to significantly improve the efficiency of humanitarian logistics. The paper is based, to a great extent, on public accounts of the event and the interviews conducted by the authors during a number of field visits to the impacted sites, as part of research projects funded by the National Science Foundation. Then, in the second part of the presentation, he will discuss policy implications of relevance to ensure an efficient flow of critical supplies to a site impacted by a natural or a man-made disaster.
This research was supported by the National Science Foundation’s grants entitled NSF-RAPID 1034365: “Field Investigation on the Comparative Performance of Alternative Humanitarian Logistic Structures;” “DRU: Contending with Materiel Convergence: Optimal Control, Coordination, and Delivery of Critical Supplies to the Site of Extreme Events” (National Science Foundation CMMI-0624083); and “Characterization of the Supply Chains in the Aftermath of an Extreme Event: The Gulf Coast Experience,” (NSF-CMS-SGER 0554949).
This support is both acknowledged and appreciated.
#40 リノベーションまちづくり国際セミナー
Date
2011年3月28日
Venue
大阪大学中之島センター2F 講義室1
リノベーションまちづくり国際セミナー
2010年度土木計画学研究委員会第17回国際セミナー
リノベーションまちづくり国際セミナー
~アジアにおける持続可能な交通まちづくり~
地球環境問題の解決は喫緊の課題であり、急速に発展するアジア地域において、持続可能な交通と都市を作り上げることは急務である。そこで、本セミナーにおいては、アジア諸都市における持続可能な交通まちづくりの実態について、計画に関わった実務者の方から報告を行ってもらい、議論を行います。
講師の一人であるLloyd WRIGHT氏は、国際交通計画コンサルタントとして、国連、アメリカ環境保護庁、ドイツ技術援助庁などでの業務として、都市交通と地球環境問題について取り組んできており、非動力系交通やBRT(Bus Rapid Transport)などに深い見識を持っておられます。また、もう一人の講師であるBounta ONNAVONG氏は、大阪大学で地球環境問題と交通に関して研究を行い、博士号を取得の後、母国ラオスに帰国しラオス政府公共事業交通省で地球環境問題と交通について、取り組んでおられ、ASEANの持続可能な交通に関する国際会議など様々な場で活躍をしておられます。このようにアジアの現場で持続可能な交通まちづくりに取り組んでおられるお二方にお越しいただき、深い議論を行いたいと思いますので、奮って、ご参加ください。
■日時:2011年3月28日(月) 13:00~17:00 開場12:30
■場所:大阪大学中之島センター 2F 講義室1
〒530-0005 大阪市北区中之島4-3-53
TEL:06(6444)2100 FAX:06(6444)2338
地図:http://www.onc.osaka-u.ac.jp/others/map/index.php
【電車によるアクセス】
○京阪「中之島駅」6番出口より徒歩5分
○京阪「渡辺橋駅」1番出口より徒歩5分
○阪神本線「福島駅」より徒歩10分
○JR東西線「新福島駅」より徒歩10分
○JR環状線「福島駅」より徒歩12分
○地下鉄四ツ橋線「肥後橋駅」より徒歩10分
定員:50名 (定員になり次第締め切らせていただきます)
日英の通訳がつきます。
参加費:無料
■プログラム
13:00 開場
13:30~13:45 開会挨拶および研究紹介
リノベーションまちづくり研究拠点 代表 新田保次
13:45~14:45 講演1「アジアにおける持続可能な交通の最先端-持続可能な財源を含めて-」
Lloyd WRIGHT氏 Viva Cities事務局長
14:45~14:55 質疑応答
14:55~15:05 休憩
15:05~15:35 講演2 「ラオスにおけるEST(Environmental Sustainable Transport )」
Bounta ONNAVONG氏 ラオス政府公共事業交通省
15:35~15:45 質疑応答
15:45~16:15 講演3 「ベトナムにおける都市・交通の低炭素化の取り組み」
児玉 健氏(日建設計総合研究所)
16:15~16:25 質疑応答
16:25~16:30 閉会挨拶
■申し込み方法
参加申込用紙に必要事項をご記入の上、3月23日(水)までに、FAXまたはメールにてお申し込みください。定員に達し、お断りさせていただく場合のみ、ご連絡させていただきます。
申し込み先:FAX:06-6879-7612、 E-mail:application@civil.eng.osaka-u.ac.jp
大阪大学大学院工学研究科地球総合工学専攻交通システム学研究室 宛て
■主催:大阪大学大学院工学研究科リノベーションまちづくり研究拠点(RITR)
■共催:財団法人災害科学研究所 交通まちづくり学研究会
■後援:大阪大学大学院工学研究科附属サステイナビリティ・デザイン・オンサイト研究センター(SDOC)
#39 Stephanie E. Chang教授 特別講義
Date
2011年3月10日
Venue
京都大学防災研究所大会議室 D1518室
Stephanie E. Chang教授 特別講義
2010年度土木計画学研究委員会第16回国際セミナー
Stephanie E. Chang教授 特別講義
日時: 2011年3月10日(木) 16:00~18:00
会場: 京都大学防災研究所大会議室 D1518室(宇治研究所本館5F)
http://www.uji.kyoto-u.ac.jp/campus/map.pdf
京都大学宇治キャンパスへのアクセスは下記をご覧ください。
http://www.uji.kyoto-u.ac.jp/campus/map.html
講師:
Stephanie E. Chang教授
School of Community and Regional Planning (SCARP)
and Institute for Resources, Environment, and Sustainability (IRES)
University of British Columbia
題目:
Modeling Social Impact of earthquakes
連絡先:
社会防災研究部門 防災社会システム分野(多々納研究室)
TEL 0774-38-4039
#37 Strategy of City Mobility Management with Community Cycle: From London to Japanese Cities
Date
2011年3月3日
Venue
共立女子大学 共立講堂
Strategy of City Mobility Management with Community Cycle: From London to Japanese Cities
2010年度土木計画学研究委員会第14回国際セミナー
「コミュニティ・サイクルによる都市モビリティ・マネジメント戦略:
ロンドンおよび日本の事例にみる新たな自転車共同利用」
“Strategy of City Mobility Management with Community Cycle:
From London to Japanese Cities”
○開催趣旨:欧州で盛んな自転車共同利用事業が国内でも実施されマスコミで報道されるようになったが、共同利用の難しさは、技術面のみでなく、都市計画における行政の関与や、経営を持続させるノウハウにある。このたび、英国ロンドンより初めてバークレイズ・サイクル・ハイアー計画の担当者が訪日することとなったので、その講演会を開催し、併せて自転車を担当する国土交通省や、富山市、名古屋市、札幌市の関係者を招いたパネルディスカッションを東京で開催する。
○日時:3月3日(木)13:00-16:30
○場所:共立女子大学 共立講堂(東京都千代田区一ツ橋2-2-1)
http://www.kyoritsu-wu.ac.jp
(地下鉄東西線竹橋駅または地下鉄半蔵門線・三田線・新宿線神保町駅
から徒歩数分)
○主催:コミュニティバイク研究会(http://community-bike.com/)
○後援:国土交通省、土木学会土木計画学研究委員会自転車空間研究小委員会、
土木学会土木計画学研究委員会交通まちづくりの実践研究小委員会、
PV共同利用MM研究会
○参加費:無料
○定員:300名
○プログラム:(逐次通訳付き)
12:30 開場
13:00-13:05 はじめに
13:05-14:00 基調講演「ロンドンのコミュニティサイクル」
Mr. Alan Stannard
(Operations Director, Serco Civil Government,
Barclays Cycle Hire Scheme)
14:00-14:15 「日本の自転車政策とコミュニティサイクルのレビュー」
菊池雅彦(国土交通省都市・地域整備局)
14:15-15:00 「日本のコミュニティサイクルの事例」
富山:猪爪勇斗(エムシードゥコー株式会社)
札幌:澤充隆(株式会社ドーコン)
名古屋:佐橋友裕(名古屋市緑政土木局)
15:00-15:15 休憩
15:15-16:15 パネルディスカッション「日本の都市におけるコミュニティサイクルの未来」
Mr. Alan Stannard
古倉宗治(㈱住信基礎研究所)
菊池雅彦(国土交通省都市・地域整備局)
猪爪勇斗(エムシードゥコー株式会社)
澤充隆(株式会社ドーコン)
佐橋友裕(名古屋市緑政土木局)
コーディネーター 大森宣暁(東京大学)
16:15-16:25 質疑応答
16:25-16:30 総括
青木英明(共立女子大学、コミュニティバイク研究会代表)
○お申し込み
コミュニティバイク研究会事務局(e-mail: symposium@community-bike.com)宛に、下記事項をご記入の上、2/25(金)までに電子メールでお申し込み下さい。
******************
お名前:
ご所属:
メールアドレス:
******************
#38 Jonathan L. Gifford教授講演会
Date
2011年2月18日
Venue
京都大学 総合研究2号館3階 マルチメディア演習室
Jonathan L. Gifford教授講演会
2010年度土木計画学研究委員会第15回国際セミナー ジョージメイソン大学 Jonathan L. Gifford教授講演会 この度,京都大学大学院工学研究科 低炭素都市圏政策ユニットの活動の一環といたしましてジョージメイソン大学・公共政策学部のJonathan L. Gifford教授(専門:交通政策)をお招きし,下記の通りに講演会を開催いたします. ■ 日 時:23年2月18日(金) 17時30分より ■ 講演者:Jonathan L. Gifford教授 (ジョージメイソン大学・公共政策学部教授,研究担当副学長兼務) ■ 講演題目:”The Financial Crossroads in the U.S. Surface Infrastructure Policy” ■ 講演概要: U.S. surface infrastructure policy is near deadlock. The interstate highway program, and the Highway Trust Fund that provided the federal financing for its construction, is essentially bankrupt, having required $35 billion in the last 2 years to remain solvent. Revenue growth has stalled because of increasing fuel efficiency. State financing is also facing a dim outlook. Thus, public funding for highway system expansion is virtually non-existent. Most existing funding is consumed with maintenance and rehabilitation. The newly elected Republican majority in the U.S. House of Representatives has no interest in raising gas taxes, and indeed seeks to cut spending governmentwide. Private finance has made some promising inroads in the last two decades. But there are substantial barriers to investment — political, financial and institutional. The primary U.S. surface transportation statute expired on September 30, 2009, and has only been extended temporarily, giving states no long-term federal financial commitment to use in planning multi-year construction and improvement programs. Experts and interest groups agree that the traditional program is badly in need of reform to make it more focused on performance, transparency and accountability. Yet doing so with flat or reduced budgets poses enormous challenges. However, difficult challenges also sometimes force consideration of alternatives that would normally be out of the question. Washington is awash in bold proposals for program reform, including streamlining, devolution, and rethinking the locus of responsibility and authority for future highway and transit investment. ■ 会 場:吉田キャンパス 総合研究2号館3階 マルチメディア演習室 (http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/access/campus/map6r_y.htm) ※総合研究2号館は百万遍の門から入って南を向いて左手(旧化学系)の建物です. ※小演習室1は「ロ」の字型の建物の東側にございます. 本件に関するご質問は,塩見(shiomi@trans.kuciv.kyoto-u.ac.jp)までお願いいたします.
#36 Jae H.Lee氏(サムスン石油化学・前CEO)講演会
Date
2011年1月21日
Venue
京都大学吉田キャンパス総合研究2号館 3F ケーススタディ演習室
Jae H.Lee氏(サムスン石油化学・前CEO)講演会
2010年度土木計画学研究委員会第13回国際セミナー
Jae H.Lee氏講演会
■日時:2月3日(木)14:45~16:15(4限)
■場所:京都大学吉田キャンパス総合研究2号館 3F ケーススタディ演習室
http://www.econ.kyoto-u.ac.jp/~wakaba/research/seminar/CSmap.pdf
■講師:Mr.Jae H.Lee
(Former CEO of Samsung-BP Petro-Chemical, and Samsung Venture Capital)
■題目:A comparative view on management of big companies in Korea
Cases of venture business incubation in Korea
(対話形式・日本語可)
#35 An instrumented traffic information platform for human security engineering
Date
2011年1月21日
Venue
京都大学桂キャンパスC1棟314室
An instrumented traffic information platform for human security engineering
2010年度土木計画学研究委員会第12回国際セミナー
12th International JSCE Seminar in fiscal year 2010
“An instrumented traffic information platform for human security engineering”
Speakers: Dr. Russell G. Thompson and Dr. Majid Sarvi, Institute of Transport Studies, Monash University
Date: 21st January 2011
Place: Room 314, C1 building, Katsura Campus, Kyoto University
Time: 14:00 to 16:00
Inquiry: Please contact Dr. Pradhananga Rojee at rojee.p[at]ks3.ecs.kyoto-u.ac.jp
#34 中国内陸部の高速鉄道ネットワークの計画
Date
2010年12月14日
Venue
山梨大学甲府キャンパス 情報メディア館5F多目的ホール
中国内陸部の高速鉄道ネットワークの計画
2010年度土木計画学研究委員会第11回国際セミナー
中国の高速鉄道計画
日時:2010年12月14日(火) 10時30分~12時30分
場所:山梨大学甲府キャンパス循環システム工学科多目的室(B1-217,218)
プログラム
10:30 開会の挨拶 山梨大学教授 北村眞一
10:35 学部長挨拶 山梨大学工学部長 豊木博泰
10:40 講演 彭其淵(西南交通大学 運輸交通学院院長)
「中国の新幹線計画」(英語)
11:50 講演 ?海峰(西南交通大学運輸交通学院副教授)
「チベット高原鉄道」(同時通訳有)
12:30:閉会の挨拶 山梨大学准教授 佐々木邦明
第42回土木計画学研究発表会・秋大会
Date
2010年11月21日(日)~23日(火・祝)
Venue
21日(日)山梨大学(甲府キャンパス)、22日(月)ベルクラシック甲府、23日(火・祝)山梨大学(甲府キャンパス)
第42回土木計画学研究発表会・秋大会
実施期日
2010年11月21日(日)~23日(火・祝)の3日間
実施場所
山梨大学(甲府キャンパス)他
講演用論文
発表会の当日に充実した議論を行うということが、本発表会の特色です。このため、講演の申し込みに際して、「土木計画学への貢献」と「議論したい 点」を明記していただきます。話題性、速報性のある論文や、調査・計画、技術検討等の事例報告も歓迎します。提出された講演用論文は、原則として無審査で 掲載されますが、会場の制約等によってお断りすることもあります。
なお、ポスターセッションを今年度も実施いたします。口頭発表とポスターでの発表のどちらを希望するかを選んで申込んでいただきます(口頭発表およびポス ターでの発表のいずれも、土木計画学研究・論文集への投稿対象となります)。本秋大会の二日目は平日であり、会場の都合上、二日目はポスター発表を主体に する予定です。多くのポスター発表をお待ちしております。
また、各セッション司会者が、発表会での議論の内容をまとめて、後日、土木計画学委員会ホームページで公開いたします。
問合先
(社)土木学会 研究事業課 田中 章一 E-mail:tanaka@jsce.or.jp
以下の該当する部分を熟読のうえ、手続きを取っていただけますようお願いいたします。
講演の申込み
(1) 申込みの手続きおよび注意点
2010年7月1日(木)~7月23日(金)17時までの期間内に、土木計画学委員会ホームページを使って、講演申込と講演原稿の投稿を同時に行ってください。原稿のファイル形式はPDF形式のみ受付けます。 原稿は「講演原稿執筆要領」に従ってご執筆ください。 申込んだ論文が正しく転送されているかを確認するための期間を2010年7月26日(月)~7月30日(金)17時に設けています。講演申込み者自身で必 ず確認してください。 申込み期間の締切り間際に投稿が集中しますと、予期せぬ事態によりサーバーがダウンし受付ができなくなる恐れがあります。締切り間際の投稿は極力避けてい ただくようお願いいたします。
なお、原稿の提出がないもの、講演原稿執筆要領に準じていないもの、および期限後に投稿されたものは原則として受理できません。原稿の差し替えおよび修正には応じられません。必ず最終原稿を電子投稿してください。
(2) 発表希望分野
申し込みに際して、発表希望分野を下記の5つの発表分野から希望順に2つ選んでください。また、キーワードにつきましては、同キーワード欄の中から最大4つ選んでください。なお、適当なキーワードが見つからない場合は、投稿者の判断によるキーワードを1つだけ加えてください。
発表希望分野
| 発表希望分野 | キーワード |
| A 計画論・計画情報 | 計画基礎論、計画手法論、システム分析、調査論、公共事業評価法、財源・制度論、プロジェクト構想、施工計画・管理、維持管理計画、意識調査分析、計画情報、情報処理、市民参加、GIS、リモートセンシング、測量、環境計画、防災計画、河川・水資源計画、ライフライン計画・設計、地球環境問題 |
| B 地域・都市・景観 | 国土計画、地域計画、都市計画、地区計画、住宅立地、産業立地、人口分布、地価分析、土地利用、市街地整備、再開発、景観、公園・緑地、観光・余暇、空間設計、イメージ分析、土木史 |
| C 交通現象分析 | 発生交通、目的地選択、交通手段選択、経路選択、出発時刻選択、活動分析、時間利用、交通行動調査、交通意識分析、交通行動分析、自動車保有・利用、駐車需要、交通ネットワーク分析、土地利用・交通・環境統合モデル、観光・余暇行動 |
| D 交通基盤計画 | 総合交通計画、地区交通計画、公共交通計画、歩行者・自転車交通計画、道路計画、鉄道計画、空港・港湾計画、ターミナル計画、駐車場計画、物流計画 |
| E 交通運用管理 | 交通流、交通容量、サービス水準、交通制御、交通管理、交通安全、交通情報、交通環境、公共交通運用、交通弱者対策、水上交通、空港管理、交通量計測、TDM、ITS、モビリティマネジメント(MM) |
(3) 発表形式
口頭発表とポスターでの発表のどちらを希望するかを選んでいただきます。なお、会場の都合でご希望に添えない場合もありますので予めご了承下さい。また、各セッション司会者が、発表会での議論の内容をまとめて、後日、土木計画学委員会ホームページで公開いたします。
(4) 投稿料
講演1本につき投稿料(参加費含む)として一般12,000円、学生9,000円を請求いたします。2本以上投稿する方については、2本目以降の投稿料は一般・学生ともに6,000円を請求いたします。振込手数料は各自でご負担願います。
講演原稿執筆要領
(a)A4判の用紙(左右210mm、上下297mm)を使用してください。
(b)左右マージン20mm、上辺マージン19mm、下辺マージン24mmの枠内に、52字×48行の2段組(片段25字+段間2字+片段25字)で作成してください。
(c)ページ数は最大6ページとします。
(d)1頁目の4行目までに、和文題目と英文題目を中心揃えで12ポイントを標準とし、ゴシック体(もしくはそれに準じたフォント)で記述してください。
(e)1頁目の5~7行目に、著者名(和文・英文共)を右揃え10ポイントを標準とし、記述してください。
(f)1頁目の9行目から、本文を2段組で記述してください。
(g)1頁目の左下の脚注に(罫線の下に本文より小さい文字で)以下の項目を記述してください。
(1)キーワード(上記のキーワード欄の中から最大4つ選んでください。)
(2)著者全員の会員種別、学位、所属、連絡者の所在地、電話番号、FAX番号もしくはE-mailアドレス
(h)章・節・項の書き方は以下の通りとします。
(1)章:1.、2.、…として3行とる。
(2)節:(1)、(2)、…として節に入る前の1行を空白行とする。
(3)項:(a)、(b)、…とする。
(i)参考文献の書き方は書式見本で提示します。
事前参加申込みについて
第36回土木計画学研究発表会(一昨年の秋大会)までは、発表者は講演申込のほかに事前参加申込みもしていただいておりましたが、第37回土木計画学研究発表会(春大会)より、講演申込のみしていただければよいこととなりました。後日(9月下旬~10月中旬頃予定)の事前参加申込は不要となりますので、予めご承知おきください(学会事務局が講演申込みデータをもとに事前参加申込みをいたします)。
なお、発表者以外の連名者および大会参加のみ希望の方は、後日(9月下旬~10月中旬頃予定)、別途ホームページ(注:発表論文投稿のためのホームページとは異なります)を用いて事前の受付が必要となります(参加費は一般6,000円、学生3,000円です)。
CD-ROM版講演集の配布について
CD-ROM版講演集は大会参加者全員に配布します。事前受付をされた方には郵送でCD-ROM版講演集を配布します。大会当日に受け付けされた方には、当日配布いたします。